論語:原文・白文・書き下し
原文(唐開成石経)
季氏將伐顓臾冉有季路見於孔子曰季氏將有事於顓臾孔子曰求無乃爾是過與夫顓臾昔者先王以爲東蒙主且在邦域之中矣是社稷之臣也何以伐爲冉有曰夫子欲之吾二臣者皆不欲也
*本章は長いのでA~Dに分割する。「將」字のつくりは〔寽〕。「過」字〔咼〕の上部内は〔人〕。
校訂
諸本
- 武内本:清家本により、爲の下に也の字を補う。釋文云、邦或は封に作る、邦封音義同じ。何以爲伐也、諸本何以伐爲に作る、最後の爲の字は助詞。
東洋文庫蔵清家本
季氏將伐顓臾冉有季路見於孔子曰季氏將有事於顓臾/孔子曰求無乃氽是過與/夫顓臾昔者先王以爲東蒙主/且在邦域之中矣/是社稷之臣也何以爲伐也/冉有曰夫子欲之吾二臣者皆不欲也
- 「將」字のつくりは寽。
- 「氽」字は音「トン」訓「うかべる」。「爾」の異体字「尒」(『敦煌俗字譜』所収)に類似。京大本・宮内庁本は「爾」と記す。
定州竹簡論語
……以為東蒙主,且在[國]463……
※國は漢高祖劉邦の避諱。
標点文
季氏將伐顓臾。冉有季路見於孔子曰、季氏將有事於顓臾。孔子曰、求無乃爾是過與。夫顓臾昔者先王以爲東蒙主、且在國域之中矣。是社稷之臣也。何以爲伐也。冉有曰、夫子欲之。吾二臣者皆不欲也。
復元白文(論語時代での表記)



 顓
顓














 顓
顓










 顓
顓

















 稷
稷






















※將→(甲骨文)・蒙→夢・欲→谷。論語の本章は赤字が論語の時代に存在しない。「顓臾」の「顓」は固有名詞のため、他のいかなる同音字とも置換可能性があるが、「社稷」の「稷」にはその可能性が無い。「有」「之」「以」の用法に疑問がある。本章は少なくとも戦国時代以降の儒者による改変がある。
書き下し
季氏將に顓臾を伐たむとす。冉有季路孔子に見えて曰く、季氏將に顓臾於事あらむとす。孔子曰く、求、無乃爾是れ過たん與。夫れ顓臾は、昔者先の王以て東蒙の主と爲し、且つ國域の中に在る矣。是れ社稷の臣也。何ぞ以て伐つを爲さむ也。冉有曰く、夫子之を欲む、吾二り臣者皆欲め不ざる也。
論語:現代日本語訳
逐語訳
季氏は今にも顓臾を伐とうとした。冉有と季路(顏路)が孔子のお目にかかって言った。
「季氏は今にも顓臾と事を構えようとしています。」
孔子が言った。
「求(冉有)よ。ではお前には過失がないのか。そもそも顓臾は、かつて先王が東方の蒙山の祭主と定めたのだ。その上我が魯の領域内にしかとある。これは魯国の臣下である。なぜ伐つのか。」
冉有が言った。
「主人季氏が望むのです。我ら二人は望まぬのです。」
〔次回へ続く〕
意訳
門閥家老筆頭の季氏が、魯の属国・顓臾を攻め潰そうとした。季氏に仕えている冉有と顏路(顔淵の父)がそれを知らせに来たので、言った。
「冉有よ、顓臾は由緒正しい豪族で、お山を祭る聖なる務めを果たす家柄だ。代々魯国の一部でもある。討つ必要があるのか?」
「あるじの季氏が望むのです。私どもは反対なのです。」
従来訳
季氏が魯の保護国顓臾を討伐しようとした。季氏に仕えていた冉有と季路とが先師にまみえていった。――
「季氏が顓臾に対して事を起そうとしています。」
先師がいわれた。――
「求よ、もしそうだとしたら、それはお前がわるいのではないのかね。いったい顓臾という国は、昔、周王が東蒙とうもう山の近くに領地を与えてその山の祭祀をお命じになった国なのだ。それに、今では魯の支配下にはいっていて、その領主は明らかに魯の臣下だ。同じく魯の臣下たる季氏が勝手に討伐など出来る国ではないだろう。」
冉有がいった。――
「主人がやりたがって困るのです。私共は二人とも決して賛成しているわけではありませんが……」下村湖人『現代訳論語』
現代中国での解釈例
季氏要攻打顓臾,冉有、季路去見孔子說:「季氏快要攻打顓臾了。」孔子說:「冉求,這不是你的錯嗎?顓臾曾做過先王的東蒙主,而且就在魯國境內。是魯國的一部分,為何要打它?」冉有說:「季氏要打的,我二人都不想打。」
季氏が顓臾を攻めようとしていた。冉有と季路が孔子に会いに行って言った。「季氏は今にも顓臾を攻めようとしています。」孔子が言った。「冉求、これはむしろお前の失敗ではないのか? 顓臾はむかし先王の命によって東蒙のあるじに任じられ、しかも魯国の境界内にある。これは魯国の一部である。何のために攻めたりするのか。」冉有が言った。「季氏が攻めたがっているのです。我ら二人はどちらも攻めたくありません。」
論語:語釈
季 氏 將 伐 顓 臾。冉 有 季 路 見 於 孔 子 曰、「季 氏 將 有 事 於 顓 臾。」 孔 子 曰、「求 無 乃 爾 是 過 與。夫 顓 臾、昔 者 先 王 以 爲 東 蒙 主、且 在 邦 域 之 中 矣、是 社 稷 之 臣 也。何 以 爲 伐 也。」冉 有 曰、「夫 子 欲 之、吾 二 臣 者、皆 不 欲 也。」
季氏(キシ)
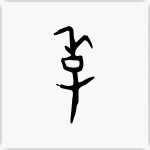
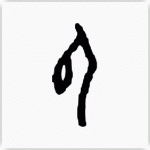
(甲骨文)
論語では、魯国門閥三家老家筆頭、季孫氏のこと。孔子が魯国の政治を執った五十代時点の当主は、季桓子(?-BC492)で、別名季孫斯とも言う。隣国斉が送った女楽団を主君定公と共に三日間楽しみ、その間政務を執らなかったので、孔子は魯国を捨てて亡命したとされる。
しかし具体的に孔子を排斥した記録はなく、孔子本人や弟子を召し抱えたりするなど、孔子が門閥の根城を壊し始めるまで協力的でさえあった。孔子帰国後の当主は季桓子の子、季康子(?-BC468)で、別名季孫肥。
「季」の初出は甲骨文。甲骨文の字形は「禾」”イネ科の植物”+「子」で、字形によっては「禾」に穂が付いている。字形の由来は不明。甲骨文では人名に用いた。金文でも人名に用いたほか、”末子”を意味した。論語ではほぼ、魯国門閥三家老家筆頭・季孫氏として登場する。詳細は論語語釈「季」を参照。
「氏」の初出は甲骨文。甲骨文の字形は人が手にものを提げた姿で、原義は”提げる”。「提」は「氏」と同音。春秋時代までの金文では官職の接尾辞、夫人の呼称に、また”氏族”の意に用いた。詳細は論語語釈「氏」を参照。
將(ショウ)


(甲骨文)
論語の本章では”今にも~しようとする”。近い将来を想像する言葉。新字体は「将」。初出は甲骨文。字形は「爿」”寝床”+「廾」”両手”で、『字通』の言う、親王家の標識の省略形とみるべき。原義は”将軍”・”長官”。同音に「漿」”早酢”、「蔣」”真菰・励ます”、「獎」”すすめる・たすける”、「醬」”ししびしお”。詳細は論語語釈「将」を参照。
伐(ハツ)
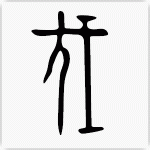

(甲骨文)
論語の本章では”攻め取る”。軍事侵攻すること。初出は甲骨文。「バツ」は慣用音。呉音は「ボチ」。字形は「人」+「戈」”カマ状のほこ”で、ほこで人の頭を刈り取るさま。原義は”首を討ち取る”。甲骨文では”征伐”、人の生け贄を供える祭礼名を意味し、金文では加えて人名(弔伐父鼎・年代不詳)に用いた。戦国の竹簡では加えて”刈り取る”を意味したが、”誇る”の意は文献時代にならないと見られない。詳細は論語語釈「伐」を参照。
顓臾(センユ)
論語の本章では、魯国の勢力範囲内にある半独立の小国。詳細は本章の解説を参照。


(篆書)
「顓」の初出は定州漢墓竹簡。論語の時代に存在しない。ただし地名・人名の場合、同音近音のあらゆる漢語が候補になり得る。字形は〔耑〕”草木のみずみずしい様”+〔頁〕”大きな頭”。原義不明。同音に「専」。戦国中末期の竹簡に「耑□」とあり、「顓頊」と釈文されている。文献時代では、地名・人名に用いた。詳細は論語語釈「顓」を参照。


(甲骨文)
「臾」の初出は甲骨文。論語では本章のみに登場。字形は〔臼〕”手2つ”の間に〔人〕。人を引き回すさま。甲骨文での語義は明らかでない。西周の金文では官職名、または人名の一部に用いた。詳細は論語語釈「臾」を参照。
冉有(ゼンユウ)
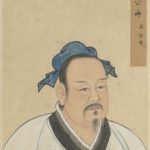

孔子の弟子。 姓は冉、いみ名は求、あざ名は子有。本章ではあざ名で呼んでおり敬称。『史記』によれば孔子より29年少。政治の才を後世に認められ、孔門十哲の一人。
孔子一門の軍事力・政治力を代表する人物で、個人武で目立つ樊須子遅に対し、武将として名をはせた。また放浪中の孔子より一歩先に魯国に帰国、あるいは放浪せず魯国に留まり、筆頭家老家である季孫家の執事を務め、孔子の帰国工作をした。
季孫家の政策に伴い、税制改革の実務を担当し、孔子から反対されたことが『春秋左氏伝』哀公十一年の記事にある(論語先進篇16解説参照)。政界を引退した孔子との関係は多少ぎくしゃくしたようで、孔子は一人前の君子として冉有を丁重に扱いつつもイヤミを言ったという伝説が論語子路篇14にある。詳細は論語の人物:冉求子有を参照。


「冉」(甲骨文)
「冉」は日本語に見慣れない漢字だが、中国の姓にはよく見られる。初出は甲骨文。同音に「髯」”ひげ”。字形はおそらく毛槍の象形で、原義は”毛槍”。春秋時代までの用例の語義は不詳だが、戦国末期の金文では氏族名に用いられた。詳細は論語語釈「冉」を参照。


(甲骨文)
「有」の初出は甲骨文。ただし字形は「月」を欠く「㞢」または「又」。字形はいずれも”手”の象形。金文以降、「月」”にく”を手に取った形に描かれた。原義は”手にする”。原義は腕で”抱える”さま。甲骨文から”ある”・”手に入れる”の語義を、春秋末期までの金文に”存在する”・”所有する”の語義を確認できる。詳細は論語語釈「有」を参照。
季路(キロ)

孔子の弟子、顔回子淵の父親。通説では孔子の一番弟子、仲由子路とするが、子路が季孫家に仕えていたのは孔子亡命前であり、冉有が仕えていたのと時期が合わない。冉有が季孫家に仕えたのは孔子が亡命から帰国する直前で、孔子の帰国工作を兼ねて季孫家に仕えた。その時期、子路は魯の隣国・衛で蒲邑の領主に収まっており、従って冉有と子路が同時期に季孫家に仕えることはあり得ない。
顔回子淵の父親は、『史記』弟子伝ではいみ名(本名)は無繇、あざ名は「路」とあるが、いみ名が二文字なのは春秋時代の漢語として理に合わない。『史記』よりやや時代が下り、論語と同様定州漢墓竹簡に含まれる『孔子家語』では、いみ名は「由」、あざ名は「季路」”末っ子の路さん”。春秋時代の名乗りとしてはむしろこちらの方が理にかなう。
顏由,顏回父,字季路。孔子始教學於閭里,而受學,少孔子六歲。
顏由、顔回の父親。あざ名は季路。孔子が故郷で学問を教授し始めると、同時に弟子となった。孔子より六歳年少。(『孔子家語』七十二弟子解)
この記事が正しければ、孔子の一番弟子は通説が言う子路ではなく、顔路(顔由)だったことになる。また『史記』弟子伝が「孔子より九歳年少」という子路より年長者でもある。
そもそも通説で季路→子路とするのは、孔子より千年後、南北朝の儒者の根拠の無い出任せが始まりで、信用出来ない。『孔子家語』にも「仲由…一字季路。」とあるが、論語同様、どこまで当時書かれた文字列か分からない。古注『論語集解義疏』は経(本文)と注(三国初期までの注釈)と疏(注の付け足し)からなるが、季路→子路説は注にもなく、後漢までは別人とされていた。
先秦両漢の記事で季路→子路と言うのはこの二件のみで、同一人物と思われていたなら、前後の漢儒が古注に記さないわけがない。『孔子家語』による季路→子路説が疑わしいのはそれが理由。混同して子路を季路と書いた記事が無いではないが、底本が先秦両漢にさかのぼるものは無い。
論語先進篇2が、前漢中期の定州竹簡論語では「政事…子路」と書いているのに、隋代の慶大蔵論語疏(つまり古注)や唐石経では「政事…季路」になってしまっているように、中国人はこの程度の改竄を平気でやる。現伝『孔子家語』の「一字季路」を後世の追って書きでないと誰が言えよう。
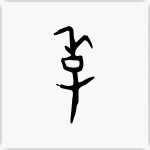

「季」(甲骨文)
「季」の初出は甲骨文。同音は存在しない。甲骨文の字形は「禾」”イネ科の植物”+「子」で、字形によっては「禾」に穂が付いている。字形の由来は不明。甲骨文では人名に用いた。金文でも人名に用いたほか、”末子”を意味した。詳細は論語語釈「季」を参照。


「路」(金文)
「路」の初出は西周中期の金文。字形は「足」+「各」”夊と𠙵”=人のやって来るさま。全体で人が行き来するみち。原義は”みち”。「各」は音符と意符を兼ねている。金文では「露」”さらす”を意味した詳細は論語語釈「路」を参照。
見(ケン)


(甲骨文)
論語の本章では”見る”→”会う”。初出は甲骨文。甲骨文の字形は、目を大きく見開いた人が座っている姿。原義は”見る”。甲骨文では原義のほか”奉る”に、金文では原義に加えて”君主に謁見する”、”…される”の語義がある。詳細は論語語釈「見」を参照。
於(ヨ)


(金文)
論語の本章では”~に”。初出は西周早期の金文。ただし字体は「烏」。「ヨ」は”~において”の漢音(遣隋使・遣唐使が聞き帰った音)、呉音(遣隋使より前に日本に伝わった音)は「オ」。「オ」は”ああ”の漢音、呉音は「ウ」。現行字体の初出は春秋中期の金文。西周時代では”ああ”という感嘆詞、または”~において”の意に用いた。詳細は論語語釈「於」を参照。
孔子(コウシ)

論語の本章では”孔子”。いみ名(本名)は「孔丘」、あざ名は「仲尼」とされるが、「尼」の字は孔子存命前に存在しなかった。BC551-BC479。詳細は孔子の生涯1を参照。
論語で「孔子」と記される場合、対話者が目上の国公や家老である場合が多い。本章もその一つ。詳細は論語先進篇11語釈を参照。


(金文)
「孔」の初出は西周早期の金文。字形は「子」+「乚」で、赤子の頭頂のさま。原義は未詳。春秋末期までに、”大いなる””はなはだ”の意に用いた。詳細は論語語釈「孔」を参照。


(甲骨文)
「子」の初出は甲骨文。字形は赤ん坊の象形。春秋時代では、貴族や知識人への敬称に用いた。季康子や孔子のように、大貴族や開祖級の知識人は「○子」と呼び、一般貴族や孔子の弟子などは「○子」と呼んだ。詳細は論語語釈「子」を参照。
曰(エツ)


(甲骨文)
論語で最も多用される、”言う”を意味する言葉。初出は甲骨文。原義は「𠙵」=「口」から声が出て来るさま。詳細は論語語釈「曰」を参照。
事(シ)


(甲骨文)
論語の本章では”事件”。初出は甲骨文。甲骨文の形は「口」+「筆」+「又」”手”で、口に出した言葉を、小刀で刻んで書き記すこと。つまり”事務”。「ジ」は呉音。詳細は論語語釈「事」を参照。
孔子曰(コウシいはく)
論語では通常、弟子など目下に対して孔子が発言する場合は「子曰」と記す。対等の貴族や、国公や家老など目上の質問に回答する場合は「孔子對曰」と記す。「孔子曰」と記す場合は、目上や対等の存在にものを言う場合に用いる。弟子相手に「孔子曰」とある論語陽貨篇6は定州竹簡論語では「子曰」になっている。論語泰伯編20、および本論語季氏篇で、相手を特定せず「孔子曰」となっているのは例外だが、その理由は分からないし、ほとんどが後世の創作。
論語の本章の場合、対話の相手、その一人目が季孫家の執事という「君子」の身分にあることが明確な冉有、二人目が弟子の顔淵の父親という「親御さん」であり、孔子としては一定の敬意を払うべき相手だったことを理由に挙げうる。
これは本章が文字史的に論語の時代に遡れないのと矛盾しない。本章のような史実が実際にあり、その様子を記した文章が後世になっていじられたと考え得るからだ。
求(キュウ)
論語の本章では孔子の弟子、冉求子有のいみ名。いみ名を呼べるのは目上に限られ、孔子は冉有の師であるゆえに「求」と呼んでいる。同格や目下が呼ぶには、あざ名を用いた。冉求の場合は「子有」。

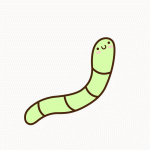
(甲骨文)
「求」の初出は甲骨文。ただし字形は「豸」。字形と原義は足の多い虫の姿で、甲骨文では「とがめ」と読み”わざわい”の意であることが多い。”求める”の意になったのは音を借りた仮借。論語の時代までに、”求める”・”とがめる””選ぶ”・”祈り求める”の意が確認できる。詳細は論語語釈「求」を参照。
無乃(ムダイ/むしろ)
論語の本章では”むしろ~ではないか”。この語法が漢語に現れるのは漢代に入ってからで、戦国末期『荀子』などに用例がないではないが、殷~春秋戦国の考古学的出土物には見られない。
『学研漢和大字典』無乃条
ムナイ・スナワチ…ナカランヤ・ムシロ:反問をあらわすことば。かえって…ではあるまいか。どちらかといえば…ではないだろうか。いっそ。むしろ。▽文末に反問の助辞をおく場合とそうでない場合がある。


(甲骨文)
「無」の初出は甲骨文。「ム」は呉音(遣隋使より前に日本に伝わった音)。甲骨文の字形は、ほうきのような飾りを両手に持って舞う姿で、「舞」の原字。その飾を「某」と呼び、「某」の語義が”…でない”だったので、「無」は”ない”を意味するようになった。論語の時代までに、”雨乞い”・”ない”の語義が確認されている。戦国時代以降は、”ない”は多く”毋”と書かれた。詳細は論語語釈「無」を参照。


「乃」の初出は甲骨文。字形の由来と原義は不明。甲骨文・金文では”そこで”、”お前の”、”お前”、”だから”の意に用いた。漢代の金文では、”やっと”の意に用いた。詳細は論語語釈「乃」を参照。
爾(ジ)


(甲骨文)
論語の本章では”お前”。初出は甲骨文。字形は剣山状の封泥の型の象形で、原義は”判(を押す)”。のち音を借りて二人称を表すようになって以降は、「土」「玉」を付して派生字の「壐」「璽」が現れた。甲骨文では人名・国名に用い、金文では二人称を意味した。詳細は論語語釈「爾」を参照。
是(シ)


(金文)
論語の本章では”~が~だ”。認定の意を示し、英語のbe動詞にあたる。「無乃爾是過與」で”(季孫家と言うより、)むしろお前が間違っているのではないか”。
字の初出は西周中期の金文。「ゼ」は呉音(遣隋使より前に日本に伝わった音)。字形は「睪」+「止」”あし”で、出向いてその目で「よし」と確認すること。同音への転用例を見ると、おそらく原義は”正しい”。初出から”確かにこれは~だ”と解せ、”これ”・”この”という代名詞、”~は~だ”という接続詞の用例と認められる。詳細は論語語釈「是」を参照。
過(カ)
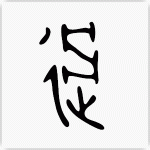

(金文)
論語の本章では”あやまち”。この語義は春秋時代では確認できない。初出は西周早期の金文。字形は「彳」”みち”+「止」”あし”+「冎」”ほね”で、字形の意味や原義は不明。春秋末期までの用例は全て人名や氏族名で、動詞や形容詞の用法は戦国時代以降に確認できる。詳細は論語語釈「過」を参照。
與(ヨ)


(金文)
論語の本章では「か」と訓読して”~ではないか”。疑問の意。この語義は春秋時代では確認出来ない。新字体は「与」。初出は春秋中期の金文。金文の字形は「牙」”象牙”+「又」”手”四つで、二人の両手で象牙を受け渡す様。人が手に手を取ってともに行動するさま。従って原義は”ともに”・”~と”。詳細は論語語釈「与」を参照。
夫(フ)


(甲骨文)
論語の本章では「それ」と読んで”そもそも”の意。この語義は春秋時代では確認できない。初出は甲骨文。論語では「夫子」として多出。「夫」に指示詞の用例が春秋時代以前に無いことから、”あの人”ではなく”父の如き人”の意で、多くは孔子を意味する。「フウ」は慣用音。字形はかんざしを挿した成人男性の姿で、原義は”成人男性”。「大夫」は領主を意味し、「夫人」は君主の夫人を意味する。固有名詞を除き”成人男性”以外の語義を獲得したのは西周末期の金文からで、「敷」”あまねく”・”連ねる”と読める文字列がある。以上以外の語義は、春秋時代以前には確認できない。詳細は論語語釈「夫」を参照。
昔者(セキシャ/むかし)
論語の本章では”むかしの話だが”。今昔物語の「今は昔」、昔話の「むかしむかし」と同じ。戦国時代になって出来た比較的新しい漢語で、論語の時代に存在しない。


(甲骨文)
「昔」の初出は甲骨文。字形は「𡿧」(災)+「日」。「𡿧」は洪水。洪水のあった過去を意味する。甲骨文の字形には部品配置が上下で入れ替わっているものがある。春秋末期までに、”むかし”の意に用いた。詳細は論語語釈「昔」を参照。


(金文)
「者」の旧字体は〔耂〕と〔日〕の間に〔丶〕一画を伴う。新字体は「者」。ただし唐石経・清家本ともに新字体と同じく「者」と記す。現存最古の論語本である定州竹簡論語も「者」と釈文(これこれの字であると断定すること)している。初出は殷代末期の金文。金文の字形は「木」”植物”+「水」+「口」で、”この植物に水をやれ”と言うことだろうか。原義は不明。初出では称号に用いている。春秋時代までに「諸」と同様”さまざまな”、”~する者”・”~は”の意に用いた。漢文では人に限らず事物にも用いる。詳細は論語語釈「者」を参照。
先王(センノウ)
論語の本章では、太古代に存在したとされていた中華世界の支配者。周の文王・武王はともかく、それ以外は架空の存在で実在を証す出土物が無い。
「先・王」の漢音は「セン・オウ」だが、続けて読むときには「センノウ」と読む習慣がある。「先王」は昔の王でも、とりわけ聖天子とされる堯や舜や禹、殷の湯王や周の文王・武王を指す。「天子」の言葉が中国語に現れるのは西周早期で、殷の君主は自分から”天の子”などと図々しいことは言わなかった。詳細は論語述而篇34余話「周王朝の図々しさ」を参照。


(甲骨文)
「先」の初出は甲骨文。字形は「止」”ゆく”+「人」で、人が進む先。甲骨文では「後」と対になって”過去”を意味し、また国名に用いた。論語の時代までの金文では、加えて”先行する”を意味した。詳細は論語語釈「先」を参照。
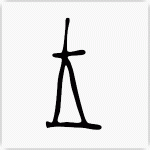

(甲骨文)
「王」の初出は甲骨文。字形はまさかりの形で、軍事権や司法権の象徴。殷代の遺蹟から実用品ではない威嚇用のまさかりが出土しており、実用品としては隕鉄を鍛造した刃に青銅のガワをかぶせた、高度な技術品が出土している。詳細は論語語釈「王」を参照。
以(イ)


(甲骨文)
論語の本章では”それで”。以前に「顓臾」という指示対象があるので、ここでは指示詞。初出は甲骨文。人が手に道具を持った象形。原義は”手に持つ”。論語の時代までに、名詞(人名)、動詞”用いる”、接続詞”そして”の語義があったが、前置詞”~で”に用いる例は確認できない。ただしほとんどの前置詞の例は、”用いる”と動詞に解せば春秋時代の不在を回避できる。詳細は論語語釈「以」を参照。
爲(イ)
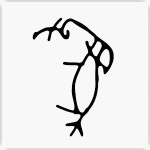

(甲骨文)
論語の本章、「以爲東蒙主」では”~にする”。「何以爲伐也」では”~をする”。新字体は「為」。字形は象を調教するさま。甲骨文の段階で、”ある”や人名を、金文の段階で”作る”・”する”・”~になる”を意味した。詳細は論語語釈「為」を参照。
東蒙*(トウボウ)
論語の本章では、魯国領内、季孫家の根城である費邑の北方にある山の名。魯の首邑である曲阜からは東方に当たり、現在の標高はwikipedia中国語版によると1,156mという。


(甲骨文)
「東」の初出は甲骨文。字形は「木」+「日」。太陽が木の幹の高さまで昇ったさま。甲骨文から春秋時代に至るまで、”ひがし”の意に用いた。詳細は論語語釈「東」を参照。


(戦国金文)
「蒙」の初出は戦国末期の金文。論語では本章のみに登場。論語の時代に存在しないが、固有名詞のため同音近音のあらゆる漢字が置換候補になりうる。字形は〔艹〕+〔冡〕”ぶた小屋”。家畜小屋を草葺きで覆うさま。「モウ」は慣用音。呉音は「ム」。詳細は論語語釈「蒙」を参照。
主(シュ)


(甲骨文)
論語の本章では”あるじ”。この語義は春秋時代では確認できない。初出は甲骨文。字形は位牌の形で、原義は”位牌”。金文の時代では氏名や氏族名に用いられるようになったが、自然界の”ぬし”や、”あるじとする”の語義は戦国初期になるまで確認できない。詳細は論語語釈「主」を参照。
且(シャ)


(甲骨文)
論語の本章では”その上”。初出は甲骨文。字形は文字を刻んだ位牌。甲骨文・金文では”祖先”、戦国の竹簡で「俎」”まな板”、戦国末期の石刻文になって”かつ”を意味したが、春秋の金文に”かつ”と解しうる用例がある。詳細は論語語釈「且」を参照。
在(サイ)


(甲骨文)
論語の本章では、”存在する”。「ザイ」は呉音(遣隋使より前に日本に伝わった音)。初出は甲骨文。ただし字形は「才」。現行字形の初出は西周早期の金文。ただし「漢語多功能字庫」には、「英国所蔵甲骨文」として現行字体を載せるが、欠損があって字形が明瞭でない。同音に「才」。甲骨文の字形は「才」”棒杭”。金文以降に「士」”まさかり”が加わる。まさかりは武装権の象徴で、つまり権力。詳細は春秋時代の身分制度を参照。従って原義はまさかりと打ち込んだ棒杭で、強く所在を主張すること。詳細は論語語釈「在」を参照。
國(コク)


(甲骨文)
論語の本章では”国の”。新字体は「国」。初出は甲骨文。字形はバリケード状の仕切り+「口」”人”で、境界の中に人がいるさま。原義は”城郭都市”=邑であり、春秋時代までは、城壁外にまで広い領地を持った”くに”ではない。詳細は論語語釈「国」を参照。
加えて恐らくもとは「邦」と書かれていたはずで、漢帝国になって高祖劉邦のいみ名を避ける(避諱)ため、当時では同義になっていた「國」に書き換えたのが、そのまま元に戻らず現伝していると考えられる。詳細は論語語釈「邦」を参照。
域(ヨク)


(金文)
論語の本章では”領域”。論語では本章のみに登場。初出は西周早期の金文。字形は城郭都市+「戈」”ほこ”。自衛武装した都市国家の姿。西周から春秋戦国時代は「或」と書き分けられず、つちへんが付けられたのは後漢の説文解字からである。論語語釈「或」も参照。「イキ」は呉音。西周の金文では人名の一部に、”地域”の意に用いた。詳細は論語語釈「域」を参照。
之(シ)


(甲骨文)
論語の本章、「國域之中」では”…の”・”これ”。「夫子欲之」では”これ”。具体的には軍事侵攻を指す。「此」が直近の事物を、「其」がやや離れた事物を指すのに対し、「之」は足元を指さすように”これ”と抜き出して指し示すのに用いる。孔子の「何以爲伐也」”なんで侵攻なんかするんだ”に対し、冉有が「夫子欲之」”ご当主がその侵攻をしたがっているのです”と答えたわけ。
字の初出は甲骨文。字形は”足”+「一」”地面”で、あしを止めたところ。原義はつま先でつ突くような、”まさにこれ”。殷代末期から”ゆく”の語義を持った可能性があり、春秋末期までに”~の”の語義を獲得した。詳細は論語語釈「之」を参照。
中(チュウ)
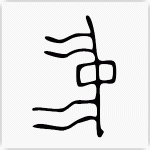

(甲骨文)
論語の本章では”~の中”。初出は甲骨文。甲骨文の字形には、上下の吹き流しのみになっているものもある。字形は軍司令部の位置を示す軍旗で、原義は”中央”。甲骨文では原義で、また子の生まれ順「伯仲叔季」の第二番目を意味した。金文でも同様だが、族名や地名人名などの固有名詞にも用いられた。また”終わり”を意味した。詳細は論語語釈「中」を参照。
矣(イ)


(金文)
論語の本章では、”~し続けている”。初出は殷代末期の金文。字形は「𠙵」”人の頭”+「大」”人の歩く姿”。背を向けて立ち去ってゆく人の姿。原義はおそらく”…し終えた”。ここから完了・断定を意味しうる。詳細は論語語釈「矣」を参照。
社稷(シャショク)
論語の本章では”国家”。具体的には魯国を指す。


「社」(金文)/「主」(甲骨文)
「社」の原義は”鎮守の森”。その土地の守護神の神域とやしろ。新字体は「社」。台湾・香港ではこちらが正字体とされる。現行字体の初出は戦国末期の金文。部品の「土」にも”大地神”の意があり、初出は甲骨文。字形は「示」”祭壇”もしくは”位牌”+「土」で、大地神を祭るさま。原義は”大地神”。「土」は甲骨文では”大地神”のほか”領土”、金文では加えて”つち”を意味し、「𤔲土」はいわゆる「司徒」を意味した。「社」は戦国の金文では「社稷」で”国家を意味した。詳細は論語語釈「社」を参照。
周が殷を滅ぼして国盗りをすると、後ろめたさから「申」”天神”の字を複雑化させて「神」(神)の字を作り、もったいをつけて”自分は天命を受けて乱暴な殷を滅ぼしたのだ”と宣伝した。そのため「土」も複雑化させて出来たのが現行の「社」。「天子」の言葉が中国語に現れるのも西周早期で、殷の君主は自分から”天の子”などと図々しいことは言わなかった。詳細は論語述而篇34余話「周王朝の図々しさ」を参照。
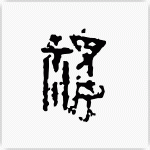

(戦国金文)
「稷」の原義は”キビ”→”穀物神”。初出は戦国時代の金文。論語の時代に存在しない。論語時代の置換候補もない。字形は「禾」”イネ科の植物”+「鬼」”頭部が大きい”+「女」”中身が詰まった”。穂の大きな穀物のさま。同音に「即」、「蝍」”飛ぶ虫の総称”、「畟」”田畑をすく”(初出説文解字)。戦国の金文では”穀物の実る”の意に、戦国の竹簡では穀物神の固有名に用いた。詳細は論語語釈「稷」を参照。
臣(シン)


(甲骨文)
論語の本章では”属国”。「ジン」は呉音(遣隋使より前に日本に伝わった音)。甲骨文の字形には、瞳の中の一画を欠くもの、向きが左右反対や下向きのものがある。字形は頭を下げた人のまなこで、原義は”奴隷”。甲骨文では原義のほか”家臣”の意に、金文では加えて氏族名や人名に用いた。詳細は論語語釈「臣」を参照。
也(ヤ)


(金文)
論語の本章、「社稷之臣也」では「なり」と読んで断定の意を示す。この語義は春秋時代では確認できない。「何以爲伐也」では「や」と読んで詠嘆(非難)をこめた疑問の意を表す。字の初出は事実上春秋時代の金文。字形は口から強く語気を放つさまで、原義は”…こそは”。春秋末期までに句中で主格の強調、句末で詠歎、疑問や反語に用いたが、断定の意が明瞭に確認できるのは、戦国時代末期の金文からで、論語の時代には存在しない。詳細は論語語釈「也」を参照。
何(カ)


(甲骨文)
論語の本章では”なぜ”。この語義は春秋時代では確認できない。初出は甲骨文。字形は「人」+”天秤棒と荷物”または”農具のスキ”で、原義は”になう”。甲骨文から人名に用いられたが、”なに”のような疑問辞での用法は、戦国時代の竹簡まで時代が下る。詳細は論語語釈「何」を参照。
夫子(フウシ)


(甲骨文)
論語の本章では季孫家の”ご当主様”。従来「夫子」は「かの人」と訓読され、「夫」は指示詞とされてきた。しかし論語の時代、「夫」に指示詞の語義は無い。同音「父」は甲骨文より存在し、血統・姓氏上の”ちちおや”のみならず、父親と同年代の男性を意味した。従って論語における「夫子」がもし当時の言葉なら、”父の如き人”の意味での敬称。
欲(ヨク)


(楚系戦国文字)
論語の本章では”もとめる”。初出は楚系戦国文字。新字体は「欲」。同音は存在しない。字形は「谷」+「欠」”口を膨らませた人”。部品で近音の「谷」に”求める”の語義があり、全体で原義は”欲望する”。論語時代の置換候補は部品の「谷」。詳細は論語語釈「欲」を参照。
吾(ゴ)


(甲骨文)
論語の本章では”我(ら二人の家臣)”。冉有と子路を差す。初出は甲骨文。字形は「五」+「口」で、原義は『学研漢和大字典』によると「語の原字」というがはっきりしない。一人称代名詞に使うのは音を借りた仮借だとされる。詳細は論語語釈「吾」を参照。
春秋時代までは中国語にも格変化があり、一人称では「吾」を主格と所有格に用い、「我」を所有格と目的格に用いた。しかし論語でその文法が崩れ、「我」と「吾」が区別されなくなっている章があるのは、後世の創作が多数含まれているため。
二(ジ)
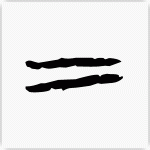

(甲骨文)
論語の本章では、数字の”に”。冉有と季路を指す。初出は甲骨文。「ニ」は呉音。「上」「下」字と異なり、上下同じ長さの線を引いた指事文字で、数字の”に”を示す。原義は数字の”に”。甲骨文・金文では原義で用いた。詳細は論語語釈「二」を参照。
皆(カイ)


(甲骨文)
論語の本章では”どちらも”。初出は甲骨文。「ケ」は呉音。上古音の同音は存在しない。字形は「虎」+「𠙵」”口”で、虎の数が一頭の字形と二頭の字形がある。後者の字形が現行字体に繋がる。原義は不明。金文からは虎が人に置き換わる。「从」”人々”+「𠙵」”口”で、やはり原義は不明。甲骨文・金文から”みな”の用例がある。詳細は論語語釈「皆」を参照。
論語:付記
検証
論語の本章について、文字史上から論語の時代そのままの文章でないことは明らかだが、内容面含めて総合的な検証は、最終部分である論語季氏篇4検証で行うこととする。とりあえず本章では、孔子晩年に季孫家による小国併合騒ぎがあったこと、ゆえに本章は伝説としては史実を伝える可能性があるのを指摘するに止める。
解説
論語の本章の主題となった「顓臾」について、以下wikipedia中国語版より引用して翻訳。
顓臾は山東省にあった風姓の古い国。伝説によると、風姓を代々受け継いだ東夷族の首領太皞が、太古の時代に顓臾方国を建てた。西周初期、周の成王がこれを顓臾王に任じ、その主要な任務として蒙山の祭祀を任せた。春秋時代には、顓臾は魯国内の属国となった。
『春秋左氏伝』僖公二十一年の条に、「任、宿、須句、颛臾は風姓である。太皞と済水の祭祀を司り、中華諸国に仕えた」とある。これら風姓の古代諸国は魯国の属国となり、顓臾は魯国の季孫氏の領地費邑の付近にあった。
春秋末期、魯国の季康子が顓臾を攻略しようとはかり、季孫氏の執事冉求と家臣の季路が彼らの師である孔子にこれを報告した。孔子は厳しく彼らを批判し、このことは『論語』季氏第十六の最初に記されている。歴史学者の李零は、この事件をBC484からBC480年のことと考証している。

出典:http://shibakyumei.web.fc2.com/
ただし「顓臾」の語が確実に現れるのは前漢初期の陸賈『新語』で、論語の本章D部分とよく似た文。
季孫貪顓臾之地、而變起於蕭墻之內。(『新語』術事6)
季孫之憂不在於顓臾、而在蕭牆之内也。(論語季氏篇4)
『春秋左氏伝』にも見え、その記述は次の通り。
任,宿,須句,顓臾,風姓也,實司大皞與有濟之祀,以服事諸夏,邾人滅須句,須句子來奔,因成風也,成風為之言於公曰,崇明祀,保小寡,周禮也,蠻夷猾夏,周禍也,若封須句,是崇皞濟而脩祀紓禍也。
僖公二十一年(BC639)。任、宿、須句、顓臾の諸国は、その君主が風姓である。実際に東方の神である大皞と、済水に宿るもろもろの精霊の祭祀を続けてきた。その事を理由に、中原諸侯国の属国となっていたが、邾国が須句を滅ぼしたので、その君主が魯国に亡命してきた。(僖公の生母である同族の)成風を頼ったのである。
成風は須句のために僖公に言った。「由緒正しい祭祀を尊び、小さな国を守るのは、周の伝統です。蛮族が中華をかき乱すのは。周にとっての災いです。もし須句に領地を与えてやるなら、それは大皞と済水の祭祀を尊び、災いを和らげることになります。」(『春秋左氏伝』僖公二十一年)
成風は『春秋公羊伝』文公五年の条に「成風者何、僖公之母也。」とある。また『春秋左氏伝』翌年の伝に、「二十二年,春,伐邾,取須句,反其君焉,禮也。」とあり、僖公は兵を出して須句の旧領を取り返してやった事が記される。
しかし孔子存命中に、季孫家がが顓臾を攻めた話は『春秋左氏伝』に無く、代わりに上掲引用にも見える邾国を攻めた話が哀公七年の条にあるのみ。儒家を含めた春秋戦国の諸子百家は、揃って孔子存命中の顓臾ばなしを伝えていない。
仮に論語の本章が史実を伝えるものだとすると、季孫家が邾国を攻めた話がいつの間にか対象を勘違いされ、前漢初期になって陸賈がウッカリ「季孫貪顓臾」と書いてしまい、漢儒が本章を論語に編入する際、邾国を顓臾にしてしまったとするなら話が通る。
ただし哀公七年だとするなら冉有が季孫家の執事でありはするが、子路は隣の衛国でまちの領主になっており、話が合わない。子路が季孫家に仕えたのは、孔子が魯国から放浪の旅に出る以前のことだからだ。
余話
(思案中)




コメント