
- 二(ジ・2画)
- 尼(ジ・5画)
- 而(ジ・6画)
- 次(ジ・6画)
- 耳(ジ・6画)
- 佴(ジ・8画)
- 貳/弐(ジ・6画)
- 慈(ジ・13画)
- 爾(ジ・14画)
- 邇(ジ・18画)
- 壐/璽(ジ・19画)
- 肉(ジク・6画)
- 七(シツ・2画)
- 失(シツ・5画)
- 實/実(シツ・8画)
- 室(シツ・9画)
- 疾(シツ・10画)
- 瑟(シツ・13画)
- 漆(シツ・14画)
- 質(シツ/チ・15画)
- 日(ジツ・4画)
- 且(シャ/ショ・5画)
- 社/社(シャ・7画)
- 車(シャ・7画)
- 者/者(シャ・8画)
- 舍(シャ・8画)
- 射(シャ・10画)
- 赦(シャ・11画)
- 奢(シャ・12画)
- 邪(ジャ・8画)
- 綽(シャク・14画)
- 若(ジャク・8画)
- 主(シュ・5画)
- 守(シュ・6画)
- 朱(シュ・6画)
- 取(シュ・8画)
- 酒(シュ・10画)
- 須(シュ・12画)
- 聚(シュ・14画)
- 需(シュ・14画)
- 趨(シュ・17画)
- 壽/寿(ジュ・7画)
- 乳(ジュ・8画)
- 儒(ジュ・16画)
- 樹(ジュ・16画)
- 孺(ジュ・17画)
- 十(シュウ・2画)
- 手(シュウ・4画)
- 舟(シュウ・6画)
- 州(シュウ・6画)
- 秀(シュウ・7画)
- 周(シュウ・8画)
- 受(シュウ・8画)
- 臭/臭(シュウ・9画)
- 首(シュウ・9画)
- 修(シュウ・10画)
- 習(シュウ・11画)
- 終(シュウ・11画)
- 脩(シュウ・11画)
- 授(シュウ・11画)
- 崇(シュウ・11画)
- 羞(シュウ・11画)
- 就(シュウ・12画)
- 眾/衆(シュウ・12画)
- 集(シュウ・12画)
- 廋(シュウ・13画)
- 銹(シュウ・15画)
- 獸/獣(シュウ・16画)
- 襲(シュウ・22画)
- 入(ジュウ・2画)
- 戎(ジュウ・6画)
- 狃(ジュウ・7画)
- 柔(ジュウ・9画)
- 從/従(ジュウ・10画)
- 縱/縦(ジュウ・16画)
- 叔(シュク・8画)
- 祝/祝(シュク・9画)
- 孰(シュク・11画)
- 宿(シュク・11画)
- 踧(シュク・15画)
- 熟(シュク・15画)
- 蹜(シュク・18画)
- 出(シュツ・5画)
- 述(ジュツ・8画)
- 恂(シュン・9画)
- 春(シュン・9画)
- 循(シュン・12画)
- 舜(シュン・13画)
- 純(ジュン・10画)
- 順(ジュン・12画)
- 閏(ジュン・12画)
- 潤(ジュン・15画)
- 處/処(ショ・5画)
- 所(ショ・8画)
- 沮(ショ・8画)
- 書(ショ・10画)
- 庶(ショ・11画)
- 暑(ショ・12画)
- 黍(ショ・12画)
- 雎(ショ・13画)
- 諸(ショ・15画)
- 女(ジョ・3画)
- 汝(ジョ・6画)
- 如(ジョ・6画)
- 恕(ジョ・10画)
- 小(ショウ・3画)
- 上(ショウ・3画)
- 升(ショウ・4画)
- 少(ショウ・4画)
- 邵/召(ショウ・5画)
- 松(ショウ・8画)
- 尙/尚(ショウ・8画)
- 承(ショウ・8画)
- 相(ショウ・9画)
- 昭(ショウ・9画)
- 笑(ショウ・10画)
- 將/将(ショウ・10画)
- 稱/称(ショウ・10画)
- 商(ショウ・11画)
- 章(ショウ・11画)
- 訟(ショウ・11画)
- 接(ショウ・11画)
- 掌(ショウ・12画)
- 勝(ショウ・12画)
- 翔(ショウ・12画)
- 證/証(ショウ・12画)
- 傷(ショウ・13画)
- 頌(ショウ・13画)
- 韶(ショウ・14画)
- 嘗(ショウ・14画)
- 裳(ショウ・14画)
- 誦(ショウ・14画)
- 賞(ショウ・15画)
- 蕭(ショウ・16画)
- 牆/墻(ショウ・17画)
- 襄/㐮(ショウ・17画)
- 醬/醤(ショウ・18画)
- 鐘(ショウ・20画)
- 仍(ジョウ・4画)
- 杖(ジョウ・7画)
- 狀/状(ジョウ・7画)
- 乘/乗(ジョウ・9画)
- 情(ジョウ・11画)
- 常(ジョウ・11画)
- 壤/壌(ジョウ・16画)
- 擾(ジョウ・18画)
- 譲/讓(ジョウ・20画)
- 攘(ジョウ・20画)
- 式(ショク・6画)
- 色(ショク・6画)
- 卽/即(ショク・7画)
- 食(ショク・9画)
- 息(ショク・10画)
- 殖(ショク・12画)
- 植(ショク・12画)
- 飾(ショク・13画)
- 稷(ショク・15画)
- 識(ショク・19画)
- 辱(ジョク・10画)
- 匿(ジョク・10画)
二(ジ・2画)
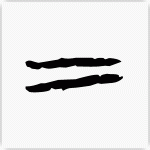

甲骨文/夨令方彝・西周早期
初出:初出は甲骨文。
字形:「上」「下」字と異なり、上下同じ長さの線を引いた指事文字で、数字の”に”を示す。原義は数字の”に”。
音:カールグレン上古音はȵi̯ər(去)。「ニ」は呉音。
用例:「漢語多功能字庫」によると、甲骨文・金文では原義で用いた。
備考:論語語釈「貳」も参照。
学研漢和大字典
指事。二本の横線を並べたさまを示すもので、二つの意を示す。二つの物がくっつくという意味では、爾(ニ)・(ジ)(そばにくっついた相手→二人称代名詞)・膩(ニ)・(ジ)(ねばってくっつく油)・泥(ナイ)・(デイ)(くっつくどろ)・人(ニン)・(ジン)(そばにくっついている仲間、隣人)・昵(ニチ)・(ジツ)(そばにくっついて親しむ)などと同系。その半面では、一つに合体せずわかれる、別になるとの意味を派生する。類義語の両・双は、二つ対(ツイ)をなすこと。再は、もう一度の意。復は、来た道をもう一度引き返すことから、もう一度の意。異字同訓に双「双子。双葉」。付表では、「二日」を「ふつか」「二十日」を「はつか」「二人」を「ふたり」「二十・二十歳」を「はたち」「十重二十重」を「とえはたえ」と読む。▽証文や契約書では、改竄(カイザン)や誤解をさけるため「弍・貳(=弐)」と書くことがある。▽草書体をひらがな「に」として使うこともある。▽「二」の全画からカタカナの「ニ」ができた。
語義
- {数詞}ふたつ。
- {動詞}ふたつにする(ふたつにす)。二分する。また、ふたつにわけて食い違わせる。《同義語》⇒弐。「二其心=其の心を二つにす」。
- {数詞}ふた。順番の二番め。「俯不俊於人二楽也=俯して人に俊ぢざるは二の楽しみなり」〔孟子・尽上〕
- {副詞}ふたたび。二度。二回。
- {形容詞}別の違ったものであるさま。《類義語》両。「二様」。
- {数詞}二三と連ねて用い、いくつかの、いろいろの、の意をあらわすことば。「二三子」「二三其徳=其の徳を二三にす」〔詩経・衛風・氓〕
- 《日本語での特別な意味》
①邦楽で、三味線の第二の糸で、一の糸よりも音が高く、三の糸より低いもの。
②「二塁」の略。「二遊間」。
字通
[指事]横線二を以て、数の二を示す。算木を二本ならべた形。卜文・金文は同様の方法で一より四までの数字を示す。〔説文〕十三下に「地の數なり。偶に從ふ」とする。〔易、繫辞伝上〕に「天は一、地は二なり」とあるのによる。古文の字は弍に作り、金文では比例や分数的表示のときにその字を用いることがある。
尼(ジ・5画)
初出は前漢の隷書。論語の時代に存在しない。カールグレン上古音はni̯ər(平)。同音は下記の通り。『大漢和辞典』に音ジ・ニ訓ちかづくは他に存在しない。音ジツ・ニチ訓ちかづくに「昵」ni̯ət(入)があるが、初出は説文解字。近音のniərの一覧は、論語語釈「泥」を参照。
| 字 | 音 | 訓 | 初出 | 声調 | 備考 |
| 尼 | ジ | ちかづく | 前漢隷書 | 平 | |
| 怩 | 〃 | はぢる | 説文解字 | 〃 | |
| 柅 | 〃 | 木の名・糸枠 | 前漢隷書 | 上 | |
| 膩 | 〃 | あぶら | 戦国末期金文 | 去 |
論語では孔子のあざ名「仲尼」として出てくる。『史記』孔子世家によると、孔子の母(顔徴在)が出生前に尼丘に祈って孔子が生まれたので、仲尼とあざ名が付いたという。だが「尼」の字が論語の時代に存在しないから、これは後世の作り話。
『学研漢和大字典』によると、「尼」の藤堂上古音はnɪerまたはneɪであり、「二」の上古音nierと近い。カールグレン上古音も「尼」ni̯ər(平)に対して「二」ȵi̯ər(去)。ここからもとは「仲二」と書き、単に”次男坊”を意味すると想像したくなる。
孔子はおそらく母が取った客の子であり、言わば社会の最底辺の出身だったからだ。つまり著名人になる前の孔子に、敬称の一種であるあざ名があったと考えがたく、あだ名が後世重々しい字で書かれるようになっただけではなかろうか。
学研漢和大字典
会意。「尸(ひとのからだ)+比(ならぶ)の略体」で、人が相並び親しむさまを示す。もと、人(ニン)(親しみあうひと)と同系。のち、「あま」の意に専用されたが、尼の原義は昵懇(ジッコン)の昵の字に保存された。
語義
ジ
- {名詞}あま。仏に仕える女性。▽梵語(ボンゴ)を漢訳した比丘尼(ビクニ)の略称。あまという日本語は、パーリ語のアンマ(母)から転化したものといわれる。「依撲果寺尼浄悟之室=撲果寺の尼浄悟の室に依る」〔謝小娥伝〕
- {動詞}ちかづく。そばによりそって親しむ。《同義語》⇒邇(ジ)・昵(ジツ)(親しむ)。
デイ
- {動詞}なずむ(なづむ)。ねばって親しむ。また、渋って動かない。《同義語》⇒泥(デイ)。「尼古=古に尼む」「或尼之=或いはこれに尼む」〔孟子・梁下〕
- 《日本語での特別な意味》出家した女子の名につけることば。「阿仏尼」。
字通
[会意]人が二人、たがいにもたれあう形。〔説文〕八上に「後ろより之れに近づく」とし、「尸(し)に從ひ、匕(ひ)聲」とするが声が合わず、人がもたれあう親昵(しんじつ)の状を示す字である。色・卬(ごう)・抑・迎などみな二人相倚(よ)る形で、尼・色・卬はいずれも男女のことを示す字。ゆえに尼声の字に、和らぐ・安んず・愛す・したしむなどの意がある。この字を尼僧の意に用いるのは、最も字の形義にそむくものである。
而(ジ・6画)


甲骨文/蔡侯墓殘鐘四十七片・春秋末期
初出:初出は甲骨文。「小学堂」によれば初出は西周末期の金文。
字形:ひげの象形とされるがその用例が確認できない。
音:カールグレン上古音はȵi̯əɡ(平)。
用例:甲骨文から”~と”の用例がある。『甲骨文合集』28403に「惟戊射虎而兕無災」とある、「これ戊に虎と兕を射て災い無からんか」と読める。
西周末期の「𡱒敖𣪕蓋」に、「戎獻金于子牙父百車。而易魯𡱒敖金十鈞」とあり、「戎、子牙父に百車金を献じ、して魯の𡱒敖金十鈞を賜う」と読め、接続詞”そして”の用法が確認できる。「易」は「賜」、「𡱒敖」はおそらく人名。
春秋中期の「叔尸鐘」に、「女不彖夙夜,宦執而政事」とあり、「なんじ夙夜たゆまず、なんじの政事を宦りて執り」と読め、二人称の用法が確認できる。
接続詞としての「而」については研究が積み重ねられてきたが(ex.戸内俊介「上古中国語文法化研究序説」)、いずれもやはり単なる時間の前後や類似を意味しない。
「漢語多功能字庫」によると、甲骨文では祭りの名、食べ物を煮て祭りを行うこと、地名に用いられ、金文では”なんじ”の意に用いられたが、”…して”のような接続詞の用例は、戦国時代まで時代が下るという(中山王鼎)。
学研漢和大字典
象形。柔らかくねばったひげの垂れたさまを描いたもの。▽ただし古くから、中称の指示詞niəg・nəgに当て、「それ」「その人(なんじ)」の意に用い、また指示詞から接続詞に転じて、「そして」「それなのに」というつながりを示す。
耳(柔らかいみみ)・屮(ジ)(柔らかい肉)・耐(ねばる)などと同系のことば。
語義
- {接続詞}しかして。しこうして(しかうして)。→語法「①」。
- {接続詞}しかも。→語法「②」。
- {代名詞}なんじ(なんぢ)。おまえ。《類義語》汝・若。「且而与其従辟人之士也=且つ而は其の人を辟くるの士に従はんよりは」〔論語・微子〕
- {指示詞}その。「而月斯征=而の月斯に征く」〔詩経・小雅・小宛〕
- {接続詞}→語法「⑥」
語法
①「しかして」「しこうして」とよみ、
- 「また~」「ここで~」と訳す。並列・選択の意を示す。
▽「~して」「~て」と直前の語に続けてよみ、訓読しないことが多い。「士不可以不弘毅、任重而道遠=士はもって弘毅(かうき)ならざる可からず、任重くして道遠し」〈士人はおおらかで強くなければならない。任務は重くて道は遠い〉〔論語・泰伯〕 - 「そして」と訳す。順接の意を示す。▽「~して」「~て」と、直前の語に続けてよみ、訓読しないことが多い。「学而時習之=学びて時にこれを習ふ」〈学んで適当な時期におさらいする〉〔論語・学而〕
②「しかも」「しかるに」「しかれども」とよみ、「~ではあるが」「しかし」「それなのに」「~であっても」と訳す。逆接の意を示す。
▽「~ども」「~ど」と直前の語に続けてよみ、訓読しないことが多い。「千里馬常有、而伯楽不常有=千里の馬は常に有れども、伯楽は常には有らず」〈千里を走る名馬はいつもいるが、名馬を見つける名伯楽はいつもいるわけではない〉〔韓愈・雑説〕
③「しかも」とよみ、「そのうえ」「さらに」と訳す。累加の意を示す。
▽「~して」「~て」と直前の語に続けてよみ、訓読しないことが多い。「積仁潔行如此而餓死=仁を積み行ひを潔(いさぎよ)くすることかくの如(ごと)くにして而(しか)も餓死す」〈あれほど仁徳を積み、清廉潔白であったのに、餓死したのである〉〔史記・伯夷〕
④「すなわち」とよみ、「そうであれば」と訳す。《同義語》則。「上下交征利、而国危矣=上下交(こもごも)利を征(と)れば而(すなは)ち国危ふからん」〈上の者も、下の者も互いに利益を取りあってばかりいては、国は危うくなるでしょう〉〔孟子・梁上〕
⑤「~して」「~にして」とよみ、「~ならば」と訳す。順接の仮定条件の意を示す。
▽「~して」「~て」と直前の語に続けてよみ、訓読しないことが多い。「倉廩実而知礼節、衣食足而知栄辱=倉廩(さうりん)実(み)ちて礼節を知り、衣食足りて栄辱を知る」〈倉庫に穀物がいっぱいになって、はじめて礼儀を心得るようになり、衣食が十分に足りてきて、はじめて名誉と恥とを知るようになる〉〔史記・管晏〕
⑥「~にして」とよみ、「~でありながら」と訳す。名詞の直後におかれ、条件文を導く。▽「~して」「~て」と直前の語に続けてよみ、訓読しないことが多い。「人而無信、不知其可也=人にして信無(な)くんば、その可なることを知らざるなり」〈人でありながら信義がなければ、うまくやっていけない〉〔論語・為政〕
字通

頭髪を切って、結髪をしない人の正面形。雨乞いをするときの巫女の姿で、需とは雨を需め、需つことを示す字で、雨と、巫女の形である而とに従う。濡・儒はその系統の字である。〔説文〕九下に「頬毛なり。毛の形に象る」とし、髵(ひげ)の初文とみている。〔段注本〕に「須なり」と改め、その象形であるという。〔説文〕の耏字条九下に「罪あるも髠に至らざるものなり」とあり、髠とは頭髪を落とす刑。耏はその一部を残すので彡を加えるが、而は髠の形である。巫祝にその状のものが多かったのであろう。請雨を需といい、その人を儒という。儒はもとその階層の、特に葬事に従うものであった。耎は懦弱の人、耑は柔毛の生ずる意であろう。而を代名詞や接続詞・助詞に用いるのは、みな仮借義である。
次(ジ・6画)


甲骨文/史次鼎・西周早期
初出:初出は甲骨文。
字体:現行字体の字形は「冫」+「欠」だが、甲骨文の字体は「𠂤」の下に「一」または「二」。「𠂤」は兵士が携行する兵糧袋で、”軍隊”を意味する。下の数字は部隊番号と思われ、全体で”予備兵”を意味する。原義は”予備”。
音:カールグレン上古音はtsʰi̯ər(去)。
用例:「甲骨文合集」7353に「乙巳卜□貞王勿次于曾」とあり、”やどる”・”とどまる”と解せる。
「漢語多功能字庫」によると、金文には氏族名・人名に用いる例が多い。
学研漢和大字典
会意。「二(並べる)+欠(人が体をかがめたさま)」で、ざっと身のまわりを整理しておいて休むこと。軍隊の小休止の意。のち、物をざっと順序づけて並べる意に用い、次第に順序をあらわすことばになった。茨(シ)(かや草をざっと並べる)・資(ざっと並べて整えた材料)などと同系。類義語に番。異字同訓に次「事件が相次ぐ。富士山に次ぐ山。取り次ぐ。次の間」 継「布を継ぐ。跡を継ぐ。引き継ぐ。継ぎ目。継ぎを当てる」 接「木を接ぐ。骨を接ぐ。接ぎ木」。
語義
- {名詞}つぎ。並んだもののうち、はじめのもののつぎ。「次年」「敢問其次=敢へて其の次を問ふ」〔論語・子路〕
- {動詞}つぐ。第一のものの下に位する。また、第一のもののあとに続く。「君又次之=君又これに次ぐ」「相次去世=相ひ次いで世を去る」。
- {副詞}つぎに。ついで。そのあとに続いて。「次叙病心=次に病む心を叙す」〔白居易・与微之書〕
- {名詞}順序。「序次」「班次(並べた順序)」「以次進至陛=次を以て進み陛に至る」〔史記・荊軻〕
- {単位詞}物事の回数・度数を数えるときのことば。また、物事の順序をあらわすことば。「数次(数回)」。
- {名詞}ある行為をしたとき。そのさい。「参内之次(サンダイノジ)(宮中にまいったとき)」。
- (ジス){動詞}やどる。とまる。もと、軍隊がざっと部署をととのえて宿営する。また、旅の間に一日だけとまる。「旅次(宿屋。また、旅の途上)」「師退次于召陵=師退きて召陵に次る」〔春秋左氏伝・僖四〕
- {名詞}星のとまる星座。また広く物のやどる場所。「胸次(むねのところ)」「席次(席のある所)」。
- 「造次」とは、そそくさと物をかたづけたり、あつらえたりすることから、あわただしい短時間のこと。
字通
[象形]人が咨嗟(しさ)してなげく形。口気のもれている姿である。〔説文〕八下に「前(すす)まず。精(くは)しからざるなり」とし、二(に)声とするが、二に従う字ではなく、〔説文〕の訓義の意も知られない。次は咨(なげ)き訴えるその口気を示す形。咨は祈るとき、その口気を祝詞の𠙵(さい)に加える形。神に憂え咨(なげ)いて訴え、神意に諮(はか)ることをいい、咨は諮の初文。そのたち嘆くさまを姿という。第二・次第の意は、おそらくくりかえすことから、また「次(やど)る」は軍行のときに用いるもので、古くは![]() (し)の字義にあたり、音を以て通用するものであろう。古文の字形は、他に徴すべきものがなく、中島竦の〔書契淵源〕に、婦人の首飾りを〔儀礼、士冠礼〕に次と称しており、その象形の字であろうという。〔説文〕の解は、〔易、夬、九四〕「其の行、次且(じしょ)」の語によって解したものであろうが、次且は二字連語、そこから次の字義を導くことはできない。
(し)の字義にあたり、音を以て通用するものであろう。古文の字形は、他に徴すべきものがなく、中島竦の〔書契淵源〕に、婦人の首飾りを〔儀礼、士冠礼〕に次と称しており、その象形の字であろうという。〔説文〕の解は、〔易、夬、九四〕「其の行、次且(じしょ)」の語によって解したものであろうが、次且は二字連語、そこから次の字義を導くことはできない。
耳(ジ・6画)
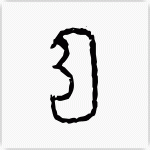

甲骨文/亞耳且丁尊・西周早期
初出:初出は甲骨文。
字形:みみを描いた象形。原義は”みみ”。
音:カールグレン上古音はȵi̯əɡ(上)。
用例:殷代末期から族徽(家紋)の用例があり、西周早期から地名・人名に用いられた。動詞”問う”・”聞く”の用例は戦国時代から。
「漢語多功能字庫」によると、甲骨文では原義と国名・人名に用いられ、金文でも同様だったが、”…のみ”のような形容詞・副詞的用法は、出土物からは確認できない。
学研漢和大字典
象形。みみを描いたもので、柔らかいの意を含む。餌(ジ)(柔らかいすりえ)・而(ニ)・(ジ)(柔らかいひげ)などと同系。草書体をひらがな「に」として使うこともある。
語義
-
- {名詞}みみ。柔らかいみみ。音を聞く役目をする器官。「耳朶(ジダ)」「側耳=耳を側つ(聞き耳をたてる)」「六十而耳順=六十にして而耳順ふ」〔論語・為政〕
- {名詞}物の両わきについたみみ状をしたもの。「鼎耳(テイジ)(かなえの両わきの突き出た所)」。
- {動詞・形容詞}みみからはいる。みみで聞いた。「耳聴途説(聞いたうわさや立ち話)」。
- {助辞}のみ。→語法「①」▽…而已(それでおわり、それだけ)をつづめて、…耳と書くようになった。
語法
①「~のみ」とよみ、文末におかれ、
- 「~なのである」と訳す。断定の意を示す。「且吾所為者極難耳=かつ吾が為す所の者は極めて難(かた)きのみ」〈たしかに、おれのやろうとすることは、とてつもなく困難なことだよ〉〔史記・刺客〕
- 「~だけ」「~であるにすぎない」と訳す。限定の意を示す。「復聚其騎、亡其両騎耳=またその騎を聚(あつ)むるに、その両騎を亡(うしな)ひしのみ」〈再び騎乗の部下を集めてみると、わずかに二騎を失っただけであった〉〔史記・項羽〕
②
- 「唯(直・但・止・徒)~耳」は、「ただ~のみ」とよみ、「ただ~であるにすぎない」「ただ~ばかりである」「わずかに~だけである」と訳す。限定の意を示す。「天下匈匈数歳者、徒以吾両人耳=天下匈匈(きゃうきゃう)たること数歳なるは、ただ吾両人をもってなるのみ」〈天下が何年も(戦乱に明け暮れ)騒然としているのは、ひとえに我ら二人のためだ〉〔史記・項羽〕
- 「独~耳」は、「ひとり~のみ」とよみ、「ただ~であるにすぎない」「ただ~ばかりである」「わずかに~だけである」と訳す。限定の意を示す。「能用秦柄者、独張儀可耳=よく秦の柄を用ゐん者は、独り張儀可なるのみ」〈秦の権力を自由にできる者は、張儀だけである〉〔史記・張儀〕
字通
[象形]耳の形。〔説文〕十二上に「聽くことを主(つかさど)るものなり」という。耳と目とは、神聖に接するのに最も重要なもので、耳目の聡明なのを合わせて聽(聴)という。聞の卜文は耳の下に壬(てい)(人の挺立する形)をかき、それに祝禱の器である𠙵(さい)を加えると、聖となる。聖とは神の声を聴きうる人をいう。聖に呪飾のある目と心とを加えた形が聽(聴)である。終助詞に用いるのは、而已(じい)の音にあてたもので、仮借の用法である。
佴(ジ・8画)

璽彙3561
初出:初出は戦国文字。
字形:「亻」+「耳」。
音:カールグレン上古音はȵi̯əɡ(去、韻目「志」字母「日」)で、同音多数。而とそれを部品とする漢字群:栭”ますがた”、胹”煮る”、鮞”はらご”、耳とそれを部品とする漢字群:咡”口(元)”、餌”粉餅”、珥”みみだま”、衈”ちぬる”、刵”耳切る”、眲”あなどる”。去声・韻目「代」字母「泥」の音は不明。
用例:「先秦甲金文簡牘詞彙資料庫」には記載が無く、先秦の用例不明。
論語時代の置換候補:同音の「而」「耳」に、”秩序”・”はじ”の語義は無い。
備考:定州竹簡論語では三ヶ章に「佴」字を用いているが、全て現伝論語では「恥」になっている。その三ヶ章いずれも、「恥」と解さないと文意が通らない。ただし定州本は「恥」字も二ヶ章で用いており、使い分けがあるのか、単なる混用かは不明。本サイトでは、とりあえず「佴」を「恥」として解することにした。論語語釈「恥」も参照。
『学研漢和大字典』『字通』には条がなく、『大漢和辞典』のみ。「漢語多功能字庫」には語釈などの情報が無い。

貳/弐(ジ・6画)

琱生簋・西周末期
初出:初出は西周末期の金文。新字体は「弐」。
字形:「戈」+「二」+「貝」”財貨”で、字形の解釈は未詳。原義は”二”。論語語釈「二」を参照。
音:「ニ」は呉音。カールグレン上古音はȵi̯ər(去)。
用例:「漢語多功能字庫」によると、金文では”二”の意に(琱生簋・西周末期)、戦国の金文では”ふたごころ”の意に用いた(中山王方壺・戦国末期)。
学研漢和大字典
会意兼形声。弍は「弋(ヨク)(棒ぐい)+(音符)二」で、二本並んだ棒を示す。貳は「貝(財貨)+(音符)弍」。「弐」は「貳(ジ)」の古い字形を用いて、筆画を簡単にしたもの。証文や契約書では、改竄(カイザン)・誤解を防ぐために「二」の代わりに用いることがある。
語義
- {数詞}ふたつ。くっついて並んだふたつ。《同義語》⇒二。
- {動詞}ふたたびする。二度くりかえす。「不弐過=過ちを弐せず」〔論語・雍也〕
- {動詞}そう(そふ)。そえる(そふ)。ふたつくっつく。そばにくっつける。「弐車(ジシャ)(そえぐるま)」「副弐(フクジ)(そえもの)」。
- {動詞}そむく。ふたつに離れる。「弐心(ふたごころ)」「有弐=弐く有り」。
《日本語での特別な意味》すけ。四等官で、大宰府の第二位。
字通
[形声]旧字は貳に作り、弍(じ)声。〔説文〕に、字を貝部六下に属し、「副益なり。貝に從ひ、弍聲」とし、「弍は古文二なり」という。貝は鼎の省形。鼎銘を刻することを則・劑(剤)といい、円鼎は則、方鼎を劑といい、盟誓・契約を約剤という。弍に従うのは、戈(か)(刀)を以て刻銘し、その副本を作る意、それで副弐・弐益の意となる。〔周礼、秋官、大司寇〕「大史・内史・司會及び六官、皆其の貳を受けて之れを藏す」とは副本の意。〔周礼、天官、酒正〕に「大祭には三貳、中祭には再貳、小祭には壹貳」とは副弐の器をいう。金文の〔琱生𣪘(ちようせいき)〕に、分数的な表示として「其の貳」「其の參」を用いる例がある。字は盟誓の副弐の意であるが、のち疑弐・違背の意となった。
慈(ジ・13画)

中山王□壺・戦国末期
初出:初出は戦国末期の金文。
字形:「茲」tsi̯əɡ(平)”蚕の繭”+「心」で、「茲」には”しげる”の語釈もあり、「滋」の原字。原義は恐らく”慈しみの心”。字形は「茲」tsi̯əɡ(平)”蚕の繭”+「心」で、「茲」には”しげる”の語釈もあり、「滋」の原字。原義は恐らく”慈しみの心”。
音:カールグレン上古音はdzʰi̯əɡ(平)。同音に「字」”やしなう・はぐくむ”・「孳」(甲骨文・金文無し)。藤堂上古音はdziəg。
論語時代の置換候補:『大漢和辞典』で音ジ訓いつくしむは、この文字しか載っていない。候補として「仁」があるが、藤堂上古音nienで音通しているとは言いかねる。
同音の「字」の原義は”屋根の下で子を大切に育てるさま”であり、論語時代の置換候補。春秋末期の「余贎兒鐘」(集成183)では「字」を「慈」と釈文する。
学研漢和大字典
会意兼形声文字で、茲(ジ)は、草の芽と細い糸とをあわせて、小さいものが成長しふえることを示す会意文字。慈は「心+〔音符〕茲」で、小さい子を育てる親心のこと。滋(ジ)(ふえる)・孳(ジ)(子どもを育てる)と同系のことば、という。
語義
- {動詞・形容詞}いつくしむ。母が子を大事に育てる。また、その愛情の深いさま。「慈母」「敬老慈幼=老を敬ひ幼を慈しむ」〔孟子・告下〕
- {動詞・形容詞}いつくしむ。父母のような愛情で、上の者が下の者をかわいがる。また、そのさま。「君之不慈臣、此亦天下之所謂乱也=君の臣を慈しまざる、此れ亦た天下の所謂乱れなり」〔墨子・兼愛上〕
- {形容詞}情け深い。また、愛情がこまやかな。「雖孝子慈孫、百世不能改也=孝子慈孫と雖も、百世改むること能はざるなり」〔孟子・離上〕
- {名詞}いつくしみ。「一曰慈=一に曰はく慈」〔老子・六七〕
- {名詞}母親のこと。《対語》⇒厳。「家慈(私の母)」。

字通
[形声]声符は兹(じ)。兹に孳生・孳育の意があり、その情を慈という。〔説文〕十下に「愛なり」とみえる。古くは子をその意に用い、金文の〔大盂鼎(だいうてい)〕に「故に天、異臨(よくりん)し、子(いつくし)みて先王を灋(法)保したまへり」、また〔也𣪘(やき)〕に「懿父(いほ)は廼(すなは)ち子まん」のように用いる。
爾(ジ・14画)


甲骨文/洹子孟姜壺・春秋末期
初出:初出は甲骨文。
字形:剣山状の封泥の型の象形で、原義は”判(を押す)”。のち音を借りて二人称を表すようになって以降は、「土」「玉」を付して派生字の「壐」「璽」が現れた。
![]()
慶大蔵論語疏では異体字「尓」と記す。「唐高延貴造彌陁像記」刻。また「𠂢」”支流”字と記し、「尓」と傍記する。別字を転用した遊び字。また異体字「尒」と記す。上掲「白石神君碑」(後漢)刻。
音:カールグレン上古音はȵi̯ăr(上)。王力上古音はȵǐei(上)。
用例:「漢語多功能字庫」によると、甲骨文では人名・国名に用い、金文では二人称を意味した(洹子孟姜壺・春秋末期)。
備考:派生字の「壐」の王力上古音はsǐei(上)、「璽」のカールグレン上古音はsni̯ăr(上)。派生字の「壐/璽」も参照。
”そうであるさま”の意は、カールグレン上古音で近音の「然」ȵi̯an(平)の空耳アワーでしかない。また「然」がこの語義を獲得するのは戦国時代であり、論語の時代の漢語ではない。論語語釈「然」も参照。
学研漢和大字典
象形。柄にひも飾りのついた大きいはんこを描いたもの。璽(はんこ)の原字であり、下地にひたとくっつけて印を押すことから、二(ふたつくっつく)と同系のことば。またそばにくっついて存在する人や物をさす指示詞に用い、それ・なんじの意をあらわす。邇(ジ)(そばにくっつく)・尼(ニ)・(ジ)(そばにくっつく人)と同系。▽現代北京語の你(ニ)はその子孫に当たることばで、你は儞の略字である。草書体をひらがな「に」として使うこともある。
語義
- {代名詞}なんじ(なんぢ)。近くにいるあい手をさす第二人称のことば。《対語》⇒我。「爾愛其羊=爾は其の羊を愛しむ」〔論語・八飲〕。「爾我之間」。
- {指示詞}しかり。しかる。それ。その。近くにある事物や前に述べた事物・事がらを示すことば。それ。そのような。《類義語》然。「問君何能爾=君に問ふ何ぞ能く爾るやと」〔陶潜・飲酒〕。「君爾妾亦然=君爾り妾も亦た然り」〔古楽府・焦仲卿妻〕
- {指示詞}しかり。そうだと肯定することば。《類義語》然(シカリ)。
- {助辞}形容詞につく助詞。もと、そのようなの意を含んでいた。「徒爾(トジ)(いたずらに)」「卓爾(タクジ)(すっくりと高く)」「莞爾(カンジ)(にっこりと)」「使己僕僕爾亟拝也=己をして僕僕爾として亟りに拝せしむるなり」〔孟子・万下〕
- {助辞}のみ。→語法「①」。
- {形容詞}ちかい(ちかし)。▽邇(ジ)(ちかい)に当てた用法。「爾雅(ジガ)(書名。雅言にちかいとの意)」。
語法
①「~のみ」とよみ、文末におかれ、
- 「~なのである」と訳す。断定の意を示す。「有本者如是、是之取爾=本有る者はかくの如(ごと)し、これをこれ取れるのみ」〈本源のあるものは、このようである、(孔子は)ほかならぬこの点をとらえたのである〉〔孟子・離下〕
- 「~だけ」「~であるにすぎない」と訳す。限定の意を示す。《同義語》耳・而已。「王大将軍当下、時咸謂無縁爾=王大将軍下らんとするに当たり、時に咸(みな)縁無(な)しと謂ふのみ」〈王大将軍(王敦)が(謀反を起こして都へ向かおうと長江を)攻め下ったとき、誰もがそんなはずはないと言うだけであった〉〔世説新語・方正〕
②
- 「唯(直・但・止・徒)~爾」は、「ただ~のみ」とよみ、「ただ~であるにすぎない」「ただ~ばかりである」「わずかに~だけである」と訳す。限定の意を示す。「新婦所乏唯容爾=新婦の乏しき所はただ容のみ」〈わたくしに欠けているのは器量だけです〉〔世説新語・賢媛〕
- 「独~爾」は、「ひとり~のみ」とよみ、「ただ~であるにすぎない」「ただ~ばかりである」「わずかに~だけである」と訳す。限定の意を示す。
③「~云爾」は、「~のみ」「しかいう」とよみ、「~というわけである」と訳す。文末におかれ、叙述をしめくくる役割を持つ。「発憤忘食、楽以忘憂、不知老之將至云爾=憤(いきどほ)りを発して食を忘れ、楽しみてもって憂ひを忘れ、老の將に至らんとするを知らざるのみ」〈(学問に)発憤しては食事も忘れ、(道を)楽しんでは心配事をも忘れ、やがて老いがやってくることにも気付かずにいるというわけだ〉〔論語・述而〕
字通
[象形]人の正面形の上半部と、その胸部に㸚(り)形の文様を加えた形。㸚を独立した字と解すれば会意となるが、全体象形と解してよい字である。㸚はその文身の模様。両乳を中心として加えるもので、爽(そう)・𡚐(せき)などは女子の文身を示す。爽の上半身の形が爾にあたる。みな爽明・靡麗(びれい)の意のある字である。〔説文〕三下に「麗爾なり。猶ほ靡麗のごときなり」とし、その字形は冂(けい)と㸚とに従い「其の孔(あな)㸚(うるは)し。𡭗(じ)聲」と形声に解し、窓飾りの格子の美しいさまであるという。㸚を二爻(こう)、疏窓の形とするものであるが、爽の字形からも知られるように、両乳の部分に文身を加えた形。通過儀礼の際に呪禁として加えるもので、おそらく死喪のとき、朱を以て絵身を施したものであろう。ゆえにまた靡麗の意となる。二人称に用い、また状態詞の語末、接続の語などに用いるのはみな仮借。〔詩、小雅、采薇〕「彼の爾(でい)たるは維(こ)れ何ぞ」の爾は薾の仮借。薾は文身の美を、花に移していうものであろう。
邇(ジ・18画)
初出は楚系戦国文字。論語の時代に存在しない。カールグレン上古音はȵi̯ăr(上)。同音は爾”はんこ・お前”(上)のみ。
学研漢和大字典
会意兼形声。「辶+(音符)爾(ジ)(紙や布にくっつけて押すはんこ)」で、ぺったりとねばりつくの意を含む。爾は璽の原字。爾(はんこ、身ぢかにいる相手)・二(ふたつくっつく)・昵(ジツ)(身ぢかになじむ)と同系。
語義
- {形容詞・名詞}ちかい(ちかし)。ちかい。また、ちかい所。《類義語》近。「遐邇(カジ)(遠近)」「道在邇而求諸遠=道は邇きに在りてしかも諸を遠きに求む」〔孟子・離上〕
- {形容詞}ちかい(ちかし)。身ぢかである。卑近である。「邇言(ジゲン)」。
字通
[形声]声符は爾(じ)。〔説文〕二下に「近きなり」という。〔書、舜典〕「遠きを柔らげ邇(ちか)きを能(をさ)む」を、金文の〔大克鼎(だいこくてい)〕に「遠きを■(卣+夔)(やは)らげ𤞷(ちか)きを能む」のようにいい、𤞷が邇のもとの字、邇はのちの形声字である。𤞷は土主の上に木を植え、犬牲を供えて祀る形で、ときには女が跪(ひざまず)いて拝する形を加えている例もあり、産土神(うぶすながみ)のような観念を示す字であろう。その本貫の地を示し、ゆえに邇近の意となったものと思われる。
壐/璽(ジ・19画)


「壐」十鐘・戦国秦/「璽」『説文解字』籀文
初出:初出は斉系戦国文字。ただし字体は「鉨」。現行字体の初出は秦戦国文字。下が「玉」になるのは後漢の『説文解字』から。
字形:「爾」”はんこ”+「土」または「玉」で、前者は封泥、後者は玉で作ったはんこを意味する。部品の「爾」ȵi̯ăr(上)が原字。
音:カールグレン上古音はsni̯ăr(上)。同音無し。
用例:戦国最末期「睡虎地秦簡」法律答問146に「亡久書、符券、公璽、衡羸(纍),已坐以論,後自得所亡,論當除不當?不當。」とあり、”印章”と解せる。
論語時代の置換候補:部品の「爾」。詳細は論語語釈「爾」を参照。
備考:「漢語多功能字庫」は「壐」条はなく、「璽」条には見るべき情報がない。
学研漢和大字典
会意兼形声。爾(ジ)は、はんこの形を描いた象形文字で、璽の原字。上部はつまみで左右に飾りのひもがついており、下は印にほった文字の形。璽は、爾がのちに指示詞に用いられるようになったので意符の玉を添えたもの。璽は「玉+(音符)爾」。紙などに押してくっつける印。くっつくの意を含む。二(ふたつ、くっつく)・邇(ジ)(近くにくっつく)・泥(ねばるどろ)と同系。
語義
- {名詞}しるし。また、特に天子*の印章。秦(シン)以前は諸侯・卿大夫(ケイタイフ)の印もいったが、秦の始皇帝以後、天子の印のみをいうようになった。「伝国璽」「皇帝六璽」。
*「天子」の言葉が中国語に現れるのは西周早期で、殷の君主は自分から”天の子”などと図々しいことは言わなかった。詳細は論語述而篇34余話「周王朝の図々しさ」を参照。
字通
[形声]声符は爾(じ)。〔説文〕十三下に土に従う字とし、「王者の印なり。以て土を主(つかさど)る」(段注本)とし、璽を籀文とする。古く銅印の類は鉩に作り、鋳印であった。
肉(ジク・6画)
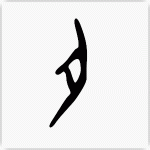

甲1823/師𡘇父鼎・西周中期
初出:初出は甲骨文。
字形:初出の字形は「月」によく似ており、切り分けた肉の象形。戦国では木に吊して血抜きをする字形が見られる。
![]()
慶大蔵論語疏は異体字「〔宀二八〕」と記す。「魏孫遼浮圖銘」(北魏)刻字近似。
音:カールグレン上古音は声母のȵ(入)のみ。藤堂上古音はniok。「ニク」は呉音。
用例:甲骨文合集22324.4に「乙丑卜貞婦爵肉子無疾」とあり、王の夫人の一人に酒とつまみの肉を与えても、腹の子にさわりがないだろうか、と占っている。
西周中期「師𡘇父鼎」(集成2813)に王の下賜品として「戈琱戈肉」とあり、彫刻の入った玉と、細かく刻んだ”肉”を与えたと解せる。
学研漢和大字典
象形。筋肉の線が見える、動物のにくのひときれを描いたもの。▽肩・肝などの字の月の部分や、祭・然の字の左上の部分は肉の字の変形である。柔(ニュウ)・(ジュウ)(やわらかい)などと同系。
語義
- {名詞}しし。柔らかくねばりのあるにく。《同義語》⇒宍。「懸肉為林=肉を懸けて林と為す」〔史記・殷〕。「三月、不知肉味=三月、肉の味を知らず」〔論語・述而〕
- {名詞・形容詞}霊魂に対して、人のからだ。また、なま身の。「肉慾(ニクヨク)」「骨肉(同じ親からうまれた親族)」「霊肉一致」。
- {名詞}にくに似た柔らかい物。「果肉」「印肉」。
- 《日本語での特別な意味》
①にく。牛肉のこと。
②にく。印肉のこと。
③にく。大体できた物事の構成につけ加えるべき細かい点。
④にく。物の厚み。
字通
[象形]切りとった肉塊の形。〔説文〕四下に「胾肉(しにく)なり」とあり、大きな一臠(れん)の肉をいう。〔釈名、釈形体〕に「肉は柔なり」とあり、その古音は相近い声であった。
七(シツ・2画)
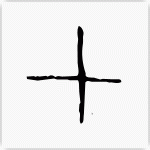

甲骨文/乙鼎・春秋晚期
初出:初出は甲骨文。
字形:たてよこに入れた切れ目。これがなぜ数字の”7”を意味するようになったかは、音を借りた仮借と解する以外に方法が無い。原義は数字の”なな”。「切」の原字とされるが、「十」形を”切る”と解せる出土物は存在しない。論語語釈「切」を参照。
音:「シチ」は呉音。カールグレン上古音はtsʰi̯ĕt(入)。
用例:「漢語多功能字庫」によると、甲骨文から戦国の竹簡まで一貫して、数字の”なな”の意で用いられている。
学研漢和大字典
指事。縦線を横線で切り止め、端を切り捨てるさまを示す。また、分配するとき、三と四になって、端数を切り捨てねばならないことから、中途はんぱな印象をもつ数を意味する。▽七は切の原字。付表では、「七夕」を「たなばた」と読む。▽「七日(なのか)」は、「なぬか」とも読む。▽証文や契約書では、改竄(カイザン)や誤解をさけるため「漆」「耽」と書くことがある。
語義
- {数詞}ななつ。「其子七兮=其の子七つ兮」〔詩経・曹風・諍鳩〕
- {数詞}なな。順番の七番め。「七位」。
- {副詞}ななたび。「七戦皆獲=七たび戦ひて皆獲」〔春秋左氏伝・哀二〕
- 《日本語での特別な意味》ななつ。昔の時刻の名。今の午前、または午後の四時。
字通
[仮借]もと、切断した骨の形。切は骨を刀で切る形。これを数の七に用いるのは、その音を仮借したものである。〔説文〕十四下に「陽の正なり。一に從ふ。微陰、中より衺(なな)めに出づるなり」と陰陽の象によって字形を解するが、卜文・金文の字形は十の縦画を短くした形。膝などの骨節の部分の形象と思われる。七は聖数とされ、〔文選〕に収める七の類、〔七発〕〔七啓〕などは、一種の呪誦文学であろうと思われる。
失(シツ・5画)


失鼎・殷代末期或西周早期/揚簋・西周晚期
初出:初出は殷代末期の金文。
字形:字形は頭にかぶり物をかぶり、腰掛けた人の横姿。それがなぜ”うしなう”の意になったかは明らかでないが、「羌」など頭に角型のかぶり物をかぶった人の横姿は、隷属民を意味するらしく(→論語語釈「羌」)、おそらく所属する氏族を失った奴隷が原義だろう。

「美」甲骨文
音:カールグレン上古音はɕi̯ĕt(入)。同音は「室」(入)のみ。論語語釈「室」を参照。
用例:初出は上掲の殷代末期『殷周金文集成』1028「失鼎」だが、「失」の一字があるだけで語義が分からない。同時期の7347「失爵」も同様。族徽=家紋のようなものだろうか。
西周早期の『殷周金文集成』5421「士上卣」文末に「用乍父癸寶彝。臣辰册失。」とあるが、語義が分からない。「臣辰失を册す」と読むのだろうが、あるいは”過失”を意味するのだろうか。9454「士上盉」にも同文が見える。
西周中期『殷周金文集成』4268「王臣簋」に「乎內史失册命王臣。」とあるのは明らかに人名で、西周末期の4285「諫𣪕」にも同文が見える。4294「揚𣪕」に「王乎內史。史失册令揚。」とあるのもおそらく同じ。
戦国の竹簡からは、”うしなう”の語義が明瞭になる。
甲骨文では、人の横姿「人」は人間一般のほかに隷属民を意味しうるが、正面形「大」はかぶり物の有無や形にかかわらず、下級者を意味しない。論語語釈「美」を参照。
「漢語多功能字庫」「国学大師」は戦国竹簡以降にのみ言及。
学研漢和大字典
会意。「手+よこへ引くしるし」で、手中のものがするりと横へ抜け去ることを示す。忘佚(ボウイツ)の佚(=逸)と同系。また更迭(コウテツ)の迭(横に抜けて入れかわる)・跌(テツ)(足がするりと横にすべる)とも縁が深い。
語義
- (シッス){動詞・名詞}うしなう(うしなふ)。とり逃がす。するりとなくすること。なくしたもの。《対語》⇒得・守・持。「損失」「猶恐失之=なほこれを失はんことを恐る」〔論語・泰伯〕
- (シッス){動詞}うしなう(うしなふ)。やるべき仕事や時期・道筋などを見のがす。「失其事=其の事を失ふ」「急撃勿失=急ぎ撃ちて失ふこと勿かれ」〔史記・項羽〕
- {名詞}あやまち。やりすぎや見のがしのしくじり。「失敗」「過失」「咎己之失=己の失を咎む」〔王陽明・勧学〕
- (シッス){動詞}うしなう(うしなふ)。中に押さえこんでおくべきものを押さえきれずに、またはうっかりして外へ出してしまう。「失言」「失火」。
- {動詞}するりと抜け去る。また、なくなる。▽佚(イツ)・逸に当てた用法。「失念」。
- 《日本語での特別な意味》野球で、「失策」の略。エラーのこと。「敵失」「凡失」。
字通

手を挙げて舞い、恍惚の状態にあることを示す。祝禱してエクスタシーの状態になること。〔説文〕十二上に「縦つなり」とし、字を手に従い、乙声とするが、乙に従う字ではない。似た字形に夭があり、身を傾けて舞う形。また夨は頭を傾けて舞う形。失は自失の意。すべて亡失のことをいう。
訓義
1)うしなう、気を失う、忘我・自失の状態となる。2)ものをうしなう、わすれる、にがす。3)あやまつ、あやまる、みだれる。4)たがう、くるう、ほしいままにする。5)佚と通じ、たのしむ。6)逸と通じ、のがれる。
大漢和辞典
實/実(シツ・8画)


㝬簋・西周末期/國差𦉜・春秋
初出:初出は西周末期の金文。
字形:「宀」”屋根”+「貫」”タカラガイのさし”。家に財貨がつまっているさま。原義は”充実”。
音:カールグレン上古音はʰi̯ĕt(入)。「ジツ」は慣用音。
用例:西周末期「㝬𣪕」(集成4317)に「實朕多禦」とあり、”まことに”と解せる。
春秋時代「國差𦉜」(集成10361)に「用實旨酉」とあり、”満たす”と解せる。
学研漢和大字典
会意。「宀(やね)+周(いっぱい)+貝(たから)」で、家の中に財宝をいっぱい満たす意を示す。中身がいっぱいで欠け目がないこと。また、真(中身がつまる)は、その語尾がnに転じたことば。質(中身)・窒(チツ)(ふさがる)・室(いきづまりのへや)などと同系。類義語の満は、容器にいっぱいに物をみたすこと。充は、中身をいっぱいにつめること。
語義
- {名詞}み。中身のつまった草木のみ。「果実」「草木之実足食也=草木の実食らふに足る」〔韓非子・五蠹〕
- {動詞}みのる。草木のみの中身がつまる。「秀而不実者有矣夫=秀して実らざる者有り」〔論語・子罕〕
- {動詞}みちる(みつ)。内容がいっぱいつまる。《対語》⇒虚。「充実」「君之倉廩実=君之倉廩実つ」〔孟子・梁下〕
- (ジツナリ){形容詞}まこと。内容があってそらごとでない。《対語》⇒虚・空。「事実」「后聴虚而黜実兮=后は虚を聴きいれて実を黜く」〔楚辞・逢紛〕
- (ジツニ){副詞}まことに。ほんとうに。実際に。「天実為之=天実にこれを為す」〔詩経・癩風・北門〕
- 「其実(ソノジツ)」とは、文頭につけて、「じつをいうと」、「実際は」の意味をあらわす。「其実皆什一也=其の実は皆什に一也」〔孟子・滕上〕
- 《日本語での特別な意味》
①じつ。真心。親身の心。「実のある人」。
②み。内容。「実のある話」。
字通
[会意]旧字は實に作り、宀(べん)+貫(かん)。〔説文〕七下に「富なり」とし、「貫を貨物と爲す」(段注本)とするが、宀は宗廟、貫は貝貨を貫き連ねた形で、貝を宗廟に献ずる意。その貫盈するところから、充実の意となる。金文の〔散氏盤(さんしばん)〕に鼎に従う字があり、また〔国差𦉜(こくさたん)〕の字は、上部が冖(べき)の形に近い。鼎中にものを充たして供える意ともみられる。充実の意から誠実・実行の意となり、その副詞に用いる。
室(シツ・9画)


甲骨文/杕氏壺・春秋末期
初出:初出は甲骨文。
字形:「宀」”屋根”+「矢」+「一」”止まる”で、矢の止まった屋内のさま。原義は人が止まるべき屋内、つまり”うち”・”屋内”。
音:カールグレン上古音はɕi̯ĕt(入)。同音は「失」(入)のみ。論語語釈「失」を参照。
用例:「漢語多功能字庫」によると、甲骨文では原義に、金文では原義(善鼎・西周中期)のほか、”一族”(杕氏壺・春秋末期)の意に用いた。戦国時代の金文では、「王室」の語が見える(曾姬無卹壺・戦国早期)。戦国時時代の竹簡では、原義・”一族”の意に用いた。
学研漢和大字典
会意兼形声。至は、矢がぴたりと目標まで届いたさま。奥までいきづまり、その先へは進めない意を含む。室は「宀(やね、いえ)+(音符)至」で、いちばん奥のいきづまりのへや。窒(チツ)(いきづまり)・膣(チツ)と同系。類義語に家。
語義
- {名詞}へや。奥まったへや。《対語》⇒堂(表の広間)。「升堂矣、未入於室也=堂に升れり、いまだ室に入らざるなり」〔論語・先進〕
- {名詞}むろ。奥深くふさいだ穴。「氷室(ヒムロ)」。
- {名詞}いえ(いへ)。すまい。うち。「家室」「盗愛其室、不愛其異室=盗は其の室を愛して、其の異室を愛せず」〔墨子・兼愛上〕
- {単位詞}家の戸数を数えることば。《類義語》戸。「千室之邑」〔論語・公冶長〕
- {名詞}さや。刀剣のさや。「刀室」「剣長操其室=剣長くして其の室を操る」〔史記・荊軻〕
- {名詞}王朝をたてた一家。「周室」「功顕於漢室=功漢室に顕かなり」〔漢書・蘇武〕
- {名詞}奥べやに住む夫人。《対語》家。「室人(つま)」「令室(奥さま)」「丈夫生而願為之有室=丈夫生まれてはこれが為に室有らんことを願ふ」〔孟子・滕下〕
- {名詞}二十八宿の一つ。規準星は今のペガスス座にふくまれる。はつい。「定」ともいう。
字通
[会意]宀(べん)+至。至は矢の至るところ。〔説文〕七下に「實なり」と音義的に解し、また「室屋は皆至に從ふ。止まる所なり」(段注本)と、人の至り、止まる意を以て解するが、至は矢の至る意。矢を放って、その造営の地を卜し、祓(はら)うことを意味する。室は祖霊の安んずるところで、いわゆる大室。屋は板屋で殯(かりもがり)する所である。臺(台)も至に従い、天を祀り、神明に接する所をいう。家・冢が犬牲を埋めて奠基(てんき)し、修祓する儀礼を示す字であるのと同じ。卜辞に中室・南室・血室などの名があり、みな祭祀の場所。また金文の冊命(さくめい)儀礼はすべて宗廟大室において行われている。金文の〔大豊𣪘(たいほうき)〕に「王、天室に祀る」とあり、室とはもと祭祀を行うところをいう。
疾(シツ・10画)


甲骨文/毛公鼎・西周晚期
初出:初出は甲骨文。
字形:「大」”人の正面形”+向かってくる「矢」で、原義は”急性の病気”。現行の字体になるのは戦国時代から。別にカールグレン上古音不明の「疒」の字が甲骨文からあり、”疾病”を意味していたが、「漢語多功能字庫」によると音が近かったので混同されたという。
音:カールグレン上古音はdzʰi̯ət(入)。
用例:「甲骨文合集」6.2に「貞其疾七月」とあり、「とう、其れやまいあらんか。七月」と読め、”やまい”と解せる。
西周末期「毛公鼎」(集成2841)に「敃天疾畏」とあり、「みだれて天とくいからん」と読め、”急速に”と解せる。
その他春秋末期までに人名の例が見られる。
「漢語多功能字庫」によると、甲骨文では、”疾病”を意味し、金文では加えて、”急いで”の意が(毛公鼎・西周)、戦国の竹簡では加えて人名に用いられたという。
学研漢和大字典

会意。甲骨文字は人をめがけて進む矢を示す会意文字。金文以下は「容+矢」で、矢のようにはやく進む、また、急に進行する病気などを意味する。迅(シン)・(ジン)は、疾の語尾がnに転じた語で、疾にきわめて近い。類義語に早・病。
語義
- {形容詞}はやい(はやし)。スピードがはやい。あっというまに進むほどはやい。《類義語》速。「疾走」「疾風迅雷(シッフ°ウジンライ)(急激な風や雷)」。
- {名詞}やまい(やまひ)。急にひどくなる病気。急性で悪性の病気。転じて、広くやまいのこと。《類義語》病。「疾病」「父母唯其疾之憂=父母にはただその疾(やま)ひをこれ憂へしめよ」〔論語・為政〕
- {名詞}つらいこと。くるしみ。悩み。悪いくせ。「民疾(人民にとってつらい悩み)」。
- {動詞}やむ。くるしむ。病気になる。また、つらいと思う。悩む。
- {動詞}にくむ。いやなことだとしてにくみきらう。《同義語》嫉。「疾之已甚=これを疾むこと已甚し」〔論語・泰伯〕
- {形容詞}にくらしそうに。いやがって。《同義語》嫉。「疾視(にくにくしげにみる)」。
字通
[会意]卜文・金文の字形は大(人の正面形)の腋(わき)の下に矢のある形。腋の下に矢を受け、負傷する意である。〔説文〕七下に「病なり」とし、矢(し)声の字とし、古文・籀文(ちゆうぶん)の二形を録するが、卜文・金文にくらべると字形は全く異なり、ことに籀文は智の初形に近い。のち疾病の意によって疒(だく)部に属する。矢創の意であるから、急疾・疾速の意がある。
瑟(シツ・13画)


花東130/包2.260
初出:初出は甲骨文とされるが、字形の由来・語義ともに不明で、『説文解字』の載せる古文に類似のため「瑟」に比定されたが、西周~春秋まで用例が無く、事実上の初出は楚系戦国文字。
字形:甲骨文とされる字形は琴状の弦楽器+人の正面形に見える。戦国文字の字形は多様で、ただし「兀」(ゴツ)形を必ず含む。おそらくテーブル状の楽器を示すか。
音:カールグレン上古音はʂi̯ĕt(入)。同音は存在しない。
用例:楚系戦国文字に楽器の名として見える。秦系戦国文字には見えない。
論語時代の置換候補:『大漢和辞典』で訓おおごとを持つ漢字は他に存在しない。
学研漢和大字典
会意。「ことの形+必(びっしりくっつく)」で、多くの弦をびっしりと並べて張った楽器。類義語に琴。
語義
- {名詞}おおごと(おほごと)。弦楽器の一つ。琴の大形のもので、弦を指でつまんで演奏する。古くは五十弦であったが、のち、二十五弦・十九弦・十五弦などになった。「由之瑟、奚為於丘之門=由の瑟、なんすれぞ丘の門においてせん」〔論語・先進〕
- 「瑟瑟(シツシツ)」とは、風のさっさっと吹くさま。
字通
[形声]声符は必(ひつ)。〔説文〕十二下に「庖犧(はうぎ)作る所の弦樂なり」とみえ、大琴をいう。必声とするが、〔説文〕所収の必声二十一文のうち、瑟声の字は他にない。古く神事に用い、その音は蕭瑟(せうしつ)、風の音や泉の流れる音などを形容する語に用いる。
※字通は篆書以降のみしか参照していないようだが、甲骨文を見れば必声でないと言う想定は当たっている。
漆(シツ・14画)

曾伯雨木二簠・春秋早期
初出:「国学大師」による初出は春秋早期の金文。「小学堂」による初出は戦国時代の金文。
字形:初出の字形は「雨」”樹木の刻み目+両手”+「桼」”樹液”。樹木に刻み目を入れて樹液をすくい取るさま。原義は”うるし”。
音:カールグレン上古音はtsʰi̯ĕt(入)。
用例:戦国の金文には「漆垣工師」「漆工」の文字列が見え、”うるし”と解せる。
「漢語多功能字庫」によると、(戦国の?)金文では地名に用いた。
論語では孔子の弟子・漆雕開の名として現れる。
学研漢和大字典
会意兼形声。右側の字は、木汁が一滴ずつしたたるさま。漆はそれをさらに水をそえたもの。うるしをシツと称するのは、おそらく、津(したたる汁)の語尾が転じたもの。あるいは、密切の切(ぴったり)と同系で、物をぴったりとくっつける役割に着目した命名であろう。証文や契約書で、改竄(カイザン)や誤解をさけるため「七」の代わりに用いることがある。(中国では柒の字を使う。)
語義
- {名詞}うるし。うるしの木。また、その樹液からつくった塗料。
- {形容詞・名詞}くろい(くろし)。うるしのようにまっくろいさま。また、その色。「漆黒」。
字通
[象形]漆の木より漆をとる形。木の幹に傷つけ、漆液の流れる形。〔説文〕六下に「木の汁なり、以て物を䰍(ぬ)るべきものなり。象形。桼、水滴の如くにして下る」という。いま漆の字を用いる。金文に■(上下に雨+桼)の字があり、古くは朱や黒に加えて用いたらしく、金文の賜与にみえる彤弓(とうきゆう)・彤矢(朱塗り)、■(偏:玄・旁:上下に𠂉+𧘇)弓(りよきゆう)・■(玄+𠂉+𧘇)矢(黒塗り)は、漆を加えて塗飾したものと考えられる。漆は東アジアの特産品であった。〔書、禹貢〕に兗(えん)州・予州より漆を貢することがみえる。
質(シツ/チ・15画)

丼人𡚬鐘・西周末期
初出:初出は西周末期の金文。
字形:「斦」”斧二ふり”+「貝」”財貨”で、「国学大師」によると初出の字は「哲」”さとる”と解されており(下掲)、字形の意味するところは不明。
音:「シツ」(入)の音で”中身”を、「チ」(去)の音で”抵当”を意味する。カールグレン上古音はti̯əd(去)またはȶi̯ət(入)。
用例:西周末期「井人鐘」(集成19)に「克質(慎)氒(厥)德」とあり、「質」は「慎」”つつしむ”と釈文されている。春秋末期に至るまでの用例は全て同様。
備考:「漢語多功能字庫」には見るべき情報がない。
学研漢和大字典
会意。斤(キン)は、重さを計る重りに用いたおの。質は「斤二つ(重さが等しい)+貝(財貨)」で、Aの財貨と匹敵するだけなかみのつまったBの財貨をあらわす。名目に相当するなかみがつまっていることから、実質、抵当の意となる。実(ジツ)(なかみ)・緻(チ)(きめ細かくなかみがつまる)・室(シツ)(つまったへや)・窒(チツ)(つまる)などと同系。また真(シン)(なかみがつまる)は、その語尾がnに転じたことば。
語義
シツ(入)
- {名詞}もと。しろ。なかにつまっているもの。なかみ。内容。《対語》⇒形。「実質」「形質倶変=形質倶に変ず」「君子義以為質=君子は義以て質と為す」〔論語・衛霊公〕
- {名詞}たち。もってうまれたなかみそのもの。もちまえ。うまれつき。「素質」「性質」。
- {名詞・形容詞}飾りけのないそのもののまま。生地のまま。すなおである。《対語》⇒文。「質、勝文則野=質、文に勝てば則ち野なり」〔論語・擁也〕
- (シッス){動詞}ただす。なかみをつきつめる。問いただす。「質問」「質諸鬼神而無疑=諸を鬼神に質して疑ひ無し」〔中庸〕
チ(去)
- {名詞}あかしをたてるだけの値うちあるものとして、相手にあずけおく人や物。人質や抵当。「納質=質を納る」「交質=質を交す」。
- (チス){動詞}人質にする。抵当に入れる。
字通
[会意]斦(ぎん)+貝。貝はもと鼎の形。二斤(きん)(手おの)を以て鼎側に銘刻を加える意で、重要な契約や盟誓の辞などを記した。これを約剤・質剤という。剤の正字は劑。齊(斉)は![]() (せい)で方鼎、その方鼎に銘刻を加えることを劑といい、質と立意の同じ字である。〔説文〕六下に質を「物を以て相ひ贅(ぜい)す」とあって、質入れすることをいうとするが、それは字の初義ではない。〔説文〕は字が斦、二斤に従う意を解しえず、その義を闕としているが、劑・則(古くは𠟭)の字形によって、その意を解くことができる。それより質要・質剤・法則などの意となる。〔周礼、天官、小宰〕「官府の八成」のうち、「七に曰く、賣買を聽くに質劑を以てす」、また〔周礼、地官、質人〕に「大市には質を以てし、小市には劑を以てす」とみえる。質は訓義の多い字であるが、質剤の義が本義、他はその引伸義である。
(せい)で方鼎、その方鼎に銘刻を加えることを劑といい、質と立意の同じ字である。〔説文〕六下に質を「物を以て相ひ贅(ぜい)す」とあって、質入れすることをいうとするが、それは字の初義ではない。〔説文〕は字が斦、二斤に従う意を解しえず、その義を闕としているが、劑・則(古くは𠟭)の字形によって、その意を解くことができる。それより質要・質剤・法則などの意となる。〔周礼、天官、小宰〕「官府の八成」のうち、「七に曰く、賣買を聽くに質劑を以てす」、また〔周礼、地官、質人〕に「大市には質を以てし、小市には劑を以てす」とみえる。質は訓義の多い字であるが、質剤の義が本義、他はその引伸義である。
訳者注:質剤→周代、官庁が発行し、交易の時、買手から売手に渡して取引の証拠とした手形証券。
日(ジツ・4画)
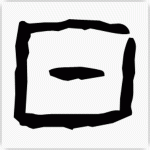

甲骨文/小臣艅犀尊・殷代末期
初出:初出は甲骨文。
字形:字形は太陽を描いた象形。原義は太陽。
音:カールグレン上古音はȵi̯ĕt(入)。
用例:「漢語多功能字庫」によると、甲骨文で原義の他”昼間”、”いちにち”、祭祀の名に、加えて金文では干支の出現前に時間的順序の一つ(作冊睘尊・西周早期)に用いられた。
備考:甲骨文では曲線を刻みにくいので、四角く描いたが、「口」と区別するため真ん中に一本棒を入れた。金文になると角が取れて、丸くなったものが見られるようになる。骨に小刀で文字を刻む甲骨文と異なり、固まる前の粘土の鋳型に、曲線を描くのは簡単だったからだ。
それが再び四角く書かれるようになったのは、後漢時代の隷書以降になる。
学研漢和大字典
象形。太陽の姿を描いたもの。ニチ・ジツということばは、尼(近づく)・昵(ジツ)(親しむ)・泥(ネイ)・(デイ)(ねっとり)などと同系で、身近にねっとりとなごんで暖かさを与える意を含む。また燃(ネン)(暖かくもえる)とも一脈のつながりがある。
付表では、「一日」を「ついたち」「二日」を「ふつか」「二十日」を「はつか」「今日」を「きょう」「昨日」を「きのう」「明日」を「あす」「日和」を「ひより」と読む。▽草書体をかな「ひ」として使うこともある。
語義
- {名詞}ひ。太陽。「日月」「浮雲翳白日=浮雲白日を翳ふ」〔孔融・臨終詩〕
- {名詞}ひ。太陽の出ている間。昼間。《対語》⇒夜。《類義語》昼。「夜以継日=夜以て日に継ぐ」〔孟子・離下〕
- {名詞}ひ。か。一昼夜。「是日=是の日」「終日」。
- {単位詞}か。日数をかぞえることば。
- {副詞}ひび。ひに。毎日。「吾日三省吾身=吾日に三たび吾が身を省みる」〔論語・学而〕
- {副詞}ひび。ひに。一日一日と。「園日渉以成趣=園は日に渉りて以て趣を成す」〔陶潜・帰去来辞〕
- {名詞}広く、時期・ころ。「暇日(カジツ)(暇な時)」「他日(将来の、ある日)」「何日是帰年=何の日か是れ帰年」〔杜甫・絶句〕
- {名詞}「日本」の略。
- 《日本語での特別な意味》
①にち。七曜の一つ。日曜日の略。
②「日向(ヒュウガ)」の略。「日州」。
字通
[象形]太陽の形。中に小点を加えて、その実体があることを示す。三日月の形に小点を加えて、夕とするのと同じ。〔説文〕七上に「實(み)てるものなり。太陽の精は虧(か)けず」とするのは、〔釈名、釈天〕の「日は實なり。~月は缺なり」とするのによるもので、音義説である。日と實、月と缺とは、今の音ははるかに異なるが、古音は近く、わが国の漢字音にはなおその古音が残されている。
※訳者注:カールグレン音で日ȵi̯ĕt・實ʰi̯ĕt、月ŋi̯wăt・缺kʰi̯watまたはkʰiwat。
且(シャ/ショ・5画)
社/社(シャ・7画)
車(シャ・7画)
者/者(シャ・8画)
舍(シャ・8画)
射(シャ・10画)
赦(シャ・11画)
奢(シャ・12画)
邪(ジャ・8画)
綽(シャク・14画)
若(ジャク・8画)
主(シュ・5画)
守(シュ・6画)
朱(シュ・6画)
取(シュ・8画)
酒(シュ・10画)
須(シュ・12画)
聚(シュ・14画)
需(シュ・14画)
趨(シュ・17画)
壽/寿(ジュ・7画)
乳(ジュ・8画)
儒(ジュ・16画)
樹(ジュ・16画)
孺(ジュ・17画)
十(シュウ・2画)
手(シュウ・4画)
舟(シュウ・6画)
州(シュウ・6画)
秀(シュウ・7画)
周(シュウ・8画)
受(シュウ・8画)
臭/臭(シュウ・9画)
首(シュウ・9画)
修(シュウ・10画)
習(シュウ・11画)
終(シュウ・11画)
脩(シュウ・11画)
授(シュウ・11画)
崇(シュウ・11画)
羞(シュウ・11画)
→論語語釈「羞」


コメント