
九(キュウ・2画)


甲骨文/𦅫鎛・春秋中期
初出:初出は甲骨文。
字形:腕の象形で、のち音を借りて数字の「きゅう」を表した。原義は”ひじ”。
音:カールグレン上古音はki̯ŭɡ(上)。
用例:「漢語多功能字庫」によると、甲骨文では原義で、また数詞に用い、金文や戦国の竹簡でも数詞に用いた(折方彝・西周早期)。
学研漢和大字典
象形。手を曲げて引き締める姿を描いたもので、つかえて曲がる意を示す。転じて、一から九までの基数のうち、最後の引き締めにあたる九の数、また指折り数えて、両手で指を全部引き締めるときに出てくる九の数を示す。究(奥深くゆきづまって曲がる最後の所)の音符となる。また、糾合(キュウゴウ)の糾、鳩合(キュウゴウ)の鳩と通じる。草書体をひらがな「く」として使うこともある。▽証文や契約書では、改竄(カイザン)や誤解をさけるため「玖」と書くことがある。
語義
- {数詞}ここのつ。《同義語》⇒玖。
- {数詞}ここの。順番の九番め。「九月九日」。
- {副詞}ここのたび。九回。九度。
- {形容詞}数が多い。また、奥深いさま。「為山九仞=山を為(つく)ること九仞なり」〔書経・旅忙〕
- {動詞}ひと所に引きしぼり集める。▽平声に読む。糾(キュウ)に当てた用法。「九合諸侯=諸侯を九合す」〔論語・憲問〕
- 《日本語での特別な意味》ここのつ。午前十二時、または午後十二時。▽江戸時代のことば。
字通
[象形]竜蛇の形。竜蛇に虫形と九形とあり、九は岐頭の形でおそらく雌竜。虫と九と組み合わせた形は禹。九州の水土を治めたとされる神である。〔説文〕十四下に「陽の變なり。其の屈曲し、究盡するの形に象る」とする。七は陽の正、九は陽の変。ゆえに〔易〕の陽爻を初九・九二・上九のようにいう。数の九に用いる。
及(キュウ・3画)

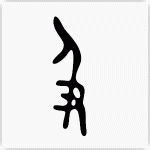
甲骨文/保卣・西周早期
初出:初出は甲骨文。
字形:「人」+「又」”手”で、手で人を捕まえるさま。原義は”手が届く”。
音:カールグレン上古音はɡʰi̯əp(入)。
用例:「漢語多功能字庫」によると、甲骨文では”捕らえる”、”…の時期に至る”の意で用い、金文では”至る”(保卣・西周早期)、”~と”(王孫𢍓鐘・春秋末期)の意に、戦国の金文では”~に”(中山王方壺・戦国早期)の意に用いた。
学研漢和大字典
「人+手」の会意文字で、逃げる人の背に追う人の手が届いたさまを示す。その場、その時にちょうど届くの意を含む。吸(口がぴたりと水面に届く→すいつく)-汲(つるべが水面に届く→くみ上げる)-給(おいつくようにぴたりとあてがう)などと同系のことば。
語義
- {動詞}およぶ。追いつく。「往言不可及=往言は及ぶべからず」〔国語・晋〕
- {動詞}およぶ。能力が追いつく。「非爾所及也=爾の及ぶ所に非ざるなり」〔論語・公冶長〕
- {動詞}およぶ。→語法「②」。
- {動詞}およぶ。そんなことまで行う。「父死不葬、爰及干戈=父死して葬らず、爰に干戈に及ぶ」〔史記・伯夷〕
- {動詞}およぼす。そこまで物事の範囲を広げる。「老吾老以及人之老=吾が老を老として以て人の老に及ぼす」〔孟子・梁上〕
- {接続詞}および。→語法「①」
語法
①「~および…」「~と…」とよみ、「~と…」と訳す。並列の意を示す。「漢軍及諸侯兵、囲之数重=漢軍及び諸侯の兵、これを囲むこと数重」〈漢軍と諸侯の兵は、幾重にも包囲した〉〔史記・項羽〕
②「~におよび(て)」とよみ、
- 「~になると」「~になったとき」と訳す。時間の到達の意を示す。「及父卒、叔斉讓伯夷=父卒するに及びて、叔斉伯夷に讓らんとす」〈父が亡くなると、叔斉は長兄の伯夷に(位を)譲ろうとした〉〔史記・伯夷〕
- 「~まで」「~に到って」と訳す。空間の到達の意を示す。「及郡下、詣太守、説如此=郡下に及び、太守に詣(いた)りて、説くことかくの如し」〈郡の役所に到って、太守にお目にかかり、しかじかと語った〉〔陶潜・桃花源記〕
- 「~に乗じて」「~という状況になると」と訳す。機会・条件の意を示す。「及其使人也、器之=その人を使ふに及びては、これを器にす」〈人を使うときには、長所に応じた使い方をする〉〔論語・子路〕
③「~と」とよみ、「~とともに」と訳す。対象・従属の意を示す。「爾尚及予一人致天之罰=爾(なんぢ)尚(こひねが)はくは予一人と天の罰を致(いた)せ」〈おまえたちよ、どうかわれと力を併せて天の罰を夏の桀に加えよ〉〔史記・殷〕
字通
人+
訓義
およぶ、追いつく、いたる、およぼす、つづく、つぐ。ともに、あわせて、あずかる。
大漢和辞典
会意。又と人の合字。又は手、後人の手が前人におよぶこと。追い及ぶ意。
字解
およぶ。およぼす。および。共に。共にする。弟が兄のあとをつぐ。もし。姓。
久(キュウ・3画)


睡虎地簡25.40・秦系戦国文字/『字通』所収金文
初出:初出は西周早期の金文。「小学堂」による初出は秦系戦国文字。白川フォントには独自の上掲金文を載せる。おそらく出典は西周末期「毛公鼎」(集成2841)。
字形:由来は不明。「国学大師」は、原義を灸を据える姿とする。
音:カールグレン上古音はki̯ŭɡ(上)。同音に「九」、「灸」、「疚」(やまい・やましい)、「玖」(黒い宝石)。”ひさしい・ながい”という語釈は、「舊」(旧、カ音ɡʰi̯ŭɡ)と音が通じて後世に生まれた語義だが、もとより「舊」と記されたとすると、むしろ「舊」の語義で解釈すべき。なお「舊」の藤堂上古音はgɪog、久はkɪuəg。詳細は論語語釈「旧」を参照。

用例:上掲西周早期「□作父庚𣪕」(集成3516)に「口乍(作)父庚寶彝。」とあり、□に「久」が部品として存在。語義は不明。
西周末期「毛公鼎」(集成2841)に「皇天引猒(厭)氒(厥)德」とある「厥」の字形は「久」。「皇天、ながく徳を引き猒せり」と読める。
備考:「漢語多功能字庫」には見るべき情報がない。
学研漢和大字典
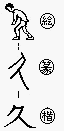
会意。背の曲がった老人と、その背の所に、引っぱるしるしを加えたもので、曲がって長いの意を含む。灸(キュウ)(もぐさで長い間、火をもやす)・柩(キュウ)(長い間、死体を保存するひつぎ)の字の音符となる。旧(長く時がたつ)・九(長く数えていきづまった数)・究(曲がりくねって奥深くはいる)・考(背の曲がった老人)などと同系のことば。草書体をひらがな「く」として使うこともある。▽草書体からひらがなの「く」ができた。また、初二画からカタカナの「ク」ができた。
語義
- {形容詞}曲がりくねって、くねくねと伸びているさま。「久腰(キュウヨウ)(老人の曲がった腰)」
(訳者注。中国哲学書電子化計画では、「久腰」の出典が確認できなかった。巢元方『諸病源候論』に「久腰痛候」という言葉はあるが、”久しい腰痛の症状”の意で、「久腰」ではない)。 - {形容詞}ひさしい(ひさし)。長く時がたっているさま。いろいろと曲折をへてのびるさま。《対語》⇒暫(ザン)(しばし)。《類義語》旧。「天長地久」「丘之禱久矣=丘(きう)の禱(いの)ること久し」〔論語・述而〕
- {動詞}ひさしくする(ひさしうす)。長く時間をかける。ずっとそのままにしている。「可以久則久=以て久しかるべくんば則ち久しうす」〔孟子・公上〕

京菓子舗”満月”名物”阿闍梨餅”のパッケージ
字通
屍体を後ろから木で支えている形。〔説文〕五下に「後よりこれを灸す。人の両脛の後に距有るに象るなり」とあり、うしろにものを詰める意とする。〔儀礼、士葬礼〕に「木桁もて之を久す」というように、木桁で支えることもあり、久とはその象であろう。これを櫃中に収めるときには匛・柩(訳者注。ともに”ひつぎ”)という。匚部十二下に「柩は棺なり」とあり、棺とは屍を綰んで納める意である。籀文の字形は匶に作る。久・舊(旧)は声義近く、通用する。久は屍を支える形、舊は鳥の足を繋いで係留する意で、ともに久遠の意において通ずる。久を久遠とするのは、顚死者(訳者注。行き倒れ)の象である眞(真)を、永遠に実在するものの意に転化するのと、相似た思弁の結果である。
訓義
1)ささえる、ものをつめる、ふさぐ、おおう。2)ひさしい、ひさしくする、とどまる、3)おくれる、まつ。
大漢和辞典

弓(キュウ・3画)


甲骨文/亘弓方簋・西周早期
初出:初出は甲骨文。
字形:弓の象形。弓弦を外した字形は甲骨文からある。原義は”弓”。
音:カールグレン上古音はki̯ŭŋ(平)。同音は無い。
用例:論語では孔子の弟子・冉雍仲弓の名としても登場。
学研漢和大字典
象形。弓の形を描いたもの。曲線をなす意を含む。躬(キュウ)(からだをまるく曲げる)・穹(キュウ)(曲線をなす天井、まるいテント)などと同系。まるく曲げたひじを貫(コウ)・肱(コウ)というのと縁が近い。類義語の弩(ド)は、留め金に弦をひっかけて、ばねで石や矢をはじくゆみ。
語義
- {名詞}ゆみ。まるくそったゆみ。《類義語》弩(ド)。「弓箭(キュウセン)(弓矢)」「弓矢斯張=弓矢斯に張る」〔孟子・梁下〕
- {単位詞}歩測で土地を測量するとき、土地の長さをあらわすことば。一弓は、一歩の長さで、六尺のこと(周代の一尺は二二・五センチメートル)。▽一説に五尺ともいう。「歩弓(歩測の幅)」。
字通
[象形]弓体の形。〔説文〕十二下に「窮むるなり。近きを以て遠きを窮むる者なり」と弓・窮の音の通ずることを以て説く。〔釈名、釈兵〕には、「弓は穹なり。之れを張ること弓隆(きゅうりゅう)(ドーム形)然たり」と、その形を以て説く。音よりいえば躬・弘などとの関係が考えられる。
丘(キュウ・5画)


甲骨文/子禾子釜・戦国
初出:初出は甲骨文。
字形:丘の象形。原義は”丘”。
音:カールグレン上古音はkʰi̯ŭɡ(平)。
用例:「漢語多功能字庫」によると、甲骨文では原義、地名に用い、戦国の金文では加えて姓氏名に用いた(廿七年安陽戈)。戦国の竹簡では人名に用いた。
論語では孔子の名「孔丘仲尼」として多く登場する。
学研漢和大字典
象形。周囲が小高くて中央がくぼんだ盆地を描いたもの。畦・邱とも書く。図の二字めの形は、鎬(=虚。くぼみ)の字の下部にあって意符として用いられる。類義語に山。
語義
- {名詞}おか(をか)。小高い所。「丘陵」。
- {名詞}小高く土盛りをした墓。塚(ツカ)。「墳丘」。
- {形容詞}おかのように大きい。「丘嫂(キュウソウ)(あによめに対する敬称)」。
- {名詞}周代の土地区画で、八家を「井」、四井を「邑(ユウ)」、四邑を「丘」という。百二十八家。「丘民」。
- {名詞}孔子の名、孔丘(コウキュウ)の略称。
字通
[象形]墳丘の象。〔説文〕八上に「土の高きものなり。人の爲(つく)る所に非ざるなり。北に從ひ、一に從ふ。一は地なり。人の居は丘の南に在り。故に北に從ふ。中邦の居は崑崙の東南に在り。一に曰く、四方高く、中央下(ひく)きを丘と爲す。象形」とあり、会意・象形の二説をあげている。墳墓は多く北郊に営まれるので、北邙のようにいう。ゆえに北一に従うとの説を生じたのであろう。〔詩、小雅、緜蛮〕は悼亡の詩。「緜蠻(めんばん)たる黄鳥 丘阿に止まる」とは、鳥形霊による死者への追想を導く発想である。
大漢和辞典
舊/旧(キュウ・5画)


甲骨文/邾公華鐘・春秋末期
初出:初出は甲骨文。
字形:鳥が古い巣から飛び立つ姿で、原義は”ふるい”。
音:カールグレン上古音はɡʰi̯ŭɡ(去)。
用例:「漢語多功能字庫」によると、甲骨文では原義、地名に用い、金文では原義(兮甲盤・西周末期)、”昔の人”(叔尸鐘・春秋中期)、”長久”(邾公華鐘・春秋末期)の意に用いた。
学研漢和大字典
形声。舊の上部は鳥のこと。下部は音をあらわす。もと鳥の名。ただし、普通は、久(年月をへて曲がった)・朽(キュウ)(曲がってくちる)と同系のことばに当てて用いる。類義語に古。
語義
- {形容詞}ふるい(ふるし)。くちて曲がった。年月をへてふるびた。また、以前の。《対語》⇒新。《類義語》古。「新旧」「旧邦」「旧令尹之政、必以告新令尹=旧令尹の政は、必ず以て新令尹に告ぐ」〔論語・公冶長〕
- {名詞}もと。以前の状態。「依旧=旧に依る」「仍旧=旧に仍る」「如旧=旧のごとし」。
- {名詞}昔なじみであること。また、昔なじみの人。《類義語》故。「故旧(昔なじみ)」「有旧=旧有り」「訪旧半為鬼=旧を訪へば半ばは鬼と為る」〔杜甫・贈衛八処士〕
- 《日本語での特別な意味》きゅう(きう)。太陰暦のこと。「旧盆」。
字通
[会意]旧字は舊に作り、萑(かん)+臼(きゆう)。臼形のものは、鳥を捕らえるための鑿歯(さくし)のある器。舊は萑がその器に足を取られて、奪去しえない状態を示す。ゆえに留止・旧久の意を生ずる。〔説文〕四上に「𨾦舊(しきう)、舊留なり」とみみずくの意とし、臼声とする。また重文として鵂を録する。〔淮南万畢術〕に「鵂もて鳥を致す」の〔注〕に、「鴟鵂を取り、其の大羽を折り、其の兩足を絆(つな)ぎ、以て媒(ばい)(おとり)と爲し、羅(あみ)を其の旁に張れば、則ち鳥聚まる」とあり、舊はその法を示す字である。金文に「舊友」「先舊」の語があり、また〔邾公華鐘(ちゆこうかしよう)〕に「元器を其れ舊(ひさ)しうせよ」のように用いる。久と声義が近い。
朽(キュウ・6画)

作冊疐鼎・西周早期
初出:初出は西周早期の金文。
字形:「丂」+「木」で、「丂」は音符とされるが、カールグレン・藤堂音ともに上古音不明。原義は不明。
音:カールグレン上古音はx(上)。藤堂上古音はhɪog。
用例:「漢語多功能字庫」によると、金文では地名に用いた(作冊疐鼎・西周早期/集成2504)。「康𥎦才朽𠂤。」とあり、春秋末期以前の用例はこの一例のみ。
論語公冶長篇9で定州竹簡論語が用いている「㱙」は、「小学堂」では「朽」の異体字として扱っており、「漢語多功能字庫」に条目が無い。初出も同じく西周早期の金文とする。大漢和辞典による語釈は”くちる・くさい”「国学大師」㱙字条も「同【朽或剐】字」という。剐は大漢和辞典にも見えないが、”つきやぶる・死刑の一種”と「国学大師」剐字条は言う。

大漢和辞典
学研漢和大字典
会意兼形声。丂(コウ)は、伸びようとするものがつかえて曲がったことをあらわす。朽は「木+(音符)丂」で、くさって曲がった木。考(腰の曲がった老人)・巧(曲がりくねった複雑な細工をする)と同系。類義語に腐。
語義
- {動詞・形容詞}くちる(くつ)。草木がくさる。くさって曲がる。また、そのさま。「朽木」。
- {名詞}くさった木。「摧朽=朽を摧く」。
- {動詞・形容詞}くちる(くつ)。古くなってだめになる。また、そのさま。「老朽」「不朽」。
字通
[形声]声符は丂(こう)。〔説文〕四下に㱙を正字とし、「腐るなり」と訓し、朽を別体の字とする。〔列子、湯問〕に「其の肉を㱙ちしめて棄て、然る後に其の骨を埋む」というのは、屍体の風化を待って葬る複葬の法をいう。丂は曲刀の形。木に斧斤を加えて、そのあとの腐朽することをいい、それを屍に及ぼして㱙という。
求(キュウ・7画)


甲骨文/廿七年衛簋・西周中期
初出:初出は甲骨文。
字形:甲骨文の字形は「豸」。字形と原義は足の多い虫の姿。甲骨文では「とがめ」と読み”わざわい”の意であることが多い。”求める”の意になったのは音を借りた仮借。
音:カールグレン上古音は声母のɡʰ(平)のみ。同音は「求」を部品とする漢字群の他、窮洚降嗥厹艽鼽(平)、昊暤浩顥泂舅臼咎(上)、鵠學(入)。うち甲骨文より存在する文字は「咎」のみ。藤堂上古音はgɪog。
用例:「漢語多功能字庫」によると、甲骨文では”求める”・”とがめる”の意が、金文では”選ぶ”(邾君鐘・おそらく春秋)、”祈り求める”(𦅫鎛・春秋)の意が加わったという。
備考:論語では、孔子の弟子・冉求子有の名としても現れる。
学研漢和大字典
象形。求の原字は、頭や手足のついた動物の毛皮を描いたもの。毛皮はからだに引き締めるようにしてまといつけるので、離れたり散ったりしないように、ぐいと引き締めること。裘(キュウ)(毛皮)はその原義を残したことば。糾(キュウ)(引き締める)・救(キュウ)(引き止める)・球(中心に引き締まった形のたま)と同系。
語義
- {動詞}もとめる(もとむ)。散らないよう、また逃げないように引き締める。《対語》⇒散・放。「求心」「求其放心而已矣=其の放心を求むるのみ」〔孟子・告上〕
- {動詞}もとめる(もとむ)。自分のものにしようとする。さがしもとめる。ほしがる。「追求」「探求」「要求」「居無求安=居には安きを求むること無し」〔論語・学而〕。「実事求是(現実に即して、それを支配する道理を求める。朱子学のスローガン)」。
- 《日本語での特別な意味》もとめる(もとむ)。買う。
字通
[象形]呪霊をもつ獣の形。この獣を用いて、求めるところを祈る。また獣皮の形で、裘(きゆう)の初文。〔説文〕に求字を収めず、裘字条八上に重文として求の字形を出し、「古文、衣を省す」という。金文に求を贖求(しよくきゆう)の意に用い、〔君夫𣪘(くんぷき)〕「乃(なんぢ)の友を儥(贖)求せよ」、〔舀鼎(こつてい)〕「乃の人を求(つぐな)へ」のようにいい、また〔𦅫鎛(そはく)〕「用(もつ)て考命(永命)彌生(びせい)ならんことを求む」のように用いる。呪霊をもつ獣皮によって祟(たたり)を祓い、欲するところを求めたので、その法を術という。術の従う朮は、古くは求と同形である。
咎(キュウ/コウ・8画)


甲骨文/毓且丁卣・商代晚期
初出:初出は甲骨文。
字形は「夊」(=止)+「人」で、人を踏みつけるさま。原義は”災い”。
音:カールグレン上古音はɡʰ(上)。平声の音は不明。藤堂上古音はgɪog(上)またはkog(平)。
用例:「漢語多功能字庫」によると、甲骨文では原義で、金文では「疒」を加えて”病気”(國差𦉜・春秋)を、戦国の金文では地名(四年咎奴蓸令戈・戦国末期)を、戦国の竹簡では原義、”追求する”、”舅”を意味した。
上声を日本語音では「キュウ」と読み、”とがめる”などの意で用いる。平声を「コウ」と読み、帝舜の家臣である咎陶(皋陶、音同じ)の名として用いる。帝舜が創作されたのは戦国初期の孟子によるもので、その聖王伝説の一環としての咎陶ばなしはそれ以降のラノベになる。「咎」を「陶」に転用したのは戦国の竹簡からで、いずれにせよ古さを装うためのおかしな音。
学研漢和大字典
会意。各は、格(ひっかかる)の原字で、歩く人の足がかたい石につかえた姿。咎は「人+各(つかえる)」で、障害につかえて順調な進みが曲がることを示す。
語義
キュウ(上)
- {名詞}とが。さしさわり。《対語》⇒休。「休咎(キュウキュウ)(吉凶)」「自遺其咎=自ら其の咎を遺す」〔老子・九〕
- {名詞}とが。過失。「以督厥咎=以て厥の咎を督さんことを」〔蜀志・諸葛亮〕
- {動詞}とがめる(とがむ)。失敗を指摘してこだわる。「既往不咎=既往は咎めず」〔論語・八佾〕
- {動詞}さしつかえる。「殺之何咎=これを殺すも何ぞ咎あらんや」〔李華・弔古戦場文〕
コウ(平)
- 「咎陶(コウヨウ)」とは、帝舜(シュン)の臣下の名。「皋陶(コウヨウ)」とも。
字通
[会意]人+夂(ち)+口。夂(ち)+口は各。神の降格する意で「各(いた)る」とよむ。口は祝詞を収める器の𠙵(さい)。神が降格して、人に罰することを求める呪詛を行う意。その呪詛によって降されるものを咎という。〔説文〕八上に「災なり。人に從ひ、各に從ふ。各なる者は相ひ違ふなり」と、各を各異の意とするが、呪詛して人にもたらされる災禍を咎といい、神罰を受けることをも咎という。金文の〔![]() 盨(しょうしゆ)〕に「廼(すなは)ち余一人の咎を作(な)さん」、〔詩、小雅、伐木〕「我をして咎有らしむること微(なか)れ」のようにいう。金文に■(疒+咎)という字があり、疒(だく)に従うのは、禍殃として病気となる意であろう。
盨(しょうしゆ)〕に「廼(すなは)ち余一人の咎を作(な)さん」、〔詩、小雅、伐木〕「我をして咎有らしむること微(なか)れ」のようにいう。金文に■(疒+咎)という字があり、疒(だく)に従うのは、禍殃として病気となる意であろう。
疚(キュウ・8画)

隷書
初出:初出は不明。「甲骨文合集」39803に一例あると「先秦甲金文資料庫」は言うが、文意が取れない上に大陸では「𤴨」”ふるえる”と釈文されている。

「甲骨文合集」39803
字形:「疒」+音符「久」ki̯ŭɡ(上)。
音:カールグレン上古音はki̯ŭɡ(去)。同音に「久」「九」「玖」”黒い玉”「灸」。下掲『字通』が「声義の関係があるようである」という「咎」のカ音はgʰ(上)。部品の「久」の初出は西周の金文。
用例:文献上の初出は論語顔淵篇4で、次いで戦国初期『墨子』七患に「今歲凶,民饑道餓,重其子此疚於隊,其可無察邪?」とあり、”空腹で病む”と解するべき。
戦国最末期『韓非子』顕学に「與人相若也,無饑饉疾疚禍罪之殃獨以貧窮者,非侈則墯也。」とあり、”病む”と解せる。
戦国最末期『呂氏春秋』に「孔子曰」として「故內省而不疚於道,臨難而不失其德。」とあり、論語顔淵篇4が戦国末期には成立していたことを示唆する。
学研漢和大字典
会意兼形声。久は「人が背をかがめた姿+ヽ印」の会意文字で、背のかがんだ老人のことである。ヽ印は老人が背をかがめて亀(カメ)のようになった、その背部をさし示す指事記号であろう。故旧の旧と同系。疚は「疒+(音符)久」で、久が、久しいという意に専用されたため、疚が原義をあらわすようになった。
語義
- {動詞・名詞}なやむ。やむ。老衰や病気のため、亀(カメ)のように背がかがんだ形になる。また、長わずらいや、老衰。
- {動詞・形容詞}やむ。やましい(やまし)。気がとがめる。なやます。また、そのさま。「内省不疚、夫何憂何懼=内に省みて疚しからざれば、それ何をか憂へ何をか懼れん」〔論語・顔淵〕
- 「在疚(ザイキュウ)」とは、喪に服していること。《同義語》⇒在柩。
字通
[形声]声符は久(きゅう)。〔釈名、釈疾病〕に「疚は久なり。久しく體中に在るなり」と久疾の意とするが、疚悔の意があることからいえば、咎と声義の関係があるようである。
急(キュウ・9画)

睡虎地簡12.54
初出:初出は秦系戦国文字。
字形:初出の字形は「又」”手”の変形+「心」で、「又」の変形はおそらく右手。上側の一画は親指。原義はおそらく”動悸”。
音:カールグレン上古音はki̯əp(入)。同音は「汲」「給」「級」「彶」(全て入)。
用例:戦国の竹簡では、「級」を「急」と釈文している例が複数ある。
戦国中末期「郭店楚簡」語叢二19に「〔辶及〕(急)生於(欲),察生於〔辶及〕(急)。」とあり、”急ぐ”と解せる。
戦国最末期「睡虎地秦簡」為吏7伍に「邦之急」とあり、”危機”と解せる。


「彶」甲骨文/毛公鼎・西周季期
論語時代の置換候補:上古音の同音に「彶」”急いで行く”・”あわただしい”があり、甲骨文から存在する。ただし”危機”の語義は春秋末期までに確認できない。
『字通』彶条
[形声]声符は及(きゅう)。及は、後ろより人を追って、これに及びつく形。その心を急といい、その行動を彶という。〔説文〕二下に「急ぎて行くなり」とあり、彶彶のように形況の語に用いる。金文の〔舀鼎(こつてい)〕「舀酒と(彶)羊、絲三鍰(くわん)を以て」のように連及の「と」、また〔不𡢁𣪕(ふきき)〕「女(なんぢ)彶(つつし)めり」のように戒急の意に用いる。
※「舀鼎」西周中期(集成2838)/「不𡢁𣪕」西周末期(集成4328)/「戒急」『大漢和辞典』では仏教用語で、「戒法を厳にして智慧を研くことを後にする人を戒急の人といひ」とある。
近音に「及」ɡʰi̯əp(入)があり初出は甲骨文だが、”苦境”の語義は無い。論語語釈「及」を参照。『大漢和辞典』で音キュウ訓きびしいに「伋」(初出は前漢隷書)、「糾」(同)、「絿」(初出『説文解字』)。以外の同音同訓は存在しない。
備考:「漢語多功能字庫」には見るべき情報がない。
学研漢和大字典
会意兼形声。及(キュウ)は「人+又(て)」の会意文字で、逃げる人のうしろから手を伸ばしてがぶっとつかまえるさま。たるみなく追いかけてやっと届く意を含む。急は「心+(音符)及」で、せかせかと追いつくような気持ち、ゆとりなく迫るような気持ちのこと。吸(息をゆるめず、ひたひたとすいつく)と同系。
語義
- {動詞}いそぐ。ゆとりがなくせかせかと物事をする。せく。《対語》⇒緩(カン)・寛(カン)。《類義語》忙(ボウ)・躁(ソウ)。「大王急渡=大王急ぎ渡れ」〔史記・項羽〕
- (キュウニ)(キフニ)・(キュウナ)(キフナ){副詞}せかせかと。ひたひたと。ゆるみなく追いたてるように。「急迫」「県官急索租=県官急に租を索む」〔杜甫・兵車行〕
- (キュウナリ)(キフナリ){形容詞}きつい。ゆとりがない。ひたひたとさし迫ったさま。《類義語》迫・緊。「緊急」「風急=風急なり」「持法急=法を持すること急なり」「相煎何太急=相ひ煎ること何ぞ太だ急なる」〔曹植・七歩詩〕
- {形容詞}傾斜がきつい。「急坂」。
- {名詞}変事・災害などで危険がさし迫った事態。「告急=急を告ぐ」「以先国家之急而後私讐也=もって国家の急を先にして私讐を後にすればなり」〔史記・廉頗藺相如〕
- 《日本語での特別な意味》
①きゅう(きふ)。雅楽などで、最後の拍子の速い部分。「序破急」。
②「急行電車」の略。「特急」「準急」。
字通
[形声]声符は及(きゅう)。〔説文〕十下に「褊(かたよ)るなり」とあり、また〔爾雅、釈言〕に「褊は急なり」とあり、互訓の字。及は後ろより人を追う意の字で、その心情を急という。心急ぐものは一褊に執するところがある。急遽・急速の意より、また緊急・急要の意となる。
糾(キュウ・9画)


相馬経2下・前漢/「丩」湯鼎・春秋
初出:初出は前漢の隷書。
字形:〔糸〕+〔丩〕(カ音不明)。「丩」の語義は”まつわる・まとう”と『大漢和辞典』は言い、初出は甲骨文。
音:カールグレン上古音はki̯ŏɡ(上)。同音に「虯」”みづち”・「赳」”つよい・はたらき”。
用例:甲骨文での「丩」の語義は欠損が多くて明らかではない。
西周早期「夌作父癸觶」(集成6449)には「夌乍丩父癸」とあり、「丩」は器名に用いられ語義不明。
「上海博物館蔵戦国楚竹簡」凡物乙15・23に「丩而視之」とあり、「丩」は「糾」と釈文され、”ただす”と解せる。
論語時代の置換候補:用例は人名の「公子糾」のみなので、同音近音のあらゆる字が置換候補となる。公子糾が当時どのように記されたかは分からない。
学研漢和大字典
会意兼形声。右側の字(音キュウ)は、二本のひもをよじるさまを描いた象形文字。糾はそれを音符とし、糸を加えた字で、ひもをあわせて一本によりあわせること。叫(のどを締めて金切り声を出す)・求(中心にむけてぐっと締める)などと同系。「糺」の代用字としても使う。「糾・糾弾・糾明」。
語義
- {動詞}あざなう(あざなふ)。よじる(よづ・よぢる)。ひもをよりあわせる。また、転じて、人々をひとまとめに寄せ集める。「糾合」。
- {名詞}よりなわ(よりなは)。よりあわせたなわ。
- {動詞・形容詞}よじれる(よぢる)。まとう(まとふ)。何本ものひも状のものがよじれる。また、中心となる物にいくすじもがまといつく。「糾紛(よじれて乱れる)」「糾纏(キュウテン)」。
- {動詞}ただす。横にそれないように、中心に向けて締める。悪人を締めあげる。きつくとり締まる。《同義語》⇒糺。《類義語》絞。「糾察」「以五刑糾万民=五刑を以て万民を糾す」〔周礼・大司寇〕
字通
[形声]声符は丩(きゅう)。丩は縄をより合わせる形で、糾の初文。〔説文〕三上に「繩三合するなり」とみえる。あざなうように合するを糾合、また糾縄を以て人を責め糾すので、糾察・糾弾の意となる。
躬(キュウ・10画)


楚系戦国文字/「身」 邾公華鐘・春秋晩期
初出:初出は楚系戦国文字。
字形:「身」+「呂」”背骨”で、原義は”からだ”。現行字形は「身」+「弓」で、体を弓のようにかがめること。英語のbowと同様。
音:カールグレン上古音は子音のkのみ(平)。同音は論語語釈「救」を参照。母音は不明。藤堂上古音はkɪoŋ。
用例:戦国早期「䣄尹朁鼎」(集成2766)に「壽躳㝅子。」とあり、「躳」は「躬」と釈文され、”自分”・”我が身”と解せる。
論語時代の置換候補:音がまるで違うが、部品の身の字(カ音ɕi̯ĕn、藤音thien)は甲骨文より存在し、”その身”の語義が春秋時代までに確認できるので、論語時代の置換候補になりうる。論語語釈「身」を参照。
備考:「漢語多功能字庫」には見るべき情報がない。
学研漢和大字典
会意兼形声。「身+(音符)弓(弓なりに曲がる)」で、屈曲するからだ。▽本字の猥は「身+呂(連なった背骨)」の会意文字。弓(曲がる)・窮(キュウ)(曲がりくねる)と同系。類義語に自。
語義
- {名詞}み。前後左右に曲がるからだ。背をかがめたからだ。《類義語》身。「鞠躬(キッキュウ)(からだをまるく曲げておじぎする)」「在爾躬=爾の躬に在り」〔論語・尭曰〕
- {名詞}わがみ。自身。
- {動詞}からだを弓形に曲げる。
- {副詞}みずから(みづから)。自分で行うさま。自分で。《類義語》身。「禹稷躬稼而有天下=禹稷は躬ら稼して天下を有つ」〔論語・憲問〕
字通
[形声]声符は弓(きゅう)。〔説文〕七下に字を呂部に属して躳に作り、「身なり。身に從ひ、呂に從ふ」と会意とし、別に一体として躬をあげる。呂は脊骨・脊椎の象。漢碑に躬に作るものが多く、躳はその譌形であろうと思われる。
宮(キュウ・10画)


合29155/散氏盤・西周末期
初出:初出は甲骨文。
字形:「宀」”屋根”+「吕」(金)”青銅”。高価な青銅器を備え付けた宮殿の意。
音:カールグレン上古音は声母のk(上)のみ。同音は論語語釈「救」を参照。藤堂上古音はkɪoŋ。「グウ」は慣用音、呉音は「ク・クウ」。
用例:「甲骨文合集」10985.2に「□龍田于宮」とあり、地名と解せる。このほか甲骨文には「于宮無災」の文字列が多く見られるが、地名か”宮殿”か明瞭でない。
西周早期「夨方彝」(集成6016)に「明公用牲于京宮」とあり、”神殿”・”祖先廟”と解せる。
西周早期「舍父鼎(辛宫鼎)」(集成2629)に「辛宫易舍父帛」とあり、人名と解せる。
西周中期「師湯父鼎」(集成2780)に「王才周新宮」とあり、”宮殿”と解せる。
音階などの意に用いたのは、戦国以降に時代が下る。
学研漢和大字典
会意。「宀(やね)+二つの口印(くちではなくて、建物のスペース)」で、奥深く、いくむねもの建物があることを示す。窮(奥深い)・究(奥深い)・曲(細かくはいりこむ)と同系。類義語に家。「神社」の意味では「グウ」「クウ」と読む。
語義
- {名詞}みや。王の住む御殿。《類義語》府(倉屋敷)。「宮中」「壊宮室以為曇池=宮室を壊ちて以て曇池と為す」〔孟子・滕下〕
- {名詞}いえ(いへ)。奥深く、いくむねもある建物。大きい屋敷。「一畝之宮、而花木叢萃=一畝之宮にして、而花木叢萃す」〔孟挑・人面桃花〕
- {名詞}宮殿や、道教・ラマ教の神殿の名につけることば。「驪宮(リキュウ)」。
- {名詞}宮中に住む皇族につける呼び名。「正宮(セイキュウ)(皇后)」「東宮(トウグウ)(皇太子)」。
- {名詞}五音の一つ。古代中国の音楽で、階名をあらわす。七音のドにあたる。▽五音は宮・商・角・徴(チ)・羽。「十二律」は、音名。「宮調」。
- {名詞}五刑の一つ。生殖器を除く刑罰。「宮刑」。
- {名詞}星座のこと。「黄道十二宮」。
- {単位詞}中国の天文学で、宇宙空間の角度をあらわすことば。一宮は、円周の十二分の一の、一つの円弧の両端の点が円心に向かってなす角度。三十度。
- 《日本語での特別な意味》
①みや。皇族。また、皇族の呼び名。「宮家」。
②みや。神社。「一の宮」。
字通
[会意]宀(べん)+呂(りよ)。宀は廟屋の象、呂は宮室の相並ぶ平面形。〔説文〕七下に「室なり」という。金文の〔伊𣪘〕に「王、周の康宮に在り。旦に王、穆の大室に格(いた)り、位に卽(つ)く」とみえるように、宮中に儀礼の室があり、室とはもと神位のある所、すなわち大室をいう。
救(キュウ・11画)


𣪕蓋・西周中期/周穴毛匜・西周末期
初出:初出は西周中期の金文「𣪕蓋」(集成4243)。「小学堂」による初出は西周末期の金文。
字形:「求」+「攴」(攵)。害虫を叩き潰すさま。「攻」(毒藥攻邪『黄帝内経』)「降」と同音であることから、原義は恐らく”虫下しして治療する”。
音:カールグレン上古音はk(去)。同音は下記の通り。藤堂上古音はkɪog。
| 字 | 義 | 音 | 訓 | 初出 | 声調 | 備考 |
| 躬 | み | キュウ | み | 楚系戦国文字 | 平 | →語釈 |
| 宮 | いえ | 〃 | いへ | 甲骨文 | 〃 | →語釈 |
| 攻 | せめる | コウ | うつ | 春秋金文 | 〃 | →語釈 |
| 捄 | 長いさま | ク | もる | 説文解字 | 〃 | |
| 梟 | フクロウ | キョウ | ふくろふ | 楚系戦国文字 | 〃 | |
| 皋 | 沢 | コウ | さは | 秦系戦国文字 | 〃 | →語釈 |
| 櫜 | 大袋 | 〃 | おほふくろ | 説文解字 | 〃 | |
| 鼛 | 太鼓 | 〃 | おほづつみ | 秦系戦国文字 | 〃 | |
| 槹 | もくこく・南京はぜ | 〃 | 木の名 | 説文解字 | 〃 | |
| 鳩 | はと | キュウ | はと | 前漢隷書 | 〃 | |
| 攪 | みだす | コウ | みだす | 説文解字 | 上 | |
| 韭 | にら | キュウ | にら | 楚系戦国文字 | 〃 | |
| 降 | くだる | コウ | くだる | 甲骨文 | 去 | →語釈 |
| 洚 | 洪水 | コウ | くだる | 甲骨文 | 〃 |
用例:西周中期の金文「𣪕蓋」(集成4243)に「內史尹册易救」とあり、人名と思われる。
春秋末期「秦王鐘」(集成37)に「秦王卑命競坪。王之定。救秦戎。」とあり、”救う”と解せる。「漢語多功能字庫」もその例を載せ、同様に解する。
学研漢和大字典
会意兼形声。求は、動物の毛皮を引き締めてからだに巻くさまを描いた象形文字。引き締める意を含む。裘(キュウ)(皮衣)の原字。救は「攴(動詞の記号)+(音符)求」で、引き締めて食い止めること。絿(キュウ)(ぐいと引き締めるひも)・球(中心に向かって引き締まった球体)と同系。類義語に助。
語義
- {動詞}すくう(すくふ)。食い止める。助ける。▽身投げや失敗などを、ぐいと引き止めて助けるのが、もとの意。《類義語》助。「救助」「救死=死を救ふ」「女弗能救与=女救ふこと能はざる」〔論語・八飲〕
- {名詞}すくい(すくひ)。困難を食い止め、または難儀の中からすくい出すこと。助け。「求救於斉=救ひを斉に求む」〔戦国策・趙
字通
[会意]求+攴(ぼく)。求は呪霊をもつ獣の形。これを殴(う)ってその呪霊を刺激し、他から加えられている呪詛を免れる共感呪術的な方法を示す字。それで救済・救助の意となる。〔説文〕三下に「止むるなり」とし、求(きゆう)声とするが、攴部の字には殴つべき対象に対して攴を加えるものが多い。殺・改なども、みな同じ立意の字である。
翕(キュウ・12画)

『説文解字』篆書
初出:初出は後漢の『説文解字』。
字形:「合」ɡʰəp(入)+「羽」gi̯wo(上)で、鳥が羽ばたきを合わせるさま。
音:カールグレン上古音はxi̯əp(入)。同音に「翕」を部品とする字の他、「吸」(入)、初出は後漢の『説文解字』。
用例:漢代になって作られた新しい言葉で、論語の時代に存在しない。孔子と同時代人である孫武の『孫武兵法』行軍篇に「諄諄翕翕」とあるが、後世の加筆の可能性を排除できない。
その他、戦国末期の『荀子』『韓非子』に用例がある。
論語時代の置換候補:『大漢和辞典』で音キュウ訓おこるは他に存在しない。訓あわせるに「繆」初出は戦国文字、「糾」初出は前漢の隷書、「歙」。
備考:「漢語多功能字庫」には、見るべき情報がない。
学研漢和大字典
会意。「隕+(音符)合(コウ)」で、鳥が羽をあわせて飛びたつ用意をすることをあらわす。合と同系。
語義
- {動詞}あつまる。おさめる(をさむ)。あう(あふ)。開いたものを寄せあわせる。《対語》⇒開。《類義語》合。「翕合(キュウゴウ)」。
- {形容詞}物事がいっせいにおこるさま。「翕然(キュウゼン)」。
- {形容詞}あつまって盛んなさま。
字通
[形声]声符は合(ごう)。合に給(きゆう)の声がある。〔説文〕四上に「起(た)つなり」とあり、鳥がいっせいに飛び立つ意。〔論語、八佾〕に孔子が楽章のことを論ずる語に「始めて作(おこ)るや、翕如たり」というのは、諸楽がいっせいに吹奏をはじめる意。その音の相和するさまをいう。鳥がいっせいに集まること、またその動作が敏速であることをいう。
給(キュウ・12画)

秦系戦国文字
初出:初出は秦系戦国文字。
字形:「糸」+「亼」+「𠙵」で、繊維品と容器に蓋をした食糧を組み合わせた配給品のさま。原義は”配り与える”。
音:カールグレン上古音はki̯əp(入)。同音は急、汲、級、彶”急いで行く”。
用例:戦国最末期の「睡虎地秦簡」倉律35に「以給客」とあり、”あたえる”と解せる。
論語時代の置換候補:同音に訓を共有する文字は無い。『大漢和辞典』に同音同訓は無い。部品の「糸」にも「合」にも”あたえる”・”たす”・”たりる”の用例は春秋末期までに無い。
備考:「漢語多功能字庫」には見るべき情報がない。
学研漢和大字典
会意。「糸+合(欠けめをふさぐ)」で、織り糸の欠けた所をすぐつぎあわすことを示す。欠けめや、すきを入れずに、くっつくの意を含む。吸(すきまを入れず息ですいあげる)・及(あき間をつめて逃げる者においつく)などと同系。類義語の与(與)は、いっしょに持てるように、わけあたえること。予(ヨ)は、自分の物を相手の前に押しやってあたえること。「相手の動作を表すことばにつけて敬意を表すことば」は、口語では普通、命令形以外は用いない。▽「たまう」「たまわる」は、「賜う」「賜る」とも書く。
語義
- (キュウス)(キフス){動詞}たりる(たる)。たす。欠けめをすぐつぎたす。「補給」「秋省斂而助不給=秋は省斂して不給を助く」〔孟子・梁下〕。「給人之求=人の求めを給す」〔荀子・礼論〕
- (キュウス)(キフス){動詞}あたえる(あたふ)。たまう(たまふ)。不足している者にあてがう。目下の者にあたえる。「支給」「酒肉衣服、給娥甚豊=酒肉衣服、娥に給すること甚だ豊かなり」〔謝小娥伝〕
- (キュウス)(キフス){動詞}用に充てる。また、必要に応じる。「給仕」「給事」。
- {名詞}あてがい。「俸給」「給不足需=給需に足らず」。
- 「口給(コウキュウ)」とは、巧みな弁舌で、とっさにつぎつぎといいたすこと。「禦人以口給=人を禦ぐに口給を以てす」〔論語・公冶長〕
- 《日本語での特別な意味》たまう(たまふ)。他人の動作にそえて尊敬の意をあらわすことば。
字通
[形声]声符は合(ごう)。合に翕・歙(きゆう)の声がある。合を金文に答の義に用いる例があり、対(こた)えて給付する意がある。〔説文〕十三上に「相ひ足すなり」とあり、足らざるところを充足するをいう。〔荀子、非十二子〕に「齊給便利にして、禮義に順(したが)はず」とは便速にしてなりふりかまわぬ意。また〔荘子、天地〕「給數(きふさく)にして以て敏なり」とは、すみやかにすることをいう。
厩/廏・廄(キュウ・12画)


彔盨・西周末期/卲王之諻簋・春秋末期
初出:初出は西周末期の金文。
字形:初出の字形は「厂」”屋根”+「食」+「犬」。粗末な小屋に犬を入れてエサを与えて飼うさま。のち「广」”棟のある屋根”+「食」+「攴」”打つ”。耐久性のある建物に家畜を入れて調教するさま。中国や台湾では「廄」が正字として取り扱われている。
![]()
慶大蔵論語疏は異体字「廐」と記す。上掲「大唐左監門衛副率哥舒季通葬馬銘」刻。
音:カールグレン上古音はkǐu(去)。
用例:西周末期「彔盨」(集成4357~4360)に「彔乍(作)鑄盨厩(簋)」とあり、「簋」ki̯wəɡ(上)”めし茶碗”と釈文されている。
春秋末期「卲王之諻簋」(集成3634・33635)に「卲(昭)王之諻(媓)之□(薦)厩(𣪘)。」とあり、「𣪘」(簋)と釈文されている。
戦国最末期「睡虎地秦簡」廄苑17に「其大廄、中廄、宮廄馬牛殹(也)」とあり、”家畜小屋”と解せる。
学研漢和大字典
会意兼形声。皀(キュウ)は、ごちそうを盛った姿に、匕印のフォークを添えた形。殳は動詞の記号。二つをあわせて食事を与えることを示す。廏はそれを音符とし、广(いえ)をそえた字で、馬に食事を与える馬屋。▽一説に糾合の糾(キュウ)(集める)と同系で、馬を集めて飼う所と解する。
語義
- {名詞}うまや。馬を集めて、かいばを食わせる所。「廏舎(キュウシャ)」「廏焚=廏焚けたり」〔論語・郷党〕
字通
[形声]声符は𣪘(きゆう)。〔説文〕九下に「馬舍なり」とし、「周禮に曰く、馬二百十四匹有るを廏と爲す。廏に僕夫有り」と〔周礼、夏官、校人〕の文によって説く。金文の〔貉子卣(はくしゆう)〕に「王■(冖+牛)を■(广+去+欠)(きよ)に■(𤔔+攴)(をさ)む」とあり、〔説文〕阹字条十四下に「山谷に依りて牛馬の圈を爲すなり」というように、阹が養馬のところであった。廏馬の数は〔周礼注〕によると二百十六匹である。
裘(キュウ・13画)


甲骨文/五祀衛鼎・西周中期
初出:初出は甲骨文。
字形:甲骨文の字形はかわごろもの襟元で、原義は”毛皮の服”。「求」は後に音を表すため付けられたと見える。
音:カールグレン上古音は声母のɡʰ(平)のみ。藤堂上古音はgɪog。「求」と同音。
用例:「漢語多功能字庫」によると、甲骨文では地名に用い、金文では氏族名、また原義で用いた(庚壺・春秋後期)。
学研漢和大字典
会意兼形声。求は、裘の原字で、頭・両足・尾のついたままのかわごろもの姿を描いた象形文字。裘は「衣+(音符)求」。求がぐっと引きしめる→もとめる、の意に使われるようになったため、かわごろもの意には裘が使われるようになった。帯でぐっと引きしめてからだにまとう、かわごろも。類義語に皮。
語義
{名詞}かわごろも(かはごろも)。獣の毛皮でつくった服。「狐裘(コキュウ)」「緇衣羔裘=緇衣(しい)には羔(こひつじ)の裘」〔論語・郷党〕
字通
[会意]求+衣。篆文の字形は衣中に求を加える。求は獣皮の象。〔説文〕八上に「皮衣なり」とし、求(きゆう)声とするが、求は裘の初文。また「一に曰く、象形。衰と同意なり」という。衰(さい)は衣に麻絰(まてつ)を加えた服喪の衣で、裘とは何の関係もない。
嗅(キュウ・13画)

海4.45
初出:初出は楚系戦国文字。ただし字形はネットで未発表。「小学堂」では初出は不明。
字形:「口」+「臭」(臭)。「臭」の派生字で、名詞”におい”に「臭」字を専用し、動詞として「嗅」が派生した。犬が口先を突き出してにおいをかぐさま。「臭」シュウにも「キュウ」の漢音がある。論語語釈「臭」を参照。
音:カールグレン上古音は不明(去)だが、「臭」はȶʰ(去)。藤堂上古音はhɪog。
用例:戦国中末期「郭店楚簡」窮達13に「〔口へん+上下に臼矢〕(嗅)而不芳」とあり、”においをかぐ”と解せる。
学研漢和大字典
会意兼形声。闌は、上古にはキュウといい「自(はな)+犬」の会意文字で、犬が鼻の細い穴を通してかぐこと。のち臭(=臭)が名詞「におい」をあらわすのに専用されたため、嗅の字で動詞をあらわすようになった。嗅は「口+(音符)臭(シュウ)」。
語義
- {動詞}かぐ。においをかぐ。《同義語》⇒軋(キュウ)。「嗅覚(キュウカク)」「三嗅而作=三たび嗅ぎて而作つ」〔論語・郷党〕
字通
[会意]正字は齅に作り、鼻+臭(臭)。嗅はその略字。〔説文〕四上に「鼻を以て臭に就くなり」といい、臭の亦声とし、「讀みて畜牲の畜(きう)の若(ごと)くす」という。その感覚を嗅覚、その器官を嗅官という。〔論語、郷党〕「三嗅して作(た)つ」は、鳥が警戒して飛び立つ意であるが、この嗅は狊(けき)の誤りであろう。〔爾雅、釈獣〕に、臭とは鳥が両翼を張る意であるという。
窮(キュウ・15画)


「![]() 」曶鼎・西周中期
」曶鼎・西周中期
初出は楚系戦国文字。論語の時代に存在しない。カールグレン上古音はɡʰ(平)。同音多数。部品の躬k(平)に”行き詰まる”の語釈は『大漢和辞典』に無い。近音同訓究k(去)の初出は西周中期の金文。ただし![]() という大変複雑な字形。糾ki̯ŏɡ(上)の初出は前漢の隷書。穹kʰi̯ŭŋ(平)の初出は後漢の説文解字。なお九ki̯ŭɡ(上)には”数の窮まり”の語義を『大漢和辞典』が載せる。初出はもちろん甲骨文。
という大変複雑な字形。糾ki̯ŏɡ(上)の初出は前漢の隷書。穹kʰi̯ŭŋ(平)の初出は後漢の説文解字。なお九ki̯ŭɡ(上)には”数の窮まり”の語義を『大漢和辞典』が載せる。初出はもちろん甲骨文。
学研漢和大字典
会意兼形声。「穴(あな)+(音符)躬(キュウ)(かがむ、曲げる)」で、曲がりくねって先がつかえた穴。穹(キュウ)(弓形に曲がる)と同系。究とも縁が近い。異字同訓にきわまる・きわめる 窮まる・窮める「進退窮まる。窮まりなき宇宙。真理を窮(究)める」 極まる・極める「不都合極まる言動。山頂を極める。栄華を極める。見極める。極めて優秀な成績」 究める「学を究(窮)める」。
語義
- (キュウス){動詞・形容詞}きわまる(きはまる)。物事がぎりぎりのところまでいってつかえる。また、いきづまって動きがとれない。おしつまったさま。《類義語》困。「困窮」「図窮而匕首見=図窮まりて而匕首見はる」〔史記・荊軻〕。「君子固窮=君子固(もと)より窮す」〔論語・衛霊公〕
- {形容詞}生活が行きづまっている。《対語》通・達。「貧窮」「窮人」。
- {動詞}きわめる(きはむ)。ぎりぎりのところまでやり尽くす。つきつめる。さいごまで見とどける。《類義語》究・尽。「窮尽(きわめつくす)」「窮理=理を窮む」「上窮碧落下黄泉=上は碧落を窮め下は黄泉」〔白居易・長恨歌〕
- {名詞}行きづまり。いちばん奥の所。はて。へんぴないなか。「窮極」「窮棲(キュウセイ)」。
- 「無窮(ムキュウ)」「不窮(フキュウ)」とは、どこまでいってもつかえ止まらないこと。《同義語》無尽。「不窮之功(フキュウノコウ)」「天壌無窮(天地のように永遠に続く)」「楽亦無窮也=楽しみも亦た窮まること無きなり」〔欧陽脩・酔翁亭記〕
字通
[会意]穴+躬(きゅう)。穴中に躬(み)をおく形で、進退に窮する意。〔説文〕七下に「極まるなり」と訓し、竆を正形とする。究・穹と声義近く、「究は窮なり」「穹は窮なり」のように互訓する。極は上下両木の間に人を入れて、これを窮極する意で、罪状を責め糾す意。窮にもその意があり、罪状を糾問することを窮治という。
牛(ギュウ・4画)



甲骨文/牛鼎・西周早期/師㝨簋・西周晚期
初出:初出は甲骨文。
字形:牛の象形。原義は”うし”。
音:カールグレン上古音はŋi̯ŭɡ(平)。
用例:「漢語多功能字庫」によると、甲骨文では原義に、金文でも原義に(友簋・西周中期)、また人名に用いた。論語では冉耕伯牛の名としても登場。
学研漢和大字典
象形。牛の頭部を描いたもの。ンゴウという鳴き声をまねた擬声語であろう。
語義
- {名詞}うし。家畜の一種。▽「楚辞」の天問や「山海経」によると、殷(イン)の王子王亥(オウガイ)がはじめて牛を飼いならしたという。
- {名詞}二十八宿の一つ。規準星(牽牛(ケンギュウ)中央大星)は今のやぎ座にふくまれる。いなみ。
- {形容詞}牛のように大ぐらいでのっそりとしたさま。「牛飲馬食」「牛歩」。
- 「牛蒡(ゴボウ)」とは、野菜の名。根は長く、食用・薬用にする。▽平安時代のころ呉音読みをして日本語に借用された。
- 《日本語での特別な意味》ぎゅう(ぎう)。牛の肉。牛肉。
字通
[象形]牛を正面からみた形。羊も同じ意象の字。〔説文〕二上に「大牲なり」とし、「角頭三、封・尾の形に象る」という。封とは肩甲墳起のところ。あるいは腰骨の形としてもよい。牛は犠牲の首たるもので、神事に供するときには一元大武という。武は足。盟誓のときにその血を用いる。主盟のことを「牛耳を執る」という。その半肉を半、その肉を「胖(ゆた)か」という。西周期の〔舀鼎(こつてい)〕は高さ二尺、深さ九寸、銘文四百四字に及ぶ大鼎で、「䵼牛鼎(しようぎゆうてい)」(牛を䵼(に)る鼎)と称している。

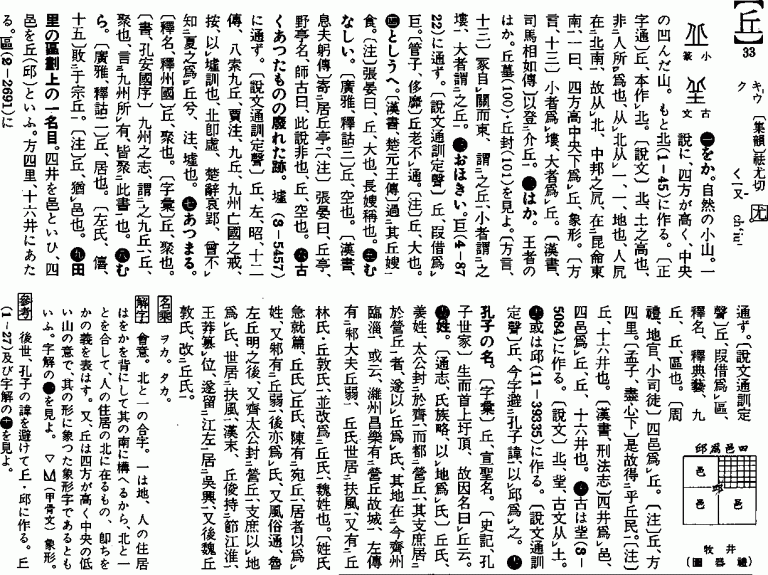


コメント