
- 心(シン・4画)
- 申(シン・5画)
- 盡/尽(シン・6画)
- 迅(シン・6画)
- 臣(シン・6/7画)
- 身(シン・7画)
- 辰(シン・7画)
- 辛(シン・7画)
- 枕(シン・8画)
- 信(シン・9画)
- 神・/神(シン・9画)
- 甚(シン・9画)
- 哂(シン・9画)
- 津(シン・9画)
- 袗(シン・10画)
- 浸(シン・10画)
- 晉/晋(シン・10画)
- 唇(シン・10画)
- 秦(シン・10画)
- 進(シン・11画)
- 深(シン・11画)
- 紾(シン/テン・11画)
- 紳(シン・11画)
- 晨(シン・11画)
- 診(シン・12画)
- 愼/慎(シン・13画)
- 新(シン・13画)
- 寑・寢/寝(シン・13画)
- 審(シン・15画)
- 親(シン・16画)
- 縝(シン・16画)
- 諶(シン・16画)
- 譖(シン・21画)
- 人(ジン・2画)
- 仁(ジン・4画)
- 仞(ジン・5画)
- 任(ジン・6画)
- 忍(ジン・7画)
- 衽(ジン・9画)
- 荏(ジン・9画)
- 訒(ジン・10画)
- 飪(ジン・13画)
心(シン・4画)
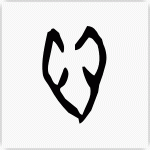

甲骨文/大克鼎・西周晚期
初出:初出は甲骨文。
字形:心臓を描いた象形。原義は心臓。
音:カールグレン上古音はsi̯əm(平)。
用例:「漢語多功能字庫」によると、甲骨文の段階で”思う”・”思い”を意味し得、その他河川の名として用いられた。
学研漢和大字典
象形。心臓を描いたもの。それをシンというのは、沁(シン)(しみわたる)・滲(シン)(しみわたる)・浸(しみわたる)などと同系で、血液を細い血管のすみずみまで、しみわたらせる心臓の働きに着目したもの。▽平安時代には、灯心(トウシミ)のように、語尾のmをミ・ムに音訳した。「腎」の代用字としても使う。「肝心」▽付表では、「心地」を「ここち」と読む。
語義
- {名詞}五臓の一つ。循環系の中心をなす器官。心臓。「心房」「心者君主之官也、神明出焉=心は君主の官なり、神明これより出づ」〔素問・霊蘭〕
- {名詞}こころ。精神。▽心臓で精神作用が営まれると考えたところから。「心理」「傾心=心を傾く」「設心=心を設く」「従心所欲=心の欲する所に従ふ」〔論語・為政〕
- {名詞}むね。《類義語》胸。「心腹」。
- {名詞}物事の中心。まん中。また、まん中にあるもの。「円心」「核心」。
- {名詞}二十八宿の一つ。規準星は、今のさそり座にふくまれる。なかご。
- 《日本語での特別な意味》こころ。つ思いやり。「心なき人」づ趣味を解する気持ち。「絵心がある」。
字通
[象形]心臓の形に象る。〔説文〕十下に「人の心なり。土の蔵、身の中に在り。象形。博士説に、以て火の蔵と爲す」とあり、蔵とは臓の意。五行説によると、今文説では心は火、古文説では土である。金文に「克(よ)く厥(そ)の心を盟(あき)らかにす」「乃(なんぢ)の心を敬明にせよ」のように、すでに心性の意に用いている。
申(シン・5画)


甲骨文/子申父己鼎・西周早期
初出:初出は甲骨文。
字形:金文までは「神」(神)と書き分けられていない。字形はいかづちの象形「申」で、”天の神”を意味した。のちに「示」”神霊一般”を添えたのが「神」。論語語釈「神」を参照。対して”地上の神”は、「示」に「土」”土地”を付した「社」(社)、「氏」”非血統的人間集団”を付した「祇」と記して区別した。詳細は論語語釈「示」を参照。
音:カールグレン上古音はɕi̯ĕn(平)。同音は論語語釈「身」を参照。
用例:西周の金文には干支のほか、人名の例が複数ある。
西周早期「乍册益卣」(集成5427)に「多申」とあるのは「神」(神)と釈文されている。
春秋末期までに、論語述而篇4の通説的解釈”のびやか”の例は見られない。
「のびやか」と読む「暢」は春秋末期の「蔡𥎦尊」(集成6010)に見えるが、ただし字形が大幅に違い、「方昜」の形を取る。
『欽定古今図書集成』経済彙編に周武王の「弓銘」として「屈申之義,廢興之行,無忘自過。」とあり、”のばす”と解せるが、いつの作文やら分からない。
前漢後期の『説苑』に「申其左臂」とあり、”伸ばす”と解せる。
「漢語多功能字庫」によると、甲骨文・金文では十二支の八番目に用いられ、金文では”神”(作冊益卣・西周中期)、”亡霊”(此鼎・西周末期)に用いた。
学研漢和大字典
会意。甲骨文字と金文とは、いなずま(電光)を描いた象形文字で、電の原字。篆文(テンブン)は「𦥑(両手)+┃印(まっすぐ)」で、手でまっすぐのばすこと。伸(のばす)の原字。電(のびるいなずま)・引(ひきのばす)・呻(シン)(声を長くのばしてうなる)・紳(からだをまっすぐのばす帯)などと同系。類義語に重。
語義
- {名詞}さる。十二支の九番め。▽時刻では、今の午後四時、およびその前後の二時間、方角では西南西、動物ではさるに当てる。「申時=申の時」「戊申(ボシン)の年」。
- {動詞}のべる(のぶ)。のばす。まっすぐに引きのばす。曲がりをためてまっすぐにする。《同義語》⇒伸。「屈申(=屈伸)」「申之、以孝悌之義=これを申ばすに、孝悌の義を以てす」〔孟子・梁上〕
- {動詞}もうす(まをす)。のべる(のぶ)。意見や気持ちを外に出して展開する。もうしのべる。《類義語》演。「申述」「申奏(上の人に所見をのべる)」。
- {動詞}力を入れてのばす。徹底させる。「申命」。
- {名詞}下級者が上級者に出す文書。「申文」。
- {名詞}上海の略称。▽上海の呉淞江(ゴショウコウ)を春申江ともいうことから。
- 《俗語》「申水(シエンシュイ)」とは、割り増し金。
字通
[象形]電光の走る形に象り、神(神)の初文。電の下部甲は、その電光の屈折して走る形。〔説文〕十四下に「神なり。七月、陰气體を成し、自ら申束(しんそく)す。𦥑(きよく)に從ふは、自ら持するなり。吏は餔時(ほじ)(食事時)を以て事を聽く。旦(あさ)の政を申(の)ぶるなり」と説くも、字形に即するところがない。〔大克鼎(だいこくてい)〕「申(かみ)に![]() 孝(けんかう)す」、〔杜伯盨(とはくしゆ)〕「其れ用(もつ)て皇申(神)祖考と好倗友とに享孝す」など、金文には申を神の意に用いる。〔詩、小雅、采薇〕「福祿、之れを申(かさ)ぬ」のように申重の意に用い、また上申・申張のように用いる。伸はその派生字である。
孝(けんかう)す」、〔杜伯盨(とはくしゆ)〕「其れ用(もつ)て皇申(神)祖考と好倗友とに享孝す」など、金文には申を神の意に用いる。〔詩、小雅、采薇〕「福祿、之れを申(かさ)ぬ」のように申重の意に用い、また上申・申張のように用いる。伸はその派生字である。
盡/尽(シン・6画)


甲骨文/中山王□壺・戦国早期
初出:初出は甲骨文。
字形:「又」”手”+たわし+「皿」”食器”で、食べ尽くした後食器を洗うさま。原義は”つきる”。
音:「ジン」は呉音。カールグレン上古音はdzʰi̯ĕnまたはtsi̯ĕn(共に上)。前者の同音は論語語釈「秦」を参照。後者の同音は論語語釈「津」を参照。
用例:「漢語多功能字庫」によると、甲骨文では人名に用い、戦国の金文では原義に用い(中山王方壺)、また”ことごとく”を意味した(商鞅量・戦国末期)。
学研漢和大字典
会意。盡は、手に持つ筆の先から、しずくが皿にたれつくすさまを示す。津(シン)(しずく)・燼(ジン)(燃えつきたかす)と同系。類義語の悉(コトゴトク)は、細かいところまで全部、の意。旧字「盡」は人名漢字として使える。▽「甚」の代用字としても使う。「食尽」。
語義
- {動詞}つきる(つく)。つくす。残りなく出してしまう。ありったけを費やす。「尽力(ジンリョク)」「事君尽礼=君に事ふるに礼を尽くす」〔論語・八飲〕。「秋風吹不尽=秋風吹いて尽きず」〔李白・子夜呉歌〕
- {動詞}つくす。最後まで全うする。おわる。「尽吾歯=吾が歯を尽くす」〔柳宗元・捕蛇者説〕
- {動詞}つくす。力をあるだけあらわして最上の程度に達する。「尽美矣=美を尽くせり」〔論語・八飲〕
- {副詞}ことごとく。→語法「①」
語法
①「ことごとく」とよみ、「残らずすべて」と訳す。《類義語》悉(シツ)・(コトゴトク)。「頭髪上指、目眥尽裂=頭髪上り指し、目眥(もくし)尽く裂く」〈その髪は逆立ち、目じりは裂けきらんばかりである〉〔史記・項羽〕
②「不尽~」は、「ことごとくは~せず」とよみ、「すべて~するとは限らない」と訳す。部分否定。「五穀尽収、則五味尽御於主、不尽収、則不尽御=五穀尽く収まれば、則(すなは)ち五味は主に尽く御(おさ)め、尽くは収めざれば、則ち尽くは御めず」〈五穀をすべて収穫できたときには、五味を調和させた食事をことごとく君主に進めることができる、五穀すべてが収穫できないときには、五味すべての味付けがされた食事などは進めることはできない〉〔墨子・七患〕
③「尽不~」は、「ことごとく~せず」とよみ、「まったく~しない」と訳す。全部否定。▽「尽」「不」の語順により意味が異なる。「問其左右、尽不知也=その左右に問ふに、尽く知らざるなり」〈左右の者に尋ねたが、だれもみな知らなかった〉〔韓非子・説林上〕
字通
[会意]旧字は盡に作り、聿(いつ)+皿+水滴の象。深い器の中を洗うために、細い木の枝のような棒(聿)を入れ、水を加えて器中を洗滌(せんでき)することを示す。〔説文〕五上に「器中、空しきなり」とあり、器中を洗うことによって終尽の意を示す。終尽の意から、すべてを傾注する、ものを究極する意となる。
迅(シン・6画)

「卂」卂伯簋・西周早期
初出:初出は西周早期の金文。ただし字形はしんにょうを欠く「卂」。「小学堂」による初出は後漢の説文解字。
字形:初出の字形は十字形の物体が風を切って飛ぶさま。現行字形は〔辶〕”道”+「卂」。
音:カールグレン上古音はsi̯ĕn(去)。同音に「新」「薪」「信」「訊」「卂」”早く飛ぶ”。「ジン」は慣用音で、呉音は「シン」。
用例:西周早期「卂伯簋」(集成3482)に「卂白(伯)乍(作)旅𣪕。」とあり、諸侯の称号、または領地の名と解せる。
学研漢和大字典
会意兼形声。右側の字は、飛の一部で、はやく飛ぶこと。迅はそれを音符とし、辶をそえた字。疾(急病、はやい)・信(さっとのびる、はやく進む)と同系。類義語に早。
語義
- {形容詞}はやい(はやし)。速度がはやい。飛ぶようにはやい。「迅速」「奮迅」。
- {名詞}はやくとどく知らせ。▽信に当てた用法。「通迅(=通信)」。
字通
[形声]声符は卂(じん)。〔説文〕二下に「疾なり」と訓し、卂声。卂十一下は「疾く飛ぶなり。飛に從うて、羽見えず」とあり、〔唐本説文〕に「隼(しゆん)は卂の省に從ふ」とあって、隼(はやぶさ)の飛ぶようなさまをいう。のち迅雷のように用いる。
臣(シン・6/7画)


甲骨文/毛公鼎・西周晚期
初出:初出は甲骨文。
字形:甲骨文の字形には、瞳の中の一画を欠くもの、向きが左右反対や下向きのものがある。字形は頭を下げた人のまなこで、原義は”奴隷”。
音:「ジン」は呉音。カールグレン上古音はȡi̯ĕn(平)。
用例:「漢語多功能字庫」によると、甲骨文では原義のほか”家臣”の意に、金文では加えて氏族名や人名に用いた。
学研漢和大字典
象形。臣は、下に伏せてうつむいた目を描いたもので、身をかたくこわばらせて平伏するどれい。臥(ガ)(ふせる)や臨(下をみる)に含まれる。上古にはギンと読み、緊(キン)(かたくしめる)・堅(ケン)(かたい)などと同系。もとの画数は六画。
語義
- {名詞}おみ。もと、かしこまってつかえるどれいのこと。転じて、家来。《対語》⇒君。「臣僕」「臣事(家来としてつかえる)」「臣事君、如之何=臣君に事ふるには、これをいかんせん」〔論語・八佾〕
- {名詞}臣下が君主に対してへりくだっていう自称のことば。《類義語》僕。「臣不能以喩臣之子=臣は以て臣の子に喩すこと能はず」〔荘子・天道〕
- (シンタリ){動詞}家来としての本分をつくす。家来らしくする。「臣不臣=臣臣たらず」〔論語・顔淵〕
- (シントス){動詞}家来とする。召し使う。「学焉而後臣之=学んでしかる後これを臣とす」〔孟子・公下〕
- 《日本語での特別な意味》おみ。八姓の一つ。天武天皇の時代に制定された八色(ヤクサ)の姓(カバネ)の六番め。
字通
目をあげて上を見る形。大きな瞳を示す。〔説文〕三下に「牽かるるなり」と、臣・牽の音の関係を以て解するが、両者の間に声義の関係はない。また字形について「君に事うる者なり。屈服する形に象る」(段注本)とするが、字は卜文の望に含まれる形と同じく、上方を見る目の形である。卜辞にみえる小臣は王族出身の者で、聖職に従い、臣を統括する。臣は多く神事に従い、もと異族犠牲や神の隷徒たる者を意味した。宮廟につかえる者を臣工といい、〔詩、周頌〕に〔臣工〕の一篇がある。金文の賜与に「臣三品」のようにいうのは、出自の異なる者三種をいう。また「臣十家」のようにいうのは、一般の徒隷と異なるものであろう。のち出自や身分に関することなく、他に服事するものをいう。
訓義
- つかえる、神廟につかえる、祭事につかえる。
- おみ、けらい、しもべ。
- めしうど、とりこ。
- たみ、人民。
- 臣下の自称。
身(シン・7画)


甲骨文/邾公華鐘・春秋晩期
初出:初出は甲骨文。
字形:人間の横姿。
音:カールグレン上古音はɕi̯ĕn(平)。同音は下記の通り。
| 字 | 音 | 訓 | 初出 | 声調 | 備考 |
| 申 | シン | かさねる | 甲骨文 | 平 | →備考 |
| 伸 | 〃 | のびる | 戦国末期金文 | 〃 | |
| 紳 | 〃 | 大帯 | 甲骨文 | 〃 | →備考 |
| 呻 | 〃 | となへる | 前漢隷書 | 〃 | |
| 身 | 〃 | みづから | 甲骨文 | 〃 |
用例:「漢語多功能字庫」によると、甲骨文では”お腹”を意味し、春秋時代までには”からだ”の派生義(師克盨・西周)、子孫に対して”その身”の意(㠱公壺・春秋)、君主の治世(庚壺・春秋後期)が生まれた。
「永保其身」の言い廻しは春秋時代に多用され、「永く其の身を保て」と読める。
漢語多功能字庫
甲金文從「人」而突出腹部(以◎表示)。◎代表半圓形的指事符號,指示腹部所在,半圓中或加一點,象肚臍形。本義是腹部。
甲骨文と金文は「人」と突出した腹部を示す記号の字形に属する。半円形のその記号は、物理的方向を示す記号で、人にお腹があることを示し、取り囲んだ中に点を一つ加えるのは、へその象形。原義はお腹。
学研漢和大字典
象形。女性が腹に赤子をはらんださまを描いたもの。充実する、いっぱいつまるの意を含み、重く筋骨のつまったからだのこと。真(いっぱいつまる)・鎮(チン)(重くつまる)などと同系。類義》語の体(=體)は、手足をはじめ、いろいろな器官の備わったからだ全体。草書体をひらがな「み」として使うこともある。
語義
- {名詞}み。からだ。また、首から上の部分を除いたからだ。《類義語》体。「身首、異処=身首、処を異にす」「身也者父母之遺体也=身也者は父母之遺せる体也」〔礼記・祭義〕
- {名詞・副詞}み。みずから(みづから)。わがみ。自分。自分で。また、三国・六朝時代には、わたくしの意の自称のことばとして用いた。「身為天子*=身は天子と為る」〔孟子・万上〕
- {動詞}みずからする(みづからす)。自分でする。「湯武身之也=湯武はこれを身らするなり」〔孟子・尽上〕
- {名詞}み。木の幹、刀のなかみ、物の体積など、物の中心やなかみのこと。「刀身」「船身」。
- め{動詞・名詞}みごもる。はらむ。こどもをはらむ。おなかの中の胎児。「大任有身=大任身める有り」〔詩経・大雅・大明〕
- 「身毒(シンドク)」とは、インドの古称。「天竺(テンジク)」とも。▽インドの地域名Sindhuの音訳。
*「天子」の言葉が中国語に現れるのは西周早期で、殷の君主は自分から”天の子”などと図々しいことは言わなかった。詳細は論語述而篇34余話「周王朝の図々しさ」を参照。
字通
[象形]みごもっている人の側身形。〔説文〕八上に「躬(み)なり」とするが、〔詩、大雅、大明〕に「大任(たいじん)身(はら)める有り」の〔伝〕に「身重きなり」とするのが字の原義。孕妊をいい、孕は腹中に子のある人の側身形。娠(しん)は身の形声字である。
辰(シン・7画)


甲骨文/二祀弋其卣・殷代末期
初出:初出は甲骨文。
字形:甲骨文の字形は人が死神のような大ガマを持った姿で、原義は”刈り取り”。その語義には後世「耨」を用いた。
音:カールグレン上古音はȡi̯ən(平)。
用例:甲骨文の用例は干支の一部を構成するものばかりで、この文字の出現は甲骨文より先行する可能性がある。
西周早期の「田蕽鼎」(集成2174)に「辰」を「農」と釈文する例がある。
西周早期の「𢦚方鼎」(集成2725)に「隹(唯)八月,辰才(在)乙亥」とあり、”とき”と解せる。
西周早期の「大盂鼎」(集成2837)に「辰」を「晨」と釈文する例がある。
“星座”の例は戦国時代にならないと現れない。
「漢語多功能字庫」によると、甲骨文では地名や国名に、金文では十二支の五番目や日時の表記に(宜侯夨簋・西周)、また氏族名・人名に用いたという。
学研漢和大字典

象形。蜃(シン)(かい)の原字で、二枚貝が開いて、ぴらぴらと弾力性のある肉がのぞいたさまを描いたもの。振・震と同系。
語義
- {名詞}たつ。十二支の五番め。▽方角では東南東、時刻では午前八時、およびその前後二時間、動物では竜にあてる。▽十二支の五番めに当てたのは、動植物がふるいたつ初夏のころの意から。
- {名詞}十二支をまとめていうことば。「浹辰(ショウシン)(子から亥(ガイ)までで一巡する十二日)」。
- {名詞}とき。時刻や日。「時辰」「吉辰(キツシン)(吉日)」。
- {名詞}時刻につれて動く天体。日、月、星の総称。「三辰(サンシン)(日月星)」「北辰(ホクシン)(北極星)」。
- {名詞}星の名。水星。「辰星(シンセイ)」。
- {形容詞}元気よくふるいたつさま。▽振に当てた用法。「辰牡孔碩=辰牡孔だ碩なり」〔詩経・秦風・駟蚶〕
字通
辰[象形]蜃蚌(しんぼう)などの貝の類が、足を出して動いている形。〔説文〕十四下に「震ふなり。三月、陽气動き、靁電振ふ。民の農時なり。物皆生ず。乙匕(いつひ)に從ふ。匕は芒達(ばうたつ)(草木の芽)に象る。厂(かん)の聲」(段注本)とする。当時の五行説によって説くものである。なお「辰は房星、天時なり」と、星の名にして農祥とし、字形中の二は上の意であるという。字は蜃の象形。その貝殻は刈器として耨(くさきり)に用いられ、蜃器に対する古い信仰を生んで、祭祀にも蜃を用いた。〔周礼、地官、掌蜃〕に「祭祀には蜃器の蜃を共(供)することを掌る」とあり、〔春秋、定十四年〕「秋、天王、石尚をして、來(きた)りて蜃を歸(おく)らしむ」のような例がある。西周期の金文の紀月の法に、「辰(とき)は五月に在り」のようにいうのは、辰が農時の意から、時期の意に転用されたものであろう。日月の会するところの十二次を辰といい、また星宿の名に用いる。
辛(シン・7画)

父辛𣪕・西周早期
初出は甲骨文。カールグレン上古音はsi̯ĕn(平)。
学研漢和大字典
象形。鋭い刃物を描いたもので、刃物でぴりっと刺すことを示す。転じて、刺すような痛い感じの意。新(切りたて、なま)・薪(切りたてのまき)と同系。鹹(カン)は、しおからい。
語義
- {名詞・形容詞}からい(からし)。五味(酸・苦・甘・辛・鹹(カン))の一つ。舌をさすようなぴりぴりする味。ぴりっとさす感じ。《類義語》辣(ラツ)。「辛辣(シンラツ)」「五辛(葵(キ)・據(カク)・薤(カイ)・葱(ソウ)・韭(キュウ)の五種のからい野菜)」。
- {名詞・形容詞}つらい(つらし)。身にこたえるつらさ。はだ身をさすように心が痛い。「辛酸」「悲辛(痛いほどの悲しみ)」。
- {名詞}かのと。十干(ジッカン)の八番め。▽五行では、庚とともに金に当てる。「かのと」は、「金の弟」の意。順位の第八位も示す。「辛亥(シンガイ)」。
- 《日本語での特別な意味》
①からし。からし菜の種からとったぴりぴりする粉。薬味などに用いる。また、からい野菜。「唐辛(トウガラシ)」。
②からい(からし)。物事に対する態度がきつい。きびしい。《対語》甘。「点が辛い」。
③「辛うじて」とは、やっとの意。
字通
[象形]把手のある大きな直針の形。これを入墨の器として用いるので、言・章・童・妾・辠(ざい)・辜(こ)・商などの字は、もと辛に従う形に作る。〔説文〕十四下に「秋時、萬物成りて孰す。金は剛、味は辛なり。辛痛しては卽ち泣(なみだ)出づ。一に從ひ、䇂(けん)に從ふ。䇂は辠(つみ)なり。辛は庚を承く。人の股に象る」とする。その説は五行配当の説によるもので、字形学的には何の意味もない。䇂はまた■(上下に立+丂)に作り、辥(せつ)・辟(へき)などの字は、もとその形に従い、曲刀の象、刳剔(こてき)するのに用いる。辛に墨だまりをつけた形は章、入墨によって文身を施すことを文章、その美しさを彣彰という。
枕(シン・8画)


信2.023/「冘」(甲骨文)
初出:初出は楚系戦国文字。
字形:現伝字形は「木」+「冘」”まくら”で、木製のまくら。
音:「チン」は慣用音。カールグレン上古音はȶi̯əm(上)で、同音は存在しない。
用例:「上海博物館蔵戦国楚竹簡」孔子詩論29に「角(枕)婦」とあり、「枕に婦とふれる」と読め、”まくら”と解せる。
論語時代の置換候補:部品の「冘」は音も示し、現在では”大勢でゆく”の意。ただし下記『学研漢和大字典』『字通』の説を採用すると、置換候補になるが、甲骨文のみで金文の出土が無い。
学研漢和大字典
会意兼形声文字で、冘(イン/チン)は、━印のかせで人の肩をおさえて、下に押しさげるさま。甲骨文字は、牛を川の中に沈めるさま。枕は「木+(音符)冘」で、頭でおしさげる木製のまくら。沈(水の下にしずめる)・耽(タン)(底にしずむ)などと同系のことば。
語義
- {名詞}まくら。寝るとき頭をのせて、頭を下に落ち着ける物。転じて、物の下にしく木や台。「陶枕(トウチン)(やきもののまくら)」。
- {動詞}まくらとする(まくらとす)。ある物をささえにして、その上に頭をのせる。▽去声に読む。「曲肱而枕之=肱を曲げてこれを枕とす」〔論語・述而〕
- {動詞}のぞむ。物の上にのって下をみる。▽去声に読む。《類義語》臨。「枕河=河に枕む」。
- 《日本語での特別な意味》まくら。前置きにする、ちょっとしたことば。
字通
[形声]声符は冘(いん)。冘に沈・鴆(ちん)の声がある。冘は人が枕して臥している形。〔説文〕六上に「臥するとき、首に薦(し)く所以の所なり」(段注本)という。〔詩、唐風、葛生〕は挽歌、「角枕粲(さん)たり」と、棺中の人を歌っている。
信(シン・9画)
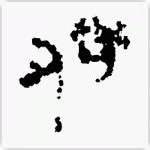
㝬叔鼎・西周末期
初出:初出は西周末期の金文。ただし字形は「㐰」。
字形:字形は「人」+「口」で、原義は”人の言葉”だったと思われる。
音:カールグレン上古音はsi̯ĕn(去)。同音は「新」、「辛」”針・小刀”、「薪」、「訊」、「迅」、「卂」”早く飛ぶ”。”信じる”の意が確認できる漢字は無い。
用例:春秋末期までの出土例は「㝬叔鼎」一点で、人名に用いられている。
隹(唯)王正月初吉乙丑,㝬弔(叔)□(信)姬乍(作)寶鼎
動詞・副詞の用例は戦国の「包山楚墓」から、形容詞としての用例は、同じく戦国の「郭店楚簡」からになる。
「漢語多功能字庫」では、初出を戦国時代の金文としているので、論語の時代の語義について記すところが無い。「国学大師」も上掲西周末期金文を載せながら、語釈は戦国時代から述べている。
学研漢和大字典
会意文字で、言は、言明(はっきりいう)の意。信は「人+言」で、一度言明したことを押し通す人間の行為をあらわす。途中で屈することなく、まっすぐのび進むの意を含む。信義の信はその派生義。進・晉(シン)(=晋)・迅(ジン)と同系のことば。
語義
- {名詞}まこと。言明や約束をどこまでも通すこと。▽前言をかえたり、途中で屈したりするのを不信という。「信義」「民無信不立=民信無(な)くんば立たず」〔論語・顔淵〕
- (シンナリ){形容詞}まこと。ほんとうであるさま。「信斯言也=信なるかな斯の言也」〔孟子・万上〕
- (シンニ){副詞}まことに。ほんとうに。「若妻信病、賜小豆四十斛=もし妻信に病めば、小豆四十斛を賜へよ」〔魏志・華佗〕
- (シンズ){動詞}信用する。「信任」「王信之乎=王これを信ずるか」〔韓非子・内儲説上〕
- {名詞}約束。また、約束のしるし。「印信(はんこ)」。
- {動詞}のびる(のぶ)。のばす。つかえずにまっすぐのびる。また、のばす。《同義語》⇒申。▽平声に読む。「屈而不信=屈して信びず」〔孟子・告上〕
- {動詞}まかせる(まかす)。引きとめずにまっすぐのばす。いくにまかせる。「信手=手に信す」「東望都門信馬帰=東のかた都門を望んで馬に信せて帰る」〔白居易・長恨歌〕
- {動詞}旅の行程をのばし二泊する。「信宿」。
- {名詞}遠くまでのび届くたよりやニュースのこと。▽訊(シン)に当てた用法。「音信」「風信」。
- 《日本語での特別な意味》「信濃(シナノ)」の略。「信州」。
字通
人+言。言は誓言、神に誓う語である。〔説文〕三上に「誠なり」という。〔穀梁伝、僖二十二年〕に「言にして信ならざれば、何を以てか言と為さん」とあり、誓約の言であるから、信誠の意がある。
訓義
1)まこと、まことにする。2)しるし、あかし、わりふ。3)あきらか、つまびらか。4)したがう、うやまう。5)任と通じ、まかせる。6)申と通じ、再宿、かさねて宿る。7)訊と通じ、たより、つかい。8)伸と通じ、のびる、ゆるやか。
大漢和辞典
まこと、まことに、まこととする、疑わない。あきらかにする、つまびらかにする。知る。しるし、あかし。割り符。従う。敬う。保つ。任せる。二晩泊まる、再宿。海水の定時の満干。使い、使者。たより、おとずれ。五音の宮をいう。五行で水神を言う。姓。〔仏〕一切の理・非理を弁別し、三宝の浄徳を楽願し、一切の善事を希望して、その心の清浄なこと。伸に通じ、のびる、のばす、ゆるくする。申に通ず。身に同じ。
神・/神(シン・9画)


寧簋蓋・西周早期/大克鼎・西周末期
初出:初出は西周早期の金文。
字形:新字体は「神」だが、台湾・大陸ではこちらが正字として扱われている。漢石経では「神」と〔礻〕を用いて記している。原字はいかづちの象形「申」。「申」は甲骨文では”稲妻”・十干の一つとして用いられ、金文から”天の神”を意味し、しめすへんを伴うようになった。論語語釈「申」を参照。「申」に「示」”神霊一般”を添えたのが本字。対して”地上の神”は、「示」に「土」”土地”を付した「社」(社)、「氏」”非血統的人間集団”を付した「祇」”氏族の開祖神”と記して区別した。詳細は論語語釈「示」を参照。
定州竹簡論語の「![]() 」字は『大漢和辞典』にも無く、偏と旁が入れ替わった「䰠」は『説文解字』から見られ「神也」とする。似た字形の字に「𩲣」音「カフ/ケフ」訓「かくれてゐる鬼」があるが初出不明。結局「
」字は『大漢和辞典』にも無く、偏と旁が入れ替わった「䰠」は『説文解字』から見られ「神也」とする。似た字形の字に「𩲣」音「カフ/ケフ」訓「かくれてゐる鬼」があるが初出不明。結局「![]() 」は定州竹簡論語に特有の「䰠」の異体字と解するほかない。
」は定州竹簡論語に特有の「䰠」の異体字と解するほかない。
音:カールグレン上古音はʰi̯ĕn(平)。藤堂上古音dien。
用例:「神」は「漢語多功能字庫」によると、金文では”神”(㝬鐘・西周末期)、”先祖”(此鼎・西周末期)の意に用いた。
備考:論語語釈「鬼」も参照。
殷代の漢字では「申」だけで”天神”を意味し、「土」だけで”大地神”意味し得た。「示」は両方を包括する神霊一般を意味した。西周になったとたんに「神」と書き始めたのは、殷王朝を滅ぼして国盗りをした周王朝が、「天命」に従ったのだと言い張るためで、文字を複雑化させたのはもったいを付けるため。「天子」の言葉が中国語に現れるのは西周早期で、殷の君主は自分から”天の子”などと図々しいことは言わなかった。詳細は論語述而篇34余話「周王朝の図々しさ」を参照。
学研漢和大字典
会意兼形声。申は、いなずまの伸びる姿を描いた象形文字。神(=神)は「示(祭壇)+(音符)申」で、いなずまのように、不可知な自然の力のこと。のち、不思議な力や、目に見えぬ心の働きをもいう。電(いなずま)と同系。類義語に鬼。旧字「閼」は人名漢字として使える。▽付表では、「神楽」を「かぐら」、「お神酒」を「おみき」と読む。
語義
- {名詞}かみ。日・月・風・雨・雷など、自然界の不思議な力をもつもの。天のかみ。▽祇(ギ)(地のかみ)・鬼(人のたましい)に対することば。「百神」「祭神如神在=神を祭るには神の在すがごとくす」〔論語・八飲〕
- {名詞}理性ではわからぬ不思議な力。「神秘」「入神」「聖而不可知之、之謂神=聖にしてこれを知るべからざる、これを神と謂ふ」〔孟子・尽下〕
- {形容詞}ずばぬけて、すぐれたさま。「神品」。
- {名詞}こころ。精神。「曠神=神を曠くす」「臣以神遇而不以目視=臣神を以て遇し目を以て視ず」〔荘子・養生主〕
- 《日本語での特別な意味》
①かみ。祖先のかみ。「天照大神(アマテラスオオミカミ)」。
②「神戸」の略。「阪神地帯」。
字通
[形声]声符は申(しん)。申は電光が屈折して走る形で、神威のあらわれと考えられ、神の初文。〔説文〕一上に「天神なり」とし、「萬物を引きて出だす者なり」と神・引の畳韻を以て訓する。〔礼記、礼運〕「鬼神に列す」の〔鄭玄注〕に「神なる者は、物を引きて出ださしむ。祖廟・山川・五祀の屬を謂ふなり」とあって、当時の音義説であった。金文の〔宗周鐘(そうしゆうしよう)〕に「皇上帝百神」、また〔大克鼎(だいこくてい)〕に「申(神)に![]() 孝(けんかう)す」とあって、祖霊も神として祀られていたことが知られる。精神的なはたらきのすぐれたものをも、神爽・神悟のようにいう。
孝(けんかう)す」とあって、祖霊も神として祀られていたことが知られる。精神的なはたらきのすぐれたものをも、神爽・神悟のようにいう。
甚(シン・9画)



西周早期・甚父戊觶1・2/甚諆鼎・西周中期
初出:初出は西周早期の金文(「甚父戊觶」集成6497)。「小学堂」による初出は西周中期の金文。
字形:初出の字形は「𠙵」”くち”または「曰」”いう”+「一」または「二」+「𠃊」”かくす”・”かくれる”。ほかに「○」+「乍」”大ガマ”の字形もある。由来と原義は不明。
音:「ジン」は呉音。カールグレン上古音はȡi̯əm(上/去)。
用例:春秋末期まで人名・器名の例が多い。
西周末期「匜」(集成10285)に「王…曰。牧牛。𠭯乃可湛(甚)。」とあり、「まきのうし、とりてすなわちしずめるべし」と読め、”沈める”と解せる。
西周末期「新收殷周青銅器銘文暨器影彙編」NA0852に「晉侯(對)乍…其用田(獸),甚(湛)樂于(原)(隰)」とあり、「湛樂」は”たのしみ・たのしむ”と解せる。
学研漢和大字典
会意。匹とは、ペアをなしてくっつく意で、男女の性交を示す。甚は「甘(うまい物)+匹(色ごと)」で、食道楽や色ごとに深入りすること。深・湛(タン)(深く水をたたえる)・探(深く手を入れてさぐる)・貪(タン)(深入りしてむさぼる)などと同系。類義語の太は、程度のはげしいこと。頗(ハ)(すこぶる)は、片よって程度を過ごすこと。「尽」に書き換えることがある。「食尽」。
語義
シン(去・上)
- {形容詞}はなはだしい(はなはだし)。ある事に深入りしている。また、ひどい。「甚矣、吾衰也=甚だしきかな矣、吾が衰へたる也」〔論語・述而〕
- {副詞}はなはだ。→語法「①」。
ソモ(唐:平)
- {副詞}《俗語》なに。どんな。《同義語》⇒什。「甚人(ソモニン)(どんな人)」「甚麼生(ソモサン)(なぜ、どうして)」。
字通
[象形]竈(かまど)の上に烹炊の器をかけている形で、烹餁(ほうじん)の意。〔説文〕五上に「尤も安樂するなり。甘匹に從ふ。匹は耦なり」と甘匹の会意とし、男女相媅(たの)しむ意とする。媅の意を以て解するが、古文の字形は竈に鍋をかけた形。斗を以てこれをくむを斟酌(しんしやく)という。〔左伝〕にみえる裨諶(ひじん)は、裨竈(ひそう)と同一人であるらしく、甚・竈対待の名字をもつ人であろう。煮すぎることを過甚という。
哂(シン・9画)
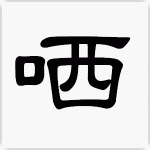
隷書
初出:初出は不明。戦国時代の資料にもないが、時代が下っても『定州竹簡論語』より新しくはない。
字形:「口」+音符「西」siər(平)。「饑」ki̯ər(平)と「饉」ɡʰi̯æn(去)が同じく”不作・飢える”を意味するように、漢代では同音や近音の語尾にnを付け、同じ意味として通用させるのが流行ったらしい。異体字に「弞」とされるが、典拠は宋儒の手に成る『古文四聲韻』などで、信用しがたい。しがたい理由は論語雍也篇3余話「宋儒のオカルトと高慢ちき」を参照。
音:カールグレン上古音はɕi̯ən(上)。同音に「娠」”はらむ”、「矧」”いわんや・ながい・はぐき”。矧の初出は後漢の隷書。”矢を矧ぐ”は日本語だけの語義。
用例:『礼記』曲礼上篇に「笑不至矧」とあるので、おそらく漢代の言葉だろう。歯茎を見せてあざけり笑うこと。
藤堂博士は根が一本気で真面目な人だから、下掲の通り一生懸命この漢字の語義を鹿爪らしく仕立てようとしているが、成功しているとは言えない。
学研漢和大字典
会意兼形声。西は、ざるを描いた象形文字で、すきまから水や息が漏れ去る意を含む。哂は「口+(音符)西」で、口もとから息が漏れること。遷(セン)(中身が抜け去る)と縁が近い。
語義
- {動詞}わらう(わらふ)。しっと歯の間から息を出して含みわらいをする。ほほえむとき、失笑するときの両方に用いる。「夫子哂之=夫子これを哂ふ」〔論語・先進〕
字通
[形声]声符は四(し)。〔玉篇〕に「笑ふなり」とあり、嘲笑的な笑いかたをいう。
津(シン・9画)

翏生盨・西周末期
初出は西周末期の金文。カールグレン上古音はtsi̯ĕn(平)。同音は以下の通り。「グウ」は慣用音、呉音は「ゴ」。『大漢和辞典』で音ゴウ訓たがやすに秴(上古音・初出不明)、耠(カ音・初出不明)、音コウ訓たがやすに耩(上古音・初出不明)、耕kĕŋ(平)・初出は楚系戦国文字。
| 字 | 音 | 訓 | 初出 | 声調 | 備考 |
| 津 | シン | つ | 西周末期金文 | 平 | |
| 盡 | シン | つきる | 甲骨文 | 上 | →語釈 |
| 戩 | セン | ほろぼす | 説文解字 | 〃 | |
| 晉 | シン | すすむ | 甲骨文 | 去 | →語釈 |
| 搢 | シン | はさむ | 説文解字 | 〃 | |
| 縉 | シン | あかぎぬ | 楚系戦国文字 | 〃 | |
| 進 | シン | すすむ | 甲骨文 | 〃 | →語釈 |
漢語多功能字庫
金文從「舟」從「淮」,黃河流域的渡口名,疑因淮水靠近黃河,故從「淮」為意符,後泛指渡口。
金文は「舟」と「淮」の字形の系統に属し、黄河流域の渡し場の固有名詞。おそらく、淮水が黄河と近寄っている場所だったので、「淮」の字形を取り入れて意味記号とし、のちに広く渡し場一般を言うようになった。
学研漢和大字典
会意兼形声。津の字の右側はもと「聿(手で火ばしを持つさま)+火(もえかす)」の会意文字で、小さい燃えかす。または、「聿(手でふでを持っているようす)+彡(しずくがたれるしるし)」の会意文字で、わずかなしずく。津はそれにさんずいを加えたもので、水が少なく、尽きようとしてたれることを示す。のち、うるおす、しめった浅瀬などの意を派生した。盡(=尽。小さくなってつきる)と同系。類義語に港。草書体をひらがな「つ」として使うこともある。
語義
- {名詞}しる。しずくとなってしたたる液体。《類義語》液。「津液(したたるしる)」「口津(つばき)」。
- {名詞}つ。水のうるおす所。浅瀬の舟着き場。渡し場。「関津(渡し場)」「問津=津を問ふ」「使子路問津焉=子路をして津を問は使む」〔論語・微子〕
- {動詞}水分でうるおう。うるおす。《類義語》潤。
- 「津津(シンシン)」とは、あとからあとからと、つばがわくように、興味がわいてくるさま。「興味津津」。
- {名詞}《俗語》生活をうるおす金。手当金。「津貼(シンチョウ)・(シンテン)」。
- {名詞}天津(テンシン)市の略称。
字通

説文解字所収古文
[形声]正字は𣸁に作り、𦘔(しん)声。𦘔は〔説文〕聿部三下に「聿(いつ)(筆)の飾りなり」とするが、𦘔は辛形の針を以て皮膚を刺し、そこより津液のにじみ出る形。その津液を器皿に収めることを𧗁(しん)といい、𧗁字条五上に「气液なり」とみえる。𦘔は入墨のときの津液、そのときの傷痛を衋(きよく)という。衋の字の従う皕(ひよく)の形は、奭(せき)の字にも含まれており、奭は女子の両乳をモチーフとして、そこに加える文身の象。その文身の美をいう字である。津は𦘔の繁文で、その形声の字。〔説文〕十一上に「水渡なり」とするのは別義の字。〔説文〕が津の古文として録する舟と淮とに従う形が、渡し場を意味する字である。〔論語、微子〕に孔子が津を問う話があり、〔書、微子〕に「大水を渉るに、其の、津涯無きが若(ごと)し」とみえる。𦘔に従うものが津液、舟・淮に従う字が津涯の意の字である。
袗(シン・10画)

詛楚文・戦国秦
初出:初出は秦系戦国文字。
字形:「衤」”ころも”+「㐱」”織り目の詰まった”。きめの細かい布で作った衣類の意。
音:カールグレン上古音はȶi̯ən(上)。同音に㐱”豊かな髪”とそれを部品とする漢字群多数。
用例:文献上の初出は論語郷党篇6。戦国時代の『孟子』にも用例がある。
論語時代の置換候補:『大漢和辞典』訓「ひとえ」の同音に「縝」(初出戦国文字)。論語語釈「縝」を参照。また「紾」(初出説文解字)。論語語釈「紾」を参照。上古音の同音は調査しきれない。
学研漢和大字典
会意兼形声。右側の字(音チン・シン)は、びっしりとつまる意を含む。袗はそれを音符とし、衣を加えた字。
語義
- {動詞・名詞}びっしりと細かいぬいとりをする。また、ぬいとりをした衣服。
- {名詞}黒い衣服。墨染め。
- {名詞}目の細かい布でつくったひとえ。単衣。
- {形容詞・名詞}衣の色が服全体に同じで、そろいになっているさま。ひと色の衣服。《類義語》袀(キン)。
字通
[形声]声符は㐱(しん)。〔説文〕八上に「玄服なり」とあり、黒い服。裖はその或る体の字。〔玉篇〕に「玄服なり、縁なり、又、單なり」と衿とりした服とし、また繍などのある礼服をいう。また、襌と通じ、単衣をもいう。
浸(シン・10画)


合13574/寺工師初壺・戦国秦
初出:初出は甲骨文。ただし西周で一旦滅んだ。
字形:甲骨文の字形は「𡨦」で、「宀」”屋根”+”水”+”箒”。雨漏りの様。この字は金文では途絶え、再出は戦国楚の竹簡からになるので、一旦滅んだ漢語と解するのに理がある。楚系戦国文字の字形は多様で、現行字形は秦系戦国文字から。「漢語多功能字庫」は河川名または地名とする。
音:カールグレン上古音はtsi̯əm(去)。同音は「祲」(平/去)”災いを起こす気”「綅」(平)”いと”。
用例:甲骨文の用例は一件のみで、損傷が激しく語義を確定しがたい。
「郭店楚簡」成之4に「君子之於教也,亓(其)道(導)民也不□(浸)」とあり、”おかす=不都合を押し付ける”と解せる。
論語時代の置換候補:日本語で同音訓おかすに「侵」、甲骨文に”おかす”の用例があるものの、金文では一件のみ人名として見られるのみ。同じく「僭」の初出は戦国の竹簡。
学研漢和大字典
会意兼形声。𠬶(シン)は「又(手)+ほうき」の会意文字で、手でほうきを持ち、しだいにすみずみまでそうじを進めていくさまを示す。浸は「水+(音符)𠬶」で、水がしだいにすみずみまでしみこむこと。侵(じわじわとはいりこむ)・沁(しみこむ)と同系。類義語の漬(シ)は、物を重ねて水の中につけこむこと。「滲」の代用字としても使う。「浸透」。
語義
- {動詞}しみる(しむ)。水がじわじわとしみこむ。《同義語》⇒滲(シン)・沁(シン)。「浸潤(しみわたる)」「浸透」。
- {動詞}ひたす。水にひたす。水の中につける。「別時茫茫江浸月=別るる時茫茫(ばうばう)として江月を浸す」〔白居易・琵琶行〕
- {副詞}ようやく(やうやく)。やや。少しずつ。じわじわと。しだいに。《類義語》漸(ゼン)・(ヨウヤク)。「国勢浸盛=国勢浸く盛んなり」。
字通
[形声]旧字は![]() に作り、帚(しん)声。〔説文〕の篆文の字形は濅に作る。帚は祼鬯(かんちよう)のとき、帚(箒(ほうき))に酒を灌いで、その祭場を清める意。濅は廟所を鬯酒(ちようしゆ)(香り酒)で祓い清める意で、その酒気を
に作り、帚(しん)声。〔説文〕の篆文の字形は濅に作る。帚は祼鬯(かんちよう)のとき、帚(箒(ほうき))に酒を灌いで、その祭場を清める意。濅は廟所を鬯酒(ちようしゆ)(香り酒)で祓い清める意で、その酒気を![]() という。〔説文〕十一上に濅を水名とし、呼沱(こだ)河の支流の名とするが、字は寝廟における祼鬯の礼をいう。その廟所をまた寢(寝)という。卜辞に「
という。〔説文〕十一上に濅を水名とし、呼沱(こだ)河の支流の名とするが、字は寝廟における祼鬯の礼をいう。その廟所をまた寢(寝)という。卜辞に「![]() するに、疾亡(な)きか」と卜する例があり、疾病を祓う儀礼にも用いた。■(示+帚)は精気感祥、これを祓うのに濅の儀礼が行われた。
するに、疾亡(な)きか」と卜する例があり、疾病を祓う儀礼にも用いた。■(示+帚)は精気感祥、これを祓うのに濅の儀礼が行われた。
晉/晋(シン・10画)

晉人簋・西周中期
初出は甲骨文。カールグレン上古音はtsi̯ĕn(去)。同音は論語語釈「津」を参照。
学研漢和大字典
会意。「二本の矢+口印(目標)」で、矢が並んで目標めがけてすすむさま。進と同じく、ずんずんと伸びすすむこと。臻(シン)・秦(シン)(すすむ)もこれとほとんど同じ。
語義
- {動詞}すすむ。ずんずんとすすむ。《同義語》⇒進。《類義語》臻(シン)(すすむ)。「孟晋(モウシン)(つとめ励んで、進歩する)」。
- {名詞・動詞}帯に差す短冊型のさしもの。また、それを差す。▽析(シン)に当てた用法。
- {名詞}春秋時代の国の名。もと周の成王の弟、叔虞が封ぜられた国。今の山西省を中心とする地。晋の文公は諸侯の覇者(ハシャ)となったが、のち韓(カン)・魏(ギ)・趙(チョウ)に分裂した。
- {名詞}山西省の別称。
- {名詞}三国時代のあとの王朝の名。司馬炎が魏(ギ)にかわってたてた。のち、元帝のとき、五胡(ゴコ)の侵入によって洛陽(ラクヨウ)から建康(南京)に移った。前半を西晋(四代。二六五~三一六)、後半を東晋(十一代。三一七~四二〇)という。
- {名詞}王朝の名。五代の一つ。石敬滅(セキケイトウ)が後唐(コウトウ)を滅ぼしてたてた。二代で契丹(キッタン)に滅ぼされた。「め」の晋と区別して後晋・石晋ともいう。
- {名詞}周易の六十四卦(カ)の一つ。陝隍(坤下離上(コンカリショウ))の形で、明るさが進んで地上に出るさまを示す。
字通
[象形]旧字は晉に作り、その初文は㬜。臸(じつ)は鏃(やじり)、その鋳型の形。曰(えつ)は鋳こみの流し口。ここから流しこんで鏃を作るので、晉は箭(せん)の初文。箭はその形声の字である。〔説文〕七上に「進むなり。日出でて萬物進む。日に從ひ、臸に從ふ」と会意に解し、また「易に曰く、明、地上に出づるは㬜なり」と〔易、晋、象伝〕の文を引く。晉・進は畳韻の訓。金文の〔師湯父鼎(しとうほてい)〕の賜与中に「矢■(上下に至+至)(しせん)」とあるのは矢箭の意。〔儀礼、大射儀、注〕に「古文、箭を晉と爲す」とするが、晉がその初文である。晉の訓義は〔易、晋〕の卦義から出ている。
唇(シン・10画)
論語微子篇11で定州竹簡論語に記載。確実な初出は説文解字。カールグレン上古音はi̯wən(平)。同音多数。部品の「辰」に、『大漢和辞典』では”くちびる”の語釈が無い。ただし音シン訓くちびるに、「脣」(カ音不明)初出は秦系戦国文字、その異体字「䫃」(上古音不明)を載せる。
定州竹簡論語はもちろん縦書きで、直下で現伝論語では「其」となっている文字の一部「口」を、誤って釈文で取り込んで、辰+口→唇とした可能性がある。

漢語多功能字庫
從「口」,「辰」聲,表示人或動物口的周圍的肌肉組織,也作「脣」。
「口」の字形の系統に属する。「辰」の音。人や動物の、口のまわりの肌部分を意味する。また「脣」とも書く。
学研漢和大字典
会意兼形声。辰(シン)の原字は、貝がらからびりびりとふるえるやわらかい貝の足が出た姿を描いた象形文字。振・震の原字で、弾力をおびてふるえる意を含む。唇は「口+(音符)辰」で、やわらかくてびりびりとふるえるくちびる。▽唇(シン)は、もと、ふるえることで、脣(シン)とは別字であったがのち混用された。
語義
シン
- {動詞}ふるえる(ふるふ)。びりっとふるえる。ふるえて驚く。《同義語》⇒震。
シュン
- {名詞}くちびる。《同義語》⇒脣。「口唇」。
字通
[形声]声符は辰(しん)。辰は蜃の初文。〔説文〕二上に「驚くなり」とあり、震驚の意とする。卜文に■(上下に辰+止)に作る字があり、「今夕、師は■(上下に辰+止)(しん)すること亡(な)きか」のように卜する。夜半に、軍中が何ごとかに震驚するというようなことがあったのであろう。唇下の口は祝禱を示す𠙵(さい)の形で、蜃によって占卜する意の字形かと考えられる。のち唇を口脣の意に用いる。辰に振動の意がある。
秦(シン・10画)


鄦子妝簠・春秋末期
初出は甲骨文。カールグレン上古音はdzʰi̯ĕn(平)。同音は下記の通り。
| 字 | 音 | 訓 | 初出 | 声調 | 備考 |
| 秦 | シン | 禾の名 | 甲骨文 | 平 | |
| 螓 | 〃 | なつぜみ | 不明 | 〃 | |
| 盡 | 〃 | つきる | 甲骨文 | 上 | →語釈 |
| 燼 | 〃 | もえのこり | 後漢隷書 | 去 | |
| 藎 | 〃 | こぶなぐさ | 説文解字 | 〃 |
漢語多功能字庫
甲金文從「午」(「杵」的初文)從「廾」(象雙手)從二「禾」或三「禾」,金文、竹簡或加從「臼」,作從「舂」從「禾」之形,疑會雙手持杵搗禾脫穀之意,脫粒是收穫的重要環節(王文耀、陳秉新),本義是舂搗禾穀。
甲骨文・金文は「午」(「杵」の最古形)と「廾」(両手の象形)と、「禾」または「耒」の字形に属する。金文や竹簡では、「臼」の字形を加えたものがある。「舂」や「禾」の字形は、おそらく両手で杵を突いて脱穀する意味だろう。脱穀は収穫の上で重要な作業過程である(王文耀、陳秉新)。原義は穀物を搗くこと。
学研漢和大字典
会意。「禾+舂(うすでつく)の略体」。もと、生長がはやい植物のこと。
語義
- {名詞}戦国時代の七雄の一つ。東周代初期より、今の陝西(センセイ)省の地を中心に領有した。
- {名詞}王朝名。戦国の七雄の一つであった秦が始皇帝のとき、他の六国を征服してたてた中国最初の統一王朝。三代で漢に滅ぼされた。前二二一~前二〇六。
- {名詞}五胡(ゴコ)十六国の一つ。読(テイ)族の苻健(フケン)がたてた。前秦。三五一~三九四。
- {名詞}五胡十六国の一つ。羌(キョウ)族の姚萇(ヨウチョウ)が前秦を滅ぼしてたてた。後秦。三八四~四一七。
- {名詞}五胡十六国の一つ。鮮卑(センピ)族の乞伏国仁(キップクコクジン)がたてた。西秦。三八五~四三一。
- {名詞}陝西(センセイ)省の別称。▽周代の秦が陝西にあったことから。
字通
[会意]午(杵(きね))+𠬞(きよう)(両手)+禾(か)。両手で午をもち、禾をうつ形。もと打穀を意味する字であろう。〔説文〕七上に「伯益の後の封ぜられし所の國なり。地、禾に宜(よろ)し」と国名に解し、また「一に曰く、秦は禾の名なり」とする。卜文・籀文は両禾に従う。秦は嬴(えい)姓、鳥首人身の始祖神の説話をもつ。
進(シン・11画)


甲骨文/𥃝圜器・西周早期
初出:初出は甲骨文。
字形は「隹」”とり”+「止」”あし”で、一説に鳥類は後ろへ歩けないことから”すすむ”を意味するという。
音:カールグレン上古音はtsi̯ĕn(去)。同音は論語語釈「津」を参照。
用例:「漢語多功能字庫」によると、甲骨文では”献上する”の意に、金文では”奉仕する”の意に(兮甲盤・西周末期)、戦国の金文では”推挙する”の意に用いた(中山王方壺・戦国初期)。戦国の竹簡では、”進歩”、”前進”の意に用いた。
学研漢和大字典
会意。「辵+隹(とり)」で、鳥が飛ぶように前にすすむことをあらわす。信(すらすらとすすむ、いつわりのないことば)と同系。異字同訓に勧める「入会を勧める。転地を勧める」 薦める「候補者として薦める」。
語義
- {動詞}すすむ。すすめる(すすむ)。すいすいと前へ出る。前へ出す。人前に出る。《同義語》⇒晋・臻。《対語》⇒退。「前進」「雖覆一簣、進吾往也=一簣を覆すと雖も、進むは吾が往くなり」〔論語・子罕〕
- {動詞}すすむ。すすめる(すすむ)。高い地位、よいほうに移る。また、高い地位、よいほうに移す。「先進」「栄進」「国君進賢、如不得已=国君賢を進むるには、已むを得ざるがごとくす」〔孟子・梁下〕
- {動詞}すすめる(すすむ)。人の前にさし出す。さしあげる。「進呈」「進言」。
- {動詞・名詞}《俗語》はいる。とりこむ。収入。《対語》⇒出。《類義語》入。「進門(チンメン)」。
- {動詞}《俗語》輸入する。《対語》出。「進口(チンコウ)(輸入)」。
- 《日本語での特別な意味》じょう。四等官で、職・坊の第三位。
字通
[形声]声符は隹(すい)。〔説文〕二下に「登(すす)むるなり」、〔玉篇〕に「前(すす)むるなり、升(のぼ)すなり、登むるなり」とあって、進饌の意とする。字はもと進退に関して、鳥占(とりうら)によってことを決する意であろう。鳥占の俗には、軍事に関することが多く、たとえば鷹狩りによって神意の応答を試みるなどのことも行われた。
深(シン・11画)


「甲骨文合集」5362 /『字通』所収金文
初出:初出は甲骨文。
字形:「氵」”川”+「罙」”さぐる”。「罙」は「探」の初文とされ、甲骨文の字形は水の入った深い容器に手を突っ込むさま。従って「深」は”川や池が深い”。
音:カールグレン上古音はɕi̯əm(平)。同音は論語語釈「審」を参照。
用例:甲骨文の用例は破損がひどくて文として解読できない。
春秋末期までの用例に石鼓文があるが、これも破損がひどくて文として解読できない。
金文の初出は戦国末期の「中山王□壺」(集成9735)で、「□(惠)□(愛)□(深)則□(賢)人□(親)」とあり、”心が深い”と解せる。
戦国早期の竹簡「曾侯乙楚墓」171は破損がひどくて文として解読できない。
戦国中末期の竹簡「郭店楚簡」五行46に「罙(深),莫敢不罙(深);淺,莫敢不淺。」とあり、”深い”と解せる。
学研漢和大字典
会意兼形声。右側は、もと「穴(あな)+火+又(手)」の会意文字で、穴の中に奥ふかく手を入れて火をさぐるさま。探(おくふかくさぐる)の原字。深はそれを音符とし、水を加えた字で、水の奥ふかいこと。湛(タン)(奥ふかい水)・潭(タン)(奥ふかい水)・甚(ふか入りしている、ひどい)・沈(奥ふかくしずむ)などと同系。
語義
- {形容詞・名詞}ふかい(ふかし)。ふかさ。水がふかいさま。また、その度合い。《対語》⇒浅。「深浅」「深淵(シンエン)」「深千尺(深さ千尺)」。
- {形容詞}ふかい(ふかし)。表面からずっと中にはいっているさま。奥ふかい程度がひどいさま。《類義語》遠。「深遠」「深刻」「智深而勇沈=智深くして而勇沈なり」〔史記・荊軻〕。「深耕易耨=深く耕して易かに耨す」〔孟子・梁上〕
- {形容詞・動詞}ふかい(ふかし)。夜がふけているさま。夜がふける。「夜深=夜深し」。
- {形容詞}ふかい(ふかし)。色がこい。《対語》浅。「深紅」。
- {副詞}ふかく。心の底にふかく。「深信=深く信ず」。
- {副詞}はなはだ。非常に。▽甚(ジン)に当てた用法。「深好=深だ好し」。
- 《日本語での特別な意味》み。奥ふかいことをあらわすことば。「深雪」「深山」。
字通
[形声]声符は罙(しん)。罙の初文を〔説文〕七下に𥥍とし、「𥥍は深なり。一に曰く、竈突(さうとつ)なり。穴に從ひ、火に從ひ、求の省に從ふ」とするが、字は火をもって穴中を照らす形である。廟中で火をもつものを叜というのと似た形である。〔爾雅、釈言〕に「㴱は測るなり」とあり、水深を測る意とする。〔礼記、楽記〕に「高きを窮め、遠きを極めて、深厚を測る」とあって、測る意のある字。ものを捜求するを探というが、罙も捜の従う叟と同じように、火を執ってものを探す意の字であろう。これを水中に及ぼして深という。
紾(シン/テン・11画)

説文解字・後漢
初出:初出は後漢の『説文解字』。
字形:「糸」+「㐱」”織り目の詰まった”。織り目の詰まった布の意。
音:カールグレン上古音はȶi̯ən(上)またはȶi̯an(上)。前者の漢音はシン、同音は「㐱」とそれを部品とする漢字群、「震」など「辰」を部品とした漢字群。後者の漢音はテン、同音は「氈」など「亶」を部品とした漢字群、「戰」など「單」を部品とした漢字群。
用例:文献上の初出は戦国時代の『孟子』。論語郷党篇6の唐石経にも見られる。ただし「紾」を現伝論語では「袗」と記す。詳細は論語語釈「袗」を参照。古注『論語集解義疏』では「縝」と記す。詳細は論語語釈「縝」を参照。
論語時代の置換候補:訓「ひとえ」では、『大漢和辞典』の同音同訓に「縝」があり、初出は楚系戦国文字。また「裖」があり一説に初出は甲骨文というが、原典に当たれず金文や戦国文字の例が無い。カールグレン上古音も不明。「袗」の初出は秦系戦国文字。
学研漢和大字典
会意兼形声。「糸+(音符)㐱(シン)(めが細かい)」。
語義
テンȶi̯an(上)
{動詞}ねじる(ねづ・ねぢる)。ねじ曲げる。間をつめてなわをよる。「紾兄之臂=兄の臂を紾る」〔孟子・告下〕
シンȶi̯ən(上)
{名詞}めの細かい織物。ひとえの着物。《同義語》⇒縝。
字通
(条目無し)
紳(シン・11画)


曾15・戦国中期/「呻」伯晨鼎・西周中期偏晚
初出:「小学堂」による初出は甲骨文とするが、字形は〔東又〕。ほかに金文「𤳞」「𤕌」などの字形を「紳」として載せるが、いずれも”おび”での用例は無い。事実上の初出は楚系戦国文字。「𤕌」については論語語釈「畜」も参照。
字形:「糸」+「𠙵」”くち”x2+「乙」”糸”+「又」”手”。つくりはのちに「申」”いなずま”へと収斂進化するが、いなずまとは関係が無く、人手をかけて織り上げること。
音:カールグレン上古音はɕi̯ĕn(平)。同音は論語語釈「身」を参照。
用例:戦国中期「曽公乙楚墓」15に「雘紳」とあり、”おび”と解せる。「雘」は上等の朱色の染料。
論語時代の置換候補:西周中末期「白䢅鼎」(集成2816)に「畫呻」とあり、”おび”と解せる。「呻」ɕi̯ĕn(平)で同音同調。
学研漢和大字典
会意兼形声。申の甲骨文字はのびていく稲妻を描いた象形文字。ただし篆文(テンブン)は「臼(両手)+┃印(まっすぐ)」の会意文字で、手でまっすぐにのばすことを示す。紳は「糸(ひも)+(音符)申」で、からだをまっすぐのばすおび。伸(のびる、のばす)と同系。
語義
- {名詞}ふとおび。からだをまっすぐのばすおび。転じて、高官が用いる礼装用の太いおび。「紳帯」「加朝服尽紳=朝服を加へ紳を尽く」〔論語・郷党〕
- {名詞}地位・教養が備わったりっぱな人。インテリ。知識人。「搢紳(シンシン)(仕官して礼服をつける官吏)」「郷紳(郷里に引退した者)」「紳士」。
字通
[形声]声符は申(しん)。申はものを束ねること。申束する意がある。〔説文〕十三上に「大帶なり」とあり、大帯には素また練を用いた。〔詩、衛風、有狐〕の〔伝〕に「帶は衣を申束(しんそく)する所以(ゆゑん)なり」、〔礼記、少儀、注〕に「帶は自ら結束する所以なり」という。〔論語、衛霊公〕「子張、諸(こ)れを紳に書す」とは、大帯の垂れた余りの部分に、孔子の語を急いで書きとどめたことをいう。
晨(シン・11画)

『字通』所収金文
初出は甲骨文。カールグレン上古音はȡi̯ən(平)。論語語釈「晶」も参照。
学研漢和大字典
会意兼形声。辰(シン)は、二枚貝が開いて、ぺらぺらと震える舌を出したさまを描いた象形文字。蜃(シン)(はまぐり)の原字。晨は「日+(音符)辰」で、日がふるいたってのぼってくること。また生気のふるいたって動きはじめるあさ。震(ふるう)・振と同系。類義語に朝。
語義
- {名詞}あさ。あした。太陽がふるいたってのぼるあさ。生気に満ちた早朝の意に用いる。「清晨(セイシン)(さわやかなあさ)」「晨炊蓐食=晨に炊げども蓐食す」〔史記・淮陰侯〕
- {名詞}とき。早朝、鶏がときを告げること。「牝鶏之晨(ヒンケイノシン)(早朝、めんどりがときを告げること。女性がいばって政治を乱すたとえ)」〔書経・牧誓〕
- {名詞}二十八宿の一つ。房星。
字通
[形声]正字は曟に作り、辰(しん)声。〔説文〕七上に「房星なり。民の田時を爲す者なり」とし、星の名とする。〔爾雅、釈天、星名〕に「大辰は房心(星宿の名)の尾なり。大火、之れを大辰と謂ふ」とあり、〔国語、周語上〕に「農祥は晨正なり」とあって、農時を示すものとされた。晶は星の象。星の初文は曐に作る。晨は晨旦・昧爽の意である。〔説文〕は䢅字条三上に「早なり。昧爽なり」とする。䢅は辰(しん)(脤肉)を両手でもつ形で、金文の〔師䢅鼎(ししんてい)〕の字は■(上下に辰+止)に従う形に作り、昧晨の字とは形が異なる。経伝の文に、昧晨の字には晨を用い、䢅を用いることはほとんどない。農の初文䢉はその形に従っており、晨を農祥とすることは、その䢉の字と関係があろう。
診(シン・12画)
初出は秦系戦国文字。論語の時代に存在しない。カールグレン上古音はȶi̯ən(上)。同音多数。
”みる”類義語の一覧については、論語語釈「見」を参照。
学研漢和大字典
会意兼形声。彡は、髪の字の右上と同じで、毛が並んで生えているさま。診の右側の字(音シン)は、すきまなく髪の毛が生えているさま。診はそれを音符とし、言を加えた字で、すみずみまで手ぬかりのないようにみて判断を下すこと。慎(シン)(すみずみまで心を配って、手ぬかりのないよう用心する)と同系。
語義
- {動詞}みる。みおとしのないようにすみずみまでみて、その事がらについて判断を下す。よくみる。また、病状をよく調べる。「診察(病状をみて、病気を判断する)」「特以診脈為名耳=特に脈を診るを以て名と為すのみ」〔史記・扁鵲〕
- {動詞}うらなう(うらなふ)。夢うらないをする。夢の内容からその吉凶の判断をする。「匠石覚而診其夢=匠石覚めて其の夢を診ふ」〔荘子・人間世〕
字通
[形声]声符は㐱(しん)。㐱は人の発疹のある形。〔説文〕三上に「視るなり」とあり、〔列子、力命〕「其の疾む所を診(み)る」のように、診察することをいう。〔荘子、人間世〕「匠石(人の名)覺めて其の夢を診(つ)ぐ」は告知する意。その験証したところを以て告げることをいう。
愼/慎(シン・13画)


師望鼎・西周中期/邾公華鐘 春秋晚期
初出:初出は西周中期の金文。
字形:新字体は「慎」。ただし「小学堂」ではコード上の正字として扱っている。
「漢語多功能字庫」による原義は”つつしむ”。初出金文の字形は、「𨸏」(阝)”はしご”+「斤」”近い”+「心」で、現行の字体とは異なる。はしごを伝って神が降りて近づいた時のような心、を言うのだろう。
音:カールグレンによる上古音はȡi̯ĕn(去)。
用例:西周中期『殷周金文集成』02812「師望鼎」に「□(阝斤心)(慎)氒(厥)德」とあり、「その徳をつつしみ」と読め、”つつしむ”の語義が確認できる。
西周末期『殷周金文集成』00109「井人鐘」に「克質(慎)氒(厥)德」とあり、「よくその徳を慎み」と読め、「質」が「慎」として用いられている。
西周末期『殷周金文集成』02836「大克鼎」では「悊」が「慎」として用いられている。
西周末期『殷周金文集成』04326「番生𣪕蓋」では「克慎氒(厥)德」とある。
春秋末期『殷周金文集成』00245「鼄(邾)公華鐘」では字形が変わって「昚」と記され、「昚」は「慎」の古字と『大漢和辞典』はいう。
備考:「斤」ki̯ənは「近」ɡʰi̯ən(上/去)の原字だが、「近」の代用として用いられた例は、戦国時代の郭店楚簡までしか遡らない。ただし西周早期の金文「征人鼎」にある「才斤」は、「近くに在り」である可能性がある。
学研漢和大字典
会意兼形声。眞(シン)(=真)は、欠けめなく充実したこと。愼は「心+(音符)眞」で、心が欠けめなくすみずみまでゆきとどくこと。填(テン)(欠けめなく詰める)と同系のことば。類義語の祗(シ)は、うやうやしいこと。謹(キン)は、こまかに気を配ること。恪(カク)は、心にかどめをつけること。虔(ケン)は、きちんと整ったこと。敬(ケイ)は、はっと緊張してかしこまること。恭(キョウ)は、両手でささげるような、うやうやしい気持ちのこと。欽(キン)は、からだをかたくとじたさまをしてつつしむこと。
異字同訓に慎む「身を慎む。酒を慎む。言葉を慎む」 謹む「謹んで聞く。謹んで祝意を表する」。旧字「愼」は人名漢字として使える。
語義
- {動詞・形容詞}つつしむ。念を入れる。欠けめなく気を配る。また、そのさま。《対語》⇒慢(マン)・怠(タイ)。「謹慎」「慎思之=慎んでこれを思ふ」〔中庸〕
- {名詞}つつしみ。つつしみ深いこと。念入りな心。
備考:『大漢和辞典』「真」条

新(シン・13画)


甲骨文/郘大叔斧・春秋
初出:初出は甲骨文。
字形:甲骨文の字形は「辛」”針または刃物”+「木」+「斤」”おの”で、早期の字形では「木」を欠く。切り出した丸太の中央に太い針を刺し、それを軸に回しながら皮を剥くさま。真新しい木肌が現れることから、原義は”新しい”。
音:カールグレン上古音はsi̯ĕn(平)。
用例:「漢語多功能字庫」によると、甲骨文では原義で、また地名・人名・祭祀名に用いた。金文でも同様。
学研漢和大字典
会意兼形声。辛は、鋭い刃物を描いた象形文字。新の左側の字(音シン)は「木+(音符)辛」の会意兼形声文字で、木を切ること。新はそれを音符とし、斤(おの)を加えた字で、切りたての木、なまなましい意。薪(シン)(なま木、まき)と同系。類義語の鮮(セン)は、なまなましいこと。草書体をひらがな「し」として使うこともある。
語義
- {形容詞}あたらしい(あたらし)。あらた。切りたてであるさま。はじまったばかりであるさま。《対語》⇒旧・故。《類義語》鮮。「新鮮」「新年」。
- {名詞}あたらしき。あたらしい物事。「温故而知新=故きを温めて新しきを知る」〔論語・為政〕。「吐故納新=故きを吐きて新しきを納る」〔荘子・刻意〕
- {動詞}あらたにする(あらたにす)。あたらしいものにする。汚れを取り去って出なおす。「面目一新(メンボクイッシン)(すっかりようすを新しくする)」「日日新=日日に新たにす」〔大学〕。「改過自新=過ちを改めて自ら新たにす」〔漢書・刑法志〕
- {副詞}あらたに。…したばかり。近ごろ。「新嫁娘(花嫁)」「潦倒新亭濁酒杯=潦倒新たに亭む濁酒の杯」〔杜甫・登高〕
- {名詞}王朝の名。漢の王莽(オウモウ)が新都侯となり、前漢を滅ぼしてたてたが、紀元八年から二三年までで滅亡した。
- 《日本語での特別な意味》
①にい(にひ)。あら。あたらしい意をあらわすことば。「新妻(ニイヅマ)」「新湯(アラユ)」。
②しん。太陽暦のことの、「新暦」の略。「新の正月」。
字通
[会意]辛(しん)+木+斤(きん)。辛は針。新木を伐るとき、選木のために矢や針をうつ俗があった。〔説文〕十四上に「木を取るなり」とし、■(上下に辛+木)(しん)声とする。〔説文〕六上は■(上下に辛+木)を「■(上下に辛+木)實なり。小栗の如し」(段注本)と榛栗の意とし、声符とするが、(上下に辛+木)は木と辛(針)とに従い、入山して新木を伐る儀礼と解すべく、かくしてえた新木を以て神位を作る。これを拝するを親という。これらの字の従う(上下に辛+木)は、みな意符とみるべきである。卜辞において、新は新廟・新宗・新家など、多く寝廟に関する字に用いる。卜文に■(宀+新)の字があり、金文に親をまた■(宀+新)に作る。いずれも廟屋の形に従う字である。草木を併せて薪といい、薪も神事に用いるもので、〔詩〕には多く采薪の俗が歌われているが、それらは祭事詩の発想に用いられている。
寑・寢/寝(シン・13画)


甲骨文/小臣卣・殷代末期
初出:「寑」の初出は甲骨文。「寢」の初出は春秋末期の金文。
字形:「宀」”屋根”+「帚」”ほうき”で、すまいのさま。原義は”住まい”。
![]()
慶大蔵論語疏は異体字「〔穴彳𠬶〕」と記す。『干禄字書』(唐)所収。
音:「寑」のカールグレン上古音はtsʰǐəm(上)。「寢」のカールグレン上古音はtsʰi̯əm(上)。
用例:「漢語多功能字庫」によると、甲骨文では原義で用い、金文では原義(麥尊・西周早期)、”祖先廟”(師遽方彝・西周中期)、官職名(𡨦魚簋 金文・年代不明)を意味した。
備考:寑
「寑」に条目があるのは『大漢和辞典』のみで、『学研漢和大字典』『字通』『漢字源』『新漢語林』『新字源』には条目が無い。『中日大字典』は「寢」の異体字として取り扱っている。「漢語多功能字庫」の条目にある情報はほぼ無し。「国学大師」は「寢」の異体字として取り扱っている。
学研漢和大字典
寑
(条目無し)
寢
会意兼形声。侵は、しだいに奥深くはいる意を含む。寢は、それに宀(いえ)を加えた字の略体を音符とし、爿(しんだい)を加えた字で、寝床で奥深い眠りにはいること。浸(水が奥深くしみこむ)と同系。類義語に睡。旧字「寢」は人名漢字として使える。
語義
- {動詞}ねる(いぬ・ぬ)。活動をやめて深い眠りにはいる。夜、眠る。または病気のため、奥のへやにはいって眠る。《対語》⇒覚。「宰予昼寝=宰予昼寝ぬ」〔論語・公冶長〕
- {名詞}寝床での本式の眠り。「就寝=寝に就く」「覚寝而説=寝より覚めて説ぶ」〔韓非子・二柄〕
- {動詞}やめる(やむ)。活動をやめる。また、採用をとりやめる。「寝其議=其の議を寝む」。
- {名詞}奥まったへや。本式の座敷。「燕寝(エンシン)(くつろぐ居室)」「正寝(奥の客間)」。
- {名詞}皇帝の墓のそばにこしらえた、墓祭りのために泊まるへや。「陵寝」。
字通
寑
(条目無し)
寢
[会意]正字は㝲に作り、夢の省文+𡪷 (しん)。夢は夢魔。夢魔によって死ぬことを薨という。㝲は寝臥中に夢魔に襲われることをいう。〔説文〕七下に「病みて臥するなり」とし、㝱の省に従い、𡨦(しん)の省声に従う字であるという。㝱は前条に「寐(い)ねて覺むること有るなり」とみえ、夢みてめざめる意。㝲はその夢魔におびやかされる意で、「寝廟」の寢とは同字でない。寝廟の寢の初文は𡨦。帚は箒の形で、これに酒を灌(そそ)いで祼鬯(かんちよう)し、霊廟を清める意で、寝廟の意となる。寢は寝臥、㝲は夢魔の象を加えた字。夢は媚蠱(びこ)(まじない)のなすところで、夢の上部は媚女の象である。
大漢和辞典
審(シン・15画)

楚王酓審盂・春秋中期
初出は西周中期の金文。カールグレン上古音はɕi̯əm(上)。同音は下記の通り。
| 字 | 音 | 訓 | 初出 | 声調 | 備考 |
| 深 | シン | ふかい | 甲骨文 | 平/去 | →語釈 |
| 沈 | チン/シン | しづむ | 甲骨文 | 去(上) | 平(去)は「朕」と同音 |
| 審 | シン | つまびらかにする | 西周中期金文 | 去(上) |
漢語多功能字庫
金文「宀」從「米」從「口」,睡虎地秦簡、馬王堆漢帛書下從「日」,構形初義不明,至小篆「米」訛變為「釆」,「口」訛變為「田」。
金文は「宀」と「米」と「口」の字形に属し、睡虎地秦簡、馬王堆漢帛書は下部に「日」を記す。字形の原義は不明、小篆になって「米」が「釆」に変わり、「口」は「田」に変わった。
学研漢和大字典
会意。番(ハン)は、穀物の種を田にばらまく姿で、播(ハ)の原字。審は「宀(やね)+番」で、家の中に散らばった細かい米つぶを、念入りに調べるさま。類義語の悉(シツ)は、細かいところまで全部知りつくすの意。詳は、明白に比べあわせて吟味すること。「つまびらか」は「詳か」とも書く。
語義
- {形容詞・副詞}つまびらか(つまびらかなり)。詳しくて、こまごました点まで明らかなさま。念入りに。《類義語》悉(シツ)。「審詳」「何相信之審耶=何ぞ相ひ信ずること之審らかなる耶」〔捜神記〕
- {動詞}つまびらかにする(つまびらかにす)。細かく見きわめる。すみずみまでよく理解する。「審考」「審法度=法度を審らかにす」〔論語・尭曰〕。「未審=いまだ審らかにせず」。
- {動詞}つまびらかにする(つまびらかにす)。細かく調べる。「審判」「審査」。
- {副詞}まことに。ほんとうに。「審如此=審に此くのごとし」。
- 《日本語での特別な意味》
①「審議会」の略。「中教審」。
②「審判員」の略。「主審」「副審」。
字通
[会意]正字は宷。宀(べん)+釆(べん)。篆文は審に作り、番に従う字とする。釆は獣爪。田はその掌。番は掌と獣爪の全体を示す形。〔説文〕二上に「悉(つく)すなり。知ること宷諦(しんてい)なるなり」とあり、釆を悉の意を以て解する。悉二上には「詳盡なり」という。宷は廟中に釆・番を供する形で、犠牲として用いるものには、その角・蹄・毛色など詳審な吟味を加えた。犠牲を慎重に扱うことから、詳審・審定の意となった。
親(シン・16画)
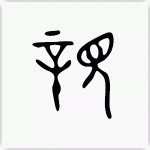
克鎛・西周晚期
初出:初出は西周末期の金文。
字形:金文の字形は「辛」”針・小刀”+「見」。おそらく筆刀を使って、目を見開いた人が自分で文字を刻む姿。
「国学大師」は犯罪者を見張るさまだという。だがそれから”みずから”の意になった理由を説明していない。「漢語多功能字庫」は字解をせず、金文での語義は”みずから”であり、例外として”衣服”を意味するという。
音:カールグレン上古音はtsʰi̯ĕn(平)。同音は「寴」”したしい”のみで、初出は西周中期の金文。去声の音は不明。
用例:西周中期の金文「盠駒尊」に、「王親旨盠。」とあり、「王したしく盠(人名)にみことのりす」と読め、”したしく”・”みずから”の語義が確認できる。
西周中期の金文「王臣𣪕」に、「易女朱黃𠦪親。玄衣黹屯。」とあるのは、「襯」”肌着”と釈文されている。
春秋末期までに、”おや”の用例は確認できない。
漢語多功能字庫
金文は「辛」と「視」の古文の字形に属し、原義は自分(で)。
学研漢和大字典
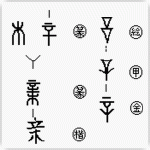

会意兼形声文字で、辛(シン)は、はだ身を刺す鋭いナイフを描いた象形文字。親の左側は薪(シン)の原字で、木をナイフで切ったなま木。親はそれを音符とし、見を加えた字で、ナイフで身を切るように身近に接して見ていること。じかに刺激をうける近しい間がらの意。類義語の戚(セキ)は、小さいの意を含み、隔ての小さいみうち。
語義
- {動詞・形容詞}したしむ。したしい(したし)。ちかい(ちかし)。身近に接している。じかにはだ身にふれる。《対語》⇒疏(ソ)(うとい)。「親疏(シンソ)」「親切」「人之親其兄之子=人の其の兄の子を親しむ」〔孟子・滕上〕
- {副詞}したしく。みずから(みづから)。自分でじかに。直接に。《類義語》自・躬(キュウ)。「親迎」「親書」「親征(天子*みずから征する)」。
- {動詞}みずからする(みづからす)。自分で行う。「弗躬弗親、庶民弗信=躬らせず親らせずんば、庶民信ぜず」〔詩経・小雅・節南山〕
- {名詞}おや。じかに接している父・母のこと。「双親(父母)」「仁之実事親是也=仁の実は親に事ふること是なり」〔孟子・離上〕
- {名詞}身近なみうち。《類義語》戚(セキ)。「親戚」「六親(父子兄弟夫婦)」「親戚畔之=親戚もこれに畔く」〔孟子・公下〕
- {名詞}結婚によって縁つづきとなった身うち。▽去声に読む。「親家(婚姻によってできた身うち)」。
- 《日本語での特別な意味》おや。勝負事や組の主となる人。
*「天子」の言葉が中国語に現れるのは西周早期で、殷の君主は自分から”天の子”などと図々しいことは言わなかった。詳細は論語述而篇34余話「周王朝の図々しさ」を参照。
字通
辛(ハリ)+木+見で、神事に用いる木を選ぶためにハリを打ち、切り出した木材を「新」といい、新で位牌を作って拝むことを「親」という。それが”おや”の意味に転じたのは、新しい位牌は父母のものであることが多いからであろう。
縝(シン・16画)
初出:初出は戦国中末期の楚系戦国文字。ただし字形が確認できない。
字形:現伝の字形は「糸」+「眞」(真)”満ちた”。織り目の詰まった布の意。北宋の『広韻』から「紾」と同義と見なされ、”単衣”の意。

慶大蔵論語疏は異体字「〔糸真〕」と記し、「糸」の下半分「小」を「一」と崩す。「唐韋端玄堂誌」刻。
音:カールグレン上古音はȶi̯ĕn(平)。同音は「眞」とそれを部品にした漢字群、「挋」”足す・束ねる”。
用例:戦国中末期「包山楚墓」122に「士尹紬縝返孓」とあり、何らかの織物と推察できる。
論語郷党篇6、現伝本では「袗」と記す。詳細は論語語釈「袗」を参照。唐石経では「紾」と記す。詳細は論語語釈「紾」を参照。
論語時代の置換候補:『大漢和辞典』に同音同訓は無い。上古音の同音に語義を共有する可能性があるのは「眞」だけだが、春秋末期までに織物を意味する用例は無い。
備考:『大漢和辞典』に『広韻』を引いて”ひとえ”の語釈がある。
学研漢和大字典
会意兼形声。「糸+(音符)眞(シン)(びっしり充実する)」。
語義
- (シンナリ){形容詞}織りめがつまって細かくて緻密(チミツ)である。「縝緻(シンチ)」。
- {名詞}びっしり生えた髪。▽螽(シン)に当てた用法。
- {名詞}目の細かいひとえの着物。
字通
[形声]声符は眞(真)(しん)。字はもと枲(し)に従って眞声。あさいとをいう。こまかく結ぶ意があり、「縝密」のように用いる。
諶(シン・16画)

諶鼎・西周末期
初出は西周末期の金文。カールグレン上古音はȡi̯əm(平)。「ジン」は呉音。
学研漢和大字典
会意兼形声。「言+(音符)甚(シン)(深い)」。
語義
- {名詞}まこと。深い心の底。真心。また真実。
- {副詞}まことに。たしかに。実に。「諶荏弱而難持=諶に荏弱(じんじゃく)にして持し難(がた)し」〔楚辞・哀郢〕
字通
[形声]声符は甚(じん)。〔説文〕三上に「誠諦なり」とあり、誠をつくすことをいう。〔書、咸有一徳〕に「天は諶(まこと)にし難し」の句がある。訦・忱と声義が通ずる。
※訦・忱:”まこと”。
譖(シン・21画)

戎生鐘・西周中期偏晚
初出:初出は西周中期の金文。
字形:「言」+「朁」”けもの2つ+𠙵”。原義不明。
音:カールグレン上古音はtʂi̯əmi̯əm(去)。
用例:西周中末期「戎生鐘」(新收殷周青銅器銘文暨器影彙編NA1616)は、あるいは春秋早期と言われ、「卑(俾)譖征□(繁)湯(陽)」とあるが、何を言っているか分からない。
「清華大学蔵戦国竹簡」清華七・越公其事47に「又(有)賞罰,善人則由,朁(譖)民則伓(背)。」とあり、”ウソをつく”と解せる。
学研漢和大字典
会意兼形声。覚(セン)は、細い所へはいりこむこと。譖は「言+(音符)覚」で、ちょっとしたすき間から、じわじわと悪口をしみこませること。潛(セン)(=潜。水にもぐる)・簪(シン)(髪の毛のすき間にさしこむかんざし)と同系。
語義
- {動詞・名詞}そしる。そしり。じわじわと悪口をいう。中傷のことば。「浸潤之譖(シンジュンノソシリ)」〔論語・顔淵〕
- (シンス){動詞・形容詞}細かい手くだで事実をかくす。いつわる。いつわって真心がない。「朋友已譖=朋友已に譖す」〔詩経・大雅・桑柔〕
字通
(条目無し)
新漢語林
- 《音訓》シン沁zèn
- 《音訓》セン艶jiàn
- うったえる。うそを言ってうったえる。
そし-る。事実をまげて悪口をいう。あることないことを言って讒言(ザンゲン)する。また、そしり。 - いつわる。たがう。=僭。
人(ジン・2画)


甲骨文/洹子孟姜壺・春秋晚期
初出:初出は甲骨文。
字形:字形は人の横姿の象形。
音:「ニン」は呉音。カールグレン上古音はȵi̯ĕn(平)。
「人」と近音で”かれ”を意味する漢字は、『大漢和辞典』によれば「爾」ȵi̯ăr(上)のみ。音素の共通は50%で、音通するとは断じかねる。
用例:甲骨文・金文では、人一般を意味するほかに、”奴隷”を意味しうる。対して「大」「夫」などの人間の正面形には、下級の意味を含む用例は見られない。論語語釈「大」を参照。
”他人”を意味しうることについては、現代日本語でも「ひと」を”他人”の意として用いるのと共通しているが、英語のhumanにその語義があるという話は聞かないので、人類の言語に普遍的現象とは言えない。
「漢語多功能字庫」によると、甲骨文で国名・氏族名で用いられ、金文では西周末期の「甫人父匜」で、”年”の意味での用例があるという。
学研漢和大字典
象形。人のたった姿を描いたもので、もと身近な同族や隣人仲間を意味した。▽孔子は、その範囲を「四海同胞」というところまで拡大し、広く隣人愛の心を仁(ジン)(ヒューマニズム)と名づけた。
二(ニ)・(ジ)(二つくっついて並ぶ)・爾(ニ)・(ジ)(そばにくっついている相手、なんじ)・尼(ニ)(相並び親しむ人)・仁と同系。類義語に民。付表では、「一人」を「ひとり」「二人」を「ふたり」「若人」を「わこうど」「大人」を「おとな」「玄人」を「くろうと」「素人」を「しろうと」「仲人」を「なこうど」と読む。
語義
- {名詞}ひと。人間。「宋人(ソウヒト)(宋の国の人)」「人而無信、不知其可也=人にして信無(な)くんば、その可なることを知らざるなり」〔論語・為政〕
- {名詞}ひと。他人。《対語》⇒己(オノレ)・我。「人我」「己欲立而立人=己立たんと欲して人を立つ」〔論語・雍也〕
- {副詞}ひとごとに。ひとびと。人々の略。「人給、家足=人ごとに給し、家ごとに足る」〔史記・太史公自序〕
- {単位詞}人数を数えることば。「三人行必有我師焉=三人行へば必ず我が師有り」〔論語・述而〕
- 《日本語での特別な意味》じん。物事を三段階に分けるときの第三。「天地人」。
字通
[象形]人の側身形。〔説文〕八上に、「天地の性、最も貴き者なり」とし、字形について「此れ籀文(ちうぶん)、臂脛(ひけい)の形に象る」という。卜文・金文はみなこの形に作り、匈(きよう)(胸)・包・身など、みなこの形に従う。
仁(ジン・4画)

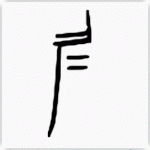
甲骨文/中山王鼎・戦国初期
初出:初出は甲骨文。春秋時代の金文「魯白愈父盤」などに![]() とあるのを「仁」と釈文することがある。しかしこれは「二千」を意味する字形で、「仁」ではない。論語語釈「千」を参照。
とあるのを「仁」と釈文することがある。しかしこれは「二千」を意味する字形で、「仁」ではない。論語語釈「千」を参照。
字形:字形は「人」+「二」”敷物”。原義は敷物に座った”貴人”。
音:カールグレン上古音はȵi̯ĕn(平)。同音は「人」(平)のみ。
用例:![]() は「姬仁朕」または「姬仁𠤳」として器の名。春秋末期までの出土例は全て
は「姬仁朕」または「姬仁𠤳」として器の名。春秋末期までの出土例は全て![]() の形で、「仁」と解せる例は無い。
の形で、「仁」と解せる例は無い。
論語では、孔子の肉声であれば”貴族(らしさ)”、後世の捏造であれば”常時無差別の高尚な愛”。論語における「仁」も参照。
漢語多功能字庫
詳解
金文從「人」從「二」,「人」亦聲,表示人與人之間的親和關係;戰國竹簡從「心」,「身」聲,一說「心」指出自人心之關愛,而「身」亦聲亦義,指懷孕的婦人,故「仁」直指對他者出自本心之關愛。
《論語.顏淵》:「樊遲問仁,子曰:『愛人。』」《左傳.隱公六年》:「親仁、善鄰,國之寶也。」《說文》:「仁,親也。从人从二。忎,古文仁从千、心。𡰥,古文仁或从尸。」
金文不從「人」而從「尸」,與《說文》古文相同,古文字的「尸」是「人」的一種寫法,象箕踞而坐的人形。「尸」亦是「仁」的聲符。《說文》古文「忎」是從「身」從「心」的戰國「仁」字的訛寫,「千」是「仁」的聲符。
金文表示仁愛,中山王鼎:「克順克卑,亡(無)不䢦(率)仁」。意謂謙卑恭順,沒有事情不遵循仁德。
戰國竹簡表示仁德,《郭店簡.唐虞之道》簡2:「利天下而弗利也,仁之至也。」《郭店簡.性自命出》簡55:「䈞(篤)於仁者也」,表示一心一意持守仁德。
璽印文字也表示仁德,《璽彙》4507:「忠仁」。
漢帛書通假為「仞」,《馬王堆帛書.老子甲本》第57行:「百仁(仞)之高,台(始)於足[下]。」《老子.第六十四章》:「千里之行,始於足下。」
金文は「人」と「二」の字形で構成。「人」は音をも表す。意味は人と人との親密な関係。戦国時代の竹簡は「心」の字形で構成。「身」の音。一説には「心」は人が他人に向ける気配りで、「身」の音は意味をも表し、妊娠中の女性を意味する。だから「仁」とは他人に対する心からの気配りを言うという。
『論語』顔淵篇22、「樊遲問仁,子曰:『愛人。』」『春秋左氏伝』隠公六年、「仁の心を養うこと、隣国との友好関係は、国の宝である。」『説文解字』「仁とは親しむことだ。人と二の字形で構成。忎は、仁の古い字形で、千と心の字形で構成。𡰥は、仁の古い字形で、尸の字形で構成されているかもしれない。」
金文は「人」ではなく「尸」の字形で構成され、『説文解字』にいう古い字形と同じ。古い字形の「尸」は「人」を描いた手法の一つで、あぐらを掻いた人の象形。「尸」は「仁」の音をも表す。『説文解字』にいう古い字形の「忎」は「身」と「心」で構成され、戦国時代の「仁」の字形をくずした文字であり、「千」は「仁」の音を表す。
金文では仁愛を意味した。中山王鼎、「克順克卑,亡(無)不䢦(率)仁」の意味は、”忠義を尽くし、仁徳に背くことがなかった”。
戦国時代の竹簡では仁徳を意味した。『郭店楚簡』唐虞之道の簡2号、「利天下而弗利也,仁之至也。」同じく性自命出の簡55号、「䈞(篤)於仁者也」とあり、ひたすら仁徳をケンジすることを意味している。
判子の文字に使われた場合でも仁徳を意味し、『璽彙』4507に「忠仁」とある。
漢代の帛書では音を通じて「仞」と書かれ、馬王堆帛書『老子甲本』第57行に、「百仁(仞)之高,台(始)於足[下]。」とあり、『老子』第六十四章に「千里之行,始於足下。」とある。
学研漢和大字典
会意兼形声文字で、「人+二」で、二人が対等に相親しむことを示す。相手を人として扱うこと。また、柔らかいこと。人(ジン)・(ニン)と二(ジ)・(ニ)と、どちらを音符と考えてもよい。
語義
- {名詞}ひと。人間。《同義語》⇒人。「井有仁焉=井に仁有り」〔論語・雍也〕
- (ジンナリ){名詞・形容詞}自分と同じ仲間として、すべての人に接する心。隣人愛や同情の気持ち。また、そのような気持ちをもつさま。「仁者愛人=仁なる者は人を愛す」〔孟子・離下〕
- {名詞}「仁ま」の心をそなえた人。仁徳をそなえた人。「仁者」「観過、斯知仁矣=過ちを観れば、斯に仁を知る」〔論語・里仁〕
- {名詞}柔らかい果物のたね。「杏仁(キョウニン)(あんずのたね)」。
- 「不仁(フジン)」とは、手足の動かない病気のこと。
字通
人+二。〔説文〕八上に「親しむなり」とし、「人に従ひ、二に従ふ」と二人相親しむ意とする。金文や、〔説文〕に古文として録する字形は、人が衽(しきもの)を敷いている形で、二人相偶するという形ではない。〔儀礼、士昏礼〕「衽を奥に御(すす)む」の中に「臥席なり」とあり、衽席を用いて安舒であることから、和親・慈愛の意が生まれたのであろう。一般に徳目に関する字は、正は征服、義は犠牲、(道)は道路の修祓、德(徳)は遹省(いつせい)巡察を原義とするので、具体的な行動や事実をいうものであった。のち次第に抽象化して、高度の観念に達する。仁もまた衽席によって和むことから、和親・仁愛の意に展開したものであろう。
訓義
したしむ、なごむ。いつくしむ、めぐむ。あわれむ、おもいやり、なさけぶかい。うるおう、うるおいがある。人としての徳、最高の徳。果実のさね。
大漢和辞典
いつくしむ、親しむ。いつくしみ、したしみ。めぐみそだてる。あはれむ。しのぶ。なさけ、おもひやり。うるほひ。徳教、教化。人、又、人の心。心の本体、性、理、覚。愛の理、心の徳。己を修めること。諸徳の総称。有徳の人。存する。五行で東・春・乾・木に配当する。果実のさね。人に通ず。民に通ず。古は忎・𡰥に作る。姓。
仞(ジン・5画)
初出は前漢の隷書。論語の時代に存在しない。カールグレン上古音はȵi̯ən(去)。同音は下記の通り。同音の「刃」が甲骨文より存在し、「仞に通ず」と『大漢和辞典』に言う。
| 字 | 音 | 訓 | 初出 | 声調 | 備考 |
| 忍 | ジン | しのぶ | 楚系戦国文字 | 平 | →語釈 |
| 刃 | 〃 | は | 甲骨文 | 去 | |
| 認 | 〃 | みとめる | 不明 | 〃 | |
| 肕 | 〃 | かたい肉 | 不明 | 〃 | |
| 仞 | 〃 | ひろ | 前漢隷書 | 〃 | |
| 軔 | 〃 | はどめ | 説文解字 | 〃 | |
| 牣 | 〃 | みちる | 説文解字 | 〃 | |
| 訒 | 〃 | なやむ | 説文解字 | 〃 | →語釈 |
漢語多功能字庫
(字解無し)
学研漢和大字典
会意兼形声。刃は、刀の刃にあたる部分を丶印で示した指事文字。仞は「人+(音符)刃(ジン)」。高さ・深さをはかるとき、からだを横にねじ曲げ、右手を上に左手を下に伸ばすと、半月形のD型となる。その弦(右手先から左手先まで)は、手尺ではかって七尺になる。半月形は刀に似ており、その弦は刀の刃にあたる部分だから、これを仞(ジン)という。
語義
- {単位詞}深さや高さの単位。一仞は、周代の七尺(一尺は二二・五センチメートル)にあたる。
字通
[形声]声符は刃(じん)。〔説文〕八上に「伸ばしたる臂(ひぢ)は一尋、八尺なり」とあり、尋と声義同じ。尋は右と左とを上下に重ねた形で、両手を左右に伸ばした長さを尋という。仞はその形声字とみてよい。ただ仞の長さについては異説もあり、また水深、溝洫(こうきよく)をはかるときの尺度とする説がある。
※尋dzi̯əm(平):仞ȵi̯ən(去)。音も声調も違う。白川のハッタリとデタラメは、時折やりきれなくなる。
任(ジン・6画)


合3521/作任氏簋・西周早期
初出:初出は甲骨文。
字形:「亻」+「工」”官職”。官職を持つ者の意。
音:カールグレン上古音はȵi̯əm(平/去)。「ニン」は呉音。
用例:「甲骨文合集」4889.1に「貞令遘以文取大任亞」とあり、”官職”と解せる。
その他西周の金文では、姓氏名に用いた。
学研漢和大字典
会意兼形声。壬(ジン)は、腹のふくれた糸巻きの軸、または、妊娠して腹のふくれた女性の姿を示す。妊娠の妊の原字。任は「人+(音符)壬(ジン)」で、腹の前に重荷を抱きかかえこむこと。転じて、かかえこんだ責任や仕事の意となる。類義語の負は、背に荷を背おうこと。担は、肩に重い荷をかつぐこと。扛(コウ)は、荷物を棒に通してかつぐこと。荷は、┓型に肩に載せてになうこと。挑は、天秤で二つにわけてになうこと。
語義
- {名詞}抱きかかえこんだ重い荷物。「任重而道遠=任重くして而道遠し」〔論語・泰伯〕
- {名詞}かかえこんだ仕事。「任務」「以為能勝其任也=以て能く其の任に勝ふと為さん」〔孟子・梁下〕
- (ニンズ){動詞}仕事を引き受ける。「任政於斉=政を斉に任ず」〔史記・管仲〕
- (ニンズ){動詞}役目や仕事を与えてまかせる。「一任」「王甚任之=王甚だこれに任ず」〔史記・屈原〕
- {形容詞}上べは柔らかだが腹黒い。「任人」。
- {動詞}まかせる(まかす)。ゆだねて思うとおりにさせる。なるままにまかせる。▽平声に読む。「放任」「曷不委心任去留=曷(なん)ぞ心を委(ゆだ)ねて去留に任せざる」〔陶潜・帰去来辞〕
- {動詞}たえる(たふ)。重みや仕事を引き受けてがまんする。▽平声に読む。「若不任羅綺=羅綺に任へざるがごとし」〔陳鴻・長恨歌伝〕
字通
[形声]声符は壬(じん)。壬は工具。工形のもので、金文の字形は縦の線に中肥のところを加えており、鍛冶(たんや)するときの台の形であろう。〔説文〕八上に「保つなり」とするが、鍛冶に堪える意。また任載の意に用い、〔礼記、王制〕「輕き任は幷(あは)せ、重き任は分つ」は荷物の意、〔詩、大雅、生民〕「是れを任(にな)ひ是れを負ふ」は負担・負任の意。そのことに堪える意より、任務・責任の意となり、人に任せることを委任という。
忍(ジン・7画)

中山王昔壺・戦国末期
初出:初出は戦国末期の金文または戦国期の竹簡。
字形は「刃」+「心」で、「刃」は音符。原義は”耐え忍ぶ”。
音:「ニン」は呉音。カールグレン上古音はȵi̯ən(上)。同音は論語語釈「仞」を参照。
用例:「漢語多功能字庫」によると、戦国時代の金文では原義で用いられた。
論語時代の置換候補:結論として存在しない。
『大漢和辞典』で音ジン/ニン訓しのぶに「訒」があるが、初出は『説文解字』。部品の刃に”しのぶ”の語義はない。また同音に認があるが、後漢の『説文解字』にすら記載が無い。近音の眕(シン・しのぶ)の初出も『説文解字』。
学研漢和大字典
会意兼形声文字で、刃(ニン)・(ジン)は、刀のはのあるほうをヽ印で示した指事文字で、ねばり強くきたえた刀のは。忍は「心+(音符)刃」で、ねばり強くこらえる心。靱(ジン)(ねばり強い)と同系のことば。
語義
- {動詞}しのぶ。つらいことをねばり強く持ちこたえる。《類義語》耐。「忍耐」「堅忍不抜」「忍而就於此=忍んで此れに就く」〔史記・淮陰侯〕
- {動詞}しのぶ。むごいことにも平気でたえる。「残忍」「有不忍人之心=人に忍びざるの心有り」〔孟子・公上〕
- 《日本語での特別な意味》
①しのぶ。しのび。人に目だたないようにする。人に目だたないように物事をすること。「人目を忍ぶ」。
②しのび。忍術。また、忍術を心得た者。「忍者(ニンジャ)・(シノビノモノ)」。
字通
[形声]声符は刃(じん)。〔説文〕十下に「能くするなり」とあり、忍耐の意。耐・能は古くは同声であった。刃声の字にもその義があるらしく、靱(じん)はもと柔皮をいい、強靱の意がある。
衽(ジン・9画)

睡虎地簡48.61 ・戦国秦
初出:戦国文字。
字形:〔衣〕+音符〔壬〕。
音:カールグレン上古音はȵi̯əm(去)。同音は「壬」とそれを部品とする漢字群多数。
用例:戦国最末期「睡虎地秦簡」封診58に「襦北(背)及中衽」とあり、”えり”と解せる。
論語時代の置換候補:「壬」に”えり”の語釈は『大漢和辞典』に無い。日本語音で同音同訓は『大漢和辞典』に存在しない。
学研漢和大字典
会意兼形声。「衣+(音符)壬(ジン)(中に入れこむ)」で、内側に入れこむ衣の部分。妊(赤ん坊を腹の中に入れこむ)と同系。
語義
- {名詞}えり。内側に入れこむえり。のち、広く、衣服のえり。「左衽(サジン)(左のえりを内に入れる)」。
- {名詞}おくみ。衣服をわきで縫いあわせるときに、そのぬいあわせ目にある布。また、和服の場合、前幅を広くつくるために、身頃(ミゴロ)に縫いつける細長い布。
- {名詞}衣服のすそ。もすそ。「斂衽=衽を斂む」。
- {名詞}柔らかいねどこ。しとね。「衽席(ジンセキ)」。
- {名詞}くぎのかわりに用いて板と板とをつなぐもの。ちぎり。▽棺をつくるときに使う。
字通
[形声]声符は壬(じん)。壬にふくらむ意がある。〔説文〕八上に「衣の䘳(えり)なり」とあり、衿は襟、衽はおくみをいう。左衽は東夷の俗。中国では死者の礼。〔儀礼、士喪礼〕「衽を奧に御(すす)む」、〔中庸、十〕「金革を衽(しとね)とす」のように、衽席の意にも用いる。仁の古い字形は、人の後ろに衽席をおく形で、安舒を原義とする字である。〔荘子、達生〕に「人の最も畏るる所は、衽席の上、飮食の閒なり」とみえる。
荏(ジン・9画)
初出は前漢の隷書。論語の時代に存在しない。カールグレン上古音はȵi̯əm(上)。同音に壬とそれを部品とする漢字群多数。
部品で同音の「壬」に平・去二つの音がありいずれも”へつらう”を意味すると『大漢和辞典』にあるが、出典は後漢の説文解字以降の文献。同音同調の「恁」に”よわい”の語釈を『大漢和辞典』が立て、「荏に通ず」といい、春秋末期の金文から存在する。

「恁」王孫遺者鐘・春秋末期
結論として「恁」が論語時代の置換候補になるわけだが、これも儒者による幼稚な自己顕示欲の表れで、調べるのがバカらしくなってくる。
学研漢和大字典
会意兼形声。壬(ニン)は、やわらかく包みこむ意を含む。荏は「艸+人+(音符)壬」で、種をやわらかく包みこんだ植物。妊(赤ん坊を腹の中に包みこむ)と同系。
語義
- {名詞}え。草の名。しその一種。種子から油をとる。えごま。
- (ジンナリ){形容詞}やわらかである。力がぬけてだらしない。じわじわとしている。「荏染(ジンゼン)」「色莞而内荏=色腰(はげ)しくして内荏なり」〔論語・陽貨〕
- 「荏菽(ジンシュク)」とは、大豆、またはえんどうのこと。
字通
[形声]声符は任(じん)。〔説文〕一下に「桂荏、蘇(そ)なり」、〔方言、三〕に「蘇も亦た荏なり。關の東西、或いは之れを蘇と謂ひ、或いは之れを荏と謂ふ」とあって、え・えごまをいう。荏菽はそらまめ。また栠と通じ、柔らかなさまをいう。
訒(ジン・10画)

隷書
初出:初出は後漢の説文解字。
字形:「言」+「刃」。「刃」は古くは”いばら”を意味し、いばらに遮られて言葉が出にくいこと。
音:カールグレン上古音はȵi̯ən(去)。同音は論語語釈「仞」を参照。
用例:文献上の初出は論語顔淵篇3。その他先秦両漢では『荀子』に一件、『説文解字』に一件見える。ここから見るに、戦国末期では”事実でない言葉”の意で、字形から”いばらで隠すように誤魔化す言葉”だったと見える。
故名足以指實,辭足以見極,則舍之矣。外是者,謂之訒,是君子之所棄,而愚者拾以為己寶。
だから名前がその指すものの本質を言い表しているなら、言葉は対象のすみずみまで明らかにしているのだから、言葉そのものは捨ててしまってもよい。そうなっていない状況を訒といい、君子はまともに取り合わない。しかし愚か者は有り難がってもてはやす。(『荀子』正名13)
訒:頓也。从言刃聲。《論語》曰:「其言也訒。」
訒とは止まって動かないことだ。字形は言に従い音は刃。論語にいわく、「その言や訒。」(『説文解字』言部)
論語時代の置換候補:同音のうち認は「訒に通ず」と大漢和辞典は言うが、初出は不明。忍は「こらえる」の語釈があるが、初出は戦国末期の金文。
学研漢和大字典
会意兼形声。「言+(音符)刃(ジン)(ねばる)」。
語義
- (ジンナリ){形容詞}口がねばるさま。口のきき方が重々しく、いいよどみがちなさま。「仁者其言也訒=仁者は其の言也訒なり」〔論語・顔淵〕
字通
認(訒)
[形声]声符は忍(にん)。字はもと訒に作り、刃(じん)声。〔説文〕三上に「訒は頓(なや)むなり」、〔広雅、釈詁三〕に「訒は難(なや)むなり」、〔玉篇〕に「訒は鈍きなり」とあり、これらの古字書に認の字はみえない。王念孫の〔広雅疏証〕に「荀子正名篇に、是れに外(はづ)るる者、之れを認と謂ふ。楊倞注に云ふ、認は難なりと。竝びに字異なるも義は同じ」という。おそらくもと同じく、のち分化した字であろう。認識とは、旧所有者が遺失の物を発見し、その所有権を主張し立証することをいう。〔三国志、呉、鍾離牧伝〕に、牧が自ら墾田して荒田二十余畝を開き、稲の熟したころ「縣民に之れを識認するもの有り」、牧はそのまま県人にこれを与えたという話がみえる。このころから、認にそのような用義を生じたのであろう。
飪(ジン・13画)

説文解字・後漢
初出:初出は楚系戦国文字。ただし字形が確認できない。「小学堂」による初出は後漢の説文解字。
字形:「食」+音符「壬」”ふくれる”。
音:カールグレン上古音はȵi̯əm(上)。同音に壬とそれを部品とする漢字群など多数。
用例:戦国時代「上海博物館蔵戦国楚竹簡」中弓附簡に1例用例があるが、欠損により語義不明。
文献時代の初出は論語郷党篇8。再出は前漢中期の『塩鉄論』。
論語時代の置換候補:『大漢和辞典』の同音同訓に「𤇲」「燖」「腍」(共に初出不明)。部品の壬(初出は甲骨文)に”煮る”の語釈は無い。
学研漢和大字典
会意兼形声。「食+(音符)壬(ニン)・(ジン)(中に入れこむ、ふんわりとする、柔らかい)」。
語義
- {動詞・名詞}にる。しんがとおって柔らかくなるまで、食物をにる。また、にかた。にえかた。「失飪不食=飪を失へるは食らはず」〔論語・郷党〕
字通
[形声]声符は壬(じん)。壬にふくらむ意がある。〔説文〕五下に「大いに孰(に)るなり」、〔方言、七〕に「熟(に)るなり。徐・揚の閒には飪と曰ふ」とみえる。〔論語、郷党〕に「失飪のものは食らはず」とあり、よく火がとおって、ふくよかになることをいう。
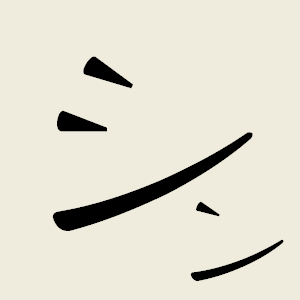


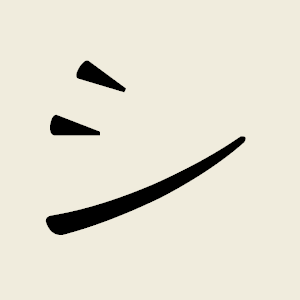

コメント