論語:原文・書き下し
原文(唐開成石経)
司馬牛問君子子曰君子不憂不懼曰不憂不懼斯謂之君子巳乎子曰內省不疚夫何憂何懼
校訂
諸本
- 経典釈文:馬犂力兮反史記作初並云字牛
※wikisource『國譯漢文大成』が「斯謂之君子矣夫」と記すのは誤植。
東洋文庫蔵清家本
司馬牛問君子子曰君子不憂不懼/曰不憂不懼斯謂之君子已乎子曰內省不疚夫何憂何懼
後漢熹平石経
(なし)
定州竹簡論語
(なし)
※論語の本章の定州竹簡論語は、学而篇と並んでこの顔淵篇の損傷が激しい。10簡しか残っていない。墓泥棒による最初の損傷の際に、顔淵篇がたまたまよく焼けてしまったのだろうか。学而篇は冒頭だから、よく焼けたのも解り易いのだが。
標点文
司馬牛問「君子」。子曰、「君子不憂不懼。」曰、「不憂不懼斯、可謂『君子』已乎。」子曰、「內省不疚、夫何憂何懼。」
復元白文(論語時代での表記)












 懼
懼 


 懼
懼 










 疚
疚 


 懼
懼
※論語の本章は「懼」「疚」の字が論語の時代に存在しない。「問」「夫」「乎」「何」の用法に疑問がある。本章は戦国時代以降の儒者による創作である。
書き下し
司馬牛君子を問ふ。子曰く、君子は憂へ不懼れ不。曰く、憂へ不懼れ不る斯、君子と謂ふ可き已乎。子曰く、內に省みて疚しから不んば、夫れ何をか憂へ、何をか懼れむ。
論語:現代日本語訳
逐語訳


司馬牛が君子を問うた。先生が言った。「君子は憂えず恐れない。」司馬牛が言った。「憂えず恐れない境地は、君子と言えるだけですか。」先生が言った。「自分を見直してやましいことがなければ、そもそも何を憂い、何を恐れようか。」
意訳
司馬牛「君子とは何ですか。」
孔子「君子は心配しない、恐れない。」
司馬牛「何事にも心配しない、恐れない程の人が、たかが君子と言われておしまいですか。」
孔子「やましいことがなければ、心配や恐れなど無い。」
従来訳
司馬牛が君子についてたずねた。先師はこたえられた。――
「君子はくよくよしない。またびくびくしない。」
司馬牛が更にたずねた。――
「くよくよしない、びくびくしない、というだけで君子といえるでしょうか。」
すると先師はいわれた。――
「それは誰にも出来ることではない。自分を省みてやましくない人だけにしか出来ないことなのだ。」下村湖人『現代訳論語』
現代中国での解釈例
司馬牛問君子。孔子說:「君子不憂不懼。」問:「不憂不懼,就能叫做君子嗎?」孔子說:「問心無愧,何來憂懼?」
司馬牛が君子を問うた。孔子が言った。「君子は憂えない、恐れない。」問うた。「憂えず恐れず、それだけで君子と言ってよいのですか?」孔子が言った。「自分に問うて後ろめたい所が無ければ、なぜ憂えたり恐れたりするのか?」
論語:語釈
司馬牛(シバギュウ)
孔子の弟子。あざ名は耕。孔子塾生には珍しく貴族の出身で、姓の通り宋国の将軍職を務める家柄だった。兄は宋国元帥で、孔子を襲撃したことになっている桓魋(論語述而篇22)。『春秋左氏伝』によると、宋国の政変で桓魋が失脚すると、司馬牛も地位や領地を捨て、それも桓魋を避けるように放浪し、なぜか魯国に来て孔子に見せつけるように自ら命を絶った。詳細は論語の人物・司馬耕子牛を参照。なお漢文では「司馬」で”将軍”を意味し、その職を世襲する者が氏族名にもした。
隋代に成った『経典釈文』は「馬犂力兮反史記作初並云字牛」と記し、論語の本章の「司馬牛」は当時「司馬犂」となっており、当時の『史記』では「司初並」と記し「あざ名は牛である」と説明するという。だいたい『経典釈文』の成った頃に日本に論語が伝わったのだが、その後の日本伝承の古注系論語は「司馬牛」と記し、「司馬犂」とは記さない。現伝の『史記』も仲尼弟子伝で「司馬耕字子牛」と記すのみで「司初並」とは書かない。なお現伝の『春秋左氏伝』は「司馬牛」と記す。
従ってこの文字列の違いは『経典釈文』独自の見解で、他にそれを支持する資料もないことから、『経典釈文』に従った校訂はしなかった。
『経典釈文』を編んだ陸徳明は南朝陳の出身だから、南朝伝来の『論語』『史記』ではそうなっていたのかもしれない。すると日本伝承の古注系『論語』は、北朝より伝来した可能性を、この一節は、示唆している。なお中国では盛唐時代に開元石経が彫られ現存し、古注系とは異なる文字列の論語が確定して現在に至っている。
原始論語?…→定州竹簡論語→白虎通義→ ┌(中国)─唐石経─論語注疏─論語集注─(古注滅ぶ)→ →漢石経─古注─経典釈文─┤ ↓↓↓↓↓↓↓さまざまな影響↓↓↓↓↓↓↓ ・慶大本 └(日本)─清家本─正平本─文明本─足利本─根本本→ →(中国)─(古注逆輸入)─論語正義─────→(現在) →(日本)─────────────懐徳堂本→(現在)
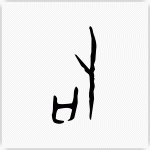

(甲骨文)
「司」の初出は甲骨文。字形は「𠙵」”口に出す天への願い事”+”幣のような神ののりしろ”。原義は”祭祀”。春秋末期までに、”祭祀”・”王夫人”・”君主”・”継ぐ”・”役人”の意に用いた。詳細は論語語釈「司」を参照。


(甲骨文)
「馬」の初出は甲骨文。「メ」は呉音。「マ」は唐音。字形はうまを描いた象形で、原義は動物の”うま”。甲骨文では原義のほか、諸侯国の名に、また「多馬」は厩役人を意味した。金文では原義のほか、「馬乘」で四頭立ての戦車を意味し、「司馬」の語も見られるが、”厩役人”なのか”将軍”なのか明確でない。戦国の竹簡での「司馬」は、”将軍”と解してよい。詳細は論語語釈「馬」を参照。


「牛」甲骨文/牛鼎・西周早期
「牛」の初出は甲骨文。字形は牛の象形。原義は”うし”。西周初期まで象形的な金文と、簡略化した金文が併存していた。甲骨文では原義に、金文でも原義に、また人名に用いた。詳細は論語語釈「牛」を参照。
問(ブン)


(甲骨文)
論語の本章では”質問する”。この語義は春秋時代では確認できない。初出は甲骨文。「モン」は呉音。字形は「門」+「口」。甲骨文での語義は不明。西周から春秋に用例が無く、一旦滅んだ漢語である可能性がある。戦国の金文では人名に用いられ、”問う”の語義は戦国最末期の竹簡から。それ以前の戦国時代、「昏」または「𦖞」で”問う”を記した。詳細は論語語釈「問」を参照。
君子(クンシ)


論語の本章では”教養のある地位ある者”。孔子生前までは単に”貴族”を意味し、そこには普段は商工民として働き、戦時に従軍する都市住民も含まれた。”情け深く教養がある身分の高い者”のような意味が出来たのは、孔子没後一世紀に生まれた孟子の所説から。詳細は論語語釈「君子」を参照。
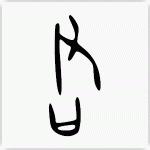

(甲骨文)
「君」の初出は甲骨文。甲骨文の字形は「丨」”通路”+「又」”手”+「口」で、人間の言うことを天界と取り持つ聖職者。春秋末期までに、官職名・称号・人名に用い、また”君臨する”の語義を獲得した。詳細は論語語釈「君」を参照。


(甲骨文)
「子」の初出は甲骨文。論語ではほとんどの章で孔子を指す。まれに、孔子と同格の貴族を指す場合もある。また当時の貴族や知識人への敬称でもあり、孔子の弟子に「子○」との例が多数ある。なお逆順の「○子」という敬称は、上級貴族や孔子のような学派の開祖級に付けられる敬称。「南子」もその一例だが、”女子”を意味する言葉ではない。字形は赤ん坊の象形で、もとは殷王室の王子を意味した。詳細は論語語釈「子」を参照。
子曰(シエツ)(し、いわく)

論語の本章では”孔子先生が言った”。「子」は貴族や知識人に対する敬称で、論語では多くの場合孔子を指す。この二文字を、「し、のたまわく」と読み下す例がある。「言う」→「のたまう」の敬語化だが、漢語の「曰」に敬語の要素は無い。古来、論語業者が世間からお金をむしるためのハッタリで、現在の論語読者が従うべき理由はないだろう。


(甲骨文)
「曰」の初出は甲骨文。原義は「𠙵」=「口」から声が出て来るさま。詳細は論語語釈「曰」を参照。
不(フウ)


(甲骨文)
漢文で最も多用される否定辞。初出は甲骨文。「フ」は呉音、「ブ」は慣用音。原義は花のがく。否定辞に用いるのは音を借りた派生義だが、甲骨文から否定辞”…ない”の意に用いた。詳細は論語語釈「不」を参照。
憂(ユウ)
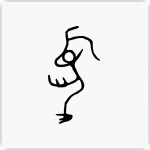

(金文)
論語の本章では”うれう”。頭が重く心にのしかかること。初出は西周早期の金文。字形は目を見開いた人がじっと手を見るさまで、原義は”うれい”。『大漢和辞典』に”しとやかに行はれる”の語釈があり、その語義は同音の「優」が引き継いだ。詳細は論語語釈「憂」を参照。
懼(ク)


(金文)
論語の本章では『大漢和辞典』の第一義と同じく”おそれる”。「グ」は呉音。初出は戦国末期の金文。論語の時代に存在しない。論語時代の置換候補もない。字形は「忄」+「瞿」で、「瞿」は「目」二つ+「隹」。鳥が大きく目を見開くさま。「懼」全体でおそれおののくさま。原義は”恐れる”。戦国の金文でも竹簡でも原義に用いた。詳細は論語語釈「懼」を参照。
斯(シ)


(金文)
論語の本章では”そのような状態”。初出は西周末期の金文。字形は「其」”籠に盛った供え物を祭壇に載せたさま”+「斤」”おの”で、文化的に厳かにしつらえられた神聖空間のさま。意味内容の無い語調を整える助字ではなく、ある状態や程度にある場面を指す。例えば論語子罕篇5にいう「斯文」とは、ちまちました個別の文化的成果物ではなく、風俗習慣を含めた中華文明全体を言う。詳細は論語語釈「斯」を参照。
可(カ)


(甲骨文)
論語の本章では”~できる”。初出は甲骨文。字形は「口」+「屈曲したかぎ型」で、原義は”やっとものを言う”こと。甲骨文から”~できる”を表した。日本語の「よろし」にあたるが、可能”~できる”・勧誘”…のがよい”・当然”…すべきだ”・認定”…に値する”の語義もある。詳細は論語語釈「可」を参照。
謂(イ)


(金文)
論語の本章では”…であると評価する”。本来、ただ”いう”のではなく、”~だと評価する”・”~だと認定する”。現行書体の初出は春秋後期の石鼓文。部品で同義の「胃」の初出は春秋早期の金文。金文では氏族名に、また音を借りて”言う”を意味した。戦国の竹簡になると、あきらかに”~は~であると言う”の用例が見られる。詳細は論語語釈「謂」を参照。
已乎(イコ)
訓読みはどちらも「のみか」。”…だけですか”の意。唐石経は「巳乎」と記し、清家本は「已乎」と記す。唐代の頃、「巳」「已」「己」字は相互に通用した。事実上の異体字と言ってよい。


(甲骨文)
「巳」(シ)の初出は甲骨文。字形はヘビの象形。「ミ」は呉音(遣隋使より前に日本に伝わった音)。甲骨文から十二支の”み”を意味し、西周・春秋の金文では「已」と混用されて、完了の意、句末の詠嘆の意、”おわる”の意に用いた。詳細は論語語釈「巳」を参照。


(甲骨文)
「已」の初出は甲骨文。字形と原義は不詳。字形はおそらく農具のスキで、原義は同音の「以」と同じく”手に取る”だったかもしれない。論語の時代までに”終わる”の語義が確認出来、ここから、”~てしまう”など断定・完了の意を容易に導ける。詳細は論語語釈「已」を参照。


(甲骨文)
「乎」の初出は甲骨文。論語の本章では形容詞・副詞についてそのさまを意味する接尾辞。この用例は春秋時代では確認できない。字形は持ち手の柄を取り付けた呼び鐘を、上向きに持って振り鳴らし、家臣を呼ぶさまで、原義は”呼ぶ”こと。甲骨文では”命じる”・”呼ぶ”を意味し、金文も同様で、「呼」の原字となった。句末の助辞として用いられたのは、戦国時代以降になるという。詳細は論語語釈「乎」を参照。
不憂不懼斯可謂君子已乎
日中の通説では、句読を「不憂不懼、斯可謂『君子』已乎」と切り、日本の訓読では「斯」を「それ」と読むが、「斯」は”そういう環境・状態・場面”を意味する語で、単なる指示詞や代名詞ではない。従って「不憂不懼斯、可謂『君子』已乎」と句読を切るべきで、「不憂不懼」”憂えない、おそれない”は「斯」”そういう境地”を修飾し、合わさって主部を構成する。その主部が「君子」と「可謂」”評価できる”「已乎」”だけか”、の意。
內(ダイ)


(甲骨文)
論語の本章では”内側”。新字体は「内」。ただし唐石経・清家本とも「内」と新字体で記す。漢音(遣隋使・遣唐使が聞き帰った音)「ダイ」で”うちがわ”、「ドウ」で”入れる”を意味する。「ナイ/ノウ」は呉音。初出は甲骨文。字形は「冂」”広間”+「人」で、広間に人がいるさま。原義は”なか”。春秋までの金文では”内側”、”上納する”、国名「芮」を、戦国の金文では”入る”を意味した。詳細は論語語釈「内」を参照。
省(セイ)


(甲骨文)
論語の本章では、”振り返って詳しく検討する”。初出は甲骨文。「ショウ」は呉音。原義は「屮」”ささげる”+「目」で、まじめな気持でじっと見つめること。詳細は論語語釈「省」を参照。
疚*(キュウ)


(隷書)
論語の本章では”やましい”。初出は不明。論語の時代に存在しない。論語時代の置換候補もない。論語では本章のみに登場。字形は「疒」+音符「久」。同音に「久」「九」「玖」”黒い玉”「灸」。文献上の初出は論語の本章で、戦国初期『墨子』では”空腹で病む”の意に、戦国最末期『韓非子』では”病む”の意に用いた。戦国最末期『呂氏春秋』に「孔子曰」として「故內省而不疚於道,臨難而不失其德。」とあり、論語の本章が戦国末期には成立していたことを示唆する。詳細は論語語釈「疚」を参照
何(カ)


(甲骨文)
論語の本章では”どうして”。この語義は春秋時代では確認できない。初出は甲骨文。字形は「人」+”天秤棒と荷物”または”農具のスキ”で、原義は”になう”。甲骨文から人名に用いられたが、”なに”のような疑問辞での用法は、戦国時代の竹簡まで時代が下る。詳細は論語語釈「何」を参照。
夫(フ)


論語の本章では”それは”の意。この語義は春秋時代では確認できない。「夫」の初出は甲骨文。論語では「夫子」として多出。「夫」に指示詞の用例が春秋時代以前に無いことから、”あの人”ではなく”父の如き人”の意で、多くは孔子を意味する。「フウ」は慣用音。字形はかんざしを挿した成人男性の姿で、原義は”成人男性”。「大夫」は領主を意味し、「夫人」は君主の夫人を意味する。固有名詞を除き”成人男性”以外の語義を獲得したのは西周末期の金文からで、「敷」”あまねく”・”連ねる”と読める文字列がある。以上以外の語義は、春秋時代以前には確認できない。詳細は論語語釈「夫」を参照。
論語:付記
検証
論語の本章は文字史から見て春秋時代に遡れず、生まれながらの上級貴族である司馬牛が「君子=貴族とは何か」を問うのも場面として考えづらい。内容としてはまず、上掲語釈に記した通り、戦国最末期の『呂氏春秋』に類似の語句が「孔子曰」としてある。
孔子窮於陳、蔡之間,七日不嘗食,藜羹不糝。宰予備矣,孔子弦歌於室,顏回擇菜於外。子路與子貢相與而言曰:「夫子逐於魯,削跡於衛,伐樹於宋,窮於陳、蔡,殺夫子者無罪,藉夫子者不禁,夫子弦歌鼓舞,未嘗絕音,蓋君子之無所醜也若此乎?」顏回無以對,入以告孔子。孔子憱然推琴,喟然而歎曰:「由與賜,小人也。召,吾語之。」子路與子貢入。子貢曰:「如此者可謂窮矣。」孔子曰:「是何言也?君子達於道之謂達,窮於道之謂窮。今丘也拘仁義之道,以遭亂世之患,其所也,何窮之謂?故內省而不疚於道,臨難而不失其德。大寒既至,霜雪既降,吾是以知松柏之茂也。昔桓公得之莒,文公得之曹,越王得之會稽。陳、蔡之阨,於丘其幸乎!」孔子烈然返瑟而弦,子路抗然執干而舞。子貢曰:「吾不知天之高也,不知地之下也。」古之得道者,窮亦樂,達亦樂。所樂非窮達也,道得於此,則窮達一也,為寒暑風雨之序矣。故許由虞乎潁陽,而共伯得乎共首。
孔子が陳・蔡のあたりで兵糧攻めに遭い、七日間絶食し、穀物のスープすら作れなかった。弟子の宰予は空腹に耐えかねたが、孔子は座敷でチンチャカ琴を弾いて歌っていた。顔回は何か食べられる野草はないかと外に出た。連れだった子路と子貢は互いに言い合った。
「先生は魯を追われ、衛では就職に失敗し、宋では休んでいた大木を引き抜かれ、とうとうこの陳と蔡で行き詰まってしまった。両大名家のお触れでは、先生を殺しても罪に問わず、こき下ろすのも禁止せずというのに、先生は琴を弾いては歌い、止めようとしない。君子としてこれほど恥ずかしい目に遭っているのにどうしたことだろう?」
顔回は何も言わずにこの話を孔子に伝えた。孔子は憐れみを含んだ目をしながら琴を置き、ため息をついて言った。「子路も子貢も修行が足らんな。ちょっと説教するから呼んで来なさい。」二人がやって来て、子貢が言った。「こうなってはもうおしまいと言うべきです。」孔子が答えた。
「馬鹿なことを言うものではない。君子だろうと思い通りに事が運べばうまく行っていると言われ、行き詰まったら行き詰まったと言われるだけに過ぎない。今わしは仁義を貫いているせいで、こうやって世の乱れのとばっちりを受けているのだが、それでも行き詰まってはおらん。自分自身にやましいところが無ければ、どんな困難に出くわしても、自分の道徳が何ら損なわれたわけではないからだ。
ここの所ずいぶん寒くなってきたし、霜や雪も降っているが、それでもマツやヒノキは茂っておるではないか(論語子罕篇29・偽作)。斉の桓公は莒で、晋の文公は曹で、越王勾践は会稽で、もうダメだと思うような目に遭っているが、のちには天下の覇者になった。ワシが今このように陳蔡の連中からひどい目に遭うのも、これ幸いというものじゃ。」
言い終わると孔子は厳かに琴を弾き始め、子路は立ち上がって盾を手に取って舞った。子貢が言った。「やれやれ、視野の狭いことを言ってしまった。私はまだ天の高さを知らない。地の深さを知らない」(論語子張篇25)。
このように昔の道を心得た者は、行き詰まっても平気でおり、順境と同様に楽しんだ。楽しみは境遇によるのではない。孔子のように道を心得たなら、順境も逆境も同じなのである。季節の寒暖が移り変わるのと同じだと思っている。だから許由は堯から帝位を譲ると言われたら、耳が汚れたと言って潁水で洗って南岸に行ってしまった。共伯は周王の代わりに政務を摂ったが、我ながら上手く政治を回せたと喜んだ。(『呂氏春秋』慎人4)
もう一つの材料は、論語子罕篇30の「智者は惑わず、仁者は憂えず、勇者は懼れず」だろう。こちらも「惑」の字の不在から、戦国最末期より前に遡ることは出来ない。論語の本章はこれと上掲『呂氏春秋』の元ネタとのニコイチで、古注に前漢儒総体の擬人化である孔安国と、前後の漢帝国の交代期を生きた包咸が注を付けていることから、前漢前半までには創作されていたとみるのが筋にかなう。
解説
まず論語の本章は、問答になっていない。「君子とは何か」と問われ「不憂不懼」と答えた孔子に、司馬牛が「不憂不懼の境地なら大人物でしょう。たかが君子ではないでしょうに」と問い詰めると、「やましいことがなければ人は不憂不懼になる」と孔子は答えた。明らかにごまかしている。
仮に論語の本章が、話そのものは史実とするなら、名門の生まれで行動にもやましいところの無かった司馬牛が、「君子君子と先生はおっしゃるが、私にこれ以上何を修業せいと言うのですか」と詰め寄られ、「お前さんがやましくなければもうご立派だ」と機嫌を取るような事を言ったわけだ。
論語では本章にしか見られない「疚」”やましい”字だが、初出がいつやらわからない上に、語義は『墨子』が”饑饉に伴う飢餓”にこの字を当てたように、「疒」”病気”のうち「久」”長引く”もの、のはずだった。それが戦国最末期になって急に、”(自分が)やましい”の意に用いられた。
論語にいくつも偽作をねじ込んだ董仲舒も、「君子不恥,內省不疚,何憂於誌,是已矣。」”君子は恥ずかしい事をせず、自分に対してやましくなければ、何を書き立てられようと恥ずかしくはない。ただこれに尽きる”と言い張っている(『春秋繁露』楚荘王2)。
おそらく「疚」ki̯ŭɡ(去)を”やましい”の意に用い始めたのは、「糾」ki̯ŏɡ(上)の空耳アワーに過ぎないだろう。「糾」なら前漢の隷書から確認出来る。『小載礼記』にも「故君子內省不疚」の句があるが、文字史から大小の礼記を戦国時代以前の作と見なす立場に訳者は賛成しない。
論語の本章の場面設定の怪しさも前章と同じで、弟子の仲では唯一といってよい上級貴族出身の司馬牛が、君子=貴族とは何かを問うのがそもそも考えづらい。次章は同じく司馬牛が、「誰にも兄弟はいるのに自分には(孔子を殺そうとした桓魋という悪党の兄しか)いない」と歎く話になっている。
次章もまた文字史から後世の偽作が確定するのだが、3話を全て史実の対話とすると、司馬牛は悪党の兄を持った故に孔子にはぐらかされ、孤独を歎いた挙げ句に、『春秋左氏伝』の言う通りなら魯の都城の正門前で自ら命を絶つという、何やら孔子に怨みを持っていたかのように読める。
論語述而篇22が文字史上から史実と見なして良いように、桓魋が孔子を襲撃したのは史実だったのだろう。そして無考えの儒者や漢文の読めない漢学教授が、ナントカの一つ覚えのように言う桓魋悪人説とは違って、『春秋左氏伝』の言う通りなら、当時の貴族としても良識派だった。
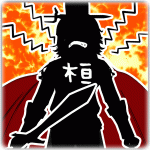

その良識も身分もある桓魋から襲撃されたのだから、孔子はよほど悪いことをしていたのだと見なさねばならない。あるいは上級貴族の司馬牛を、政治的に利用するようなことをし、死に追いやった可能性はある。それなら桓魋が、弟の復讐に現れて当然で、一連の話がよく分かるのだが。
論語の本章、新古の注は次の通り。
古注『論語集解義疏』
司馬牛問君子子曰君子不憂不懼註孔安國曰牛兄桓魋將為亂牛自宋來學常憂懼故孔子解之曰不憂不懼斯謂之君子矣乎子曰內省不疚夫何憂何懼註苞氏曰疚病也內省無罪惡無所可憂懼也
本文「司馬牛問君子子曰君子不憂不懼」。
注釈。孔安国「牛の兄は桓魋で今にも騒動を起こそうとしていた。牛は宋から来て学んだが、いつも兄の企てを恐れていた。だから孔子はその恐れを取り除いてやったのである。」
本文「曰不憂不懼斯謂之君子矣乎子曰內省不疚夫何憂何懼」。
注釈。包咸「疚とは気に病むことである。自分を反省して罪悪が無いのなら、心配し恐れることなどないのである。」
高祖劉邦の名を避諱しないことなどから、孔安国は実在の個人ではなく、前漢儒の総体を擬人化したものと見なすべきだが、儒者の「無考え」とはこういうことをいう。孔子を絶対の聖人に仕立てるため、うそデタラメをいくらでも書く。『春秋左氏伝』が当時も現伝の通りだったとするなら、孔安国はまじめに読んでいなかったとしか言えない。
桓魋は宋の景公からの寵愛が過ぎて失脚したのだが、放逐を言い出したのは情緒不安定な景公の方で、実に身勝手な理由から地位を失ったことになる。桓魋は配下の軍勢で反抗するのも可能だったが、国人の反対を恐れて戦わず亡命した。「今にも騒動を起こそう」としたわけではない。
新注『論語集注』
司馬牛問君子。子曰:「君子不憂不懼。」向魋作亂,牛常憂懼。故夫子告之以此曰:「不憂不懼,斯謂之君子已乎?」子曰:「內省不疚,夫何憂何懼?」夫,音扶。牛之再問,猶前章之意,故復告之以此。疚,病也。言由其平日所為無愧於心,故能內省不疚,而自無憂懼,未可遽以為易而忽之也。晁氏曰:「不憂不懼,由乎德全而無疵。故無入而不自得,非實有憂懼而強排遣之也。」
本文「司馬牛問君子。子曰:君子不憂不懼。」
向魋(=桓魋)が乱を起こそうとしているのを、牛はいつも心配し恐れていた。だから先生はこのように言って諭した。
本文「曰:不憂不懼,斯謂之君子已乎?子曰:內省不疚,夫何憂何懼?」
夫の音は扶である。牛の再問は、やはり前章と同じで納得できなかったので、このように問いを繰り返した。疚とは気に病むことである。言葉の意味するところはこうである。普段から自分の心に恥じるようなことが無ければ、反省してもやましいことが無い。そして自然と憂いも恐れもなくなる。まだそういう境地に達していなければ、心が揺れ動くのも当然である。
晁説之「心配せず恐れず、これは道徳が完成し欠点の無いことで達成される。だから道徳がそこまでに至っていないと自分でこの境地を体感できない。憂いや恐れは実在するのではない。道徳が完成すれば、強制的に追い払うことが出来るのだ。」
こういう高慢ちきを言った晁説之は、『宋史』に伝が立つ晁補之の弟のようだが、当人には伝が無く、何をした人物か分からない。だがこういう空理空論は、本当に飢えや戦乱や天災に巻き込まれたことのない者の言い分で、経験がないのは当人のせいではなくとも、そういう景色は身の回りにゴロゴロ転がっていたはずで、想像力も無ければ「かわいそうに」と同情する心も無い化け物にしか言えないことだ。
年代から見て北宋の崩壊した靖康の変には遭遇しただろうが、新注に名の見える少なからぬ儒者は口先で強硬論を説き、戦乱が迫ると山奥に逃げ、南宋がやっと成立するとノコノコ現れて官職を要求する連中がほとんどだった。新注をはじめ宋儒の言い分などまじめに取り合うに値しない。詳細は論語雍也篇3余話「宋儒のオカルトと高慢ちき」を参照。
余話
(思案中)


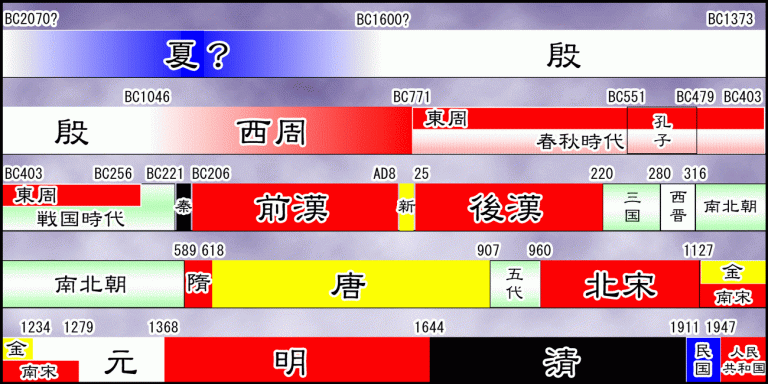


コメント