論語:原文・書き下し
原文(唐開成石経)
司馬牛問仁子曰仁者其言也訒曰其言也訒斯謂之仁巳乎子曰爲之難言之得無訒乎
校訂
諸本
- 『経典釈文』:也訒音刃孔云難也鄭云不忍言也字或作仞
- 正平本・足利本・根本本:其言也訒斯可謂之仁已矣乎
- 文明本:其言也訒斯可謂之仁已乎
- 宮内庁蔵『論語注疏』:唐石経と同。
- 早大蔵『四書集注』・早大蔵新注:其言也訒斯謂之仁矣乎
※Wikisource『國譯漢文大成』が「其言也訒斯謂之仁已夫」と記すのは誤植。
東洋文庫蔵清家本
司馬牛問仁子曰仁者其言也訒也/曰其言也訒斯謂之仁已矣乎子曰爲之難言之得無訒乎
定州竹簡論語
……牛問仁。子曰:「仁[者]313……
標点文
司馬牛問「仁」。子曰、「仁者、其言也訒也。」曰、「其言也訒斯、謂之『仁』已矣乎。」子曰、「爲之難、言之得無訒乎。」
復元白文(論語時代での表記)











 訒
訒



 訒
訒 














 訒
訒
※仁→(甲骨文)。論語の本章は訒の字が論語の時代に存在しない。「問」「也」「乎」の用法に疑問がある。本章は前漢帝国の儒者による創作である。
書き下し
司馬牛仁を問ふ。子曰く、仁者其の言也訒き也。曰く、其の言也訒き斯、之を仁と謂ふ已矣る乎。子曰く、之を爲すは難し、之を言ふに訒かる無きを得む乎。
論語:現代日本語訳
逐語訳


司馬牛が仁を問うた。先生が言った。「仁はその(説明の)言葉は言いにくいのだ。」司馬牛が言った。「言いにくい、そうしたことだけで、それが仁であると言ってしまっていいものでしょうか。」先生が言った。「仁を実行するのは難しい。仁を言うのに言いにくいわけにはいかないよ。」
意訳
司馬牛「仁とは何ですか。」
孔子「言葉で説明できるようなことじゃない。」
司馬牛「言葉で説明できない、それですぐに仁であると言い切っていいものでしょうか。」
孔子「仁は実行が難しい。簡単に説明などできんよ。」
従来訳
司馬牛が仁についてたずねた。先師はこたえられた。――
「仁者というものは、言いたいことがあっても、容易に口をひらかないものだ。」
司馬牛が更にたずねた。――
「容易に口をひらかない、――それだけのことが仁というものでございましょうか。」
すると先師はいわれた。――
「仁者は実践のむずかしさをよく知っている。だから、言葉をつつしまないではいられないのだ。」下村湖人『現代訳論語』
現代中国での解釈例
司馬牛問仁。孔子說:「仁者言談謹慎。」說:「言談謹慎,就能叫做仁嗎?」孔子說:「做起來很難,言談能不謹慎嗎?」
司馬牛が仁を問うた。孔子が言った。「仁者は言葉を慎む。」言った。「言葉を慎む、それだけで仁と言ってよいのですか?」孔子が言った。「その実行が難しい。言葉を慎まないでいられるだろうか?」
論語:語釈
司馬牛(シバギュウ)
孔子の弟子。あざ名は耕。孔子塾生には珍しく貴族の出身で、姓の通り宋国の将軍職を務める家柄だった。兄は宋国元帥で、孔子を襲撃したことになっている桓魋(論語述而篇22)。『春秋左氏伝』によると、宋国の政変で桓魋が失脚すると、司馬牛も地位や領地を捨て、それも桓魋を避けるように放浪し、なぜか魯国に来て孔子に見せつけるように自ら命を絶った。詳細は論語の人物・司馬耕子牛を参照。
漢文では「司馬」で”将軍”を意味し、その職を世襲する者が氏族名にもした。
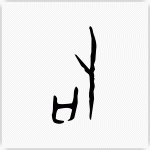

(甲骨文)
「司」の初出は甲骨文。字形は「𠙵」”口に出す天への願い事”+”幣のような神ののりしろ”。原義は”祭祀”。春秋末期までに、”祭祀”・”王夫人”・”君主”・”継ぐ”・”役人”の意に用いた。詳細は論語語釈「司」を参照。


(甲骨文)
「馬」の初出は甲骨文。「メ」は呉音。「マ」は唐音。字形はうまを描いた象形で、原義は動物の”うま”。甲骨文では原義のほか、諸侯国の名に、また「多馬」は厩役人を意味した。金文では原義のほか、「馬乘」で四頭立ての戦車を意味し、「司馬」の語も見られるが、”厩役人”なのか”将軍”なのか明確でない。戦国の竹簡での「司馬」は、”将軍”と解してよい。詳細は論語語釈「馬」を参照。


「牛」甲骨文/牛鼎・西周早期
「牛」の初出は甲骨文。字形は牛の象形。原義は”うし”。西周初期まで象形的な金文と、簡略化した金文が併存していた。甲骨文では原義に、金文でも原義に、また人名に用いた。詳細は論語語釈「牛」を参照。
問(ブン)


(甲骨文)
論語の本章では”質問する”。この語義は春秋時代では確認できない。初出は甲骨文。「モン」は呉音。字形は「門」+「口」。甲骨文での語義は不明。西周から春秋に用例が無く、一旦滅んだ漢語である可能性がある。戦国の金文では人名に用いられ、”問う”の語義は戦国最末期の竹簡から。それ以前の戦国時代、「昏」または「𦖞」で”問う”を記した。詳細は論語語釈「問」を参照。
仁(ジン)


(甲骨文)
論語の本章では、”天下万物に対する無差別の愛”。この語義は孔子没後一世紀後に現れた孟子による、「仁義」の語義であり、孔子や高弟の口から出た「仁」の語義ではない。字形や音から推定できる春秋時代の語義は、敷物に端座した”よき人”であり、”貴族”を意味する。詳細は論語における「仁」を参照。初出は甲骨文。字形は「亻」”ひと”+「二」”敷物”で、原義は敷物に座った”貴人”。詳細は論語語釈「仁」を参照。
子曰(シエツ)(し、いわく)

論語の本章では”孔子先生が言った”。「子」は貴族や知識人に対する敬称で、論語では多くの場合孔子を指す。この二文字を、「し、のたまわく」と読み下す例がある。「言う」→「のたまう」の敬語化だが、漢語の「曰」に敬語の要素は無い。古来、論語業者が世間からお金をむしるためのハッタリで、現在の論語読者が従うべき理由はないだろう。


(甲骨文)
「子」の初出は甲骨文。論語の本章では、「子曰」で”先生”、「猶子也」で”息子”、「二三子」で”諸君”の意。字形は赤ん坊の象形。春秋時代では、貴族や知識人への敬称に用いた。詳細は論語語釈「子」を参照。


(甲骨文)
「曰」の初出は甲骨文。原義は「𠙵」=「口」から声が出て来るさま。詳細は論語語釈「曰」を参照。
者(シャ)


(金文)
論語の本章では”~は~だ”。新字体は「者」(耂と日の間に点が無い)。ただし唐石経・清家本ともに新字体と同じく「者」と記す。初出は殷代末期の金文。金文の字形は「木」”植物”+「水」+「口」で、”この植物に水をやれ”と言うことだろうか。原義は不明。初出では称号に用いている。春秋時代までに「諸」と同様”さまざまな”、”~する者”・”~は”の意に用いた。漢文では人に限らず事物にも用いる。詳細は論語語釈「者」を参照。
其(キ)


(甲骨文)
論語の本章では”その者の”という指示詞。初出は甲骨文。甲骨文の字形は「𠀠」”かご”。それと指させる事物の意。金文から下に「二」”折敷”または「丌」”机”・”祭壇”を加えた。人称代名詞に用いた例は、殷代末期から、指示代名詞に用いた例は、戦国中期からになる。詳細は論語語釈「其」を参照。
言(ゲン)


(甲骨文)
論語の本章では”発言”。初出は甲骨文。字形は諸説あってはっきりしない。「口」+「辛」”ハリ・ナイフ”の組み合わせに見えるが、それがなぜ”ことば”へとつながるかは分からない。原義は”言葉・話”。甲骨文で原義と祭礼名の、金文で”宴会”(伯矩鼎・西周早期)の意があるという。詳細は論語語釈「言」を参照。
也(ヤ)
唐石経「訒」→清家本「訒也」。現存最古の論語本である定州竹簡論語ではこの部分を欠損している。清家本の年代は唐石経より新しいが、より古い古注系の文字列を伝えており、唐石経を訂正しうる。これに従い「訒也」へと校訂した。論語の伝承について詳細は「論語の成立過程まとめ」を参照。
原始論語?…→定州竹簡論語→白虎通義→ ┌(中国)─唐石経─論語注疏─論語集注─(古注滅ぶ)→ →漢石経─古注─経典釈文─┤ ↓↓↓↓↓↓↓さまざまな影響↓↓↓↓↓↓↓ ・慶大本 └(日本)─清家本─正平本─文明本─足利本─根本本→ →(中国)─(古注逆輸入)─論語正義─────→(現在) →(日本)─────────────懐徳堂本→(現在)


(金文)
論語の本章、「其言也」では”…こそは…だ”。主格を表す。「訒也」では「なり」と読んで”~である”。断定の意を示す。断定の語義は春秋時代では確認できない。詠嘆「かな」と回してこの問題を回避することは可能だが、本章そのものが「訒」字の不在により、必ずしも春秋時代の漢語で解する必要は無い。初出は事実上春秋時代の金文。字形は口から強く語気を放つさまで、原義は”…こそは”。春秋末期までに句中で主格の強調、句末で詠歎、疑問や反語に用いたが、断定の意が明瞭に確認できるのは、戦国時代末期の金文からで、論語の時代には存在しない。詳細は論語語釈「也」を参照。
訒(ジン)


(古文)
論語の本章では”言葉にし難い”。物証としての初出は後漢の『説文解字』、文献上は論語の本章に次いで戦国最末期の『荀子』。先秦両漢の文献ではこの三点以外に見られない、極めて珍しい漢語。論語の時代に存在せず、論語時代の置換候補も無い。字形は「言」+「刃」で、「刃」は金文以前は”いばら”を意味し得た。いばらの茂みに隠すように、言葉の本質を隠すこと。詳細は論語語釈「訒」を参照。
『荀子』によれば、「訒」とは名前と中身が合っていないことを意味し、君子にとって禁忌とすべき行為だった。戦国末期に儒家の総帥だった荀子の教説と、論語の教説に対立があることになる。従って論語の本章は、戦国最末期より前に成立したとは考えづらく、前漢儒による創作と断じるのに理がある。
前漢の漢語としての「訒」を、古注で孔安国は「難也」と記し、「其言也訒也」→「其言也難也」と置き換えるべく、直訳すれば”その言葉はまさに難しいのである”となる。
斯(シ)


(金文)
論語の本章では”そのような状態”。初出は西周末期の金文。字形は「其」”籠に盛った供え物を祭壇に載せたさま”+「斤」”おの”で、文化的に厳かにしつらえられた神聖空間のさま。意味内容の無い語調を整える助字ではなく、ある状態や程度にある場面を指す。例えば論語子罕篇5にいう「斯文」とは、ちまちました個別の文化的成果物ではなく、風俗習慣を含めた中華文明全体を言う。詳細は論語語釈「斯」を参照。
謂(イ)


(金文)
論語の本章では”…であると評価される”。本来、ただ”いう”のではなく、”~だと評価する”・”~だと認定する”。現行書体の初出は春秋後期の石鼓文。部品で同義の「胃」の初出は春秋早期の金文。金文では氏族名に、また音を借りて”言う”を意味した。戦国の竹簡になると、あきらかに”~は~であると言う”の用例が見られる。詳細は論語語釈「謂」を参照。
之(シ)


(甲骨文)
論語の本章では”これ”。初出は甲骨文。字形は”足”+「一」”地面”で、あしを止めたところ。原義はつま先でつ突くような、”まさにこれ”。殷代末期から”ゆく”の語義を持った可能性があり、春秋末期までに”~の”の語義を獲得した。詳細は論語語釈「之」を参照。
巳(シ)→已(イ)
論語の本章では「のみ」と読んで”…だけ”。限定を示す。定州竹簡論語ではこの部分を欠損している。唐石経、は「巳」字で記し、清家本は「已」字で記す。唐代の頃、「巳」「已」「己」字は相互に通用した。事実上の異体字と言ってよい。


(甲骨文)
「巳」(シ)の初出は甲骨文。字形はヘビの象形。「ミ」は呉音(遣隋使より前に日本に伝わった音)。甲骨文から十二支の”み”を意味し、西周・春秋の金文では「已」と混用されて、完了の意、句末の詠嘆の意、”おわる”の意に用いた。詳細は論語語釈「巳」を参照。


(甲骨文)
「已」の初出は甲骨文。字形と原義は不詳。字形はおそらく農具のスキで、原義は同音の「以」と同じく”手に取る”だったかもしれない。論語の時代までに”終わる”の語義が確認出来、ここから、”~てしまう”など断定・完了の意を容易に導ける。詳細は論語語釈「已」を参照。
矣(イ)
清家本は「已」の後ろに「矣」を付ける。”…てしまう”の意。また漢文ではしばしば「已矣」は「やんぬるかな」と読んで”もうだめだ”の意に用いる。


(金文)
初出は殷代末期の金文。字形は「𠙵」”人の頭”+「大」”人の歩く姿”。背を向けて立ち去ってゆく人の姿。原義はおそらく”…し終えた”。ここから完了・断定を意味しうる。詳細は論語語釈「矣」を参照。
乎(コ)


(甲骨文)
論語の本章、「已矣乎」では「か」と読んで疑問の意。「無訒乎」では「かな」と読んで詠嘆の意。これらの語義は春秋時代では確認出来ない。「乎」の初出は甲骨文。字形は持ち手の柄を取り付けた呼び鐘を、上向きに持って振り鳴らし、家臣を呼ぶさまで、原義は”呼ぶ”こと。甲骨文では”命じる”・”呼ぶ”を意味し、金文も同様で、「呼」の原字となった。句末の助辞として用いられたのは、戦国時代以降になるという。詳細は論語語釈「乎」を参照。
其言也訒斯謂之仁已矣乎
主部が「其言也訒斯」で”発言が言いにくそうである状態”、述語動詞が「謂」”~であると評価される”。目的語1が「之」=「其言也訒斯」、目的語2が「仁」。「已矣乎」は接尾辞で”~であるだけであるか”。
日中ともにこの部分は「其言也訒、斯謂之『仁』已矣乎。」と句読をつけるのが通説だが、「斯」とは単なる”これ”という指示詞・代名詞ではなく、”そういう環境・場面・状態”という語義を持つ。従って「其言也訒」は「斯」の修飾部と解すべく、”発言が言いにくそうである状態”と一句にまとめるのが理にかなう。
爲(イ)


(甲骨文)
論語の本章では”する”。新字体は「為」。字形は象を調教するさま。甲骨文の段階で、”ある”や人名を、金文の段階で”作る”・”する”・”~になる”を意味した。詳細は論語語釈「為」を参照。
難(ダン/ダ)
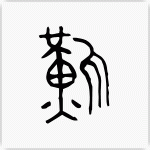

(金文)
論語の本章では”めったにない”→”難しい”。初出は西周末期の金文。新字体は「難」。「ダン」の音で”難しい”、「ダ」の音で”鬼遣らい”を意味する。「ナン」「ナ」は呉音。字形は「𦰩」”火あぶり”+「鳥」で、焼き鳥のさま。原義は”焼き鳥”。それがなぜ”難しい”・”希有”の意になったかは、音を借りた仮借と解する以外にない。西周末期の用例に「難老」があり、”長寿”を意味したことから、初出の頃から、”希有”を意味したことになる。詳細は論語語釈「難」を参照。
得(トク)


(甲骨文)
論語の本章では”手に入れる”→”~できる”。初出は甲骨文。甲骨文に、すでに「彳」”みち”が加わった字形がある。字形は「貝」”タカラガイ”+「又」”手”で、原義は宝物を得ること。詳細は論語語釈「得」を参照。
無(ブ)


(甲骨文)
論語の本章では”…無しで”。初出は甲骨文。「ム」は呉音。甲骨文の字形は、ほうきのような飾りを両手に持って舞う姿で、「舞」の原字。その飾を「某」と呼び、「某」の語義が”…でない”だったので、「無」は”ない”を意味するようになった。論語の時代までに、”雨乞い”・”ない”の語義が確認されている。戦国時代以降は、”ない”は多く”毋”と書かれた。詳細は論語語釈「無」を参照。
論語:付記
検証
論語の本章は、訒の字が論語の時代に存在しない以上、後世の創作と断じざるを得ないのだが、先秦両漢に三件しか使用例の無い「訒」が、本当に論語の本章に書いてあった保証もまた無い。仮に本章が史実だとするなら、訒ȵi̯ən(去)が慎ȡi̯ĕn(去)だったのかもしれない。
司馬牛問「仁」。子曰、「仁者、其言也愼。」曰、「其言也愼、斯謂之『仁』已夫。」子曰、「爲之難、言之得無愼乎。」
司馬牛仁を問う。子曰く、仁者は、其の言也慎む。曰く、其の言也慎む、斯れを之れ仁と謂う已夫。子曰く、之れを為すや難し、之れを言うに慎み無きを得ん乎。
司馬牛が仁を問うた。
孔子「仁の者は、言葉に慎(重)の者だ。」
司馬牛「そうやって言葉を濁す、それだけで仁者と言い張るのですか。」
孔子「言葉を慎むのがそもそも難しい。仁を言いよどむのも当然だ。」
現存する論語の最古の注釈である古注に、「孔安國曰訒難也」とあり、孔安国は前漢武帝期の儒者とされているから、すでに訒と書かれていたことになるが、孔安国は実在そのものが疑われており、うっかり信用するわけにも行かない。
だが上掲語釈の通り、「訒」の解釈は戦国最末期の荀子までとそれより後でぜんぜん異なり、「訒」を厭えと教えた荀子の教説は論語の本章と矛盾することになる。従って本章は、前漢期の創作と考えるのに理がある。
解説
まず司馬耕子牛の人物とその変死については、論語の人物・司馬耕子牛を参照。
子牛は孔子塾生には珍しい貴族の出で、その出身国は宋であり、孔子の時代で言えば、宋は前王朝殷の末裔という由緒正しき諸侯国だった。その宋国で代々上級貴族として続いた家柄の子牛が、論語の時代の仁=貴族らしさとは何か、を孔子に尋ねること自体が場面として想像しがたい。
英国王が顧問官に「国王とは何だろうな」と尋ねるのは、愚痴やため息としてはあり得ても、未知への疑問としてはあり得ないのと同じ。従って論語の本章で言う「仁」は、孟子が言いだした「仁義」の意と解すべきで、「仁義」の価値を高騰させてメシを食った漢儒の作りそうな話である。
「孔子様ですら言葉では説明できないと仰ったのだから、仁を理解したければ、我ら儒者にもっとお金を寄こして教えを乞いなさい」というわけである。
論語の本章、新古の注は次の通り。
古注『論語集解義疏』
司馬牛問仁子曰仁者其言也訒註孔安國曰訒難也牛宋人弟子司馬犂也曰其言也訒斯謂之仁矣乎子曰為之難言之得無訒乎註孔安國曰行仁難言仁亦不得不難矣
本文「司馬牛問仁子曰仁者其言也訒」。
注釈。孔安国「訒とは難しいということである。牛は宋人の弟子で司馬犂のことである。」
本文「曰其言也訒斯謂之仁矣乎子曰為之難言之得無訒乎」。
注釈。孔安国「仁の実践は言葉にし難いのである。だからむずかしくないわけがないのである。」
新注『論語集注』
司馬牛問仁。司馬牛,孔子弟子,名犁,向魋之弟。子曰:「仁者其言也訒。」訒,音刃。訒,忍也,難也。仁者心存而不放,故其言若有所忍而不易發,蓋其德之一端也。夫子以牛多言而躁,故告之以此。使其於此而謹之,則所以為仁之方,不外是矣。曰:「其言也訒,斯謂之仁已乎?」子曰:「為之難,言之得無訒乎?」牛意仁道至大,不但如夫子之所言,故夫子又告之以此。蓋心常存,故事不苟,事不苟,故其言自有不得而易者,非強閉之而不出也。楊氏曰「觀此及下章再問之語,牛之易其言可知。」程子曰:「雖為司馬牛多言故及此,然聖人之言,亦止此為是。」愚謂牛之為人如此,若不告之以其病之所切,而泛以為仁之大概語之,則以彼之躁,必不能深思以去其病,而終無自以入德矣。故其告之如此。蓋聖人之言,雖有高下大小之不同,然其切於學者之身,而皆為入德之要,則又初不異也。讀者其致思焉。
本文「司馬牛問仁。」
司馬牛とは孔子の弟子で、いみ名は犁、向魋(=桓魋)の弟である。
本文「子曰:仁者其言也訒。」
訒の音は刃である。訒とはやりづらい、難しいの意である。仁者は気を確かに持ってちゃらんぽらんをやらかさないので、もし言いづらいことがあればむやみに口に出さないが、たぶんこれが仁者の徳の一部であろう。先生は牛がおしゃべりで浮ついたのを見て取り、だからこのように言って諭した。このように慎み深い態度でいれば、必ず仁を実践する方法になり得、失敗はあり得ないからである。
本文「曰:其言也訒,斯謂之仁已乎?子曰:為之難,言之得無訒乎?」
牛は仁の道が至って大きいと知っていたが、先生が言うようなことだけではないと思っていた。だから先生はこのように言葉を重ねて言ったのである。たぶん不動心を確かに持てば、行動はちゃらんぽらんにならず、ちゃらんぽらんでなければ、発言は自然と簡単にはできなくなる道理で、無理やりに口を閉ざしているわけではない。
楊時「本章と次章で質問している態度から、牛のおしゃべりぶりが知れる。」
程頤「司馬牛がこれほどおしゃべりだといっても、聖人はきちんとお説教して、この通りの言葉で善導した。」
愚かな私朱子が思うに、牛の性格はこの通りだが、もしその性格のゆがみをお説教しなければ、仁についてデタラメを言いふらしたに違いない。つまりこの浮ついた性根では、必ず自分のゆがみを深く反省することは出来ないから、徳の何たるかも知らずに生涯を終えただろう。だからこのようにお説教した。たぶん聖人の言葉は、相手によって高下大小の違いがあり、儒学を学ぶ者が学びの要点にさしかかっている時、その誰にも徳の何たるかを理解させる要点を語るに当たっては、初めから教えが異なったことがない。論語を読む者はこのあたりをよく考えるように。
余話
(思案中)





コメント