
- 是(ゼ/シ・9画)
- 井(セイ・4画)
- 正(セイ・5画)
- 生(セイ・5画)
- 世(セイ・5画)
- 成(セイ・6画)
- 西(セイ・6画)
- 聲/声(セイ・7画)
- 齊/斉(セイ・8画)
- 姓(セイ・8画)
- 性(セイ・8画)
- 妻(セイ・8画)
- 征(セイ・8画)
- 省(セイ・9画)
- 星(セイ・9画)
- 政(セイ・9画)
- 城(セイ・9画)
- 逝(セイ・10画)
- 栖(セイ・10画)
- 祭(セイ・11画)
- 淸/清(セイ・11画)
- 濟/済(セイ・11画)
- 情(セイ・11画)
- 盛(セイ・11画)
- 細(セイ・11画)
- 晶(セイ・12画)
- 聖(セイ・13画)
- 誠(セイ・13画)
- 歲/歳(セイ・13画)
- 腥(セイ・13画)
- 靜/静(セイ・14画)
- 際(セイ・14画)
- 精/精(セイ・14画)
- 請(セイ・15画)
- 騂(セイ・17画)
是(ゼ/シ・9画)
井(セイ・4画)


甲骨文/大盂鼎・西周早期
初出:初出は甲骨文。
字形:井桁の象形とされ、原義は”井戸”と言われる。ただし春秋末期までの出土物に、明確にそれと解せる例は無い。
音:カールグレン上古音は不明。藤堂上古音はtsieŋ(上)。
用例:甲骨文に「婦井」の語が複数見え、おそらく諸侯の一つ。「井」国出身の王夫人だから「婦井」という。また「井人」の語も複数見える。
西周早期「史鼎」(集成2575)に「史才井」とあり、「先秦甲金文簡牘詞彙資料庫」では「型」と釈文している。”かたどる”の意だろうか。
西周末期「師同鼎」(集成2779)に「其井。」とあり、「先秦甲金文簡牘詞彙資料庫」では「刑」と釈文している。
西周末期「新收殷周青銅器銘文暨器影彙編」NA0745に「出戡(捷)于井阿」とあるが、意味するところが分からない。地名だろうか。
「漢語多功能字庫」によると、甲骨文・金文では国名「邢」に用いた。金文では”刑罰”(兮甲盤・西周末期)、”法律・刑法”(毛公鼎・西周末期)、”見習う”(〔大〕盂鼎・西周早期)に用いた。戦国の竹簡では下に「土」が加えられ、”刑罰”・”かたどる”の意に用いた。
学研漢和大字典
象形。井は、四角いわく型を描いたもので、もと、ケイと読む。形や型の字に含まれる按印の原字。丼は、「四角いわく+・印」の会意文字で清水のたまったさまを示す。セイと読み、のち、両者の字形が混同して井と書くようになった。井は、また、四角にきちんと井型に区切るの意を派生する。「井」の全画の変形からカタカナの「ヰ」ができた。
語義
- {名詞}い(ゐ)。いど。
- {名詞}人が集まって住んでいる所。▽公共の井戸を掘ると、人が集まり周囲に住居ができるので、市(まち)を「市井」といい、郷村を「郷井」という。
- {形容詞}井げたのように、正方形にきちんとくぎったさま。「井然」。
- {名詞}周代、土地の行政区画で、一里四方の区画。「井田」「方里而井、井九百畝=方里にして而井なり、井は九百畝なり」〔孟子・滕上〕
- {名詞}二十八宿の一つ。規準星は今のふたご座にふくまれる。ちちり。
- {名詞}周易の六十四卦(カ)の一つ。巽下坎上(ソンカカンショウ)の形で、井戸が人を養うような恩沢があるさまを示す。
字通
[象形]井げたのわくの形。〔説文〕五下に「八家一井、構韓(こうかん)(井の垣)の形に象る」とする。篆字は丼に作り、丼中の点を「𦉥(かめ)の象なり」と解し、伯益がはじめて井を作ったという起原説話をしるしている。卜文・金文には字を邢(けい)という国名に用いるほか、井の形には、人の首足に加える枷(かせ)の形で、のちの刑となるもの、鋳型のわくの形で、のちの形・型となるもの、陥穽として設けるもので、のちの穽となるものがあり、井は邢・刑・形・型・穽の初文である。〔孟子〕にみえるような井田法は、西周期の資料にその徴証を求めることはできず、文字が生まれた殷代には、もとより存しなかったものである。
正(セイ・5画)
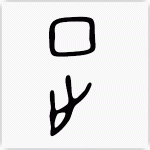

甲骨文/君夫簋蓋・西周中期
初出:初出は甲骨文。
字形:字形は「囗」”城塞都市”+そこへ向かう「足」で、原義は”遠征”。
音:カールグレン上古音はȶi̯ĕŋ(平/去)。同音は下記。論語語釈「政」も参照。
用例:西周早期の「大盂鼎」(殷周金文集成02837)に「㽙正厥民」とあり、「たおさ、その民を正す」と読め、”正しくする”と解せる。
「漢語多功能字庫」によると、甲骨文では”遠征”の意に用いるが、同時に「正月」をすでに年始の月とした。また地名・祭礼名にも用いた。金文では、”征伐”・”年始”のほか、”長官”(五祀衛鼎・西周)、”審査”(師遽𣪕蓋・西周)の意に用いた。”正直”の意は戦国時代の竹簡から。また同時期に「征」”徴税”の字が派生した。
『定州竹簡論語』は「正・政可通、古多以政為正。」”正は政を代用できる。古くは政を正と書いた例が多い”と言う。
おそらくその理由は漢帝国が、秦帝国の正統な後継者であることを主張するため、始皇帝のいみ名「政」を避けたため。その結果『史記』では項羽を中華皇帝の一人に数え、本紀に伝記を記した。その必要があったからだ。
高祖劉邦は「法三章」=秦の法律を緩める、と公約して人心を得たが、天下を取るとごっそり秦の法律を復活した。その後ろめたさ、加えて劉邦が秦の下級官吏だったのに反乱を起こした不条理を誤魔化すため、「乱暴この上ない項羽を滅ぼして、秦帝国最盛時同様の秩序を回復した」と言い張ったのである。

学研漢和大字典
会意。「一+止(あし)」で、足が目標の線めがけてまっすぐに進むさまを示す。征(まっすぐに進む)の原字。聖(純正な人)・貞(ただしい)・挺(まっすぐ)などと同系。また是(ゼ)・(シ)(ただしい)と縁が近い。類義語に匡。
語義
- {形容詞・名詞}ただしい(ただし)。まっすぐであるさま。まっすぐであること。《対語》⇒邪(よこしま)。「公正」「正義」「其身正、不令而行=其の身正しければ、令せずして行はる」〔論語・子路〕
- {動詞}ただす。まっすぐにする。また、誤りを道理にあうように直す。「改正」「就有道而正焉=有道に就いて正す」〔論語・学而〕
- {形容詞}まともであるさま。また、まっすぐに向いているさま。まんなかの。《対語》⇒反・裏。「正面」「正中」「正坐(セイザ)」。
- {形容詞}まじりけのないさま。また、ほんとうのものであるさま。《類義語》純。「正白(まっしろ)」「正方形」。
- {形容詞}主なものである。本式のものである。《対語》副・従・略。「正式」「正三位」「正本」。
- {名詞}役目の長官。「楽正(音楽をつかさどる役所の長官)」。
- {名詞・形容詞}ちょうどの時刻。また、時刻がちょうどであるさま。「正五時」「正午(ちょうど十二時)」。
- {名詞}中国の暦法で、一年の基準になるもの。▽平声に読む。「正月」「正朔(セイサク)(こよみ)」「改正(王朝が変わった時、正月をいつとするかの規準を改めて、新たに暦をきめること)」。
- {名詞}まと。弓を射てまっすぐにあてるまと。▽平声に読む。「正鵠(セイコク)(まとの中心)」。
- {副詞}まさに。まさしく。ちょうど。「正当其時=正に其の時に当たる」「正唯弟子不能学也=正に唯れ弟子学ぶ能はざるなり」〔論語・述而〕
- {名詞}数学で、負に対して、零より大きいこと。プラス。「正数」。
- 《日本語での特別な意味》
①かみ。四等官で、司・監の第一位。
②電子の電荷のうち、陽性に生じるもの。プラス。《対語》負。
③特定の官職で、その上位であることをあらわすことば。「検事正」。
字通
[会意]一+止。卜文・金文の字形は、一の部分を囗(い)の形に作り、囗は都邑・城郭の象。これに向かって進む意であるから、正は征の初文。征服者の行為は正当とされ、その地から貢納を徴することを征といい、強制を加えて治めることを政という。〔説文〕二下に「是なり。止に從ひ、一以て止まる」とするが、一に従う字ではない。その支配にあたるものを正といい、周初の金文〔大盂鼎(だいうてい)〕に「殷の正百辟」という語がみえ、官長たる諸侯の意。官の同僚を「友正」という。征服・征取・政治の意より、正義・中正、また純正・正気の意となる。
生(セイ・5画)


七年趞曹鼎・西周中期/甲骨文
初出:初出は甲骨文。
字形:字形は「屮」”植物の芽”+「一」”地面”で、原義は”生える”。
音:カールグレン上古音はsĕŋ(平)。
用例:「甲骨文合集」1977.1に「己卯卜㱿(殻)貞壬父乙婦好生保」とあり、”生む”と解せる。
「漢語多功能字庫」によると、甲骨文で、”育つ”・”生き生きしている”・”人々”・”姓名”の意があり、金文では”月齢の一つ”(豐卣・西周中期)、”生命”(蔡姞簋・西周)の意があるが、”発生する”の意は戦国時代の「中山王鼎」まで下るという。
論語語釈「性」si̯ĕŋ(去)も参照。
『孟子』など先秦の文書では「性」を意味する漢字として用いられるが、ブツとしては「姓」を意味するものが知られる。定州竹簡論語では現伝論語で「性」とあるところを「生」と記している(論語陽貨篇2)。『論語』も『孟子』も漢代に書き加えられた箇所が多数あり、「生」→「性」と断じるにはなお検討を必要とする。
先秦の文献では『呂氏春秋』に「生」とある箇所を、『四部叢刊初編』所収の版本では注で「生、性也」というが信じがたい。明清では朱子学が正統とされ、朱子学では『孟子』と性理論を重んじるから、それに頭をやられた儒者のデタラメに過ぎない。
始生之者,天也;養成之者,人也。能養天之所生而勿攖之謂天子。天子之動也,以全天為故者也。此官之所自立也。立官者以全生也。今世之惑主,多官而反以害生,則失所為立之矣。譬之若修兵者,以備寇也,今修兵而反以自攻,則亦失所為修之矣。

生命の始まりは天である。天に養われて姿を形作ったのが人である。天が生み出した者を養うことが出来、いじめない者を天子という。天子の行動は、全て天に根拠を持っているからだ。
だから政府というのはあるべくしてあるのであり、存在意義を問われない。政府の役割は人の生命を保証することにあるからだ。ところが今の諸王は、むやみに巨大な政府を組織して、却って人の生命を脅かしている。つまり存在意義を失っているのだ。
例えば軍備は侵略を防ぐためにあるはずが、今の諸王は逆に侵略のために軍備を整えている。つまり軍隊の存在意義を失っているのだ。(『呂氏春秋』本生1)
「天子」の言葉が中国語に現れるのは西周早期で、殷の君主は自分から”天の子”などと図々しいことは言わなかった。詳細は論語述而篇34余話「周王朝の図々しさ」を参照。
論語陽貨篇2「性・生」の語釈も参照。
学研漢和大字典
会意。「若芽の形+土」で、地上に若芽のはえたさまを示す。いきいきとして新しい意を含む。青(あおあお)・清(すみきった)・牲(いきている牛)・姓(うまれによってつける名)・性(うまれつきのすんだ心)などと同系。異字同訓に産む・産まれる「卵を産み付ける。産みの苦しみ。産み月。予定日が来てもなかなか産まれない」。「棲」の代用字としても使う。「生息」また、「栖」の代用字としても使う。「生息」▽付表では、「芝生」を「しばふ」と読む。
語義
- {動詞}いきる(いく)。いかす。《対語》⇒死。《類義語》活。「生活」「生存」「両虎共闘、其勢不倶生=両虎共に闘はば、其の勢ひ倶には生きず」〔史記・廉頗藺相如〕
- {動詞}うむ。うまれる(うまる)。子をうむ。子がうまれる。物をつくり出す。物ができる。《類義語》産。「産生」「与顔氏女野合而生孔子=顔氏の女と野合して孔子を生む」〔史記・孔子〕
- (ショウズ)(シャウズ){動詞}はえる(はゆ)。おう(おふ)。おこる。発生する。植物の芽がはえる。「生春草=春草生ず」「本立而道生=本立ちて而道生ず」〔論語・学而〕
- {形容詞・名詞}なま。いきいきとして新しいさま。煮たきしてない。また、そのもの。《対語》熟。《類義語》鮮。「生鮮」「与一生樹肩=一生樹肩をあたふ」〔史記・項羽〕
- {名詞}いきていること。いきているもの。また、いのち。「生物」「生命」「養生喪死=生を養ひ死を喪ふ」〔孟子・梁上〕
- {名詞}学問をしている若い人。「学生」「生員」「儒生」「諸生」。
- {名詞}自分のことをへりくだって、でし、また、青二才の意を含めていうことば。「晩生(後輩。自称の語)」。
- {名詞}中国旧劇の男役。「老生(ふけ役)」「武生(武者役)」。
- {形容詞・副詞}いきながら。いきたまま。「生擒(セイキン)(いけどり)」「生劫之=生きながらこれを劫さん」〔史記・荊軻〕
- {形容詞・副詞}うまれながら。うまれつき。「生来」「人、生而有欲=人、生まれながらにして欲有り」〔荀子・礼論〕
- {形容詞}《俗語》なれていないさま。未熟なさま。《対語》熟。「生硬」「生路(ションルウ)(なれないみち)」。
- {副詞}《俗語》ひどく。非常に。《類義語》死。「生憎(ひどくにくらしい。あやにくと訓じる)」「生怕(ションパア)(ほんとにこわい)」。
- 《日本語での特別な意味》
①き。まじりけのない。純な。「生一本(キイッポン)」「生粋(キッスイ)の江戸っ子」。
②うぶ。ういういしい。
③なる。草木の実がなる。
字通
[象形]草の生え出る形。〔説文〕六下に「進むなり。艸木の生じて土上に出づるに象る」と生・進の音を以て解するが、声義の関係はない。卜辞の多生は多姓、金文の百生は百姓で、姓の意に用いる。また〔𦅫鎛(そはく)〕に「用(もつ)て考命彌生(びせい)ならんことを求む」とあるように、生命の義に用いる。〔舀鼎(こつてい)〕の「𣪘生覇(きせいは)」の生を眚の形に作り、目の部分は種の形で、種の発芽の状を示す。生は発芽生成の象を示す字である。すべて新しい生命のおこることをいう。
世(セイ・5画)


寧簋蓋・西周早期/吳方彝蓋・西周中期
初出:初出は西周早期の金文。

唐開成石経
字形:字形は枝葉の先で、年輪同様、一年で伸びた部分。派生して”世代”の意となった。唐石経では〔七丨〕形で記し、太宗李世民のいみ名を避諱している。
音:「セ」は呉音。カールグレン上古音はɕi̯ad(去)。
用例:西周早期「且日庚𣪕」(集成3992)に「用笹亯孝」とある「笹」は「世」と釈文されており、「用いて世々孝をいたせ」と読め、”代々”と解せる。
「漢語多功能字庫」によると、金文では”一生”(獻簋・西周早期)、”世代”(郘鐘・西周)、戦国末期では”人界”を意味した(中山王壺・戦国早期)。戦国の竹簡では”世代”を意味した。
学研漢和大字典
会意。十の字を三つ並べて、その一つの縦棒を横に引きのばし、三十年間にわたり期間がのびることを示し、長くのびた期間をあらわす。泄(セツ)・(エイ)(もれて、横にのびて流れる)・拽(エイ)(横に引きのばす)と同系。草書体をひらがな「せ」「よ」として使うこともある。▽草書体からひらがなの「せ」、また、草書体の変形からカタカナの「セ」ができた。
語義
- {名詞}親が子に引き継ぐまでの約三十年間。ゼネレーション。「世代」「必世而後仁=必ず世にして而後に仁ならん」〔論語・子路〕
- {名詞}よ。時代。「中世」「上古之世(ジョウコノヨ)」。
- {名詞}よ。人間の社会。「世間」「能与世推移=能く世と推移す」〔楚辞・漁父〕
- {副詞}よよ。代々。「項氏世世為楚将=項氏は世世楚の将為り」〔史記・項羽〕
- {形容詞}代々の。先祖からの。「世交」。
- 地質時代の区分で、「紀」と「期」の間。「沖積世」。
字通
[象形]草木の枝葉が分かれて、新芽が出ている形。新しい枝葉を示す。〔説文〕卉部三上に「三十年を一世と爲す。卉(き)に從ひて、之れを曳長す。亦た其の聲を取るなり」とするが、形も声も異なる。字形は生に近く、生もまた草木枝葉の生ずる形である。金文に世を枻・枼に作る。木には世、草には生の形となる。世をまた葉といい、万世を万葉という。
成(セイ・6画)


甲骨文/獻侯鼎・西周早期
初出:初出は甲骨文。
字形は「戊」”まさかり”+「丨」”血のしたたり”で、処刑や犠牲をし終えた様。甲骨文の字形には「丨」が「囗」”くに”になっているものがあり、もっぱら殷の開祖大乙の名として使われていることから、”征服”を意味しているようである。いずれにせよ原義は”…し終える”。
音:カールグレン上古音はȡi̯ĕŋ(平)。
用例:「漢語多功能字庫」によると、甲骨文では地名・人名、”犠牲を屠る”に用い、金文では地名(何尊・西周早期)、人名(史墻盤・西周中期)、”盛る”(弔家父簠・春秋早期)、戦国の金文では”完成”(中山王方壺・戦国早期)の意に用いた。
学研漢和大字典
会意兼形声。丁は、打ってまとめ固める意を含み、打の原字。成は「戈(ほこ)+(音符)丁」で、まとめあげる意を含む。▽締(ひとまとめ)の語尾がngに転じたことば。城(土で固めあげたしろ)・誠(まとまって欠けめのない心)と同系。
語義
- {動詞}なる。つくろうとしたものがしあがる。できあがる。「落成」「学難成=学成り難し」「大器晩成=大器は晩成す」〔老子・四一〕
- {動詞}なす。しあげる。りっぱになし遂げる。「成家=家を成す」「覇業可成=覇業成すべし」「悪乎成名=いづくにか名を成さんや」〔論語・里仁〕
- {動詞}なる。なす。変化して、ある状態になる。また、そうする。「成空=空と成る」「衰病已成翁=衰病已に翁と成る」〔杜甫・客亭〕
- {形容詞}できあがった。既成の。「成見(既成の考え)」「成事不説=成事は説かず」〔論語・八飲〕
- {名詞}すでにしあがった状態。「守成(すでに完成した現状を守り続けること)」。
- {名詞}たいらぎ(たひらぎ)。平和。また、争いごとのまとめ。「求成=成を求む」。
- {単位詞}音楽の段落や、土盛りの層を数えることば。「九成(九段落)」。
- {名詞・単位詞}古代、十里四方の田畑のこと。また、それを数えることば。
- {単位詞}《俗語》北京(ペキン)語で、十分の一。「一成(一割)」。
字通

[会意]戈(か)+丨(こん)。〔説文〕十四下に「就(な)るなり。戊に從ひ、丁(てい)聲」とするが、卜文・金文の字形は、戈(ほこ)に綏飾としての丨を加える形。器の制作が終わったときに、綏飾を加えてお祓いをする意で、それが成就の儀礼であった。就は凱旋門である京の完成のときに、犬牲を加えて、いわば竣工式を行う意。すべて築造や制作の完成のときには、その成就の儀礼を行ったものである。
西(セイ・6画)


『字通』所収甲骨文/戍B180鼎・殷代末期
初出:初出は甲骨文。
字形:西日が差す日暮れになって鳥が帰る巣の象形と言われる。
音:カールグレン上古音はsiər(平)。呉音では「サイ」。同音は論語語釈「洒」を参照。
用例:「甲骨文合集」5116.2に「丁酉卜古貞王往省从西大 小告」とあり、”にし”と解せる。
西周早期「高卣」(集成5431)に「王酓(飲)西宮」とあり、”西の”と解せる。
学研漢和大字典
象形。ざる・かごを描いたもので、栖(セイ)(ざる状の鳥の巣)にその原義が残る。ざるに水を入れるとさらさらと流れ去って、ざるが後に残ることから、日の光や昼間の陽気が、ざるの目からぬけるように流れ去る方向、つまり「にし」を意味することとなった。洒(セイ)(さらさらと流し去る)・遷(セン)(形を残して中身がうつり去る)と同系。
語義
- {名詞}にし。日の沈む方角。五行では金、季節では秋、色では白に当てる。「関西(カンセイ)・(カンサイ)(中国では、函谷関(カンコクカン)より西の地方。日本では、逢坂の関より西、おもに近畿地方)」。
- {名詞・形容詞}東洋・中(中国)・和(日本)に対して、ヨーロッパのこと。▽「西洋」の略。「泰西(タイセイ)(欧米)」「西医(西洋式の医者)」。
- {名詞}《仏教》仏のいる死後の世界。極楽。▽「西方浄土(サイホウジョウド)」の略。仏教はインドから伝わったので、西方を仏の地と考えた。「帰西(キセイ)・(キサイ)(死んで魂が仏土に帰すること)」。
- {動詞}にしする(にしす)。西方に向かって進む。「且布聞之、鼓行而西耳=且つ布これを聞き、鼓行して西するのみ」〔漢書・張良〕
- {副詞}にしのかた。西に向かって。また西のほうで。「西流」「西出陽関無故人=西のかた陽関を出づれば故人無からん」〔王維・送元二使安西〕
- 《日本語での特別な意味》「西班牙(スペイン)」の略。スペインのこと。「米西戦争」「西和辞典」。
字通
[仮借]卜文・金文の字形は、荒目の籠(かご)の形。〔説文〕十二上に「鳥、巢上に在るなり。象形。日、西方に在りて、鳥西す(巣に入る)。故に因りて以て東西の西と爲す」とする。方位の字はみな仮借。東は橐(たく)(ふくろ)の象形、南は南人(苗族)の聖器として用いる銅鼓の象形で、苗人はその器を南任という。北は相背く形。西の篆文の字形は疑うべく、東西の意に用いるのは仮借である。
聲/声(セイ・7画)


甲骨文1/2
初出:初出は甲骨文。金文は未発掘。
字形:台座に吊された打楽器を打つ様。原義は”音”。
音:カールグレン上古音はɕi̯ĕŋ(平)。
用例:甲骨文合集合集27632に「申卜聲穧其蒸兄辛」とあり、訳者の解独力を超える。「漢語多功能字庫」は「馨」”香り”だとし、「意謂進獻芳香的黃米」という。
学研漢和大字典
会意。声は、石板をぶらさげてたたいて音を出す、磬(ケイ)という楽器を描いた象形文字。殳は、磬をたたく棒を手に持つ姿。聲は「磬の略体+耳」で、耳で磬の音を聞くさまを示す。広く、耳をうつ音響や音声をいう。旧字「聲」の草書体をひらがな「せ」として使うこともある。
語義
- {名詞}こえ(こゑ)。▽人の声、動物の鳴き声、物の響きを含めていう。「音声」「聞其声不忍食其肉=其の声を聞けば其の肉を食らふに忍びず」〔孟子・梁上〕
- {名詞}うわさ。評判。「名声」「声、振礼羌=声、礼羌に振るふ」〔李娃伝〕
- {名詞}おと。音楽の響き。「錚錚然有京都声=錚錚然として京都の声有り」〔白居易・琵琶行・序〕
- {単位詞}こえ(こゑ)。声や、響きの回数を数えることば。「二三声(ニサンセイ)」。
- 「五声」とは、音楽の階名で、宮・商・角・徴(チ)・羽の五種(=五音)のこと。
- {名詞}中国語で、声調の区別。「四声」。
- {名詞}語頭子音のこと。「声母」⇒韻
字通
[会意]旧字は聲に作り、殸(けい)+耳。殸は声(けい)(磬石)を鼓(う)つ形。その鼓つ音を聲という。声(けい)は磬石を繋けた形である。〔説文〕十二上に「音なり。耳に從ふ。殸聲」という。卜文に声・殸に作り、ときに祝禱を収める器の形である𠙵(さい)を加えることがあり、磬声は神を招くときに鼓つものであった。もと神聴に達する音をいう。
齊/斉(セイ・8画)
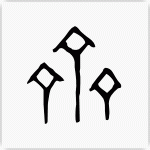

(甲骨文)/齊侯敦・春秋晚期
初出:初出は甲骨文。
字体:新字体は「斉」。甲骨文の字形には、◇が横一線にならぶものがある。字形の由来は不明だが、「漢語多功能字庫」は穀粒の姿とする。
![]()
慶大蔵論語疏では判読不能字の横に「𪗋」と傍記する(論語子罕篇10)。『大漢和辞典』によると「𪗋」は”縫う・もすそ”の意で、「通じて齊に作る」ともいう。また異体字「〔丿齊〕」と記す。上掲「斛斯祥墓誌」(唐)刻。
![]()
また論語郷党篇4では派生字「〔齊𧘇〕」と記す。「𧘇」は「衣」の略体。多義語の「齊」のうち、”すそ”であることを明らかにするための派生字と思われる。「魏凝禪寺三級浮圖頌」(東魏)刻。

また異体字「〔齊丿〕」と記す。「亠」を「广」に変えた形。上掲「韓顯宗墓誌」(北魏)刻。
![]()
また異体字「〔文日〕」と記す。「魏懷令李超墓誌銘」(北魏)刻字近似。
![]()

また「〔丿齋〕」と記し、「𪗋」と傍記する。前者は「隋張通妻陶貴墓誌」刻。後者は「唐孔子家廟(陜西本)」刻。物的初出は後漢の『説文解字』。論語の時代に存在しない。論語時代の置換候補もない。字形は「齊」”縫う”+「衣」。『漢書』で”もすそ”の意に用い、『説文解字』は”縫う”と語釈する。詳細は論語語釈「𪗋」を参照。
音:「サイ」は慣用音。カールグレン上古音はdzʰiər(平)。去声の音は不明。
用例:西周中期「新收殷周青銅器銘文暨器影彙編」NA0671に「王才(在)康宮,各齊白室」とあり、「各の白室(空き部屋?)を斉う」と読め、”整える”と解せる。
「漢語多功能字庫」によると、甲骨文では地名に用いられ、金文では加えて人名・国名に用いられた(陳侯午敦・戦国中期)。論語語釈「斎」も参照。
学研漢和大字典

象形文字で、◇印が三つそろったさまを描いたもの。のち下に板または布のかたちをそえた。
儕(セイ)(そろった仲間)・臍(セイ)(上下左右そろったまん中にあるへそ)・劑(セイ)(=剤。そろえて切る)・濟(サイ)(=済。水量をそろえる)などと同系のことば。
意味〔一〕セイ/ザイ
- {動詞・形容詞}ととのう(ととのふ)。ひとしい(ひとし)。きちんとそろう。大小・長さ・行為などが、ちぐはぐすることなくそろう。「均斉」「整斉」「斉一」。
ま{動詞}ととのえる(ととのふ)。ひとしくする(ひとしくす)。きちんとそろえる。「斉駒並駕(セイクヘイガ)(車馬をそろえて進む)」「斉之以刑=これを斉ふるに刑を以てす」〔論語・為政〕 - {名詞}過不足なくそろえて調和した状態。調和のとれた味。「八珍之斉(ハッチンノセイ)」〔周礼・食医〕
- {副詞}ひとしく。そろって。みんな。《類義語》均。「民不斉出於南畝=民は斉しく南畝に出でず」〔史記・平準書〕
- {名詞}国名。周代に太公望呂尚(リョショウ)の封ぜられた国。今の山東省。桓公(カンコウ)の代に覇者(ハシャ)となった。戦国時代には臣下の田氏が国を奪って、戦国の七雄となったが、前二二一年秦(シン)に滅ぼされた。
- {名詞}王朝名。南北朝時代、南朝の一つ。南斉。蕭斉。蕭道成(ショウドウセイ)が宋(ソウ)から位を奪ってたて、建康(今の南京)に都をおいた。七代で梁(リョウ)に滅ぼされた。四七九~五〇二。
- {名詞}王朝名。南北朝時代、北朝の一つ。北斉。高斉。高洋がたて五代で北周に滅ぼされた。五五〇~五七七。
- {名詞}心身をきちんとととのえること。ものいみ。▽斎に当てた用法。zh(iと読む。「斉戒以事鬼神=斉戒してもつて鬼神に事ふ」〔礼記・表記〕
意味〔二〕セイ/ザイ
- {名詞}層がきちんと重なった赤色の雲母。
意味〔三〕シ
- {名詞}衣のすそ。▽長さをそろえてあるので斉という。「斉衰(シサイ)(衣のすそを縫わず、切ったままにした喪服)」「摂斉升堂=斉を摂げて堂に升る」〔論語・郷党〕
字通
[象形]髪の上に、三本の簪笄(しんけい)を立てて並べた形。祭祀に奉仕するときの婦人の髪飾り。祭卓の形である示を加えると齋(斎)となり、斎敬をいう。〔説文〕七上に「禾麥(くわばく)穗を吐きて、上平らかなり」と禾穂の象とするが、髪飾りの整うことをいう字である。簪笄を中央に集める形は參(参)で、簪(かんざし)の「参(まじ)わり」「参差(しんし)」として美しい意となる。〔詩、召南、采蘋〕「齊(うるは)しき季女有り」の齊を、〔玉篇〕に引いて䶒に作り、婦人簪飾の姿をいう。殷周期の方鼎を、自名の器に「齎(せい)」としるしており、斉に方斉の意がある。訓義の多い字であるが、斉敬の義の引伸義が多い。
姓(セイ・8画)


合14027/羅兒匜・春秋末期
初出:初出は甲骨文。
字形:「女」+「生」。甲骨文の字形には部品の配置が逆のものがある。女系の血統を意味する。
音:カールグレン上古音はsi̯ĕŋ(去)。「ショウ」は呉音。
用例:「甲骨文合集」14027に「姓娩其嘉」とあり、女性名の一部と解せる。

𦅫鎛・春秋中期
金文では一旦この語が忘れられ、ほぼ「生」で「姓」と釈文する。復活するのは春秋時代で、中期の「𦅫鎛(齊𥎦鎛)」(集成271)に「𠍙余子𠇷」とあり、「𠇷」を「姓」と釈文する例があるが、「孫」と解する方が理に叶う。
その後春秋末期の「羅兒匜」NA1266には、「姓」として見られる。
備考:論語語釈「氏」も参照。血統集団の意が強い「姓」に対して、「氏」は祭祀・軍事共同体あるいは財団法人で、現代語的に言うと「族」に近い。「姓」は女系、「氏」はローマのgensのような男系と考える事も出来るが、それをまるまる論語の時代に当てはめると勘違いの素となる。(→wiki「氏」)
周代の諸侯に、周王と同じ「姫」姓を名乗る者は多いが、そのほとんどがうそデタラメであること、とうに宮崎市定博士が論文に書いたとおりだ。江戸期の大大名に「松平」姓が多いのと同じで、これはあくまで立て前である。事情が変われば薩長のように倒幕に走る。
対して、中国の「氏」は山賊だと思えばよい。まるで血のつながりはないが、あたかも家族のように結束が強く、末端はお山のためなら命も捨てる。そうでない山賊は、あっという間に崩壊する。イメージとデタラメが先行する「姓」とは違うのだ(論語憲問篇41付記参照)。
学研漢和大字典
会意兼形声。「女+(音符)生」で、うまれた血筋をあらわし、かつ女系祖先にちなむ名なので、女へんを添えた。生・性(うまれつき)と同系。
語義
- {名詞}かばね。血筋をあらわす名。▽姜姓(キョウセイ)(斉(セイ)の姓)・姫姓(キセイ)(周の姓)のように、多くは女系の祖の名に由来し、またはその祖先の住んだ地名にちなむ。同姓は結婚しないというおきては最近にまで及んだ。氏(シ)(うじ)は、職業・身分の名や、地名などにちなんでつける。漢以後は姓と氏は混同し、合わせて姓といい、女性には氏ということが多い。「姓氏」「異姓」「同姓不婚(ドウセイフコン)」。
- (セイトス){動詞}その姓を名のる。「封於項、故姓項氏=項に封ぜらる、故に項氏を姓とす」〔史記・項羽〕
- み「百姓(ヒャクセイ)」とは、もろもろの姓。転じて、多くの庶民のこと。
- 《日本語での特別な意味》かばね。上代、家がらや、世襲の職業をあらわした称号。朝廷からたまわるもので、古くは、臣(オミ)・連(ムラジ)・国造(クニノミヤツコ)・県主(アガタヌシ)などがあった。のち、天武天皇のとき、家がらの尊卑をあらわす称号として、真人(マヒト)・朝臣(アソミ)・宿禰(スクネ)・忌寸(イミキ)・道師(ミチノシ)・臣・連・稲置(イナギ)の八種の姓をおいた。
▽訓の「かばね」は、もと、骨のこと。父系の血筋は、骨に宿ると考えられたことから。
字通
[形声]声符は生(せい)。〔説文〕十二下に「人の生まるる所なり。古の神聖人、母、天に感じて子を生む。故に天子*と稱す」(段注本)と、感生帝説話を以て解する。姓の起原が多く神話の形態で語られているからであろう。金文に百生・多生・子■(亻+生)のように、生・(亻+生)の字を用いる。卜文の好・妌・妊など、女部の字には、その姓を示すものが多いと考えられる。
*「天子」の言葉が中国語に現れるのは西周早期で、殷の君主は自分から”天の子”などと図々しいことは言わなかった。詳細は論語述而篇34余話「周王朝の図々しさ」を参照。
性(セイ・8画)

七年趞曹鼎・西周中期
初出:初出は西周中期の金文。ただし「生」と書き分けられていない。りっしんべんが付くようになったのは、後漢の『説文解字』から。
字形:「生」”地面から植物が生い育つさま”。原義は”生き物”で、のち”生き物の性質”を表すためりっしんべんが付いた。
音:「ショウ」は呉音。カールグレン上古音はsi̯ĕŋ(去)で、同音は「省」「姓」「騂」。「生」とは若干音が異なる。論語語釈「生」sĕŋ(平)も参照。
用例:春秋末期までに「性」と釈文されている「生」は一例のみで、西周中期「蔡姞𣪕」(集成4198)に「厥生。霝冬。其萬年無彊。」とある第一句を「小学堂」で「彌厥性」と釈文する。「そのさがをいやまさん」と読むのだろうか。
これは金文のおしまいによく見られる文例で、長寿を祈り、子孫に代々受け継ぐように説教しておわるのだが、素直に「その生をいやまさん」と読むべきではないだろうか。
備考:下掲『字通』にあるように、文献的には先秦の時代からある。「生」は金文で「姓」を表す例があるが、「性」を表す例は上記の一例のみ。定州竹簡論語・陽貨篇2では、現行論語で「性」とあるのを「生」と記している。だからといって、「生」が「性」を意味するとは限らない。
備考:「漢語多功能字庫」には見るべき情報がない。
学研漢和大字典
会意兼形声。生は、芽が地上に生え出るさま。性は「心+(音符)生」で、うまれつきのすみきった心のこと。情とは、心から生じるむきだしの反応の働きのことで、感情の意。
語義
- {名詞}うまれつき持っている心の働きの特徴。▽人間にうまれつき与えられたのが、おおらかな良知だと考えるのが性善説であり、うまれつき与えられたのが、欲求不満だと考えるのが性悪説である。「人之性悪=人之性は悪なり」〔荀子・性悪〕
- {名詞}さが。ひととなり。人や物に備わる本質・傾向。たち。「性本愛邱山=性本邱山を愛す」〔陶潜・帰園田居〕
- {名詞}肉体上の男女の区別。また、インド=ヨーロッパ語文法における名詞・代名詞の性質の一つ。「中性」。
- {名詞}中にひそむもの。外形のもとになるもの。《対語》⇒形(外にあらわれたもの)。「形性」「物性」。
- 《日本語での特別な意味》せい。インド=ヨーロッパ語などにみられる男性・中性・女性などの文法上の区別。
字通
[形声]声符は生(せい)。〔説文〕十下に「人の陽气、性善なる者なり」という。〔左伝、昭二十五年〕「地の性に因る」、〔孟子、告子上〕「是れ豈に水の性ならんや」のように、生物でなくても、それぞれのもつ本質や属性についてもいう。
妻(セイ・8画)
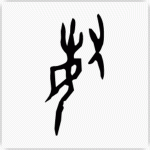

甲骨文/鑄叔皮父簋・春秋早期
初出:初出は甲骨文。
字形:女性に冠のようなものを手でかぶせる姿で、身分ある貴婦人を成人させるさま、あるいは君主の妻として認める儀式のさま。原義は”めとる”。
音:「サイ」は呉音。カールグレン上古音はtsʰiər(平/去)。
用例:「漢語多功能字庫」によると、甲骨文では”夫人”、金文では”とつぐ”(農卣・西周中期)の意で用いた。
学研漢和大字典
会意。又(て)は、家事を処理することを示す。妻は「又(て)+かんざしをつけた女」で、家事を扱う成人女性を示すが、サイ・セイということばは、夫と肩をそろえるあいてをあらわす。斉(整える、そろう)と同系。また、淒(セイ)(雨足がそろう)とも同系。草書体をかな「め」として使うこともある。
語義
- {名詞}つま。夫の配偶者。「荊妻(ケイサイ)」「糟糠之妻(ソウコウノツマ)(生活苦をともにしたつま)」「兄弟妻子離散=兄弟妻子離散す」〔孟子・梁上〕
- {動詞}めあわす(めあはす)。とつがせてつまとする。▽去声に読む。訓の「めあはす」は「め(女)+あはす」から。《類義語》嫁。「以其子妻之=其の子を以てこれに妻す」〔論語・公冶長〕
字通
[象形]髪飾りを整えた婦人の形。髪に三本の簪(かんざし)を加えて盛装した姿で、婚儀のときの儀容をいう。夫は冠して笄(けい)を加えた人の形。夫妻は結婚するときの儀容を示す字である。〔説文〕十二下に「婦なり。己と齊(ひと)しき者なり」(小徐本)とし、字形について女・屮(てつ)・又(ゆう)に従い、「又は事を持す。妻の職なり」とするが、字形に又を含まず、字も屮声ではない。妻が祭事にいそしむ字は敏で、その字形は妻に手をそえた形である。
征(セイ・8画)

『字通』所収金文
初出は甲骨文。カールグレン上古音はȶi̯ĕŋ(平)。
学研漢和大字典
会意兼形声。正は「━印+止(あし)」の会意文字で、遠方の目標線を目ざして、まっすぐ足を進めること。征は「彳(いく)+(音符)正」。のち正がまっすぐ、正しいの意となったため、征の字で、原義をあらわした。挺(テイ)(まっすぐ)・整(まっすぐにする)と同系。類義語に往。
語義
- {動詞}いく。ゆく。遠方を目ざして、まっすぐいく。《類義語》適・之(シ)・往。「征旅(セイリョ)(旅人)」「孤蓬万里征=孤蓬万里を征く」〔李白・送友人〕
- (セイス){動詞}うつ。敵を目がけてまっしぐらに進む。上の者が下の者をうつ。▽「孟子」尽心篇上に「征者上伐下也=征とは上の下を伐つなり」とある。「征伐(セイバツ)」。
- (セイス){動詞}もとめる(もとむ)。とる。下の者からとりたてる。めしあげる。《類義語》徴(チョウ)。「征税=税を征す」「上下交征利=上下交利を征す」〔孟子・梁上〕
- {名詞}人民からとりたてるもの。また、とりたてること。とりたて。
- {動詞}はっとする。しまったと思う。▽春(セイ)・懲に当てた用法。「征愁(セイショウ)(はっとしてたちすくむ)」。
字通
[形声]声符は正(せい)。正は征の初文。〔説文〕二下に正字を𨒌に作り、「正行なり」とするが、征役・征取をいう字である。正は囗(い)(城郭)に向かって進み、攻撃する意で、征の初文。征服して賦貢を徴することを征といい、その支配を行うことを政という。
省(セイ・9画)


甲骨文/大盂鼎・西周早期
初出:初出は甲骨文。
字形:おそらく「屮」”捧げる”+「目」。原義は”厳粛に見つめる”。
音:「ショウ」は呉音。カールグレン上古音はʂi̯ĕŋまたはsi̯ĕŋ(共に上)。
用例:漢語多功能字庫「屮」条によると、「屮」は甲骨文で祭祀を意味し、神霊に”捧げる”事であるらしい。挙げられている事例は次のように読める。
- 甲骨文合集27218「新鬯屮且乙。」→新たなる鬯もて且なる乙に屮ぐ。
- 甲骨文合集19811正「巫屮至𤉲隹。」→巫もて𤉲隹に至して屮ぐ。
すると「省」の原義は、祭祀を行うときのような厳粛な視線を意味しうる。「屮」”芽生え”は”「屮」”左手”と酷似しており、漢語多功能字庫は区別していないが、『大漢和辞典』は区別している。おそらく「省」の部品は「テツ」ではなく「サ」だろう。
備考:”みる”類義語の一覧については、論語語釈「見」を参照。
漢語多功能字庫
甲金文從「屮」從「目」,表示眼睛生出一個東西,被東西擋住,看不清楚眼前的事物。「屮」是「草」的初文,表示眼睛長出的東西,就像地上長草(沈培)。本義是一種目疾、眼病。後假借為省察的「省」。
甲骨文と金文は「屮」と「目」の字形に属し、目玉に出来物が出来て、ものに塞がれて、目の前のものがはっきり見えないさま。「屮」は「草」の初文で、目玉から長いものが出たのを示し、地上の長い草の象形(沈培)。原義は眼病の一種。のちに音を借りて”反省”の意となった。
学研漢和大字典
会意文字で、「目+少(小さくする)」で、目を細めてこまごまとみること。析sek(細かくわける)はその語尾がkに転じたことば。
意味〔一〕セイ
- (セイス){動詞}みる。目を細くして注意してみる。細かに分析して調べてみる。「省察」「退而省其私=退いて其の私を省す」〔論語・為政〕
- {動詞}かえりみる(かへりみる)。自分の心を細かにふりかえってみる。「反省」「吾日三省吾身=吾日に三たび吾が身を省みる」〔論語・学而〕
- {動詞}人の安否をねんごろにたずねる。親の安否をよくみてたしかめる。▽親のきげんを朝にうかがうのを定、夕方にたずねるのを省という。「省問」「帰省」。
意味〔二〕ショウ
- {動詞}はぶく。よけいな部分をとりさる。へらす。《類義語》略。「省略」「省刑罰=刑罰を省く」〔孟子・梁上〕
- {名詞}中国の行政区画の一つ。行政区画の単位として最も大きい。「省政府」。
- {名詞}役所。また、役所のランクをあらわすことば。「中書省」。
字通

卜文・金文の形は生に従い、生声。〔説文〕四上に屮に従う形とし、「視るなり。眉の省に従い、屮に従う」という。〔段注〕に「眉に従う者は、未だ目に形われざるなり。屮に従う者は、之れを微に察するなり」とするが、屮はおそらくもと目の上の呪飾、のち生の声が意識されて屮の下部に肥点を加える形になったものであろう。卜辞に王の順省を卜して「王省するに、往来災い亡きか」という。金文に「遹省」の語があり、遹は矛を台上に樹てて示威巡察を行う意。古くは眉飾などを施し、あるいは黥目を加えたものであろう。わが国の「など黥ける利目」もその類であろう。巡察することにより省察の意となり、省察して除くべきものを去るので省略の意となる。
訓義
1)みる、めぐりみる、つまびらかにみる。2)かえりみる、あきらかにする、さとる。3)あやまちをみる、あやまちをさる。4)はぶく、さる、へらす、すくなくする。5)役所、公卿の居る所、禁中、行政の区画名。6)眚と通じ、わざわい。
大漢和辞典



星(セイ・9画)


甲骨文/麓伯星父簋・西周
初出:初出は甲骨文。
字形:甲骨文の字形は「晶」tsi̯ĕŋ(平)”三つ星”+「生」sĕŋ(平、去声は不明)で、原義は”ほし”。「生」が加わった理由は不明だが、「晶」と何らかの意味の違いがあったと思われる。論語語釈「生」・論語語釈「晶」も参照。
音:カールグレン上古音はsieŋ(平)。
用例:「漢語多功能字庫」によると、甲骨文では原義のほか”晴れる”、金文では加えて人名に用いられ(麓伯簋・年代不明)、戦国の竹簡で”なまぐさい”を意味したという。
学研漢和大字典
会意兼形声。「きらめく三つのほし+(音符)生」で、澄んで清らかに光るほし。晶(ショウ)・(セイ)と生(ショウ)・(セイ)のどちらを音符と考えてもよい。生は、はえ出たばかりのみずみずしい芽の姿。晶(清らかな光)・青(澄み切ったみず色)・清(澄み切った水)などと同系。
語義
- {名詞}ほし。清らかに光るほし。《類義語》宿。「星宿」。
- {形容詞・名詞}星粒のように小さい。小さい点。「星星(点々と小さい)」「零星(細かい)」。
- {名詞}星占い。「星家」「星士(星占いをする人)」。
- {名詞}かぶとに点々と打ちつけたくぎの頭。
- {名詞}きら星のように並んだ将軍や高官。「将星」。
- {名詞}二十八宿の一つ。規準星は今のうみへび座にふくまれる。ほとほり。
- 《日本語での特別な意味》ほし。つ点。づめぼし。ねらった点。「図星」てねらいをつけた容疑者。「星をあげる」。
字通
[形声]声符は生(せい)。正字は晶に従い、曐に作り、晶は星光の象。〔説文〕七上に「萬物の精、上りて列星と爲る」という。參(参)(しん)は簪(かんざし)の形で、その初形は晶の形を含み、簪の玉光を示す形であった。
政(セイ・9画)


甲骨文/蔡侯紐鐘・春秋晚期
初出:初出は甲骨文。
字形:甲骨文の字形は「足」+「丨」”筋道”+「又」”手”。人の行き来する道を制限するさま。現行字体の初出は西周早期の金文で、「正」+「攴」。「正」はさらに「一」”目標線”+「足」に分解でき、「攴」はさらに”筆”と「又」に分解できる。全体で目標を定めいきさつを記すさま。原義は”兵站の管理”。
音:カールグレン上古音はȶi̯ĕŋ(去)。
用例:上掲『甲骨文合集』14499の字形は破損がひどくて判読できない。
西周早期の「𤼈鐘」(殷周金文集成00251)に「曰古文王,初盭龢于政」とあり、「盭龢」の意味は不明(やわらぎにもどる/のっとる?)だが「政」に”せいじ”の意が確認できる。
備考:「漢語多功能字庫」は「丨」を武器と解し、「征」が原義と言い、のち政治の意になったという。金文では”征伐”(虢季子白盤・西周)、”政治”を意味し(王孫遺者鐘・春秋)、また戦国時代に”徴収”(鄂君啟舟節・戦国)を意味したという。
論語語釈「正」も参照。定州竹簡論語では「正」と記し、理由は恐らく秦の始皇帝のいみ名を避けたため(避諱)。『史記』で項羽を本紀に記し、正式の中華皇帝として扱ったのと理由は同じで、前漢の認識では漢帝国は秦帝国に反乱を起こして取って代わったのではなく、正統な後継者と位置づけていた。
学研漢和大字典
会意兼形声文字で、正とは、止(あし)が目標線の━印に向けてまっすぐ進むさまを示す会意文字。征(セイ)(まっすぐ進む)の原字。政は「攴(動詞の記号)+(音符)正」で、もと、まっすぐに整えること。のち、社会を整えるすべての仕事のこと。
正・整(セイ)と同系のことば、という。
語義
- {名詞}まつりごと。社会生活をただしくとりしきる仕事。▽「まつりごと」の訓は、祭りが社会統制のための行事であった日本古代の祭政一致の意識を伝えている。「政治」「任政=政に任ず」「為政者(政をなす者)」「必聞其政=必ず其の政を聞く」〔論語・学而〕
- {動詞}ただす。ただしくする。《類義語》正。「呈政(テイセイ)(著書を他人に贈呈してただしてもらう)」。
- {名詞}物事を行うときの一定の決まりや、やり方。「家政(家を管理する仕事と、そのとりしきり方)」「塩政(塩の専売に関する仕事)」。
- {名詞}公務の責任者。「学政(清(シン)代の学務の長官)」「主政(主任)」。
字通
声符は正。正は他邑を征服すること。これに攴撃を加えて、支配する事を政という。〔説文〕三下に「正なり。攴に從ひ、正に從ふ。正は亦聲なり」とする。正は征服、征は征取、政は支配することをいう。金文の〔禹鼎〕に、「井(邢)方を政めよ」、〔毛公鼎〕に「命を敷き政を敷くに𩁹て、小大の楚賦(胥賦・賦税)を![]() めよ」とあり、政治的経済的な支配を意味するが、ときには〔叔夷鎛〕「朕が三軍を政めよ」のように、軍事・軍政にもいう。
めよ」とあり、政治的経済的な支配を意味するが、ときには〔叔夷鎛〕「朕が三軍を政めよ」のように、軍事・軍政にもいう。
訓義
まつりごと、おさめる。つかさどる、ただす。おきて、おきてとする、とりきめ。えたち、征役。正と通じ、まさに、まさしく。征と通じ、うつ。
大漢和辞典
会意形声文字。攴(軽く叩いて注意する)と正の合字。注意を与えて正す義。正しくないものを正す意。正は声を兼ねて形声。
字解
ただす。まつりごと。おきて、行政を行う。政治を行う人。やくめ。えだち、ぶやく、役。教え、道、人の道。人民の生活を支えるもの。つかさどる。星、日月五星。まさに、まさしく。清朝で京察における人物挙用の基準。姓。とりたて。伐つ。
城(セイ・9画)


甲骨文/元年師兌簋・西周晚期
初出:「国学大師」による初出は甲骨文。「小学堂」による初出は西周早期の金文。
字形:「高」”物見櫓”二つ+「○」”城壁”+「成」”カマ状のほこ+斧”で、武装した都市国家のさま。原義は”まち”。
音:「ジョウ」は呉音。カールグレン上古音はȡi̯ĕŋ(平)。
用例:西周早期「班𣪕」(集成4341)に「王令毛白更虢城公服。」とあり、「王毛伯をして虢城を更ぎ公として服えしむ」と読め、”まち”と解せる。
西周末期「元年師兌𣪕」(集成4274)に「用乍皇且城公䵼𣪕。」とあり、人名と解せる。
春秋末期「武城戈」(集成10966)に器名通り「武城戈」とあり、「武城」というまちの名と解せる。
「漢語多功能字庫」によると、戦国の金文では”城壁”(𠫑羌鐘・戦国早期)の意に用いた。
学研漢和大字典
会意兼形声。成は「戈(ほこ)+(音符)丁(うって固める)」の会意兼形声文字で、とんとんたたいて、固める意を含む。城は「土+(音符)成」で、住民全体をまとめて防壁の中に入れるため、土を盛って固めた城のこと。「説文解字」には「城とは民を盛るもの」とある。成・城・盛は同系。
語義
- {名詞}しろ。都市をめぐる城壁。▽中国では、日本とは違い、町全体を城壁でとり巻き、その中に住民をまとめて住まわせる。四方に城門がある。城外の街道沿いに発達した市街地には、さらに郭(外城)をめぐらして、外敵から守る。「城郭」「今雖割六城何益=今六城を割くと雖も何ぞ益せん」〔史記・虞卿〕
- {名詞}城壁で囲まれた町全体。「城市」「城春草木深=城春にして草木深し」〔杜甫・春望〕
- {動詞}きずく(きづく)。城をつくる。「城彼朔方=彼の朔方に城く」〔詩経・小雅・出車〕
- 《日本語での特別な意味》
①しろ。敵を防ぐために土や石で堅固にきずいた大規模な構造物。
②「山城(ヤマシロ)」の略。「城州」。
字通
[形声]声符は成(せい)。成に戍守の意がある。〔説文〕十三下に「以て民を盛(い)るるなり」とし、成を盛れる意とする。〔釈名、釈宮室〕にも「盛なり」とするが、盛はもと粢盛(しせい)(お供え)をいう字であった。成は武器の制作に呪祝を加える意であるから、城とは武装都市をいう。国の初文或(わく)も、城邑の形(囗(ゐ))と戈とに従い、城邑をいう字である。
逝(セイ・10画)

説文解字・後漢
初出:初出は戦国中末期の楚系戦国文字。「小学堂」による初出は後漢の『説文解字』。
字形は「辵」(辶)”ゆく”+「折」”折れる”で、「折」の意味するところは不明。原義は”行く”。”世を去る”の意は派生義。「折」は音符でもあるとされるがdʰi̯ad(平)/ȶi̯at(入)/ȡi̯at(入)と三つの音を持ち、いずれか判断するのは訳者の能力を超える。
音:カールグレン上古音はȡi̯ad(去)。
用例:戦国中末期の「郭店楚簡」老子甲22に「大曰(逝),(逝)曰〔辶叀〕(遠),〔辶叀〕(遠)曰反。」とあり、現伝『老子道徳経』と同じで、”うつろいゆくもの”と解せる。
論語時代の置換候補:日本語音で同音の「𠧟」(廼)。
同音の「忕」”ならう”・「誓」・「筮」”うらなう”・「澨」”つきぢ・みぎわ”には、”いく”の語義が無い。「噬」”およぶ”の初出は同じく『説文解字』。
日本語音で同音の「𠧟」は、カールグレン上古音・藤堂上古音が不明だが、”ゆく”の意があり、甲骨文から存在する。「廼」と釈文され、「甲骨文合集」27791.3に「廼歸」とあることから、”ゆく”の意を確認できる。
また征のカ音はȶi̯ĕŋで、音通するとは言いがたいが、”ゆく”の意があり、甲骨文より存在する。
『大漢和辞典』で音セツ訓ゆくに「𨄊」があり、上古音も初出も不明、『康煕字典』に「倉結切,音妾。行也」という。
備考:「漢語多功能字庫」には見るべき情報がない。
学研漢和大字典
会意兼形声。「辵+(音符)折」。ふっつりと折れるようにいってしまうこと。類義語に死。
語義
{動詞}ゆく。さる。いってしまう。思いきってたち去る。また、ふっつりと死ぬ。「逝者如斯夫=逝く者は斯くの如きかな」〔論語・子罕〕。「騅不逝兮=騅逝かず」〔史記・項羽〕
字通
[形声]声符は折(せつ)。〔説文〕二下に「往くなり」とあり、〔書、大誥〕「昔朕(われ)逝きしとき」、〔詩、小雅、小弁(しょうはん)〕「我が梁(りやう)に逝くこと無(なか)れ」のような古い用例がある。また〔詩〕に「逝(ここ)に」という語詞の用法が多い。のち長逝死去の意に用いる。
栖(セイ・10画)
現行字体の初出は三国時代の隷書。論語の時代に存在しない。「棲」の字体では秦系戦国文字。カールグレン上古音はsiər(平)。同音は論語語釈「洒」を参照。”巣・住む”の意では部品の「西」が通用するが、「西」に”せかせか”の語義は『大漢和辞典』にない。
学研漢和大字典
会意兼形声。西は、ざる状をした、鳥のすを描いた象形文字。栖は「木+(音符)西」で、ざるの形をした木の上の鳥のす。類義語に巣。「生」に書き換えることがある。「生息」▽「ねぐらとして住む」の意味では「棲」とも書く。また、「すみか」は「住処」とも書く。
語義
- {名詞}す。ざる状をした、鳥のすみか。《同義語》⇒棲。
- {動詞}すむ。鳥が、すでいこうように、動物が自分のすみかにすむ。《同義語》⇒棲。「栖息(セイソク)(=棲息)」。
- 「栖栖(セイセイ)」とは、息をはずませて忙しそうなさま。せかせか。▽現代音はx4と読む。《同義語》⇒棲棲。「微生畝謂孔子曰、丘何為是栖栖者与=微生畝孔子に謂ひて曰はく、丘なんすれぞ是く栖栖たるや」〔論語・憲問〕
字通
[形声]声符は西(せい)。〔説文〕十二上に「西は、鳥、巣上に在るなり。象形」とし、その鳥巣の形。樹上に巣のあることを栖という。棲はその形声の字。
大漢和辞典
忙しいさま。棲棲、皇皇、徨徨と同じ。「棲棲」は、車馬を調べるさま。安居しないさま。落ち着かないさま。あくせくするさま。忙しいさま。求める所あるが如くで得ない意。栖栖、徨徨。
祭(セイ・11画)


合36514/史喜鼎・西周
初出:初出は甲骨文。
字形:「月」”肉”+「示」”位牌”+「又」”手”で、位牌に肉を供えるさま。原義は”故人を供養する”
音:「サイ」は呉音。カールグレン上古音はtsi̯adまたはtsăd(共に去)で、「政」ȶi̯ĕŋ(去)や「正」ȶi̯ĕŋ(平/去)とは音が異なる。日本で言う「チンチンドコドン」の”おまつり”ではなく、法事に当たる。
用例:「甲骨文合集」22931.2に「丙戌卜行貞翌丁亥祭于祖丁無在九月」とあり、”祖先の祭祀”と解せる。春秋末期までの金文も同様。
学研漢和大字典
会意。「肉+又(手)+示(祭壇)」。肉のけがれを清めて供えることをあらわす。擦(よごれをこすりとる)・察(よごれをとってよく見る)などと同系。類義語の祀(シ)は、つつしんで人為をこらし、神のきげんをうかがうこと。
語義
- {動詞}まつる。供え物や祭壇を清める儀式を行い、神霊をまつる。《類義語》祀(シ)。「祭礼」「王祭不共(オウサイフキョウ)(王室が衰え、王の祭りに供え物が欠ける)」〔春秋左氏伝・僖四〕。「祭之以礼=これを祭るに礼を以てす」〔論語・為政〕
- {名詞}まつり。神霊をまつる儀式。《類義語》祀(シ)。「祭祀(サイシ)」「俶祭(テイサイ)(年末の大祭)」。
- 《日本語での特別な意味》まつり。神社のまつり。また、転じて、記念の行事。「記念祭」。
字通
[会意]肉+又(ゆう)+示。示は祭卓の象。その上に牲肉を供えて祭る。〔説文〕一上に「祭祀なり」とあり、祀とは巳(蛇)の形に従う字で、自然物を祀ることをいう。
→祀
[形声]声符は巳(し)。巳は蛇の形。自然神を祀ることを祀という。〔説文〕一上に「祭りて已(や)むこと無きなり」とし、旁(つくり)を「已む」と解するが、卜文・金文の字形は巳に従う。〔周礼、春官、司服〕「群小祀を祭る」の〔注〕に「林澤(りんたく)墳衍(ふんえん)(丘)、四方百物の屬なり」とあり、すべて地物を祀ることをいう。重文として録する禩は異に従う。異は鬼の正面形で、その尸坐する形。百物の怪異を祀る意である。蛇はわが国でも夜刀(やと)の神といい、渓谷を支配する神とされた。祀を年歳の意に用いるのは、殷の祖祭の体系で周祭五祀とよばれるものが、終始一巡するのにあたかも一年を要するので、その一巡するを一祀・二祀と数えたからである。もと自然神を祀る意の祀が、そのころには祖祭をよぶのに用いられた。祭祀という祭の字は、示(祭壇)に肉を薦める形で、祭儀の形式をいう字である。
淸/清(セイ・11画)

者減鐘・春秋早期
初出:初出は春秋早期の金文。
字形:新字体は「清」で、中国・台湾・香港ではこちらのコードが正字体として扱われている。字形は「氵」+「青」で、青く澄み切った綺麗な水のさま。
音:「シン」は唐音=宋代以降の発音。カールグレン上古音はtsʰi̯ĕŋ(平)。
用例:春秋早期「奠義白𦉢」(集成9973)に「我酉(酒)既清」とあり、”濁りが取れて澄んだ”と解せる。
「漢語多功能字庫」によると、金文での語義は不詳で、戦国の竹簡では酒が”すっきりとしてコクがある”、”静か”の意に用いた。
学研漢和大字典
会意兼形声。青(セイ)は「生(芽ばえ)+井戸の中に清水のある姿」からなり、きよくすんだことを示す。清は「水+(音符)青」で、きよらかにすんだ水のこと。▽呉音のショウは、六根清浄(ショウジョウ)や清水(ショウズ)のような特殊な場合にしか用いない。浄(きよい)・精(すんだ米)・晴(すみきった日)・睛(セイ)(すみきった目)・晶(すみきった光)などと同系。類義語の澄は、水面にのぼったうわずみのこと。潔は、さっぱりして欲がないこと。付表では、「清水」を「しみず」と読む。
語義
- {動詞}すてる(すつ)。ふりすてる。思いきりよくすてさる。《類義語》捨。「放棄」「棄甲曳兵而走=甲を棄て兵を曳いて走る」〔孟子・梁上〕
字通
[形声]声符は青(せい)。〔説文〕十一上に「朖(あき)らかなり」とあり、清朗の意とし、また「澂(す)みたる水の皃なり」と清澄の意とする。澂は澂澈(ちょうてつ)、澄みきった水をいう。
濟/済(セイ・11画)

石鼓文.霝雨
初出:初出は春秋末期の石鼓文。
字形:「氵」+「齊」で、原義は河の名。
音:カールグレン上古音はtsiər(上)
用例:石鼓文の文字列はネット上で公開が無いため不明。
「清華大学蔵戦国竹簡」清華二・繫年112に「述(遂)以伐齊=(齊,齊)人(焉)(始)爲長城於濟」とあり、原義の河の名と解せる。
「上海博物館蔵戦国楚竹簡」孔子詩論06、戦国末期「中山王方壺」(集成9735)に「濟濟」とあり、”数多く揃って立派なさま”と『学研漢和大字典』は語釈する。
「上海博物館蔵戦国楚竹簡」容成31に「淒(濟)於(廣)川」とあり、河を”渡る”・”渡す”と解せる。
論語では雍也篇30のみに用い、”救う”の意とされる。
情(セイ・11画)

「郭店楚簡」語2.1・戦国楚
初出:初出は楚系戦国文字。
字形:「靑」(青)+「心」。澄み切った心、誠実や情け深さ。
音:「ジョウ」は呉音。カールグレン上古音は不明。
用例:戦国の竹簡「上海博物館蔵戦国楚竹簡」孔子詩論18に「則情憙(喜)丌(其)至也」とあり、”心”と解せる。
論語時代の置換候補:存在しない。『大漢和辞典』で同音同訓の字に、春秋末期以前に遡れ、かつ”こころ”の意を持つ漢字は無い。近音同訓に「狀」(状)dʐʰi̯aŋ(去)があるが、初出は秦系戦国文字。論語語釈「状」を参照。
盛(セイ・11画)
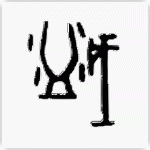

後2.24.3/殳季良父壺・西周末期
初出:初出は甲骨文。「小学堂」による初出は西周末期の金文。
字形:甲骨文の字形は「水」+「皿」+「戈」”カマ状のほこ”。犠牲をほふって血を皿に満たすさま。殷代の風習は血祭りを好んだので、転じて”高調した祭の雰囲気”の意。金文以降では「水」が省かれ、さらに「阝」”はしご”→”天界とやりとりする通路”が書き加えられた。
音:カールグレン上古音はȡi̯ĕŋ(平)。
用例:西周中期「師湯父鼎」(集成2780)に「王乎宰雁易盛弓」とあり、”力が強い”と解せる。
西周末期「史免簠」(集成4579)に「從王征行,用盛□(稻)□(粱)」とあり、”新たに実った”と解せる。
学研漢和大字典
会意兼形声。丁は、たんたんとたたくことをあらわし、打の原字。成は「戊(ほこ)+(音符)丁(テイ)」からなり、四方から土をもりあげたんたんとたたいて城壁をつくることを示す。城(ジョウ)・(セイ)(土を盛った城壁)の原字。盛は「皿(さら)+(音符)成」で、容器の中に山もりにもりあげること。類義語の昌は、明るくさかんなこと。隆は、高くたちのぼってさかんなこと。熾(シ)は、あかあかと目だってさかんなこと。壮は、元気よく強そうなこと。
語義
- {動詞}もる。四方からつみあげて△型にまとめあげる。山もりにする。「盛於盆=盆に盛る」〔礼記・礼器〕
- {名詞}器に山もりにいれたもの。「粢盛(シセイ)(穀物をもったお供え)」。
- {形容詞・動詞・名詞}さかん。さかる。さかんにする(さかんにす)。さかり。力や勢いがたっぷりあるさま。力や勢いがもりあがっているさま。力や勢いが充実する。また、充実させる。また、その状態。▽去声に読む。《対語》⇒衰(おとろえる)。《類義語》昌・隆。「盛大」「茂盛(さかんにしげる)」「盛服(はれ着)」「盛徳之至也=盛徳之至り也」〔孟子・尽下〕
- 《日本語での特別な意味》
①もる。薬を調合して紙や皿にのせる。土をもりあげる。「毒を盛る」「土を盛る」。
②もり。もりあげた量。「盛りがよい」。
③さかり。さかんにあらわれ出る時。「花盛り」。
④さかり。動物が交尾しようとする衝動。「盛りがつく」。
字通
[形声]声符は成(せい)。〔説文〕五上に「黍稷(しよしよく)、器中に在り。以て祀る者なり」とあり、黍稷を盛る意とする。金文の〔史免簠(しめんほ)〕の銘文に「用(もつ)て稻粱を盛(い)る」とあり、その供薦するところを粢盛(しせい)という。〔左伝、哀十三年〕に「旨酒一盛」とあって、酒にもいう。簠には大型の器もあり、多く供えて祀るので、盛多・豊盛の意となる。また尊称として盛意・盛旨など、相手の行為につけていう。
細(セイ・11画)

睡.日乙57(隸)・戦国最末期
初出:初出は秦系戦国文字。
字形:「糸」+「由」。後漢の『説文解字』でも、つくりが「由」になっている。字形の由来は不明。
音:カールグレン上古音は不明。藤堂上古音はser(去)。「サイ」は呉音。王力上古音はsiei(去)、同音無し。董同龢上古音はsiei、同音に「西」「棲」「犀」。周法高上古音はser、同音に董同龢+「洗」「栖」「洒」「𣳦」”川の名”。李方桂上古音はsidh、同音は「𣳦」のみ。
用例:秦系戦国文字の用例は破損がひどく、しかも占いの部分なので何を言っているか分からない。
文献上の初出は論語郷党篇8。『墨子』『荘子』『荀子』にも用例がある。
論語時代の置換候補:『大漢和辞典』の同音、訓「かすか」に「精」(初出楚系戦国文字)、「ちいさい」に「癠」(初出不明)「笙」(初出楚系戦国文字)、「ほそい」に「笙」。
学研漢和大字典
会意兼形声。囟は、小児の頭にある小さいすきまの泉門を描いた象形文字。細は「糸(ほそい)+(音符)囟(シン)・(セイ)」で、小さくこまかく分離していること。先(小さく分離した足さき)・洗(水をほそく分離して流す)・私(小さくわける)・汚(シ)(息が小さくわかれて出る)などと同系。セン(sen)とセイ(ser→sei)の音は、語尾の転じた形で、もと同系。類義語の繊は、先がほそくて物の中にはいりこむこと。「こまやか」は普通「濃やか」と書く。
語義
- {形容詞}ほそい(ほそし)。《類義語》小。「細小」「細声(こごえ)」「膾不厭細=膾は細きを厭はず」〔論語・郷党〕
- {形容詞・名詞}こまかい(こまかし)。こまごましたさま。また、小さい事がら。《対語》粗・略。《類義語》些(サ)。「細密」「詳細」。
- 《俗語》「細作」「奸細(カンサイ)」とは、スパイのこと。
- 《日本語での特別な意味》ささ。名詞について、小さい、かわいらしいの意味をあらわすことば。
字通
[形声]正字は囟(し)に従い、囟声。のち略して田となった。〔説文〕十三上に「𢼸(び)なり」(段注本)と訓し、囟声とする。囟は細かい網目の形。もと織り目の細かいことをいう字であったが、のち細微・微賤の意となる。
※𢼸=微。段注本でなければ元からそう書いてある。
晶(セイ・12画)

合31182
初出:初出は甲骨文。
字形:三つ星の象形。論語語釈「星」を参照。
音:カールグレン上古音はtsi̯ĕŋ(平)。「ショウ」は呉音。
用例:「甲骨文合集」11503に「㞢(有)新大晶(星)並火」とあり、”ほし”と解せる。
西周中期「媯壺」(集成9555)に「媯乍寶壺。」とあり、人名の一部「」の部品として用いられ、語義は明瞭でない。
戦国の竹簡では、易文に「三」のもったいを付けるために「晶」と記した例が多数ある。また「参」と釈文される例もある。
学研漢和大字典
象形。晶は、星が三つ光るさまを描いたもの。澄みきった意を含む。星(澄みきって光るほし)・晴(澄んだ空)・清(澄んだ水)などと同系。類義語の昌(ショウ)は、盛んに明るく光ることで、澄みきったという意は含まない。
語義
- {形容詞}あきらか(あきらかなり)。澄みきって輝いている。きらきらする。《類義語》昌(ショウ)。「晶払(ショウケイ)(きらきら光る)」「天高日晶=天高く日晶かなり」〔欧陽脩・秋声賦〕
- {名詞}「水晶」の略称。きらきら光る鉱石である。
字通
[象形]星の光。三星を以てその晶光を示す。昔の夜空の星は、明るかったのであろう。〔説文〕七上に「精光なり。三日に從ふ」とするが、三日の光というものはありえない。星の卜文・金文は晶に従う形である。また參(参)の卜文・金文の字形も晶に従い、參とは珠玉を飾った簪(かんざし)を髪に刺している婦人の側身形で、珠光を示すために彡(さん)を加える。
聖(セイ・13画)


甲骨文/大克鼎・西周晚期
初出:初出は甲骨文。
字形:甲骨文・金文の段階では、「聞」「聴」と判別しがたい。論語語釈「聞」・論語語釈「聴」を参照。

「聴」(甲骨文)
「漢語多功能字庫」によると、字形は耳の大きな人物+口というが誤り。甲骨文に比定されている字形は「聴」に比定されているものとまったく同じで、「口」+「斧」+「人」。斧は王権の象徴で、殷代の出土品にその例がある。口は臣下の奏上、従って甲骨文の字形が示すのは、臣下の奏上を王が聞いて決済すること。
音:カールグレン上古音はɕi̯ĕŋ(去)。
用例:甲骨文の用例(合集18094)は欠損がひどくて判別できない。
西周早期「班𣪕」(集成4341)に「王(姒)聖孫」とあり、『字通』によると先人への美称”高貴な”という。
西周中期「尹姞鬲」(集成754)に「休天君弗望穆公聖粦明□事先王。」とあり、”人並み優れた者”の意だろうか。
西周末期「乎𣪕」(集成4157)に「用𦔻𡖊(夙)夜」とあり、「𦔻」は「聖」と釈文され、”聞く”と解せる。
春秋早期「上曾大子鼎」(集成2750)に「心聖若(慮),哀哀利錐,用考(孝)用(享)」とあり、”研ぎ澄ます”と解せる。
備考:「耳順」が”天命を素直に聞き入れる”であることから(論語為政篇4)、論語での「聖」は史実の場合、”言語にならない天命を理解し、言語化して人に伝えることの出来る者”を意味する。
論語の時代、甲骨文から引き継ぐ”高貴な”の語感は伴っただろうが、”神聖”ではない。論語でいう「天命」も”自然界の予兆”。おそらく無神論者だったろう孔子は、神秘主義や黒魔術を一切説かなかった。その一方で、自然の猛威をなめてかかる愚か者でもなかった。孔子はなぜ偉大なのかを参照。
学研漢和大字典
会意兼形声。壬(テイ)は、人が足をまっすぐのばしたさま。呈(テイ)は、それに口をそえて、まっすぐ述べる、まっすぐさし出すの意を示す。聖は「耳+(音符)呈」で、耳がまっすぐに通ること。わかりがよい、さといなどの意となる。
語義
- {名詞}ひじり。賢くて、徳のすぐれた人。▽儒家では最高の人格者をいう。《類義語》賢・智。「聖賢」「亜聖(孔子につぐ聖人。孟子のこと)」「必也聖乎=必ず也聖乎」〔論語・雍也〕
- {形容詞}おかしがたくおごそかなさま。「神聖」「聖域」。
- {名詞・形容詞}その道で最高にすぐれた人。この上なくすぐれている。「詩聖」「書聖」。
- {名詞・形容詞}天子*のこと。また、天子に関する事につけることば。「今聖」「聖諭(天子のおおせ)」。
- 《日本語での特別な意味》
①ひじり。すぐれた僧。「日蓮聖人(ニチレンショウニン)」「高野聖(コウヤヒジリ)」。
②キリスト教のすぐれた宣教師の名につけることば。▽英語Saint。「聖フランシスコ」。
*「天子」の言葉が中国語に現れるのは西周早期で、殷の君主は自分から”天の子”などと図々しいことは言わなかった。詳細は論語述而篇34余話「周王朝の図々しさ」を参照。
字通
旧字は![]() に作り、耳+口+壬。〔説文〕十二上に「通なり」と通達の意とし、字を呈声に従うものとするが、字形と合わず、声もまた異なる。卜文に、壬(人の挺立する形)の上に耳をそえた形に作り、聞の初文。神の声を聞きうる人をいう。口(𠙵)は祝禱を収める器の形で、その神の声を聞きうる人を聖という。〔左伝、襄十八年〕に、当時神瞽といわれた師曠が、晋と楚とが戦うにあたって、その勝敗を卜し、風声を聞いて「南風競わず、死声多し」と、楚の敗北を予言した話がある。そのような者が聖者であった。周初の金文〔班𣪘〕に「文王王娰の聖孫」という語がみえ、また金文に「聖なる祖考」や「聖武」「哲聖」など、先人に聖を付していうことが多い。〔詩、小雅、正月〕に「具な予をば聖なりと曰うも、誰か烏の雌雄を知らんや」の句がある。〔論語、述而〕に、孔子は「聖と仁の若きは、則ち吾豈に敢えてせんや」と述べており、聖は人間最高の理想像とされた。
に作り、耳+口+壬。〔説文〕十二上に「通なり」と通達の意とし、字を呈声に従うものとするが、字形と合わず、声もまた異なる。卜文に、壬(人の挺立する形)の上に耳をそえた形に作り、聞の初文。神の声を聞きうる人をいう。口(𠙵)は祝禱を収める器の形で、その神の声を聞きうる人を聖という。〔左伝、襄十八年〕に、当時神瞽といわれた師曠が、晋と楚とが戦うにあたって、その勝敗を卜し、風声を聞いて「南風競わず、死声多し」と、楚の敗北を予言した話がある。そのような者が聖者であった。周初の金文〔班𣪘〕に「文王王娰の聖孫」という語がみえ、また金文に「聖なる祖考」や「聖武」「哲聖」など、先人に聖を付していうことが多い。〔詩、小雅、正月〕に「具な予をば聖なりと曰うも、誰か烏の雌雄を知らんや」の句がある。〔論語、述而〕に、孔子は「聖と仁の若きは、則ち吾豈に敢えてせんや」と述べており、聖は人間最高の理想像とされた。
誠(セイ・13画)


故宮477・戦国秦/「成」獻侯鼎・西周早期
初出:初出は秦系戦国文字。
字形:「言」+「成」。発言が成り立つこと、つまり”事実である”。
音:カールグレン上古音はȡi̯ĕŋ(平)。同音は「成」、「城」、「盛」。
用例:戦国の竹簡「上海博物館蔵戦国楚竹簡」子羔06に「舜之惪(德)則城(誠)善」とあり、「城」は「誠」と釈文され、”事実である”と解せる。
戦国最末期「睡虎地秦簡」封診38に「甲臣,誠悍」とあり、”事実である”と解せる。
論語時代の置換候補:『大漢和辞典』の同音同訓「成」は、春秋末期までに”まこと”の用例が無い。詳細は論語語釈「成」・論語語釈「情」を参照。
学研漢和大字典
会意兼形声。成(セイ)は「戈(ほこ)+(音符)丁(とんとうつ)」からなり、道具でとんとんとうち固めて城壁をつくること。かけめなくまとまるの意を含む。誠は「言+(音符)成」で、かけめない言行。城(かけめなく固めたしろ)・成(かけめなくまとまる)などと同系。類義語に信。「まこと」は「実」「真」とも書く。
語義
- {名詞}まこと。うそのない心。また、ごまかしのない言行。▽訓は「真事(まこと)」の意。《類義語》真。「推誠=誠を推す」「誠者天之道也=誠なる者は天之道也」〔中庸〕
- (セイナリ){形容詞}まこと。かけめやごまかしのない。真実の。「誠心誠意」「誠哉是言也=誠なる哉是の言也」〔論語・子路〕
- {動詞}まことにする(まことにす)。ごまかしのない状態にする。かけめのないものにしあげる。「誠之者人之道也=これを誠にするは人の道なり」〔中庸〕
- {副詞}まことに。→語法「①」
語法
①「まことに」とよみ、「本当に」「いつわりなく」と訳す。「是誠不能也=これ誠に能はざるなり」〈これは本当にできないのです〉〔孟子・梁上〕
②「まことに~ば」「もし~ば」とよみ、「かりに~だとすると」と訳す。強い仮定条件の意を示す。反訓のひとつ。「誠如是則覇業可成、漢室可興矣=誠にかくの如(ごと)くんば則(すなは)ち覇業成る可く、漢室興る可し」〈もしこのようになるならば、天下を平定することもできるし、漢の帝室を復興させることもできる〉〔蜀志・諸葛亮〕
字通
[形声]声符は成(せい)。〔説文〕三上に「信なり」と訓する。〔書、太甲下〕に「鬼神に常享(じゃうきゃう)無し。克(よ)く誠なるものは享(う)く」とあり、誠信・誠実をいう。言は神に対する誓約、成は戈に呪飾を施して聖化したもので、これを加えて、其の意を誠にすることをいう。
歲/歳(セイ・13画)


合32054/公子土折壺・春秋末期
初出:初出は甲骨文。
字形:初出の字形は「戉」”まさかり”で、「越」gi̯wăt/ɡʰwɑt(入)”時間が進む”の意。日本で言う「年越し」とはこの意をよく表している。甲骨文の段階で「夂」”あし”の形を加えて”まさかり”と区別した例がある。旧字体の部品が「𣥂」であるのに対し新字体は「小」で、総画数は同じだが字形は「歳」。
![]()
慶大蔵論語疏では異体字「〔山戌一川〕」と記す。「魏元偃墓誌」刻といい、元偃は北魏の皇族。
音:カールグレン上古音はsi̯wad(去)。「サイ」は呉音。
用例:「甲骨文合集」9659.2に「來歲不其受年」とあり、”とし”と解せる。
備考:木星を歳星と呼ぶのは、黄道(星座を固定した背景と考えた場合の天球上を1年かけて太陽が進む軌道)に沿って約12年で天球を一周することから、暦上での1年の基準とされたため。同様の天文学がバビロニアにもあったとwikはいう。
学研漢和大字典
会意。「戉(エツ)(刃物)+歩(としのあゆみ)」で手鎌の刃で作物の穂を刈りとるまでの時間の流れを示す。太古には種まきから収穫までの期間をあらわし、のち一年の意となった。穂(スイ)(作物のほがみのる)と縁が近い。もと、サイのほかに、カイ(クワイ)という音もあった。年は稔(ネン)と近く、作物の実がねばりをもって成熟するまでの期間。殷(イン)代には、一年のことを一祀といった。付表では、「二十・二十歳」を「はたち」と読む。▽年齢を表すとき、俗に「歳」の代わりに「才」を用いることがある。
語義
- {名詞}とし。よわい(よはひ)。一年。また、としつき。年齢。《類義語》年・載(サイ)・祀(シ)。「歳暮」「歳月不待人=歳月人を待たず」〔陶潜・雑詩〕
- {名詞}そのとしの作物のみのり。作柄。また、豊作。《類義語》年(ネン)。「歳凶=歳凶なり」〔礼記・曲礼下〕
- {名詞}その時の運勢。としまわり。「歳、不我与=歳、我にくみせず」〔論語・陽貨〕
- {副詞}としごとに。毎年。一年について。「歳一見=歳ごとに一たび見る」。
- {名詞}木星のこと。▽木星は、ほぼ十二年で太陽を一周するので、これを「歳星」といい、略して「歳」という。昔は歳星の位置を天文測量のたいせつな目じるしとした。「歳在鶉火=歳は鶉火に在り」〔春秋左氏伝・昭八〕
- {単位詞}としや年齢を数えるときのことば。
字通
[会意]字の初形は犠牲を割く戉(えつ)(鉞(まさかり))の形。のちその刃部に步(歩)を大小に分けてしるし、歲の字形となった。従って今の字形は、戉+步。〔説文〕二上に「木星なり」とし、步に従って戌(じゆつ)声とするが、戌に従う字ではない。卜文に祭名として戉の字がみえ、のち歲の字形を用いる。戉は犠牲を宰割する意であろう。〔書、洛誥〕に「王、新邑に在りて烝・祭・歲す」とあって、古くは祭名に用いた。金文の〔毛公鼎〕に「用(もつ)て歲し、用て政(征)せよ」とあるのも祭祀の意。また卜辞や〔舀鼎(こつてい)〕に「來歲」、斉器の〔国差𦉜(こくさたん)〕に「國差、立事(事に涖(のぞ)む)の歲」のように、年歳の意とする。おそらく歳祭は、年に一度の大祭であったのであろう。木星を歳星といい、古い暦術と関係が深いが、歳星の知識は戦国期以後にみえる。
腥(セイ・13画)

説文解字・後漢
初出:初出は後漢の説文解字。それ以前、戦国最末期「睡虎地秦簡」日甲53背參に「星」を「腥」と釈文し”なまぐさい”と解せる例はあるが、”なまにく”の意ではない。
字形:「月」”にく”+音符「星」sieŋ(平)。「星」の初出は甲骨文。論語語釈「星」を参照。「星」の近音に「生」sĕŋ(平)があり、全体で”なまにく”の意。論語語釈「生」を参照。
音:カールグレン上古音はsieŋ(平)。同音は「星」「醒」「猩」。
用例:文献上の初出は論語郷党篇14。『列子』『荀子』『韓非子』にも用例がある。
論語時代の置換候補:『大漢和辞典』の同音同訓に「胜」(初出前漢隷書)。部品の「星」を「腥」の意で使った初出は戦国最末期。上古音の同音に語義を共有する漢字は無い。
学研漢和大字典
会意兼形声。「肉+(音符)星(ちかちか光るほし、刺激がするどい)」。醒(セイ)(つんと刺激されてさめる)と同系。「なまぐさ」「なまぐさい」は「生臭」「生臭い」とも書く。
語義
- {名詞・形容詞}なまぐさい(なまぐさし)。なま肉や脂肪の、つんと鼻にくるにおい。また、そのようなにおいがするさま。「高原水出山河改、戦地風来草木腥=高原水出でて山河改まり、戦地風来たりて草木腥し」〔元好問・壬辰十二月〕
- {名詞}においがつんと鼻にくるなま肉。「君賜腥、必熟而薦之=君腥を賜へば、必ず熟してこれを薦む」〔論語・郷党〕
字通
[形声]声符は星(せい)。〔説文〕四下に「星の見(あら)はるる食豕(しよくし)なり。肉中をして小息肉を生ぜしむるなり。肉星に從ひ、星は亦聲なり」とあり、小息肉とは小さなつき肉をいう。〔周礼、天官、庖人〕に「膏腥(かうせい)を膳す」とあり、脂肪の多い生肉をいい、臭気の強いものである。〔書、酒誥〕に「腥聞、上に在り」のように、古くから腥臭の意に用いる。しもふり肉は、星に従うことからの転義であろう。
靜/静(セイ・14画)
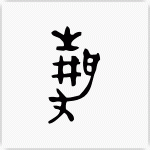
靜卣・西周早期
初出:初出は西周早期の金文。
字形:”苗”+「井」+「爭」”大ガマで草を刈る”で、畑を耕すさま。字形から来る原義は不詳だが、おそらく”穏やかに耕作する暮らし”。
音:カールグレン上古音はdzʰi̯ĕŋ(上)。
用例:「漢語多功能字庫」によると、金文では人名に用いたほか、”平定する”(班簋・西周早期)、”安静”(師訇簋・西周末期)の意に用いた。
学研漢和大字典
会意兼形声。「爭(とりあい)+(音符)靑」。靑(=青)は、すみきった意を含み、とりあいをやめて、しんとすみわたった雑音のない状態になること。清(すみわたる)・靖(セイ)(しずまる)と同系。類義語の閑(カン)はなにもしないであいまがあくこと。異字同訓に鎮まる・鎮める「内乱が鎮まる。反乱を鎮める。痛みを鎮める」 沈める「船を沈める」。旧字「靜」は人名漢字として使える。
語義
- {形容詞・動詞}しずか(しづかなり)。しずめる(しづむ)。しずまる(しづまる)。しんとすみわたった。雑音や動きがなくしずまりかえったさま。しんとする。動かない。《対語》⇒動・噪(ソウ)(さわがしい)・乱。「安静」「静寂」「鎮静」。
- {名詞・形容詞}からだや心を動かさないこと。また、そのさま。▽禅宗では、さとりに入る静坐(セイザ)を重んじ、宋(ソウ)学では主静(心を散らさないことを重んじる)の説をとなえた。「静止」。
- {名詞}しずけさ。動かない状態。しずかな所。「処静=静に処る」。
字通
[会意]旧字は靜に作り、靑(青)+爭(争)。靑は青丹、爭は力(耒耜(らいし)の形。すき)を上下よりもつ形。争奪の爭とは同じでない。耜(すき)を清めて虫害を祓う儀礼。〔説文〕五下に「審らかにするなり」、〔繋伝〕に「丹靑明審するなり」と采色を施す意とするが、耜を修祓する儀礼。これによって耕作の寧静をうることができるとされたのであろう。周初の金文〔班𣪘(はんき)〕に「東或(国)を靜(やす)んず」、後期の〔毛公鼎(もうこうてい)〕に「大いに從(みだ)れて靜(やす)らかならず」とみえ、寧静の意に用いる。本来は農耕儀礼として農器を修祓する儀礼であった。粢盛(しせい)の清らかなことを〔詩、大雅、既酔〕に、「籩豆(へんとう)靜嘉」といい、嘉も字形中に力(すき)の形を含み、鼓声を加え、祝禱して祓う農耕儀礼をいう字であった。静嘉と合わせて、粢盛の明潔の意とする。竫(せい)・靖(せい)・瀞(せい)には通用の義がある。斉器の〔国差■(缶+詹)(こくさたん)〕に「用(もつ)て旨酒を實(みた)さん。旨(うま)からしめ靜(きよ)からしめん」とあるのは、瀞の意である。
際(セイ・14画)
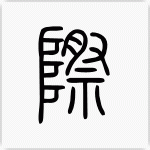
説文解字・後漢
初出:初出は前漢中期の定州竹簡論語。「小学堂」による初出は後漢の『説文解字』。
字形:「阝」”はしご”+「祭」で、天の祭りに天との通信路を開くこと。原義は”その時”。
音:カールグレン上古音はtsi̯ad(去)。同音に「祭」、「穄」”くろきび”。「サイ」は呉音。
用例:論語泰伯編20で「唐虞之際」とあり、”とき”と解せる。
論語時代の置換候補:『大漢和辞典』に同音同訓は存在しない。部品の「祭」(カ音tsi̯adまたはtsăd)に”その時”の語釈は『大漢和辞典』に無い。
学研漢和大字典
会意兼形声文字。祭は「肉+手+示(まつり)」からなる会意文字で、お供えの肉をこすってよごれをとることを示す。こすりあわせるの意を含む。際は「阜(かべ)+(音符)祭」で、壁と壁とがこすりあうように、すれすれに接することをあらわす。察(サツ)(こすってよごれをとって見る)・擦(こすってよごれをとる)などと同系。また、搓(サ)(こする)・拶(サツ)(こする、もみあう)などとも縁が近い
語義
- (サイス){動詞・名詞}相接してたがいにすれあう。ふれあう。また、他とのふれあいや交わり。「際会」「交際(人と人とがもみあいふれあうこと)」「国際(国どうしがふれあうこと)」「高不可際=高くして際すべからず」〔淮南子・原道〕
- {名詞}きわ(きは)。二つの物がすれすれに接する境め。「水際」「天際(空と地の接するさかいめ)」「秋冬之際(秋と冬の接するさかい)」。
- {名詞}きわ(きは)。他のものとのふれあい方。また、互いの領域の接しぐあい。「分際(他とのふれあいからみた自分の領域)」「実際(物事のふれあい方の実情)」「真際(物事のふれあい方の真相)」。
- {名詞}時勢や変化などとのふれあい方。また、その時の接しぐあい。しおどき。めぐりあわせ。「際遇」「際可之仕(サイカノシ)」〔孟子・万下〕
- 《日本語での特別な意味》とき。また、場合。「この際はとりやめる」。
字通
[会意]𨸏(ふ)+祭(さい)。𨸏は神霊の陟降する神梯。そこに祭卓をすえて祭る。神と人との相接するところ、いわゆる神人の際である。〔説文〕十四下に「壁の會なり」と壁間の空隙の意とするが、際は人の至りうる極限のところで、〔淮南子、原道訓〕「高くして際(いた)るべからず」のようにいう。際会・際限のように用いる。金輪際とは、地底の果てをいう。
精/精(セイ・14画)

郭.緇.39・戦国
初出:初出は楚系戦国文字。
字形:初出の字形は「米」”穀物”+”石臼”+「口」。戦国最末期の秦系戦国文字からは、「米」+「青」”透き通った”。中国・台湾では「精」がコードの上の正字として扱われている。
音:カールグレン上古音はtsi̯ĕŋ(平)。同音に「菁」”ニラの花”、「晶」”ひかり”、「旌」”はた”。
用例:戦国「上海博物館蔵戦国楚竹簡」慎子1に「精灋(以)巽□(藝)。」とあり、”くわしい”と解せる。出土した楚系戦国文字はおおむね”くわしい”の意。
戦国最末期「睡虎地秦簡」為吏2壹に「必精絜正,」とあり、”きよい”と解せる。
論語時代の置換候補:『大漢和辞典』に「しらげよね」の訓で同音は無い。
同音の「晶」に水晶という如く鉱物結晶の意があり、「精に通ず」と大漢和辞典は語釈を立てている。晶は甲骨文から存在する。ただし”搗いた穀物”・”くわしい”の用例が春秋以前に確認できない。論語語釈「晶」を参照。
学研漢和大字典
会意兼形声。青(セイ)は「生(はえたばかりの芽)+丼(井戸にたまった清い水)」の会意文字で、よごれなく澄んだ色をあらわす。精は「米+(音符)青」で、よごれなく精白した米。清(すみきった)・靜(セイ)(=静。しんとすみきった)・睛(セイ)(すんだひとみ)・晴(すみきった空)などと同系。
語義
- {名詞}きれいについて白くした米。▽粗・喞(ソウ)(玄米)に対する。「精米」「食不厭精=食は精を厭かず」〔論語・郷党〕▽この用例は、「精を厭(イト)はず」と読み、「精白するほどよい」とする説もある。
- {名詞}よごれやまじりけをとり去って残ったエキス。「酒精(アルコール)」「精髄」。
- {名詞}こころ。人間のエキスであるこころ。「精気」「励精(心をはげます)」「精神」「精、交接以来往兮=精、交接して以て来往す兮」〔宋玉・神女賦〕
- {名詞}もののけ。山川にひそむ神。「精霊」「山精水怪(山の精と、海のばけもの)」。
- {名詞}男性のエキスである液。「精液」「遺精」「精子」「男女構精、万物化生=男女精を構せて、万物化生す」〔易経・壓辞下〕
- {形容詞}よごれがなく澄みきっている。「精白」「精良」。
- {形容詞}くわしい(くはし)。手がゆきとどいていてきれいなさま。また、巧みですぐれているさま。《対語》⇒粗(あらい)・雑。「精巧」「精兵」「精明強幹(ゆきとどいて、やり手である)」「尤精書法=尤も書法に精し」「精義入神、以致用也=義を精しうして神に入るは、以て用を致すなり」〔易経・壓辞下〕
- {形容詞}雑念をまじえず、それひと筋であるさま。《類義語》専。「専精」「精進(ショウジン)」「心意不精=心意精ならず」。
- {形容詞}《俗語》きれいさっぱり。「精光」。
- {名詞}すみきった光。▽晶に当てた用法。「五精(五つのすみきった星)」「水精(=水晶)」。
- {名詞}澄んだひとみ。▽睛(セイ)に当てた用法。「目精(ひとみ)」。
字通
[形声]声符は靑(青)(せい)。〔説文〕七上に「擇ぶなり」とあり、米を択ぶ意とする。〔論語、郷党〕に「食(し)は精を厭(いと)はず」とあり、また〔山海経、中山経〕に「糈(しよ)(供米)には五種の精を用ふ」とあって、糈とは神に供えるため、しらげた穀米をいう。のちすべて精美・精良のものをいい、精神をもいう。
請(セイ・15画)

中山王壺・戦国末期
初出:初出は上掲戦国末期の金文。ごんべんを伴わない「靑」(青)の初出は殷代末期の金文。
字形:「言」+「青」で、「青」tsʰieŋ(平)はさらに「生」+「丹」(古代では青色を意味した)に分解できる。「青」は草木の生長する様で、また青色を意味した。「請」では音符としての役割のみを持つ。
音:また音には平声(カールグレン上古音dzʰi̯ĕŋ:うける)と去声(tsʰi̯ĕŋ:もとめる)の二系統がある。
用例:ごんべんを伴わないが、西周中期「新收殷周青銅器銘文暨器影彙編」NA0067に「隹(唯)四月既生霸戊申,匍即于氐,青公吏(使)𤔲(司)史(使)艮曾(贈)匍于柬」とあり、「請」である可能性がある。
ごんべんを伴わない初出の一つに「上海博物館蔵戦国楚竹簡」容成03があり、「思役百官而月青(請)之。」とあり、”乞う”と解せる。
ごんべんを伴った初出の一つに「上海博物館蔵戦国楚竹簡」用曰15があり、「請命之所●」とあり、”乞う”と解せる。
「漢語多功能字庫」によると、戦国の金文では”安定・鎮撫”の意に用いた。
論語時代の置換候補:『学研漢和大字典』に以下の通り言う。
従って論語の時代には「靑」(青)と書いた可能性があり、こちらは論語時代の金文が存在する。
平声の同音に靜(静)の字がある。『大漢和辞典』によるその語釈に”はかる”があり、四声を無視すれば音通する。
また同音に情の字があって、”こころ・意欲”の意があり、音通するが、戦国文字までしか遡れない。後者の同音は清と凊”つめたい”で、意味上からは置換候補にならない。
学研漢和大字典
会意兼形声。青(セイ)とは「生(あお草)+丼(井戸の清水)」をあわせた会意文字で、あおく澄んでいること。請は「言+(音符)青」で、澄んだ目をまともに向けて、応対すること。心から相手に対するの意から、まじめにたのむの意となった。類義語の乞は、物ごいをすること。
語義
セイ/シン(上声)
- {動詞・名詞}こう(こふ)。まともに目を向けて相手にお願いする。心からたのむ。たのみごと。《類義語》乞(キツ)。「懇請」「請託」「請益=益さんことを請ふ」〔論語・雍也〕
- {動詞}こう(こふ)。上役や君主にお願いする。「請示(指示を願う)」「請罪=罪を請ふ」。
- {動詞}こう(こふ)。→語法「①」。
- {動詞}まともに接待する。また、目上の人に心をこめておめにかかる。《同義語》腟。「請安(心からごきげんをうかがう)」「召請(まねいて、たいせつにもてなす)」。
- 「普請(フシン)」とは、寺社をたてるため、あまねく寄附をこうこと。
セイ/ジョウ(平声)
- {動詞}もらいうける。「勧請(カンジョウ)(寺社で寄附をもらいうけること)」。
- 《日本語での特別な意味》うける(うく)。うけとる。また、引きうける。「請け合う」「請負(ウケオイ)」。
字通
形声・声符は青。〔説文〕三上に「謁するなり」とあり、入謁することをいう。情と通用することがあり、〔荀子、成相〕「其の請を明らかにす」〔史記、礼書〕「請文倶に尽くす」の例がある。
騂(セイ・17画)



甲骨文/者減鐘・春秋/「康煕図」篆書
初出:初出は甲骨文。
字形:初出の字形は![]() (上下に羊+牛)で、篆書の段階でへんとして「馬」が加わり、さらに前漢の隷書からつくりが「辛」に変わって現行書体となる。原義は”犠牲獣”。「辛」字は刑罰に関する字に多く出ることから、「馬」+「辛」は馬を犠牲にして屠ることを意味する。春秋以前は馬を犠牲にして祀る例が羊や牛より少なかった事を物語る。
(上下に羊+牛)で、篆書の段階でへんとして「馬」が加わり、さらに前漢の隷書からつくりが「辛」に変わって現行書体となる。原義は”犠牲獣”。「辛」字は刑罰に関する字に多く出ることから、「馬」+「辛」は馬を犠牲にして屠ることを意味する。春秋以前は馬を犠牲にして祀る例が羊や牛より少なかった事を物語る。
西周早期「新收殷周青銅器銘文暨器影彙編」NA1439に「亢」を「騂」と釈文した例を除き、戦国時代まで一貫して字形は「羊」+「牛」。
音:カールグレン上古音はsi̯ĕŋ(平)。なお犠牲の「牲」はsĕŋ(平)。

用例:「漢語多功能字庫」は「甲骨文合集」1552に存在すると言うが、元画像は上掲の通りで、ここからどうやって判読したのか判然としない。「先秦甲金文簡牘詞彙資料庫」では、「巳卜爭來甲子侑于祖豕」と釈文し、「国学大師」では「□子(巳)卜,爭*〔鼎(貞)〕:來甲子㞢于且(祖)乙。」と釈文しており、「騂」の字は出てこない。

上掲西周中期「大𣪕」(集成4165)に「王在奠。蔑大𤯍。易苑![]() (騂)犅。」とあり、”あかうま”か”あかうし”か判別しがたい。そもそも、”あか”であるとは限らない。「犅」は”牡牛”。”王の御苑にいた犠牲用の牡牛を賜った”と解するべきではないか?
(騂)犅。」とあり、”あかうま”か”あかうし”か判別しがたい。そもそも、”あか”であるとは限らない。「犅」は”牡牛”。”王の御苑にいた犠牲用の牡牛を賜った”と解するべきではないか?
春秋早期「者減鐘」(集成196)に「自乍鐘、不帛(白)不![]() (騂)」とあり、ここから「騂」を”あかい”と読むことになった。なお論語雍也篇での例を”あかい”と解したのは古注による。
(騂)」とあり、ここから「騂」を”あかい”と読むことになった。なお論語雍也篇での例を”あかい”と解したのは古注による。
註犁雜文也騂赤色也(『論語集解義疏』)
「漢語多功能字庫」によると、甲骨文では原義に用い、金文では”赤い犠牲獣”(大簋・西周中期)、”赤い”(者減鐘・春秋末期)の意に用いた。
学研漢和大字典
形声。「馬+(音符)辛(シン)」。あるいは、辛(刃物で切る)と同系で、切った血のようにあかい意か。
語義
- {名詞}あかうま。やや黄色がかったあかい毛色の馬。
- {形容詞・動詞}あかい(あかし)。あかい。また、あかくする。「騂顔(セイガン)」「渉筆騂我顔=渉筆我が顔を薹うす」〔陸游・秋興〕
- {名詞}いけにえにする、あかい毛色の牛。
- 「薹薹(セイセイ)」とは、弓の調子のよいさま。「騂騂角弓、翩其反矣=騂騂たる角弓は、翩として其れ反す矣」〔詩経・小雅・角弓〕
字通
[形声]もと𩥍に作り、声符は![]() (せい)。卜文にその字がある。赤黄色の馬、また牛をいう。〔説文新附〕十上に「馬の赤色なるものなり」とあり、犠牲に用いた。〔論語、雍也〕に「犂(り)牛(雑毛の耕牛)の子も、騂(あか)くして且つ角あらば、用ふること勿(なか)らんと欲すと雖も、山川(の神)其れ諸(こ)れを舍(す)てんや」とみえる。
(せい)。卜文にその字がある。赤黄色の馬、また牛をいう。〔説文新附〕十上に「馬の赤色なるものなり」とあり、犠牲に用いた。〔論語、雍也〕に「犂(り)牛(雑毛の耕牛)の子も、騂(あか)くして且つ角あらば、用ふること勿(なか)らんと欲すと雖も、山川(の神)其れ諸(こ)れを舍(す)てんや」とみえる。




コメント