論語:原文・書き下し
原文(唐開成石経)
子曰吾十有五而志于學卅而立四十而不惑五十而知天命六十而耳順七十而從心所欲不踰矩
※「踰」字のつくりは「俞」。〔亼月刂〕で、「兪」〔亼月巜〕ではない。
校訂
東洋文庫蔵清家本
子曰吾十有五而志乎學三十而立/四十而不惑/五十而知天命/六十而耳順/七十而縱心所欲不踰矩
後漢熹平石経
…乎學卅…
定州竹簡論語
……[吾十]有五而志乎a學,卅b而立,卌c而不惑,五十而4……而耳順,七十而5……
- 乎、阮本作「于」、皇本作「於」、漢石経、高麗本均作「乎」。
- 卅、阮本、皇本作「三十」、漢石経作「卅」。
- 卌、阮本、皇本作「四十」、漢石経作「卌」。
標点文
子曰、「吾十有五而志乎學。卅而立。卌而不惑。五十而知天命。六十而耳順。七十而縱心所欲、不踰矩。」
復元白文(論語時代での表記)






 志
志






 惑
惑 

















 踰
踰
※縱→從・欲→谷。論語の本章は、「志」「惑」「踰」が論語の時代に存在しない。「乎」「矩」の用法に疑問がある。
書き下し
子曰く、吾十有五にし而學乎志す。三十にし而立つ。四十にし而惑は不。五十にし而天命を知る。六十にし而耳順ふ。七十にし而心の欲むる所に縱ふも、矩を踰え不。
論語:現代日本語訳
逐語訳

先生が言った。私は十と五つで学者になろうと決意した。三十で学者として食べていけるようになった。四十で好悪の迷いが無くなった。しかし五十になって天の命令を知った。六十になって何事も耳に入るようになった。七十になって心の思うままに行動しても、決まりからはみ出すことはなくなった。
意訳
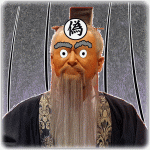
十五で学者を志望し三十で食えるようになり、四十で好き嫌いから解放された。
ところが五十になって、政治家になれと言う天の声を聞いた。迷いはあったが六十になるとその声がはっきり聞こえるようになった。今七十を過ぎて、好き勝手に振る舞っても、カッチリ作法を守れるようになった。
従来訳
先師がいわれた。――
「私は十五歳で学問に志した。三十歳で自分の精神的立脚点を定めた。四十歳で方向に迷わなくなつた。五十歳で天から授かった使命を悟った。六十歳で自然に真理をうけ容れることが出来るようになつた。そして七十歳になってはじめて、自分の意のままに行動しても決して道徳的法則にそむかなくなった。」下村湖人『現代訳論語』
現代中国での解釈例
孔子說:「我十五歲立志於學習,三十歲有所建樹,四十歲不困惑,五十理解自然規律,六十明辨是非,七十隨心所欲,不違規。」
孔子が言った。「私は十五歳で学問をしようと決意した。三十歳でその効果があった。四十歳で迷いが無くなった。五十で自然の法則を理解した。六十ではっきりとものの善し悪しが分かった。七十で好きなように振る舞っても、おきてに外れなくなった。」
論語:語釈
子曰(シエツ)(し、いわく)

論語の本章では”孔子先生が言った”。「子」は貴族や知識人に対する敬称で、論語では多くの場合孔子を指す。「子」は赤ん坊の象形、「曰」は口から息が出て来るさま。「子」も「曰」も、共に初出は甲骨文。辞書的には論語語釈「子」・論語語釈「曰」を参照。
この二文字を、「し、のたまわく」と読み下す例がある。「言う」→「のたまう」の敬語化だが、漢語の「曰」に敬語の要素は無い。古来、論語業者が世間からお金をむしるためのハッタリで、現在の論語読者が従うべき理由はないだろう。
吾(ゴ)


(甲骨文)
論語の本章では”わたし”。初出は甲骨文。字形は「五」+「口」で、原義は『学研漢和大字典』によると「語の原字」というがはっきりしない。一人称代名詞に使うのは音を借りた仮借だとされる。詳細は論語語釈「吾」を参照。
春秋時代までは中国語にも格変化があり、一人称では「吾」を主格と所有格に用い、「我」を所有格と目的格に用いた。しかし論語でその文法が崩れ、「我」と「吾」が区別されなくなっている章があるのは、後世の創作が多数含まれているため。
秦漢帝国以降の漢文や、現代中国語には格変化が無いが、古代にはあり、論語の時代である周代は、それが消え去りつつある時代だった。山東=太行山脈以東の黄河下流域に発生した、農耕都市国家の夏・殷王朝と、それを滅ぼし、元ははるか西方の渭水流域で、羊を飼って暮らしていた周王朝では、かなり言語が違ったのだろう。
青銅器や祭祀など、周は滅ぼした殷の都市国家文明は引き継いだし、文明語としての殷語もかなり取り入れたはずだが、日本人がrとlの違いを聞き取れないように、まるで違う言語の受け入れには、どうしても限界があったのだろう。
十有五(シュウユウゴ)
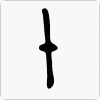
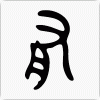
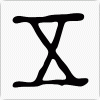
(金文)
論語の本章では”十五歳”。「十」→「ジュウ」は呉音(遣隋使より前に日本に伝わった音)。ここでの「有」は助辞(中国語の付属語や、それを示すのに用いられる漢字のこと。たとえば焉(エン)・矣(イ)・哉(サイ)・也(ヤ)・乎(コ)など。前置詞の於(オ)や于(ウ)などを含めることもある)で、さらに輪をかけて、その上に加えての意を示すことば。詳細は論語語釈「十」・論語語釈「有」・論語語釈「五」を参照。


助辞は漢文訓読では置字(オキジ)といって読まないことが多いが、それが平安朝のおじゃる公家以降、漢文をデタラメに読む伝統の言い訳になってきた。受験漢文程度なら助辞は読まずに済ませられるが、原文を読もうとするなら、しつこく意味を追い回さなければならない。
而(ジ)


(甲骨文)
論語の本章では”そして”。初出は甲骨文。原義は”あごひげ”とされるが用例が確認できない。甲骨文から”~と”を意味し、金文になると、二人称や”そして”の意に用いた。英語のandに当たるが、「A而B」は、AとBが分かちがたく一体となっている事を意味し、単なる時間の前後や類似を意味しない。詳細は論語語釈「而」を参照。
志(シ)


(金文)
論語の本章では”こころざし”。『大漢和辞典』の第一義も”こころざし”。初出は戦国末期の金文で、論語の時代に存在しない。論語時代の置換候補は”知る”→「識」を除き存在しない。字形は「止」”ゆく”+「心」で、原義は”心の向かう先”。詳細は論語語釈「志」を参照。
孔子は巫女を母に持つ母子家庭に生まれ、早くに孤児となった。社会の最底辺と言って間違いないが、唯一強みがあったのは、巫女の家の出だけに文字が読めたこと。だが論語の当時は本屋も図書館も無く、庶民の入る学校もほぼ皆無だったから、やりたいと決意しなければ学問など出来る環境ではなかった。なお当時の学校の有無については下記する。
于(ウ)→乎(コ)
現存最古の論語版本である定州竹簡論語は「乎」と記す。論語の本章に関して現存最古の古注本である宮内庁蔵清家本も同様。これに従い校訂した。唐石経は「于」と記す。論語注疏、新注の古本も同様。一部の版本では「於」と記す。いずれも、”~に”の意で文意は変わらない。詳細は「論語の成立過程まとめ」を参照。
原始論語?…→定州竹簡論語→白虎通義→ ┌(中国)─唐石経─論語注疏─論語集注─(古注滅ぶ)→ →漢石経─古注─経典釈文─┤ ↓↓↓↓↓↓↓さまざまな影響↓↓↓↓↓↓↓ ・慶大本 └(日本)─清家本─正平本─文明本─足利本─根本本→ →(中国)─(古注逆輸入)─論語正義─────→(現在) →(日本)─────────────懐徳堂本→(現在)
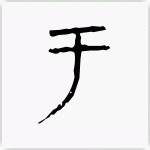

「于」(甲骨文)
「于」の初出は甲骨文。字形の由来と原義は不明。春秋末期までに”至る”・”~に”の用例がある。詳細は論語語釈「于」を参照。


(甲骨文)
「乎」の”~に”の語義は春秋時代では確認できない。字の初出は甲骨文。甲骨文の字形は持ち手を取り付けた呼び鐘の象形で、原義は”呼ぶ”こと。甲骨文では”命じる”・”呼ぶ”を意味し、金文も同様で、「呼」の原字となった。句末の助辞や助詞として用いられたのは、戦国時代以降になる。ただし「烏乎」で”ああ”の意は、西周早期の金文に見え、句末でも詠嘆の意ならば論語の時代に存在した可能性がある。詳細は論語語釈「乎」を参照。


(金文)
「於」の初出は西周早期の金文。ただし字体は「烏」。「ヨ」は”~において”の漢音(遣隋使・遣唐使が聞き帰った音)、呉音(遣隋使より前に日本に伝わった音)は「オ」。「オ」は”ああ”の漢音、呉音は「ウ」。現行字体の初出は春秋中期の金文。西周時代では”ああ”という感嘆詞、または”~において”の意に用いた。詳細は論語語釈「於」を参照。
學(カク)


(甲骨文)
論語の本章では”学問”。「ガク」は呉音(遣隋使より前に日本に伝わった音)。初出は甲骨文。新字体は「学」。原義は”学ぶ”。座学と実技を問わない。上部は「爻」”算木”を両手で操る姿。「爻」は計算にも占いにも用いられる。甲骨文は下部の「子」を欠き、金文より加わる。詳細は論語語釈「学」を参照。
三十→卅/四十→卌
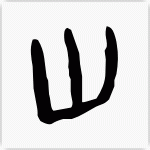
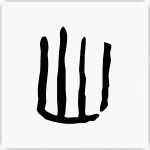
「卅」「卌」(甲骨文)
文字史の上から言えば「卅」「卌」との表記は甲骨文からあったが、論語の時代の通例とは言えない。つまり漢代の儒者が論語を古風に見せ無用の威嚇を行うためのハッタリである。詳細は論語語釈「三」・論語語釈「四」を参照。
立(リュウ)


(甲骨文)
論語の本章では”確立した”。初出は甲骨文。「リツ」は慣用音。字形は「大」”人の正面形”+「一」”地面”で、地面に人が立ったさま。原義は”たつ”。甲骨文の段階で”立てる”・”場に臨む”の語義があり、また地名人名に用いた。金文では”立場”・”地位”の語義があった。詳細は論語語釈「立」を参照。
『学研漢和大字典』では本章の「三十而立」を引いて”足を地につけて、しっかりと生活をする”と解するが、どうにもそのけしきを絵図に描けない。現代中国での解釈”三十歳でその効果があった”の方が、妥当なのではなかろうか。
不(フウ)


(甲骨文)
漢文で最も多用される否定辞。初出は甲骨文。「フ」は呉音(遣隋使より前に日本に伝わった音)、「ブ」は慣用音。原義は花のがく。否定辞に用いるのは音を借りた派生義だが、甲骨文から否定辞”…ない”の意に用いた。詳細は論語語釈「不」を参照。
惑(コク)


(金文)
論語の本章では”まよう”。初出は戦国時代の竹簡。論語の時代に存在しない。論語時代の置換候補もない。「ワク」は呉音。同音に語義を共有する漢字は無い。字形は「或」+「心」。部品の「或」は西周初期の金文から見られ、『大漢和辞典』には”まよう・うたがう”の語釈があるが、原義は長柄武器の一種の象形で、甲骨文から金文にかけて地名・人名や、”ふたたび”・”あるいは”・”地域”を意味したが、「心」の有無にかかわらず、”まよう・うたがう”の語義は、春秋時代以前には確認できない。詳細は論語語釈「惑」を参照。
既存の論語本では藤堂本の類書に、次のように言う。
古代人の心には、数々の魔物と精霊とがつきまとっていた。…孔子はこれらの「鬼神」を、人間の魂からおい払った。…こうして、人々は古代社会のいまわしいきずなから開放ママされた。人々の魂は、重苦しい原始信仰から脱することができた。これこそ「自由の宣言」であった。けれども、人々の魂をとりまく厄介な邪魔物がまだある。それは私欲や憎悪である。これこそ、古代現代を問わず、永久に人生につきまとう厄介物だ。人間の知性を愛した孔子は、この邪魔物を惑と読んだ、人間の心をとりまくワクのようなものである。
…「四十にして惑わず」とは、ふつうフラフラと色や利欲に迷わされぬと解している。がそうではない。「憎愛の感情のワクに、とらわれぬようになった。」ということである。マドウという日本語にマドワされてはいけない。(『漢文入門』論語のこころ)
五十(ゴシュウ)




(甲骨文)
論語の本章では”五十才”。初出は甲骨文。「五」も「十」も、甲骨文には二系統の字形がある。「十」(ジュウ)は呉音。論語語釈「五」・論語語釈「十」を参照。
知(チ)


(甲骨文)
論語の本章では”知る”。現行書体の初出は春秋早期の金文。春秋時代までは「智」と区別せず書かれた。甲骨文で「知」・「智」に比定されている字形には複数の種類があり、原義は”誓う”。春秋末期までに、”知る”を意味した。”知者”・”管掌する”の用例は、戦国時時代から。詳細は論語語釈「知」を参照。
天命(テンメイ)
論語の本章では”天が与えた使命”。
『学研漢和大字典』によると意味は次の通り。
- 天から与えられた運命。「盛衰之理、雖曰天命、豈非人事哉=盛衰の理は、天命と曰ふと雖も、あに人事に非ざらんや」〔欧陽脩・伶官伝叙論〕
- 天が与えた使命。「五十而知天命=五十にして天命を知る」〔論語・為政〕
- 「天寿」と同じ。「楽夫天命復奚疑=かの天命を楽しんで復たなにをか疑はん」〔陶潜・帰去来辞〕
- 天が人に定め与えたもの。「天命之謂性=天命これを性と謂ふ」〔中庸〕

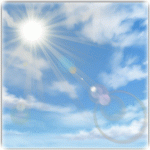
「天」(甲骨文1)
「天」の初出は甲骨文。字形は人の正面形「大」の頭部を強調した姿で、原義は”脳天”。高いことから派生して”てん”を意味するようになった。甲骨文では”あたま”・地名人名に用い、金文では”天の神”を意味し、また「天子」”周王”や「天室」”天の祭祀場”の用例がある。詳細は論語語釈「天」を参照。
なお殷代まで「申」と書かれた”天神”を、西周になったとたんに「神」と書き始めたのは、殷王朝を滅ぼして国盗りをした周王朝が、「天命」に従ったのだと言い張るためで、文字を複雑化させたのはもったいを付けるため。「天子」の言葉が中国語に現れるのも西周早期で、殷の君主は自分から”天の子”などと図々しいことは言わなかった。詳細は論語述而篇34余話「周王朝の図々しさ」を参照。


「令」(甲骨文)
「命」の初出は甲骨文。ただし「令」と未分化。現行字体の初出は西周末期の金文。「令」の字形は「亼」”呼び集める”+「卩」”ひざまずいた人”で、下僕を集めるさま。「命」では「口」が加わり、集めた下僕に命令するさま。原義は”命じる”・”命令”。金文で原義、”任命”、”褒美”、”寿命”、官職名、地名の用例がある。詳細は論語語釈「命」を参照。
六(リク)


(甲骨文)
論語の本章では”ろく”。初出は甲骨文。「ロク」は呉音。字形は「入」と同じと言うが一部の例でしかないし、例によって郭沫若の言った根拠無き出任せ。字形の由来と原義は不明。屋根の形に見える、程度のことしか分からない。甲骨文ですでに数字の”6”に用いられた。詳細は論語語釈「六」を参照。
耳順(ジシュン)
論語の本章では”素直に(天命を)聞き取れるようになった”。
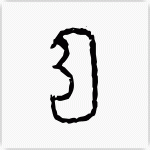

「耳」(甲骨文)
「耳」の初出は甲骨文。初出は甲骨文。字形はみみを描いた象形。原義は”みみ”。甲骨文では原義と国名・人名に用いられ、金文でも同様だったが、”…のみ”のような形容詞・副詞的用法は、出土物からは確認できない。詳細は論語語釈「耳」を参照。
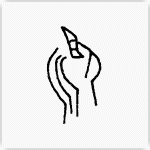

「順」(甲骨文)
「順」の初出は甲骨文。初出は甲骨文。「ジュン」は呉音。字形は人が川をじっと眺める姿で、原義は”従う”だったと思われる。甲骨文での語釈は不詳。金文では原義のほか、”教え諭す”(𣄰尊・西周)の用例がある。論語語釈「順」を参照。
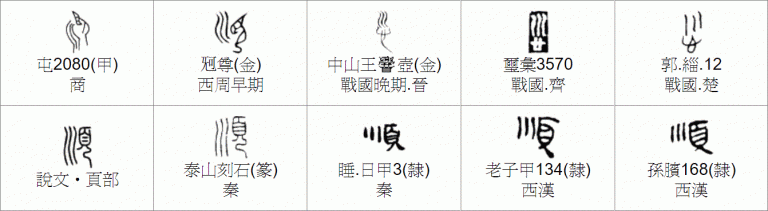
「小学堂」で参照すると、字形は「川+見」であり、人が川を見て何らかを読み取ろうとする姿。中華文明的に重要なのは、洪水の予兆を知ることであり、中国の大河川に起きる洪水は津波と同じで、被害の甚大な災害だったから、川の様子に従うことが原義だろう。
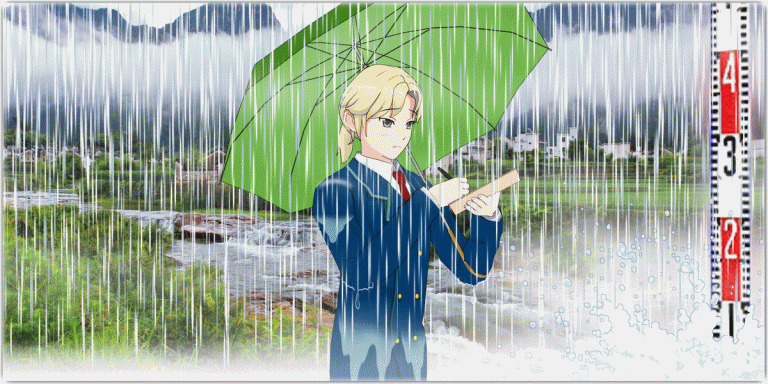
従って論語の本章では、史実性の如何にかかわらず、「耳が従う」とは、人の言語で知らされる何かに従うことではなく、人知を超えた何者かの声に従うこと、それも存在が証明できない何かではなく、自然が表した大事の予兆を知ること、を意味する。
孔子は古代人には珍しく、ほぼ無神論と言える立場に立ったが(孔子はなぜ偉大なのか)、それでも大自然の猛威をなめてかかるようなうかつ者ではなかった。だから孔子の場合「人知を超えた何者か」とは自然現象を指し、カミサマや占いのたぐいでは断じてない。
七(シツ)
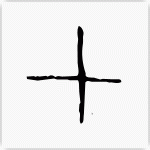

(甲骨文)
論語の本章では数字の”なな”。初出は甲骨文。「シチ」は呉音。字形は「切」の原字と同じで、たてよこに入れた切れ目。これがなぜ数字の”7”を意味するようになったかは、音を借りた仮借と解する以外に方法が無い。原義は数字の”なな”。「漢語多功能字庫」によると、甲骨文から戦国の竹簡まで一貫して、数字の”なな”の意で用いられている。詳細は論語語釈「七」を参照。
縱(ショウ)
論語の本章は定州竹簡論語にこの部分を欠き、次いで古い慶大本に従い「縱」とした。


「縦」(秦系戦国文字)
論語の本章では”したがう”。新字体は「縦」。「ジュウ」は慣用音。初出は秦系戦国文字で、論語の時代に存在しない。”ゆるむ”・”ゆるめる”・”ほしいままにさせる”の意で「從」(従)が論語時代の置換候補となる。字形は「糸」+「従」で、織機の横糸が従うべき縦糸。原義は”縦糸”。詳細は論語語釈「縦」を参照。


「從」(甲骨文)
唐石経は近音で部品の「從」(従)と記す。”したがう”の意があり、初出は甲骨文。その略形「从」は、現代中国での通用字になっている。「ジュウ」は呉音。字形は「彳」”みち”+「从」”大勢の人”で、人が通るべき筋道。原義は筋道に従うこと。甲骨文での解釈は不詳だが、金文では”従ってゆく”、”好きなようにさせる”の用例がある。”聞き従う”の用例は戦国時代まで時代が下る。詳細は論語語釈「従」を参照。
心(シン)
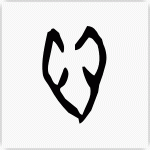

(甲骨文)
初出は甲骨文。字形は心臓を描いた象形。原義は心臓。甲骨文の段階で”思う”・”思い”を意味し得、その他河川の名として用いられた。詳細は論語語釈「心」を参照。
所(ソ)


(金文)
論語の本章では”…するところの…”。初出は春秋末期の金文。「ショ」は呉音。字形は「戸」+「斤」”おの”。「斤」は家父長権の象徴で、原義は”一家(の居所)”。論語の時代までの金文では”ところ”の意がある。詳細は論語語釈「所」を参照。
欲(ヨク)


(楚系戦国文字)
論語の本章では”もとめる”。初出は楚系戦国文字。新字体は「欲」。同音は存在しない。字形は「谷」+「欠」”口を膨らませた人”。部品で近音の「谷」に”求める”の語義があり、全体で原義は”欲望する”。論語時代の置換候補は部品の「谷」。詳細は論語語釈「欲」を参照。
踰(ユ)
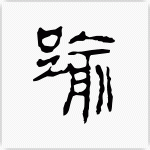

(隷書)
論語の本章では『大漢和辞典』の第一義と同じく”超える”。初出は前漢の隷書。論語の時代に存在しない。同音多数で兪はその一つ。字形は「足」+「兪」”超える”で、原義は”超える”・”越える”。「兪」→”こえる”の語義は春秋時代以前に確認できず、論語の時代の置換候補は無い。詳細は論語語釈「踰」を参照。
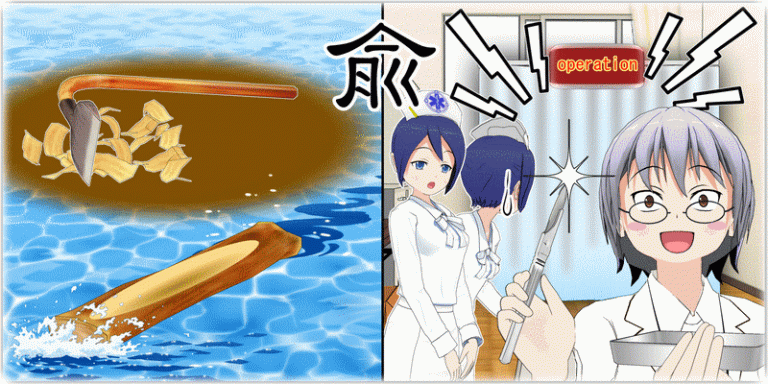
矩(ク)
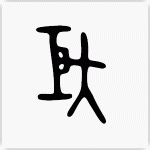
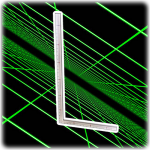
(金文)
論語の本章では「格」と同じく、”カタ(にはめる)”こと。この語義は春秋時代では確認できない。論語では本章のみに登場。初出は西周早期の金文。カールグレン上古音はki̯wo(上)。字形は「工」”直角工具”+「人」。原義は”直角工具を用いる”。金文で人名や地名に用いた例がある。詳細は論語語釈「矩」を参照。
論語:付記
検証
孔子が自分の一生を振り返った言葉として大変有名な本章だが、上記の検討通り後世の偽作はほぼ確実で、漢字の用法から見て創作時期は漢代以降に下るのも確実。
定州竹簡論語にあることから、前漢前半までには創作されていただろうが、論語の本章の「三十而立」は、後漢前期の『白虎通義』に再録されるまで誰も引用していない。「四十不惑」以降が再録されるのは、後漢初期の王充『論衡』からになる。
解説
六十歳を「耳順」と呼ぶその「順」の字について、その原義は上記の通り、川をじっと眺めて観察し、その様子に従って洪水の備えをするなどだが、論語をはじめとする中華文明と、洪水との縁は深い。

黄河は史上、何度も流路を変えたし、そのたびごとに大規模な洪水があったことは疑いない。1939年に蒋介石が意図的に起こした洪水は、前後の洪水と合わせて、多くて400万人の死者を出したとされる。古代でも洪水の脅威は、黄河下流域の中国人万人に共有されていた。
その自然災害の予兆をいち早く感じ、人々に納得できるよう言葉に出来たのがすなわち聖人であり、論語の時代では道徳的な価値でそう呼ばれたわけではない。地道に観察し、記録を取り、類推できる能力者であり、孔子が必須科目として算術を入れたのは一つにそのためだ。
「怪力乱神を語らず」(論語述而篇20)とあるのも同じ理由による。
孔子が就職したのは、五十を過ぎて中都のまちの代官「中都宰」に任じられた時で、それまでは公室や家老家の倉庫管理や牧場管理をしていたと『史記』は言う。本章と合わせ考えると、小役人のかたわら、古典研究と弟子の育成が四十代までの孔子の生涯と言える。
中都宰から昇進して魯国の宰相格になって以降は、生涯を終えるまで政治革命に邁進したが、一人息子や有力な弟子に次々死なれた七十頃、意訳のように気力を落とした。加えて期待した呉国が留守を越に襲われて没落したことも、決定的だったろう。

それにしても初の仕官が五十頃というのは、現代でも遅く思えるし、平均寿命が三十ほどだった論語時代では、ものすごい老人と言っていい。確かに貴族階級には七・八十まで生きる例が珍しくないが、孔子はもともと庶民で、それも最下層に近い出身だった。
逆に考えると、底辺からのし上がって政治家になるまでには、超老人になるまでかかったということで、当時の身分差別の厳しさを、思い知らされるような感覚になる。それだけ孔子がずば抜けた体力と生命力を持っていたことになり、孔子青びょうたん説には同意できない。
また論語の一読者として本章を読めば、孔子のような超人でも四十になるまで迷ったというなら、凡人である訳者如きはその倍は迷って良かろう。つまり一生迷っていても構わないわけで、学がなって立つまでも、六十だろうといいことになる。いや、開き直りはいけないか。
なお論語に基づいて、後の中国では十五歳を学問始めとし、「志学」といった。しかし貴族だろうと儒者だろうと皆が皆、十五で学問を好んだわけではない。当たり前の事なのだが、有名詩人陶淵明の息子たちも、そろって勉強が大嫌いだった。
「責子」陶淵明 「子を責む」陶淵明
白髮被兩鬢 肌膚不復實 白髪は両鬢を被い、肌膚復た実ならず
雖有五男兒 總不好紙筆 五男児有りと雖も、総べて紙筆を好まず
阿舒已二八 懶惰故無匹 阿舒は二八なるに、懶惰なること故に匹無し
阿宣行志學 而不好文術 阿宣は行く行く志学なるも、而も文術を愛せず
雍端年十三 不識六與七 雍と端とは年十三なるも、六と七とを識らず
通子垂九齡 但覓梨與栗 通子は九齢に垂んとするも、但だ梨と栗とを覓むるのみ
天運苟如此 且進杯中物 天運苟し此くの如くんば、且く杯中の物を進めん
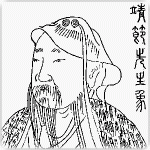
「子を責める」陶淵明
髪は両側とも真っ白、肌も老いぼれてつやを失った。
男の子が五人いるが、全て勉強が大嫌いだ。
阿舒は十六になると言うのに、ぶらぶら怠けて手の着けようがない。
阿宣はそろそろ十五だが、読むのも書くのもイヤだという。
雍と端は歳十三、六と七の違いも知らない。
通子はもうすぐ九歳だが、ナシとクリを欲しがるばかり。
運命はさても残酷だよ。やめやめ、酒だ酒だ!
だが子供は常に親の写し絵、ただ食いできる田園がある程度には名門に生まれ、生涯まともに働かずぶらぶらニート生活を送った陶淵明が、子供の勉強嫌いを責められるわけがない。肖像画通り陶淵明はクズだがばかではないから、それに気付いてはいただろう。クズの子はほぼクズである。
こんな子がまじめになったら、それは親を見限ったという事だ。この親子の不真面目は、時代的雰囲気の反映で、南朝はふざけた社会だった。現代ポンニチ同様、上流階級ほどろくでもなく、そんな社会でまじめだと損をした。詳細は論語為政篇16余話「魏晋南朝の不真面目」を参照。
また孔子の「志学」について、論語と同時代に、孔子の母国の隣国である鄭には、庶民の通う学校があったと儒者は言っているが、その語釈は例によって極めて怪しい。
鄭人游于鄉校,以論執政,然明謂子產曰,毀鄉校何如,子產曰,何為,夫人朝夕退而游焉,以議執政之善否,其所善者,吾則行之,其所惡者,吾則改之,是吾師也,若之何毀之。」

鄭の民百姓は”郷校”に寄り集まって、政治の善し悪しをあげつらっていた。そこで〔貴族の〕然明が、〔宰相の〕子産に「”郷校”を潰してしまっては」と言った。
子産「なんでそんなことをするのかね。民が朝夕集まって、政治の善し悪しを言うのなら、私はその評判のいいことを行って、悪いことは改める。つまり私のよき教師だ。潰してどうしようというのかね。」
(『春秋左氏伝』襄公三十一年。『新序』雑事四・『孔子家語』にも引用)

通説では「郷校」を”村の学校”と解する。しかし「校」が”学校”の意味になるのは、「爻」(二本一組で用いる算木を交差させたさま)の音通で、もとは交叉させた木組みに人や動物を”囲い込んで集める場所”を意味していた。つまり「郷校」とは村の寄合所。
教師がものを教える”学校”ではない。論語語釈「学」・論語語釈「校」を参照。
余話
天狗の作り方
外国でプログラミングの経験の無い人に、初歩的なアプリを作って示すと、まるで「不思議の国から来た魔女のように扱われた」と訳者の旧友は言った。現代でも一部の技術者が崇拝の対象になることがあるが、それではかえって数理から遠ざかるし、論語の理解にも邪魔になる。
自分で「聖人でない」と言わされた孔子は(論語述而篇33)、その数理的観察力と記帳によって、正確な帳簿を付け牧場の家畜を殖やし、国公や門閥貴族の注目を引いたとされる(『史記』孔子世家)。文明のか細い古代にあって、合理と数理能力が、孔子を孔子にした。
だが地道に観察し記録し理論を立てる科学者として出世した者が、生涯合理性を保てるとは限らない。岡潔のように、晩年は宗教の開祖みたくなってしまった人もいる。youtubeで講演を聴いたことがあるが、漢籍について知ったかぶりのデタラメを語るのを聞いて途中で止めた。
人文に携わる者が数学が出来ないからといって、数学の出来る者が人文について間違いを言いふらしてていい理由にはならない。ネット識者として名を売った元名大教授のT先生も、人文について誤った受け売りを得意げに仰るので、理系話まで信用できなくなってしまう。
ほかに書籍の例を挙げよう。
沈黙の闇に包まれていた縄文文化は徐々に宴の跡をかいま見せ始めた。その最盛期は大陸における仰韶文化から竜山、殷文化のそれと重なり、またオリエント文化躍進時とも重なる暗示的要素を持つ。(伊達宗行『「理科」で歴史を読み直す』ちくま新書)
前書きでもうパチモン臭がする。中国学を3日でも学んだ者なら、仰韶と書くならなぜ竜山と書かないのだ、といぶかしむだろう。訳者のような数理の分からない者に、元物理学会の会長さんが、理科を平たくお教え下さるのは有り難いが、税込円程度には夢を見せて頂けぬか。
ご覧の通り、広東語でも「龍種」は「ロンジ(=チ)ョン」である。話を戻そう。
こういうのは編集者が注意してもよさそうだ、と本の買い手は思いたくもなろうが、𠮷外相手にまじめに仕事をしても損しかしないのは編集者も他の職と同じなので、こういう原稿は黙って通す。ヒラ教授ですらそうするから、学会の会長ともなれば誰も本当の事を言わず更生の機会が無い。
世間にチヤホヤされると天狗になってしまうのが常人のさがで、それは数理的論理能力とはあまり関係が無いようだ。数理以外の諸学問は、おおむねお金が儲かるわけでもないし、お腹が膨れるわけでもない。だが人格形成には人文を含め片寄り無く学ぶことが必要なのだろう。
訳者の知人にトーダイ出の理系人が何人かいるが、その一人は数学や理科が出来ない人を、しつこく「片寄っている」と馬鹿にする割に、程のよい高校生なら知っている人類史を知らない。数理も人類史も向き不向きであるのを知らない、これを片寄っているという。
だからゆえなく自分をを馬鹿にしにくる者に、怯える必要は何も無い。
参考記事
- 論語雍也篇27余話「そうだ漢学教授しよう」
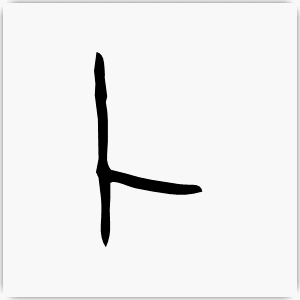

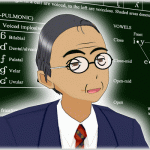

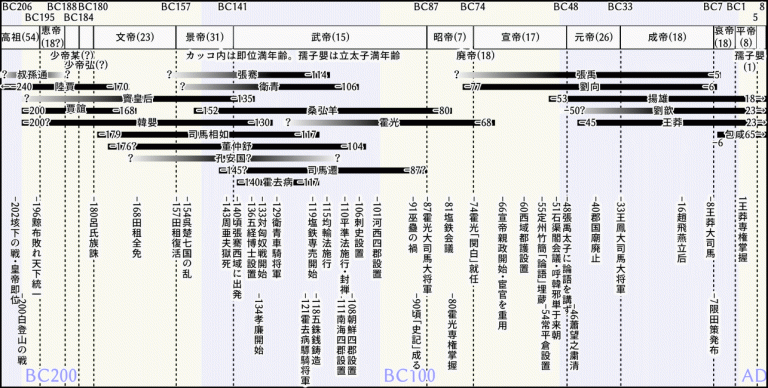
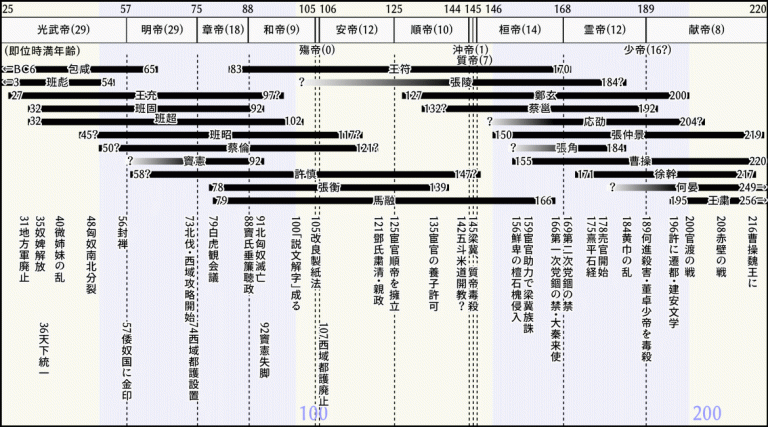


コメント
七十路を過ぎた拙老の考えです。
儒教も宗教ですから嘘も方便だとすれば仕方ありません。
キリスト教の聖書や仏教の仏典と同じで、論語も後世の世情の変化にともなって、諸派の都合よく方便で変わってきたと推測できます。
いつ、どの派が何を書きかえたかが分かれば完璧ですね。