孔子が偉大な理由は、無慮二千年間人間を奴隷化した儒教の開祖だからではなく、身長2mの巨人で武術の達人だったからでもない。千載一遇の運を拾って宰相になった、出世物語の成功者だからでもない。そんなのはいくらでもいる。
別して孔子はその精神が、古代人にもかかわらず高々と明るかったからだ。
こんにち、ネット以前の社会は想像もし難い。だがそれより前から現代文明が続いているとするなら、その始まりはガガーリン少佐が、閉じこめられた轟音と振動の中で「Поехали!」(行くぞ!)と絶叫して宇宙に飛びだしてからだと信じる。人類の視野は宇宙的に拡大した。

「地球は青かった」という言葉を、政治的に対立していた日本でさえ、誰もがもてはやした、この人類の興奮は、訳者ごときの筆に負えるものではない。
この興奮を理解しなければ、現代文明は分からない。そして多分、他の文明ばかりか、人類の退化もわからない。人類は常に進歩するとは限らない。古代のプラトンは地球が動くと思っていたが、中世にそれを言ったジョルダーノ・ブルーノは、ローマ教会によって焼き殺された。
人は退化もする。自ら視野を狭め、よってたかってアホウになりもする。直接原因は、欲タカリのローマ坊主のような古今東西の野蛮人が野蛮だからだが、根本的にはローマ帝国が飛び抜けた悪政を行ったせいでも、東洋から蛮族が押し寄せたからでもないと分かっている。
スティリコ将軍の悲劇は、そう理解して然るべきだ。
それらは結果であって原因ではない。地球規模の寒冷化がそうさせたのだ。それも並の儒者やローマ坊主ならボヤで済むが、行きつく果てはモズグス様で、滅び行く世界で人間の命はどうでもよくなり、信じた教えの純粋が汚されたと感じて即、人を焼いて回る狂信がまかり通る。
人は人が嫌いだ。それを認めない限り何も分からない。

だが殷を倒した周王朝は、少なくとも火あぶりの如き野蛮と手を切った。『字通』によると、雨乞いの際ふるくは巫女を焼き殺して祈ることがあり、「漢」という字の旁「𦰩」はそれを意味するという(歎条)。だが周代になると、そのような無残は野蛮で無意味と考えられた。
【周】
夏,大旱,公欲焚巫尪,臧文仲曰,非旱備也,脩城郭,貶食省用,務穡勸分,此其務也,巫尪何為,天欲殺之,則如勿生。
夏、日照りが続いたので、雨乞いに失敗したこびとのみこを、(魯国公の)僖公は焼き殺そうと考えた。
(家老の)臧文仲「そんなことでは日照りは収まりません。城壁を堅固にして飢えた賊の襲来を防ぎ、食事を質素にして出費を減らし、農耕に力を入れて貧者に配給し、労働力を増すのが、当面のやるべき事です。みこなど焼き殺して何になるのですか。天がみこを殺すおつもりなら、今なおのうのうと生きている道理が無いではないですか。」(『春秋左氏伝』僖公二十一年(BC639))
魯の殿様ですら、腹立ち紛れにみこを焼き殺そうとしているだけで、焼けば雨が降るとは思っていない。同時期、「宋襄の仁」の故事成語でバカにされる宋の襄公が、つまずいた始めは神へのお供えだと言って、捕らえた小国の殿様を二人も斬り殺したことだ(『左伝』僖公19)。

だから誰にも相手にされなくなり、大国楚相手にケンカを売って自滅した。なお宋とは、むやみに人をいけにえにして、他国人から「殷」(上掲金文)=人の生きギモを取る野蛮な奴ら、と呼ばれた、前王朝・商(これは自称)の末裔である。この点、現代中国も退化していないか?
対して「周は二代に鑑みて、郁郁乎として文なるかな。吾は周に従う」(論語八佾篇14)と孔子が表明したのは、周の人間主義ゆえに他ならない。人は貴い。中国人も異民族も、文明の程度は違えど同じだ。その意識が普及した春秋時代にあって、孔子はなお飛び抜けていた。
孔子の時代、人々はなお神霊や亡霊、精霊を恐れていた。しかし孔子は疫病などの際に潔斎=自分をジャブジャブ洗って清潔にはしたが(論語述而篇12)、神頼みをしようとはしなかったし、祟りを恐れもしなかった。論語では神頼みを否定している。
先生が病気になり、危篤になった。
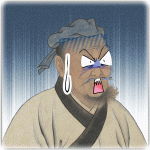
子路「お祓いしましょう。」
孔子「なんぞ霊験あらたかな祝詞でもあるのか。」
子路「ここにあります。えーと、病魔退散~かしこみ~祈りまほ~す~。」
孔子「その程度の祈りなら、自分でずっとやっているよ。」(論語述而篇34)
加えて「子は怪力乱神を語らず」と論語述而篇に言う。「鬼神を敬して遠ざく」と論語雍也篇に言う。「霊魂に仕える法など知らん」と論語先進篇では突き放した。孔子は、その目に神が見える人ではなかったのだ。「人の世は人のものだ。」孔子は2,500年前の人物で、ブッダやソクラテスとほぼ同時代人である。現代でもバカげた新興宗教が流行っているというのに、孔子の視野の明るさ先進性は、時代を飛び抜けた精神というしかない。
それを踏まえないと、論語八佾篇の一連の章は全くの誤読をするはめになる。
子曰く、禘既に灌ぎ而自り往者、吾之を觀ることを欲さざる矣。
(従来訳)
先師がいわれた。――
「禘の祭は見たくないものの一つだが、それでも酒を地にそそぐ降神式あたりまではまだどうなりがまんが出来る。しかしそのあとはとても見ていられない。」(拙訳)
禘の祭りでは酒を撒き、それでご先祖様のたましいを呼び申す、ことになっておる。たましいが降りてきた振りした神官どもの、偽善めいた振る舞いは、阿呆らしくて見るに堪えない。
或るひと禘之說を問ふ。子曰く、知らざる也。其の說を知る者之天下に於ける也、其れ諸を斯に示すが如き乎」と。其の掌を指せり。
(従来訳)
ある人が禘の祭のことを先師にたずねた。すると先師は、自分の手のひらを指でさしながら、こたえられた。――
「私は知らない。もし禘の祭のことがほんとうにわかっている人が天下を治めたら、その治績のたしかなことは、この手のひらにのせて見るより、明らかなことだろう。」(拙訳)
ある人「禘の祭って、なんかすごいチンチンどんどんをやりますが、あれには何か謂われがあるんでしょうか。」
孔子「あるものか。神主どもがもったいつけてやっとるだけじゃよ。謂われ? そんなもん、誰が知っとるというのかね。」と空の手の平を指さした。
祭るに在すが如くし、神を祭るに神在すが如くせり。子曰く、吾與らず。祭りて祭らざるが如ければなり。
(従来訳)
先師は、祖先を祭る時には、祖先をまのあたりに見るような、また、神を祭る時には、神をまのあたりに見るようなご様子で祭られた。そしていつもいわれた。――
「私は自分みずから祭を行わないと、祭ったという気がしない。」(拙訳)
お供えの時には、祖先や神様がおわすと思ってお供えしていた。それを見た先生が言った。
「ワシはやらん。バカげとる。誰もおりゃあせんぞ。」
子太廟に入りて事每に問ふ、或るひと曰く、孰か鄹人之子禮を知ると謂ふ乎。太廟に入りて事每に問ふと。子之を聞いて曰く、是れ禮也と。
(従来訳)
先師が大廟に入つて祭典の任に当られた時、事ごとに係の人に質問された。それをある人があざけっていった。――
「あの鄹の田舎者のせがれが、礼に通じているなどとは、いったいだれがいい出したことなのだ。大廟に入つて事ごとに質問しているではないか。」
先師はこれをきかれて、いわれた。――
「慎重にきくのが礼なのだ。」(拙訳)
若い頃、国公の祭殿で祭祀の手伝いをしたことがある。バカげた偽善ごっこを神官どもがやっていたから、一体何の意味があるのかと一々問い詰めてやった。そしたらある神主が笑ったそうだ。「誰だ、あの乱暴者の小僧が礼法を知ると言ったのは」。聞いてつぶやいた。「迷信に付き合わんのが貴族のたしなみなんだがな」と。
孔子がこのような視点が持てたのは、拝み屋の母の私生児という生まれが与っている。母に付き添い、バカげた仕草に一般人がどれほど怯えるか、うんざりするほど見てきただろう。坊主が本尊を磨くのは、光った方がお賽銭が増えるからで、でなければ平気で焼きもする。
念のために申し添えるが、訳者は従来訳をなさった下村湖人先生の人の善さも、学識も疑っていない。先生が誤訳をしたのは時代的制約であって先生のせいではない。それより腹が立つのは、文明が進んだのに、今なお論語を黒魔術風に訳して、世間から金を取るバカどもだ。
それこそ火あぶりでもやりかねないし、学者人生に限るなら、実際火あぶりをやっている。訳者のようにネットでぐちぐちとこうした駄文を書けるのはまだいい方で、無念に無残に涙を呑んで消えていった学生院生は膨大にいる。…話を孔子に戻そう。
孔子はその冷徹により、自分の死をも飾ろうとしなかった。大げさな葬儀の用意をした子路を叱り飛ばし(論語子罕篇12)、弟子にも孔子自身の死を語ることを禁じた。弟子は偉大な師の死を、語りたかったはずである。なのに論語のどこにも、孔子の死について記した箇所が無い。

論語子罕篇の後半が、それとなく匂わせているだけだ。こんにち孔子の死の前後について知れるのは、司馬遷が孔子の故郷で古老の話を聞き取って、それを史記に記しておいたおかげである。ただし、古老が一杯機嫌でデタラメを語っていないとは、誰一人言うことが出来ない。
この冷徹は、同世代の賢者である、ブッダと比較するとよりはっきりする。ブッダの知力は、あるいは孔子を凌ぐであろう。だがブッダは死に際して、打ってほぐした布を用意せいだの、天から琵琶弾きが降りて来るだの、沙羅双樹が咲くだのと、じたばたと弟子に語り続けた。
ブッダがその死を愚劣から救ったのは、最後の言葉の透明さにある。「全て形あるものは、瞬時もその姿を留めない。」「だからお前達は、怠らず修行せよ。」ブッダは死ぬ寸前になって、やっとウソを言わざるを得ない俗世から離れた。寸前の寸前までそうでなかった。
涅槃をインドの古語でニルヴァーナと言うらしい。ブッダの最期を語った経典を、マハーパリニッバーナ・スッタンタと言う、と岩波の表紙に書いてある。ブッダは30ほどで一旦ニルヴァーナしながら、マハー(=大なる)・ニルバーナまで、作り事を語るしか無かったらしい。
無論ブッダ自身は、そのようなものは有りはしない、と知っていただろう。解脱とはつまりそれだ。だが生涯作り話を続けたのは事実である。ブッダは社会の底辺に生まれた孔子と違い、自身が将来の国王に生まれ、出家してさえ、大国コーサラやマガダの国王から帰依された。
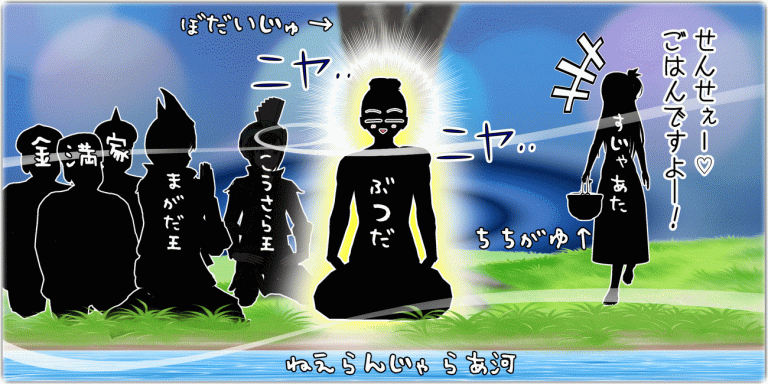
他人と関わらないと生きていけないのである。仏教の縁起説を受け入れる前に、それを吟味する必要がある。宇宙には自分とそれ以外しかないが、それ以外なしに自分が成立するか、成立しないのはなぜか、成立する条件は何か、するならどう自分があるべきかを仏教は教えない。
それゆえに、旦那衆の気に入るような話を、言って聞かせるしかなかった。「仏のウソをば方便という」という、明智光秀の言った通りだが、「神なんて居ない」という冷徹は、『スッタニパータ』にも『ダンマパダ』にも、『マハーパリニッバーナ・スッタンタ』にも無い。
またブッダの教団では、出家者は一切の世俗事を行わない。主家者は在家の信者に養われるか、乞食行によって生活の糧を得た。在家の王族や大商人、または一般の施与者に向かって、「死んだらそれまで」などと言おうものなら、直ちにブッダとその弟子は飢えるのである。
ブッダの高弟とされるサーリプッタやモガラーナが暗殺されたと伝えられるのも、高弟ゆえに「死んだらそれまで」と確信しており、それを他の教団から敵視されたからだ。ブッダ自身も暗殺されたと考えられなくはないが、80を超えた年齢では、自然死と考えてもよいだろう。
だから言う。お釈迦様は見えないものを見たんだ。さて財の話をしよう。
孔子は、誰が旦那でもない。魯の宰相だった時、衛に亡命した時には、孔子は現代換算で111億円の年俸を得ていた(論語憲問篇20)。弟子の数三千という誇大を考え合わせると、別に養って貰わなくても、弟子共々食えたのである。無論、生活の糧に困った時もあった。
例えば論語衛霊公篇26などが、その事情を示している。だが弟子にはアキンド子貢という、唸るような大富豪がいた(『史記』子贛伝)。加えて孔子は弟子に、世俗事を禁じていない。弟子はアルバイトにも励めたのである。だからこそ、孔子は作り事を言う必要が無かった。
誰はばかること無く、孔子は有るものを有る、無いものを無いと言えたのだ。それが被差別階級に生まれながら、一国の宰相にまで上り詰めた男の凄みである。その死生観を、論語に次ぐ孔子語録であり、考古学的発掘によって偽作の冤罪が晴れた『孔子家語』はこう記す。
孔子「私があると言ってしまえば、世の孝行者はいつまでも弔い続けて、自分の生きる努力を止めてしまうだろう。ないと言ってしまえば、親不孝者が弔いもせずに放置するだろう。だからあるかないかは、放っておけ。今知る必要も無いだろう。いずれ自分も死ぬのだから、自分で思い知るだろうよ。」(致思16)
現代でさえ、有るものを有る、無いものを無いと言えるのは、広い中国に恐らくただの一人もいない。後世の中国人が孔子を評して「素王」=無冠の帝王と賞賛したのは、まことにその凄みを反映した呼び名と言えよう。その生涯は、今なお読む価値があると訳者は信じる。
西欧かぶれが嬉しがるフランス革命の最終解に現れたナポレオンは、自分以外の全てをあざ笑いつつ欧州の覇王にのし上がり、ローマ教皇を呼びつけて自分で帝冠をかぶった。ナポレオンは少なくとも350万人、多くて700万人を殺した。そのシリアルキラーが自分が死ぬ段になって言った。
「お坊さんを呼んでくれ。」
みっともなさと図々しさにもほどがある。なお余話として、孔子がその理性から、根拠の無い差別などバカげていると思っていたとする伝承があるが、残念ながら後世の偽作が確定している。
互鄕のむらは口に出すのがはばかられた。そこから一人の奴隷がやってきて入門を願ったが、弟子は互いに「うわー」と言うだけで取り次がない。様子に気付いた孔子が言った。
「あきらめず、自分で人生を切り拓こうとしてるんだ。手助けしてやろうじゃないか。ひどいじゃないかお前たち。過去を綺麗さっぱり捨て去ろうとしてるんだ。立派じゃないか。」(論語述而篇28)
- 参考動画

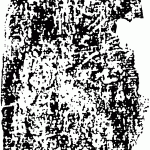


コメント