論語:原文・書き下し
原文(唐開成石経)
舜有臣五人而天下治武王曰予有亂臣十人孔子曰才難不其然乎唐虞之際於斯爲盛有婦人焉九人而巳三分天下有其二以服事殷周之德其可謂至德也巳矣
- 亂臣:「臣」字傍刻。
校訂
諸本
- 武内本:釋文、亂十人一本或は亂臣十人に作る。唐石経臣の字行旁にあり、蓋し後人の補う所、もと亂十人に作る釋文と同じ、此本(=清家本)臣の字ある一本と合す。呂氏春秋古樂篇注、此章を引く。文王爲西伯三分天下云々とあり、今の論語は文王爲西伯の五字を脱す。德、唐石経周之德に作る。
東洋文庫蔵清家本
舜有臣五人而天下治/武王曰予有亂臣十人/孔子曰才難不其然乎唐虞之際於斯爲盛有婦人焉九人而已/三分天下有其二以服事殷周德其可謂至德也已矣
後漢熹平石経
(なし)
定州竹簡論語
……乎?唐吴a之際209……而已。三b分天下有其二,以服事殷。周c德,其可謂210……
- 吴、今本作「虞」。吴為虞之省。
- 三、皇本・『釋文』作「参」、阮本作「三」。
- 阮本「周」下有「之」字、皇本・高麗本無「之」字。
標点文
舜有臣五人而天下治。武王曰、「予有亂十人。」孔子曰、「『才難』、不其然乎。唐吴之際、於斯爲盛。有婦人焉、九人而已。三分天下有其二、以服事殷。周德、其可謂至德也已矣。」
復元白文(論語時代での表記)
舜





 治
治 


















 際
際 





 焉
焉 
























※論語の本章は赤字が論語の時代に存在しない。「然」「乎」「唐」「虞」(吴)「事」「也」の用法に疑問がある。論語の時代に存在しない「婦人」の熟語がある。本章は漢帝国以降の儒者による創作である。
書き下し
舜に臣五人有り而天が下治まる。武王曰く、予亂き臣十人有りと。孔子曰く、才難しと、其れ然らず乎。唐吴之際、斯於盛なりと爲す。婦人有り焉、九人にし而已む。天が下を三つに分ちて其の二つを有ち、以て殷に服い事ふ。周の德は、其れ德の至りと謂ふ可き也る已矣。
論語:現代日本語訳
逐語訳

舜には五人の臣下がいてそれで天下が治まった。武王は言った。「私によい家臣が十人いる」と。孔子が言った。「才人は得難いものだ、そうではないか。唐や虞の時代、その時代を中華の繁栄期とする。女性がいた。九人しかいなかった。それで天下を三分してその二を所有しながら、なお殷王朝に従い仕えていた。周に秘められた力、それは最高だったと評価してよいのであるんであるんである。」
意訳

舜は家臣五人だけで、天下がよく治まった。周の武王は「私には乱を鎮めた家臣が十人いる」と言った。天下の全てを治めるのに、五人とか十人とか、いやはや人材とは得難いものだ。そうだろう、武王さまの家臣のうち一人はお妃さまだから、たった九人で天下を治めたのだ。しかも天下の三分の二を支配しながら、それでも殷王朝に服属する慎みがあった。周王朝にはこれほどの、秘められたパワーがあったのだ。最高であるぞよ。
従来訳
舜帝には五人の重臣があって天下が治った。周の武王は、自分には乱を治める重臣が十人あるといった。それに関連して先師がいわれた。――
「人材は得がたいという言葉があるが、それは真実だ。唐・虞の時代をのぞいて、それ以後では、周が最も人材に富んだ時代であるが、それでも十人に過ぎず、しかもその十人の中一人は婦人で、男子の賢臣は僅かに九人にすぎなかった。」
またいわれた。――
「しかし、わずかの人材でも、その有る無しでは大変なちがいである。周の文王は天下を三分してその二を支配下におさめていられたが、それでも殷に臣事して秩序をやぶられなかった。文王時代の周の徳は至徳というべきであろう。」下村湖人『現代訳論語』
現代中国での解釈例
舜有五個能人而使天下大治,武王說:「我有十個賢才。」孔子說:「人才難得,難道不是這樣的嗎?堯、舜、武王時期,人才最多,也不過如此,武王的十個賢人中還有一個女性。周文王掌握著國家三分之二的面積,卻仍然服從中央的領導。他的品德,真算至高無上了。」
舜には五人の賢臣がいて天下がよく治まった。武王が言った。「私には十人の賢臣がいる。」孔子が言った。「人材とは得がたいものだ。まさかこのようで無かったのか? 堯、舜、武王の時、人材は一番豊富だったが、それでもこの通りだった。武王の十人の賢臣には女性が一人いる。周の文王は、天下の三分の二を配下に収めながら、それでも依然として中央の指示に従った。彼の人柄は、まったくこの上なく高かったと言える。」
論語:語釈
舜 有 臣 五 人、而 天 下 治。武 王 曰、「予 有 亂 臣 十 人。」 孔 子 曰、「『才 難』、不 其 然 乎。 唐 吴(虞) 之 際、於 斯 爲 盛 、有 婦 人 焉、九 人 而 已。三 分 天 下 有 其 二、以 服 事 殷、周 之 德、其 可 謂 至 德 也 已 矣。」
舜(シュン)


(金文)
論語の本章では、創作上の古代の聖王。現伝する『史記』によると、卑屈が過ぎる親孝行の他は、賢者に政治を任せたことがあるだけで、これといって何をしたわけでもない。「舜」の初出は戦国文字で、論語の時代に存在しない。詳細は論語語釈「舜」を参照。
有(ユウ)


「有」(甲骨文)
論語の本章では”保有する”。初出は甲骨文。ただし字形は「月」を欠く「㞢」または「又」。字形はいずれも”手”の象形。金文以降、「月」”にく”を手に取った形に描かれた。原義は”手にする”。原義は腕で”抱える”さま。甲骨文から”ある”・”手に入れる”の語義を、春秋末期までの金文に”存在する”・”所有する”の語義を確認できる。詳細は論語語釈「有」を参照。
臣(シン)


(甲骨文)
論語の本章では”家臣”。「ジン」は呉音(遣隋使より前に日本に伝わった音)。甲骨文の字形には、瞳の中の一画を欠くもの、向きが左右反対や下向きのものがある。字形は頭を下げた人のまなこで、原義は”奴隷”。甲骨文では原義のほか”家臣”の意に、金文では加えて氏族名や人名に用いた。詳細は論語語釈「臣」を参照。
五(ゴ)


(甲骨文)
論語の本章では数字の”5”。初出は甲骨文。「五」の甲骨文には五本線のものと、線の交差のものとがある。前者は単純に「5」を示し、後者はおそらく片手の指いっぱいを示したと思われる。甲骨文より数字の”5”を意味した。詳細は論語語釈「五」を参照。
人(ジン)


(甲骨文)
論語の本章では人間の助数詞、また「婦人」として熟語の一部で”ひと”を示す。初出は甲骨文。原義は人の横姿。「ニン」は呉音。甲骨文・金文では、人一般を意味するほかに、”奴隷”を意味しうる。対して「大」「夫」などの人間の正面形には、下級の意味を含む用例は見られない。詳細は論語語釈「人」を参照。
舜有臣五人
既存の論語解説では新注に、治水に成功して夏王朝を開いた禹(ウ)、農業を司った稷(ショク)、民政を司った契(セツ)、司法を司った皋陶(コウトウ)、狩猟を司った伯益(ハクエキ)だというが、別に史実の裏付けがある訳ではない。
而(ジ)


(甲骨文)
論語の本章では”そして”。初出は甲骨文。原義は”あごひげ”とされるが用例が確認できない。甲骨文から”~と”を意味し、金文になると、二人称や”そして”の意に用いた。英語のandに当たるが、「A而B」は、AとBが分かちがたく一体となっている事を意味し、単なる時間の前後や類似を意味しない。詳細は論語語釈「而」を参照。
天下(テンカ)

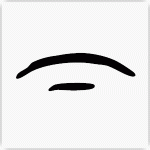
(甲骨文)
論語の本章では”天下”。天の下に在る人界全て。
「天」の初出は甲骨文。字形は人の正面形「大」の頭部を強調した姿で、原義は”脳天”。高いことから派生して”てん”を意味するようになった。甲骨文では”あたま”、地名・人名に用い、金文では”天の神”を意味し、また「天室」”天の祭祀場”の用例がある。詳細は論語語釈「天」を参照。
「下」の初出は甲骨文。「ゲ」は呉音。字形は「一」”基準線”+「﹅」で、下に在ることを示す指事文字。原義は”した”。によると、甲骨文では原義で、春秋までの金文では地名に、戦国の金文では官職名に(卅五年鼎)用いた。詳細は論語語釈「下」を参照。
治(チ)

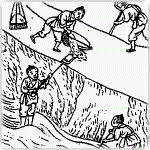
(秦系戦国文字)
論語の本章では”世の中が安定する”。初出は戦国文字。論語の時代に存在しない。”おさまる”の意では論語時代の置換候補は存在しない。「ジ」は呉音。字形は「氵」+「台」で、「台」は「㠯」”すき”+「𠙵」”くち”で、大勢が工具を持って治水をするさま。原義は”ととのえる”。同音や近音には置換候補があるが、春秋時代以前に”おさまる”の用例が確認できない。詳細は論語語釈「治」を参照。
武王(ブオウ)
論語の本章では、周王朝の初代君主。殷を滅ぼして取って代わった。
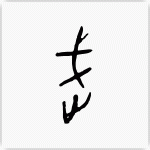

「武」(甲骨文)
「武」の初出は甲骨文。字形は「戈」+「足」で、兵が長柄武器を執って進むさま。原義は”行軍”。甲骨文では地名、また殷王のおくり名に用いられた。金文では原義で用いられ、周の事実上の初代は武王とおくりなされ、武力で建国したことを示している。また武力や武勇を意味した。加えて「文」の対語で用いられた。詳細は論語語釈「武」を参照。
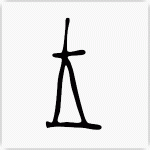

(甲骨文)
「王」の初出は甲骨文。字形は司法権・軍事権の象徴であるまさかりの象形。「士」と字源を同じくする漢字で、”斧・まさかりを持つ者”が原義。武装者を意味し、のちに戦士の大なる者を区別するため「士」に一本線を加え、「王」の字が出来た、はずだが、「王」の初出が甲骨文なのに対し、「士」の初出は西周早期の金文。甲骨文・金文では”王”を意味した。詳細は論語語釈「王」を参照。
曰(エツ)


(甲骨文)
論語で最も多用される、”言う”を意味する言葉。初出は甲骨文。原義は「𠙵」=「口」から声が出て来るさま。詳細は論語語釈「曰」を参照。
予(ヨ)

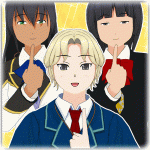
(金文)
論語の本章では”わたし”。初出は西周末期の金文で、「余・予をわれの意に用いるのは当て字であり、原意には関係がない」と『学研漢和大字典』はいうが、春秋末期までに一人称の用例がある。”あたえる”の語義では、現伝の論語で「與」となっているのを、定州竹簡論語で「予」と書いている。字形の由来は不明。金文では氏族名・官名・”わたし”の意に用い、戦国の竹簡では”与える”の意に用いた。詳細は論語語釈「予」を参照。
亂(ラン)


(金文)
論語の本章では、”よい”。新字体は「乱」。初出は西周末期の金文。ただし字形は「乚」を欠く「𤔔」。初出の字形はもつれた糸を上下の手で整えるさまで、原義は”整える”。のち前漢になって「乚」”へら”が加わった。それ以前には「司」や「又」”手”を加える字形があった。春秋時代までに確認できるのは、”おさめる”・”なめし革”で、”みだれる”と読めなくはない用例も西周末期にある。詳細は論語語釈「乱」を参照。
十(シュウ)


(甲骨文)
論語の本章では数字の”10”。初出は甲骨文。甲骨文の字形には二種類の系統がある。横線が「1」を表すのに対して、縦線で「10」をあらわしたものと想像される。「ト」形のものは、「10」であることの区別のため一画をつけられたものか。「ジュウ」は呉音。甲骨文から数字の”10”を意味した。詳細は論語語釈「十」を参照。
予有亂臣十人
論語の本章では、”わしによき家臣が十人いる”。既存の論語の解説書では、以下のように十人を挙げる。
- 文王の妃だった邑姜
- 後に摂政となった周公旦
- 同じく召公奭
- 武王の軍師の太公望
- 周の同族で革命戦争の際に護衛を務めた畢公
- 榮(栄)公
- 太顚
- 閎夭
- 散宜生は周の賢臣と言われる人
- 南宮适は同名の人物が孔子の弟子にいるが未詳。
ただしこれも史実の裏付けがある訳ではない。下図はみんな顔も格好もそっくりだ。区別がつかない。
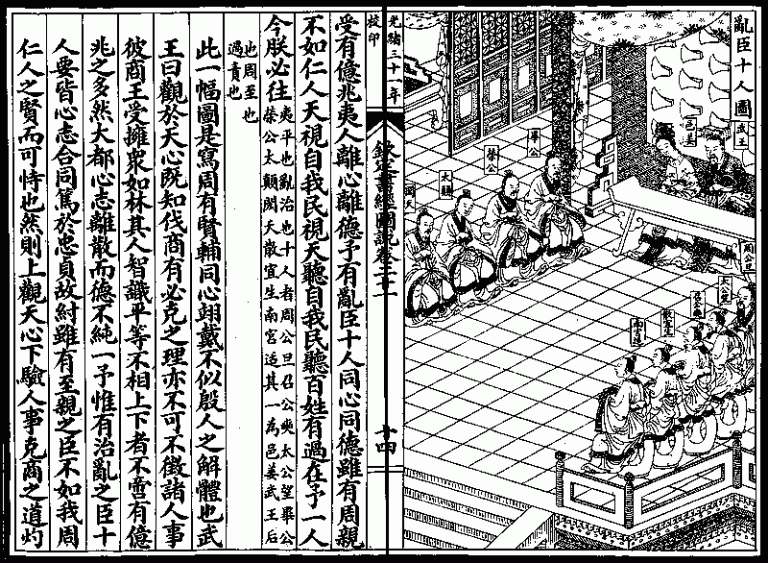
孔子(コウシ)

論語の本章では”孔子”。いみ名(本名)は「孔丘」、あざ名は「仲尼」とされるが、「尼」の字は孔子存命前に存在しなかった。BC551-BC479。詳細は孔子の生涯1を参照。
論語で「孔子」と記される場合、対話者が目上の国公や家老である場合が多い。
才(サイ)
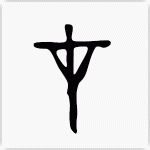

(甲骨文)
論語の本章では”有能な者”。初出は甲骨文。字形は地面に打ち付けた棒杭による標識の象形。原義は”存在(する)”。金文では「在」”存在”の意に用いる例が多い。春秋末期までの金文で、”才能”・”財産”・”価値”・”年”、また「哉」と釈文され詠嘆の意に用いた。戦国の金文では加えて”~で”の意に用いた。詳細は論語語釈「才」を参照。
難(ダン/ダ)
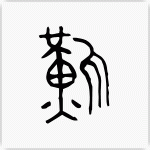

(金文)
論語の本章では”めったにない”。初出は西周末期の金文。新字体は「難」。「ダン」の音で”難しい”、「ダ」の音で”鬼遣らい”を意味する。「ナン」「ナ」は呉音。字形は「𦰩」”火あぶり”+「鳥」で、焼き鳥のさま。原義は”焼き鳥”。それがなぜ”難しい”・”希有”の意になったかは、音を借りた仮借と解する以外にない。西周末期の用例に「難老」があり、”長寿”を意味したことから、初出の頃から、”希有”を意味したことになる。詳細は論語語釈「難」を参照。
不(フウ)


(甲骨文)
漢文で最も多用される否定辞。初出は甲骨文。「フ」は呉音(遣隋使より前に日本に伝わった音)、「ブ」は慣用音。原義は花のがく。否定辞に用いるのは音を借りた派生義だが、甲骨文から否定辞”…ない”の意に用いた。詳細は論語語釈「不」を参照。
其(キ)


(甲骨文)
論語の本章では”その”という指示詞。初出は甲骨文。甲骨文の字形は「𠀠」”かご”。それと指させる事物の意。金文から下に「二」”折敷”または「丌」”机”・”祭壇”を加えた。人称代名詞に用いた例は、殷代末期から、指示代名詞に用いた例は、戦国中期からになる。詳細は論語語釈「其」を参照。
然(ゼン)


(金文)
論語の本章では”そうなる”。この語義は春秋時代では確認できない。初出は春秋早期の金文。「ネン」は呉音。初出の字形は「黄」+「火」+「隹」で、黄色い炎でヤキトリを焼くさま。現伝の字形は「月」”にく”+「犬」+「灬」”ほのお”で、犬肉を焼くさま。原義は”焼く”。”~であるさま”の語義は戦国末期まで時代が下る。詳細は論語語釈「然」を参照。
乎(コ)


(甲骨文)
論語の本章では”…ではないか”。詠歎を表す。この語義は春秋時代では確認できない。初出は甲骨文。論語の本章では形容詞・副詞についてそのさまを意味する接尾辞。この用例は春秋時代では確認できない。字形は持ち手の柄を取り付けた呼び鐘を、上向きに持って振り鳴らし、家臣を呼ぶさまで、原義は”呼ぶ”こと。甲骨文では”命じる”・”呼ぶ”を意味し、金文も同様で、「呼」の原字となった。句末の助辞として用いられたのは、戦国時代以降になるという。詳細は論語語釈「乎」を参照。
唐*(トウ)
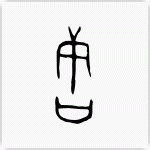
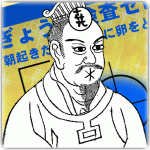
(甲骨文)
論語の本章では、架空の聖王・帝堯のこと。この語義は春秋時代では確認できない。前漢中期の『史記』以降、堯の氏は「陶唐氏」とされるのが確定した。初出は甲骨文。字形は「庚」”太陽を観測するさま”+「𠙵」”くち”。太陽に祈る姿だろうと想像されるが、原義ははっきりしない。甲骨文には大量の用例があるが、地名・人名・氏族名に用いた。金文でも同様だが、殷の開祖湯王を「唐」と記した例がある(春秋末期「叔尸鐘」集成285)。詳細は論語語釈「唐」を参照。を参照。
虞*(グ)→吴(ゴ)

論語の本章では、架空の聖王である舜の王朝の名。舜は舜王とも帝舜とも呼ぶ。この語義は春秋時代では確認できない。
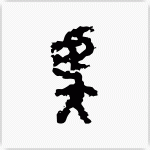

(金文)
「虞」の初出は西周早期の金文。字形は「虍」”トラの頭”+「人」。のち「𠙵」”くち”が加わる。「人」は正面形で、かつ首が曲がっている事から、身分ある者がトラに喰われるさまと見える。用例:西周早期「宜𥎦𣪕」(集成4320)に「乍虞公父丁彝」とあり、地名、人名と解せる。春秋末期までに、地名・人名に用い、また”長く”と解せなくもない用例がある。詳細は論語語釈「虞」を参照。
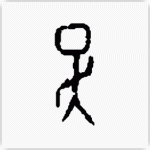

(甲骨文)
定州竹簡論語は「吴」と記す。初出は甲骨文。甲骨文の字形は手を振り上げた頭の大きな人。原義は未詳。異体字に「吳」。金文では「虞」で「吳」を記した例がある。甲骨文の用例は、破損がひどくて語義が明らかでない。金文では国名に用いた。詳細は論語語釈「呉」を参照。
「吴」は『大漢和辞典』に引く『姓氏急就篇』に「舜後封虞、虞・呉音相近、故舜後亦姓呉」とあるが、どうでもよろしい。要するに「虞」の略字である。
之(シ)


(甲骨文)
論語の本章では”…の”。初出は甲骨文。字形は”足”+「一」”地面”で、あしを止めたところ。原義はつま先でつ突くような、”まさにこれ”。殷代末期から”ゆく”の語義を持った可能性があり、春秋末期までに”~の”の語義を獲得した。詳細は論語語釈「之」を参照。
際(セイ)
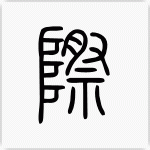

(篆書)
論語の本章では”その頃”。論語では本章のみに登場。初出は前漢中期の定州竹簡論語。論語の時代に存在しない。論語時代の置換候補もない。字形は「阝」”はしご”+「祭」で、天の祭りに天との通信路を開くこと。原義は”その時”。同音に「祭」、「穄」”くろきび”。「サイ」は呉音。詳細は論語語釈「際」を参照。
於(ヨ)


(金文)
論語の本章では”~で”。初出は西周早期の金文。ただし字体は「烏」。「ヨ」は”…において”の漢音(遣隋使・遣唐使が聞き帰った音)、呉音は「オ」。「オ」は”ああ”の漢音、呉音は「ウ」。現行字体の初出は春秋中期の金文。西周時代では”ああ”という感嘆詞、または”~において”の意に用いた。詳細は論語語釈「於」を参照。
斯(シ)


(金文)
論語の本章では、”その時代”。初出は西周末期の金文。字形は「其」”籠に盛った供え物を祭壇に載せたさま”+「斤」”おの”で、文化的に厳かにしつらえられた神聖空間のさま。意味内容の無い語調を整える助字ではなく、ある状態や程度にある場面を指す。例えば論語子罕篇5にいう「斯文」とは、ちまちました個別の文化的成果物ではなく、風俗習慣を含めた中華文明全体を言う。詳細は論語語釈「斯」を参照。
爲(イ)
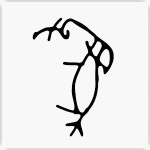

(甲骨文)
論語の本章では”…だとする”。新字体は「為」。字形は象を調教するさま。甲骨文の段階で、”ある”や人名を、金文の段階で”作る”・”する”・”…になる”を意味した。詳細は論語語釈「為」を参照。
盛*(セイ)
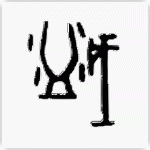

(甲骨文)
論語の本章では”栄えた”。初出は甲骨文。甲骨文の字形は「水」+「皿」+「戈」”カマ状のほこ”。犠牲をほふって血を皿に満たすさま。殷代の風習は血祭りを好んだので、転じて”高調した祭の雰囲気”の意。金文以降では「水」が省かれ、さらに「阝」”はしご”→”天界とやりとりする通路”が書き加えられた。春秋末期までに、”力が強い”・”新たに実った(穀物)”の意に用いた。詳細は論語語釈「盛」を参照。
婦*人(フウジン)
論語の本章では”女性”。論語の時代は一字一語が原則で、「婦」と言えば「人」に決まっているから、このような熟語は存在した可能性が極めて少ない。
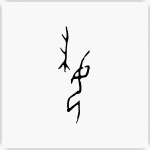

「婦」の初出は甲骨文。字形は「帚」”ほうき”+「女」。ほうきは主婦権の象徴。殷代の女性の地位は高く、王妃は政治・軍事に関わった。論語語釈「帰」も参照。「フ」は慣用音。呉音は「ブ」。甲骨文から”夫人”の意に用い、殷代末期~西周早期の金文では、「姑」とは別の概念だったと分かる。ただし春秋末期までの用例に、女性一般を意味するものは見つかっていない。詳細は論語語釈「婦」を参照。
焉(エン)
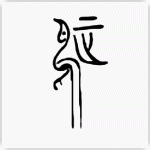

(金文)
論語の本章では「ぬ」と読んで、断定を意味することば。初出は戦国早期の金文で、論語の時代に存在せず、論語時代の置換候補もない。漢学教授の諸説、「安」などに通じて疑問辞と解するが、いずれも春秋時代以前に存在しないか、疑問辞としての用例が確認できない。ただし春秋時代までの中国文語は、疑問辞無しで平叙文がそのまま疑問文になりうる。
字形は「鳥」+「也」”口から語気の漏れ出るさま”で、「鳥」は装飾で語義に関係が無く、「焉」は事実上「也」の異体字。「也」は春秋末期までに句中で主格の強調、句末で詠歎、疑問や反語に用いたが、断定の意が明瞭に確認できるのは、戦国時代末期の金文からで、論語の時代には存在しない。詳細は論語語釈「焉」を参照。
九(キュウ)


(甲骨文)
論語の本章では数字の”9”。初出は甲骨文。字形は腕の象形で、のち音を借りて数字の「きゅう」を表した。原義は”ひじ”。甲骨文では原義で、また数詞に用い、金文や戦国の竹簡でも数詞に用いた。詳細は論語語釈「九」を参照。
已(イ)
論語の本章、「而已」では「やむ」と読んで”~で終わった”。「已矣」では「のみ」と読んで”~だけ”。
定州竹簡論語は「已」と釈文している。唐石経は「巳」と記す。清家本は「已」と記す。清家本の年代は唐石経より新しいが、より古い古注系の文字列を伝えており、唐石経を訂正しうる。また現存最古の論語本である定州竹簡論語が「已」を支持する。
唐代頃までは「巳」”へび”と「已」”すでに”と「己」”おのれ”は相互に異体字として通用した。従って本章でも異体字として扱った。論語の伝承について詳細は「論語の成立過程まとめ」を参照。
原始論語?…→定州竹簡論語→白虎通義→ ┌(中国)─唐石経─論語注疏─論語集注─(古注滅ぶ)→ →漢石経─古注─経典釈文─┤ ↓↓↓↓↓↓↓さまざまな影響↓↓↓↓↓↓↓ ・慶大本 └(日本)─清家本─正平本─文明本─足利本─根本本→ →(中国)─(古注逆輸入)─論語正義─────→(現在) →(日本)─────────────懐徳堂本→(現在)


(甲骨文)
「巳」の初出は甲骨文。字形はヘビの象形。「ミ」は呉音。甲骨文では干支の六番目に用いられ、西周・春秋の金文では加えて、「已」”すでに”・”ああ”・「己」”自分”・「怡」”楽しませる”・「祀」”まつる”の意に用いた。詳細は論語語釈「巳」を参照。


(甲骨文)
「已」の初出は甲骨文。字形と原義は不詳。字形はおそらく農具のスキで、原義は同音の「以」と同じく”手に取る”だったかもしれない。論語の時代までに”終わる”の語義が確認出来、ここから、”~てしまう”など断定・完了の意を容易に導ける。詳細は論語語釈「已」を参照。
三(サン)


(甲骨文)
論語の本章では数字の”3”。初出は甲骨文。原義は横棒を三本描いた指事文字で、もと「四」までは横棒で記された。「算木を三本並べた象形」とも解せるが、算木であるという証拠もない。詳細は論語語釈「三」を参照。
分*(フン)
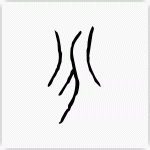

(甲骨文)
論語の本章では”分ける”。初出は甲骨文。字形は〔八〕”分ける”+「刀」。刃物で切り分けるさま。「フ」は慣用音。呉音は「ブ」。甲骨文の用例は欠損がひどくて語義を確定しがたい。一説に汾河周辺の地名に用いたという。西周の金文で”分ける”の意に用いたが、数量詞としての「分」は、戦国時代の「商鞅量」にならないと見られない。詳細は論語語釈「分」を参照。
二(ジ)
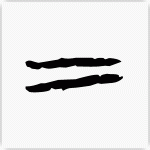

(甲骨文)
論語の本章では数字の”2”。初出は甲骨文。字形は「上」「下」字と異なり、上下同じ長さの線を引いた指事文字で、数字の”に”を示す。「ニ」は呉音。甲骨文・金文では数字の”2”の意に用いた。詳細は論語語釈「二」を参照。
以(イ)


(甲骨文)
論語の本章では”そして”。初出は甲骨文。人が手に道具を持った象形。原義は”手に持つ”。論語の時代までに、名詞(人名)、動詞”用いる”、接続詞”そして”の語義があったが、前置詞”~で”に用いる例は確認できない。ただしほとんどの前置詞の例は、”用いる”と動詞に解せば春秋時代の不在を回避できる。詳細は論語語釈「以」を参照。
服(フク)


(甲骨文)
論語の本章では”従う”。初出は甲骨文。字形は「凡」”たらい”+「卩」”跪いた人”+「又」”手”で、捕虜を斬首するさま。原義は”屈服させる”。甲骨文では地名に用い、金文では”飲む”・”従う”・”職務”の用例がある。詳細は論語語釈「服」を参照。
事(シ)


(甲骨文)
論語の本章では”奉仕する”。この語義は春秋時代では確認できない。初出は甲骨文。甲骨文の形は「口」+「筆」+「又」”手”で、口に出した言葉を、小刀で刻んで書き記すこと。つまり”事務”。「ジ」は呉音。詳細は論語語釈「事」を参照。
殷(イン)


(甲骨文)
論語の本章では”殷王朝”。殷はBC17CごろからBC1046まで中国を支配したとされる王朝で、たびたび都を変えた。後期の都である殷墟から甲骨文が出てきたので、漢字を発明した集団とされる。「殷」は他称で、”人の生きギモを取る残忍な奴ら”の意。自称は「商」で、”おおいなる都・国”を意味した。異民族を捕らえたり、服属国から献上を強いたりして、祭祀のたびに大量の人間を生け贄に投じたので、怨まれた末に西方の周に滅ぼされた。詳細は論語語釈「殷」を参照。
周(シュウ)
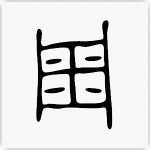

(甲骨文)
論語の本章では”周王朝”。初出は甲骨文。甲骨文の字形は彫刻のさま。原義は”彫刻”。金文の字形には下に「𠙵」”くち”があるものと、ないものが西周早期から混在している。甲骨文では諸侯としての”周”に用い、金文では「周」と「君」が相互に通用した可能性がある。春秋末期までに、人名・青銅器名に、また”たまをみがく”の意に用いた。ただし同音から、”おわる”、”掃く・ほうき”、”奴隷・人々”、”祈る(人)”、”捕らえる”の語義はありうる。詳細は論語語釈「周」を参照。
德(トク)
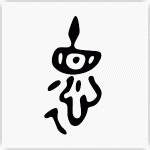

(金文)
論語の本章では”能力”。初出は甲骨文。新字体は「徳」。甲骨文の字形は、〔行〕”みち”+〔丨〕”進む”+〔目〕であり、見張りながら道を進むこと。甲骨文で”進む”の用例があり、金文になると”道徳”と解せなくもない用例が出るが、その解釈には根拠が無い。前後の漢帝国時代の漢語もそれを反映して、サンスクリット語puṇyaを「功徳」”行動によって得られる利益”と訳した。孔子生前の語義は、”能力”・”機能”、またはそれによって得られる”利得”。詳細は論語における「徳」を参照。文字的には論語語釈「徳」を参照。
可(カ)


「可」(甲骨文)
論語の本章では”…できる”。初出は甲骨文。字形は「口」+「屈曲したかぎ型」で、原義は”やっとものを言う”こと。甲骨文から”…できる”を表した。日本語の「よろし」にあたるが、可能”~できる”・勧誘”~のがよい”・当然”~すべきだ”・認定”~に値する”の語義もある。詳細は論語語釈「可」を参照。
謂(イ)


(金文)
論語の本章では”…だと評価する”。本来、ただ”いう”のではなく、”~だと評価する”・”~だと認定する”。現行書体の初出は春秋後期の石鼓文。部品で同義の「胃」の初出は春秋早期の金文。金文では氏族名に、また音を借りて”言う”を意味した。戦国の竹簡になると、あきらかに”~は~であると言う”の用例が見られる。詳細は論語語釈「謂」を参照。
至(シ)
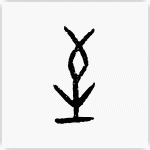

(甲骨文)
論語の本章では”至った頂点”。甲骨文の字形は「矢」+「一」で、矢が届いた位置を示し、”いたる”が原義。春秋末期までに、時間的に”至る”、空間的に”至る”の意に用いた。詳細は論語語釈「至」を参照。
也(ヤ)


(金文)
論語の本章では、「なり」と読んで断定の意に用いている。この語義は春秋時代では確認できない。初出は事実上春秋時代の金文。字形は口から強く語気を放つさまで、原義は”…こそは”。春秋末期までに句中で主格の強調、句末で詠歎、疑問や反語に用いたが、断定の意が明瞭に確認できるのは、戦国時代末期の金文からで、論語の時代には存在しない。詳細は論語語釈「也」を参照。
矣(イ)


(金文)
論語の本章では、”(きっと)~である”。初出は殷代末期の金文。字形は「𠙵」”人の頭”+「大」”人の歩く姿”。背を向けて立ち去ってゆく人の姿。原義はおそらく”…し終えた”。ここから完了・断定を意味しうる。詳細は論語語釈「矣」を参照。
也已矣(ヤイイ)
逐語訳すれば「であるに、なりきって、しまった」。アルツハイマーに脳をやられた大隈重信が、演説で「あるんであるんである」と言ったように、もったいの上にもったいを付けたバカバカしい言葉。断定を示したいなら「也」「已」「矣」のどれか一字だけで済む。
つまり「也已矣」以前がうそデタラメだから、大げさに言って読む者聞く者をびっくりさせ、信じさせてしまおうという、見え透いた悪辣の表現。


漢文業界では「也已」の二字で「のみ」と訓読する座敷わらしだが、確かに「也已」は”であるになりきった”の意だから「のみ」という限定に読めなくはないが、それは正確な漢文の翻訳ではない。意味の分からない字を「置き字」といって無視するのと同じ、平安朝の漢文を読めないおじゃる公家以降、日本の漢文業者が世間を誤魔化し思考停止し続けた結果で、現代人が真似すべき風習ではない。
曹銀晶「談《論語》中的”也已矣”連用現象」(北京大学)によると、「也已矣」は前漢宣帝期の定州論語では、そもそもそんな表現は無いか、「矣」「也」「也已」と記されたという。要するに、漢帝国から南北朝にかけての儒者が、もったいを付けて幼稚なことを書いたのだ。
論語:付記
検証
論語の本章は、前漢中期の定州竹簡論語にあるから、その頃までには論語の一章として成立していたことになるが、再録や引用は、後漢の徐幹『中論』まで下り、それ以外には先秦両漢では後漢から南北朝にかけて編まれた『後漢書』にしか見られない。
賢者稱於人也,非以力也;力者必須多,而知者不待眾也。故王七萬,而輔佐六卿也。故舜有臣五人而天下治,周有亂臣十人而四海服,此非用寡之驗歟!
賢者が人を讃えるのは、能力があるからではない。能のある者は大勢居るだろうが、知者は大勢を当てにしないものだ。だから天下の王者は七万の文武百官を抱えながら、じかに相談するのは六人の閣僚に過ぎない。だから舜は五人の家臣だけで天下を治めきり、周には十人の賢臣がいるだけで全世界が従った。これこそ、少数精鋭の効果というものか!(『中論』亡国4)
光和二年…時連有災異,郎中梁人審忠以為朱瑀等罪惡所感,乃上書曰:「臣聞理國得賢則安,失賢則危,故舜有臣五人而天下理,湯舉伊尹不仁者遠。」
光和二年(179)、この時天変地異が相次ぎ、宮内官で河南省出身の審忠が、権勢を振るっていた朱瑀らが悪いせいだと考え、次のように上奏した。「やつがれが聞きますところによると、国政には賢者を用いれば安定するといいます。ですから為政者が賢者でないと乱れる道理です。だから舜は五人の賢者を用いるだけで天下が安定し、湯王が賢者の伊尹を用いると、人でなしどもが御殿から逃げ出した(論語顔淵篇22)と言います。」(『後漢書』宦者伝49)
論語の本章の創作が、前漢時代であるのはほぼ確定だが、創作動機は前章同様、この泰伯編を膨らませたかったからか、あるいは自説を論語にねじ込んで、金儲けのタネにしようとしたかのいすれかだろう。
解説
論語の本章、新古の注は次の通り。
古注『論語集解義疏』舜有臣五人而天下治註孔安國曰禹稷契臯陶伯益也武王曰予有亂臣十人註馬融曰亂理也理官者十人也謂周公旦召公奭太公望畢公榮公大顛閎夭散宜生南宫适其餘一人謂文母也孔子曰才難不其然乎唐虞之際於斯為盛有婦人焉九人而已註孔安國曰唐者堯號也虞者舜號也際者堯舜交㑹之間也斯此也此此於周也言堯舜交㑹之問比於此周周最盛多賢才然尚有一婦人其餘九人而已大才難得豈不然乎參分天下有其二以服事殷周徳其可謂至徳也已矣註苞氏曰殷紂淫亂文王為西伯而有聖徳天下之歸周者三分有二而猶以服事殷故謂之至徳也
本文。「舜有臣五人而天下治。」
注釈。孔安国「五人とは、禹、稷、契、臯陶、伯益である。」
本文。「武王曰予有亂臣十人。」
注釈。馬融「亂とは整えることである。公務を統制したのが十人だったというのである。うちわけは、周公旦、召公奭、太公望、畢公、榮公、大顛、閎夭、散宜生、南宫适と、さらに一人は文母(文王の母?)である。
本文「孔子曰才難不其然乎唐虞之際於斯為盛有婦人焉九人而已。」
注釈。孔安国「唐とは堯の名乗りである。虞は舜の名乗りである。際とは堯と舜がこもごも君主だった期間をいう。斯とは”これ”の意である。此とは、”周については”の意である。堯と舜の在位時代が周と比べてもより栄えた時代だったというのである。賢臣も多くて、そこには婦人も混じっていた。それ以外は九人だけしたというのである。
本文。「才難得豈不然乎參分天下有其二以服事殷周徳其可謂至徳也已矣。」
注釈。包咸「殷は紂王の時代に政治が乱れて、文王は西方の諸侯のかしらだった。しかも神聖な道徳を備えていたので天下の諸侯で周に従う者が三分の二になった。それでも文王は殷に従い奉仕していたが、まことに道徳の頂点と言うべきである。」
新注『論語集注』
舜有臣五人而天下治。治,去聲。五人,禹、稷、契、皋陶、伯益。武王曰:「予有亂臣十人。」書泰誓之辭。馬氏曰:「亂,治也。」十人,謂周公旦、召公奭、太公望、畢公、榮公、太顛、閎夭、散宜生、南宮适,其一人謂文母。劉侍讀以為子無臣母之義,蓋邑姜也。九人治外,邑姜治內。或曰:「亂本作乿,古治字也。」孔子曰:「才難,不其然乎?唐虞之際,於斯為盛。有婦人焉,九人而已。稱孔子者,上係武王君臣之際,記者謹之。才難,蓋古語,而孔子然之也。才者,德之用也。唐虞,堯舜有天下之號。際,交會之間。言周室人才之多,惟唐虞之際,乃盛於此。降自夏商,皆不能及,然猶但有此數人爾,是才之難得也。三分天下有其二,以服事殷。周之德,其可謂至德也已矣。」春秋傳曰,「文王率商之畔國以事紂」,蓋天下歸文王者六州,荊、梁、雍、豫、徐、揚也。惟青、論、冀,尚屬紂耳。范氏曰:「文王之德,足以代商。天與之,人歸之,乃不取而服事焉,所以為至德也。孔子因武王之言而及文王之德,且與泰伯,皆以至德稱之,其指微矣。」或曰:「宜斷三分以下,別以孔子曰起之,而自為一章。」
本文「舜有臣五人而天下治。」
治は尻下がりに読む。五人とは、禹、稷、契、皋陶、伯益。である。
本文「武王曰予有亂臣十人。」
この言葉は、書経の泰誓篇に載っている。馬融は「亂とは治まることだ」といった。十人とは、周公旦、召公奭、太公望、畢公、榮公、太顛、閎夭、散宜生、南宮适に加え、もう一人を文母という。劉侍の言い分では、子が母親を臣下にするなどとんでもないから、文母とは武王の母で文王の妻だった人でなく、武王の妃の邑姜だろう。九人が政務・軍務を取り仕切り、邑姜が王室を取り仕切った。ある人「亂の字はむかし乿と書き、いにしえの”治まる”の意だ。」
本文。「孔子曰:才難,不其然乎?唐虞之際,於斯為盛。有婦人焉,九人而已。」
ここで孔子を持ち出したのは、武王の君臣関係を書き記すにあたり、本章の作者がじかに記すのは畏れ多かったからだ。才難とは、たぶん昔の言葉だろう。そして孔子は才難をその通りだと認めた。才とは、道徳の実践例である。唐虞とは、堯舜が天下を治めていたときの王朝名である。際とは、こもごもあった間、の意である。周の家臣には人材が多かったが、唐虞の時代はそれよりも世が栄えていたと言うのである。夏や殷の時代になると、唐虞時代ほどの人物は現れず、人口は増えたが賢者はめったに居なかったというのである。
本文。「三分天下有其二,以服事殷。周之德,其可謂至德也已矣。」
春秋伝に言う。「文王は殷に背いた諸侯を従えながら、なお殷に服属していた。」多分天下で文王に従ったのは、中国全土九州のうち六州、すなわち荊、梁、雍、豫、徐、揚州だろう。しかし青、論、冀州は、なお紂王に従っていた。
范祖禹「文王の道徳は、殷に取って代わる資格があったしかも天が味方し、ひとが従った。それでも天下取りをせず殷に従った。だから究極の道徳だと評価できるのである。孔子は武王の言葉で文王の道徳を讃え、また泰伯についても道徳を讃えた(論語泰伯編1)。言葉は少ないが意味するところは大きい。」
ある人「”三分”以下はここで章を切って、”孔子曰”から新しい章と見なし、一章として独立させるべきである。」
余話
みな死んだ方が
論語の本章、上掲新注には「おや」と思える点がある。オカルトの張本人だった朱子までが、本章の史実性を疑っている点で、「稱孔子者,上係武王君臣之際,記者謹之。」は「孔子を称うるは、武王君臣の際に係るを上い、記す者これを謹めばなり」と訓読した。
- 論語雍也篇3余話「宋儒のオカルトと高慢ちき」
帝政中国史は、ゴマすり者ばかりの臣下と、たいていは常人未満の知能しか持たない皇帝が、普段は偽善極まる奉納芝居を演じた走馬灯ゆえに、馬鹿馬鹿しい「謹み」がまかり通った。司馬遷と漢の武帝もその例である。詳細は論語雍也篇11余話「生涯現役幼児の天子」を参照。
皇帝など畏れるべき対象を記述する際、枠の上にはみ出して書く座敷わらしもその一つ。詳細は二・二六事件叛乱軍蹶起趣意書:現代語訳・訳注を参照。だから奉納芝居だというのだが、それでも他の人類圏と違い、漢以降は君臣の間でも、不死というトンデモは言わなかった。
その理由を中国人が現実主義だから、と言うのは説明にならない。「ナントカ主義ですか。はあそうですか」と納得する人がいるわけないからだ。それより、庶民・役人・皇帝にかかわらず、中国人は一生に一度は「死んだ方がまし」という目に遭ったからだと言った方がいい。
おそらく蒸気機関の発明まで、中国は人類の最先端技術大国でもあったが、それでもマルサスの呪いから自由でなく、稼ぐ以上に子供をぽこぽこ作ったから、生涯に何度か飢餓を経験するのが常だった。時に帝室も例外でなく、仮に例外でもなお帝室内部は親子兄弟で殺し合う。
唐の高宗と言えば王朝の最大版図を誇った君主だが、そのかみさんである則天武后は、自分の地位向上のためなら平気で自分の赤ん坊を殺した。規模を変えれば官僚の出身母体でもある各地方の大地主も同様で、だから誰もが「死んだ方がまし」という経験を持つわけだ。
それゆえ現皇帝の死も、やがて当然にくるであろうと思っていた。ただし「謹み」はしたから、臣下が皇帝の死後をうんぬんする時、「陛下万歳ののち」という言い方をする。人も亀も万年も生きるわけが無いが、そこは奉納芝居ゆえの演出で、目くじら立てるには及ばない。
「万歳」の漢音は「バンセイ」で、「バンザイ」は漢音+呉音「サイ」のなまり。「マンザイ」はさらに慣用音+呉音のなまり。この言葉が日本語化したのは新しく、明治になってから天皇を讃えるのに、呉音漢音の区別がつかない帝大教授が発案したらしい(→wiki)。
もっとも、天皇の即位式に「萬歳」のノボリを立てるのは、訳者が知る限り遅くとも江戸期の画像に描かれている。ただし早くても漢文読みが朝廷に出入りし始めた、天武・持統朝(論語述而篇19余話「せせら笑う漢文書き」)よりさかのぼれはしないだろう。だがどうでもいい。
この言葉で多くの日本人が、永の別れをしたのを覚えている。六月二十三日記す。

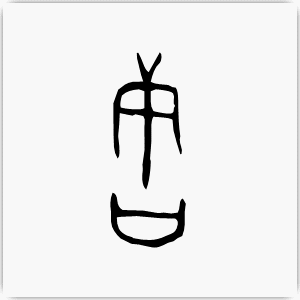

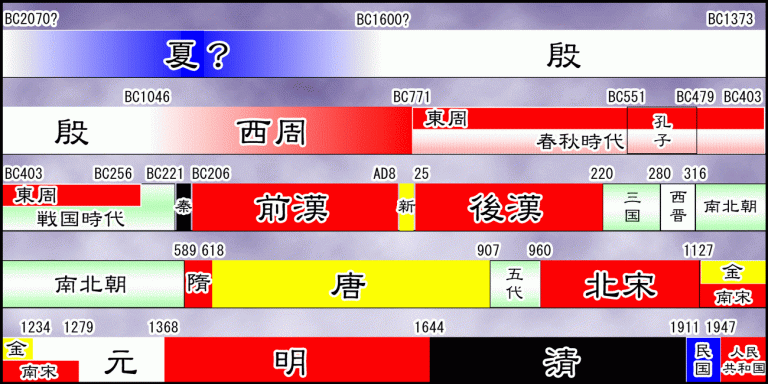


コメント