論語:原文・書き下し
原文(唐開成石経)
樊遟問仁子曰愛人問知子曰知人樊遲未達子曰舉直錯諸枉能使枉者直樊遲退見子夏曰郷也吾見於夫子而問知子曰舉直錯諸枉能使枉者直何謂也子夏曰富哉言乎舜有天下選於衆舉皋陶不仁者逺矣湯有天下選於衆舉伊尹不仁者逺矣
※「選」字は〔己〕ではなく〔巳〕。
校訂
諸本
東洋文庫蔵清家本
遅遟遅問仁子曰愛人問智子曰知人樊遅未達子曰舉𥄂錯諸抂能使抂者𥄂/樊遅退見子复曰嚮也吾見於夫子而問智子曰舉𥄂錯諸抂能使抂者𥄂何謂也子复曰富哉是言乎/舜有天下選於衆舉皋陶不仁者逺矣湯有天下選於衆舉伊尹不仁者逺矣
後漢熹平石経
(なし)
定州竹簡論語
(なし)
標点文
樊遲問仁。子曰、「愛人。」問「智」。子曰、「知人。」樊遲未達、子曰、「舉直錯諸枉、能使枉者直。」樊遲退、見子夏曰、「嚮也吾見於夫子而問智、子曰、舉直錯諸枉、能使枉者直、何謂也。」子夏曰、「富哉是言乎。舜有天下、選於衆舉皋陶、不仁者遠矣。湯有天下、選於衆舉伊尹、不仁者遠矣。」
復元白文(論語時代での表記)





















 錯
錯 枉
枉 
 枉
枉





















 錯
錯 枉
枉 
 枉
枉











 舜
舜




























※仁→(甲骨文)・愛→哀・舉→居・富→(甲骨文)・嚮→鄕・皋→(古文)。論語の本章は、赤字が論語の時代に存在せず、「舜」の概念も存在しない。「問」「未」「直」「鄕(嚮)」「何」「謂」「乎」の用法に疑問がある。本章は戦国時代以降の儒者による創作である。
書き下し
樊遲仁を問ふ。子曰く、人を愛せよ。智を問ふ。子曰く、人を知れ。樊遲未た達らず。子曰く、直きを擧げて諸枉れるに錯かば、枉れる者を使て直からしむるを能ふと。樊遲退き、子夏を見て曰く、嚮也吾夫子於見え而智を問ふ、子曰く、直きを擧げて諸枉れるに錯かば、枉れる者を使て直からしむるを能ふと。何の謂ぞ也。子夏曰く、富める哉言乎。舜天下を有ち、衆於選んで皋陶を擧げて、不仁者遠ざかれ矣。湯天下を有ち、衆於選んで伊尹を擧げて、不仁者遠ざかれ矣。
論語:現代日本語訳
逐語訳
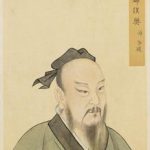

樊遅が常時無差別の愛(仁)を質問した。先生が言った。「人を愛しなさい。」智を問うた。先生が言った。「人を知りなさい。」樊遅には分からなかった。先生が言った。「正直者を一人、悪党どもの上に据えれば、悪党どもも真人間になる。」樊遅は先生の前を下がって、子夏に出会ったので言った。「今、先生に智を質問したら、先生は、正直者を一人、悪党どもの上に据えれば、悪党どもも真人間になると仰った。何を言っているのだろうね。」子夏が言った。「含みに富んだお言葉ですね。舜が天下を取ってから、みんなの意見を聞いて皋陶を高い地位に就けたら、人でなしが遠ざかりました。殷の湯王が天下を取ってから、みんなの意見を聞いて伊尹を高い地位に就けたら、人でなしが遠ざかりました。」
意訳
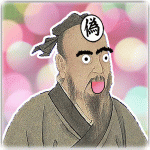

樊遅「仁とは何ですか。」
孔子「人を愛する事だよ。」
樊遅「智とは何ですか。」
孔子「他人を理解してあげる事だよ。」
樊遅「??」
孔子「正直者を、悪党のかしらに据えると、悪党も真人間になる。」
樊遅「はぁ。そうですか。」
樊遅が首をかしげながら孔子の部屋を出ると、年下だが弟子としては先輩の子夏に出会った。
樊遅「子夏くん、いい所へ来てくれたね。どうか教えて貰えまいか。いま先生に智を尋ねたんだが、かくかくしかじかとお答えになった。どういうことだろうね。」
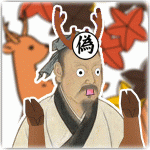
子夏「そうでしたか兄者。さすがに含みのある先生のお言葉ですね。私が思うにこういうことです。太古、聖王の舜が天下を取って、正直者の皋陶をお目付役にしました。殷の湯王も、正直者の伊尹をお目付役にしました。すると人でなしどもが、お館から逃げ出したそうです。昔の偉い王様は、人を見る目、悪党の追い出し方、これらを知っていたんですね。」
従来訳
樊遅が仁の意義をたずねた。先師はこたえられた。
「人間を愛することだ。」
樊遅がさらに知の意義をたずねた。先師はこたえられた。――
「人間を知ることだ。」
樊遅はまだよくのみこめないでいた。すると先師がいわれた。――
「まっすぐな人を挙用して、まがった人の上におくと、まがった人も自然に正しくなるものだ。」
樊遅は室を出たが、子夏を見るとすぐたずねた。――
「さきほど、私は先生にお会いして、知についておたずねしました。すると先生は、まっすぐな人を挙用して、まがった人の上におくと、まがった者も自然に正しくなる、といわれましたが、これはどういう意味でございましょうか。」
子夏がこたえた。――
「含蓄の深いお言葉だ。昔、舜帝が天下を治めた時、衆人の中から賢人皐陶を挙げて宰相に任じたら、不仁者がすがたをひそめたのだ。また殷の湯王が天下を治めた時、衆人の中から賢人伊尹を挙げて宰相に任じたら、不仁者がすがたをひそめたのだ。」下村湖人『現代訳論語』
論語:語釈
樊 遲 問「仁」。子 曰、「愛 人。」問「智(知)」。子 曰、「知 人。」樊 遲 未 達、子 曰、「舉 直 錯 諸 枉(抂)、能 使 枉(抂) 者 直。」樊 遲 退、見 子 夏 曰、「嚮(郷) 也 吾 見 於 夫 子 而 問『智(知)』、子 曰、『舉 直 錯 諸 枉(抂)、能 使 枉(抂) 者 直』、何 謂 也。」子 夏 曰、「富 哉 言 乎 舜 有 天 下、選 於 眾、舉 皋 陶、不 仁 者 遠 矣。湯 有 天 下、選 於 眾、舉 伊 尹、不 仁 者 遠 矣。」
樊遲(ハンチ)
孔子の弟子、『史記』によると孔子より36年少。おそらくは子路が仕官してのち、身辺警護を樊遅が務めたと思われる。哀公十一年(BC484)の対斉防衛戦では、武勲を挙げている。詳細は論語の人物:樊須子遅を参照。
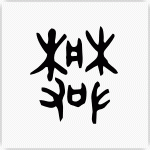

「樊」(金文)
「樊」の初出は西周早期の金文。金文の字形は早くは「口」を欠く。字形は「棥」”垣根”+「又」”手”二つで、垣根を作るさま。金文では人名に用いた。詳細は論語語釈「樊」を参照。


「遲」(甲骨文)
「遲」の初出は甲骨文。新字体は「遅」。唐石経・清家本は、異体字「遟」(〔尸〕の下が〔辛〕)と記す。現行字体に繋がる字形は〔辶〕+「犀」で、”動物のサイ”。字形に「牛」が入るようになったのは後漢の『説文解字』からで、それまでの「辛」を書き間違えたと思われる。詳細は論語語釈「遅」を参照。
問(ブン)


(甲骨文)
論語の本章では”問う”。この語義は春秋時代では確認できない。初出は甲骨文。「モン」は呉音(遣隋使より前に日本に伝わった音)。字形は「門」+「口」。甲骨文での語義は不明。西周から春秋に用例が無く、一旦滅んだ漢語である可能性がある。金文では人名に用いられ、”問う”の語義は戦国時代の竹簡以降になる。詳細は論語語釈「問」を参照。
仁(ジン)


(甲骨文)
論語の本章では、”天下万物に対する無差別の愛”。この語義は孔子没後一世紀後に現れた孟子による、「仁義」の語義であり、孔子や高弟の口から出た「仁」の語義ではない。本章は文字史から後世の偽作が確定するので、「仁義」の意に解してよい。
字形や音から推定できる春秋時代の語義は、敷物に端座した”よき人”であり、”貴族”を意味する。詳細は論語における「仁」を参照。初出は甲骨文。字形は「亻」”ひと”+「二」”敷物”で、原義は敷物に座った”貴人”。詳細は論語語釈「仁」を参照。
子曰(シエツ)(し、いわく)

論語の本章では”孔子先生が言った”。「子」は貴族や知識人に対する敬称で、論語では多くの場合孔子を指す。この二文字を、「し、のたまわく」と読み下す例がある。「言う」→「のたまう」の敬語化だが、漢語の「曰」に敬語の要素は無い。古来、論語業者が世間からお金をむしるためのハッタリで、現在の論語読者が従うべき理由はないだろう。


「子」(甲骨文)
「子」は貴族や知識人に対する敬称。初出は甲骨文。字形は赤ん坊の象形で、古くは殷王族を意味した。春秋時代では、貴族や知識人への敬称に用いた。孔子のように学派の開祖や、大貴族は、「○子」と呼び、学派の弟子や、一般貴族は、「子○」と呼んだ。詳細は論語語釈「子」を参照。


(甲骨文)
「曰」は論語で最も多用される、”言う”を意味する言葉。初出は甲骨文。原義は「𠙵」=「口」から声が出て来るさま。詳細は論語語釈「曰」を参照。
愛(アイ)


(金文)
論語の本章では”愛する”。初出は戦国末期の金文。一説には戦国初期と言うが、それでも論語の時代に存在しない。同音字は、全て愛を部品としており、戦国時代までしか遡れない。
「愛」は爪”つめ”+冖”帽子”+心”こころ”+夂”遅れる”に分解できるが、いずれの部品も”おしむ・あいする”を意味しない。孔子と入れ替わるように春秋時代末期を生きた墨子は、「兼愛非行」を説いたとされるが、「愛」の字はものすごく新奇で珍妙な言葉だったはず。
ただし同訓近音に「哀」があり、西周初期の金文から存在し、回り道ながら、上古音で音通する。論語の時代までに、「哀」には”かなしい”・”愛する”の意があった。詳細は論語語釈「愛」を参照。
人(ジン)


(甲骨文)
論語の本章では”他人”。自分以外の全ての人。初出は甲骨文。原義は人の横姿。「ニン」は呉音。甲骨文・金文では、人一般を意味するほかに、”奴隷”を意味しうる。対して「大」「夫」などの人間の正面形には、下級の意味を含む用例は見られない。詳細は論語語釈「人」を参照。
知(チ)→智(チ)


(甲骨文)
論語の本章では”知る”。現行書体の初出は春秋早期の金文。春秋時代までは「知」は「智」と区別せず書かれた。甲骨文で「知」・「智」に比定されている字形には複数の種類があり、原義は”誓う”。春秋末期までに、”知る”を意味した。”知者”・”管掌する”の用例は、戦国時時代から。詳細は論語語釈「知」を参照。
定州竹簡論語は、普段は「智」の異体字「𣉻」と記す。二つの字形の違いによる、語義の違いは知る手がかりがぜんぜん無い。いずれ漢儒のもったい付けで、大きな寺の坊主が読み上げている経本が、たいていキンキラキンに飾られているのと同じ、大した理由はありそうに無い。
通例、清家本は「知」と記し、正平本も「知」と記す。文字的には論語語釈「智」を参照。
未(ビ)


(甲骨文)
論語の本章では”まだ…ない”。この語義は春秋時代では確認できない。初出は甲骨文。「ミ」は呉音。字形は枝の繁った樹木で、原義は”繁る”。ただしこの語義は漢文にほとんど見られず、もっぱら音を借りて否定辞として用いられ、「いまだ…ず」と読む再読文字。ただしその語義が現れるのは戦国時代まで時代が下る。詳細は論語語釈「未」を参照。
達(タツ)


(甲骨文)
論語の本章では”そこに至る”→”理解する”。初出は甲骨文。甲骨文の字形は↑+「止」”あし”で、歩いてその場にいたるさま。原義は”達する”。甲骨文では人名に用い、金文では”討伐”の意に用い、戦国の竹簡では”発達”を意味した。詳細は論語語釈「達」を参照。
舉(キョ)


(金文)
論語の本章では”上に乗せる”。論語為政篇19(偽作)に「舉直錯諸枉」という全く同じ句が出るが、為政篇では殿さまに孔子が答えた君主としての心得だから、”真っ直ぐな者を曲がった者の上司に据えなさい”と解せるが、下級士族に過ぎない樊遅に大した人事権などありそうにない。
新字体は「挙」。初出は戦国末期の金文。論語の時代に存在しない。初出の字形は「與」(与)+「犬」で、犬を犠牲に捧げるさま。原義は恐らく”ささげる”。論語時代の置換候補は、”あげる”・”あがる”の意で近音の「喬」、”おく・すまわせる”の意で同音の「居」。詳細は論語語釈「挙」を参照。
直(チョク)


(甲骨文)
論語の本章では”正直者”。この語義は春秋時代では確認できない。初出は甲骨文。論語の本章では欠いているが、定州竹簡論語では異体字「𥄂」と記す。「ジキ」は呉音。甲骨文の字形は「丨」+「目」で、真っ直ぐものを見るさま。原義は”真っ直ぐ見る”。甲骨文では祭礼の名に、金文では地名に、戦国の竹簡では「犆」”去勢した牡牛”の意に、「得」”~できる”の意に用いられた。詳細は論語語釈「直」を参照。
錯(サク)
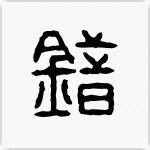

(秦系戦国文字)
論語の本章では”おく”。初出は戦国時代の金文。論語の時代に存在せず、論語時代の置換候補もない。”おく”意味での発音は去声(尻すぼみの銚子)、”まじえる”の意味での発音は入声。現伝の字形は「金」+「昔」だが、この字形に定まる後漢より以前の字形は、つくりが明らかに「昔」ではなく、何を表しているかは分からない。詳細は論語語釈「錯」を参照。
諸(ショ)


(秦系戦国文字)
論語の本章では”さまざまな”。論語の時代では、まだ「者」と「諸」は分化していない。「者」の初出は西周末期の金文。ごんべんのある現行字体の初出は秦系戦国文字。金文の字形は「者」だけで”さまざまな”の意がある。「者」も春秋時代までにその用例がある。「之於」(シヲ)と音が通じるので「…を…に」を意味する合字とされるが、言い出したのは清儒で、例によって全く根拠を言っておらず、真に受ける必要はまるで無い。詳細は論語語釈「諸」を参照。
枉(オウ)・抂(オウ)
唐石経は「枉」と記し、東洋文庫蔵清家本は「抂」と記す。時系列からは唐石経の方が古いが、唐朝廷の都合でそれまでの文字列を書き換えた箇所が少なからずある。清家本は時代が下るが、遅くとも隋代に日本へ輸入された古注系の文字列を伝承しており、唐石経より古い文字列を保存していると想像できる。従って清家本により「抂」と校訂すべきだが、「抂」字の初出は北宋で、明らかに唐石経より新しい。従って校訂しなかった。
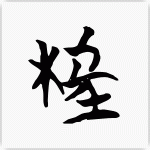

(楚系戦国文字)
論語の本章では”曲げる・悪用する”。初出は戦国文字で、論語の時代に存在しない。論語時代の置換候補もない。同音別漢字は存在しない。字形は「木」+「㞷」”はびこる”で、樹木が群がりしげるさま。原義は”まがる”とされている。詳細は論語語釈「枉」を参照。
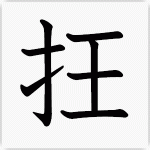

(楷書)
「抂」字について『新漢語林』は「枉の俗字」と片づける。初出は北宋の『集韻』。「キョウ」の音で「狂」と同じく”乱れる”の意、「オウ」の音で「枉」と同じく”まがる”・”まげる”の意。詳細は論語語釈「抂」を参照。
舉直錯諸枉(なほきをあげてもろまがれるにおかば)
舉(V)直(O),錯(V)諸枉(O)の複文。直”まじめな者一人”を舉”昇格させて”、諸”複数の”枉”曲がった者”の上に錯”据える”の意。
能(ドウ)


(甲骨文)
論語の本章では”~できる”。字の初出は甲骨文。「ノウ」は呉音。原義は鳥や羊を煮込んだ栄養満点のシチューを囲んだ親睦会で、金文の段階で”親睦”を意味し、また”可能”を意味した。詳細は論語語釈「能」を参照。


「能~」は「よく~す」と訓読するのが漢文業界の座敷わらしだが、”上手に~できる”の意と誤解するので賛成しない。読めない漢文を読めるとウソをついてきた、大昔に死んだおじゃる公家の出任せに付き合うのはもうやめよう。
使(シ)(…しむ)


(甲骨文)
論語の本章では”~させる”。初出は甲骨文。甲骨文の字形は「事」と同じで、「口」+「筆」+「手」、口に出した事を書き記すこと、つまり事務。春秋時代までは「吏」と書かれ、”使者(に出す・出る)”の語義が加わった。のち他動詞に転じて、つかう、使役するの意に専用されるようになった。詳細は論語語釈「使」を参照。
者(シャ)


(金文)
論語の本章では”…のような者”。新字体は「者」(耂と日の間に点が無い)。ただし唐石経・清家本ともに新字体と同じく「者」と記す。初出は殷代末期の金文。金文の字形は「木」”植物”+「水」+「口」で、”この植物に水をやれ”と言うことだろうか。原義は不明。初出では称号に用いている。春秋時代までに「諸」と同様”さまざまな”、”~する者”・”~は”の意に用いた。漢文では人に限らず事物にも用いる。詳細は論語語釈「者」を参照。
退(タイ)


(甲骨文)
論語の本章では”(孔子の面前から)下がる”。初出は甲骨文。甲骨文の字形は「豆」”食物を盛るたかつき”+「夊」”ゆく”で、食膳から食器をさげるさま。原義は”さげる”。金文では辶または彳が付いて”さがる”の意が強くなった。甲骨文では祭りの名にも用いられた。詳細は論語語釈「退」を参照。
見(ケン)


(甲骨文)
論語の本章では”見る”→”顔を合わせる”、会うこと。初出は甲骨文。甲骨文の字形は、目を大きく見開いた人が座っている姿。原義は”見る”。甲骨文では原義のほか”奉る”に、金文では原義に加えて”君主に謁見する”(麥方尊・西周早期)、”…される”(沈子它簋・西周)の語義がある。詳細は論語語釈「見」を参照。
子夏(シカ)
孔子の弟子。本の虫、カタブツとして知られ、文学に優れると孟子に評された(孔門十哲の謎)、孔門十哲の一人。主要弟子の中では若年組に属する。詳細は論語の人物:卜商子夏を参照。

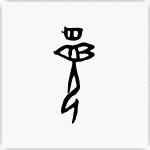
(甲骨文)
「夏」の初出は甲骨文。甲骨文の字形は「日」”太陽”の下に目を見開いてひざまずく人「頁」で、おそらくは太陽神を祭る神殿に属する神官。甲骨文では占い師の名に用いられ、金文では人名のほか、”中華文明圏”を意味した。また川の名に用いた。詳細は論語語釈「夏」を参照。
鄕(キョウ)→嚮(キョウ)


(甲骨文)
論語の本章では”先に”。「向」と古音が同じであることから来た派生義で、甲骨文から”向かって”の意での用例はあるが、”先に”の語義は春秋時代以前では確認できない。
初出は甲骨文。新字体は「郷」、「鄕」は異体字。周初は「卿」と書き分けられなかった。中国・台湾・香港では、新字体に一画多い「鄉」がコード上の正字とされる。定州竹簡論語も「鄉」と釈文している。唐石経・清家本は新字体と同じく「郷」と記す。「ゴウ」は慣用音、「コウ」は呉音。字形は山盛りの食事を盛った器に相対する人で、原義は”宴会”。甲骨文では”宴会”・”方角”を意味し、金文では”宴会”(曾伯陭壺・春秋早期)、”方角”(善夫山鼎・西周末期)に用い、また郷里・貴族の地位の一つ・城壁都市を意味した。詳細は論語語釈「郷」を参照。
日本伝承の古注系論語では「嚮」と記す。意味は変わらない。論語の文字列は、隋代ごろ日本に伝承したが、中国では次代の唐になってかなり文字の入れ替えがあり、その後古注は滅んだ。従って日本伝承の古注系論語と、唐石経を祖本とする中国伝承の論語で文字が違う場合、唐石経より古い文字列が日本に伝承していると考えるのに理がある。江戸末まで中国崇拝の強かった日本で、勝手に文字を書き換える動機が見当たらないからだ。
伝承として論語の本章で現存最古の文字列は隋代の『経典釈文』になるが、物証としての最古は唐石経ついで清家本で、清家本では「嚮」としるす。これに従って校訂した。字は甲骨文から用例があるが、字形は戦国末期まで「鄕」と未分化。詳細は論語語釈「嚮」を参照。
原始論語?…→定州竹簡論語→白虎通義→ ┌(中国)─唐石経─論語注疏─論語集注─(古注滅ぶ)→ →漢石経─古注─経典釈文─┤ ↓↓↓↓↓↓↓さまざまな影響↓↓↓↓↓↓↓ ・慶大本 └(日本)─清家本─正平本─文明本─足利本─根本本→ →(中国)─(古注逆輸入)─論語正義─────→(現在) →(日本)─────────────懐徳堂本→(現在)
也(ヤ)


(金文)
論語の本章、「鄕也」では「や」と読んで”まさに”、主格の強調の意を示す。「謂也」は「や」と読んで”…か”。疑問の意を示す。
初出は事実上春秋時代の金文。字形は口から強く語気を放つさまで、原義は”…こそは”。春秋末期までに句中で主格の強調、句末で詠歎、疑問や反語に用いたが、断定の意が明瞭に確認できるのは、戦国時代末期の金文からで、論語の時代には存在しない。詳細は論語語釈「也」を参照。
吾(ゴ)


(甲骨文)
論語の本章では”わたしの”。初出は甲骨文。字形は「五」+「口」で、原義は『学研漢和大字典』によると「語の原字」というがはっきりしない。一人称代名詞に使うのは音を借りた仮借だとされる。詳細は論語語釈「吾」を参照。
古くは中国語にも格変化があり、一人称では「吾」(藤堂上古音ŋag)を主格と所有格に用い、「我」(同ŋar)を所有格と目的格に用いた。しかし論語で「我」と「吾」が区別されなくなっているのは、後世の創作が多数含まれているため。
於(ヨ)


(金文)
論語の本章、「見於夫子」では”~に”。「選於衆」では”~から”。初出は西周早期の金文。ただし字体は「烏」。「ヨ」は”~において”の漢音(遣隋使・遣唐使が聞き帰った音)、呉音は「オ」。「オ」は”ああ”の漢音、呉音は「ウ」。現行字体の初出は春秋中期の金文。西周時代では”ああ”という感嘆詞、または”~において”の意に用いた。詳細は論語語釈「於」を参照。
夫子(フウシ)
論語の本章では”あの方”。具体的に孔子を指す。この語義は春秋時代では確認できない。論語では孔子を指す「夫子」として多出。「夫」に指示詞の用例が春秋時代以前に無いことから、”あの人”ではなく”父の如き人”の意で、多くは孔子を意味する。つまり孔子以外を「夫子」と呼ぶのは、春秋時代の漢語ではない。加えて出土資料で「夫子」が確認出来るのは、戦国時代以降になる。


(甲骨文)
「夫」の初出は甲骨文。「フウ」は慣用音。字形はかんざしを挿した成人男性の姿で、原義は”成人男性”。「大夫」は領主を意味し、「夫人」は君主の夫人を意味する。固有名詞を除き”成人男性”以外の語義を獲得したのは西周末期の金文からで、「敷」”あまねく”・”連ねる”と読める文字列がある。以上以外の語義は、春秋時代以前には確認できない。詳細は論語語釈「夫」を参照。
而(ジ)


(甲骨文)
論語の本章では”そして”。「而」の初出は甲骨文。原義は”あごひげ”とされるが用例が確認できない。甲骨文から”~と”を意味し、金文になると、二人称や”そして”の意に用いた。英語のandに当たるが、「A而B」は、AとBが分かちがたく一体となっている事を意味し、単なる時間の前後や類似を意味しない。詳細は論語語釈「而」を参照。
何(カ)


「何」(甲骨文)
論語の本章では”どんな”。この語義は春秋時代では確認できない。初出は甲骨文。字形は「人」+”天秤棒と荷物”または”農具のスキ”で、原義は”になう”。甲骨文から人名に用いられたが、”なに”のような疑問辞での用法は、戦国時代の竹簡まで時代が下る。詳細は論語語釈「何」を参照。
謂(イ)


(金文)
論語の本章では”意味する言葉”。この語義は春秋の通例から外れる。本来の語義は、ただ”いう”のではなく、”~だと評価する”・”~だと認定する”。現行書体の初出は春秋後期の石鼓文。部品で同義の「胃」の初出は春秋早期の金文。金文では氏族名に、また音を借りて”言う”を意味した。戦国の竹簡になると、あきらかに”~は~であると言う”の用例が見られる。詳細は論語語釈「謂」を参照。
富(フウ)

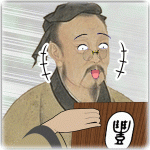
(甲骨文)
論語の本章では”豊か”→”意味の深い”。初出は甲骨文。字形は「冖」+「フ」は呉音。「酉」”酒壺”で、屋根の下に酒をたくわえたさま。「厚」と同じく「酉」は潤沢の象徴で(→論語語釈「厚」)、原義は”ゆたか”。詳細は論語語釈「富」を参照。
哉(サイ)


(金文)
論語の本章では”…ですねえ”。詠嘆の意。初出は西周末期の金文。ただし字形は「𠙵」”くち”を欠く「𢦏」で、「戈」”カマ状のほこ”+「十」”傷”。”きずつく”・”そこなう”の語釈が『大漢和辞典』にある。現行字体の初出は春秋末期の金文。「𠙵」が加わったことから、おそらく音を借りた仮借として語気を示すのに用いられた。金文では詠歎に、また”給与”の意に用いられた。戦国の竹簡では、”始まる”の意に用いられた。詳細は論語語釈「哉」を参照。
是(シ)


(金文)
論語の本章では”この…”。初出は西周中期の金文。「ゼ」は呉音(遣隋使より前に日本に伝わった音)。字形は「睪」+「止」”あし”で、出向いてその目で「よし」と確認すること。同音への転用例を見ると、おそらく原義は”正しい”。初出から”確かにこれは~だ”と解せ、”これ”・”この”という代名詞、”…は…だ”という接続詞の用例と認められる。詳細は論語語釈「是」を参照。
言(ゲン)


(甲骨文)
論語の本章では”発言”。初出は甲骨文。字形は諸説あってはっきりしない。「口」+「辛」”ハリ・ナイフ”の組み合わせに見えるが、それがなぜ”ことば”へとつながるかは分からない。原義は”言葉・話”。甲骨文で原義と祭礼名の、金文で”宴会”(伯矩鼎・西周早期)の意があるという。詳細は論語語釈「言」を参照。
乎(コ)


(甲骨文)
論語の本章では、「か」と読んで”…ですねえ”、詠嘆の意。この語義は春秋時代では確認できない。初出は甲骨文。字形は持ち手の柄を取り付けた呼び鐘を、上向きに持って振り鳴らし、家臣を呼ぶさまで、原義は”呼ぶ”こと。甲骨文では”命じる”・”呼ぶ”を意味し、金文も同様で、「呼」の原字となった。句末の助辞として用いられたのは、戦国時代以降になるという。詳細は論語語釈「乎」を参照。
舜(シュン)
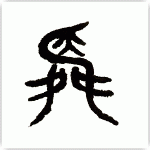

(金文)
論語の本章では、創作上の古代の聖王。現伝する『史記』によると、卑屈が過ぎる親孝行の他は、賢者に政治を任せたことがあるだけで、これといって何をしたわけでもない。「舜」の初出は戦国文字で、論語の時代に存在しない。詳細は論語語釈「舜」を参照。
有(ユウ)


「有」(甲骨文)
論語の本章では”保有する”。初出は甲骨文。ただし字形は「月」を欠く「㞢」または「又」。字形はいずれも”手”の象形。金文以降、「月」”にく”を手に取った形に描かれた。原義は”手にする”。原義は腕で”抱える”さま。甲骨文から”ある”・”手に入れる”の語義を、春秋末期までの金文に”存在する”・”所有する”の語義を確認できる。詳細は論語語釈「有」を参照。
天下(テンカ)

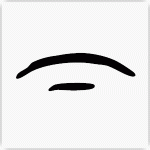
(甲骨文)
論語の本章では”天下”。天の下に在る人界全て。
「天」の初出は甲骨文。字形は人の正面形「大」の頭部を強調した姿で、原義は”脳天”。高いことから派生して”てん”を意味するようになった。甲骨文では”あたま”、地名・人名に用い、金文では”天の神”を意味し、また「天室」”天の祭祀場”の用例がある。詳細は論語語釈「天」を参照。
「下」の初出は甲骨文。「ゲ」は呉音。字形は「一」”基準線”+「﹅」で、下に在ることを示す指事文字。原義は”した”。によると、甲骨文では原義で、春秋までの金文では地名に、戦国の金文では官職名に(卅五年鼎)用いた。詳細は論語語釈「下」を参照。
選*(セン)
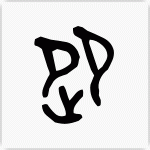

九年衛鼎・西周中期
論語の本章では”選び出す”。初出は西周中期の金文。字形は「㔾」”跪いた人”×2人+「止」”止まる”。大勢の人から望む者を選び抜くさま。西周中期の金文に「巽」とあるのは、「選」と釈文されている。春秋の金文に字形不明瞭ながら「選」と釈文される字があり、”えらぶ”と解せる。西周末期の金文では、「選」とも、「從」とも釈文されている。論語語釈「従」を参照。日本語で同音同訓に「撰」(サン/セン)。論語語釈「撰」を参照。詳細は論語語釈「選」を参照。
衆(シュウ)
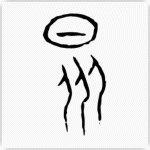

(甲骨文)
論語の本章では”民衆”。「眾」と「衆」とは異体字。初出は甲骨文。字形は「囗」”都市国家”、または「日」+「人」三つ。都市国家や太陽神を祭る神殿に隷属した人々を意味する。論語の時代では、”人々一般”を意味した可能性がある。詳細は論語語釈「衆」を参照。
皋陶*(コウヨウ)
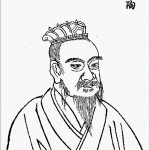
論語の本章では、夏王朝より以前の架空の聖王・舜に仕えた司法長官の、架空の人名。論語では本章のみに登場。現伝『史記』が伝えるようなはなしは、もとより作り話で史実ではない。

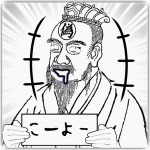
皐陶よ、蛮族(蛮夷)が中華(夏)の地を乱し、盗賊や謀反人がいる。そなたは司法長官(士)になれ。入れ墨・鼻削ぎ・足切り・去勢・死刑の五刑には基準がある。五刑の処刑場には三つの定まった場所がある。五刑をゆるめた五流には、決まった流し場所がある。五つの流し場所には遠・中・近の三つの区別がある。それらに明らかに従い、偽りのない司法を行え。(『史記』五帝本紀)
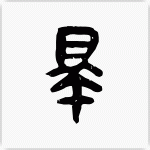

(秦系戦国文字)
「皋」の初出は秦系戦国文字。論語の時代に存在しないが、固有名詞のため同音近音のあらゆる漢字が置換候補になり得る。字形は上下に「白」+「夲」。字形の意味するところや原義は不明。同音は論語語釈「救」を参照。戦国の竹簡では、人名に用いられた。詳細は論語語釈「皋」を参照。
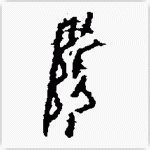

(甲骨文)
「陶」の初出は甲骨文。字形は「阝」”階段”+”腰をかがめた人”2人。登り窯で陶器を焼く様。金文から戦国文字に至るまで、地名・人名に用いた。詳細は論語語釈「陶」を参照。
不(フウ)


(甲骨文)
漢文で最も多用される否定辞。初出は甲骨文。「フ」は呉音(遣隋使より前に日本に伝わった音)、「ブ」は慣用音。原義は花のがく。否定辞に用いるのは音を借りた派生義だが、甲骨文から否定辞”…ない”の意に用いた。詳細は論語語釈「不」を参照。
遠(エン)


(甲骨文)
論語の本章では”遠ざかる”。初出は甲骨文。字形は「彳」”みち”+「袁」”遠い”で、道のりが遠いこと。「袁」の字形は手で衣を持つ姿で、それがなぜ”遠い”の意になったかは明らかでない。ただ同音の「爰」は、離れたお互いが縄を引き合う様で、”遠い”を意味しうるかも知れない。詳細は論語語釈「遠」を参照。
矣(イ)


(金文)
論語の本章では、”てしまう”。初出は殷代末期の金文。字形は「𠙵」”人の頭”+「大」”人の歩く姿”。背を向けて立ち去ってゆく人の姿。原義はおそらく”…し終えた”。ここから完了・断定を意味しうる。詳細は論語語釈「矣」を参照。
湯*(トウ)
論語の本章では、殷の開祖の王とされる人名。ただしもとは「唐」「大乙」と記され、家臣の伊尹とともに、物証の初出は甲骨文で、金文では春秋末期の金文で、丁度孔子が生まれた頃に世を去った斉の霊公時代の作に見られる。詳細は論語為政篇23余話「叔尸鐘」を参照。
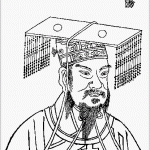

(金文)
「湯」の初出は西周中期の金文。字形は「氵」+「日」+「丁」”掲げる竿”。南中の陽に当てられて温まった水のさま。西周~春秋の金文では人名のほか”鋳る”・”南”・”行き渡る”の意に用いた。戦国の竹簡では「揚」に通じ、また地名に用いた。詳細は論語語釈「湯」を参照。
伊*尹*(イイン)
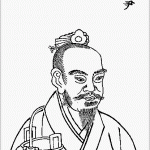
殷の開祖、湯王を補佐したという伝説のある人物。甲骨文から名は見えるが、現伝『史記』が伝えるような活躍をしたかどうかは分からない。
當是時,夏桀為虐政淫荒,而諸侯昆吾氏為亂。湯乃興師率諸侯,伊尹從湯。
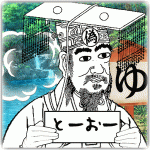
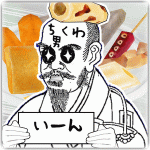
この時、夏の桀王は暴政を敷きすさんだ生活を送っていた。だから諸侯の一人、昆吾氏が反乱を起こした。湯王は軍隊を編成して諸侯を率い、伊尹は湯王に付き従った。(『史記』殷本紀7)

(甲骨文)
「伊」の初出は甲骨文。字形は「亻」+「丨」”天地をつなぐ通路”+「又」”手”。「丨」「又」「𠙵」”くち”で、天にもの申し、天意を口で人に伝えるべき「君」を構成するのに対し、「君」と天の交信を補助すべき人物の意。殷の開祖湯王の名臣「伊尹」の人名として甲骨文から見える。「伊」単独でも見えるが語義が明瞭でない。西周・春秋の金文では地名・人名として用いた。詳細は論語語釈「伊」を参照。
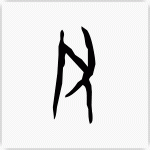
(甲骨文)
「尹」の初出は甲骨文。字形は「丨」天界と人界を繋ぐ筋道を「又」手に取って管理する神官のさま。原義は”神官・高官”。「君」から「𠙵」”くち”を欠いた字形。甲骨文では「伊尹」の人名として用い、西周の金文では”統治”を意味した。詳細は論語語釈「尹」を参照。
論語:付記
検証
論語の本章は文字史から戦国時代までしか遡れず、前漢中期の定州竹簡論語にも無い。ただし古注が前後の漢帝国交代期を生きた包咸の注を載せているので、前漢後期には論語の一章として成立していたことになる。なお司馬遷や董仲舒と同時代人とされる孔安国も注をつけているが、この人物は実在が疑わしく、時間軸を証明する材料にならない。
解説
論語の傾向として、その章でしか用いられない漢字があれば、だいたい偽作を疑っていいのだが、本章もその例。「舉直錯諸枉」との言い廻しは、論語為政篇19から切り取ってきたのは明らかで、「富哉言」も前章の「善哉問」のパクリだろう。儒者の創作力の貧困を示している。
儒者は『詩経』が孔子の撰述であるという権威性から、作るに規則の多いポエム書きには熱を上げたが、物語の創作はからきしダメで、似たようなことしか書く能がない。その上「物語など下らん人間が読み書きするものだ」といって馬鹿にした。以下は『封神演義』の例。
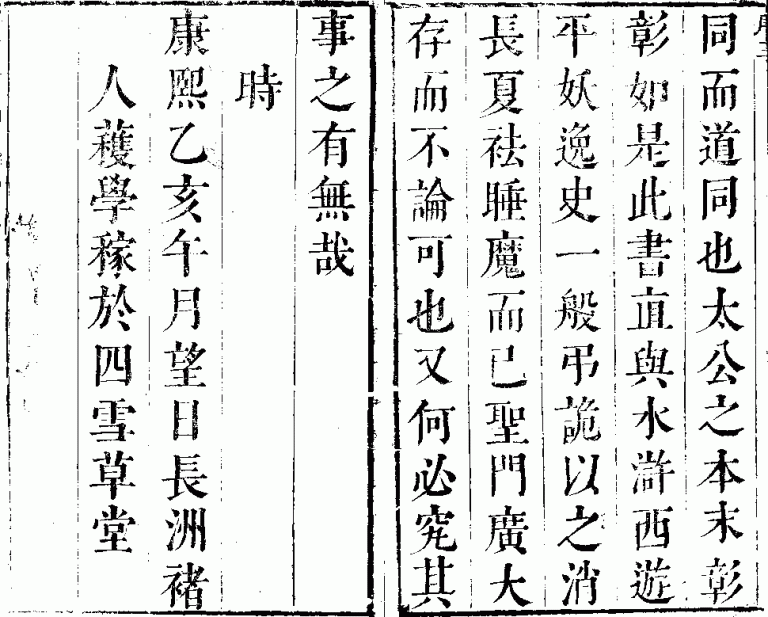
この本は結局の所、『西遊記』や『水滸伝』と共に、妖怪退治物語を伝える歴史小話で、矛盾に満ちている。読んだ所で中華の盛衰が分かる本ではなく、眠気を払う役にしか立たない。孔子様の広大な教えが、論じることが出来ないほどの規模であることを思えば、こんな下らない本の真偽を論じても、仕方がないのである。(『封神演義』序文)
これが儒者=中国の行政但当者から、想像力を奪う一因となったから、それが亡国をもたらしたことを思うと、ラノベを馬鹿にした罪は存外軽くない。だから論語の本章のような、余りにバカバカしい絵空事が大手を振ってまかり通るのだが、同じ論語に問答の半分は本物らしいのがある。
孔子「治水のような民が望む政策推進に励み、妖怪話は敬う振りして真に受けないことだな。」
樊遅「仁って何です?」
孔子「貴族が難しい仕事を終えた後で、自分の報酬を受け取ることだな。それでこそ立派なサムライだ。」(論語雍也篇22)
論語の本章、新古の注は次の通り。
古注『論語集解義疏』
樊遲問仁子曰愛人問智子曰知人樊遲未達子曰舉直錯諸枉能使枉者直註苞氏曰舉正直之人用之廢置邪枉之人則皆化為直也樊遲退見子夏曰嚮也吾見於夫子而問智子曰舉直錯諸枉能使枉者直何謂也子夏曰富哉是言乎註孔安國曰富盛也舜有天下選於衆舉臯陶不仁者逺矣湯有天下選於衆舉伊尹不仁者逺矣註孔安國曰言舜湯有天下選擇於衆舉臯陶伊尹則不仁者逺矣仁者至矣
本文「樊遲問仁子曰愛人問智子曰知人樊遲未達子曰舉直錯諸枉能使枉者直」。
注釈。包咸「正直者を推挙してその人を腐れきった悪党の中に置けば、悪党は感化されて皆おりこうさんになるのである。」
本文「樊遲退見子夏曰嚮也吾見於夫子而問智子曰舉直錯諸枉能使枉者直何謂也子夏曰富哉是言乎」。
注釈。孔安国「富とは盛んであるの意である。」
本文「舜有天下選於衆舉臯陶不仁者逺矣湯有天下選於衆舉伊尹不仁者逺矣」。
注釈。孔安国「舜や湯が天下を取って人民から臯陶や伊尹を取り立てたら、すぐさま不仁な者が逃げ散り、仁者がやってきたというのである。」
世には善人より悪党の方が圧倒的に多いのだから、朱に交われば赤くなるの例えの通り、悪党の中に善人を混ぜると、むしろ善人の方が悪に染まるのが世の習いと思うのだが、包咸は世にも希なまじめ人間だったから、こういう呆けたことを書いても不思議は無い。
新注『論語集注』
樊遲問仁。子曰:「愛人。」問知。子曰:「知人。」上知,去聲,下如字。愛人,仁之施。知人,知之務。樊遲未達。曾氏曰:「遲之意,蓋以愛欲其周,而知有所擇,故疑二者之相悖爾。」子曰:「舉直錯諸枉,能使枉者直。」舉直錯枉者,知也。使枉者直,則仁矣。如此,則二者不惟不相悖而反相為用矣。樊遲退,見子夏。曰:「鄉也吾見於夫子而問知,子曰,『舉直錯諸枉,能使枉者直』,何謂也?」鄉,去聲。見,賢遍反。遲以夫子之言,專為知者之事。又未達所以能使枉者直之理。子夏曰:「富哉言乎!歎其所包者廣,不止言知。舜有天下,選於眾,舉皋陶,不仁者遠矣。湯有天下,選於眾,舉伊尹,不仁者遠矣。」選,息戀反。陶,音遙。遠,如字。伊尹,湯之相也。不仁者遠,言人皆化而為仁,不見有不仁者,若其遠去爾,所謂使枉者直也。子夏蓋有以知夫子之兼仁知而言矣。○程子曰:「聖人之語,因人而變化。雖若有淺近者,而其包含無所不盡,觀於此章可見矣。非若他人之言,語近則遺遠,語遠則不知近也。」尹氏曰:「學者之問也,不獨欲聞其說,又必欲知其方;不獨欲知其方,又必欲為其事。如樊遲之問仁知也,夫子告之盡矣。樊遲未達,故又問焉,而猶未知其何以為之也。及退而問諸子夏,然後有以知之。使其未喻,則必將復問矣。既問於師,又辨諸友,當時學者之務實也如是。」
本文「樊遲問仁。子曰:愛人。問知。子曰:知人。」
ここで知の字は尻下がりに読むが、以降は字に従って平らな調子で読む。愛人とは、仁を施すことである。知人とは、相手を知って便宜を図ってやることである。
本文「樊遲未達。」
曾氏(詳細不明)「樊遅が思ったのは、たぶん自分勝手な愛欲をまわりにまき散らして、その上でどれを選ぶかを知りたがったわけで、もともと仁と知が並び立たない性質のものだった。」
本文「子曰:舉直錯諸枉,能使枉者直。」
まじめ人間を悪党に交えるのが、知である。悪党がおりこうさんになるのが、すなわち仁である。この通り、仁と知は並び立たないわけで無く、互いに相互補完するものだ。
本文「樊遲退,見子夏。曰:鄉也吾見於夫子而問知,子曰,『舉直錯諸枉,能使枉者直』,何謂也?」
鄉は尻下がりに読む。見は賢-遍の反切で読む。樊遅は先生の教えを、ただ「知」への答えだけだと勘違いした。また話をよく理解出来なかったので、悪党をおりこうさんに出来る理屈が分からなかった。
本文「子夏曰:富哉言乎!歎其所包者廣,不止言知。舜有天下,選於眾,舉皋陶,不仁者遠矣。湯有天下,選於眾,舉伊尹,不仁者遠矣。」
選の字は、息-戀の反切で読む。陶の音は遙である。遠は本来の音で読む。伊尹は、湯王の大臣である。不仁者遠とは、人々が皆頭をやられておりこうさんになったので、不見な者がいなくなり、あるいは逃げだした。こういうのを悪党をまじめ人間にするという。子夏はたぶん、先生が知と仁を組み合わせて説明した理由が分かっていた。
程頤「聖人の言葉は、聞き手によって変えて語られる。理解の浅い者が居たとしても、教えを余すところなく含んで言い残しが無いような説明をする。この章にはそれが見て取れる。そのあたりの連中の言葉では無いから、はっきりとものを言っても含蓄は深く、遠回しに言ってもやはり含蓄が深いのである。」
尹焞「儒学を学ぶ者の質問は、単に答えを聞こうとするだけでなく、必ずその実践方法を聞きたがる。実践方法を聞きたがるだけで無く、必ず実際に手ずから行いたいと願う。樊遅が仁と知を聞いた場合でも、先生は余すところなく説明した。だが樊遅には理解出来ず、だからまた問い直した。それでもなお、実際にどうやっていいかは理解出来なかった。先生の前を下がって子夏に質問したあとで、やっと理解出来た。例えを使って説明しないと、必ずまた問い返しただろう。まず先生に質問し、学友にも説明して貰うのが、当時儒学を学ぶ者の実態だっったのだ。」
余話
(思案中)





コメント