論語:原文・書き下し
原文(唐開成石経)
子曰天生德於予桓魋其如予何
- 「魋」字:〔由〕→〔田〕。
校訂
東洋文庫蔵清家本
子曰天生德於予桓魋其如予何
- 「魋」字:〔由〕→〔田〕。
後漢熹平石経
(なし)
定州竹簡論語
……「[天]生德於予,桓魋其如予何?」165
標点文
子曰、「天生德於予、桓魋其如予何。」
復元白文(論語時代での表記)











※桓→𧻚・魋→椎。
書き下し
子曰く、天德を予於生せり、桓魋其れ予に如くこと何ぞ。
論語:現代日本語訳
逐語訳

天は私に人格力を発生させた。桓魋ごときが私に及ぶとは何か。
意訳
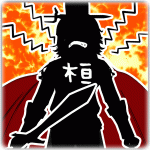
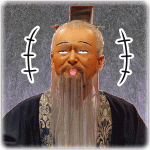
宋国の将軍・桓魋が暴れ込んできた。
孔子「お前さんと違って天から授かった能がある。やられたりするものか。」
従来訳
先師がいわれた。――
「私は天に徳を授かった身だ。桓魋などが私をどうにも出来るものではない。」下村湖人『現代訳論語』
現代中国での解釈例
孔子說:「老天賦予我高尚的品德,追殺我的人能把我怎樣?」
孔子が言った。「お天道様は私に高尚な人徳を与えた。私を追い詰め殺すような人は私に何が出来るか?」
論語:語釈
子曰(シエツ)(し、いわく)

論語の本章では”孔子先生が言った”。「子」は貴族や知識人に対する敬称で、論語では多くの場合孔子を指す。「子」は赤ん坊の象形、「曰」は口から息が出て来るさま。「子」も「曰」も、共に初出は甲骨文。辞書的には論語語釈「子」・論語語釈「曰」を参照。
この二文字を、「し、のたまわく」と読み下す例がある。「言う」→「のたまう」の敬語化だが、漢語の「曰」に敬語の要素は無い。古来、論語業者が世間からお金をむしるためのハッタリで、現在の論語読者が従うべき理由はないだろう。
前漢中期に埋蔵された、現存最古の論語本で、上掲の上掲定州竹簡論語は、「[天]生德於予」で始まっており、文字の上の•は「簡の上部に欠損がなく、この文字から文字列が始まっている」事を示す記号。つまり「子曰」が無かったことになる。論語が現伝の形式に整う前の姿を伝えているのだろうが、すると誰の発言かという問題が生じる。
論語の本章では、発言者は「予」と自称している。春秋末期までの出土例では、青銅器を独自に鋳るほどの大貴族が、自称して「予」と言っている。文献時代になると、漢儒の編んだ『小載礼記』に天子の一人称として「予一人」が見える。つまり「予」は貴人の一人称。
論語の登場人物で最も尊貴と言えるのは孔子だから、現伝の通り「子曰」を補っても構わないと判断し、書き加えた。また論語雍也篇28では、孔子は「予」と自称している。
中国伝承の京大蔵唐石経、現存最古の論語の紙本で完本、宮内庁蔵『論語注疏』は「子曰」を記し、日本伝承の清家本、正平本、文明本を定本とする懐徳堂本も、「子曰」を記す。
原始論語?…→定州竹簡論語→白虎通義→ ┌(中国)─唐石経─論語注疏─論語集注─(古注滅ぶ)→ →漢石経─古注─経典釈文─┤ ↓↓↓↓↓↓↓さまざまな影響↓↓↓↓↓↓↓ ・慶大本 └(日本)─清家本─正平本─文明本─足利本─根本本→ →(中国)─(古注逆輸入)─論語正義─────→(現在) →(日本)─────────────懐徳堂本→(現在)
天(テン)


(甲骨文)
論語の本章では漠然とした”摂理”。初出は甲骨文。字形は人の正面形「大」の頭部を強調した姿で、原義は”脳天”。高いことから派生して”てん”を意味するようになった。甲骨文では”あたま”、地名・人名に用い、金文では”天の神”を意味し、また「天室」”天の祭祀場”の用例がある。詳細は論語語釈「天」を参照。
最高神、天の神と解してもよいが、それには別に「帝」の字がある。孔子は「怪力乱神を語らず」(論語述而篇20)と言われるとおり、古代にあっては例外的に無神論的人物で、極めて明るい視野を持っていた。それゆえに、大自然の猛威に対しては敬虔で、人格神ではない抽象的な摂理を「天」と呼んで恐れたと思われる。詳細は孔子はなぜ偉大なのかを参照。
なお殷代まで「申」と書かれた”天神”を、西周になったとたんに「神」と書き始めたのは、殷王朝を滅ぼして国盗りをした周王朝が、「天命」に従ったのだと言い張るためで、文字を複雑化させたのはもったいを付けるため。「天子」の言葉が中国語に現れるのも西周早期で、殷の君主は自分から”天の子”などと図々しいことは言わなかった。詳細は論語述而篇34余話「周王朝の図々しさ」を参照。
生(セイ)


「生」(甲骨文)
論語の本章では”発生させる”→”授ける”。漢語は全く変化無しで他動詞にも自動詞にも化ける。初出は甲骨文。字形は「屮」”植物の芽”+「一」”地面”で、原義は”生える”。甲骨文で、”育つ”・”生き生きしている”・”人々”・”姓名”の意があり、金文では”月齢の一つ”、”生命”の意がある。詳細は論語語釈「生」を参照。
德(トク)
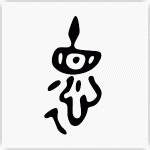

(金文)
論語の本章では”人格に備わった機能”。初出は甲骨文。新字体は「徳」。甲骨文の字形は、〔行〕”みち”+〔丨〕”進む”+〔目〕であり、見張りながら道を進むこと。甲骨文で”進む”の用例があり、金文になると”道徳”と解せなくもない用例が出るが、その解釈には根拠が無い。前後の漢帝国時代の漢語もそれを反映して、サンスクリット語puṇyaを「功徳」”行動によって得られる利益”と訳した。孟子以降では”道徳”の意となった。詳細は論語における「徳」を参照。文字的には論語語釈「徳」を参照。
本章では、2mを超す孔子の身長や、ペニシリンの無い時代に70過ぎまで生きた健康や、武術の達人であることや、大勢の物騒な弟子を統制して引き連れていることも「徳」の範疇に入る。放浪中の桓魋など、暴れ込んできても返り討ちは簡単だったのだ。
於(ヨ)


(金文)
論語の本章では”~に”。初出は西周早期の金文。ただし字体は「烏」。「ヨ」は”…において”の漢音(遣隋使・遣唐使が聞き帰った音)、呉音(遣隋使より前に日本に伝わった音)は「オ」。「オ」は”ああ”の漢音、呉音は「ウ」。現行字体の初出は春秋中期の金文。西周時代では”ああ”という感嘆詞、または”~において”の意に用いた。詳細は論語語釈「於」を参照。
予(ヨ)

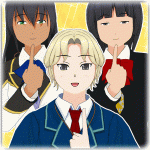
(金文)
論語の本章では”わたし”。初出は西周末期の金文で、「余・予をわれの意に用いるのは当て字であり、原意には関係がない」と『学研漢和大字典』はいうが、春秋末期までに一人称の用例がある。”あたえる”の語義では、現伝の論語で「與」となっているのを、定州竹簡論語で「予」と書いている。字形の由来は不明。金文では氏族名・官名・”わたし”の意に用い、戦国の竹簡では”与える”の意に用いた。詳細は論語語釈「予」を参照。
桓魋(カンタイ)
論語の本章では、代々宋国の司馬(陸相兼参謀総長)を務めた家柄の出で、孔子の弟子・司馬牛の兄。『学研漢和大字典』によると、姓名は向魋。宋に来た孔子を殺そうとした。宋の景公には気に入られたが、罪を得て曹・衛に逃れた。
「宋に来た孔子を殺そうとした」というのは『史記』孔子世家にそうあるからだが、それでは桓魋が孔子をあやめようとした理由の説明が付かない。司馬遷の打ち上げたホラ(論語雍也篇14余話)か、一杯機嫌で司馬遷にデタラメを語った古老の受け売りと断じて構わない。

これを受けて後世、「孔子が桓魋を恐れて変装のまま宋国をコソコソと走り逃げた」という伝説と下手くそな漫画が作られたが、もとより信じるに値しない。桓魋の襲来は、弟で孔子の弟子だった司馬耕子牛の変死への復讐と考えるべきで、その年時は孔子死去の前年か前々年で、すでに孔子は魯に帰国している。
同字典では「向」の漢音(遣隋使・遣唐使が聞き帰った音)を「キョウ」、呉音(それより前に日本に伝わった音)を「コウ」としているのだが、ここだけ「ショウ」とふりがなを付けている理由は不明。同字典による上古音はhɪaŋ(去)、カールグレン上古音はxi̯aŋ(去)、現代北京語音はxiàng。ただし『大漢和辞典』は国名・地名・姓としての音を「ショウ」と記す。論語語釈「向」も参照。
桓魋が「桓」の氏を名乗った理由は、宋の桓公の末裔だからという説があるが、言い出したのは孔子没後1600年以上後に生まれた朱子で、真に受けて良いかどうかは疑問がある。『春秋左氏伝』では向魋と記される。弟の司馬牛について詳細は、論語の人物:司馬耕子牛を参照。
論語の本章で孔子を襲ったとされることから、後世の儒者によって悪党として描かれたが、もちろん何の根拠も無いでっち上げである。むしろ良心的な人物だったことは、解説に記した。
司馬耕,宋人,字子牛。牛為性躁,好言語,見兄桓魋行惡,牛常憂之。
司馬耕は宋の出身で、あざ名は子牛。性格が軽薄ではしゃぎ、おしゃべりだった。ただし兄の桓魋が悪行をはたらくので、それをいつも心配のタネにしていた。(『孔子家語』七十二弟子解・子馬耕)


(金文)
「桓」の初出は西周末期の金文で、ただし字形は「𧻚」。現伝字体の初出は前漢の隷書。字形は「木」+「亘」で、「亘」は甲骨文で占い師の名に用いたほかは、戦国時代の竹簡まで出土が無い。”うずまき”とも、”明らかな太陽”とも解せる。一種の装飾的署名だと思う。「桓」は何かを明らかに示すための標識。同音多数。西周末期の金文に、”あきらかで勢いの良い”の意で用いた。詳細は論語語釈「桓」を参照。


(秦系戦国文字)
「魋」の初出は秦系戦国文字。字形は「鬼」”頭の大きな化け物”+「隹」。原義未詳。上古音は「鎚」”かなづち”と同じ。上掲の印章の他は、文献時代になってから見られる文字で、論語や『春秋左氏伝』に人名として用いる。論語時代の置換候補は、固有名詞のため、同音近音のあらゆる文字が置換候補になり得る。「魋」は”さいづちまげ”を意味し、「椎」と『大漢和辞典』はいう。。「椎」は甲骨文から存在する。詳細は論語語釈「魋」を参照。
さいづちまげとは、髪を後ろに垂らしておでこを強調した髪型で、南越の風習だと『大漢和辞典』は言う。
其(キ)


(甲骨文)
論語の本章では”そ奴”。桓魋の言い換え。”桓魋ごときが”という蔑称。初出は甲骨文。原義は農具の箕。ちりとりに用いる。金文になってから、その下に台の形を加えた。のち音を借りて、”それ”の意をあらわすようになった。人称代名詞に用いた例は、殷代末期から、指示代名詞に用いた例は、戦国中期からになる。詳細は論語語釈「其」を参照。
別解として、”それ”という指示詞ではなく副詞。あり得ないこと、あり得ては困ることを示す(戸内俊介「上古中国語文法化研究序説 ――「于」「而」「其」の意味機能変化を例に――」)。ただし春秋時代に用例が見られない。
如(ジョ)


「如」(甲骨文)
論語の本章では”~と同じになる”。この語義は春秋時代では確認できない。初出は甲骨文。字形は「口」+「女」。甲骨文の字形には、上下や左右に部品の配置が異なるものもあって一定しない。原義は”ゆく”。詳細は論語語釈「如」を参照。
予(ヨ)

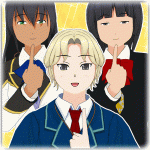
(金文)
論語の本章では”わたし”。初出は西周末期の金文で、「余・予をわれの意に用いるのは当て字であり、原意には関係がない」と『学研漢和大字典』はいうが、春秋末期までに一人称の用例がある。”あたえる”の語義では、現伝の論語で「與」となっているのを、定州竹簡論語で「予」と書いている。字形の由来は不明。金文では氏族名・官名・”わたし”の意に用い、戦国の竹簡では”与える”の意に用いた。詳細は論語語釈「予」を参照。
何(カ)


「何」(甲骨文)
「何」は論語の本章では”何だ”→”どういうわけだ”。この語義は春秋時代では確認できない。初出は甲骨文。字形は「人」+”天秤棒と荷物”または”農具のスキ”で、原義は”になう”。甲骨文から人名に用いられたが、”なに”のような疑問辞での用法は、戦国時代の竹簡まで時代が下る。詳細は論語語釈「何」を参照。
如予何(われにしくはなんぞ)
伝統的には「如何」”どうしよう”の間に目的語の「予」”わたし”が入った形と説明され、「われをいかん」と読み、”私をどうするのか”と解する。
しかし春秋時代は一字一義が原則で熟語はない。「如何」やおなじく「いかん」と読む「何如」が見られるのは戦国の竹簡から。また間に目的語を挟む形は、「如〇何」は戦国の竹簡から見られるが、「何〇如」は先秦両漢の文献にも見られない。
論語の本章の場合は、文字史的に後世の偽作を疑う必要がないので、一字一義と解し、「われにしくはなんぞ」と読み、”(徳を備えた)私に(徳の無いお前が)及ぶとはどういうわけだ”と解するのが妥当。
一般的に「いかん」は次のように解する。


- 「如・何」→従うべきは何か→”どうしましょう”・”どうして”。
- 「何・如」→何が従っているか→”どう(なっている)でしょう”
「いかん」と読み下す一連の句形については、漢文読解メモ「いかん」を参照。
論語:付記
検証
論語の本章は、春秋戦国時代での引用が無く、再出は前漢中期の『史記』孔子世家になる。また論語の本章をもじって、新を建てた王莽は、敗死する寸前に「天生德於予,漢兵其如予何」と言った(『漢書』王莽伝77)。文字的には論語の時代に遡れるから、本章は史実の孔子の言葉として扱ってよい。
解説
従来訳のような解釈は、頭のおかしな爺さんが、気の狂った自慢をしているとしか聞こえない。間違いの元は、孔子が人格者だなどという、儒者のでっち上げを真に受けるからだ。春秋時代の身分制をひっくり返した革命家でありながら、命を狙われないわけがない。
儒教徒も認めるように、孔子は社会の底辺に生まれた。そして魯国の宰相格にまで出世した。弟子を連れて国外逃亡し、諸国で政治活動を行ったことも、儒家は認めざるを得ないだろう。既得権益がひしめく所に、「孔子の理想」の実現化とは、つまりクーデターに他ならない。
貴族制の当時、政権交代には追放や暗殺が付き物で、斉の国公は四割が殺されている。
孔子はとんでもない危険人物だったのだ。だから諸国で追い出され、包囲されて一行は枕を並べて討ち死に寸前まで行ったとされる(論語衛霊公篇2)。以上はおおかた、儒教徒も認める伝説を綴り合わせたものだが、それだけで孔子が人格者などではない事が証明できる。
その上、春秋時代では「徳」とは能力のことだ。生物の持つ機能と言って良い。平均寿命が30そこそこの時代に70過ぎまで生き、身長2mの体軀で武芸の師範だった孔子は、まぎれもない「徳」の人である。それが人徳の意味になったのは、「君子」同様、孟子が自分の金儲けのために、論語を改変して偽善的な意味をくっつけてからだ。真に受ける必要がどこにあろう。
『史記』では本章の出来事を、魯哀公二年(BC493)・孔子59歳の時のこととする。

「孔子聖蹟図」宋人伐木
しかしなぜ桓魋が孔子を憎み、木を引っこ抜いてまでして迫ったのか説明が付かない。それより哀公十四年(BC481)、孔子71歳で司馬牛が変死した際のことと考えた方が話が通る。すなわち司馬牛が孔子一門に見捨てられたのを怨んで、復讐に訪れたと考えたい。


司馬牛は孔子一門には珍しく、れっきとした貴族、それも領地を持つ宋国の名門上級貴族だった。政治革命の宿志を持つ孔子が、司馬牛をただの弟子として扱ったとは思えない。おそらくは宋での政治工作の拠点を、司馬牛に提供させただろう。
司馬牛は普段は宋国にいて、兄の桓魋が失脚するまで住んでいた。しかしなぜか兄を避けるようにし、亡命した斉国に兄が向かっていると聞くと、あてがわれた領地も捨てて呉国に逃亡している。そして呉国にもいられなくなった理由を、『左伝』は国人に憎まれたと書く。
そして司馬牛が向かったのは魯国だった。恐らくその際の問答が、論語には二つある。
孔子「言いにくそうにものを言うことだ。」
司馬牛「たったそれだけ? それだけで仁なのですか?」
孔子「言いにくそうにするのは難しい。仁を語りにくいのももっともだ。」
(論語顔淵篇3)
孔子はまるで突き放すように、司馬牛をまともに扱っていない。その結果。
子夏「そうでもないでしょう。生きるも死ぬも運命です。富貴だって同じです。君子は君子らしく振る舞えば、世界中が兄弟です。それが礼法の教えというものです。」
司馬牛「ハハハハハ。君はいいな。何もわかっちゃいない。」
(論語顔淵篇5)
「ハハハハ」は訳者の付け足しだが、司馬牛の絶望をここに見る。『左伝』は言う。
司馬牛は自分の領地と爵位を示す玉の笏を宋の公室に返上し、斉に行った。
一方すでに宋国を出ていた兄の向魋(=桓魋)は、衛を去った。その途上、公文氏が桓魋を攻めかけて、夏后氏の璜(たま)を奪おうとした。桓魋は公文氏に他の玉を与え、斉に逃亡した。
斉の執権・陳成子が桓魋を迎えて次卿(=準家老)に任命すると、司馬牛は斉で与えられていた領地を返上して、呉に逃げた。
しかし呉の国人が司馬牛を憎んだので居られなくなった。そこで晋の執権・趙簡子が司馬牛を呼び寄せ、陳成子も呼び寄せたが、司馬牛は城門で死んだ。阬氏が司馬牛を丘輿に埋葬した。
おそらくは魯の郊外で自ら命を絶ったのだろう。桓魋は左伝によると決して乱暴者ではなく、失脚して亡命した曹国で、無関係の曹国人を巻き込まないよう配慮するなど、むしろ論語時代の貴族としては例外的と言えるほど道徳的な人物だった。
その桓魋が弟をこのように扱われ、復讐に来た。
訳者はこの説を、ほとんど史実のように思っている。あるいはまた、孔子が華南の陳・蔡国で政治工作をし、呉国に両国を攻めさせて、ほとんど滅亡同然にまで至らせたが、宋国は陳・蔡国の隣国で、あるいは宋国もまた呉国に攻められていた可能性がある。
孔子は怨まれるようなことを、ずいぶんしてきたのだ。
ただし孔子にも言い分がある。仕官して身分差別を乗り越える野心に燃えた若者が、武装して集っているのが孔子塾。しかも弟子のほとんどは庶民の出。だから孔子塾に入門を願う者は、出身地や身分を捨て去らねばならなかった。武装した若者集団で差別が流行ればどうなるか。

内部で血の雨が降ること、日本の新撰組やドイツのSAと同じ。差別禁止は孔子塾の鉄則だった。ところが司馬牛は、『史記』に「口数が多くてはしゃぐ」と書かれたことから、おそらく自分の身分を鼻に掛けたのだろう。そんな司馬牛を、孔子は許すことが出来なかったのだ。
| BC | 魯哀公 | 孔子 | 魯国 | その他 | |
| 481 | 14 | 71 | 斉を攻めよと哀公に進言、容れられず。弟子の顔回死去。弟子の司馬牛、宋を出奔して斉>呉を放浪したあげく、魯で変死 | 孟懿子死去。麒麟が捕らわれる | 斉・簡公、陳成子(田常)によって徐州で殺され、平公即位。宋・桓魋、反乱を起こして曹>衛>斉に亡命 |
| 480 | 15 | 72 | 弟子の子路死去 | 子服景伯と子貢を斉に遣使 | 斉、魯に土地を返還、田常、宰相となる。衛、出公亡命して蒯聵=荘公即位。 |
| 479 | 16 | 73 | 死去。西暦推定日付3/4。曲阜城北の泗水河畔に葬られる | ギリシア、プラタイアの戦い | |
論語の本章、新古の注は次の通り。
古注『論語集解義疏』子曰天生徳於予桓魋其如予何註苞氏曰桓魋宋司馬黎也天生徳於予者謂授我以聖性也合徳天地吉而無不利故曰其如予何也

本文「子曰天生徳於予桓魋其如予何」
注釈。包咸「桓魋は宋の陸軍大臣で名を黎という。天生徳於予とは、自分に神聖な本性を与えたという意味である。その本性で天地が幸福になるような道徳を全て身につけた。だから不運とは縁が無かった。それを踏まえて、自分をどうすることも出来ないと言った。
新注『論語集注』子曰:「天生德於予,桓魋其如予何?」魋,徒雷反。桓魋,宋司馬向魋也。出於桓公,故又稱桓氏。魋欲害孔子,孔子言天既賦我以如是之德,則桓魋其奈我何?言必不能違天害己。

本文「子曰:天生德於予,桓魋其如予何?」
魋の字は、徒-雷の反切で読む。桓魋は、宋の陸軍大臣で名を向魋といった。先祖が宋の桓公だったので、桓氏を名乗った。桓魋は孔子を殺そうとしたが、孔子いわく、天が味方しこのような道徳を身につけさせた。だから桓魋は私をどうにもできない、と。つまり天に逆らって自分をあやめることなどできない、と言ったのだ。
余話
今後はどうだか分からない
孔子とブッダとソクラテスは、同時代を生きた賢者だが、それ以外にも共通点がある。
ブッダはクシャトリアに生まれた。論語における君子と同様、戦士と貴族を兼ねた身分で、おそらく出家前には何度か出陣している武人だった。ペニシリンのない古代に80歳前後生き、岩波文庫が正しければ、死の寸前までその足で歩いてインド各地を旅して回った。
ソクラテスはアテネ市民に生まれた。論語における君子と同様、戦士と有権者を兼ねた身分で、ペロポネソス戦争で勇名を馳せた武人だった。ペニシリンのない古代に70歳以上生き、武勲を立てた時には46歳で、しかも死因は裁判の結果服毒自殺を強いられたことにある。
孔子は父が誰とも分からない巫女の子に生まれた。論語における君子に成り上がったのち、弟子に武術の稽古を付けるほどの武人だった。ペニシリンのない古代に70歳過ぎまで生き、訳者の見立てが正しければ、死の前年か前々年まで現役軍人の桓魋を叩き返す腕力を誇った。
三人とも極めて頑健な肉体を持ち、死の直前まで健康を維持し、スパッと死んだ。
当人を除く家族を含めた全員に、「さっさと○ねばいいのに」と思われつつ、公金をガツガツと食い尽くしグズグズと生きている人間の、存在を否定する権利は訳者にない。だが人類史上珍無類の現象だと断じることは出来る。そもそも専門家による医療が、人類の珍事なのだ。
それを当然の権利と勘違いすると、いずれしっぺ返しを喰らうのではないかと恐れている。対してスパッと死んだ人がかっこよく思えるのは、物心いずれかの利益がない限り、人は人など必要としない事実を物語る。過去の偉人が有り難いのは、生きてカネを要求しないからだ。
日本人の平均寿命が40を超えたとはっきり分かるのは、明治も末ごろのことであるらしい。昭和22年では、男50女54だったと厚労省のサイトにある。孔子の生きた時代は、ものすごくおおざっぱに言って30ほどだったという発掘調査があるという。過去では老人が希少だった。
だから社会にとって老人に価値があった。人には強者を拝む習性がある。老人は長寿だけでも拝む対象で、しかも経験に基づく社会の知恵袋でもあった。その価値が暴落したのは、数理に基づく科学の発達、その精華である現代医療が普及したからだ。普及自体は祝うしかない。
その代償に、人類は膨大な資源を消費する。環境多様性を破壊もする。おかしな男の気分次第で、人類史を終える手段まで持っている。時と共に生存可能性を低めており、一瞬での終焉が防がれているのは偶然でしかない。今書いている2022年現在、誰にも理解して貰えるだろう。
似たような出来事は過去にもあった。キューバ危機の際、ソ連の指導者は核戦争を決意し、米国近海を航行していた潜水艦に、核兵器の使用を命じた。命がけでそれを阻止したのは、副長だったワシリー・アルヒーポフ氏だった。同氏はのちに、海軍兵学校の校長を務めた。
1983年、ソ連の防空システムが暴走し、米国の核兵器がソ連に迫っているとの警報を発した。当直士官だったスタニスラーフ・ピェトローフ氏は、直ちに誤報と判断し、核発射指令を阻止し続けた。こちらはソ連指導部の不興を買い、同氏は退役を余儀なくされた。

過去、ロシア人は英知で人類の滅亡を阻んだ。今後や他国はどうだか分からない。



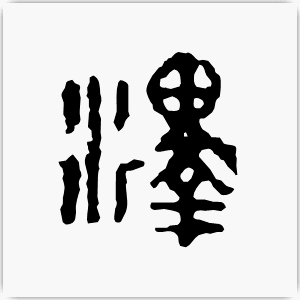

コメント