論語:原文・書き下し
原文(唐開成石経)
子曰我三人行必得我師焉擇其善者而從之其不善者而改之
校訂
諸本
- 武内本:三の上に我の字を補う。釋文云、一本我の字なく、得を有に作る。疏本は一本に同じく、此本(=清家本)及唐石経は釋文に同じ。
東洋文庫蔵清家本
子曰我三人行必得我師焉擇其善者而從之其不善者而改之
後漢熹平石経
(なし)
定州竹簡論語
子曰:「我a三人行,[必得b我師]焉:澤c其善者而從[之,其]163……善者而改164……
- 我、阮本無、皇本・唐石経・高麗本・『釋文』等有「我」字。
- 得、阮本作「有」、皇本・唐石経・高麗本・『釋文』等有「得」字。
- 澤、今本作「擇」。澤借為擇。
※「阮本」とは清儒の阮元が北宋儒の邢昺が編んだ『論語注疏』を復刻したもの。「高麗本」は正平本の誤り。
標点文
子曰、「我三人行、必得我師焉。澤其善者而從之、其不善者而改之。」
復元白文(論語時代での表記)









 焉
焉 













※澤→擇。論語の本章は、「焉」が論語の時代に存在しないが、無くても意味は変わらない。
書き下し
子曰く、我三人行かば、必ず我が師を得る焉。其の善き者を澤び而之に從ひ、其の善から不る者をし而之を改む。
論語:現代日本語訳
逐語訳

先生が言った。「私が三人で共に行けば私の師が見つかるよ。そのよい点を選んでそれに従い、そのよくない点を選んでそれを改める。」
意訳
誰だろうと自分を含め三人連れ立っていれば、どちらか一人は自分を高める助けになる。その長所を見習い、短所を見て、ああならないようにしようと心掛けよう。
従来訳
先師がいわれた。――
「三人道連れをすれば、めいめいに二人の先生をもつことになる。善い道連れは手本になってくれるし、悪い道連れは、反省改過の刺戟になってくれる。」下村湖人『現代訳論語』
現代中国での解釈例
孔子說:「三人走路,必有人可作為我的老師。選擇他的優點向他學習,借鑒他的缺點進行自我改正。」
孔子が言った。「三人が道を行けば、必ず自分の師となるべき人物がいる。彼の優れた点を見習い、欠点を反省材料にして自分の向上に役立てる。」
論語:語釈
子曰(シエツ)(し、いわく)

論語の本章では”孔子先生が言った”。「子」は貴族や知識人に対する敬称で、論語では多くの場合孔子を指す。「子」は赤ん坊の象形、「曰」は口から息が出て来るさま。「子」も「曰」も、共に初出は甲骨文。辞書的には論語語釈「子」・論語語釈「曰」を参照。
この二文字を、「し、のたまわく」と読み下す例がある。「言う」→「のたまう」の敬語化だが、漢語の「曰」に敬語の要素は無い。古来、論語業者が世間からお金をむしるためのハッタリで、現在の論語読者が従うべき理由はないだろう。
我(ガ)


(甲骨文)
論語の本章では”わたし”。初出は甲骨文。字形はノコギリ型のかねが付いた長柄武器。甲骨文では占い師の名、一人称複数に用いた。金文では一人称単数に用いられた。戦国の竹簡でも一人称単数に用いられ、また「義」”ただしい”の用例がある。詳細は論語語釈「我」を参照。
古くは中国語にも格変化があった名残で、一人称では「吾」(古代音ŋag)を主格と所有格に用い、「我」(同ŋar)を所有格と目的格に用いた。ただし甲骨文の時代ですでに、両者の混同現象が見られる。
三(サン)


(甲骨文)
論語の本章では数字の”三”。の初出は甲骨文。原義は横棒を三本描いた指事文字で、もと「四」までは横棒で記された。「算木を三本並べた象形」とも解せるが、算木であるという証拠もない。詳細は論語語釈「三」を参照。
人(ジン)


(甲骨文)
論語の本章では”他人”。初出は甲骨文。原義は人の横姿。「ニン」は呉音。甲骨文・金文では、人一般を意味するほかに、”奴隷”を意味しうる。対して「大」「夫」などの人間の正面形には、下級の意味を含む用例は見られない。詳細は論語語釈「人」を参照。
我三人(われみたり)
”三人+自分一人”と解することも可能だが、漢語の原則はSVO型なので、”自分を含めて三人”→”我々三人”と解する方が文法的な理がある。
行(コウ)


(甲骨文)
論語の本章では”行く”。初出は甲骨文。「ギョウ」は呉音。十字路を描いたもので、真ん中に「人」を加えると「道」の字になる。甲骨文や春秋時代の金文までは、”みち”・”ゆく”の語義で、”おこなう”の語義が見られるのは戦国末期から。詳細は論語語釈「行」を参照。
必(ヒツ)


(甲骨文)
論語の本章では”必ず”。この語義は春秋時代では確認できない。初出は甲骨文。原義は先にカギ状のかねがついた長柄道具で、甲骨文・金文ともにその用例があるが、”必ず”の語義は戦国時代にならないと、出土物では確認できない。『春秋左氏伝』や『韓非子』といった古典に”必ず”での用例があるものの、論語の時代にも適用できる証拠が無い。詳細は論語語釈「必」を参照。
得(トク)
日本伝承本は室町期の清家本から江戸期の根本本まで一貫して「得」と記し、ただし元禄五年(1692)刊の早大蔵新注は「有」と記す。中国伝承本も宮内庁蔵宋版『論語注疏』までは「得」と記し、ただし乾隆御覽四庫全書薈要本の新注では「有」と記す。現存最古の論語本である定州竹簡論語は「得」と記すので、「得」のままとした。論語の伝承について詳細は「論語の成立過程まとめ」を参照。
原始論語?…→定州竹簡論語→白虎通義→ ┌(中国)─唐石経─論語注疏─論語集注─(古注滅ぶ)→ →漢石経─古注─経典釈文─┤ ↓↓↓↓↓↓↓さまざまな影響↓↓↓↓↓↓↓ ・慶大本 └(日本)─清家本─正平本─文明本─足利本─根本本→ →(中国)─(古注逆輸入)─論語正義─────→(現在) →(日本)─────────────懐徳堂本→(現在)


(甲骨文)
論語の本章では”手にする”→”手に入れる”。初出は甲骨文。甲骨文に、すでに「彳」”みち”が加わった字形がある。字形は「貝」”タカラガイ”+「又」”手”で、原義は宝物を得ること。詳細は論語語釈「得」を参照。


(甲骨文)
「有」の初出は甲骨文。ただし字形は「月」を欠く「㞢」または「又」。字形はいずれも”手”の象形。原義は両腕で抱え持つこと。詳細は論語語釈「有」を参照。
師(シ)
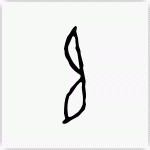

「𠂤」(甲骨文)
論語の本章では”師匠”。初出は甲骨文。部品の「𠂤」の字形と、すでに「帀」をともなったものとがある。「𠂤」は兵糧を縄で結わえた、あるいは長い袋に兵糧を入れて一食分だけ縛ったさま。原義は”出征軍”。「帀」の字形の由来と原義は不明だが、おそらく刀剣を意味すると思われる。全体で兵糧を担いだ兵と、指揮刀を持った将校で、原義は”軍隊”。
金文では原義の他、教育関係の官職名に、また人名に用いられた。さらに甲骨文・金文では、”軍隊”の意ではおもに「𠂤」が用いられ、金文でははじめ「師」をおもに”教師”の意に用いたが、東周になると「帀」を”技能者”の意に用いた。詳細は論語語釈「師」を参照。
焉(エン)
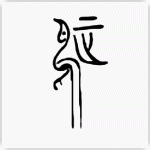

(金文)
論語の本章では「かな」と読んで、”~であろうよ”を意味する詠嘆のことば。断定と解し、または句読を切り直して次の句の冒頭に疑問辞として解するのも戦国以降の漢文としては間違いではないが、春秋時代に適用するのは難しい。
字の初出は戦国早期の金文で、論語の時代に存在せず、論語時代の置換候補もない。漢学教授の諸説、「安」などに通じて疑問辞や完了・断定の言葉と解するが、いずれも春秋時代以前に存在しないか、その用例が確認できない。ただし春秋時代までの中国文語は、疑問辞無しで平叙文がそのまま疑問文になりうるし、完了・断定の言葉は無くとも文意がほとんど変わらない。
字形は「鳥」+「也」”口から語気の漏れ出るさま”で、「鳥」は装飾で語義に関係が無く、「焉」は事実上「也」の異体字。事実上「也」の異体字。「也」は春秋末期までに句中で主格の強調、句末で詠歎、疑問や反語に用いたが、断定の意が明瞭に確認できるのは、戦国時代末期の金文からで、論語の時代には存在しない。詳細は論語語釈「焉」を参照。
擇(タク)→澤(タク)
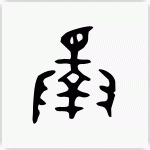

(金文)
論語の本章では”選ぶ”。初出は西周末期の金文。新字体は「択」。字形は「睪」+「廾」”両手”で、「睪」の甲骨文は向かってくる矢をじっと見つめる姿。全体で、よく見て吟味し選ぶこと。原義は”選ぶ”。金文では原義で用いた。詳細は論語語釈「択」を参照。


定州竹簡論語では「澤」と記す。新字体は「沢」。論語の本章に限れば、「擇」の誤字と考える以外に方法が無い。初出は戦国文字。字形は「氵」”川”+「睪」。矢のように細く素早く流れる川の意。戦国の竹簡に”さわ”の用例がある。戦国末期までに、”えらぶ”の語義は確認できない。詳細は論語語釈「沢」を参照。
其(キ)


(甲骨文)
論語の本章では”その”。初出は甲骨文。原義は農具の箕。ちりとりに用いる。金文になってから、その下に台の形を加えた。のち音を借りて、”それ”の意をあらわすようになった。人称代名詞に用いた例は、殷代末期から、指示代名詞に用いた例は、戦国中期からになる。詳細は論語語釈「其」を参照。
善(セン)


(金文)
論語の本章では、”善事”。もとは道徳的な善ではなく、機能的な高品質を言う。「ゼン」は呉音。字形は「譱」で、「羊」+「言」二つ。周の一族は羊飼いだったとされ、羊はよいもののたとえに用いられた。「善」は「よい」「よい」と神々や人々が褒め讃えるさま。原義は”よい”。金文では原義で用いられたほか、「膳」に通じて”料理番”の意に用いられた。戦国の竹簡では原義のほか、”善事”・”よろこび好む”・”長じる”の意に用いられた。詳細は論語語釈「善」を参照。
者(シャ)


(金文)
論語の本章では、”…である者”。旧字体は〔耂〕と〔日〕の間に〔丶〕一画を伴う。新字体は「者」。ただし唐石経・清家本ともに新字体と同じく「者」と記す。現存最古の論語本である定州竹簡論語も「者」と釈文(これこれの字であると断定すること)している。初出は殷代末期の金文。金文の字形は「木」”植物”+「水」+「口」で、”この植物に水をやれ”と言うことだろうか。原義は不明。初出では称号に用いている。春秋時代までに「諸」と同様”さまざまな”、”…は”の意に用いた。漢文では人に限らず事物にも用いる。詳細は論語語釈「者」を参照。
而(ジ)


(甲骨文)
論語の本章では”…であって同時に”。初出は甲骨文。原義は”あごひげ”とされるが用例が確認できない。甲骨文から”~と”を意味し、金文になると、二人称や”そして”の意に用いた。英語のandに当たるが、「A而B」は、AとBが分かちがたく一体となっている事を意味し、単なる時間の前後や類似を意味しない。詳細は論語語釈「而」を参照。
從(ショウ)


(甲骨文)
論語の本章では、”従う”。初出は甲骨文。新字体は「従」。「ジュウ」は呉音。字形は「彳」”みち”+「从」”大勢の人”で、人が通るべき筋道。原義は筋道に従うこと。甲骨文での解釈は不詳だが、金文では”従ってゆく”、「縦」と記して”好きなようにさせる”の用例があるが、”聞き従う”は戦国時代の「中山王鼎」まで時代が下る。詳細は論語語釈「従」を参照。
之(シ)


(甲骨文)
論語の本章では”これ”。初出は甲骨文。字形は”足”+「一」”地面”で、あしを止めたところ。原義はつま先でつ突くような、”まさにこれ”。殷代末期から”ゆく”の語義を持った可能性があり、春秋末期までに”~の”の語義を獲得した。詳細は論語語釈「之」を参照。
不(フウ)


(甲骨文)
漢文で最も多用される否定辞。初出は甲骨文。「フ」は呉音(遣隋使より前に日本に伝わった音)、「ブ」は慣用音。原義は花のがく。否定辞に用いるのは音を借りた派生義だが、甲骨文から否定辞”…ない”の意に用いた。詳細は論語語釈「不」を参照。
改(カイ)
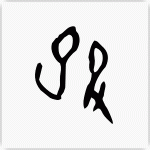

(甲骨文)
論語の本章では”あらためる”。初出は甲骨文。甲骨文の字形は「巳」”へび”+「攴」”叩く”。蛇を叩くさまだが、甲骨文から”改める”の意だと解釈されており、なぜそのような語釈になったのか明らかでない。詳細は論語語釈「改」を参照。
論語:付記
検証
論語の本章は、論語里仁篇17とほとんど同じで、論語の時代に於ける「焉」の不在も同じ。従来の説に、論語の前十篇と後十篇でおおむね編者が違うというのがあるが、もっと複雑に入り組んでいると考えた方がいい。再録は前漢中期の『史記』孔子世家から。「焉」の字の論語時代に於ける不在はどうにもならないが、無くても意味は変わらないし、「焉」は事実上「也」の異体字だから、論語の本章は史実の孔子の発言として扱ってよい。
解説
論語では「焉」の扱いで解釈が大きく変わることが多い。なぜか従来の論語の解説では、できるだけ焉を句末に置きたがる。しかし句頭に置いた方が無理な訳をせずに済む場合は、ためらいなく句読の疑問辞として解した方がよい。
例えば直後に「曰く」がある場合は、これは話者がそこで切り替わっているのだから、焉は句末で意味は断定と取るしかない。しかし本章のように、句頭に置いても差し支えない場合、「焉んぞ」と読んで疑問の意味ではないかと考えておく必要はある。
我三人行かば、必ず我が師を得ん。焉んぞ其の善者を澤び而之に從はん。其の不善なる者は、し而之を改む。
三人連れ立てば、必ず先生が見つかる。だが(優れた人はめったにいないから、)どうしてその長所を見習えるのか。短所を見て、(自分の)欠点を改める。
検討の上で、例えば本章の場合、「補わなければならない言葉が多すぎる」と判断し、「焉」を句末に持ってくるのはよい。ただ、最初から決めてかかって漢文を読んではならないということだ。
過去の句読や解釈を、疑わずに読むのも論語の読み方ではあるが、その結果読者は恐ろしくつまらない思いを論語に感じる場合が多い。儒者は商売上孔子を神聖な人として扱わなければならなかったのであり、商売に差し支えるわけでなければ、現代の論語読者は自由でいい。
なお本章で「三人」というのは、必ず数が三である意味ではない。漠然と少なくない数を、漢文では三と書く場合が多い。従って訳をさらに丸めると、「人と交われば必ず手本がいる。しかし賢者はめったにいないから、馬鹿者を見て真似しないよう気を付けなさい。」
三で”たくさん”を意味するのは、漢字の成り立ちも同じで、「衆」の現代中国語簡体字「众」は、古い書体に先祖返りした形で、人三つで”たくさんの人”を意味している。同様に木なら「森」、物体なら「品」、石なら「磊」で、石がゴロゴロしているさまをいう。
論語の本章、新古の注は次の通り。
古注『論語集解義疏』
子曰我三人行必得我師焉擇其善者而從之其不善者而改之註言我三人行本無賢愚擇善從之不善改之故無常師也疏子曰至改之 此明人生處世則宜更相進益雖三人同行必推勝而引劣故必有師也有勝者則諮受自益故云擇善而從之也有劣者則以善引之故云其不善者而改之然善與不善即就一人上為語也人不圓足故取善改惡亦更相師改之義也故王朗曰于時道消俗薄鮮能崇賢尚勝故託斯言以厲之夫三人之行猶或有師沉四海之內何求而不應哉縱能尚賢而或滯於一方者又未盡善也故曰擇其善者而從之其不善者而改之或問曰何不二人必云三人也荅曰二人則彼此自好各言我是若有三人則恒一人見二人之有是非明也 註言我至師也 云言我三人行本無賢愚者就注意亦是敵者也既俱非圓徳則遞有優劣也云擇善云云者我師彼之長而改彼之短彼亦師我之長而改我之短既更相師法故云無常師也


本文「子曰我三人行必得我師焉擇其善者而從之其不善者而改之」。
注釈。「我三人行」と言ったのは、もとは賢愚の話では無かった。孔子は善を選んで従い、不善を改めたから、「決まった師匠がいなかった」(論語子張篇21)のである。
付け足し。先生は改める事の極致を言った。これは人の生き方を明らかにした話で、だから互いに高め合うなら、たった三人の同行者でも、優れた者が優れていないものを教えその逆もある。だから必ず参考になる。優れた者は問われることで一層自分を高め、だから”善を選んでこれに従う”と言った。劣った者は優れた者に引き上げてもらい、だから”不善は改める”と言った。
だが善不善は、一人の人間にも言えることだ。人には足りない点があるから、善を取って悪を改めるなら、善悪がそれぞれの参考になって高め合うことが出来るのだ。だから王朗が言った。「時代によって道徳が衰えることはある。賢者や善人に学ぶ機会が減ることもある。だからこの話をして、人を励ましたのだ。たった三人でも参考になるなら、広い世界のどこでも学ばずにはいられないではないか。賢者を尊び従うあまり、人格に片寄りが出てしまえば、それも善を尽くしたとは言えないではないか。だから”善人を敬って従い、不善人は改める”と言ったのだ。」
ある人「どうして二人でなく三人なのですか?」
答えた人「二人だと互いに、自分が正しいと言い張って参考にならない。第三者がいるなら、どちらが正しいか判断して貰えるからだ。」
注釈。これは自分にとっての最高の師を言ったものだ。「我三人行」と言ったのは、もとは賢愚の話では無かった、とあるのは、対等の者にも学ぶべき点があることを指摘したものだ。一緒に行動しても、人格的に足りない点があるなら、お互いの優れた所で劣った所を補うのである。「善を選び」うんぬんは、同行者の優れた点に学び、劣った点を改めてやる、そして逆もまた同じということだ。互いに弟子となり師匠となる、この変転があるから、常の師は居ないのである。
新注『論語集注』
子曰:「三人行,必有我師焉。擇其善者而從之,其不善者而改之。」三人同行,其一我也。彼二人者,一善一惡,則我從其善而改其惡焉,是二人者皆我師也。尹氏曰:「見賢思齊,見不賢而內自省,則善惡皆我之師,進善其有窮乎?」


本文「三人行,必有我師焉。擇其善者而從之,其不善者而改之。」
三人で同行すれば、その一人は自分である。ほかの二人は、あるいは善くてあるいは悪いだろう。だから自分は他人の善さを見習い、自分の悪を改める。こうして他の二人は共に自分の師となる。
尹焞「賢者を見たら自分もああなろうと思う。賢くない者を見たらああならないようにしようと心に思う(論語里仁篇17)。つまり他人の善も悪も、全て自分の教訓となる。そして善を磨き上げることに、どうして終わりがあるだろうか?」
余話
中国人と物理法則
中国人と他人の善行愚行との関係は、ひとえに利益のあるなしによる。利益があれば悪人や愚者の真似を平気でするし、利益がなければ善人や賢者の真似など決してしない。これは中国人に限ったことではないし、日本人を含めて人間はそういうふうに出来上がっている。

マラッカ海峡。2012.4.3
シンガポールに旅したとき、ホテルのカフェテリアで朝食を摂ろうとしたら破壊的騒音が轟いていた。ある中国人の集団が一隅に陣取り、席は強化ガラスの仕切りで分けられていたが、その一団に属する幼児が、金属製のカトラリーでガンガンとしつこくガラスを叩く音だった。
強化ガラスだろうと設計限界を超えた衝撃が加われば割れる道理で、それら中国人は阿鼻叫喚の負傷を被るはずだが、一団の誰一人気にもとめず、ガツガツと家畜のようにめしを食っていた。一団は海外旅行する程度に金はあるが、脳みその中身は猿と大差ないと見えた。
現代日本に住んでいるとうっかり、親は子に「危ないことは止めなさい」と言うのが当たり前だと思ってしまう。しかし中国人は古来、子はいずれ食うために用意するものと覚悟しており、運良く生涯食わずに済んでも、老後や冥土の生計を立てるための合理的手段でしかない。
- 論語為政篇24余話「中国人と科学」
その参考動画。閲覧注意。さらに日本人にしたところで、もとは子をそんなに大事とは思っていなかった。子の複数形が子たちでなく子どもであるのがその証拠で、勝手に生えてくる何かとしか思っていなかったふしがある。それが商業主義に煽られてお子様へと大出世した。
子ですらかくのごとし、まして夫婦など食い合いの対象でしかない。
祭仲專,鄭伯患之,使其婿雍糾殺之,將享諸郊。雍姬知之,謂其母曰,父與夫孰親,其母曰,人盡夫也,父一而已,胡可比也?遂告祭仲曰,雍氏舍其室,而將享子於郊,吾惑之,以告,祭仲殺雍糾,尸諸周氏之汪,公載以出,曰,謀及婦人,宜其死也。
(中国の春秋時代初期、鄭国の覇権を支えた筆頭家老の祭仲は、コンビを組んだ主君の荘公が世を去ると、あとを継いだ厲公がバカ殿だったので、)祭仲は勝手に政治を動かした。厲公が不満をつのらせ、祭仲の娘婿である雍糾をそそのかして、「殺してしまえ」と命じた。
雍糾は「野遊びでお義父上をもてなし申したい」と祭仲を誘い出そうとしたが、妻の雍姫が夫の陰謀を知り、どうしたものかと母親に相談した。
雍姫「父と夫ではどちらが大切なのでしょうね?」
母親「そんなの決まっている。夫などは取り替えが利くが、父に代わりは居ない。なぜそんなことを言い出す?」
雍姫はそう言われて事の次第を父の祭仲に告げた。「ウチの人はわらわを留守にして、野遊びと言って父上をもてなそうとしていますが、どうもコソコソと何か企んでいるようです。念のため父上はご用心下さい。」
聞いた祭仲は先手を打って雍糾を捕らえ殺し、なきがらを周氏の屋敷の池に放り込んだ。厲公はアワを食って宮殿から逃げ出し、おつきの者に愚痴をこぼした。「小娘にはかられたわ。くたばれ!」(『春秋左氏伝』桓公十五年2)
愛も夢も無いと立腹される諸賢もおられるかも知れない。だが人の夢と書いて儚いと読む。はか無し、当てにならないの意。そんな愛に期待するから、いつまでも他人や自分に振り回され、おのれの不幸が減らない。自分の妄想に自分が苦しむのは、馬鹿らしいと思いませんか。
妄想は美しいが、常に哀しい。
類人猿とヒトとで、遺伝子に1%程度の違いしか無いらしい。類人猿対象の生物学をサル学と呼ぶようだが、ヒトとサルとの違いを定義づけるのは、えらく困難な仕事であると聞く。ならばヒトは放置すればサル同然になるのが理の当然で、日本のDKがよくその道理を証している。
- 論語子罕篇23余話「DK畏るべし」
中華文明の弱点はここで、現実的な行動様式にもかかわらず、知識人でも利益がなければ数理を受け入れないから、死なぬでいい人が死にもする。中国史上、洪水・疫病・饑饉、役人や蛮族や他村民による拉致略奪暴行殺人は連年起こるから、非常事態には慣れているはずだが。
- 論語学而篇4余話「中華文明とは何か」

天災の際に真っ先に死ぬのは、運の無い人で、カネや権力の有無も運次第だから、それらゆえに死ぬのも運の無さに統合できる。次に死ぬのは頭の悪い人で、くだんのシンガポールの中国人が、誰一人怪我もせずに済んだのは、単なる偶然であってカネや脳みそのおかげではない。
概して東洋人は勉強が好きだという生物学的研究を読んだことがある。中華文明も同様で、論語の本章のように学ぶことを勧める言葉はあまたある。だが学ぶにしても空理空論やデタラメをどんなに学んだところで、ますます自分を窮地に追い詰める結果になるばかりだ。
それを自覚しない者が、「学問とは積み重ねだ」と偉そうに説教するのを聞いたら、鼻でせせら笑ってやるといい。その者はただ運がいいだけで、金はあるかも知れないが、頭が悪くてたいていは、金の不足を歎いている。不足を歎く程度の知能だから、偉そうに説教などもする。
人が説教をする理由は、一つに損害に対する腹立ちゆえ、もう一つは娯楽ゆえだ。娯楽と言っても高級なものではなく、サディズムの一種で明確に精神医学上の疾病である。我慢した後のしょうべんのように説教を垂れてくる者は、聞き手が精神科医でないなら関わっても利益は無い。
加虐者はほぼ過去に被虐している。過去の加虐者が死んじまったか、怖くて報復できないから、「どうでもいいや」と思っている相手に加虐を始める。つまり返す相手を間違えているか、返す方法を知らないからの八つ当たり、すなわち脳機能の障害ゆえにサドを疾病と言う。
脳機能の障害だから虐待の連鎖に気付かず、連鎖を断ち切るには「加虐すまじ」を断行すべきことわりを知らない。八つ当たりで心は癒されず、周囲の不幸を増大させ、人には嫌われいたずらに敵を増やし、やがてさっさと死んだ方がいいと思える目に遭う恐れを抱かない。
若い人は、どうかそうした虚喝者の言うことに、恐れを抱かないで頂きたい。
参考記事
- 論語述而篇27余話「嫌われてるとも知らないで」
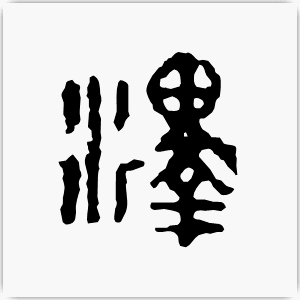

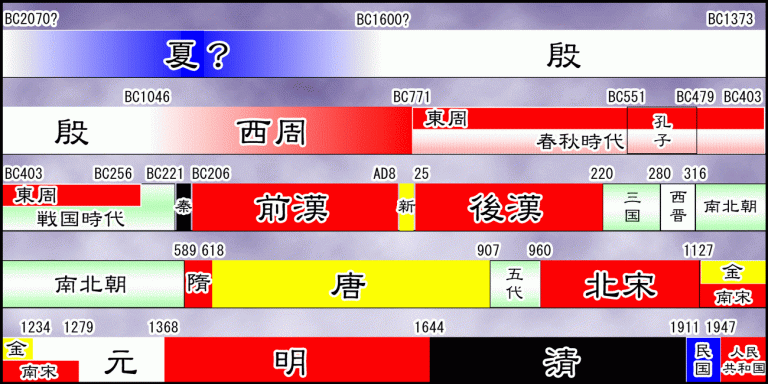


コメント