論語:原文・書き下し
原文(唐開成石経)
子曰非其鬼而祭之諂也見義不爲無勇也
※「鬼」字は〔人田儿人〕。「勇」字は「田」ではなく「用」。
校訂
諸本
- 武内本:宋本章末也の字あり、正和本嘉暦本なし、縮臨本也の字ある宋本によって補うところ。
東洋文庫蔵清家本
子曰非其鬼而祭之謟也/見義不為無勇
※「鬼」字は〔田儿厶〕
後漢熹平石経
(なし)
定州竹簡論語
[子]曰:「非其鬼而[祭]之,[諂]也。□□□□□□36
標点文
子曰、「非其鬼而祭之、諂也。見義不爲、無勇。」
復元白文(論語時代での表記)







 諂
諂







※論語の本章は、「諂」が論語の時代に存在しない。「其」「義」の用法に疑問がある。本章は前漢帝国の儒者による創作である。
書き下し
子曰く、其の鬼に非ずし而之を祭るは、諂也。義を見て爲不るは、勇無し。
論語:現代日本語訳
逐語訳

先生が言った。「自分の先祖の霊でもないのに祭るのは、へつらいだよ。筋の通った行為を行わないのは、勇気がない。」
意訳

よその仏を拝むのはおべっかだぞ。正義を行わない奴には勇気がない。
従来訳
先師がいわれた。――
「自分の祭るべき霊でもないものを祭るのは、へつらいだ。行うべき正義を眼前にしながら、それを行わないのは勇気がないのだ。」下村湖人『現代訳論語』
現代中国での解釈例
孔子說:「祭奠別人的先人,是諂媚;遇到符合道義的事不敢做,是懦夫。」
孔子が言った。「他人の先祖の法事をするのは、ごますりだ。正義にかなった事件に出くわして真っ先に行動しないのは、いじけた男だ。」
論語:語釈
子曰(シエツ)(し、いわく)

論語の本章では”孔子先生が言った”。「子」は貴族や知識人に対する敬称で、論語では多くの場合孔子を指す。「子」は赤ん坊の象形、「曰」は口から息が出て来るさま。「子」も「曰」も、共に初出は甲骨文。辞書的には論語語釈「子」・論語語釈「曰」を参照。


(甲骨文)
この二文字を、「し、のたまわく」と読み下す例がある。「言う」→「のたまう」の敬語化だが、漢語の「曰」に敬語の要素は無い。古来、論語業者が世間からお金をむしるためのハッタリで、現在の論語読者が従うべき理由はないだろう。
非(ヒ)


(甲骨文)
初出は甲骨文。甲骨文の字形は互いに背を向けた二人の「人」で、原義は”…でない”。「人」の上に「一」が書き足されているのは、「北」との混同を避けるためと思われる。甲骨文では否定辞に、金文では”過失”、春秋の玉石文では「彼」”あの”、戦国時代の金文では”非難する”、戦国の竹簡では否定辞に用いられた。詳細は論語語釈「非」を参照。
其(キ)


(甲骨文)
論語の本章では”その”という指示詞。初出は甲骨文。甲骨文の字形は「𠀠」”かご”。かごに盛った、それと指させる事物の意。金文から下に「二」”折敷”または「丌」”机”・”祭壇”を加えた。人称代名詞に用いた例は、殷代末期から、指示代名詞に用いた例は、戦国中期からになる。詳細は論語語釈「其」を参照。
鬼(キ)
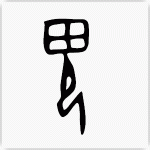

(甲骨文)
論語の本章では、角を生やした”オニ”ではなく、”亡霊・祖先の霊”。字形は「囟」”大きな頭”+「卩」”ひざまずいた人”で、目立つが力に乏しい霊のさま。原義は”亡霊”。甲骨文では原義で、また国名・人名に用い、金文では加えて部族名に、「畏」”おそれ敬う”の意に用いられた。詳細は論語語釈「鬼」を参照。
而(ジ)


(甲骨文)
論語の本章では”それで”。初出は甲骨文。原義は”あごひげ”とされるが用例が確認できない。甲骨文から”~と”を意味し、金文になると、二人称や”そして”の意に用いた。英語のandに当たるが、「A而B」は、AとBが分かちがたく一体となっている事を意味し、単なる時間の前後や類似を意味しない。詳細は論語語釈「而」を参照。
祭(セイ)


(甲骨文)
論語の本章では”祭祀を行う”。初出は甲骨文。「サイ」は呉音。「チンチンドコドン」の”おまつり”ではなく、日本で言う法事に当たる。字形は「月」”肉”+「示」”位牌”+「又」”手”で、位牌に肉を供えるさま。原義は”故人を供養する”。甲骨文では、原義で用いられ、金文では加えて、人名に用いられた。詳細は論語語釈「祭」を参照。
之(シ)


(甲骨文)
論語の本章では”これ”。初出は甲骨文。字形は”足”+「一」”地面”で、あしを止めたところ。原義はつま先でつ突くような、”まさにこれ”。殷代末期から”ゆく”の語義を持った可能性があり、春秋末期までに”~の”の語義を獲得した。詳細は論語語釈「之」を参照。
諂(テン)


(隷書)/「臽」(金文)
論語の本章では、こびへつらいのうち、”相手を落とし穴にはめるようなへつらい”。初出は前漢の隷書。論語の時代に存在しない。論語時代の置換候補も無い。同音は存在しない。字形は「言」+「臽」”落とし入れる”で、言葉で人を落とし入れること。詳細は論語語釈「諂」を参照。
也(ヤ)


(金文)
論語の本章では、「かな」と読んで詠嘆の意、または「なり」と読んで断定の意に用いている。後者の語義は春秋時代では確認できない。初出は事実上春秋時代の金文。字形は口から強く語気を放つさまで、原義は”…こそは”。春秋末期までに句中で主格の強調、句末で詠歎、疑問や反語に用いたが、断定の意が明瞭に確認できるのは、戦国時代末期の金文からで、論語の時代には存在しない。詳細は論語語釈「也」を参照。
文末の「也」は、唐石経とそれを祖本とする現伝論語は記すが、現存最古の古注本である宮内庁蔵清家本は記さず、現存最古の論語本である定州竹簡論語は「見義不爲無勇」と同じく6文字分の判読不能字があり、その後ろは欠損している。定州竹簡論語の簡36号を横書きにして示せば次の通り。
「子」の上には、簡の頭に欠損がなく、かつそれ以前に文字が記されていなかった記号が付いているが、簡の尾には欠損がある。なお「一枚に記された文字は19-21字」という。つまり定州本は、文末の「也」の有無を明かす証拠にならない。よって時系列に従い、宮内庁蔵清家本の通り文末の「也」は無いものとして校訂した。
上掲武内本に「宋本によって補うところ」と言い、宮内庁蔵南宋本『論語注疏』は確かにそうなっているが、宋本は唐石経を引き継いだだけで、特に「宋本によって補」ったわけではない。
論語の伝承について詳細は「論語の成立過程まとめ」を参照。
原始論語?…→定州竹簡論語→白虎通義→ ┌(中国)─唐石経─論語注疏─論語集注─(古注滅ぶ)→ →漢石経─古注─経典釈文─┤ ↓↓↓↓↓↓↓さまざまな影響↓↓↓↓↓↓↓ ・慶大本 └(日本)─清家本─正平本─文明本─足利本─根本本→ →(中国)─(古注逆輸入)─論語正義─────→(現在) →(日本)─────────────懐徳堂本→(現在)
見(ケン)


(甲骨文)
論語の本章では”見る”。初出は甲骨文。甲骨文の字形は、目を大きく見開いた人が座っている姿。原義は”見る”。甲骨文では原義のほか”奉る”に、金文では原義に加えて”君主に謁見する”、”…される”の語義がある。詳細は論語語釈「見」を参照。
義(ギ)


(甲骨文)
論語の本章では”行うべき正義”。この語義は春秋時代では確認できない。初出は甲骨文。字形は「羊」+「我」”ノコギリ状のほこ”で、原義は儀式に用いられた、先端に羊の角を付けた武器。春秋時代では、”格好のよい様”・”よい”を意味した。詳細は論語語釈「義」を参照。
不(フウ)


(甲骨文)
漢文で最も多用される否定辞。初出は甲骨文。原義は花のがく。否定辞に用いるのは音を借りた派生義。詳細は論語語釈「不」を参照。現代中国語では主に「没」(méi)が使われる。
爲(イ)
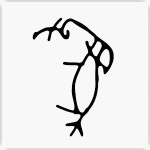

(甲骨文)
論語の本章では”する”。新字体は「為」。字形は象を調教するさま。甲骨文の段階で、”ある”や人名を、金文の段階で”作る”・”する”・”~になる”を意味した。詳細は論語語釈「為」を参照。
無(ブ)


(甲骨文)
論語の本章では”…が無い”。初出は甲骨文。「ム」は呉音(遣隋使より前に日本に伝わった音)。甲骨文の字形は、ほうきのような飾りを両手に持って舞う姿で、「舞」の原字。その飾を「某」と呼び、「某」の語義が”…でない”だったので、「無」は”ない”を意味するようになった。論語の時代までに、”雨乞い”・”ない”の語義が確認されている。戦国時代以降は、”ない”は多く”毋”と書かれた。詳細は論語語釈「無」を参照。
勇(ヨウ)


(金文)
論語の本章では、”勇気”。現伝字形の初出は春秋末期あるいは戦国早期の金文。部品で同音同訓同調の「甬」の初出は西周中期の金文。「ユウ・ユ」は呉音。字形は「甬」”鐘”+「力」で、チンカンと鐘を鳴るのを聞いて勇み立つさま。詳細は論語語釈「勇」を参照。
論語:付記
検証
論語の本章は、同文を前漢後期の劉向が『説苑』反質2で孔子の言葉として再録するまで、誰も引用していない。恐らく本章は、儒家が道家をパクって作った。似たような話が『老子』にある。
治大國若烹小鮮。以道蒞天下,其鬼不神;非其鬼不神,其神不傷人;非其神不傷人,聖人亦不傷人。夫兩不相傷,故德交歸焉。

大国を治めようとするなら、小魚を料理するように慎重にしたらよい。宇宙の根本法則を理解した上で天下に君臨するなら、亡霊も精霊のような力を持たない。精霊も人を傷付けない。だから聖人もまた、人を傷付けない。君主も霊魂も共に人を傷付けないから、互いに補い合って天下が上手く回るのだ。(『老子道徳経』60)
もちろんこれは、周王室の文書館長を務め、若き日の孔子に教えを垂れた実在の老子、その人の言葉ではなく、恐らくは戦国時代の道家が『荘子』をもじったもの。
故曰:其動也天,其靜也地,一心定而王天下;其鬼不祟,其魂不疲,一心定而萬物服。

だから言うのだ。天体は動くが大地は動かない。大地のように情緒が安定して、やっと君主が務まる。それなら幽霊も祟らないし、亡霊も生きた人間にお供えをせびらない。そこまで情緒が安定して、やっと人も自然も逆らわなくなるのだ。(『荘子』天道1)
解説
高校世界史的理解では、前漢中期の武帝の時代に儒教は国教化され、少し詳しい中国史では、漢の高祖劉邦が儒教を取り入れて天下を安定させたとする。だが実情はかなり違う。武帝の少年期、帝室を仕切っていた竇太后は道教マニアで、反論する儒者をひどい目に遭わせた。
景帝の母である竇太后は、老子の本を好んでいた。あまりに入り浸ったので、ふと儒者の轅固が、普段見せる高慢ちきな顔を思い出し、呼び付けて老子に恐れ入らそうと考えた。だがしかし。
轅固「とんでもない。老子の言い分など奴隷根性のたわごとです。」
兄弟は奴隷という出身の太后は、痛い所を突かれて激怒した。「皆の者、こやつを牢にブチ込んで、休日無しの煉瓦づみにしやれ!」
というわけで轅固は牢に放り込まれたが、それでも老子の悪口を言い続けたので、「檻の中でイノシシと決闘せい」と命じられた。話を聞いた景帝は思った。「母上は怒っておいでだが、轅固の正直はお認めの筈だ。」
というわけで轅固によく切れる刀を渡し、イノシシの檻に閉じこめた。だが儒者には珍しいことに、轅固は一突きでイノシシの心臓を貫き仕留めた。
見物していた太后は黙ってしまい、かといって見物人が多すぎて、新たな罪をなすりつけるわけにもいかなかった。轅固は釈放、ほとぼりが冷めてから、景帝は息子の清河王の守り役頭に取り立てた。轅固は長年仕事に励み、老年を理由に退職となった。(『史記』儒林伝)
また武帝が儒教に肩入れしたのも、竇太后など道教マニアの帝室の年長者に、よってたかっていじめられた反感からで、別に儒学が好きだったわけではない。だから国教化は半ばウソで、事実上武帝のあとを継いだ宣帝は、「儒者という役立たず」と平気で言い放った。
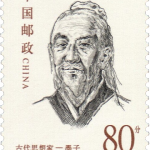

古代中国の学問は、事実上孔子から始まるのだが、その後の学界が、つねに儒家に仕切られていたわけではない。孔子没後は墨家が主導権を握り、墨子没後は百家争鳴状態になった。孟子は確かに儒家を再興したが、大して出世できなかったし、何より教説が幼稚に過ぎた。
幼稚というなら現伝の『墨子』も、実に幼稚な話が連なっている。だが現伝『墨子』は戦国末の墨家による作文はほぼ明らかだし、何より墨家には、古代なりの科学技術が伴っていた。対して孟子は口先で言いくるめるだけが能で、教説を真に受けた諸侯はひどい目に遭っている。
そうでなくとも孟子一党の素行の悪さには、誰もがあきれた。
孟子が子分どもを引き連れて滕の国へ巡業し、殿様の屋敷に逗留した。子分の一人が、窓の上に置いてあったスリッパをくすね、屋敷の管理人が探しても見つからない。
管理人「ああたの従者って、平気で人のものを盗むんですね。」
孟子「管理人どの、我らがスリッパ泥棒の巡業に来たとでも?」
管理人「そうまでは言いませんが…。」(『孟子』盡心下76)
というわけで秦帝国が統一を果たしても、やはり学界は百家争鳴だった。確かに法家が権力と結びついて優位に立ったが、のちの儒家のように、道家を除く他学派を、ことごとく滅ぼすようなことはなかった。儒家もその他の学派も、ちゃんと秦帝国の博士官になっている。
帝政中国の儒家が道家を滅ぼせなかったのは、息をするように絵空事を言い(聖王伝説)、「お前だけそうしろ」と他人に自己犠牲を説教し(忠孝)、知りもしない未来を予測できるとウソ八百を並べ立てた(『中庸』)からで、九分九厘の中国人から馬鹿の集まり(書呆子)だと見なされたからだ。
訳者はDK世代の残忍を体験したから分かる事だが、思想≒宗教の違いで人は平気で虐殺をやるし、日本にも戦前は特高やらがうろついていた。中国史上の思想弾圧は常時のことで、簡単な理由で人は一族郎党が刑殺に追いやられる。殺られるまえに殺れ、という社会。
それを踏まえて本章を読み返すと、儒家がネタに困って道家をパクったと理解できる。親子でも平気で叩き売るのが人間というもので、はるか古代にその社会的合意が出来てしまったから、中国人はいま世界中から嫌われているのだが、漢の儒者ももちろんその例外ではない。
なお戦国の竹簡からは、明確に『老子道徳経』とわかる資料が出土しているが、論語は似た文字列がいくつか出土しているだけで、版本の成立としては『老子道徳経』よりはるかに新しい。
余話
中国人と科学(We planet)
科学が分からないからと言って、決して中国人を侮ってはならない。
中華文明の真髄の究極は、自身の生存への揺るぎない信仰にある。だから始皇帝が巨大な陵墓を築き、人民は原始時代から他人をいびり出し、「やっていいよ」と毛沢東に言われた瞬間、「お前は死ね俺は生きる」を全中国でやらかした。そして信仰と現代科学は相容れない。
正教の信仰を捨てたのち、ロシア人はスプートニクとガガーリン少佐を打ち上げた。
敵を震え上がらせ給え/正教のツァーリ
(ロシア帝国国歌)(→youtube)
誰も我らの救済者ではない/神は救わずツァーリも救わず、英雄も我らを救わない
我らは自分で自分を解放するのだ/それぞれの自分の手で
(1944年までのソ連国歌「インターナショナル」)(→youtube)
だからロシア人とその歴史が似ているようでいて、中国人は下掲動画が訴える”We planet”が理解出来ない。狂信者が善事と確信し、異端者を火あぶる薪をイソイソと運ぶように、中国人は正気で、なぜこんなに嫌われるか分からない。合理を突き詰めた時代が長過ぎたからだ。
安能務曰く「誰もが自分の足元を軸に地球が回ると思っている」。従って工業化後の現在も中国人は物理法則を受け入れず(論語述而篇21余話)、個人の終焉も受け付けない。つまり中国人には科学が分からず、分かった中国人は中華文明を捨てた、中国人ならざる人に他ならない。
それが社会の圧倒的少数だから、中国はいつまでも独裁を抜け出せない。訳者はそうした少数派の、中国人をやめた人を何人か知っているが、目の前で唐詩などを解読してみせると目を丸くする。中華文明の標識の一つは漢字だが、科学的元中国人に漢文が読める人は少ない。
対して普通の中国人は合理を一周し、かえって自分を客観的に見られない。売れるものは親子兄弟だろうと売り飛ばす。饑饉には他人と子を取り替えて食った。儲かって後難がなければ何でもやる。約束は相手に守らせるものだ。そのどこが悪いのだろう、と心底から思っている。
黙って売り飛ばされるのを、論語で「孝悌」という。自分でない人を洗脳して食う中華文明の精華で、自分がすべき道徳ではない。ここを踏まえない漢文語りは、読めもしない漢文を読んだとウソをついているか、だます気満々かのどちらかで、たいていは両者を兼ねている。
中国の饑饉は生涯に五六度はある。つまり全中国人は食われるのを承知で子を他人に売った。
ミツバチが姉妹のためにイソイソと蜜を集め、死も恐れずスズメバチと戦うのは、姉妹で遺伝子の3/4を共有し、1/2しか共有しない親子より近しいからだが、中国人は遺伝子生物学の例外で、我が身以外に守る気は無く、子が必要なのは食うか老後と冥土の生計を立てるためだ。
これは古今変わらない。「他人のためにはスネ毛一本抜かない」。伝聞だから話半分に聞いて頂きたいが、それまでパンダを見慣れた野獣と思っていた山村民に、wwfの白人職員が監視と通訳の共産党員を伴いパンダの貴重を訴えた翌日、村長が村民を集めてパンダ狩りを始めた。
中国人だけではない。制度的に隠蔽されているが、日本は割合で言えば世界最大の堕胎天国だ。下半身に振り回された助平親どもが、面倒くさいと思えば簡単に子殺しをする。最も力のない胎児は、最も殺して良い対象であると優生保護法が言う。中国人も日本人も変わらない。
そうでもない親御さんに恵まれた世の親御さんたち。よーく聞きなさい。タマネギをなめてスライスに失敗した指の出血のように、子供をなめてかかって可愛がらないと、いずれ訪れる自分の老いの時、すさまじい復讐を返され、さっさと死んだ方がいいと思える目に遭いますぞ?
そもそも人間が出来ていないから親になるのであり、産むにしてもこんなむごい宇宙に平気で子供を放り出す程度には、親は子の事情など考えていない。親に人格を求める、それは間違いなわけ。そういうことは全然ないわけ。怨むべきは自分の不運と覚悟したのち道が開く。
親どもと宇宙は放っておこう。生まれてしまったのだから、宇宙を遊び場と見よう。
詳細は論語述而篇19余話を参照。「戦争の暴虐を神に歎くな。間違ったのは我々だ」と良識派ドイツ将校のホーゼンフェルトは言ったという。上の句は産み落とされた暴虐も同様で、居もしないカミホトケに文句を言っても、何一つ解決しない。坊主や神主が儲かるだけだ。
中国と中国人と中華文明と、論語に話を戻そう。
これは目で見た人から直に聞いた話だが、日本のとある街に集まり住んだ中国人が、市役所前の池に住む亀を片端から捕らえて食った。「亀とったらいかんがな」と説教されると、タッパーに入れた亀肉を差し出して目こぼしを願い出た。中国人とワイロは不可分の関係にある。
これは訳者が実見したことだが、近所の親水公園には多数のコイが泳いでいた。なにがしかの偶然によって錦鯉のたぐいも泳いでいたが、網を持った中国人が目を皿のようにしてすくい取り、公園に残ったのは真っ黒なコイばかりになった。「魚取り禁止」の看板は無意味だった。
コイばかりでない。その公園には多数のモクズガニがいた。季節どきになると歩道にまでその行列が見られたほどだった。モクズガニは中国で高級食材と珍重される上海ガニの一種である。中国人が近所に住まい始めてしばらくすると、公園のカニは一匹残らずいなくなった。
訳者のように否応なく長年中国人と付き合っていると、中国人かどうかは五感で分かるが。
その言動はDQNでない日本人の想像を超える。だが科学と漢字が両方分かるのは、世界でも日本人だけの特権だ。個人の生存のために果てしなく合理的な中華文明を理解できるし、その世界に安住する中国人を理解できる。論語は中華文明を理解するには、必須の教本に違いない。
理解するとは拝むことでもさげすむことでもない。本サイトはその試みである。
科学が分からないからと言って、決して中国人を侮ってはならない。中国人を侮って、日本帝国は壊滅的な敗戦を招いた。科学が分からないのに、数千年を生き延び、繁殖し、繁栄しているのだと恐れるべきだ。中華文明とは、そうした生存を教える、人類の一つの智恵である。
引用動画”We planet”
歌詞訳者訳
1.
白夜の中にライラックの葉
風が時にささやか、時に激しく揺らす
白夜の中、私が眠りに就くまさにその時
私は夢見る、驚くほど白い夢を
鳥が魔法の羽を羽ばたき
そして私は、あなたの姿をそれとなく知る
白夜の中、あなたと一緒に出掛けよう
不思議な世界へ、不思議な世界へ
※
白夜が雲のように降りてきた
風が若葉に告げる
聴き慣れたあなたの声が聞こえ、姿が見えると
ああ、でもどうして夢の中だけで?
※(繰り返し)
2.
夜明けの彩り、空は高く
哀れにも私の夢見は短く終わる
繰り返される夢、私は探す、何度でも
でもこんなに白夜は短い、いつも
心にたった一つの希望と
そしてほほえみと共に旅立つ
夢の中になんていないと知りながら
あなたに会いに、あなたに会いに
※※(繰り返し)
『論語』為政篇おわり
お疲れ様でした。



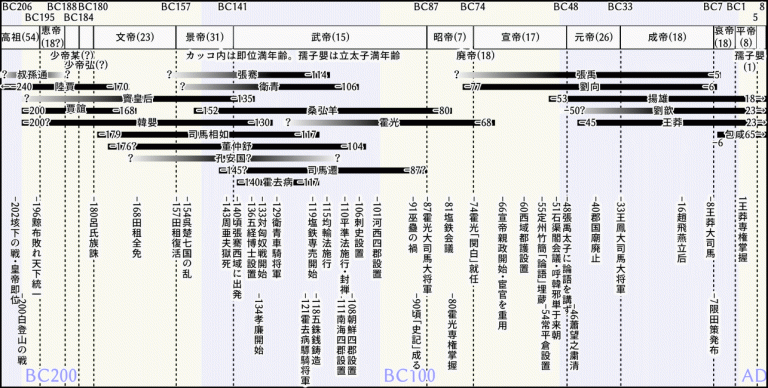
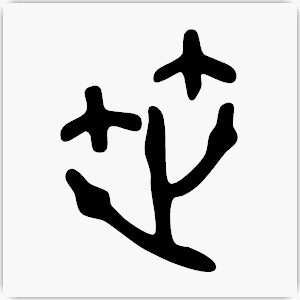
コメント