論語:原文・書き下し
原文(唐開成石経)
子曰人而無信不知其可也大車無輗小車無軏其何以行之哉
校訂
東洋文庫蔵清家本
子曰人而無信不知其可也/大車無輗小車無軏其何以行之哉
後漢熹平石経
(なし)
定州竹簡論語
[子曰:「人而無信,不智其可也。大]輿a無輗,小輿a無[軏],31……[何以行之哉?]」32
- 輿、阮本、皇本作「車」。
標点文
子曰、「人而無信、不智其可也。大輿無輗、小輿無軏、其何以行之哉。」
復元白文(論語時代での表記)













 輗
輗 

 軏
軏 





※輿→(甲骨文)・輗・軏→(古文)。論語の本章は、「輗」「軏」が論語の時代に存在しない。論語のつじつま合わせのために古く見せかけて作成した疑いがある。「信」「其」「何」の用法に疑問がある。論語の本章は、漢帝国以降の儒者官僚による作文である。
書き下し
子曰く、人にし而信無きは、其の可を智ら不る也。大き輿輗なく、小さき輿軏無くんば、其れ何ぞ以ゐて之を行らん哉。
論語:現代日本語訳
逐語訳

先生が言った。「人であって信用のない者は、それが悪くはないかを知り得ないなあ。大車に輗のくさびが無く、小車に軏のくさびがなければ、それらはどうしてそれでこれらを走らせようか。」
意訳

ウソツキは能の有る無しも分からないな。車の引き棒にくさびが付いていなければ、走れないのと同じだ。
従来訳
先師がいわれた。――
「人間に信がなくては、どうにもならない。大車に牛をつなぐながえの横木がなく、小車に馬をつなぐながえの横木がなくては、どうして前進が出来よう。人間における信もその通りだ。」下村湖人『現代訳論語』
現代中国での解釈例
子說:「人無信譽,不知能幹什麽?就象大車沒有車軸,小車沒有車軸,怎麽能啟動?」
先生が言った。「人に信用が無いなら、どの程度仕事が出来るか分からないだろう? 丁度大きな車に引き棒が無く、小さな車に引き棒が無いと、どうやっても動かしようがないように。」
論語:語釈
子曰(シエツ)

論語の本章では”孔子先生が言った”。「子」は貴族や知識人に対する敬称で、論語では多くの場合孔子を指す。「子」は赤ん坊の象形、「曰」は口から息が出て来るさま。「子」も「曰」も、共に初出は甲骨文。辞書的には論語語釈「子」・論語語釈「曰」を参照。


(甲骨文)
この二文字を、「し、のたまわく」と読み下す例がある。「言う」→「のたまう」の敬語化だが、漢語の「曰」に敬語の要素は無い。古来、論語業者が世間からお金をむしるためのハッタリで、現在の論語読者が従うべき理由はないだろう。
人(ジン)


(甲骨文)
論語の本章では”人間一般”。初出は甲骨文。原義は人の横姿。「ニン」は呉音(遣隋使より前に日本に伝わった音)。甲骨文・金文では、人一般を意味するほかに、”奴隷”を意味しうる。対して「大」「夫」などの人間の正面形には、下級の意味を含む用例は見られない。詳細は論語語釈「人」を参照。
而(ジ)


(甲骨文)
論語の本章では”~かつ~”。初出は甲骨文。原義は”あごひげ”とされるが用例が確認できない。甲骨文から”~と”を意味し、金文になると、二人称や”そして”の意に用いた。英語のandに当たるが、「A而B」は、AとBが分かちがたく一体となっている事を意味し、単なる時間の前後や類似を意味しない。詳細は論語語釈「而」を参照。
無(ブ)


(甲骨文)
論語の本章では”…でない”・”…がない”。初出は甲骨文。「ム」は呉音(遣隋使より前に日本に伝わった音)。甲骨文の字形は、ほうきのような飾りを両手に持って舞う姿で、「舞」の原字。その飾を「某」と呼び、「某」の語義が”…でない”だったので、「無」は”ない”を意味するようになった。論語の時代までに、”雨乞い”・”ない”の語義が確認されている。戦国時代以降は、”ない”は多く”毋”と書かれた。詳細は論語語釈「無」を参照。
信(シン)
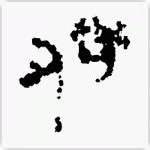

(金文)
論語の本章では、”他人を欺かないこと”。この語義は春秋時代では確認できない。初出は西周末期の金文。字形は「人」+「口」で、原義は”人の言葉”だったと思われる。西周末期までは人名に用い、春秋時代の出土が無い。”信じる”・”信頼(を得る)”など「信用」系統の語義は、戦国の竹簡からで、同音の漢字にも、論語の時代までの「信」にも確認出来ない。詳細は論語語釈「信」を参照。
不(フウ)


(甲骨文)
論語の本章では”~でない”。漢文で最も多用される否定辞。初出は甲骨文。原義は花のがく。否定辞に用いるのは音を借りた派生義。詳細は論語語釈「不」を参照。現代中国語では主に「没」(méi)が使われる。
知(チ)→智(チ)


(甲骨文)
論語の本章では”知る”。現行書体の初出は春秋早期の金文。春秋時代までは「智」と区別せず書かれた。甲骨文で「知」・「智」に比定されている字形には複数の種類があり、原義は”誓う”。春秋末期までに、”知る”を意味した。”知者”・”管掌する”の用例は、戦国時時代から。詳細は論語語釈「知」を参照。
其(キ)


(甲骨文)
論語の本章では”その”という指示詞。この語義は春秋時代では確認できない。初出は甲骨文。原義は農具の箕。金文になってから、その下に台の形を加えた。のち音を借りて、”それ”の意をあらわすようになった。”それ・その”のような人称代名詞に用いた例は、殷代末期から、指示代名詞に用いた例は、戦国中期からになる。詳細は論語語釈「其」を参照。
可(カ)


(金文)
日本古語の「よろし」と同じく、”悪くない”。初出は甲骨文。原義は”紆余曲折あってやっと言う”ことで、積極的に評価する言葉ではない。秦帝国の成立以降、皇帝は臣下の上奏を裁可する際、「可」と言った。「よし」と読み下すが、”許して遣わそう”に当たる。まれに機嫌がよいときは、「善」「美」などと言って裁可する。「可」と同様、どちらも「よし」と読み下すが、意味としては”あっぱれじゃ”に当たる。詳細な語釈は論語語釈「可」を参照。
也(ヤ)


(金文)
論語の本章では、「かな」と読んで詠歎の意に解せる。「なり」と読んで断定の意に解してもいいが、この語義は春秋時代では確認できない。初出は春秋時代の金文。原義は諸説あってはっきりしない。「や」と読み主語を強調する用法は、春秋中期から例があるが、「也」を句末で断定に用いるのは、戦国時代末期以降の用法で、論語の時代には存在しない。詳細は論語語釈「也」を参照。
大(タイ)
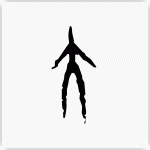

(甲骨文)
論語の本章では”大きな”。初出は甲骨文。「ダイ」は呉音。字形は人の正面形で、原義は”成人”。春秋末期の金文から”大きい”の意が確認できる。詳細は論語語釈「大」を参照。
車(シャ/キョ)→輿(ヨ)
現存最古の論語本である定州竹簡論語は「輿」と記し、論語の本章について現存最古の古注本である宮内庁蔵清家本、唐石経とそれを祖本とする現伝論語は「車」と記す。時系列に従い、「輿」へと校訂した。
論語の伝承について詳細は「論語の成立過程まとめ」を参照。
原始論語?…→定州竹簡論語→白虎通義→ ┌(中国)─唐石経─論語注疏─論語集注─(古注滅ぶ)→ →漢石経─古注─経典釈文─┤ ↓↓↓↓↓↓↓さまざまな影響↓↓↓↓↓↓↓ ・慶大本 └(日本)─清家本─正平本─文明本─足利本─根本本→ →(中国)─(古注逆輸入)─論語正義─────→(現在) →(日本)─────────────懐徳堂本→(現在)


(甲骨文)
論語の本章では”くるま”。初出は甲骨文。甲骨文・金文の字形は多様で、両輪と車軸だけのもの、かさの付いたもの、引き馬が付いたものなどがある。字形はくるまの象形。原義は”くるま”。甲骨文では原義で、金文では加えて”戦車”に用いる。また氏族名・人名に用いる。「キョ」の音は将棋の「香車」を意味する。詳細は論語語釈「車」を参照。


(甲骨文)
定州竹簡論語の「輿」の初出は甲骨文。字形は「車」+四つの「又」”手”。担ぎ挙げる乗り物の姿。原義は”こし”。戦国の金文では「與」に通じて古戦場として知られる地名「閼與」(山西省)の一部に用いた(閼輿戈・戦国末期)。戦国の竹簡では「舉」(挙)に通じて”(神霊に)供える”の意に用いた。また戦国末期の秦の竹簡では、”くるま”の意に用いられた。詳細は論語語釈「輿」を参照。
定州竹簡論語埋蔵と同時期の劉向『新序』も、「輿」と記すと『論語集釋』は指摘する。
輗(ゲイ)・軏(ゲツ)
論語の本章では、”車の長柄と横木を止めるくさび”とされる。大きな車用を輗、小さな車用を軏という、という。
輗の初出は定州竹簡論語。カールグレン上古音はŋieg、同音無し。部品の兒”みどりご”はȵi̯ĕɡで、同音は唲”へつらうさま”。軏の初出は定州竹簡論語。カールグレン上古音はŋi̯wătまたはŋwətで、前者の同音は月、刖”足切り”、跀”足切り”、抈”折る”。後者は兀”高い”、扤”動く”、杌”枝の無い木”、𠨜”危うい”。


輗・軏
上掲は古文と呼ばれる書体で、宋の杜従古(ペンネームであろう)が編んだ『集篆古文韻海』という本に載っていたらしきもので、杜従古は「ドコソコから採取した由緒正しい文字であるぞ」とのたもうて本を編んだのだろうが、日本のいわゆるお経のほとんどが、砂漠坊主か中華坊主のでっち上げであるように、中国人は欲望に身を任せて平気でうそデタラメを書くこと、日本人と変わらない。従って信用できず、論語のためにでっち上げられた可能性すらある。
日本にも「天狗が書いた証文」が各地の地方文書にあり、いくら暇な坊主でもそんな山奥には行かないだろうと思うような僻地にまで、空海の杖突井戸とか西行の腰掛石とかがある。
そもそも「輗・軏」が、車のくさびを意味しているというのが、「そうなんじゃないかな」という程度の想像であり、論語の時代にももちろんくさびはあったはずだが、それが何と呼ばれていたかは分からない。恐らくごく普通に、「契」kʰiad(去)”くさび”と言ったのだろう。それなら当時の金文から出土している。
小(ショウ)


(甲骨文)
論語の本章では”小さな”。初出は甲骨文。甲骨文の字形から現行と変わらないものがあるが、何を示しているのかは分からない。甲骨文から”小さい”の用例があり、「小食」「小采」で”午後”・”夕方”を意味した。また金文では、謙遜の辞、”若い”や”下級の”を意味する。詳細は論語語釈「小」を参照。
何(カ)


(甲骨文)
論語の本章では”なに”。この語義は春秋時代では確認できない。初出は甲骨文。字形は「人」+”天秤棒と荷物”または”農具のスキ”で、原義は”になう”。甲骨文から人名に用いられたが、”なに”のような疑問辞での用法は、戦国時代の竹簡まで時代が下る。詳細は論語語釈「何」を参照。
以(イ)


(甲骨文)
論語の本章では”…を用いて”。初出は甲骨文。人が手に道具を持った象形。原義は”手に持つ”。論語の時代までに、名詞(人名)、動詞”用いる”、接続詞”そして”の語義があったが、前置詞”~で”に用いる例は確認できない。ただしほとんどの前置詞の例は、”用いる”と動詞に解せば春秋時代の不在を回避できる。詳細は論語語釈「以」を参照。
行(コウ)


(甲骨文)
論語の本章では”行かせる”。初出は甲骨文。「ギョウ」は呉音。十字路を描いたもので、真ん中に「人」を加えると「道」の字になる。甲骨文や春秋時代の金文までは、”みち”・”ゆく”の語義で、”おこなう”の語義が見られるのは戦国末期から。詳細は論語語釈「行」を参照。
之(シ)


(甲骨文)
論語の本章では”これ”。初出は甲骨文。字形は”足”+「一」”地面”で、あしを止めたところ。原義はつま先でつ突くような、”まさにこれ”。殷代末期から”ゆく”の語義を持った可能性があり、春秋末期までに”~の”の語義を獲得した。詳細は論語語釈「之」を参照。
哉(サイ)


(金文)
論語の本章では”…だろうか”。反語の意を示す。初出は西周末期の金文。ただし字形は「𠙵」”くち”を欠く「𢦏」で、「戈」”カマ状のほこ”+「十」”傷”。”きずつく”・”そこなう”の語釈が『大漢和辞典』にある。現行字体の初出は春秋末期の金文。「𠙵」が加わったことから、おそらく音を借りた仮借として語気を示すのに用いられた。金文では詠歎に、また”給与”の意に用いられた。戦国の竹簡では、”始まる”の意に用いられた。詳細は論語語釈「哉」を参照。
其何以行之哉
論語の本章では、”それら=大小のくさびの無い車(其)は、(何)がそのような車を用いて(以)まともな車(之)のように走らせる(行)だろうか(哉)”。
『学研漢和大字典』によると、其は「此(この)に対して、やや遠いところを指す」といい、之は「其‐之、彼‐此が相対して使われる。また、之は客語になる場合が多い」という。本章での「其」は「大輿無輗、小輿無軏」の車を指し、それらに対してまともなくさびのある車「之」を走らせる「行」のは「何」だろうか、そんなものはないと言っている。
| 大輿無輗 | 其 ”そうした車は” |
何 ”いったいどんな方法が” |
以 ”用いて” |
行 ”走らせる” |
之 ”くさびのある車のように” |
哉 ”というのか” |
| 小輿無軏 |
情景としては、孔子がまともな車「之」を手でポンポンと叩いて、”くさびの無い車があるとするなら、大きかろうが小さかろうが、この車のようにまともに走らせる事は出来ない。ウソばかり付く人間も同じだ”と説教する場面を想像すると分かり易い。
儒者はウソばかり付くのがほとんどで、漢学教授は儒者の猿まねするのがほとんどだから、それらに頼らず解読しないと、本章はわけが分からなくなる。「大車輗なく、小車軏無くんば、其れ何を以て之を行らんや」と訓読するのが通例だが、「其」「之」が何を指しているか、この読みだけでは分からない。
論語:付記
検証
論語の本章は、前半についてはよく似た表現が前漢末の『楊氏法言』に出てくるが、それ以外の誰一人引用していない。
衣而不裳,未知其可也;裳而不衣,未知其可也。衣裳其順矣乎?
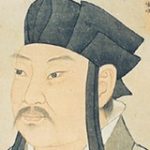
上着を着ただけで下がすっぽんぽんでは、似合うかどうか以前の話だ。スカート(中国では男もスカートをはいた)だけで上が裸では、やはり似合うとも何とも言えない。衣類とは、そういう秩序を示すものとは言えまいか?(『楊氏法言』問神22)
後半の「輗」は論語の後では、戦国末期の『韓非子』、前漢の『新序』に見られ、「軏」は戦国時代の『楚辞』、前漢の『新序』に見られる。『孟子』『荀子』など戦国時代の儒教書からすっぽり抜け落ちている所を見ると、本章はおそらく漢帝国に入って以降の創作だろう。
しかも後漢末期の漢石経に欠けていることから、論語の本章の成立は、あるいは三国・南北朝まで時代が下るかも知れない。
解説

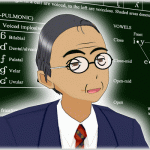
既存の論語本では吉川本で、輗を大車=牛車のくびき、軏を小車=馬車のくびきという。藤堂本では輗・軏を、それぞれ大車・小車の長柄とくびきをつなぐくさびという。
輗・軏、この二つの言葉が仮に論語の時代にあったにせよ、それから500年過ぎた後漢初期には、もう意味が分からなくなり、儒者が注を付けた。それが正しいという保証はどこにも無い。しかしそれを否定する材料も無い。
古注『論語集解義疏』
註苞氏曰大車牛車輗者轅端橫木以縛枙者也小車駟馬車也軏者轅端上曲拘衡者也

注釈。包咸「大きな車や牛車の”輗”は、車の引き棒の先端とくびきを繋ぐくさびである。小さな車や四頭立ての馬車については、”軏”は引き棒の先端の上側に取り付けた丸いカギで、くびきと繋いだ。」
新注を書いた朱子はこのダイジェストを載せるのみなので、省略する。
なお現代中国語では「車軸」(车轴)と解しているようだが、おそらく「しゃじく」ではなく引き棒だろう。百度で「农用拖车车轴」(農作業用荷車車軸)を画像検索してみると分かる。日本の中国翻訳物にも、この手の手抜き翻訳があるので、読者は十分な警戒を要する。

余話
騎兵と鐙
中国にズボンとシャツとロングコートの組み合わせが入るのは、戦国時代の趙の武霊王(?-BC295)からで、これを「胡服」”蛮族の服”と言った。北方遊牧民の騎馬戦術に目を付けた武霊王は、趙の軍事力強化のために騎兵を求め、嫌がる貴族に無理やり着せた。
それまで中国人は、馬のようなまたがる乗りものに乗らなかったから、ズボンが要らず、シャツやジャンパーは作業着としてはあっただろうが、下半身は男も女もスカートをはいた。しかも鐙が現れるのは西晋時代とされ(→wikipedia)、それまで馬上で扱えるのは弓とサーベルだけだった。
スキタイ(BC9C-BC4C)や匈奴(BC4C-5C)が、ついに突厥やモンゴルのような大帝国になれなかった理由は、鐙の不在にほかならない。遺物に見えるスキタイ兵も匈奴兵も、長柄武器を持っていないから薙ぐことが出来ず、歩兵に取り囲まれるとタコ殴刂にされる。
『三国志演義』の関羽も張飛も、馬上で長柄武器を振り回して敵兵を追い散らしているが、あれはお芝居だからのサービスだ。覇王項羽も絵に描くと、たいてい長柄武器を持っているが、三人とも本当にそうなら、下半身の筋力が人間離れしていると言ってよい。

カスティリオーネ「畫阿玉錫持矛盪寇圖」國立故宮博物院蔵
騎兵の長所は速度と打撃力で、それを最も発揮できる戦法とは、密集して槍を構えた突撃に他ならない。だから史上有名な騎馬軍団の主兵器は槍だった。欧州騎士もモンゴル兵もシパーヒーも八旗騎兵もグランダルメ騎兵もコサックも、突撃には槍を用いた(→youtube)。
十九年春正月,…召肥義與議天下,五日而畢。…召樓緩謀曰:「…夫有高世之名,必有遺俗之累。吾欲胡服。」樓緩曰:「善。」群臣皆不欲。

武霊王十九年(BC307)、元老の肥義を呼んで天下の計略を練り、五日もかかって終わった。…次に参謀役の樓緩を呼んで計略を練り、王は言った。「名高い物事はたいがい見かけ倒しで、シロアリに食い荒らされた大邸宅と同じだ。わしは胡服を断行するぞ。」樓緩「よろしいでしょう。」ところが群臣がこぞっていやがった。「あんな恥ずかしい格好ができるか!」
於是肥義侍,…王曰:「吾不疑胡服也,吾恐天下笑我也。狂夫之樂,智者哀焉;愚者所笑,賢者察焉。世有順我者,胡服之功未可知也。雖驅世以笑我,胡地中山吾必有之。」於是遂胡服矣。
そこでもう一度肥義を呼んで言った。「…胡服の有利は明らかだ。わしは天下の笑いものになるだろうし、𠮷外沙汰だともの知り先生方から憐れまれよう。だが馬鹿者どもが笑う真の理由は何か、賢者なら分かるはずだ。確かにわしを支持する者たちもおるが、それでも胡服の効果はほとんど知るまい。天下こぞってわしを笑おうとも、西北の中山国は必ず、胡服を着た騎兵で踏み潰してくれる。」こうしてついに、王は胡服を着て朝廷に出、たまげた朝臣は大騒ぎになった。
…公子成再拜稽首曰:「…王命之,臣敢對,因竭其愚忠。曰:臣聞中國者,蓋聰明徇智之所居也,萬物財用之所聚也,賢聖之所教也,仁義之所施也,詩書禮樂之所用也,異敏技能之所試也,遠方之所觀赴也,蠻夷之所義行也。今王捨此而襲遠方之服,變古之教,易古人道,逆人之心,而怫學者,離中國,故臣願王圖之也。」使者以報。王曰:「吾固聞叔之疾也,我將自往請之。」
反対派の急先鋒は王族の公子成である。「王殿下のご命令でも、あえて反対を申し上げる。それがそれがしの忠義でござる。そもそも中国とは、賢者が多く学問も技術も進んでおり、物資も豊か。いにしえの賢者の教えが受け継がれ、人の道とは何か誰でも知ってござる。文化の香り高く、技術革新も盛んで、とんでもない遠くから見物人が来るほどで、蛮族でも一度来れば大人しくなり申す。王殿下は世界中が仰ぐこの文明の輝きを捨て、いにしえの賢者の教えを捨て、聖人の掟を破り、嫌がる者に無理強いし、学者を信用せず、中華の看板を捨てようとなさる。どうかお考えをお改め下さい。」
武霊王「ほう。そういえば叔父上は病んでおられたな。早々にお帰りなされ。わし自らお屋敷に出向き、とくとお願いすることと致そう。」
王遂往之公子成家,因自請之,曰:「…。」公字成再拜稽首曰:「臣愚…臣敢不聽命乎!」再拜稽首。乃賜胡服。明日,服而朝。於是始出胡服令也。
武霊王は公子成の屋敷に出向いて説教した。「クドクドクドクドクド…。」うんざりした公子成は這いつくばって言った。「それがしは愚かにて…王殿下に従い申します。」武霊王は一揃えの胡服を公子成の屋敷に置いて帰り、公子成は仕方なく胡服を着て朝廷に出た。これを胡服令の始まりとする。
趙文、趙造、周袑、趙俊皆諫止王毋胡服,如故法便。王曰:「先王不同俗,何古之法?…循法之功,不足以高世;法古之學,不足以制今。子不及也。」遂胡服招騎射。
それでも王族の趙文などが反対した。武霊王「いにしえの聖王でも、今とは違う格好をしておったのだぞ? そちらが言う古法とは何じゃ。…律儀におきてを守ったところで、国を栄えさすことは出来ない。昔の教えを学んだところで、今の国難を解決できない。もうよい。そちらにこれ以上話しても無駄じゃ。」こうして胡服を着た家臣を集めて騎兵隊を編成した。
二十年,王略中山地。…二十一年,攻中山。…二十七年…傳國。…於是詐自為使者入秦。秦昭王不知,已而怪其狀甚偉,非人臣之度,使人逐之,而主父馳已脫關矣。惠文王…三年,滅中山。
二十年、中山国に侵攻を始めた。二十一年、中山国を攻めた。…二十七年…太子の恵文王に王位を譲った。…身分を隠して秦国への使者になった。(侵略王として悪名高い)秦の昭襄王は、はじめ気付かなかったが、一行にどう見ても立派すぎる人物がおり、人の家臣とは思えなかった。使者が帰ったあとでやっと身分を知り、(楚の懐王を監禁した時と同様に)「捕まえろ!」とわめいたが、武霊王とその一行は得意の騎馬ですでに国境を抜けており、間に合わなかった。恵文王…三年、ついに中山国を滅ぼした。(『史記』趙世家)
ちなみに太平洋戦争中に米兵が持っていた「カービン銃」の原義は”騎兵銃”で、短く扱いが容易なことから歩兵も持った。イタリアのカラビニエリ”騎兵隊”とは国家憲兵だが、これも18世紀以降にフランスやイタリアで生まれた、政権にとって使い勝手のよい兵の意だという。
ナチスドイツの歩兵が持っていた銃も、もとは騎兵銃のKar98kである。さらには短機関銃も装備した。短機関銃とは安い拳銃弾を呑み込んで吐き出すだけのしろものだが、水道管に穴を開けた程度のステン銃でも時に勝敗を決した。代わりに弾の消費がすさまじくなった。
主要参戦国でも貧乏な日本は、「一発必中」を兵に強い、短機関銃どころか、当たりは良いが長々とした三八式を持たせるしかなかった。身の回りの装備も、列国がファスナーやスナップボタンを多用したのに、とにかく「ヒモ」「結わえる」で済ませ、取り回しを考えない。

野営の焚火作業服として帝国陸軍の迷彩服をまとう訳者(右)。首回りの二つのボタン以外は、全てヒモで結んだりくくったりする作りになっている。真っ白にもかかわらず迷彩服と言うのは、ソ連赤軍の雪中服とは事情が違い、兵が自分で現地に都合のよい色に染めろという、陸軍省のありがたい軍官僚さまのお達し。
孫子の言う通り、貧乏国は戦う前に負けている。金持ちこそケンカする。アメリカを見ればよく分かる。中国も貧乏なうちは、「韜光養晦」”控えめに振る舞う”が国是だった。カネを持ったとたんに居丈高になった。どうやら最近の様子では、軍部の暴走を抑えられていない。
これは現在の中共政権に限らない。清の乾隆帝の治世は、中華帝国が最も豊かな時代だった。そして八旗という軍部で政治勢力が根を張っていた。乾隆帝は無駄ないくさを四方に仕掛けた挙げ句、その多くに負けたが誤魔化した。「十全老人」とはその言い張りである。
金が無くなったらこうは行くまい。ヒラリー元国務長官が、「もっかい貧乏にしてやる」とヒステリックに叫んだのももっともだ。今にひどい目に遭わされよう。経験のある日本人には分かる。だが中国人は高慢ちきが過ぎ、先進国で唯一同情的だった日本人を踏みにじった。
自業自得とはこのことだ。だから歎くには当たらない。



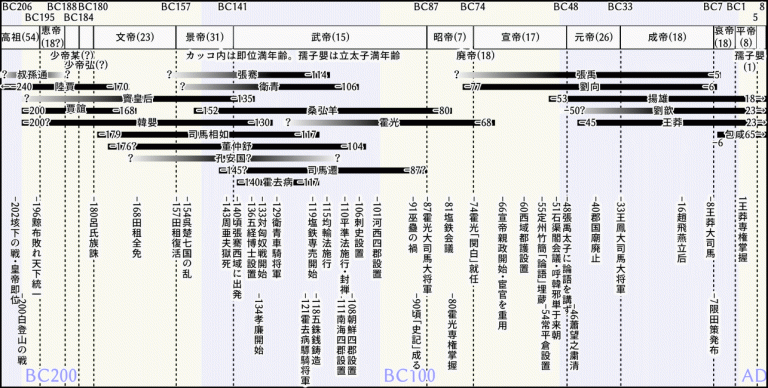

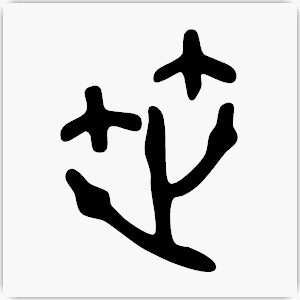
コメント