論語:原文・書き下し
原文(唐開成石経)
子曰不患人之不己知患不知人也
校訂
諸本
東洋文庫蔵清家本
子曰不患人之不已知也患已不知人也
後漢熹平石経
…人之不…
※続けて「章」の字があるが、これは篇末に章数字数を計上した刻字と思われる。
定州竹簡論語
(なし)
標点文
子曰、「不患人之不己知、患己不知人也。」
復元白文(論語時代での表記)















※患→圂。
書き下し
子曰く、人之己を知ら不るを患へ不れ、己人を知ら不るを患へよ也。
論語:現代日本語訳
逐語訳

先生が言った。「他人が私を知らないのを悩むな、自分が他人を知らないのを悩めよ。」
意訳
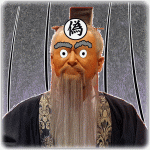
他人が自分を理解してくれないのは気にするな。自分が他人を理解しないのを気にしなさいよ。
従来訳
先師がいわれた。――
「人が自分を知ってくれないということは少しも心配なことではない。自分が人を知らないということが心配なのだ。」下村湖人『現代訳論語』
現代中国での解釈例
孔子說:「不怕沒人瞭解自己,就怕自己不瞭解別人。」
孔子が言った。「他人が私を理解してくれないのを恐れない。それより先に、自分が他人を理解しないのを恐れる。」
論語:語釈
子曰(シエツ)(し、いわく)

論語の本章では”孔子先生が言った”。「子」は貴族や知識人に対する敬称で、論語では多くの場合孔子を指す。「子」は赤ん坊の象形、「曰」は口から息が出て来るさま。「子」も「曰」も、共に初出は甲骨文。辞書的には論語語釈「子」・論語語釈「曰」を参照。
この二文字を、「し、のたまわく」と読み下す例がある。「言う」→「のたまう」の敬語化だが、漢語の「曰」に敬語の要素は無い。古来、論語業者が世間からお金をむしるためのハッタリで、現在の論語読者が従うべき理由はないだろう。
不(フウ)


(甲骨文)
漢文で最も多用される否定辞。初出は甲骨文。「フ」は呉音(遣隋使より前に日本に伝わった音)、「ブ」は慣用音。原義は花のがく。否定辞に用いるのは音を借りた派生義だが、甲骨文から否定辞”…ない”の意に用いた。詳細は論語語釈「不」を参照。
患(カン)
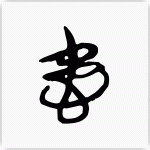
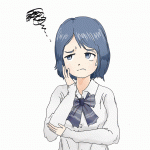
(楚系戦国文字)
論語の本章では、”気に病む”。初出は楚系戦国文字。論語の時代に存在しない。字形は「毋」”暗い”+「心」。「串」に記すのは篆書以降の誤り。論語時代の置換候補は近音の「圂」または「困」。詳細は論語語釈「患」を参照。
人(ジン)


(甲骨文)
論語の本章では”他人”。初出は甲骨文。原義は人の横姿。「ニン」は呉音(遣隋使より前に日本に伝わった音)。甲骨文・金文では、人一般を意味するほかに、”奴隷”を意味しうる。対して「大」「夫」などの人間の正面形には、下級の意味を含む用例は見られない。詳細は論語語釈「人」を参照。
之(シ)


(甲骨文)
論語の本章では、”…の”という所有格を作る助詞。初出は甲骨文。字形は”足”+「一」”地面”で、あしを止めたところ。原義はつま先でつ突くような、”まさにこれ”。殷代末期から”ゆく”の語義を持った可能性があり、春秋末期までに”~の”の語義を獲得した。詳細は論語語釈「之」を参照。
己(キ)
論語の本章は現存最古の論語の版本である定州竹簡論語に全文を欠き、ついで古い漢石経は残石のみ、晩唐初期に刻まれた唐石経は、唐朝廷の都合により儒教経典の版本による異同を統一するため、かなり書き換えられている。しかも本章には一部磨滅がある。現伝の論語は唐石経を祖本に、宋代の論語注疏→論語集注と伝わった中国伝承の新注系論語。
対して唐石経以前の隋代に日本には古注系の論語が伝わり、その最も古い版本は慶大蔵論語疏だが子罕篇と郷党篇しか見つかっていない。従って論語の本章に関して現存最古の古注本は、東洋文庫蔵清家本になる。おそらく唐石経より古い文字列を伝えているだろう。これに従い「已」に改めるべきだが、語義は”自分”で変わらないし、つまり唐代頃までは「巳」”へび”と「已」”すでに”と「己」”おのれ”は相互に異体字として通用した。従って本章でも異体字として扱った。
論語の伝承について詳細は「論語の成立過程まとめ」を参照。
原始論語?…→定州竹簡論語→白虎通義→ ┌(中国)─唐石経─論語注疏─論語集注─(古注滅ぶ)→ →漢石経─古注─経典釈文─┤ ↓↓↓↓↓↓↓さまざまな影響↓↓↓↓↓↓↓ ・慶大本 └(日本)─清家本─正平本─文明本─足利本─根本本→ →(中国)─(古注逆輸入)─論語正義─────→(現在) →(日本)─────────────懐徳堂本→(現在)
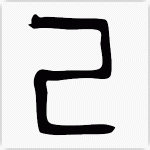

(甲骨文)
「己」の初出は甲骨文。「コ」は呉音。字形はものを束ねる縄の象形だが、甲骨文の時代から十干の六番目として用いられた。従って原義は不明。”自分”の意での用例は春秋末期の金文に確認できる。詳細は論語語釈「己」を参照。


(甲骨文)
「已」の初出は甲骨文。字形と原義は不詳。字形はおそらく農具のスキで、原義は同音の「以」と同じく”手に取る”だったかもしれない。論語の時代までに”終わる”の語義が確認出来、ここから、”~てしまう”など断定・完了の意を容易に導ける。詳細は論語語釈「已」を参照。


(甲骨文)
なお宮内庁蔵清家本は「巳」と記す。慶大蔵論語疏は本章を欠くが、現存する章ではやはり同じく「己」「已」を「巳」と記す。初出は甲骨文。字形はヘビの象形。「ミ」は呉音。甲骨文では干支の六番目に用いられ、西周・春秋の金文では加えて、「已」”すでに”・”ああ”・「己」”自分”・「怡」”楽しませる”・「祀」”まつる”の意に用いた。詳細は論語語釈「巳」を参照。
知(チ)


(甲骨文)
論語の本章では”好意的に理解する”。現行書体の初出は春秋早期の金文。春秋時代までは「智」と区別せず書かれた。甲骨文で「知」・「智」に比定されている字形には複数の種類があり、原義は”誓う”。春秋末期までに、”知る”を意味した。”知者”・”管掌する”の用例は、戦国時時代から。詳細は論語語釈「知」を参照。
不己知
論語の本章では、”(他人が)自分を知らない”。漢語の語順はSVO型だが、ここはO-Vと逆転しており、論語には同様の例が8例ある。
漢語の語順の特例として、否定文では甲骨文以来、間接目的語(”~に”が付く語)が否定辞の直後に出ることがある。
帝我に其の祐を受け不らんか。(「甲骨文合集」6272.2)
しかし論語の本章その他のO-V逆転例は、否定辞の直後に出た語は直接目的語(”~を”がつく語)であり同列に分類できない。しかも同じ本章の「不知人」がなぜnot-O-V「不人知」にならないかの説明も付かない。「己」を動詞”整える”と解読しても、やはり後句「不知人」と繋がらない。
仮に「知」が”知る”ではなく”知られる・有名である”の意だったとしても、それなら主語は「己」(または「吾」)であり、語順は「己不知」となるべきはずで、「不己知」はどのように工夫してもつじつまを付ける事が出来ないから、壊れた漢語と断じてよい。
下掲検証に記したように「不己知」文例は、戦国最末期だがいつ筆写されたか分からない『呂氏春秋』に一例見られるのが初めで、漢以降もこのO-V逆転はほぼ使われず、論語と、類書と言って良い『史記』孔子世家独特の言い回しと言っても良い。考えられる筋書きは、
- もと「不知己」とあったのだが、漢儒がもっともらしさを出すため勝手に語順を入れ替えた。
- 「己」は動詞だったが、漢儒が第二句をつけ加えたため”おのれ”として読むしかなくなった。
- 元の文章が断片だけしか伝わらず、わけが分からなくなった。
となる。いずれにせよ文法的、かつ不可逆に壊れた漢文で、元を復元するのは不可能だ。
也(ヤ)


(金文)
論語の本章では、「や」と読んで詠歎の意に用いている。初出は春秋時代の金文。原義は諸説あってはっきりしない。「や」と読み主語を強調する用法は、春秋中期から例があるが、疑問あるいは反語の語義も確認できる。また春秋末期の金文で「也」が句末で疑問や反語に用いられ、詠嘆の意も獲得されたと見てよい。詳細は論語語釈「也」を参照。
患不知人也→患己不知人也
論語の本章では”自分が他人を知らない事を気にかけよ”。主語が省略されているが、主語が変更された記号も特にないので、上の句の「不患人之…」と同じく”自分”と解するのが妥当。
唐石経拓本ではこの部分が磨滅し、磨滅以前の写しである京大蔵唐石経では「患不知人也」と「人」が入るが、先行する南北朝最末期の『経典釈文』では「患不知也」とあり「人」が無い。おそらく『経典釈文』が古形を伝えるだろうが、残念ながら出版当時の隋版が未発見。

欽定四庫全書『経典釈文』
論語の本章に関して最古の古注本である清家本では「已」(己)「人」を記す。先行する漢石経は本章この部分を欠き、定州竹簡論語は論語の本章全体を欠く。唐石経は晩唐になって刻まれ清家本より年代は古いが、唐朝廷の都合で少なからぬ改竄が見られる。従って清家本に従い校訂した。
『論語集釋』は言う。
中論考僞篇引「不患人之不己知,」「知」下有「者」字。釋文:「患不知也」,本或作「患己不知人也」。俗本妄加字。今本「患不知人也」。皇本作「不患人之不己知也患己不知人也。」臧琳經義雜記:蓋與里仁「不患莫己知,求爲可知也」、先進「居則曰:不吾知也。如或知爾,則何以哉」語意相同。今邢疏本作「患不知人也」,「人」字淺人所加。潘氏集箋:邢疏本無王注,皇本有之。今據注意,則釋文所云「本或作『患己不知人也』」似卽王本。
劉氏正義:皇本有。王注云:「但患己之無能知也。」己無能知,卽未有知之義,則皇本「人」字爲俗妄加無疑。天文本論語校勘記:古本、足利本、唐本、津藩本、正平本均作「患己不知人也」。

後漢の『中論』考偽篇には「不患人之不己知」とあって、「知」の下に「者」の字が付いている。隋末の『経典釈文』には「患不知也」とあって、もとはあるいは「患己不知人也」だったという。俗な本ではむやみに字を書き足している。現伝本では「患不知人也」。皇侃の『論語義疏』では、「不患人之不己知也患己不知人也」と記す。
清儒・臧琳の『経義雑記』は言う。「里仁篇の”不患莫己知、求爲可知也”と、先進篇の”居則曰、不吾知也。如或知爾、則何以哉”と多分意味は同じだ。だが今通用している邢昺の『論語注疏』では、”患不知人也”と記している。教養の足りない連中が、書き加えたのだ。」
清儒・潘維城の『論語古註集箋』は言う。「邢昺の注疏本には王粛の注が記されていない。皇侃の義疏本にはある。考えてみるに、『経典釈文』のいう「もとはあるいは”患己不知人也”だった」というのは、王粛の注を指している。」
清儒・劉宝楠『論語正義』は言う。「皇侃の義疏本には記されている。王粛の注にいわく、”ひとえに自分が知ることが出来ないのを気にかける”。自分が知ることが出来ない、というなら、つまり”自分はまだ知らない”ということであり、皇侃の義疏本にある”人”の字は、無教養な連中が勝手に書き加えたこと疑いない。日本の天文本『論語』校勘記は言う。「古本、足利本、唐本、津藩本、正平本はすべて”患己不知人也”と記す」。
「俗本妄加字」”下品な本がデタラメに文字を書き加える”とは、科挙合格者の程樹徳だから言えるのだが、聖俗の判別はイワシの頭も信心からで、個人の感情でしかなく、史実は聖俗で決まらない。聖俗は確かに人間界で猛威を振るうが、それで太陽が地球を回り出したりしない。

コペルニクス(ポーランド国立銀行:旧1000ズロチ紙幣)
以上、多くの読者諸賢には無意味な引用をしてしまったが、ただいたずらに先人の解釈をパクパク食べるだけでなく、本当にそうかと思い、しつこく調べ上げないと、上記したように「従来通りの解釈でよい」などと偉そうな事は書けない。無名な訳者には作業過程の公開が要る。
そうでもないと、信用して貰えないからだ。
論語:付記
検証
論語の本章の中心は、V-Oが逆転したnot-O-V「不己知」で、同じ言葉で自分の無名を歎く章は論語の中にあまたあるが、戦国の儒者も他学派も前漢の儒者も、全く本章を引用していない。定州竹簡論語にもない。さらに第二句「不知人」がO-V逆転していないことの説明も付かない。
上掲の通り、論語には「否定辞-目的語-知」の例が8例もあるのに、他の文献上では戦国最末期の『呂氏春秋』に初めて見られ、次いで漢代の『韓詩外伝』になる。また甲骨文・金文には「己知」の句形が全く見られず、戦国の竹簡にも見られない。「知己」はあるが”自分を知る”の意。
訓読:己を智るは人を智るゆえんにして、人を智るは命を智るゆえんなり。(戦国中末期「郭店楚簡」尊德9)
加えて『呂氏春秋』とほぼ同時期の『韓非子』は、「不己知」を”私は知らない”の意で使っている。
一曰。魏王遺荊王美人,荊王甚悅之,夫人鄭袖知王悅愛之也,亦悅愛之,甚於王,衣服玩好擇其所欲為之,王曰:「夫人知我愛新人也,其悅愛之甚於寡人,此孝子所以養親,忠臣之所以事君也。」夫人知王之不以己為妒也,因為新人曰:「王甚悅愛子,然惡子之鼻,子見王,常掩鼻,則王長幸子矣。」於是新人從之,每見王,常掩鼻,王謂夫人曰:「新人見寡人常掩鼻何也?」對曰:「不己知也。」王強問之,對曰:「頃嘗言惡聞王臭。」王怒曰:「劓之。」夫人先誡御者曰:「王適有言,必可從命。」御者因揄刀而劓美人。

あるとき、魏王が楚王に美人を贈った。楚王はとても喜び、その様子を夫人の鄭袖はしかと知った。一計を案じた夫人は美人を可愛がる振りをし、楚王に「あの者の望みは全て叶えてやって下さいませ」とまで言った。楚王はコロリとだまされ、「う~む見上げた婦道じゃ。古今東西にも聞いたことがない」と夫人を今まで以上に重んじた。
ある時夫人は美人を呼んで言った。「王殿下はそなたをとても気に入っておられるが、一つだけお気に召さぬ所があるようじゃ。」「なんでごさいましょう?」「鼻じゃ。じゃから御前では鼻を隠すようにすれば、王殿下は一層お喜びになる。」
美人は言う通りにした。怪訝に思った楚王は夫人に尋ねた。「あの者は最近、ワシの前で鼻を隠すようになった。なぜじゃと聞いても誤魔化して答えぬ。どうしてかのう?」「わらわは存じません。」「古今にも賢明なそなたのことじゃ、見当ぐらいはつくじゃろう?」「そうですねえ。そういえばあの者は、殿下がクサいと言った事がございました。」
楚王は激怒し、美人の鼻をそぎ落とした。(『韓非子』内儲説下119)
しかも『呂氏春秋』も『韓非子』も、当時の版本は見つかっておらず、いつ書き換えられたか分からない。以上から、「不己知」など「否定辞-目的語-知」の句形は漢代の、それも特殊な漢語と見なすべきで、本章は文字史からは論語の時代に遡れても、文法的に漢儒の創作と断じてよい。
また本章を引用したのは後漢末期の徐幹『中論』からで、本章は相当に新しい。加えて本章は句の構成が揃っておらず、おそらく原文から壊れた、あるいはいじくり回されて妙ちきりんになった文字列だと判断できる。
| 子曰 | 患人 | 之 | 不己知也 |
| 患己 | (なし) | 不知人也 |
解説
論語には何度も繰り返して「不己知」を歎く話がある。「あなたはちりであるから、ちりに帰る」は中国人には通用しない。魯迅の『阿Q正伝』に見られるように、中国人の自尊心は奴隷に身を落としてもすり減らない。『呂氏春秋』にある「不己知」の例はそれを伝える。
晏子之晉,見反裘負芻息於塗者,以為君子也,使人問焉,曰:「曷為而至此?」對曰:「齊人累之,名為越石父。」晏子曰:「譆!」遽解左驂以贖之,載而與歸。至舍,弗辭而入。越石父怒,請絕。晏子使人應之曰:「嬰未嘗得交也,今免子於患,吾於子猶未邪也?」越石父曰:「吾聞君子屈乎不己知者,而伸乎己知者,吾是以請絕也。」晏子乃出見之曰:「嚮也見客之容而已,今也見客之志。嬰聞察實者不留聲,觀行者不譏辭。嬰可以辭而無棄乎!」越石父曰:「夫子禮之,敢不敬從。」晏子遂以為客。俗人有功則德,德則驕;今晏子功免人於阨矣,而反屈下之,其去俗亦遠矣。此令功之道也。
斉の宰相・晏嬰が晋国に向かう途上、かわごろもを減らないよう裏返しに着、まぐさをかついで道ばたで休んでいる者に出会った。ひとかどの人物と見て、晏嬰はお付きに「どうしてこのようなさまになられた」と問わせた。「斉の者に借金をして、返せなくなったので奴隷となりました。名は越石父と言います」と答えた。
「それはお気の毒に」と晏嬰は言い、その場で馬車の引き馬のうち左側を差し出して借金の肩代わりをし、車に乗せて共に宿に向かった。だが宿に着くと、晏嬰は越石父に一言も言わないでスタスタと中に入ってしまった。越石父が怒って、絶交を申し出た。
晏嬰はお付きにこう言わせた。「別に友人になったわけではありません。こうやってお救い申しただけです。あなたにとって私は絶交どうのという関係ではないでしょう?」
越石父「君子は自分を理解しない者には頭を下げ、理解する者には頭を上げるものです。だから絶交を願うのです。」
聞いた晏嬰は出てきて越石父の前で言った。「先ほどまではあなたの外見を見て人柄を量りました。今は志が分かりました。ものの道理を見極めた者は人に名を告げず、人の行動を観察する者は言葉に避難を加えないものです。私が何かお気に召すようなことを言えば、あなたは絶交しないでしょうか。」
越石父「閣下がそこまで私を敬ってくださるなら、敬い順わずにはいられません。」
こうして晏嬰は越石父を対等の客としてもてなした。俗人は儲りさえすれば相手を褒めそやす。誉められれば誰でもいい気になって思い上がる。この時晏嬰の働きは、人の苦難を救ったのだが、その上相手を敬ってへり下った。晏嬰が俗人とは懸け離れていたことが分かる。これが働きに十分な結果をもたらす道である。(『呂氏春秋』観世2。この話は『史記』晏嬰伝にもある。論語公冶長篇16解説を参照。)
では孔子や弟子たちは、自分らが世間に知られないのを歎きつつ暮らしたのだろうか。とんでもない。孔子は亡命しても諸国で「その政を聞く」と論語学而篇10に記された。この章が後世の偽作であるにせよ、主要弟子の多くが各国に仕官し、子路は衛で領主貴族にまでなっている。
どころか、子路の弟弟子だった子羔まで仕官していたことが論語先進篇24の伝説に記されているし、この話が偽作であるにしても、子路の最期の場面で子羔が「逃げて下さい」と子路を説得する話が『史記』衛世家に見える。孔子塾卒業生の就職率はよかったのだ。
子供や老人向けおとぎ話には勧善懲悪の素朴な話が受けるように、常人未満の知能しか持たなかった漢の武帝(論語雍也篇11余話「生涯現役幼児の天子」を参照)をだまくらかすには、孔子一門が門閥と対立したとか、弟子一同が不遇だったとか、お涙頂戴の作り事が有効だった。
だから董仲舒を筆頭とした、いわゆる儒教の国教化を進めた連中が、でっち上げをせっせとこしらえたので、本章始め「不己知」ばなしは、なべて漢儒の偽作と断じてよい。
余話
ニースの巡洋艦
貧富の差で中国人の「面子」(自尊心)がくじけないことはなおさらだ。『笑府』は言う。
千金子驕語人曰。我當甚。汝何得不奉。其人曰。汝自有金。于我何與而奉汝耶。曰。儻分半與汝。何如。荅曰。汝五百。我亦五百。我汝等耳。何奉焉。又曰。悉以相授。難道猶不奉我。荅曰。汝失千金而我得之。汝又當奉我矣。

大金持ちが威張って言った。「ワシの財産はすごいものだ。なのに何でお前はヘコヘコせぬのだ。」
言われた人「金と言ってもあんたのじゃないか。いくらあろうが、何で私にヘコヘコしなきゃならない義理がある?」
金持ち「ではワシの財産を半分お前にやったらどうだ。」
言われた人「なら同額の金持ちじゃないか。なんでヘコヘコする必要がある?」
金持ち「じゃ、全部やったらどうだ。これで文句ないだろう?」
言われた人「あるさ。あんたは一文無しになって、私は大金持ちだ。あんたこそ私にヘコヘコすべきじゃないか。」(『笑府』巻十三・不奉富)

始皇帝始め歴代の皇帝が巨大な陵墓に莫大な財宝を副葬したのを、「馬鹿げたことをしたものだ」とあるいは思うかも知れない。だが中国人にとっての「面子」は、兵馬俑も金持ちに言い返した男も、表現が違うだけで根は同じ。おそらく現代中国人も変わらないに違いない。
それは中華文明の真髄の究極、自身の生存への揺るぎない信仰にあるのだから。中国人は死を、あの世への引っ越しとしか考えていないから、皇帝は陵墓を作り庶民は先祖に紙銭を焼いて送金する。皇帝になるのも乞食になるのも、無限の人生の一コマでしかない。
唐の太宗李世民が、ある夜うっかり死んでしまって、側近たちが睡眠の最中に冥土へ向かい、閻魔大王にワイロを払って主君を身請けしに行った、という伝説がある。中国人とワイロが不可分であると分かると同時に、死はあの世への引っ越しでしかない中華的信条を物語る。
こうした中国人の自尊心は、片や現代中国の内外に対する乱暴を生んでいるのだが、考えようによっては「人は所詮、裸一貫、富貴にだろうとくじけることはない」という自信をもたらす知恵でもある。幼少期から漢文に親しんだ影響か、訳者にもこれに近い体験があった。
日本で「勝ち組負け組」が言われ出した頃、後者の訳者には相応の精神的へこみがあった。そんな時、機会あって西欧に旅したのだが、ニースでトンデモないものをこの目で見た。船旗が私有と示していたが、まるで巡洋艦のようなクルーズ船から、ヘリが飛び立とうとしていた。



英国海軍旗/英国公船旗/英国籍私有船旗
それまで日本で目にした「勝ち組」も、こんなのに比べると「負け組」でしかない。それ以降、殊更に人を卑屈にさせたがる言説を、鼻で笑って過ごせるようになった。もし漢文に現代的意義が在るなら、こうした境地を知る事も、意義の一つに数えていいかも知れない。
さて現代中国の北京語で、否定には「没」(見えない)を使うように、漢文の否定辞は状態を否定し、本章では「己知」(自分の知られる)という状態を「不」(~でない)は否定している。すると一見目的語「おのれを」に見える「己」は、修飾語”おのれの”の意でなければならないことになる。
太古の中国語には格変化があり、一人称の所有格には「我」ではなく「吾」を用いることが多い。「己」の原義は一人称ではなく”直角定規”で、一人称に転用されるようになった頃、格変化が残っていたか不明だが、少なくとも用例としては、一人称所有格=修飾語を意味し得る。
しかしこうした格変化は早くにくずれ、「我」「吾」「己」は混用されるようになった。
これは甲骨文の昔からそうであるらしい。大島正二『中国語の歴史』によると、目的語が代名詞や指示詞で、かつ否定文の場合、「帝不我又」(帝我が又けたら不るか)のような文例があるという。これは「帝我を又け不るか」と読むのがお作法だが、厳密には正しくない。

「帝」=神が「我」=自分の「又」=味方に「不」=ならないだろうか、と問うているわけで、日本語の「この道は通れます」のような、主語が目的語となっている。中国語学の世界では、これを「受事主語」と言うらしいが、専門用語を作れば漢文が読めるわけではない。
それでも訳者が文法にこだわるのは、論語のみならず漢文の原書を、望むなら誰もが読めるようにするにはこれしかない、と思っているから。ただ大学入試程度の漢文なら、返り点が付いているからこうした議論は無用だし、そもそも入試に漢文がある学校が少ない。
しかし若者がもし中国史や中国思想など、漢文を原書で読まねばならない分野を志す時、その心をくじきいたずらに卑屈にさせ、ついにはどうにもならない無人情家にさせてしまいがちなのは、第一に漢文読解の無秩序さがある。文法がないので、権威に頼るしかないからだ。

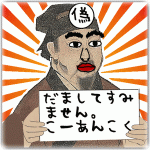
そしてその論語の権威たる儒者は、開祖にすら平気でウソを語らせる。儒者のでたらめを訳者は狂信と表現したが、この意味では儒者の意識は間違いなく冷静で、要は自分の儲けに関わるから、狂った振りをしているだけだ。福禄寿の奴隷とはそういう生物である。
漢文も言語であるからには、おのずから文法があって当然なのだが、ここまでいくつか紹介したように、「この場合はこう読む」といった例外が多すぎる。ではその例外の根拠はと言えば、現代の漢学者であれ昔の儒者であれ、「偉い人がこう言った」という恣意に過ぎない。
これでは共通の議論の場など成立しようが無く、若者が新説を唱えても、なんら合理的根拠のない罵倒や叱責が降ってくるだけで、若者は首をすくめて引き下がるしかない。これは科学とは言えないだろう。先学のいう事に理がないならば、学問と呼ぶのもはばかられる。
こうして心をズタズタにされながら、漢学を学ぶ者はあるいは学校を去り、残った者は論語を読んでおりながら、例えば仁義の情けなどみじんも身に付いていない者に成り下がる。人文は思想だろうが文学だろうが歴史だろうが、学んで人が良くならなければ意味がない。
これは人に食い物にされろ、お人好しになれと言うのではない。数多くの人間類型を知って、目の前の人にもこういう事情がある、と思いやることが出来るようになることだ。人は不可解からいらだちを感じるが、他人の行動に理由を見いだせれば、要らぬ腹立ちを覚えずに済む。
怒りは怒るべき人に怒るべき時に怒り、そして勝って怒り終えねばならない。武道人が平素の温和に努めるのは、このことわりを体得するためだ。怒って負ければ心がいじけ、いじけた者は鬱憤を晴らそうと、高い周波数で吠える狂犬に成り下がる。そうならぬための人文だ。
ところがどういうわけか、漢学界にはむやみに他人に噛みつく人が多く、とりわけ弱い者いじめを好む人が少なくない。精神医学上の病人と言うべきだろうが、これではどれほど数多くの人物の名を知り、出来事を知っていたにせよ、ただの薄気味悪いオタクではないか。

人文はもとより橋を架けたり病気を治す力もない。しかも人がむしろ悪くなるなら、人文、とりわけ漢学が世間から忘れられ、設置大学も減り、目指す若者も少なくなるのは、理の当然だろう。もし漢学がこの後も必要とされ、論語も読まれるならば、変わらねばならない。
そこで訳者如きが拙いながら、唯一見つけた漢文読解法が、語順を最優先することだ。時代が下った漢文は、ねじ曲げて読むのが前提になったものが多いから、必ずしもこれで読解できるとは限らない。しかし論語は漢文として最古の部類に入り、その懸念が比較的薄い。
だから拙訳で語順重視の読みを提示するのは、いたずらに自己宣伝したいからではない。孔子が何を言ったか、それを知りたいがためである。ゆえに陰険な儒者の自己宣伝も、漢学教授の事大主義も、論語を知りたいという目的にはそぐわない。だから真に受けないで訳している。
もちろん、過去に論語に付けられた注や解説が、なべて間違いだとは思わない。しかし名を売って職を得る・金を得るための解説は、その難解さやもったい付けで、自ずからそれが原意に忠実でないことを白状している。数十年以上も漢文を読めば、それぐらいは見分けが付く。
いわゆる碩学の論語解説にも、価値あるものはたくさんある。しかし世間が褒めた人だからと言って、信用してはならないとは当の論語に書いてあることだ(論語子路篇24)。もし若者が論語を読むなら、どうかそうした世間師にだまされることなく、朗らかに読んで貰いたい。

参考記事
『論語』学而篇おわり
お疲れ様でした。




コメント
漢文読解に文法重視の意見、至極当然に思います。時代考証も入れ、的確な訳出だと思いました。すべて拝読したわけではありませんが、このような訳を出されているのは素晴らしいことだと思います。これからもこのスタイルでの訳出をしていただければ、多くの人の参考になると思います。
激励忝く存じます。