論語:原文・書き下し
原文(唐開成石経)
子曰吾與回言終日不違如愚退而省其私亦足以發回也不愚
校訂
東洋文庫蔵清家本
子曰吾與回言終日不違如愚/退而省其私亦足以發回也不愚
後漢熹平石経
(なし)
定州竹簡論語
[子曰]:「吾與回言終日,不違,[如]愚。退而省其私,亦足14……
標点文
子曰、「吾與回言終日、不違如愚。退而省其私、亦足以發。回也不愚。」
復元白文(論語時代での表記)










 愚
愚 


 私
私 





 愚
愚
※論語の本章は、「私」「愚」が論語の時代に存在しない。「如」「亦」「發」の用法に疑問がある。本章は戦国時代以降の儒者による捏造である。
書き下し
子曰く、吾回與言ひて終日、違は不るは愚なるが如し。退い而其の私を省み、亦に發くに以ゆるに足れり。回也愚なら不。
論語:現代日本語訳
逐語訳

先生が言った。「私は顔回と対話すること一日中だったが、言葉が食い違わないことあたかも愚人のようだった。しかし顔回は私の前を退いてその私生活を省みて、(私の言葉を)気付くのに使ってまったく足りている。顔回はまことに愚人ではないなあ。」
意訳
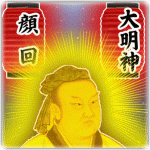

顔回に一日中、仁者のあるべき姿について熱く語っても、はい、はい、とまるで愚か者のように逆らわない。加えて彼は私の見ていない所でも、私の話を自分に当てはめて、人格修養の効果が十分に上がっている。顔回は愚か者どころじゃないぞ。
従来訳
先師がいわれた。――
「回と終日話していても、彼は私のいうことをただおとなしくきいているだけで、まるで馬鹿のようだ。ところが彼自身の生活を見ると、あべこべに私の方が教えられるところが多い。回という人間は決して馬鹿ではないのだ。」下村湖人『現代訳論語』
現代中国での解釈例
孔子說:「我曾整天同顏回談話,他從不反駁,象笨人。後來觀察,發現他理解透徹、發揮自如,他不笨。」
孔子が言った。「私はかつて一日中顔回と顔を突き合わせて語ったが、彼は聞き従って反論せず、まるで間抜けのようだった。のちに観察すると、彼の理解は徹底し、教えを実践できているとわかった。彼は間抜けではない。」
論語:語釈
子曰(シエツ)(し、いわく)

論語の本章では”孔子先生が言った”。「子」は貴族や知識人に対する敬称で、論語では多くの場合孔子を指す。「子」は赤ん坊の象形、「曰」は口から息が出て来るさま。「子」も「曰」も、共に初出は甲骨文。辞書的には論語語釈「子」・論語語釈「曰」を参照。
この二文字を、「し、のたまわく」と読み下す例がある。「言う」→「のたまう」の敬語化だが、漢語の「曰」に敬語の要素は無い。古来、論語業者が世間からお金をむしるためのハッタリで、現在の論語読者が従うべき理由はないだろう。
吾(ゴ)


(甲骨文)
論語の本章では”わたし”。初出は甲骨文。字形は「五」+「口」で、原義は『学研漢和大字典』によると「語の原字」というがはっきりしない。一人称代名詞に使うのは音を借りた仮借だとされる。詳細は論語語釈「吾」を参照。
古くは中国語にも格変化があり、一人称では「吾」(藤堂上古音ŋag)を主格と所有格に用い、「我」(同ŋar)を所有格と目的格に用いた。しかし論語で「我」と「吾」が区別されなくなっているのは、後世の創作が多数含まれているため。論語語釈「我」も参照。
與(ヨ)


(金文)
論語の本章では”~と”。新字体は「与」。金文の字形は「牙」”象牙”+「又」”手”四つで、二人の両手で象牙を受け渡す様。人が手に手を取ってともに行動するさま。従って原義は”ともに”・”~と”。詳細は論語語釈「与」を参照。
回(カイ)

論語の本章では、孔子の弟子、顔回子淵のこと。BC521ごろ – BC481ごろ。諱は回、字は子淵。顔淵ともいう。魯国出身、『史記』に依れば孔子より30年少。論語先進篇2で孟子からは徳=人格力の実践に優れていると評され、孔門十哲の一人でもっとも愛された弟子(孔門十哲の謎)。
存命中の人物では、ただ一人孔子から仁者だと評された(論語雍也篇7)。
従って孔子にその将来を嘱望されたが、孔子に先立つこと二年前に死去。仕官もせず名誉を求めず、貧窮生活にありながら人生を楽しみ、ひたすら仁の修養に邁進したという後世の儒者によるゴマスリ伝説がある。ここから老荘思想発生の一源流とみなす説もあるが、儒者にだまされているだけに思える。詳細は論語の人物:顔回子淵を参照。
顔回の本名とあざ名の呼応について、「顔回、字は子淵、淵は回水の意」と字通に言う。

回水とは渦を巻く水で、渦を巻くような深さがあるので淵という。日本ではカッパが淵から上がってくることになっているが、普段は水中深くに潜んでいるのだ。但し遠野のカッパ淵はさほど深くない。ここが漢字に関して日本人のうっかりし所で、淵と沼の区別がついていない。
沼と池の区別もついていない。普通の日本人が、気軽に漢文を読めるような気でいながら、実はちっとも読めないのはこのあたりに一因がある。漢字は字が違えば言葉が違い、意味が違うのだ。ともあれ顔回も死後の神格化が激しく、有子・曽子と並んで顔子と宗匠扱いされた。
つまりひたすら「偉かった。賢かった」というでっち上げがどしどし付け加わったわけで、とても人間とは思えないような存在に化けた。カッパと変わらない。だから論語の顔回ばなしも、いくぶん割り引いて解釈する必要がある。少なくとも神格化は剥ぎ取らねばならない。
なお孔子の母親の名は顔徴在で、孔子が亡命して最初にわらじを脱いだのは、隣国衛の任侠道の大親分、顔濁鄒の屋敷である。顔回とこの二者とを結びつける記録は無いが、顔回の父・顔路も孔子の弟子とされることからみて、世に出る際の孔子は、顔一族の支援を得たのだろう。
顔濁鄒親分の縄張りは、衛だけでなく斉にまで至ったとする記録があり、また斉に頼まれて私兵を貸してやったこともあるらしい。どうやら顔一族は、大行山脈以東の中原=山東に広く隠然とした力を持つ一大勢力であり、その支援を受けた孔子がどれだけ助かったかわからない。

孔子が顔回を深く賞賛するのも、根にはそういう大人の事情がありそうである。


「亘」(甲骨文)
「回」の初出は甲骨文。ただし「亘」と未分化。現行字体の初出は西周早期の金文。字形は渦巻きの象形で、原義は”まわる”。詳細は論語語釈「回」を参照。
言(ゲン)


(甲骨文)
論語の本章では”語る”。初出は甲骨文。字形は諸説あってはっきりしない。「口」+「辛」”ハリ・ナイフ”の組み合わせに見えるが、それがなぜ”ことば”へとつながるかは分からない。原義は”言葉・話”。甲骨文で原義と祭礼名の、金文で”宴会”の意がある。詳細は論語語釈「言」を参照。

なお論語の時代に通用した金文には、「言」と「音」を書き分けていないものが見られる。
終(シュウ)


(甲骨文)
論語の本章では、”ずっと”。初出は甲骨文。字形はひもの先端を締めくくったさまで、すなわち”おわり”が原義となる。詳細は論語語釈「終」を参照。
日(ジツ)
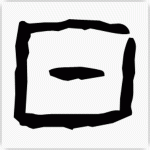

(甲骨文)
論語の本章では”いちにち”。初出は甲骨文。「ニチ」は呉音。原義は太陽を描いた象形文字。甲骨文から”昼間”、”いちにち”も意味した。詳細は論語語釈「日」を参照。
終日(ひねもし)
論語の本章では”一日中”。朝から晩まで。
不(フウ)


(甲骨文)
漢文で最も多用される否定辞。初出は甲骨文。「フ」は呉音(遣隋使より前に日本に伝わった音)、「ブ」は慣用音。原義は花のがく。否定辞に用いるのは音を借りた派生義だが、甲骨文から否定辞”…ない”の意に用いた。詳細は論語語釈「不」を参照。
違(イ)
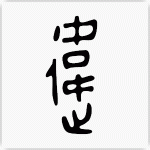

(金文)
論語の本章では”反対する”。初出は西周早期の金文。字形は「辵」”あし”+「韋」”めぐる”で、原義は明らかでないが、おそらく”はるかにゆく”だったと思われる。論語の時代までに、”そむく”、”はるか”の意がある。詳細は論語語釈「違」を参照。
如(ジョ)
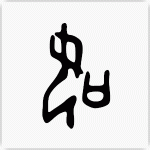

甲骨文
論語の本章では”~のようである”。この語義は春秋時代では確認できない。初出は甲骨文。甲骨文の字形は「女」+「𠙵」”くち”で、”ゆく”の意と解されている。春秋末期までの金文には、「女」で「如」を示した例しか無く、語義も”ゆく”と解されている。詳細は論語語釈「如」を参照。
愚(グ)


「愚」(金文)
論語の本章では、”馬鹿者”。初出は戦国末期の金文。論語の時代に存在しない。論語時代の置換候補もない。同音に「禺」”かりそめの・真ん中でない”とそれを部品に持つ漢字群。字形は「禺」+「心」で、まっとうでない心のさま。原義は”愚か”。詳細は論語語釈「愚」を参照。
なお孔子は論語先進篇17で曽子を「ウスノロ」と評すると同時に、弟子の子羔を「柴や愚」と評している。
退(タイ)


(甲骨文)
論語の本章は”引き下がる”。初出は甲骨文。甲骨文の字形は「豆」”食物を盛るたかつき”+「夊」”ゆく”で、食膳から食器をさげるさま。原義は”さげる”。金文では辶または彳が付いて”さがる”の意が強くなった。甲骨文では祭りの名にも用いられた。詳細は論語語釈「退」を参照。
而(ジ)


(甲骨文)
論語の本章では”そして”。初出は甲骨文。原義は”あごひげ”とされるが用例が確認できない。甲骨文から”~と”を意味し、金文になると、二人称や”そして”の意に用いた。英語のandに当たるが、「A而B」は、AとBが分かちがたく一体となっている事を意味し、単なる時間の前後や類似を意味しない。詳細は論語語釈「而」を参照。
省(セイ)


(甲骨文)
論語の本章では、”振り返って詳しく検討する”。初出は甲骨文。「ショウ」は呉音。原義は「屮」”ささげる”+「目」で、まじめな気持でじっと見つめること。詳細は論語語釈「省」を参照。
其(キ)


(甲骨文)
論語の本章では”その”。初出は甲骨文。甲骨文の字形は「𠀠」”かご”。かごに盛った、それと指させる事物の意。金文から下に「二」”折敷”または「丌」”机”・”祭壇”を加えた。人称代名詞に用いた例は、殷代末期から、指示代名詞に用いた例は、戦国中期からになる。詳細は論語語釈「其」を参照。
私
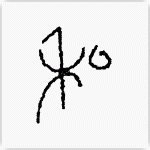

(金文)
論語の本章では”私生活”。同音は「死」のみ。初出は戦国末期の金文。論語の時代に存在しない。論語時代の置換候補も無い。詳細は論語語釈「私」を参照。


「㠯」(金文)・「厶」(䜌書缶)
同訓の「厶」の初出は孔子より約一世紀前の「䜌書缶」で、㠯(シ・すき、カ音不明)と同じ形で記された。ただし「以」”用いる”の意で使われており、論語の時代に”わたし”を意味した証拠が無い。「厶」が”わたし”の語義を獲得するのは、燕系戦国文字からになる。
退而省其私
従来の論語本では”顔回が退いて孔子がその私生活を見ると”と解すが、主語が統一されているとここでは判断した。変更の記号がないからだ。
亦(エキ)


(甲骨文)
論語の本章では”おおいに・たいそう”。初出は甲骨文。原義は”人間の両脇”。春秋末期までに”…もまた”の語義を獲得した。”おおいに”の語義は、西周早期・中期の金文で「そう読み得る」だけで、確定的な論語時代の語義ではない。詳細は論語語釈「亦」を参照。
足(ショク/シュ)
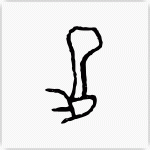

「疋」(甲骨文)
論語の本章では”足りる”→”…するのに十分だ”。初出は甲骨文。ただし字形は「正」「疋」と未分化。”あし”・”たす”の意では「ショク」と読み、”過剰に”の意味では「シュ」と読む。同じく「ソク」「ス」は呉音。甲骨文の字形は、足を描いた象形。原義は”あし”。甲骨文では原義のほか人名に用いられ、金文では「胥」”補助する”に用いられた。”足りる”の意は戦国の竹簡まで時代が下るが、それまでは「正」を用いた。詳細は論語語釈「足」を参照。
以(イ)


(甲骨文)
論語の本章では”用いる”。「亦足以發」とあるのだから、「以」は「足」”足りる”の目的語で、「足以」で”使うのに足りている”。「發」(発)は「以」の目的語で、「以發」は”開発するのに使う”。「亦足以發」で、「おおいにひらくにもちゆるにたる」または「ひらくにもちゆるにおおいにたる」と訓読し、”(自分を)開発するのに使うのにまったく足りている”。
中国語は殷代の太古を除いて修飾語→被修飾語、主語→述語の順だから、つねに返り点が付いている心得で訓読しないと誤読する。
字の初出は甲骨文。人が手に道具を持った象形。原義は”手に持つ”。論語の時代までに、”率いる”・”用いる”・”そして”の語義があったが、「もって」と読んで副詞や前置詞に用いる例は確認できない。詳細は論語語釈「以」を参照。
發(ハツ)
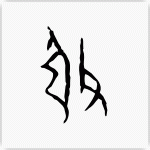

(甲骨文)
論語の本章では、”開発する”。この語義は春秋時代では確認できない。新字体は「発」。『大漢和辞典』の第一義は”射る”。初出は甲骨文。ただし字形は「㢭」または「𢎿」。字形は「弓」+「攴」”手”で、弓を弾いて矢を射るさま。原義は”射る”。甲骨文では人名の他、否定辞に用いられた。金文では人名や官職名に用いられた。詳細は論語語釈「発」を参照。
也(ヤ)
論語の本章、「回也」では”回こそまさに”という主語の強調。一部の版本は章末「不愚」の後ろにも「也」を記す。「なり」と訓読し”~である”という断定の語義は春秋時代には確認出来ない。主語の強調の派生義として、「かな」と訓読し”…だなあ”の詠嘆の意と解することは可能。
文末の「也」は定州竹簡論語では欠く。本来無いのではなく簡の欠損、つまりあったかどうか分からない。漢石経は論語の本章全体を欠損、論語の本章に関して現存最古の古注本である清家本は欠く。これに従い章末の「也」は無いものとして校訂した。
宋版論語注疏、早大蔵新注、正平本も欠く。対して本願寺坊主の手に成る文明本、その後発である足利本、根本本、懐徳堂本は記す。文明本は足利本→根本本がこの系統なので、日本伝承の論語の元となった。文明本は他の箇所でもそれまでの日本伝承や中国伝承と文字列が異なることがある。何か根拠があったのかは不明。論語の伝承について詳細は「論語の成立過程まとめ」を参照。
原始論語?…→定州竹簡論語→白虎通義→ ┌(中国)─唐石経─論語注疏─論語集注─(古注滅ぶ)→ →漢石経─古注─経典釈文─┤ ↓↓↓↓↓↓↓さまざまな影響↓↓↓↓↓↓↓ ・慶大本 └(日本)─清家本─正平本─文明本─足利本─根本本→ →(中国)─(古注逆輸入)─論語正義─────→(現在) →(日本)─────────────懐徳堂本→(現在)
江戸時代までの日本人は中国に対してしおらしく、論語の書き換えはしなかった。だがそれまで曼荼羅の端で葬儀屋を営んでいた阿弥陀を教義の中心仏物に据え、念仏を唱えるだけで救われるという、釈迦が聞いたら仰天するだろう教説を説いた一向宗なら、論語の書き換えをやりかねない。
釈迦が仰天しても浄土真宗の坊主は困らないようで、その仏壇には阿弥陀と親鸞と蓮如は飾ってあるが仏陀は飾っていない。浄土三部経は「仏説」と言うからブッダに責任をなすりつけているものの、仏教を標榜しつつブッダはどうでもいいというわけだ。論語の改作もやって不思議は無い。
ゲーム「信長の野望」の、役者若かりし頃のバージョンでは、勝手に他人の領地で一揆を煽っておきながら、「み仏の力を思い知ったか」とか本願寺坊主が言う。これでは信長に寺や一揆勢を丸焼きにされたり、秀吉になで斬りにされても仕方がないと思ったものだ。


(金文)
論語の本章では、「回也」では「や」と読んで主格の強調に、「不愚也」では「かな」と読んで詠歎に用いている。後者は断定の意と解してもかまわないが、この語義は春秋時代では確認できない。初出は事実上春秋時代の金文。字形は口から強く語気を放つさまで、原義は”…こそは”。春秋末期までに句中で主格の強調、句末で詠歎、疑問や反語に用いたが、断定の意が明瞭に確認できるのは、戦国時代末期の金文からで、論語の時代には存在しない。詳細は論語語釈「也」を参照。
論語:付記
検証
論語の本章は春秋戦国の誰も引用せず、秦・前後の漢でも、前漢中期の『史記』が弟子伝に再録し、さらに宣帝期の定州竹簡論語に記しているのを除いて見られない。武帝期の董仲舒がいわゆる儒教の国教化を進める段階で、創作したと考えるのが筋が通る。
董仲舒についてより詳しくは、論語公冶長篇24余話を参照。
解説
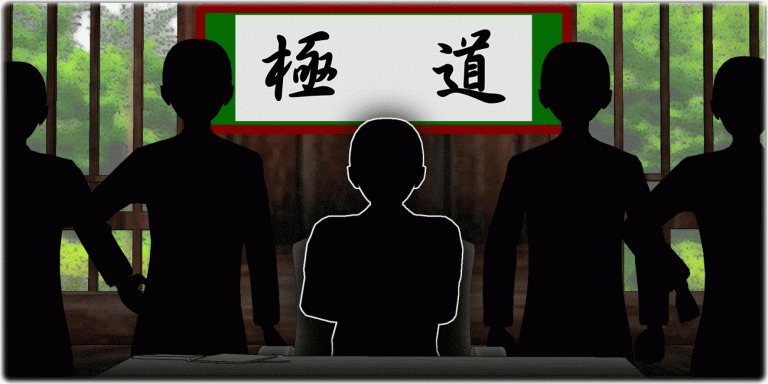
論語の本章は、いわゆる極道の一族出身だった、顔淵(顔回)神格化のために作られたと言ってよい。神格化の点では、論語の第二章で登場の有若と同様だが、ボンクラ伝説が伝わる有若と違って、顔淵の否定ばなしは管見の限り見たことが無い。
儒者官僚が無慮二千年にわたって、顔淵の否定ばなしを消しに消したのかもしれないが、こうまで証拠が出てこないと、孔子にも弟子仲間にも好かれた人物で、孔子の教えた六芸には一通り通じた、出来の良い人だっただろう。ただし、ワルいことをしなかったわけではない。
孔子一門が、各地で政府転覆を謀るワルい集団だったからにはなおさらだ。亡命先の衛の霊公に、現代換算で111億円もの年俸を貰いながら国盗りを謀ったり(論語憲問篇20)、諸国の内乱や戦争をけしかけたり(『墨子』非儒篇)、孔子一門の悪行はかなりのものだった。
その謀略を支えたのが顔淵と孔子の母(顔徴在)が属した顔氏一族で、その総領が、屋敷を衛国に、山塞を梁父山に構える顔濁鄒親分で、極道と傭兵団を足しっぱなしにしたような存在だった。孔子は生国の魯で失脚すると、一目散に親分の屋敷を目指してわらじを脱いでいる。
詳細は孔門十哲の謎を参照。
だがそれにしても、後世の儒者によるゴマスリは激しすぎる。儒者のゴマスリを含んだハッタリは、孔子没後一世紀に現れた孟子が始まりだが、存外孟子は、顔回にごまをすっていない。『孟子』の地の文や弟子の言葉では、顔回を敬称しているのに、孟子は呼び捨てている。
禹、稷當平世,三過其門而不入,孔子賢之。顏子當亂世,居於陋巷。一簞食,一瓢飲。人不堪其憂,顏子不改其樂,孔子賢之。孟子曰:「禹、稷、顏回同道。禹思天下有溺者,由己溺之也;稷思天下有飢者,由己飢之也,是以如是其急也。禹、稷、顏子易地則皆然。今有同室之人鬬者,救之,雖被髮纓冠而救之,可也。鄉鄰有鬬者,被髮纓冠而往救之,則惑也,雖閉戶可也。」

禹や稷は世を平らげるため、自宅の門を三度通り過ぎても入らなかった。それを孔子は讃えた。一方顔回先生は、乱れた世の中で貧民街に隠れ住み、粗食で暮らした。常人なら耐えられないが、顔回先生は楽しく暮らし、孔子はそれを讃えた。
孟子「禹や稷と、顔回は同じだ。禹は天下に溺死者が出るのを思ったが、自分のせいだった。稷は天下に餓死者が出るのを思ったが、それも自分のせいだった。だから家にも帰らずイソイソ働いた。もし顔回先生が禹や稷と同じ立場だったら、同じように働いただろう。今仮に、同じ部屋にいる人がケンカを始めるとしたら、ざんばら髪になって冠が飛んでも助太刀しようと思う、これはまあいい。だが近所でケンカがあると聞いて飛び出すのは、血迷ったと言われても仕方がない。部屋に閉じこもっていても、非難は出来ないのだ。」(『孟子』離婁下)
孟子は曽子の系統を引くから、曽子の神格化はさんざんやったことになっているが、顔淵に対しては動機が無かったらしい。すると顔淵の神格化は、儒教が国教化された、漢帝国に始まると言えるようだ。帝国の儒者がなぜ顔淵を好んだのだろう。
だが推測は出来る。顔淵を語り手としただろう初めての本、『公羊顏氏記』十一編があったことが、『漢書』芸文志に記されている。漢帝国で公羊学を提唱したのは董仲舒で、この男は武帝の幼少期のトラウマに付け込んで、変な教えを吹き込み、いわゆる儒教の国教化を進めた。

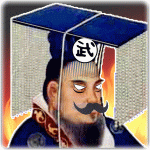
この男が出なかったら、いま論語を読めないかも知れないが、この男が一番怪しい。董仲舒について更には、論語公冶長篇24余話を参照。董仲舒による顔淵神格化の詳細は、論語先進篇3解説を参照。
余話
書けないようなこと
聖人と呼ばれた孔子や、四人の宗家=四聖の一人に数えられた顔淵が、謀略に手を染めていたなどあり得ない、と思われるかも知れない。だが顔淵はともかく孔子については、墨子のみならず『春秋左氏伝』『史記』『越絶書』にも国際的政治工作が記されている。
それを単に「外交」と言って仕舞えもするが、国主でもない孔子とその一門が国際関係の中で盛んに活動していたのだ。しかもその集団は重武装しており、桓魋の襲撃や蒲邑での突破戦、陳蔡の包囲戦など、何度も激しい戦闘があったことを『史記』は記す。
現在に置き換えるなら、PMC(民間軍事会社)が諜報も兼ねて行っている、と言って差し支えない。あるいは母と顔氏一族の持つ国際情報ネットワークを、初めて政治の場に持ち込んだのが孔子だったと言えるのかも知れない。その威力は諸侯国が孔子を迎えたがるのに十分だった。
だが、今でもネットを触れない要人がネットを毛嫌いするように、孔子が提供する情報ネットワークによる政治は、既存の利権集団を脅かす。GAFAを規制したがる諸国がいくつもあるように、諸国に迎えられた孔子を好意的に見た貴族はむしろ少数だったろう。
だからこそ陳蔡の包囲戦のような目に一門は遭わされた。孔子一行が恐るべき存在でなければ、決してあり得ない事態である。そして有名弟子のうち、何をやったかはっきりしている者の方がむしろ少ない。つまりそれは、はっきり書けないようなことをしていたということだ。
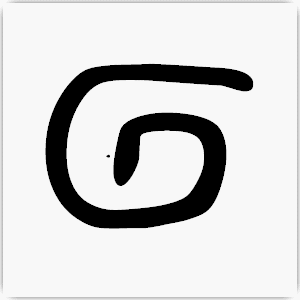


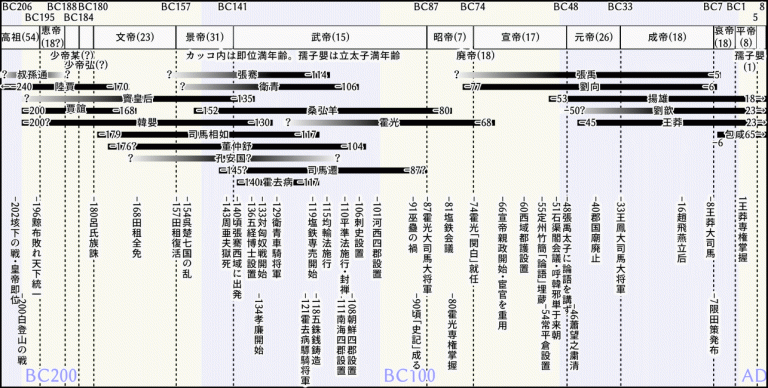


コメント