論語:原文・書き下し
原文(唐開成石経)
哀公問曰何爲則民服孔子對曰舉𥄂錯諸枉則民服舉枉錯諸𥄂則民不服
- 「民」字:「叚」字のへんで記す。唐太宗李世民の避諱。
校訂
諸本
- 武内本:釋文、錯鄭本措に作る。措は置也、顔淵篇第二十二章参照。
東洋文庫蔵清家本
哀公問曰何爲則民服/孔子對曰舉𥄂錯諸枉則民服/舉枉錯諸𥄂則民不服
後漢熹平石経
…白何爲則民服孔子對白…
定州竹簡論語
[哀公問]曰:「何為則[民服?」孔子對]曰:「舉𥄂錯a諸[枉,則民]25……舉枉錯諸𥄂,則民不服。」26
- 錯、『釋文』云、「鄭本作”措”、投也。」阮元『校勘記』云、「措、正字、古経伝多仮”錯”為之。」
標点文
哀公問曰、「何爲則民服。」孔子對曰、「舉𥄂錯諸枉、則民服。舉枉錯諸𥄂、則民不服。」
復元白文(論語時代での表記)














 錯
錯 枉
枉 


 枉錯
枉錯





※舉→喬。論語の本章は、「錯」「枉」が論語の時代に存在しない。「問」「何」「則」「諸」の用法に疑問がある。本章は戦国時代以降の儒者による創作である。
書き下し
哀公問ふて曰く、何ぞ爲れば則ち民服はん。孔子對へて曰く、𥄂を擧げて諸枉れるに錯かば、則ち民服ふ。枉を擧げて諸𥄂に錯かば、則ち民服は不。
論語:現代日本語訳
逐語訳


哀公が質問した。「何が実現すれば民が服従するだろうか。」孔子が答えて言った。「真っ直ぐな者を一人、曲がった者どもの上に置くと、民は服従します。曲がった者を一人、真っ直ぐな者どもの上に置くと、民は服従しません。」
意訳


若殿「どうすれば皆の者が言うことを聞くかのう。」
孔子「ろくでなしの長に正直者を据えなされ。逆だから言うことを聞かぬのです。」
従来訳
哀公がたずねられた。――
「どうしたら人民が心服するだろうか。」
先師がこたえられた。――
「正しい人を挙用して曲った人の上におくと、人民は心服いたします。曲った人を挙用して正しい人の上におくと、人民は心服いたしません。」下村湖人『現代訳論語』
現代中国での解釈例
哀公問:「怎樣使人心服?」孔子說:「以正壓邪,則人心服;以邪壓正,則人心不服。」
哀公が問うた。「どうすれば世論が〔余に〕なびくのだろう。」
孔子が言った。「正義の人で邪悪な者を取り締まれば、即座に世論はなびきます。邪悪な者で正義の人を取り締まれば、即座に世論はそっぽを向きます。」
論語:語釈
哀公(アイコウ)

第27代魯国公。?-BC467。魯(現在の中国山東省南部)の第26代君主の定公の子。BC494年に即位した。BC487年に隣国の呉に攻められるも奮戦し、和解した。その後斉に攻められ敗北した。BC485年には呉と同じく斉へ攻め込み大勝した。
翌年また斉に攻められ、BC483年に孔子が斉の君主・簡公討伐を勧めるが実現しなかった。その3年後のBC481年、斉の簡公が宰相の田恒に弑殺されたのを受けて、孔子が再び斉への進軍を3度も勧めるが、哀公はすでに門閥家老・三桓に力を奪われており実現しなかった。
BC471年に哀公は晋と同じく斉へ指揮官として進軍した。BC468年、三桓氏の武力討伐を試みるもその軍事力に屈し、衛や鄒を転々とした後に越へ国外追放され、BC467年にその地で没した。
詳細は『史記』魯世家:哀公を参照。論語語釈「哀」・論語語釈「公」も参照。
孔子の晩年の主君で、孫ほど年が離れていた。執権の季康子と共に、放浪中の孔子を魯国に呼び戻し、何やら相談役のような地位に就けたらしい。それゆえ儒者が孔子伝説のラノベを書く際、孔子の説教を有り難く拝聴する、人はいいが、やや足りないボウヤとして登場する。
呼び戻しはしたが相談役にしかしなかったのは、孔子が日の出の勢いの呉国をバックに付けていたためで、魯は呉に脅されて、牛・羊・豚の焼肉セット100人前(百牢)を供応させられるなど、いいようにされていた。そのヒモ付きの孔子は、よく言って危険人物だったわけ。
だが呉が留守を越に攻められて没落すると、哀公はすぐさま孔子を追いやり、ろくに給料も払わなかったらしい。そのせいで孔子は息子の葬儀費用にすら事欠いたことが論語先進篇7に記されている。しかも孔子が世を去った時、哀公はうそ泣きだけして済ませている。
それを目撃した子貢は、「ろくな死に方をしないぞ」と哀公を非難したが、因果応報と言うのだろうか、すでに実権を奪われていた哀公は、孔子の弟子でもある有力家老の孟武伯にいびられ、「ワシを殺す気か」と問うたが「知らねえよ」と返され、肝を潰して国外逃亡した。

子貢「哀公はきっと国外に逃亡するハメになるだろう。先生の生前には閑職に追いやっておきながら、亡くなってからオイオイ泣き叫ぶのは礼法破りだ。私一人が取り残されたって? その言い方は周王の特権だ。まともには死ねないぞ。」(『史記』孔子世家)
そしてはるか南方の越国で客死する。論語の時代、どの諸侯も実権を失っていたが、それはそれなりの時代背景ゆえで、そんな時代にも隣国衛の霊公のように、ガッチリと国政を手に握った君主はいた。要するに哀公は当時の平均的な国公で、つまりは世間に無用とされたのだ。
問(ブン)


(甲骨文)
論語の本章では”問う”。この語義は春秋時代では確認できない。初出は甲骨文。「モン」は呉音。字形は「門」+「口」。甲骨文での語義は不明。西周から春秋に用例が無く、一旦滅んだ漢語である可能性がある。戦国の金文では人名に用いられ、”問う”の語義は戦国最末期の竹簡から。それ以前の戦国時代、「昏」または「𦖞」で”問う”を記した。詳細は論語語釈「問」を参照。
曰(エツ)


(甲骨文)
論語で最も多用される、”言う”を意味する言葉。初出は甲骨文。原義は「𠙵」=「口」から声が出て来るさま。詳細は論語語釈「曰」を参照。
漢石経では「曰」字を「白」字と記す。古義を共有しないから転注ではなく、音が遠いから仮借でもない。前漢の定州竹簡論語では「曰」と記すのを後漢に「白」と記すのは、春秋の金文や楚系戦国文字などの「曰」字の古形に、「白」字に近い形のものがあるからで、後漢の世で古風を装うにはありうることだ。この用法は「敬白」のように現代にも定着しているが、「白」を”言う”の意で用いるのは、後漢の『釈名』から見られる。論語語釈「白」も参照。
何(カ)


(甲骨文)
論語の本章では”なに”。この語義は春秋時代では確認できない。初出は甲骨文。字形は「人」+”天秤棒と荷物”または”農具のスキ”で、原義は”になう”。甲骨文から人名に用いられたが、”なに”のような疑問辞での用法は、戦国時代の竹簡まで時代が下る。詳細は論語語釈「何」を参照。
爲(イ)
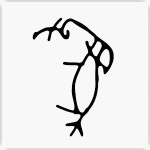

(甲骨文)
論語の本章では”する”。新字体は「為」。字形は象を調教するさま。甲骨文の段階で、”ある”や人名を、金文の段階で”作る”・”する”・”~になる”を意味した。詳細は論語語釈「為」を参照。
何爲(なんぞなれば)
論語の本章では”何が実現すれば”。主語が「何」で述語動詞が「爲」だから、”何が為る=実現すれば”の読みと意になる。「何を爲さ(orせ)ば」は主述関係を無視した間違った訓読。”What time is it now?”を”いつを今か?”と訳したらペケを付けられるのと同じ。”掘ったイモいじるでねぇ”と訳した方が、まだ笑いが取れるだけ気が利いている。
則(ソク)


(甲骨文)
論語の本章では、「則AB」で”AがBになる”。初出は甲骨文。字形は「鼎」”三本脚の青銅器”と「人」の組み合わせで、大きな青銅器の銘文に人が恐れ入るさま。原義は”法律”。論語の時代=金文の時代までに、”法”・”則る”・”刻む”の意と、「すなわち」と読む接続詞の用法が見える。詳細は論語語釈「則」を参照。
民(ビン)


(甲骨文)
論語の本章では”たみ”。初出は甲骨文。「ミン」は呉音。字形は〔目〕+〔十〕”針”で、視力を奪うさま。甲骨文では”奴隷”を意味し、金文以降になって”たみ”の意となった。唐の太宗李世民のいみ名であることから、避諱して「人」などに書き換えられることがある。唐開成石経の論語では、「叚」字のへんで記すことで避諱している。詳細は論語語釈「民」を参照。
哀公は直轄領の住民が言うことを聞かないのを歎いた可能性はあるが、上掲のようにそれより恐いのは貴族層で、彼らが言うことを聞かないのを歎いた可能性の方が高い。そして当時の貴族=有権者とは、領主貴族だけでなく、広く都市住民を意味していた(→卿大夫士)。
服(フク)


(甲骨文)
論語の本章では”従う”。初出は甲骨文。字形は「凡」”たらい”+「卩」”跪いた人”+「又」”手”で、捕虜を斬首するさま。原義は”屈服させる”。甲骨文では地名に用い、金文では”飲む”・”従う”・”職務”の用例がある。詳細は論語語釈「服」を参照。
孔子(コウシ)

論語の本章では”孔子”。いみ名(本名)は「孔丘」、あざ名は「仲尼」とされるが、「尼」の字は孔子存命前に存在しなかった。BC551-BC479。詳細は孔子の生涯1を参照。
論語で「孔子」と記される場合、対話者が目上の国公や家老である場合が多い。本章もその一つ。詳細は論語先進篇11語釈を参照。


(金文)
「孔」の初出は西周早期の金文。字形は「子」+「乚」で、赤子の頭頂のさま。原義は未詳。春秋末期までに、”大いなる””はなはだ”の意に用いた。詳細は論語語釈「孔」を参照。


(甲骨文)
「子」の初出は甲骨文。字形は赤ん坊の象形。春秋時代では、貴族や知識人への敬称に用いた。季康子や孔子のように、大貴族や開祖級の知識人は「○子」と呼び、一般貴族や孔子の弟子などは「○子」と呼んだ。詳細は論語語釈「子」を参照。
對(タイ)


(甲骨文)
論語の本章では”回答する”。初出は甲骨文。新字体は「対」。「ツイ」は唐音。字形は「丵」”草むら”+「又」”手”で、草むらに手を入れて開墾するさま。原義は”開墾”。甲骨文では、祭礼の名と地名に用いられ、金文では加えて、音を借りた仮借として”対応する”・”応答する”の語義が出来た。詳細は論語語釈「対」を参照。
舉*(キョ)


(金文)
論語の本章では”登用する”。新字体は「挙」。初出は戦国末期の金文。論語の時代に存在しない。初出の字形は「與」(与)+「犬」で、犬を犠牲に捧げるさま。原義は恐らく”ささげる”。ただし初出を除く字形は「與」+「手」で、「與」が上下から両腕を出して象牙を受け渡す様だから、さらに「手」を加えたところで、字形からは語義が分からない。論語時代の置換候補は、”あげる”・”あがる”に限り近音の「喬」。また上古音で同音の「居」に”おく・すまわせる”の語釈が『大漢和辞典』にあり、初出は春秋時代の金文。ある人物をある地位に就けることを意味する。ただし春秋時代での語義は、”古くからその地位にいる”ことであり、”推挙する”ではない。詳細は論語語釈「挙」を参照。
直(チョク)→𥄂(チョク)


(甲骨文)
論語の本章では”正直者”。この語義は春秋時代では確認できない。初出は甲骨文。定州竹簡論語の「𥄂」は異体字。「ジキ」は呉音。甲骨文の字形は「丨」+「目」で、真っ直ぐものを見るさま。原義は”真っ直ぐ見る”。甲骨文では祭礼の名に、金文では地名に、戦国の竹簡では「犆」”去勢した牡牛”の意に、「得」”~できる”の意に用いられた。詳細は論語語釈「直」を参照。
錯(サク)
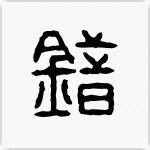

(秦系戦国文字)
論語の本章では”おく”。初出は戦国時代の金文。論語の時代に存在せず、論語時代の置換候補もない。”おく”意味での発音は去声(尻すぼみの銚子)、”まじえる”の意味での発音は入声。現伝の字形は「金」+「昔」だが、この字形に定まる後漢より以前の字形は、つくりが明らかに「昔」ではなく、何を表しているかは分からない。詳細は論語語釈「錯」を参照。
『経典釈文』が言う「錯」→「措」は、鄭玄本がいろいろ怪しい残巻の敦煌本を別として消失した現在となっては、物証を確かめようもない。また訳者が確認出来た範囲では、論語の本章は敦煌本の残巻に含まれていない。
仮に鄭玄本が「措」だったとしても、初出は戦国の金文で、論語の時代に存在しない。また後漢末期の人物である鄭玄の本にそうあるなら、古注が反映してもおかしくないが、古注では「錯」のまま。校訂の必要は無いと判断した。詳細は論語語釈「措」を参照。
『論語集釋』は次のように言う。
七經考文:古本「服」下有「也」字。 釋文:「錯」,鄭本作「措」。劉氏正義:漢費鳳碑:「舉直措枉。」與鄭本合。說文云:「措,置也。」「措」正字,「錯」叚借字。
『七経考文』とは根本武夷とともに古注を広めた江戸儒・山井崑崙の著書。「古本」とは何を言うのか判然としないが、「也」は清家本、正平本、足利本、根本本は記さない。本願寺坊主の手による、何かと文字列の怪しい文明本だけが記す。「錯は音を借りた仮借字である」というのはその通りだが、だからといって校訂の根拠にはならない。
論語の伝承について詳細は「論語の成立過程まとめ」を参照。
原始論語?…→定州竹簡論語→白虎通義→ ┌(中国)─唐石経─論語注疏─論語集注─(古注滅ぶ)→ →漢石経─古注─経典釈文─┤ ↓↓↓↓↓↓↓さまざまな影響↓↓↓↓↓↓↓ ・慶大本 └(日本)─清家本─正平本─文明本─足利本─根本本→ →(中国)─(古注逆輸入)─論語正義─────→(現在) →(日本)─────────────懐徳堂本→(現在)
諸(ショ)


(秦系戦国文字)
論語の本章では”複数の”。論語の時代では、まだ「者」と「諸」は分化していない。「者」の初出は西周末期の金文。ごんべんのある現行字体の初出は秦系戦国文字。漢和辞典で「之於」(シヲ)と音が通じるので一字で代用した言葉とされることがあるが、論語の本章の場合そう理解しては文意が分からない。
金文の字形は「者」だけで”さまざまな”の意がある。「者」も春秋時代までにその用例がある。詳細は論語語釈「諸」を参照。
枉(オウ)
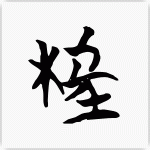

(楚系戦国文字)
論語の本章では”曲げる・悪用する”。初出は戦国文字で、論語の時代に存在しない。論語時代の置換候補もない。同音別漢字は存在しない。字形は「木」+「㞷」”はびこる”で、樹木が群がりしげるさま。原義は”まがる”とされている。詳細は論語語釈「枉」を参照。
舉𥄂錯諸枉(なほきをあげてもろまがれるにおかば)
舉(V)𥄂(O),錯(V)諸枉(O)。「諸」は単数のものに対する”複数の”の意で、通説のように無考えに「これ」と訓読している限り、漢文と億万年にらめっこしても、何が書いてあるか分からない。
不(フウ)


(甲骨文)
漢文で最も多用される否定辞。初出は甲骨文。「フ」は呉音(遣隋使より前に日本に伝わった音)、「ブ」は慣用音。原義は花のがく。否定辞に用いるのは音を借りた派生義だが、甲骨文から否定辞”…ない”の意に用いた。詳細は論語語釈「不」を参照。
論語:付記
検証
論語の本章は、先秦両漢の誰一人引用していない。「民服」という言葉は論語とほぼ同時代の『孫武兵法』に出てくるが、こちらも論語同様に、史実の孫武の言葉とは言えない話が多数あることが、すでに指摘されている。古注では、新~後漢の包咸だけが注を書き付けている。
古注『論語集解義疏』
註苞氏曰哀公魯君之諡也…註苞氏曰錯置也舉用正直之人廢置邪枉之人則民服其上矣

注釈。包咸「哀公は魯の国公のおくり名である。…錯とは置くことである。正直な人を取り挙げて、よこしまな人を取り除く。そうすれば民は必ず目上に従うのである。」
従って本章は、前漢儒者による創作と考えるのが筋が通る。
解説
哀公は『孔子家語』に多数の孔子との問答が載るが、そのほとんどはでっち上げだろう。なお孔子が呉国とつるんでいたことは、史料にははっきりと記されていないが、時間軸を並べるとその推測が成り立ち、また子貢に限れば、呉国と親しかった記述は史料にある。
| BC | 魯哀公 | 孔子 | 魯国 | その他 | |
| 484 | 11 | 68 | 孔文子に軍事を尋ねられる。衛を出て魯に戻る。のち家老の末席に連なる。弟子の冉求、侵攻してきた斉軍を撃破 | 呉と連合して斉に大勝 | 呉・伍子胥、呉王夫差に迫られて自殺 |
| 483 | 12 | 69 | もう弟子ではないと冉有を破門 | 季康子、税率を上げ、家臣の冉求、取り立てを厳しくする | |
| 482 | 13 | 70 | 息子の鯉、死去 | 呉王夫差、黄池に諸侯を集めて晋・定公と覇者の座を争う。晋・趙鞅、呉を長と認定(晋世家)。呉は本国を越軍に攻められ、大敗 | |
| 481 | 14 | 71 | 斉を攻めよと哀公に進言、容れられず。弟子の顔回死去。弟子の司馬牛、宋を出奔して斉>呉を放浪したあげく、魯で変死 | 孟懿子死去。麒麟が捕らわれる | 斉・簡公、陳成子(田常)によって徐州で殺され、平公即位。宋・桓魋、反乱を起こして曹>衛>斉に亡命 |
論語の本章、新注は次の通り。
新注『論語集注』
哀公問曰:「何為則民服?」孔子對曰:「舉直錯諸枉,則民服;舉枉錯諸直,則民不服。」哀公,魯君,名蔣。凡君問,皆稱孔子對曰者,尊君也。錯,捨置也。諸,眾也。程子曰:「舉錯得義,則人心服。」謝氏曰:「好直而惡枉,天下之至情也。順之則服,逆之則去,必然之理也。然或無道以照之,則以直為枉,以枉為直者多矣,是以君子大居敬而貴窮理也。」
本文「哀公問曰:何為則民服?」孔子對曰:「舉直錯諸枉,則民服;舉枉錯諸直,則民不服。」
哀公とは魯の国君でいみ名は蔣。すべて主君に問われた場合、「孔子對曰」と記すのは、主君を尊重するからである。錯は捨て置くことである。諸とは、多くの、の意である。
程頤「昇進や降格に基準があれば、皆の心が従う。」
謝良佐「正直を好んで悪党を憎むのは、天下の誰もが持つ心証である。それに従えば従われるし、逆らえば刃向かわれる。当たり前の道理だ。場合によりよこしまな者が栄えることがあるが、そういうときは正直者に悪党の始末を任せる。すると改心する悪党が増えることになり、こうやって君子は大いに身を慎んでものの道理を極めることができる。」
余話
仁君は居ないか長生きしない
なお「舉」(挙)について。中国では王朝交替があると、禅譲であれ放伐であれ、前王朝の宗室は一人残らず皆殺しにされるのが普通で、新しい王朝は反乱の火種になる前王室を執拗に全土の隅々まで追い回して命を絶つ。そうでないとやられるのは新しい王朝とその一族だからだ。
これが征服王朝ともなると強烈で、「蛮族のくせに」という中国人の反感を根こそぎにするには、反感の核となる旧宗室はただの一人も生かしてはおけない。中国史上希な名君とされる清の康煕帝が、明帝室の生き残りを徹底的に捜索し捕縛し虐殺したのはその一例。
かろうじてまだ満洲時代の清に服属した明宗室の一人が、すでに八旗に編入されていたから、明朝諸帝の墓守として残されただけ(→延恩侯)。文化面についても同様で、前王朝で当たり前に行われた文化が、王朝と共に消滅する事がある。延恩侯も明の礼式は一切許されなかった。
「舉」は「與」(与)”褒美として象牙を下賜する”+「丰」”豊かな実りをお供えする”だと記した。現行字体では「丰」は「手」になっているが、その理由はただ一つ、後漢の『説文解字』が、字形を誤解して「手」だと言い張ったことに始まる。そして後漢の儒者は信用できない。
詳細は論語解説「後漢というふざけた帝国」を参照。編者の許慎はもと軍人で、退役後に文化事業として儒者を集めて字書を編ませたのだが、後漢の儒者は信じがたいほど不真面目で、まともにものを考えない。従って「手」と解するのは誤りと断じてよく、「舉」の下半分は「丰」である。
前漢末までの字形では、確かに「丰」になっている。「手」を部品とする、出所が如何わしい多数の字形が古文として比定されているが、何一つ証拠があるわけではない。ゆえに「舉」は「與」が上→下へと手渡すさまに対し、下→上へと手渡すさまを意味した。
「丰」の原義は豊かに実った作物で、それを神霊などに”奉じる”慣習は、古代から南朝までは残っていたらしい。それがかろうじて日本に伝わり、玉串として現存するのだが、本場中国では消滅した。匈奴の別種である鮮卑人の隋によって、南朝が征服されたからだ。
南朝最後の皇帝は、珍しいことに軟禁状態ではあったが隋によって生かされた。隋はよほど自信があったらしい。だが南朝に残った古代中華文明の多くが、永遠に失われた。「丰」もその一つで、隋唐帝国になると意味が分からなくなり、ついに「手」と書くに至った。
それが現行の「擧」(挙)の字である。なお定州本・古注は「舉」と記し〔丰〕ではない。
舉(定州竹簡論語/古注)





コメント