
處/処(ショ・5画)


史墻盤・西周中期/㝬鐘・西周晚期
初出:初出は西周中期の金文。
字形:”人の横姿”+「几」で、腰掛けに座った人の姿。原義は”そこに居る”。
音:カールグレン上古音はȶʰi̯o(上/去)。
用例:「漢語多功能字庫」によると、金文では原義で用いた。
学研漢和大字典
会意。処は「夂(あし)+几(だい)」。足を止めて床几(ショウギ)に腰を落ち着ける意を示す。處は、のち音符として虎の略体「虍」を添えた会意兼形声文字。居・据と同系。また、著(ひと所に止まる)や定着の着とも縁が近い。「ところ」は「所」とも書く。▽旧字「處」の草書体をひらがな「そ」として使うこともある。
語義
- {動詞}おる(をる)。ある場所に落ち着く。《対語》⇒出。《類義語》居。「処世=世に処る」「処女(家にいてまだ嫁にいかない娘)」「夫賢士之処世也、譬若錐之処苦中=夫(そ)れ賢士の世に処るや、譬(たと)へば錐(きり)の苦中(なうちゅう)に処るが若(ごと)し」〔史記・平原君〕
- {動詞}おく。しかるべきところにおく。「何以処我=何を以て我を処かん」〔礼記・檀弓下〕
- (ショス){動詞}あるべき所に落ち着ける。しまつする。「処理」「処置」。
- (ショス){動詞}しかるべく決める。「処刑=刑に処す」。
- {名詞}ところ。しかるべきところ。▽去声に読む。「到処(イタルトコロ)」「白雲生処有人家=白雲生ずる処人家有り」〔杜牧・山行〕
- {単位詞}場所を数える単位。▽去声に読む。「期山東為三処=山の東に三処と為らんと期す」〔史記・項羽〕
- 《日本語での特別な意味》ところ。「…したところが」という接続のことばに当てる。「候処(ソウロウトコロ)」。
字通
[会意]旧字は處に作り、虎+几(き)。虎形のものが几(腰かけ)にかけている形。〔説文〕十四上に処を正字とし、「止まるなり。夂(ち)(足)、几を得て止まるなり。夂几に從ふ」とし、重文として處を録するが、金文の字形は、すべて處に作る。虎は虎皮を蒙るもので、戲(戯)・劇がその形に従うように、神事的な所作で、軍戯のように軍事に際して行われた。金文の〔井人鐘(けいじんしよう)〕「疐(とど)まりて宗室に處(を)らん」、〔叔夷鎛(しゆくいはく)〕「禹の堵(と)(水土を治めた地)に處る」など、聖所に処る意に用いる。〔左伝、襄四年〕「民に寢廟有り、獸に茂草有り。各〻其の處る所有り」とは、霊の安んずるところ。所も〔叔夷鎛〕「桓武なる靈公の所に共(供)する又(あ)り」のように、もと廟所を意味する字であった。所は名詞、處は動詞的な語であったように思われる。
所(ショ・8画)
沮(ショ・8画)

耳卣・西周早期
初出は甲骨文。現在発掘されている金文は、「且」tsʰi̯ɔ(上)と区別されていない。カールグレン上古音はdzʰi̯o(上)またはtsi̯o(去)。同音は以下の通り。上声での「ソ」は慣用音、呉音は「ゾ」。去声では漢音で「ショ」、呉音で「ソ」。
| 字 | 音 | 訓 | 初出 | 声調 | 備考 |
| 咀 | ショ | 味はふ | 説文解字 | 上 | |
| 沮 | ショ | はばむ | 甲骨文 | 〃 |
| 字 | 音 | 訓 | 初出 | 声調 | 備考 |
| 且 | シャ | かつ | 甲骨文 | 平 | →語釈 |
| 蛆 | ショ | うじ | 不明 | 〃 | |
| 苴 | ショ | くつの中のしき草 | 甲骨文 | 平/上 | |
| 沮 | ショ | しめる | 甲骨文 | 去 |
漢語多功能字庫
(解字無し)
学研漢和大字典
会意兼形声。且(ショ)は、物を積み重ねたさまを描いた象形文字。沮は「水+(音符)且」で、水が重なってひかない湿地。また、阻(石や土を重ね積んで、行く手をはばむ)と同じに用いる。祖(世代の重なり)・助(力を重ねてやる→たすける)などと同系。「阻」に書き換えることがある。「阻・阻止・阻喪」。
語義
上
- {動詞}はばむ。さえぎって止め、じゃまをする。《同義語》⇒阻(ソ)。「沮止(ソシ)」「有臧倉者沮君=臧倉なる者有りて君を沮む」〔孟子・梁下〕
- {動詞}じゃまされて気持ちがくさる。くじける。《同義語》⇒阻。「意気沮喪(イキソソウ)(がっかりして元気を失う)」。
去/平
- {名詞}水がたまってひかない湿地。「沮洳(ソジョ)(湿地)」。
- {名詞}川の名。湖北省中部にあり長江に注ぐ。沮水(ショスイ)。▽平声に読む。
字通
[形声]声符は且(そ)。〔説文〕十一上に「水名」とするが、もと沮洳(そじよ)の地、すなわち低湿の地をいう。そのため交通が沮害されるので、沮止・沮敗のようにいい、勢いのそがれることを沮喪という。
書(ショ・10画)


甲骨文/頌簋・西周晚期
初出:初出は甲骨文。
字形:甲骨文の字形は”ふでを取る手”+「𠙵」”くち”で、言葉を書き記すさま。原義は”記す”。甲骨文を筆記するには筆刀という小刀を使うが、木札や布に記す場合は筆を用いた。今日春秋時代以前の木札や竹札、字を記した布が残っていないのは、全て腐り果てたため。紙は漢代にならないと発明されない。
戦国時代の金文から「晝」(昼)字のように記される様になった。論語語釈「昼」を参照。
音:カールグレン上古音はɕi̯o(平)。同音は論語語釈「黍」を参照。
用例:「漢語多功能字庫」によると、金文では文書を意味し(頌簋・西周末期)、また人名に用いた(欒書缶・春秋)。
備考:論語では『書経』、別名『尚書』のこと。歴史書の一種で、孔子時代までの為政者の宣言を集めた書。現在では失われており、後世の創作のみ伝わる。
学研漢和大字典
形声文字で、「聿(ふで)+(音符)者」で、ひと所に定着させる意を含む。筆で字をかきつけて、紙や木簡に定着させること。類義語の写は、Aの場所にかかれたものをBの場所にうつすこと。つまりかきうつす意、という。
語義
- (ショス){動詞}かく。かきつける。《類義語》著・写。「書写」「子張書諸紳=子張諸を紳に書す」〔論語・衛霊公〕
- {名詞}ふみ。書物。またはかきしるしたもの。「書籍」「何必読書=何ぞ必ずしも書を読まん」〔論語・先進〕
- {名詞}ふみ。手紙。「書信」「家書」「叔向使詒子産書=叔向子産に書を詒らしむ」〔春秋左氏伝・昭六〕
- {名詞}意見や命令をかきつけた文書。「上書(意見書を奉る)」「詔書」。
- {名詞}文字。または文字のかき方。字をかく術。「六書(リクショ)(漢字の六種の造字法)」「書法」。
- {名詞}文字のスタイル。▽篆書(テンショ)・隷書(レイショ)・楷書(カイショ)・行書(ギョウショ)・草書(ソウショ)など。
- {名詞}「書経」のこと。上古の歴史や皇帝の命令を載せた書物。「詩書礼楽」「尽信書、則不如無書=尽く書を信ずれば、則ち書無きに如かず」〔孟子・尽下〕
字通
[会意]聿(いつ)+者。〔説文〕三下に「箸(あら)はすなり」と書・箸の畳韻を以て訓し、者(しや)声とする。聿は筆、者が書そのものに外ならぬ形であるから、会意字である。者は遮蔽されている曰(えつ)。曰は呪符を収めた器。曰の上は、小枝を交え、土をかけた形で、曰を土中に埋める意。古代の聚落には、おおむね馬蹄形にお土居を作って守ったが、そのお土居中に書をおいて呪禁とした。そのお土居を堵(と)(かき)といい、その呪禁としてしるしたものを書という。のち、ひろく書冊・文字をいう。
恕(ショ・10画)

□𧊒壺・戦国末期晉
初出:初出は戦国末期の金文。
字形:「如」”…と同様の”+「心」。戦国時代の竹簡では、「上海博物館蔵戦国楚竹簡」競建06の「㣽」、同・平王問1の「𦬑」(ただしくさかんむりではなく卝)、「郭店楚簡」性自38の「𫌳」の三例が「恕」と釈文されている。
音:「ジョ」は慣用音。カールグレン上古音はɕi̯o(去)。同音は論語語釈「黍」を参照。それらに”思いやる”の語は無い。
用例:「漢語多功能字庫」によると、戦国の金文・竹簡では、みな「怒」の意で用いる。”思いやる”の語義は、文献時代にならないと現れない。
論語時代の置換候補:結論として存在しない。
類語「如」はȵi̯o(平)で、音素の共通率は66.7%。ただし「如」に”思いやる”の語釈は『大漢和辞典』に無い。
| 恕 | ɕ | i̯ | o |
| 如 | ȵ | i̯ | o |


「如」(甲骨文)・「恕」(古文)
『字通』では、「心+如」とし、如は巫女がお祈りしてエクスタシー状態になり、神意をうかがい、はかる意とする。それゆえ恕は、他の心意をうかがいはかることという。

しかし『説文解字』に載せる古文の形は「心+如」ではなく、「心+女」で、古文の時代には辞書に見られるような意味でなかった。


「妾子𧊒壺」戦国末期・「荊門郭店楚墓竹簡‧語叢2.26」戦国後期
『荀子』は孔子の言葉として記すというウソを行いつつも、”他人を自分と対等に扱う”・”お互い様”の意で用いている。
戦国末期に”お互い様”を示す文字=言葉として表れた「恕」を、”相手を思いやる”という言葉に用い始めたのは、おそらく前漢の儒者である。詳細は論語における恕を参照。
学研漢和大字典
会意兼形声。如は、汝(ジョ)(自分とペアをなす相手)と同系のことば。自分と同じような対者という意味を含む。恕は「心+(音符)如(ジョ)」で、相手を自分と同じように見る心のこと。類義語に許。
語義
- {動詞・名詞}自分を思うのと同じように相手を思いやる。思いやり。「其恕乎、己所不欲勿施於人=其れ恕か、己の欲せざる所は人に施すこと勿かれ」〔論語・衛霊公〕
- {動詞}ゆるす。自分に引き比べてみて、他人を寛大に扱う。また、同情して相手をとがめずにおく。「寛恕(カンジョ)」「宥恕(ユウジョ)」。
字通
[形声]声符は如(じょ)。〔説文〕十下に「仁なり」とし、如声とする。如は女巫がお祈りしてエクスタシーの状態となり、神意をうかがい、はかる意。他の心意をうかがいはかることを、恕という。〔論語、里仁〕に「夫子(ふうし)の道は忠恕のみ」とあり、それが仁への道とされた。
大漢和辞典
庶(ショ・11画)


合10399/邾公華鐘・春秋末期
初出:初出は甲骨文。
字形:甲骨文・金文の字形は「𤇈」で「石」+「火」。原義は明らかでない。
音:カールグレン上古音はȶiaɡ(去)。
用例:甲骨文の用例は数が少なく、欠損も激しいので、語義を確定しがたい。
西周早期「宜𥎦𣪕」(集成4320)に「易宜庶人六百又□六夫」とあり、”多い”・”もろもろの”と解せる。
春秋末期「九里墩鼓座」(集成429)に「余以共旒示□帝(嫡)庶子」とあり、”めかけばらの”と解せる。
このほか西周から春秋にかけて人名に用いたが、明らかに”庶民”を意味する用例は、戦国時代にならないと確認できない。また論語先進篇18「其庶乎」は”それは近いだろうか”と解するのが通説だが、”近い”の用例は文献時代まで時代が下り、『孟子』が初出。
学研漢和大字典
会意。この字の下部は動物の頭(廿印)のあぶらを燃やすさまで、光の字の古文。庶はそれに广(いえ)を添えたもので、家の中で火を集め燃やすこと。さらにまた、諸(これ)と同様に、近称の指示詞にあて「これこそは」と強く指示して、「ぜひこれだけは」の意をあらわす副詞に転用された。煮(にる)・暑(あつい)と同系のことば。また、集める意を含み、仙(セキ)(集める)・諸(もろもろ)とともに、多くの物が集まった意に用いられる。貯(チョ)(多く集めてたくわえる)と同系。類義語に民。
語義
- {名詞・形容詞}もろもろ。多くの物。数多くの。《類義語》諸(ショ)。「庶物(多くの物)」「臣庶(多くの家来)」。
- {名詞}もろびと。大衆。「庶無罪悔=庶に罪悔無し」〔詩経・大雅・生民〕
- {形容詞}おおい(おほし)。物が豊かで多い。「富庶(フウショ)」「庶矣哉=庶き矣哉」〔論語・子路〕
- 「庶子(ショシ)」とは、嫡子(チャクシ)・適子(テキシ)に対して、めかけの子のこと。▽正妻の子は限られているが、めかけの子は多いことから。
- {形容詞}ちかい(ちかし)。→語法「②」。
- {動詞}こいねがう(こひねがふ)。ぜひこれだけはと、望む。「庶幾(コイネガウ)」。
- {副詞}こいねがわくは(こひねがはくは)。→語法「①」
語法
①「こいねがわくは~せん」とよみ、
- 「どうか~したい」と訳す。自らの願望の意を示す。「庶竭駑鈍攘除姦凶=庶(こひねが)はくは駑鈍(どどん)を竭(けつ)して姦凶を攘除(じゃうじょ)せんことを」〈どうか、にぶくて劣った才能をふりしぼり、悪者をはらいのけたい〉〔蜀志・諸葛亮〕▽「庶幾」も「こいねがわくは~せん」とよみ、意味・用法ともに同じ。「庶幾息兵革=庶幾(こひねが)はくは兵革を息(や)めんことを」〈戦争をやめたいと願った〉〔史記・秦始皇〕
- 「どうか~してほしい」と訳す。相手への願望の意を示す。「庶可已矣=庶(こひねが)はくは已(や)む可し」〈どうかおやめになってください〉〔国語・魯〕▽「庶幾」も、「こいねがわくは~せん」とよみ、意味・用法ともに同じ。「王庶幾改之=王庶幾(こひねが)はくはこれを改めよ」〈王よ、どうか考えを改めくだされ〉〔孟子・公下〕
②「ちかし」とよみ、「おおかた」「ほとんど」と訳す。状況・程度に接近する意を示す。「回也其庶乎=回やそれ庶(ちか)きか」〈回(顔淵)はまあ(理想に)近いね〉〔論語・先進〕
字通
[会意]广(げん)+廿(じゆう)+火。〔説文〕九下に「屋下の衆なり。广炗に從ふ。炗は古文の光字なり」とし、徐鉉は「光も亦た衆盛なり」と補説している。衆庶の意とするものである。广は廚房(ちゆうぼう)、廿は鍋など烹炊(ほうすい)の器の形。鍋の下に火を加え、烹炊を原義とする字。煮はその形声字である。者(者)は堵中に呪符として埋めた書であるから、これは煮るべきものではない。また庶は煮る意の字であるが、それを諸の意に用い、庶人・衆庶のようにいう。〔儀礼〕に正饌(せいせん)に対して盛り合わせたものを庶羞(しよしゆう)といい、庶はもと炊き合わせたものをいう。それで庶多の意となり、衆庶の意となり、嫡庶の意となる。庶幾は、それに近い状態をねがうことをいう。
暑/暑(ショ・12画)

包2.185・戦国
初出:初出は楚系戦国文字。
字形:「日」+音符「者」(者)。「者」ȶi̯ɔ(上)の同音に「赭」”真っ赤になる”があり、太陽が真っ赤に燃えさかって暑いさま。
音:カールグレン上古音はɕi̯o(上)。同音は論語語釈「黍」を参照。
用例:戦国中末期「郭店楚簡」緇衣9に「〔夏〕日□(暑)雨少」とあり、”暑い”と解せる。
論語時代の置換候補:『大漢和辞典』の同音同訓に「炙」があるが、初出は戦国文字。音もȶi̯ăɡ(去)またはȶi̯ăk(入)で音通とは言いがたい。上古音の同音に語義を共有する漢字は無い。
学研漢和大字典
会意兼形声。者(=者)は、こんろで柴を燃やすさま。火力を集中する意を含み鐚(=煮。にる)の原字。鏃は「日+(音符)者」で、日光のあつさが集中すること。炙(シャ)(あぶる)・赭(シャ)(まっかに焼ける)などと同系。類義語の熱は、じわじわとねつを加えて柔らげること。暖は、ぬくぬくとあたたかいこと。異字同訓に熱い「熱い湯」 厚い「厚い壁で隔てる。支持者の層が厚い。手厚いもてなし」。旧字「暑」は人名漢字として使える。
語義
- {形容詞・名詞}あつい(あつし)。あつさ。日光が集中して、うだるようにあつい。また、夏のあつさ。《対語》⇒寒・涼。「残暑」「暑熱」「寒往則暑来=寒往けば則ち暑来たる」〔易経・壓辞下〕
字通
[形声]声符は者(者)(しや)。〔説文〕七上に「熱きなり」とあり、暑熱をいう。火を用いるものは庶。者は堵中の呪符であるが、庶・者の声近く、暑は者声をとる。者と庶と、声符として互易する例が多い。
黍(ショ・12画)

仲𠭯父盤・西周
初出は甲骨文。カールグレン上古音はɕi̯o(上)。同音は下記の通り。
| 字 | 音 | 訓 | 初出 | 声調 | 備考 |
| 書 | ショ | かく | 西周中期金文 | 平 | →語釈 |
| 舒 | 〃 | のびる | 戦国末期金文 | 〃 | |
| 紓 | 〃 | ゆるい | 説文解字 | 〃 | |
| 暑 | 〃 | あつい | 楚系戦国文字 | 上 | →語釈 |
| 鼠 | 〃 | ねずみ | 甲骨文 | 〃 | |
| 黍 | 〃 | きび | 甲骨文 | 〃 | |
| 癙 | 〃 | 気やみ | 不明 | 〃 | |
| 恕 | 〃 | おもひやり | 戦国末期金文 | 〃 | →語釈 |
漢語多功能字庫
甲骨文「黍」,初義是一種農作物。其字主要有三種構形︰或單以一株黍之象形表示,或加從「水」,又或在黍之象形的線條間加點或圈(一說象水點,一說象黍的穀粒)。三者的共同特徵在於黍的穗子都是散垂的。
甲骨文の「黍」は、はじめは農作物の一種を意味した。この字には三種類の字形がある。あるいはキビが一株植わった象形で、あるいは「水」の字形をつけ加える。あるいはキビの象形として、線の間に点を加えたものがある。(一説には水滴を意味し、一説には穀粒を意味する)。三者三種類とも共通して、キビの穂の垂れた様子を描く。
学研漢和大字典
会意。「禾(いね科の作物)+水または雨」。水気を吸収して育つ作物をあらわす。一説に、暑(ショ)と同系で、暑いさなかに育つからともいう。庶(ショ)(多い)・貯(チョ)(たっぷりたくわえる)と同系。
「きび」は「稷」とも書く。
語義
- {名詞}きび。穀物の名。実は赤、白、黄、黒など数種ある。▽北中国では主食にし、飯・かゆをつくり、酒をかもすのにも用いた。
ま{単位詞}きびの粒は大きさ・目方が一定なので、度量衡の単位に用い、きび一粒(一黍)の直径を一分、きび百粒(百黍)の重さを一銖(シュ)、きび二千四百粒(二千四百黍)の体積を一合とした。
字通
[会意]禾(か)+水。〔説文〕七上に「禾の屬にして黏(ねば)りある者なり。大暑を以て種(う)う。故に之れを黍と謂ふ。禾に從ひ、雨(う)の省聲なり」とするが、卜文は禾と水とに従う。黍酒を作る意であろう。卜辞に「黍は年(みのり)を受(さづ)けられんか」と卜する例が多い。祭祀には黍稷(しよしよく)や黍酒を多く用いた。〔書、君陳〕「黍稷馨(かんば)しきに非ず。明德惟(こ)れ馨し」の語がある。祭器の簋は、黍稷を盛(い)れるものであった。
雎(ショ・13画)

馬王堆帛書縦横家書4・前漢隷書
初出:初出は前漢の隷書。
字形:「且」(音符)+「鳥」で、ミサゴを意味するとされる。上掲の隷書はおそらく、戦国末期の縦横家范雎の名を記したもの。
音:カールグレン上古音はtsʰi̯o(平)で、同音は「且」を部品に持つ漢字群。「𪂓」は異体字。
用例:論語では、『詩経』の題「関雎」として登場する。下記『学研漢和大字典』のいう「雌雄の別が正しいとされる。夫婦間に正しい礼儀があることにたとえる」というラノベがあるからには、恐らく詩経のこの歌も、後世の儒者のでっち上げだろう。
論語時代の置換候補:結論として存在しない。殷周の金文では、部品の「且」は「祖」と釈文されている。そうで無い事例は、地名または人名と思われる。さらにその例外は、欠損が激しく解読できない。
備考:「漢語多功能字庫」には見るべき情報がない。
学研漢和大字典
会意兼形声。「隹(とり)+(音符)且(ショ)」。
語義
- 「雎鳩(ショキュウ)」とは、みさご。水辺にすむ鳥。雌雄の別が正しいとされる。▽夫婦間に正しい礼儀があることにたとえる。「関関雎鳩、在河之洲=関関たる雎鳩は、河の洲に在り」〔詩経・周南・関雎〕
字通
[形声]声符は且(しよ)。〔詩、周南、関雎〕「關關たる雎鳩」の〔伝〕に「王雎なり」とあって、みさごと解されているが、みさごは海辺の巌島に住む猛禽で、房中歌としての〔関雎〕の発想としてふさわしいものではない。雎鳩は、おそらくかもめのような川鳥であろう。この詩は原詩を改編したもので、原詩は祭事詩、雎鳩は鳥形霊としてその発想に用いられたものであろう。「參差(しんし)たる荇菜」は、原詩においては神前にそなえる水草であったと考えられる。
諸(ショ・15画)


兮甲盤・西周末期/秦系戦国文字・陶彙5.389
初出:初出は西周末期の金文。論語の時代では、まだ「者」と「諸」は分化していない。現行字体の初出は秦系戦国文字。
字形:「者」の金文の字形は「木」”植物”+「水」+「口」で、”この植物に水をやれ”と言うことだろう。
音:カールグレン上古音はȶi̯o(平)。平声で麻-章の音は不明。
用例:「先秦甲金文簡牘詞彙資料庫」では、春秋末期までの用例をほぼ「諸侯」の「諸」、または人名としている。
西周中期の「九年衛鼎」(殷周金文集成02831)に「衛小子逆者」とあるのを「衛小子者を逆う」と読み得、”これ”の語義を確認できる。
春秋末期の「戉王矛」(集成11512)に「睗旨(稽)者(諸)於戉(越)王」とあり、「これを越王より稽(人名?)にたまう」と読め、”これを…に”の語義を確認できる。
「漢語多功能字庫」では、金文では”さまざまな”の意で用いられる他、”これ”・”…は”の意で用いられるという。論語語釈「者」を参照。
戦国末期の「秦詔量」には「諸侯」とあり、”もろもろ”を意味した。
備考:”これを…に”の語義は、日中の漢学業界で「之於」(シヲ:ȶi̯əɡ(平)+ʔo(平))または「之乎」(ȶi̯əɡ(平)+ɡʰo(平))→「諸」ȶi̯o(平)と音が通じてこの意味を獲得したとされる。
訳者の知る限り、そう言いだしたのは清の嘉慶年間に第三位で進士に通った王引之の著『経伝釈詞』で、「諸,之乎也。…此皆之乎二字之合聲。」と「諸」条にいい、『大漢和辞典』は補巻に「諸,之於也。」とあると引く。つまりずいぶん新しい説で、しかもなぜそうなるかの説明は一切ない。
加えて清朝考証学は不当に高く評価されており(論語顔淵篇21余話「試験秀才を当てにしない」)、清儒は根拠の無い出任せを記す場合がある。現伝の論語は、ほとんどが後漢までに成立しているから、清儒の言い分を当てはめて読まねばならない理由は無い。
古いから、儒者だから、進士だから、中国人だからというだけで、思考停止してそれらの言うがままになる限り、論語を万年眺めても解読できない。下らない権威主義とはスッパリ手を切らないと、現代の論語読者は儒者の狙い通りの、頭のおかしな喰われ者に成り下がると覚悟していただきたい。
学研漢和大字典
会意兼形声文字で、者(シャ)(=者)は、こんろに薪をいっぱいつめこんで火気を充満させているさまを描いた象形文字で、その原義は暑(=暑)・煮(=煮)などにあらわれている。諸は「言+〔音符〕者」で、ひと所に多くのものが集まること。
転じて、多くの、さまざまな、の意を示す。▽者・諸の音を借りて「これ」という近称の指示詞をあらわすのは当て字。都(=都。人が多く集まるみやこ→すべての)に近く、また、庶民(おおぜいの人々)の庶(ショ)とほとんど同じ。
語義
- {形容詞}もろもろ。多くの。また、さまざまな。《類義語》庶。「諸人」「諸大夫皆曰不可、勿聴=諸大夫皆不可なりと曰ふも、聴く勿かれ」〔孟子・梁下〕
- {指示詞}これ。→語法「①②」。
- {助辞}語調をととのえることば。「日居月諸=日や居月や諸」〔詩経・邶風・日月〕
語法
①「これ」とよみ、「これを」「これに」と訳す。近称の指示詞。▽「之於=シオ」の二字をあわせて一字にしたもの。「之於」と意味・用法ともに同じ。「君子求諸己、小人求諸人=君子はこれを己に求め、小人はこれを人に求む」〈君子はこれ(失敗の原因)を自分に求めるが、小人は他人に求める〉〔論語・衛霊公〕
②「これ~や」とよみ、「どうして~か(いやそのようなことはない)」と訳す。反語の意を示す。「之乎」の二字をあわせて一字にしたもの。「之乎」と意味・用法ともに同じ。「一言而可以興邦、有諸=一言にしてもって邦(くに)を興す可きこと、これ有りや」〈ひとことで国を盛んにできるということがあるだろうか〉〔論語・子路〕
③「~其諸…乎(与)」は、「~それこれ…や」とよみ、「~は…だろうか(いやそうではない)」「~はなんと…だなあ」と訳す。▽「~其…乎=~それ…や」を強調したいい方。「夫子之求之也、其諸異乎人之求之与=夫子のこれを求むるや、それこれ人のこれを求むるに異なるや」〈先生の求めかたといえば、そう、他人の求めかたとは違うらしいね〉〔論語・学而〕
字通
声符は者(者)。〔説文〕三上「辯なり」とあり、〔爾雅、釈訓〕「諸諸・便便は辯なり」との訓をとる。「あまねし」の意である。〔段注〕に「辯つなり」の誤りとし、分別より諸多の意となったという。金文に「者侯」「者士」など、者を諸の意に用いる。者は、邑落をめぐらした堵仲に、呪禁として埋めた書をいう。その祝禱の辞が種々の呪禁に及ぶので、それを諸というのであろう。
訓義
もろもろ、多くの辞、多い。之と通じ、これ、之於・之乎と通じ、これを~に、これ~か(や)の意に合字として用いる。語末に付けて、形容の語を作る。忽諸。
女(ジョ・3画)

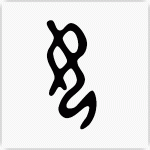
甲骨文/彭女甗・西周早期
初出:初出は甲骨文。
字形:ひざまずいた女の姿で、原義は”女”。
音:カールグレン上古音はni̯o(上/去)。
用例:西周早期「尊」(集成5979)に「從王女南」とあり、”ゆく”と解せる。
春秋末期「陵公戈」(集成11358)に「獻鼎之歲。羕陵公君之褱所造。冶己女。」とあり、最後の三字は「己を冶かすがごとし」とよめ「然」”…のようなさま”と解せなくも無い。
戦国の金文「子禾子釜」(集成10374)に「而厶□發退女關人」とあるのは、「して□をもって関人(罪人)がごとくはなちしりぞく」と読め、”~のようだ”と解せる。
「漢語多功能字庫」によると、甲骨文では原義のほか”母”、「毋」として否定辞、「每」として”悔やむ”、地名に用いられた。金文では原義(師㝨簋・西周末期)、”母”(司母戊方鼎・殷代後期)、二人称(夨令方彝・西周早期)に用いられた。「如」として”~のようだ”の語義は、戦国時代まで時代が下る(中山王鼎・戦国末期)。
備考:さんずいのついた「汝」(ȵi̯o。汝の字も甲骨文から出土がある)と同じく”お前”を意味することがある。唐石経では、もれなく汝を女と書いている。
学研漢和大字典
象形文字で、なよなよとしたからだつきの女性を描いたもの。弱(ジャク)・(ニャク)・若(ジャク)・(ニャク)(柔らかい)・娘(ジョウ)・(ニョウ)と同系のことば、という。
語義
- {名詞}おんな(をんな)。め。《対語》⇒男。「士与女、方秉拂兮=士と女と、方し拂を秉る」〔詩経・鄭風・溌粘〕
- ま{名詞}むすめ。ある人のおんなの子。「楊家有女初長成=楊家に女(むすめ)有り初めて長成す」〔白居易・長恨歌〕
- {名詞}娘や嫁が親に対して自分をさしていうことば。「女行無偏斜=女の行ひに偏斜無し」〔古楽府・焦仲卿妻〕
- {代名詞}なんじ(なんぢ)。おまえ。第二人称。《同義語》⇒汝。《類義語》爾。「予及女偕亡=予と女及偕に亡びん」〔孟子・梁上〕
- {名詞}二十八宿の一つ。規準星は今のみずがめ座に含まれる。うるき。
- {動詞}めあわす(めあはす)。嫁にやる。とつがせる。▽去声に読む。《類義語》妻。「女以驪姫=女すに驪姫を以てす」〔春秋左氏伝・荘二八〕
字通
[象形]女子が跪(ひざまず)いて坐する形。〔説文〕十二下に「婦人なり。象形」とあり、手を前に交え、裾をおさえるように跪く形。動詞として妻とすること、また代名詞として二人称に用いる。代名詞には、のち汝を用いる。
汝(ジョ・6画)

(甲骨文)
初出:初出は甲骨文。
字形は〔氵〕+〔女〕で、原義は氏族名だったと思われる。
音:カールグレン上古音はȵi̯o(上)。
用例:「甲骨文合集」14026に「貞汝娩不其嘉」とあり、「汝」氏族出身の王の妾を意味すると思われる。この「汝」は鏡文字になっている。
西周早期「中甗」(集成949)に「王令曰:余令女(汝)史(使)小大邦」とあり、”お前(ら)”と解せる。
上古の時代、「女」「汝」はほぼ区別されず使われたが、「汝」はなぜか金文では見られない。再出は戦国の竹簡(「上海博物館蔵戦国楚竹簡」彭祖2など)になる。
「漢語多功能字庫」によると、原義は人名で、金文では二人称では「女」を用いた。そのほか地名や川の名に用いられた。
論語の場合、定州竹簡論語、唐石経では、もれなく汝を女(ni̯o)と書いている。
学研漢和大字典
形声。「水+(音符)女」で、もと、汝水という川の名。昔は二人称代名詞をniag・niakなどといったので、その音に近い発音をもつ女(おんな)nɪag・汝niag・若(わかい)niakなどの字を当ててあらわした。漢字の仮借(当て字)の用法の一つである。▽「書経」は汝を用い、「論語」は多く女を用いている。「なんじ」は「爾」とも書く。
語義
- {代名詞}なんじ(なんぢ)。きみ。おまえ。おまえたち。《対語》⇒吾(われ)・我。《類義語》女(ナンジ)・若(ナンジ)・爾(ナンジ)。「汝我之間(ジョガノアイダ)(きみ、ぼくというほどの親しいつきあい)」「汝平水土=汝水土を平らかにせよ」〔書経・舜典〕
- {名詞}川の名。河南省の嵩(スウ)県から発して東流し、淮水(ワイスイ)に注ぐ。汝水(ジョスイ)。▽臨汝(リンジョ)・汝陽(ジョヨウ)などはその沿岸の地名。
字通
[形声]声符は女(じょ)。女は汝の初文。〔説文〕十一上に水の名とする。〔詩、周南、汝墳〕にその名がみえる。二人称として、〔詩、大雅、蕩〕「咨(ああ)、汝殷商」のように用いるが、金文にはすべて女を用いる。
如(ジョ・6画)
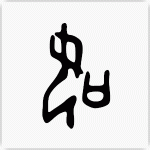

甲骨文/十年鈹・戦国末期
初出:初出は甲骨文。
字形は「女」+「口」。甲骨文の字形には、上下や左右に「口」+「女」と記すものもあって一定しない。
音:カールグレン上古音はȵi̯o(平)。去声の音は不明。
用例:「漢語多功能字庫」は甲骨文の用例「王曰丁不如」を挙げて、原義を”ゆく”だとする。
春秋末期までの金文での例は、全て「如」と釈文できる「女」字。
西周早期の「尊」(『殷周金文集成』05979)に「從王女南」とあるのは、”ゆく”の意と思われる。
西周中期の「師艅鼎」に「王女上𥎦。師俞從王。」とあるのも、”ゆく”の意と思われる。
「女」字の「如」として”~のようだ”の語義は、戦国時代まで時代が下る。詳細は論語語釈「女」を参照。
備考:『学研漢和大字典』の語釈「もしくは」は、論語先進篇26を偽作した前漢の儒者が、偽作を古くさく見せるために、「與」zi̯o(上)と書くべき所に「如」ȵi̯o(平)と記したハッタリで、こんな珍妙な語義は、同時代以降の猿真似を除けば、やはり前漢儒者による『儀礼』の「公如大夫」・『書経』の「如五器」ぐらいしかない。
『殷周金文集成』所収の戦国末期「十年鈹」に「十年。得工嗇夫𡉣相女(=如)。左得工工帀韓段。冶𪱛朝執齊」とある。
学研漢和大字典
会意兼形声文字で、「口+〔音符〕女」。もと、しなやかにいう、柔和に従うの意。ただし、一般には、若とともに、近くもなく遠くもない物をさす指示詞に当てる。
「A是B」とは、AはとりもなおさずBだの意で、近称の是を用い、「A如B(AはほぼBに同じ、似ている)」という不即不離の意を示すには中称の如を用いる。仮定の条件を指示する「如(モシ)」も、現場にないものをさす働きの一用法である。
語義
- {指示詞・動詞}ごとし。→語法「①-(1)」。
- {動詞}しく。…と同じぐらいだ。…に匹敵する。▽「しく」とは奈良時代の日本語で「及ぶ、届く」の意。「不如(シカズ)(…に及ばない)」「莫如(シクナシ)・(シクハナシ)(それに及ぶものはない)」→語法「②③④」。
- {動詞}ごとくする(ごとくす)。…のようにする。「如約=約のごとくせん」〔史記・高祖〕
- {動詞}ゆく。いく。《類義語》之(ユク)。「公、将如棠、観魚者=公、まさに棠に如き、魚する者を観んとす」〔春秋左氏伝・隠五〕
- {接続詞}もし。→語法「⑤」。
- {接続詞}もしくは。→語法「⑥」。
- {接続詞}ごときは。→語法「①-(2)」。
- {動詞}いかん。いかんせん。→語法「⑦⑧」。
- {助辞}状態をあらわす形容詞につくことば。《類義語》…然(ゼン)。「申申如也」〔論語・述而〕
語法
①
- 「~のごとし」とよみ、「~のようだ」と訳す。比較して判断する意を示す。《同義語》若。「其仁如天、其知如神=その仁は天の如(ごと)く、その知は神の如し」〈その慈愛心(の大きいこと)は、天のようであり、その智恵(の秀いでたこと)は、神のようである〉〔史記・五帝〕。「富貴不帰故郷、如衣繍夜行=富貴にして故郷に帰らざるは、繍を衣(き)て夜行くが如(ごと)し」〈富貴の身となったのに故郷に帰らぬというのでは、美しい錦を着て、夜歩くようなものだ〉〔史記・項羽〕
- 「~のごときは」とよみ、「~の場合は」「~に関しては」と訳す。話題の程度を進める、また話題を転換する意を示す。「如其礼楽、以俟君子=その礼楽の如(ごと)きは、もって君子に俟(ま)たん」〈礼楽などのことは、それは君子にたのみます〉〔論語・先進〕
②「しく」とよみ、「同等である」と訳す。比較して優劣を判定する意を示す。「為之両相如=これを為るに両(ふた)つながらあひ如(し)く」〈二つ作るのに両方とも似たようにする〉〔墨子・備城門〕
③
- 「~不如…」は、「~は…にしかず」とよみ、「~は…に及ばない」「~より…の方がよい」と訳す。比較して優劣を判定する意を示す。「百聞不如一見=百聞は一見に如(し)かず」〈百回聞くことは、一回見ることには及ばない〉〔漢書・趙充国〕
- 「~未如…」は、「~いまだ…にしかず」とよみ、「~はいまだ…に及ばない」と訳す。比較して優劣を判定する意を示す。「今学曾未如肬贅、則具然欲為人師=今の学は曾(すなは)ち未だ肬贅(いうぜい)にも如(し)かざるに、則(すなは)ち具然(ぐぜん)として人の師為らんことを欲す」〈今の学者ときたら、まだいぼやこぶほどの知識も持っていないのに、一人前の顔をして他人の師になろうと思っている〉〔荀子・宥坐〕
④「~莫如…」は、「~は…にしくはなし」とよみ、「~に関しては…に及ぶものはない(=…が最もよい)」と訳す。比較して優劣を判定する意を示す。「知臣莫如君=臣を知るは君に如(し)くは莫(な)し」〈臣下を知ること主君に優るものはない〉〔史記・斉太公〕
⑤
- 「もし~せば」とよみ、「もし~ならば」と訳す。順接の仮定条件の意を示す。「王如知此、則無望民之多於隣国也=王如(も)しこれを知らば、則(すなは)ち民の隣国より多からんことを望む無(な)かれ」〈王がそのことをお分かりでしたら、人民が隣国より多くなるのを望んではなりません〉〔孟子・梁上〕
- 「もし~ども」とよみ、「もし~としても」と訳す。逆接の仮定条件の意を示す。「如有周公之才之美、使驕且吝、其余不足観也已=如(も)し周公の才の美有りとも、驕(おご)りかつ吝(やぶさ)かなら使めば、その余は観るに足らざる」〈たとえ周公ほどの立派な才能があったとしても、傲慢で物惜しみするようなら、そのほかは目をとめるねうちもない〉〔論語・泰伯〕
⑥「~如…」は、「~もしくは…」とよみ、「~か…かのどちらか」と訳す。選択の意を示す。《類義語》或(アルイハ)。「安見方六七十、如五六十、而非邦也者=安(いづく)んぞ方六七十、如(も)しくは五六十にして、邦(くに)に非(あら)ざる者を見ん」〈どうして六七十里か五六十里四方で国でないものがあるだろうか〉〔論語・先進〕
⑦「何如」は、
- 「いかん」とよみ、「どうであるか」と訳す。内容・状態・真偽を問う疑問の意を示す。《同義語》何若。「子貢問曰、賜也何如=子貢問ひて曰く、賜や何如(いかん)」〈子貢がお尋ねして、賜(この私)などはどうでしょうかと言う〉〔論語・公冶長〕
- 「いかんせん」とよみ、「どうしたらよいか」と訳す。方法・処置を問う疑問・反語の意を示す。「鳳兮鳳兮何如徳之衰=鳳鳳徳の衰へたるを何如(いかん)せん」〈鳳(おおとり)よ、おまえの徳が衰えたことをどうしたらよいか〉〔荘子・人間世〕
- 「いかなる」とよみ、「どんな」と訳す。「斉王亦何如主也=斉王はまた何如(いか)なる主ぞ」〈斉王はいったいどういう君主かな〉〔韓非子・外儲説右下〕
⑧「如何~」は、
- 「~をいかん(せん)」とよみ、「~をどうするか」「どうしたらよいか」と訳す。方法・処置を問う疑問の意を示す。目的語がある場合は「如~何」と、その目的語を間にはさむ。《同義語》若何。「是則可憂也、憂之如何=これ則(すなは)ち憂ふ可きなり、これを憂へば如何(いかん)せん」〈これこそまことに憂うべきことなのである、これを憂えるならばどうすればよいのか〉〔孟子・離下〕
- 「いかんぞ~せん」「~をいかんせん」とよみ、「どうして~しようか(いやそうしない)」と訳す。原因・手段を問う疑問・反語の意を示す。「斯居三公位、如何令盗如此=斯三公の位に居りながら、如何(いかん)ぞ盗をしてかくの如(ごと)くなら令むる」〈(李)斯は宰相という最高の地位にありながら、どうして盗賊をこのように横行させたのか〉〔史記・李斯〕
字通

会意、「女+口」。女は巫女。口は祝詞を収めた𠙵器。巫女が祈祷文を前にして祈る形で、その手をかざして舞う形は「若」。〔説文〕十二下に「従い随うなり」とあり、〔段注〕に「随従するに必ず口を以てす。女に従う者は、女子は人に従う者なればなり」とするが、如・若に従う意があるのは、巫女によって示された神意に従うことをいう。〔爾雅、釈詁〕に「謀るなり」とは、神意に諮う意。〔郭璞注〕に茹と同声とし、茹る意。茹は若と同構の字。卜辞に「王は其れ如らんか」という例があり、巫によって神意を諮う意であろう。神意を受けて従うので、また従順の意となり、「如くす」と意となる。「如何」とは、神意を問うことをいう。字の用義は若と近く、形義に通ずるところがある。
訓義
- はかる、神にはかる、神意をとう。
- したがう、神意に従う、神意のままにする。
- ごとくする、ごとし、神意に合うようにする。
- しく、およぶ、神意に近づく、ゆく、いたる。
- 如何、いかん、神意は何かととう、いかんせん。
- 若と通じ、もし。形容語を作る、忽若~忽茹。



コメント