論語:原文・書き下し
原文(唐開成石経)
季文子三思而後行子聞之曰再斯可矣
校訂
諸本
- 論語集釋: 三國志吴書诸葛恪傳注同。 皇本、高麗本作「再思斯可矣」。
※「高麗本」は正平本の誤り。
東洋文庫蔵清家本
季文子三思而後行子聞之曰再思斯可矣
後漢熹平石経
(なし)
定州竹簡論語
季文子三思而後行。子聞之,曰:「再,斯可矣a。」100
- 再斯可矣、唐石経作「再思可矣」、皇本、高麗本作「再思斯可矣」。
※「高麗本」は正平本の誤り。
標点文
季文子三思而後行。子聞之曰、「再、斯可矣。」
復元白文(論語時代での表記)
















※論語の本章は、「行」の用法に疑問がある。
書き下し
季文子、三たび思ひ而後に行ふ。子之を聞きて曰く、再びせば、斯可しき矣。
論語:現代日本語訳
逐語訳

季文子は三度考えてから事を行った。先生がこれを聞いて言った。「二度で、その状況でいいのだ。」
意訳
かつて魯の家老季文子は、思いつきを三度考えてから実行した。

先生が言った。「二度考えりゃ充分だ。」
従来訳
季文子は何事も三たび考えてから行った。先師はそれをきいていわれた。――
「二度考えたら十分だ。」下村湖人『現代訳論語』
現代中国での解釈例
季文子遇事總要思考三次,然後才行動。孔子聽說後,說:「思考兩次就可以了。」
季文子は事あるごとに三度考えてから、その後でやっと行動した。孔子がその話を聞いて言った。「二度考えただけで、それでよいだろう。」
論語:語釈
季文子
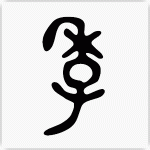
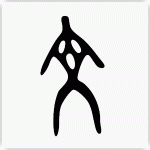
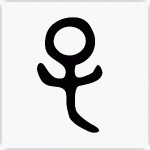
(金文)
BC651?-BC568。魯の大夫。姓は姫、氏は季(当主は尊称して季孫)、名は行父。魯の門閥三家老筆頭・季氏の当主。孔子と同時代の季氏当主・季桓子から三代前にあたる。軍事・外交を何度か担った(→wiki)。
『春秋左氏伝』によると、前々章の臧文仲の次代を担った家老であり、慎重さで知られたという。その在任中、東南の新興国・呉との接触があり、将来軍事的な脅威になると警告を残した。孔子誕生の頃の魯国公・襄公が四歳の幼さで即位すると、事実上の宰相として補佐した。
慎重さの例として、『春秋左氏伝』は文子が晋国に招かれた際、葬礼に出くわしたときの用意をしてから出掛けたら、果たして晋公が亡くなった、と記している(下掲)。
質素に暮らし、死去に当たって葬礼を簡素にせよと遺言し、「文」の諡を遺贈された。まずまずの名家老と言っていい。
文字的には論語語釈「季」・論語語釈「文」・論語語釈「子」を参照。
三(サン)


(甲骨文)
論語の本章では”三たび”。初出は甲骨文。原義は横棒を三本描いた指事文字で、もと「四」までは横棒で記された。「算木を三本並べた象形」とも解せるが、算木であるという証拠もない。詳細は論語語釈「三」を参照。
思(シ/サイ)


(金文)
論語の本章では、”考える”。初出は春秋末期の金文。画数が少なく基本的な動作を表す字だが、意外にも甲骨文には見えない。字形は「囟」”人間の頭”+「心」で、原義は頭で思うこと。金文では人名、戦国の竹簡では”派遣する”の用例がある。詳細は論語語釈「思」を参照。
而(ジ)


(甲骨文)
論語の本章では”そして”。初出は甲骨文。原義は”あごひげ”とされるが用例が確認できない。甲骨文から”~と”を意味し、金文になると、二人称や”そして”の意に用いた。英語のandに当たるが、「A而B」は、AとBが分かちがたく一体となっている事を意味し、単なる時間の前後や類似を意味しない。詳細は論語語釈「而」を参照。
後(コウ)


(甲骨文)
論語の本章では”あとでは”。「ゴ」は慣用音、呉音は「グ」。初出は甲骨文。その字形は彳を欠く「幺」”ひも”+「夂」”あし”。あしを縛られて歩み遅れるさま。原義は”おくれる”。甲骨文では原義に、春秋時代以前の金文では加えて”うしろ”を意味し、「後人」は”子孫”を意味した。また”終わる”を意味した。人名の用例もあるが年代不詳。詳細は論語語釈「後」を参照。
行(コウ)


(甲骨文)
論語の本章では”行う”。この語義は春秋時代では確認できない。初出は甲骨文。「ギョウ」は呉音。十字路を描いたもので、真ん中に「人」を加えると「道」の字になる。甲骨文や春秋時代の金文までは、”みち”・”ゆく”の語義で、”おこなう”の語義が見られるのは戦国末期から。詳細は論語語釈「行」を参照。
子(シ)


(甲骨文)
論語の本章では”(孔子)先生”。初出は甲骨文。字形は赤ん坊の象形。春秋時代では、貴族や知識人への敬称に用いた。季康子や孔子のように、大貴族や開祖級の知識人は「○子」と呼び、一般貴族や孔子の弟子などは「○子」と呼んだ。詳細は論語語釈「子」を参照。
聞(ブン)
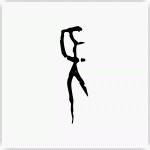
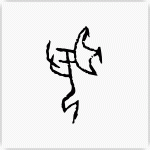
(甲骨文1・2)
論語の本章では”聞く”。初出は甲骨文。「モン」は呉音(遣隋使より前に日本に伝わった音)。甲骨文の字形は「耳」+「人」で、字形によっては座って冠をかぶった人が、耳に手を当てているものもある。原義は”聞く”。「耳」+「人」と見える字形も甲骨文にはある。詳細は論語語釈「聞」を参照。
「聞」の字形が「斧」または「耳」+「人」であるのに対し、「聴」は「𠙵」”くち”が伴うことから、「聞」は間接的に聞くこと、「聴」は直接的に聞くこと。
之(シ)


(甲骨文)
論語の本章では「これ」と読んで”それを”。初出は甲骨文。字形は”足”+「一」”地面”。足を止めたところ。原義は”これ”。”これ”という指示代名詞に用いるのは、音を借りた仮借文字だが、甲骨文から用例がある。”…の”の語義は、春秋早期の金文に用例がある。詳細は論語語釈「之」を参照。
曰(エツ)


(甲骨文)
論語で最も多用される、”言う”を意味する言葉。初出は甲骨文。原義は「𠙵」=「口」から声が出て来るさま。詳細は論語語釈「曰」を参照。
再(サイ)
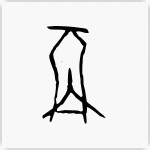
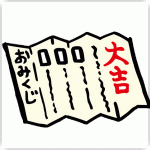
(甲骨文)
論語の本章では”二度”。初出は甲骨文。字形は「二」+「介」”甲骨板”+「人」”裂け目”で、二度甲骨を焼いて占うさま。原義は”再度”。戦国の金文では数字の”に”と原義に用いた。戦国の竹簡では加えて、「在」”存在する”または”察する”の意に用いた。
甲骨文の出土例では、都合のよい裂け目が出来るようあらかじめ細工したもの、都合のよい結果が出るまで何度も占いを繰り返したものがあることが知られている。詳細は論語語釈「再」を参照。
斯(シ)


(金文)
論語の本章では、”その状況”。二度考えた程度で、の意。初出は西周末期の金文。字形は「其」”籠に盛った供え物を祭壇に載せたさま”+「斤」”おの”で、文化的に厳かにしつらえられた神聖空間のさま。意味内容の無い語調を整える助字ではなく、ある状態や程度にある場面を指す。例えば論語子罕篇5にいう「斯文」とは、ちまちました個別の文化的成果物ではなく、風俗習慣を含めた中華文明全体を言う。詳細は論語語釈「斯」を参照。
可(カ)


(甲骨文)
論語の本章では、”それでどうにかいいだろう”、または”それだけでいいだろう”の意。積極的に”よい”と誉める意味はない。初出は甲骨文。字形は「口」+「屈曲したかぎ型」で、原義は”やっとものを言う”こと。甲骨文から”~できる”を表した。日本語の「よろし」にあたるが、可能”~できる”・勧誘”…のがよい”・当然”…すべきだ”・認定”…に値する”の語義もある。詳細は論語語釈「可」を参照。
矣(イ)


(金文)
論語の本章では、”~である”。初出は殷代末期の金文。字形は「𠙵」”人の頭”+「大」”人の歩く姿”。背を向けて立ち去ってゆく人の姿。原義はおそらく”…し終えた”。ここから完了・断定を意味しうる。詳細は論語語釈「矣」を参照。
論語:付記
検証
論語の本章は先秦の誰一人引用せず、再録もしていない。定州竹簡論語にあることから、前漢の前半には論語の一章として成立していたのだろうが、誰の興味も引かなかったらしい。ただし文字史的には論語の時代まで遡れるので、史実の孔子の言と断じてよい。
解説
中国人の数字の感覚では、「三」は多すぎない最小の数で、「三思」とは慎重ではあるがグズグズしていもしない、ということ。戦国末期に儒家のボスだった荀子は、「三思」について次のように書いているが、正直言ってぜんぜん面白くない。
孔子曰:「君子有三思而不可不思也:少而不學,長無能也;老而不教,死無思也;有而不施,窮無與也。是故君子少思長,則學;老思死,則教;有思窮,則施也。」


孔子「君子には三つの考慮すべき事があって、これをしないでは君子たり得ない。
一つ。若いときに勉強しない。すると年取っても何も出来ない。
二つ。年取って若い者に教えない。すると死んでも誰も悲しまない。
三つ。金があるのに施さない。すると貧乏しても誰も恵んでくれない。
だから君子は若いときから壮年以降の自分を思い、勉強に励む。死後を思い、教える。貧乏を思い、施すのだ。」(『荀子』法行8)
孔子は「学びて思わざらばすなわちくらし」(論語為政篇15)と後世の儒者に言わされたが、政治の場に出て行くについては、「君子は機敏に行動しろ」(論語里仁篇24)と言った。論語衛霊公篇17では、もっとはっきりと、行動のノロい者を罵倒している。

愚物が一日中わあわあと集まって相談し、まっとうなやり方は誰ひとり言わず、小細工ばかり自慢し合っている。どうしようもないな。
それを踏まえての「二度でよかろう」であって、慎重であることをおとしめたわけではない。自身は非常に饒舌な孔子が、弟子には寡黙を求めた論語の章はほぼ後世の創作で、くっちゃべっていてはいけないが、考え無しに行動するのもまたいけなかった(論語衛霊公篇12)。
論語の本章、新古の注は次の通り。
古注『論語義疏』
季文子三思而後行子聞之曰再思斯可矣註鄭𤣥曰季文子魯大夫季孫行父也文諡也文子忠而有賢行其舉事寡過不必及三思也疏季文子至可矣 云季文子三思而後行者言文子有賢行舉事必三過思之也云子聞之曰再思斯可矣者孔子美之言若如文子之賢不假三思唯再思此則可也斯此也有一通云言再過二思則可也人季彪曰君子之行謀其始思其中慮其終然後允合事機舉無遺算是以曾子三省其身南容三復白圭夫子稱其賢且聖人敬慎於教訓之體但當有重耳固無緣有减損之理也時人稱季孫名遇其實故孔子矯之言季孫行事多闕許其再思則可矣無緣乃至三思也此蓋矯抑之談耳非稱美之言也


本文「季文子三思而後行子聞之曰再思斯可矣」。
注釈。鄭玄「季文子は魯の大夫であり季孫行の父である。文は送り名である。季文子は忠義者で賢者であり、言動を起こす前に必ず三度考えたから間違いが少なかった。」
付け足し。季文子はまあまあの出来だと記された。季文子三思而後行とは、季文子には行動を起こす前に必ず考える賢さがあったことを言う。子聞之曰再思斯可矣とは、孔子は季文子のような行いを誉めはしたが、賢者ゆえに三度も考える必要は無く二度で十分だと言ったのである。一説に、間違いを二度仕出かしてその結果二度考えれば良いとも言う。
季彪「君子の行動とは、先によく考え、行動中も考え、終えてからも考える。そうすれば時宜にもかなうし思い残すことも無い。だから曽子は日にその身を三省し、南容は玉磨きの歌を三度歌って先生に誉められた。また聖人は教えに慎重であり、教えの言葉を本体とするが、時宜に応じて教えたことの優先順位が変わる。だから教えには損な話が無いのである。当時の人は季孫の実績によりその名を讃えた。だから孔子はやり過ぎを指摘し二度考えれば良い、三度も考えるのは無用だと言った。だから多分、季文子を誉めたのではなく、良くない事例として語っただけだろう。」
新注『論語集注』
三,去聲。季文子,魯大夫,名行父。每事必三思而後行,若使晉而求遭喪之禮以行,亦其一事也。斯,語辭。程子曰:「為惡之人,未嘗知有思,有思則為善矣。然至於再則已審,三則私意起而反惑矣,故夫子譏之。」愚按:季文子慮事如此,可謂詳審,而宜無過舉矣。而宣公篡立,文子乃不能討,反為之使齊而納賂焉,豈非程子所謂私意起而反惑之驗歟?是以君子務窮理而貴果斷,不徒多思之為尚。


三の字は尻下がりに読む。季文子は魯の家老で、いみ名は行父。事あるごとに三度考えてから行動した。晋国に使いに出るとき、葬礼に出くわしたときの用意をさせたのがその一例である。斯の字は、意味内容を持たない。
程頤「悪行をはたらく者は、考えるという事を知らない。行動に出る前に考えれば、善事を行うようになるものだ。だが考えると言っても、二度考えればもうはっきりと分かるから、三度目の考えでは却って欲が出て迷うことになる。だから先生は批判したのだ。」
愚か者である私が思うに、季文子の思慮深さはこの通りで、よく見極めたと言ってよく、間違いが無かったと評していい。だが宣公が公位を奪って就いた時、季文子は討伐できなかった。それどころか隣の大国・斉に出向いて賄賂を贈り、即位を責めねいよう取り計らった。これが程伊川先生の言う、三度目には欲が出て迷う、ということであろうか。
「晋へ使い」云々は次の通り。
八月,乙亥,晉襄公卒
文公六年(BC621)…秋、季文子が招かれて晋国に使いに出る前に、葬礼に出くわしたときの、礼法に従った用意を下されたいと家臣に求めさせてから出掛けた。
家臣「そんな必要ありますかね?」文子「備えあれば憂い無しじゃ。いにしえからのよき伝統である。こちらから出くわしたくなくても、災いは向こうからやって来る。用意を求めても害にはなるまい。」
八月乙亥の日、晋の襄公が亡くなった。(『春秋左氏伝』文公六年2)
「宣公が公位を奪って」云々は次の通り。
文公二妃,敬嬴生宣公,敬嬴嬖,而私事襄仲,宣公長,而屬諸襄仲,襄仲欲立之,叔仲不可,仲見于齊侯而請之,齊侯新立,而欲親魯,許之。
夫人姜氏歸于齊,大歸也,將行哭而過市,曰天乎,仲為不道,殺適,立庶,市人皆哭,魯人謂之哀姜。
文公十八年(BC609)…二月丁丑の日、文公が亡くなった。
文公には妃が二人いた。第二夫人の敬嬴がのちの宣公を産み、敬嬴は文公に寵愛されたが、ひそかに襄仲(公子遂)と相談し、この子が成長したら襄仲の後ろ盾で国公に即位させて欲しいと望んだ。襄仲は同意して、宣公を位に就けようとした。だが叔仲が反対した。そこで叔仲は隣の斉公に会見して協力を願った。斉公は位に就いたばかりだったので、魯の好意を得たいと考えて同意した。
文公正夫人の姜氏は斉に帰り、二度と帰らなかった。出発するに当たって泣きながら、人々で賑わう市場を通り、「ああ天よ、襄仲が不道をはたらいた。嫡子を殺して庶子を立てた。」と叫んだ。市場にいた者は同情してみな泣き、魯の者は正夫人を哀姜(かわいそうな斉公室出身の奥方)と呼んだ。(『春秋左氏伝』文公十八年2)
余話
多すぎない最小の数
前漢後期の劉向は、論語の本章と似ているようで違う話を記している。
衛將軍文子問子貢曰:「季文子三窮而三通,何也?」子貢曰:「其窮事賢,其通舉窮,其富分貧,其貴禮賤。窮而事賢則不悔;通而舉窮則忠於朋友,富而分貧則宗族親之;貴而禮賤則百姓戴之。其得之,固道也;失之,命也。」曰:「失而不得者,何也?」曰:「其窮不事賢,其通不舉窮,其富不分貧,其貴不理賤,其得之,命也;其失之,固道也。」

衛国の将軍・文子が子貢に尋ねた。「季文子は三度貧乏して三度切り抜けたと言います。どういうことですか?」
子貢「貧乏したときには賢者に従いました。切り抜けたときには貧乏している者を引き上げました。富んでいるときには貧者に分け与えました。身分が上がったときには身分なき者を敬いました。貧乏して賢者に従えば悔いが残らず、切り抜けて困っている者を引き上げればよき友人になれます。富んで貧者に分け与えれば一族が仲良くなります。地位が上がって身分なき者を敬うと庶民が味方になります。だから季文子が地位や財産を得たのは道理というものです。ですが失ったのはただの偶然です。」
文子「地位や財産を失って取り戻すことが出来ないのは、なぜですか?」
子貢「貧乏したときに賢者に従わず、切り抜けたときに貧乏している者を助けず、富んだときに貧者に分け与えず、身分が上がったときに身分なき者を放置した。そういう者が地位財産を得たのは、ただの偶然ですが、失うのはそれこそ道理というものです。」(『説苑』善説25)
また次のような伝説を伝えている。
季文子相魯,妾不衣帛,馬不食粟。仲孫它諫曰:「子為魯上卿,妾不衣帛,馬不食粟,人其以子為愛,且不華國也。」文子曰:「然乎?吾觀國人之父母衣麤食蔬,吾是以不敢。且吾聞君子以德華國,不聞以妾與馬。夫德者得於我,又得於彼,故可行;若淫於奢侈,沈於文章,不能自反,何以守國?」仲孫它慚而退。
季文子は魯国の宰相になった。それなのに妻たちには絹を着させず、馬にアワ*を食わせなかった。
仲孫它「ケチもほどほどになされよ。宰相ともあろうお方が、奥方は絹を着ず、馬はアワを食えないとは。魯国の者は閣下をケチだと思い、貧乏くさい国になってしまったと歎きますぞ。」
季文子「そうかね? ワシが見回った限りでは、民の者は老いた両親にボロをまとわせ、まずいものを食わせるしかないほど貧乏している。それなのにワシは贅沢する気にはならん。それにな、まともな貴族は自分の仕事で国を栄えさせるもので、かみさんや馬に何を着せたり食わせるかで、国が栄えたとは聞いたことがない。
貴族の仕事とは、自分と民、自分も相手も得になるときに発揮すべきで、ぜいたくにふけり、意味なく公文書の言葉をひねくり、その馬鹿さ加減に自分で気付かぬようでは、どうやって国を守るというのだ?」
仲孫它「いや全く仰せの通りです。失礼致しました。」(『説苑』反質13)
*アワ:春秋時代では俸給に支給された事実上の通貨。現代換算すると1リットルで約1万円の価値があった。孔子も給料をアワで受け取っており、人間が食べるべき上質の穀物とされていた。
ここで「仲孫它」として登場する仲孫家は、孔子の時代には孟孫家と呼ばれ、無名の庶民に過ぎなかった若き日の孔子を見出したのは当主の孟僖子、その子で孔子が家庭教師として教えた同世代の当主は孟懿子、共に孔子を政界へと押し上げた門閥貴族三家老=三桓の一家。
既存の論語本では吉川本に、古注によると本章の読みは「季文子ほどの賢者であれば、二度考えれば充分だっただろうに、三度とはまた丁寧なことだ」と言い、孔子は感心していたと解せるという。しかしそれでは、「可」の意味を正しく読み取ったことにならない。
また続けて、「季文子は…孔子よりも一世代前の人物であり、同時代の人物ではない。…あだママかも同時代人の人物の事跡を伝聞したような書き方をしているのは、どういうことなのであろうか」とも書く。しかし本章は別段、「同時代人」であるかのような文体ではない。
吉川は「聞」(間接伝聞)と「聴」(直接聴取)の違いをまだ知らず、「聞」を直接聴取のように感じたのだろうか。ただし季文子と孔子との年齢差は、生年で言えば丁度100年で、「一世代前」どころではない。漢文では30年を一世代とするのがお作法なのだが。
これもまた、「三」を多すぎない最小の数と捉える中国人の世界観を反映している。
参考記事
- 論語先進篇5余話「最小の幸せな数」





コメント