論語:原文・書き下し
原文(唐開成石経)
子曰加我數年五十以學易可以無大過矣
校訂
東洋文庫蔵清家本
子曰加我數年五十以學易可以無大過矣
定州竹簡論語
……以學,亦a可以毋b大過矣。」157
- 亦、阮本作「易」。連上句読為「學易」。『釋文』云、「魯読易為亦。按『魯論』作”亦”、連下句読」。鄭注、「魯読”易”為”亦”」。
- 毋、今本作「無」。
標点文
子曰、「加我數年、五十以學、亦可以毋大過矣。」
復元白文(論語時代での表記)



 數
數











※論語の本章は數の字が論語の時代に存在しない。占いの易は論語の時代に存在しない。「可以」は戦国中期にならないと確認できない。「加」「亦」の用法に疑問がある。本章は戦国時代以降の儒者による創作である。
書き下し
子曰く、我に數年を加へて、五十以て學ばば、亦以て大過毋かる可き矣。
論語:現代日本語訳
逐語訳

先生が言った。「私にもう数年の寿命を加えて、五十になっても学ぶなら、それでまあ、大きな間違いをしなくて良いに違いない。」
意訳

あと数年、五十になっても勉強するなら、まず大失敗をしでかさずに済むに違いない。
従来訳
先師がいわれた。――
「私がもう数年生き永らえて、五十になる頃まで易を学ぶことが出来たら、大きな過ちを犯さない人間になれるだろう。」下村湖人『現代訳論語』
現代中国での解釈例
孔子說:「如果我能多活幾年,五十歲學《周易》,就可以無大錯了。」
孔子が言った。「もしもう幾年か生きられたら、五十歳で”周易”を学び、つまりそれで大きな間違いをしないようになれるだろう。」
論語:語釈
子曰(シエツ)(し、いわく)

論語の本章では”孔子先生が言った”。「子」は貴族や知識人に対する敬称で、論語では多くの場合孔子を指す。「子」は赤ん坊の象形、「曰」は口から息が出て来るさま。「子」も「曰」も、共に初出は甲骨文。辞書的には論語語釈「子」・論語語釈「曰」を参照。
この二文字を、「し、のたまわく」と読み下す例がある。「言う」→「のたまう」の敬語化だが、漢語の「曰」に敬語の要素は無い。古来、論語業者が世間からお金をむしるためのハッタリで、現在の論語読者が従うべき理由はないだろう。
加(カ)


(金文)
論語の本章では”付け加える”。この語義は春秋時代では確認できない。初出は西周早期の金文。字形は「又」”右手”+「𠙵」”くち”。人が手を加えること。原義は”働きかける”。金文では人名のほか、「嘉」”誉める”の意に用いた。詳細は論語語釈「加」を参照。
我(ガ)


(甲骨文)
論語の本章では”わたし”。初出は甲骨文。字形はノコギリ型のかねが付いた長柄武器。甲骨文では占い師の名、一人称複数に用いた。金文では一人称単数に用いられた。戦国の竹簡でも一人称単数に用いられ、また「義」”ただしい”の用例がある。詳細は論語語釈「我」を参照。
數(ス/サク/ショク)


(金文)
論語の本章では”いくらかの”。「スウ」は慣用音。新字体は「数」。初出は戦国末期の金文で、論語の時代に存在しない。論語時代の置換候補もない。漢音(遣隋使・遣唐使が聞き帰った音)で「ス」は”かず・かぞえる”を、「サク」は”わずらわしい・しばしば”を、「ショク」は”細かい”を意味する。字形は「婁」”女性が蚕の繭を扱うさま”+「攴」”手を加える”で、原義は”数える”。詳細は論語語釈「数」を参照。
近音の「須」には”しばらく”の語義があり、「須年」で「数年」の置換候補となる可能性がある。ただし春秋末期までの出土例では、「須」は「盨」(青銅器の一種)として用いられるか、人名に用いられるかで、論語時代の置換候補になり得ない。
「数」は孔子塾の必須科目、六芸の一つに数えられているが、六芸の初出は『周礼』で、編纂されたのは漢代。文字的に言えば「いわゆる六芸の数は存在しない」事になってしまうし、類義語の「算」も初出は楚系戦国文字だから、言い出すと論語が崩壊しかねない。なにかしら算術的教養の教授はあったと思いたい。
年(デン)
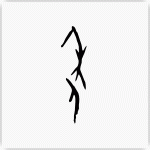

(甲骨文)
論語の本章では”一年”。初出は甲骨文。「ネン」は呉音。甲骨文・金文の字形は「秂」で、「禾」”実った穀物”+それを背負う「人」。原義は年に一度の収穫のさま。甲骨文から”とし”の意に用いられた。詳細は論語語釈「年」を参照。
五十(ゴシュウ)


(甲骨文)
論語の本章では”五十才”。初出は甲骨文。「五」も「十」も、甲骨文には二系統の字形がある。「十」(ジュウ)は呉音。論語語釈「五」・論語語釈「十」を参照。
以(イ)


(甲骨文)
論語の本章では”それで”。初出は甲骨文。人が手に道具を持った象形。原義は”手に持つ”。論語の時代までに、名詞(人名)、動詞”用いる”、接続詞”そして”の語義があったが、前置詞”…で”に用いる例は確認できない。ただしほとんどの前置詞の例は、”用いる”と動詞に解せば春秋時代の不在を回避できる。詳細は論語語釈「以」を参照。
學(カク)


(甲骨文)
論語の本章では”学ぶ”。「ガク」は呉音(遣隋使より前に日本に伝わった音)。初出は甲骨文。新字体は「学」。原義は”学ぶ”。座学と実技を問わない。上部は「爻」”算木”を両手で操る姿。「爻」は計算にも占いにも用いられる。甲骨文は下部の「子」を欠き、金文より加わる。詳細は論語語釈「学」を参照。
易(エキ)→亦(エキ)
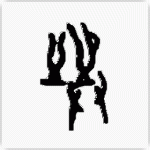
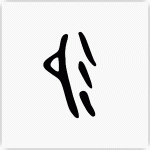
(甲骨文1・2)
論語の本章では、”…しやすい”→”それでまあ”。この語義は春秋時代では確認できない。初出は甲骨文。甲骨文の字形は、「匜」”水差し”に両手を添え、「皿」=別の容器に注ぐ形で、略体は「盤」”皿”を傾けて液体を注ぐ形。「益」と語源を同じくし、原義は”移し替える”・”増やす”。古代中国では「対飲」と言って、臣下に褒美を取らせるときには、酒を注いで飲ませることがあり、「易」は”賜う”の意となった。戦国時代の竹簡以降に字形が乱れ、トカゲの形に描かれるようになり、現在に至っている。論語の時代までに確認できるのは”賜う”の意だけで、”替える”・”…しやすい”の語義は戦国時代から。漢音は”変える”の場合「エキ」、”…しやすい”の場合「イ」。詳細は論語語釈「易」を参照。


(甲骨文)
前漢宣帝期の定州竹簡論語には「学亦」とあり、論語の本章では”それでまあ”。婉曲の意を示す。初出は甲骨文。原義は”人間の両脇”。春秋末期までに”…もまた”の語義を獲得した。”おおいに”の語義は、西周早期・中期の金文で「そう読み得る」だけで、確定的な論語時代の語義ではない。詳細は論語語釈「亦」を参照。
古注に「易窮理盡性以至於命」”易は宇宙のことわりを明らかにし、ものごとの性質を見極め、それらによって天命を伺い知る”とあることから、おそらくは後漢の時代に何者かが、勝手に「亦」zi̯ăk(入)を「易」di̯ĕk(入)に書き換えたと思われる。その意図は易の権威付けのためであり、世間師として易を売り出した儒者が儲けるためである。

儒教に易を持ち込んだのは戦国末期の荀子であることは定説となっている。孔子の生前、易の字に”占い”の語義は無く、亀の甲や動物の骨をあぶる占いは甲骨文の昔から存在したが、筮竹のたぐいを操っての占いは、論語の時代に存在したという証拠が無い。
また孔子は論語衛霊公篇37で、はっきりと占いを否定している。
子曰く、君子は貞ひて諒はざれ。

諸君は貴族を目指すのだから、迷信に惑わされてはならない。天命を占ったところで、信じるに足りる理由は何もない。他人を納得させるために占いの真似を見せはしても、自分が信じてどうする。
現伝「周易」の基本思想である陰陽の概念は、孔子没後170年ごろの戦国時代に生まれた鄒衍からしか確認できず、『史記』が易による占いを周の昔に遡らせているのはほぼ妄想。
自古受命而王,王者之興何嘗不以卜筮決於天命哉!其於周尤甚,及秦可見。代王之入,任於卜者。太卜之起,由漢興而有。
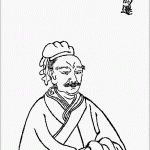

古来より天の命令で王が決まり、王者が勢いづくのは易によって天命を知ったからに他ならない。易の占いは周の時代にもっとも盛んとなり、秦代にも見られた。やがて王者に代わって天命をうかがい知るために、卜者(宮廷易者)を任命するようになった。その長官である太卜を置いたのは、漢帝国の始めからになる。(『史記』日者列伝)
*訳の続きは「余話」にて。
なお日者列伝を後世の創作とする説があるのは承知しているが、その真偽を質す手段が無いからとりあえずおく。「太卜」の名は『呂氏春秋』にも見えるから、『史記』よりも遡ることにはなるが、孔子の時代にまでは至らない。いずれにせよ論語の時代に占いの易は存在しない。


なお武内本には「釋文云、魯論は易を読みて亦とす、蓋し易は亦と同音のため仮借せられたるもの」とあり、いわゆる占いの「易」だとは、必ずしも解されなかったという。
ただし易と亦が同音というのは、カールグレン上古音がすでに発表されていたゆえに、戦前だろうと誤りで、上掲の通り「亦」zi̯ăk(入)と「易」di̯ĕk(入)で近音ではありえても、同音ではない。「爺いT」と「DDT」、「歯」と「屁」を聞き間違えるだろうか。なお◌̯は音節副音(弱い音)を、 ̆(ブリーヴ)は極短音を、入声はつまった音を意味する。
可以(カイ)
論語の本章では”…できる”。現代中国語でも同義で使われる助動詞「可以」。ただし出土史料は戦国中期以降の簡帛書(木や竹の簡、絹に記された文書)に限られ、論語の時代以前からは出土例が無い。春秋時代の漢語は一字一語が原則で、「可以」が存在した可能性は低い。ただし、「もって~すべし」と一字ごとに訓読すれば、一応春秋時代の漢語として通る。
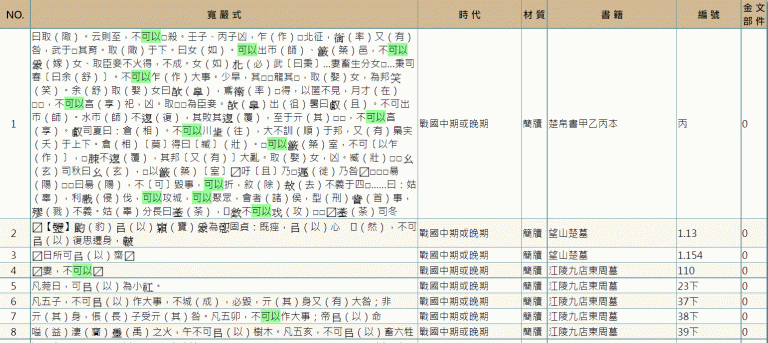
「先秦甲骨金文簡牘詞彙庫」
ただし「以て…す可し」と読めば、春秋時代での不在を回避できる。


「可」(甲骨文)
「可」の初出は甲骨文。字形は「口」+「屈曲したかぎ型」で、原義は”やっとものを言う”こと。甲骨文から”…できる”を表した。日本語の「よろし」にあたるが、可能”~できる”・勧誘”~のがよい”・当然”~すべきだ”・認定”~に値する”の語義もある。詳細は論語語釈「可」を参照。
無(ブ)→毋(ブ)


(甲骨文)
論語の本章では”ない”。初出は甲骨文。「ム」は呉音。甲骨文の字形は、ほうきのような飾りを両手に持って舞う姿で、「舞」の原字。その飾を「某」と呼び、「某」の語義が”…でない”だったので、「無」は”ない”を意味するようになった。論語の時代までに、”雨乞い”・”ない”の語義が確認されている。戦国時代以降は、”ない”は多く”毋”と書かれた。詳細は論語語釈「無」を参照。


(金文)
『経典釋文』の「毋」の、現行書体の初出は戦国文字で、無と同音。春秋時代以前は「母」と書き分けられておらず、「母」の初出は甲骨文。「毋」と「母」の古代音は、頭のmが共通しているだけで似ても似付かないが、「母」məɡ(上)には、”暗い”の語義が甲骨文からあった。詳細は論語語釈「毋」を参照。
大(タイ)
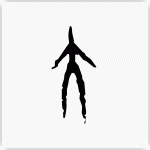

(甲骨文)
論語の本章では”大きな”。初出は甲骨文。「ダイ」は呉音。字形は人の正面形で、原義は”成人”。春秋末期の金文から”大きい”の意が確認できる。詳細は論語語釈「大」を参照。
過(カ)
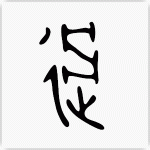

(金文)
論語の本章では”あやまち”。この語義は春秋時代では確認できない。初出は西周早期の金文。字形は「彳」”みち”+「止」”あし”+「冎」”ほね”で、字形の意味や原義は不明。春秋末期までの用例は全て人名や氏族名で、動詞や形容詞の用法は戦国時代以降に確認できる。詳細は論語語釈「過」を参照。
矣(イ)


(金文)
論語の本章では、”(きっと)~である”。初出は殷代末期の金文。字形は「𠙵」”人の頭”+「大」”人の歩く姿”。背を向けて立ち去ってゆく人の姿。原義はおそらく”…し終えた”。ここから完了・断定を意味しうる。詳細は論語語釈「矣」を参照。
論語:付記
検証
論語の本章は春秋戦国を含む先秦両漢に引用が無く、初出は前漢中期の定州竹簡論語で、再出は後漢から南北朝にかけて編まれた古注になる。ただし下掲新注が言うように、「假我數年」より後ろは全然違う文字列で『史記』にある。
孔子晚而喜易,序彖、繫、象、說卦、文言。讀易,韋編三絕。曰:「假我數年,若是,我於易則彬彬矣。」
孔子は晩年になって易の占いを喜んだ。そこで易にあれこれと注釈を書き加えた。そのためもととなった易の巻物を何度も読み返したので、巻物の綴じ紐が三度も切れたほどだった。その上で言った。「私にあと数年の寿命があったら、このようにして、私は易について奥義まで明らかに知ることが出来るだろう。」(『史記』孔子世家)
このように故事成句「韋編三絶」の元となった論語の本章だが、春秋時代に於ける「數」の字の不在、占いとしての「易」の不在から、本章は前漢儒によって創作された後、後漢儒によって占いの話に作り替えられたものだと断定できる。
「『史記』に韋編三絶とあるではないか」というのは反論にならない。現存最古の『史記』版本は宮内庁蔵の南宋版で、それまでに書き換えが無かったとは言えないのは論語と事情が同じだからだ。
宋儒は儒教経典の中でも易を重んじ、朱子も自ら注釈を書いているほどで、宋儒の商売の都合上、孔子には易を重んじてもらわないと困るのである。そのためなら平気で『史記』を書き換えたに違いないのは言うまでもない。

宮内庁蔵宋版『史記』該当部分
解説
論語八佾篇の一連の章から明らかになるように、孔子は古代人らしからぬ合理主義者で、神も占いも信じなかった(孔子はなぜ偉大なのか)。
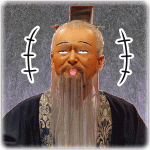
禘の祭りでは酒を撒き、それでご先祖様のたましいを呼び申す、ことになっておる。たましいが降りてきた振りした神官どもの、偽善めいた振る舞いは、アホらしくて見るに堪えない。(論語八佾篇10)
またおそらくは本章を易の宣伝に書き換えた儒者の出た後漢の時代は、オカルトや偽善がまかり通ったとんでもない時代でもある(論語解説「後漢というふざけた帝国」)。訳者としてはこのようなデタラメの下手人を突き止めたい所ではあるが、今のところ「こいつだ」という確信が無い。
なにせ易の字は”占い”とともに、”変更する”というありふれた動詞でも使われる漢字であり、漢籍から検索して引っかかった膨大な易の字を、一々解読していては寿命が尽きてしまう。また下手人が前漢の儒者である可能性も、否定できる根拠を持たず、ただの勘でしかない。
論語の本章、新古の注は次の通り。
古注『論語集解義疏』
…註易窮理盡性以至於命年五十而知天命以知命之年讀至命之書故可以無大過也

注釈。易の占いは宇宙の真理を詳しく知り、万物の性質を全て明らかにするので、天の命ずる運命を知る乎とが出来る。孔子は五十になって天命を知ると言った(論語為政篇4)。天命を知った年齢こそが、天命を明らかにする易の本を読んだ年だった。だから大きな間違いをしないだろう、と言えた。
注釈者の記名が無いことから、この注釈を書いたのは後漢末から三国を生きた何晏ということになるが、ここから論語の本章を占いばなしに仕立てたのが、後漢儒であることが判明する。儒者の虚偽は通時代的に甚だしいが、品の無いことにかけては後漢もその最高期だった。
新注『論語集注』
劉聘君見元城劉忠定公自言嘗讀他論,「加」作假,「五十」作卒。蓋加、假聲相近而誤讀,卒與五十字相似而誤分也。愚按:此章之言,史記作為「假我數年,若是我於易則彬彬矣」。加正作假,而無五十字。蓋是時,孔子年已幾七十矣,五十字誤無疑也。學易,則明乎吉凶消長之理,進退存亡之道,故可以無大過。蓋聖人深見易道之無窮,而言此以教人,使知其不可不學,而又不可以易而學也。

劉聘君*が元城出身の劉忠定公(劉安世)の言葉として、”以前異論を調べたときに「加」の字は「假」(仮)の字になっており、「五十」は「卒」の字になっていた”と言っている。思うに、「加」と「假」は音が近いので読み間違いやすく、「卒」は「五十」は形が似ているので間違って二文字に読みやすい。愚か者である私(朱子)が考えるに、本章の言葉は『史記』が「假我數年,若是我於易則彬彬矣」と伝えている。だから「加」は「假」が正しく、「五十」は元は無かったのだ。たぶんこの時孔子はすでに七十歳に近く、「五十」が間違いであるのは疑いない。易を学べば、必ず吉凶や物事の行く末が明らかになるから、行動の原則として大きな間違いをせずに済む。たぶん聖人孔子は易の奥深さを知り尽くして、本章の言葉で弟子を諭し、易を学ばないではいられないことを教え、同時にその学びが容易ではないことを教えたのだ。
*劉聘君:詳細不明。元に梅隠という人があってあざ名が「聘君」だが、姓も時代も違う。『宋史』を検索しても「聘君」はヒットしない。また劉聘君の名は明人劉元卿のあざ名またはおくり名としても見えるが、全く時代が違うことは梅隠と同じ。
一生懸命合理主義者であることを示そうとしているが、まるでオトツイの結論を記していることは言うまでもない。「雪に隠されたものは春になれば明らかになる」とロシアの諺に言うように、時というのは常に冷徹で、残忍で、場合によっては滑稽を作り出しもする。
余話
中国古代の易者
話はこれでおしまいだが、上掲『史記』日者列伝の続きが面白いので訳しておく。
司馬季主者,楚人也。卜於長安東市。
宋忠為中大夫,賈誼為博士,同日俱出洗沐,相從論議,誦易先王聖人之道術,究遍人情,相視而嘆。賈誼曰:「吾聞古之聖人,不居朝廷,必在卜醫之中。今吾已見三公九卿朝士大夫,皆可知矣。試之卜數中以觀采。」二人即同輿而之市,游於卜肆中。天新雨,道少人,司馬季主閒坐,弟子三四人侍,方辯天地之道,日月之運,陰陽吉凶之本。二大夫再拜謁。司馬季主視其狀貌,如類有知者,即禮之,使弟子延之坐。坐定,司馬季主復理前語,分別天地之終始,日月星辰之紀,差次仁義之際,列吉凶之符,語數千言,莫不順理。
宋忠、賈誼瞿然而悟,獵纓正襟危坐,曰:「吾望先生之狀,聽先生之辭,小子竊觀於世,未嘗見也。今何居之卑,何行之汙?」

前漢帝国が天下を平定すると、南方の楚に生まれた易者の司馬季主は、都の長安に出て市場に占いの店を出した。
そのころ、中大夫(政務議官)に任じられた宋忠と、博士(学術顧問官)に任じられた賈誼(『新書』の著者)が、連れだって銭湯に出掛ける道すがら、易について語り合った。易はまことに先王・聖人が生み出した素晴らしい技術であり、あらゆる人の思いを推し量れるわざであると思うと、互いに「すごいすごい」と讃え合うのだった。
賈誼「私の知る限り、いにしえの聖人は朝廷に仕えるのでないなら、易者や医者を開業していた。そこで今の閣僚や高官を見回すと、大した能のある者はいない。だから聖人に出会いたければ、いちまちの易者から探すしかない。」
そこで二人は、同乗した車を市場に向けさせ、占い師が店を連ねる一角に入った。その時雨が降り出して人出はまばらで、司馬季主の店は暇だったので、弟子に占いの講義を行っていた。それがいかにも詳しかったので、宋忠と賈誼の二人は聖人かもしれんと二度拝んで店に入った。
司馬季主は二人がいかにも賢そうな顔をしているので、恭しくお辞儀したあと、弟子に敷物を敷かせて迎え入れた。二人が腰を下ろすと、司馬季主はさらに易の講釈を詳しく始め、長々と数千語にまで至ったが、どれももっともなことわりで矛盾が無い。
たまげた二人は衣冠を正し、正座して言った。「先生のお説はまことに、世にも貴く思われます。それなのになんでまた、こんなむさ苦しい所で、卑しい易者など開業しておられるのですか?」
司馬季主捧腹大笑曰:「觀大夫類有道術者,今何言之陋也,何辭之野也!今夫子所賢者何也?所高者誰也?今何以卑汙長者?」二君曰:「尊官厚祿,世之所高也,賢才處之。今所處非其地,故謂之卑。言不信,行不驗,取不當,故謂之汙。夫卜筮者,世俗之所賤簡也。世皆言曰:『夫卜者多言誇嚴以得人情,虛高人祿命以說人志,擅言禍災以傷人心,矯言鬼神以盡人財,厚求拜謝以私於己。』此吾之所恥,故謂之卑汙也。」
司馬季主「ホーホッホッホ。お二方は見る目をお持ちのようだ。だがおかしな事を仰いましたな? 易者が卑しいというのなら、いったいどんなお方が、世にも貴いと仰るのですかな?」
二人「官位と俸禄が高いのを、世では貴いと申し、賢者がそうなると言われています。先生はそうではありませんから、むさ苦しいと申し上げたのです。それにこういうところに店を出す者は、だいたい口を開けばウソを言い、言ったことはデタラメで、占っても全然当たらない。だから卑しいと申し上げたのです。
世間ではそう言いますし、こういう悪口も聞きますぞ? いわく、易者はハッタリで客を脅し、まやかしで客を怖がらせ、デタラメで客の心を傷付け、お化けを語って金を取り、私利私欲ばかり貪る連中だ、と。」
続きは論語衛霊公篇37余話で。





コメント