論語:原文・書き下し
原文(唐開成石経)
子曰德之不脩學之不講聞義不能徙不善不能改是吾憂也
校訂
諸本
- 武内本:徙は改と韻をふむ。此本(=清家本)從に作るは誤なるべし。
東洋文庫蔵清家本
子曰德之不脩也學之不講也聞義不能從也不善不能改也是吾憂也
後漢熹平石経
(なし)
定州竹簡論語
[子曰]:「德之不脩也,學之不[講]也,聞義不能徙也,[不善]140[不]能改也a,是吾憂也。」141
- 德之不脩也,學之不講也,聞義不能徙也,不善不能改也、阮本作「德之不脩、學之不講、聞義不能徙、不善不能改」、皇本与簡本同。
標点文
子曰、「德之不脩也、學之不講也、聞義不能徙也、不善不能改也、是吾憂也。」
復元白文(論語時代での表記)




























※脩→攸・講→冓。
書き下し
子曰く、德之脩まら不る也、學之講まら不る也、義しきを聞いて徙る能は不る也、善から不るを改むる能は不る也、是れ吾が憂ひ也。
論語:現代日本語訳
逐語訳

先生が言った。「人格が完成していない。学問が高まらない。正義を聞いても取りかかれない。よくない行為が改められない。これが私の心配事だなあ。」
意訳

人格の出来がよくない。学問が進まない。やるべき事が出来ない。やってはいけないことを改められない。これが私の心配事だよ。
従来訳
先師がいわれた。――
「修徳の未熟なこと、研学の不徹底なこと、正義と知ってただちに実践にうつり得ないこと、不善の行を改めることが出来ないこと。――いつも私の気がかりになっているのは、この四つのことだ。」下村湖人『現代訳論語』
現代中国での解釈例
孔子說:「對品德不進行培養,對學問不進行鑽研,聽到好人好事不能跟著做,有了錯誤不能及時改正,這就是我所擔憂的。」
孔子が言った。「人品の修養が進まない、学問の研鑽が進まない、良き人良き行いを聞いて真似できない、間違いを起こしてその都度改めない、つまりこれらが私の悩みだ。」
論語:語釈
子曰(シエツ)(し、いわく)

論語の本章では”孔子先生が言った”。「子」は貴族や知識人に対する敬称で、論語では多くの場合孔子を指す。「子」は赤ん坊の象形、「曰」は口から息が出て来るさま。「子」も「曰」も、共に初出は甲骨文。辞書的には論語語釈「子」・論語語釈「曰」を参照。


(甲骨文)
この二文字を、「し、のたまわく」と読み下す例がある。「言う」→「のたまう」の敬語化だが、漢語の「曰」に敬語の要素は無い。古来、論語業者が世間からお金をむしるためのハッタリで、現在の論語読者が従うべき理由はないだろう。
德(トク)
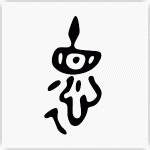

(金文)
論語の本章では”人格力”。初出は甲骨文。新字体は「徳」。甲骨文の字形は、〔行〕”みち”+〔丨〕”進む”+〔目〕であり、見張りながら道を進むこと。甲骨文で”進む”の用例があり、金文になると”道徳”と解せなくもない用例が出るが、その解釈には根拠が無い。前後の漢帝国時代の漢語もそれを反映して、サンスクリット語puṇyaを「功徳」”行動によって得られる利益”と訳した。孔子生前の語義は、”能力”・”機能”、またはそれによって得られる”利得”。詳細は論語における「徳」を参照。文字的には論語語釈「徳」を参照。
之(シ)


(甲骨文)
論語の本章では”…の”。初出は甲骨文。字形は”足”+「一」”地面”で、あしを止めたところ。原義はつま先でつ突くような、”まさにこれ”。殷代末期から”ゆく”の語義を持った可能性があり、春秋末期までに”~の”の語義を獲得した。詳細は論語語釈「之」を参照。
不(フウ)


(甲骨文)
漢文で最も多用される否定辞。初出は甲骨文。「フ」は呉音、「ブ」は慣用音。原義は花のがく。否定辞に用いるのは音を借りた派生義だが、甲骨文から否定辞”…ない”の意に用いた。詳細は論語語釈「不」を参照。
脩(シュウ)


(晋系戦国文字)
論語の本章では”修養する”。初出は晋系戦国文字。論語の時代に存在しない。論語時代の置換候補は部品の「攸」。字形は「攸」”人を棒で打つ”+「月」”にく”。原義は不明。辞書が「ほじし」”干し肉”と解しているのは、南北朝時代の儒者・皇侃のデタラメで、根拠が無い。論語における束脩を参照。字の詳細は論語語釈「脩」を参照。
也(ヤ)


(金文)
論語の本章では、句中では「や」と読んで主格の強調。”…はまさに”。文末では「かな」と読んで詠歎の意。「なり」と読んで断定と解してもよいが、断定の語義は春秋時代では確認できない。初出は事実上春秋時代の金文。字形は口から強く語気を放つさまで、原義は”…こそは”。春秋末期までに句中で主格の強調、句末で詠歎、疑問や反語に用いたが、断定の意が明瞭に確認できるのは、戦国時代末期の金文からで、論語の時代には存在しない。詳細は論語語釈「也」を参照。
學(カク)


(甲骨文)
論語の本章では”学習”。「ガク」は呉音(遣隋使より前に日本に伝わった音)。初出は甲骨文。新字体は「学」。原義は”学ぶ”。座学と実技を問わない。上部は「爻」”算木”を両手で操る姿。「爻」は計算にも占いにも用いられる。甲骨文は下部の「子」を欠き、金文より加わる。詳細は論語語釈「学」を参照。
講(コウ)


論語の本章では”組み立てる”こと。論語では本章のみに登場。初出は前漢の隷書。論語の時代に存在しない。論語時代の置換候補は”高く上げる”の語義に限り部品の「冓」。字形は「言」”ことば”+「冓」”組み上げる”。順を追って高度なことを説明すること。論語以降の文献では、前漢初期の『韓詩外伝』に「禮樂之不講」とある。なお近音に「高」「亢」があり、いずれも”高める”・”高まる”の語義を持つ。詳細は論語語釈「講」を参照。
聞(ブン)
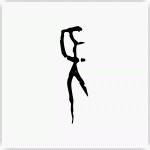
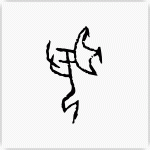
(甲骨文1・2)
論語の本章では”聞く”。初出は甲骨文。「モン」は呉音。甲骨文の字形は”耳の大きな人”または「斧」+「人」で、斧は刑具として王権の象徴で、殷代より装飾用の品が出土しており、玉座の後ろに据えるならいだったから、原義は”王が政務を聞いて決済する”。詳細は論語語釈「聞」を参照。
義(ギ)


(甲骨文)
論語の本章では”正義”。初出は甲骨文。字形は「羊」+「我」”ノコギリ状のほこ”で、原義は儀式に用いられた、先端に羊の角を付けた武器。春秋時代では、”格好のよい様”・”よい”を意味した。詳細は論語語釈「義」を参照。
能(ドウ)


(甲骨文)
論語の本章では”~できる”。初出は甲骨文。「ノウ」は呉音。原義は鳥や羊を煮込んだ栄養満点のシチューを囲んだ親睦会で、金文の段階で”親睦”を意味し、また”可能”を意味した。詳細は論語語釈「能」を参照。


「能~」は「よく~す」と訓読するのが漢文業界の座敷わらしだが、”上手に~できる”の意と誤解するので賛成しない。読めない漢文を読めるとウソをついてきた、大昔に死んだおじゃる公家の出任せに付き合うのはもうやめよう。
徙*(シ)
唐石経、定州竹簡論語は「徙」と記すが、清家本は「從」と記す。武内本は「徙は改と韻をふむ。此本(=清家本)從に作るは誤なるべし」と言うが、「徙」のカールグレン上古音はsi̯ĕɡ(上)、「改」はkəɡ(上)で同調だが語尾しか合わない。なお「從」は”したがう”の意ではdzʰi̯uŋ/tsʰi̯uŋ(共に平)で「改」と韻を踏むとも踏まないとも言えない。論語語釈「従」も参照。
いずれにせよ時系列の古い定州竹簡論語に従い「徙」のままとしたが、散文にも韻を気にするようになったのは唐詩の流行ったまさに唐石経の頃からで、安易に上古の論語に当てはめる「べし」とは賛成できない。唐人が韻を気にしたあまりデタラメな論語の書き換えをした例は、”野良トリ”を勝手に”メス雉”に仕立てた論語郷党篇19解説を参照。
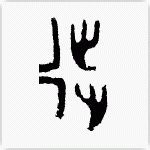

(金文)
初出は甲骨文。ただし字形は「歩」。現行字形の初出は西周早期の金文。字形は「彳」”みち”+「歨」”歩く”で、道を歩いて行くこと。殷代末期の金文は、いずれも族徽(家紋)と見なせる。春秋末期までに、”ゆく”の用例がある。詳細は論語語釈「徙」を参照。
善(セン)


(金文)
論語の本章では、”善事”。もとは道徳的な善ではなく、機能的な高品質を言う。「ゼン」は呉音。字形は「譱」で、「羊」+「言」二つ。周の一族は羊飼いだったとされ、羊はよいもののたとえに用いられた。「善」は「よい」「よい」と神々や人々が褒め讃えるさま。原義は”よい”。金文では原義で用いられたほか、「膳」に通じて”料理番”の意に用いられた。戦国の竹簡では原義のほか、”善事”・”よろこび好む”・”長じる”の意に用いられた。詳細は論語語釈「善」を参照。
改(カイ)
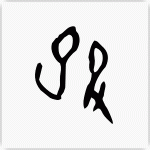

(甲骨文)
論語の本章では”あらためる”。初出は甲骨文。甲骨文の字形は「巳」”へび”+「攴」”叩く”。蛇を叩くさまだが、甲骨文から”改める”の意だと解釈されており、なぜそのような語釈になったのか明らかでない。詳細は論語語釈「改」を参照。
是(シ)


(金文)
論語の本章では”これ”。初出は西周中期の金文。「ゼ」は呉音(遣隋使より前に日本に伝わった音)。字形は「睪」+「止」”あし”で、出向いてその目で「よし」と確認すること。同音への転用例を見ると、おそらく原義は”正しい”。初出から”確かにこれは~だ”と解せ、”これ”・”この”という代名詞、”~は~だ”という接続詞の用例と認められる。詳細は論語語釈「是」を参照。
吾(ゴ)


(甲骨文)
論語の本章では”わたしの”。初出は甲骨文。字形は「五」+「口」で、原義は『学研漢和大字典』によると「語の原字」というがはっきりしない。一人称代名詞に使うのは音を借りた仮借だとされる。詳細は論語語釈「吾」を参照。
古くは中国語にも格変化があり、一人称では「吾」(藤堂上古音ŋag)を主格と所有格に用い、「我」(同ŋar)を所有格と目的格に用いた。しかし論語で「我」と「吾」が区別されなくなっているのは、後世の創作が多数含まれているため。
憂(ユウ)
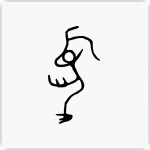

(金文)
論語の本章では”うれい”。頭が重く心にのしかかること。初出は西周早期の金文。字形は目を見開いた人がじっと手を見るさまで、原義は”うれい”。『大漢和辞典』に”しとやかに行はれる”の語釈があり、その語義は同音の「優」が引き継いだ。詳細は論語語釈「憂」を参照。
論語:付記
検証
論語の本章は、全体が前漢前半の『史記』孔子世家に引用がある。その他の文献では、後漢から三国時代にかけて編まれた『孔叢子』に「德之不脩」が見えるのみで、これら以外は先秦両漢の引用例が無い。文字史的には論語の時代まで遡れるので、史実として扱ってよい。
解説

「三内丸山遺跡」©663highland。上下をトリミングして転載
孔子が「学を講じられない」と歎いたのは、ウンチクを語れないと悩んだのではない。「講」の論語時代に於ける置換候補「冓」は、三内丸山遺跡の櫓のように、材を組み上げて高く造った構造を指し、一定の理論背景で情報が整理されており、雑多なウンチクの集合ではない。
雑多なウンチクと知識体系の違いについては、論語雍也篇27余話を参照。
古注では、論語述而篇の冒頭から本章までを一つの章として扱っている。
古注『論語集解義疏』
註孔安國曰夫子常以此四者為憂也
注釈。孔安国「先生は常にこの四つを心配事としたのである。」
新注では独立した章として記しているが、朱子は自分では注釈せず、引用で済ませている。
新注『論語集注』
尹氏曰:「德必脩而後成,學必講而後明,見善能徙,改過不吝,此四者日新之要也。苟未能之,聖人猶憂,況學者乎?」

尹焞「徳は必ず修養した後で身に付き、学問は必ず研究した後で明らかになる。善事を見ればすぐ実行でき、誤りを改めるのをためらわない。この四つは、毎日自分を向上させていくための要点である。この四つがまだ出来なくても、聖人ですら心配の種だったのだから、一般の儒学徒はなおさらだろう?」
尹焞は宋儒には珍しく善意の人で、このように書いて後進を励ました。
余話
飯を食ったりいちゃついたり
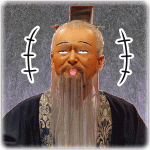
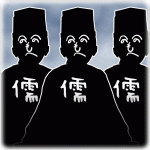
孔子は万能を自称しなかったことになっている(論語子罕篇6)。しかし儒者は本章に別の意味を貼り付けた。万能の孔子ですらこのような謙虚を言う、凡人はもっと謙虚でなければならない、と他人に言った。批判のしようがない古人を持ち出す悪弊が生まれた。
行父問「德之不修」一段。曰:「須先理會孝弟忠信等事,有箇地位,然後就這裏講學。『聞義不能徙』,這一件事已是好事。」
弟子の行父が論語述而篇「徳の修めざる」章の解説を問うた。
朱子「必ず先に、親孝行、年長への敬意、主君への忠義、友人への誠実と言ったことわりを理解して、実践できた後に、やっと学問を究めることが出来る。つまり”正義を実行できない”、この一言に集約されきっている。」(『朱子語類』徳之不修条5)
だからといって、教師としての孔子の偉大さが損なわれるわけではない。孔子の責任ではないからだ。だが訳者の子供時代までは、この悪弊が残っていて、昔の人は偉かった式の説教を数多く聞かされた。変化のない時代だけに通用するやり方で、今はもう一掃されただろう。
子供たちや若手社員は言ってやれば良かったのだ。じゃあなんで戦争に負けたの? なんで業績が上がらないの? それにそのエラい人はあなたじゃない。あなたがそのエラい人同等の業績を挙げてからお話を伺いましょうと。組織では論理的に正しい事は通用しないものだ。
古人だって飯を食ったり屁を垂れたり異性といちゃついたりしていたのである。
論語に話を戻すと、もし既存の論語本を買って読もうと思う場合、目の付け所が一つある。それは出来るだけ、漢語が日本語に直っていることだ。従来訳のように「修徳」「不善の行」といった漢語をそのまま用いて訳している本は、十中八九自分で訳していない。儒者の孫引き。
儒者だって嘘つきばかりではないから、儒者だから悪いとは言えない。しかし訳をする場合、儒者を参考にするまではいいが、儒者だって人間という事実を忘れてはいけない。辞書を引くのが面倒だからと言って、儒者のコピペをしたのでは、論語を訳したことにならない。
ただ訳せないかどうか自体は、人格とはまるで関係が無い。



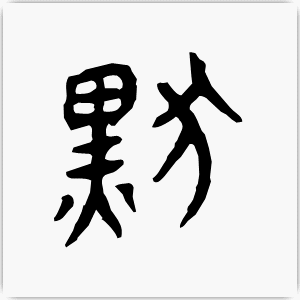

コメント