論語:原文・書き下し
原文(唐開成石経)
冉有曰夫子爲衞君乎子貢曰諾吾將問之入曰伯夷叔齊何人也曰古之賢人也曰怨乎曰求仁而得仁又何怨出曰夫子不爲也
校訂
東洋文庫蔵清家本
冉有曰夫子爲衞君乎/子貢曰諾吾將問之入曰伯夷叔齊何人也子曰古之賢人也曰怨乎曰求仁而得仁又何怨乎/出曰夫子不爲也
後漢熹平石経
…問之…
定州竹簡論語
……貢曰:「若a,吾[將問]152……賢人者b□153……[何怨c]?」出,曰:「夫子弗d為也。」154
- 若、今本作「諾」。若借為諾。
- 者、今本作「也」。
- 皇本、高麗本、足利本、「怨」下有「乎」字。
- 弗、今本作「不」。
標点文
冉有曰、「夫子爲衞君乎。」子貢曰、「若、吾將問之」。入曰、「伯夷叔齊、何人也。」子曰、「古之賢人者。」曰、「怨乎。」曰、「求仁而得仁、又何怨。」出曰、「夫子弗爲也。」
復元白文(論語時代での表記)




















































※貢・將・仁→(甲骨文)・怨→夗。論語の本章は、「之」「也」の用法に疑問がある。
書き下し
冉有曰く、夫子は衞君を爲けむ乎。子貢曰く、若、吾將に之を問はむと。入りて曰く、伯夷叔齊は何人ぞ也。子曰く、古之賢人なる者ぞ。曰く、怨みたる乎。曰く、仁を求め而仁を得たり、又何ぞ怨みむと。出でて曰く、夫子は爲け弗る也。
論語:現代日本語訳
逐語訳
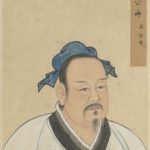

冉有が言った。「先生は衛の国君を助けるだろうか。」子貢が言った。「わかった。私がすぐに聞いてみよう。」先生の部屋に入って子貢が言った。「伯夷叔斉は何者ですか。」先生が言った。「まことに昔の賢人だ。」子貢が言った。「怨みましたか。」先生が言った。「仁を求めて仁を得た。またどうして怨むだろうか。」子貢は部屋を出て言った。「先生は助けないぞ。」
意訳
一門が衛国滞在中、その国でお家争いが起きそうだった。国公のバカ息子が勘当されて国外逃亡し、なんと敵国の晋の軍勢を引き連れて、復讐に来るとの噂である。
冉求「先生は今の衛国公に味方なさるかな?」
子貢「よし、俺が伺ってみよう。」
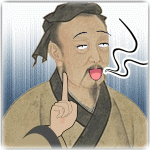

子貢「失礼します。先生、伯夷叔斉ってどんな人ですかね。」
孔子「何のなぞかけだ。そりゃあ天下公認の昔の偉人だろうが。」
子貢「せっかく周王軍の前で、大義名分を持ち上げる演説をぶったのに、アブナイ人扱いはされる、食いはぐれて飢え死にはする、やるんじゃなかったと怨んだに違いないでしょう?」
孔子「いや。仁を看板にしてべらべら喋って、名前だけでも天下公認の仁者になれたんだ。怨まなかっただろうよ。だが私はそんな真似しないぞ。こんなチマチマした国の跡目争いに付き合ってたら、いつになったら国盗りが出来るかわかったものじゃない。」
子貢「そりゃそうですよね。わかりました。」


子貢「オイ冉求、先生は味方なさらねえおつもりだぜ。」
従来訳
冉有がいった。――
「先生は衛の君を援けられるだろうか。」
子貢がいった。――
「よろしい。私がおたずねして見よう。」
彼は先師のお室に入ってたずねた。――
「伯夷・叔斉はどういう人でございましょう。」
先師はこたえられた。――
「古代の賢人だ。」
子貢――
「二人は自分たちのやったことを、あとで悔んだのでしょうか。」
先師――
「仁を求めて仁を行うことが出来たのだから、何の悔むところがあろう。」
子貢は先師のお室からさがって、冉有にいった。――
「先生は衛の君をお援けにはならない。」下村湖人『現代訳論語』
現代中国での解釈例
冉有說:「老師打算輔佐衛國的君主嗎?」子貢說:「哦,我去問問。」子貢進去後,問:「伯夷、叔齊那種人?」答:「古代賢人埃」問:「他們後悔嗎?」答:「求仁而得仁,後悔什麽?」子貢出來說:「老師不會去。」
冉有が言った。「先生は衛国の君主を補佐するつもりがあるか?」子貢が言った。「ああ、私が行って聞いてみよう。」子貢は進み出て、言った。「伯夷叔斉とはどんな人ですか。」答えた。「古代の賢者だな。」問うた。「彼らは後悔しましたか?」答えた。「仁を求めて仁を得た。後悔するか?」子貢は出てきて言った。「先生は決して行かない。」
論語:語釈
冉 有 曰、「夫 子 爲 衞 君 乎。」子 貢 曰、「諾、吾 將 問 之。」入 曰、「伯 夷 叔 齊、何 人 也。」子 曰、「古 之 賢 人 也。」曰、「怨 乎。」曰、「求 仁 而 得 仁、又 何 怨。」出、曰、「夫 子 不 爲 也。」
冉有(ゼンユウ)


(甲骨文)
孔子の弟子。 姓は冉、名は求、あざ名は子有。本章ではあざ名で呼んでおり敬称。『史記』によれば孔子より29年少。政治の才を孔子に認められ、孔門十哲の一人。孔子一門の軍事力を代表する人物で、個人武で目立つ樊須子遅に対し、武将として名をはせた。詳細は論語の人物:冉求子有を参照。
孔子一門の実務家ということでは、子貢と並ぶ人物であり、本章の記述から、似た者同士で仲がよかったと思われる。下記「弗」の語釈に記したとおり、仲間同士の気軽なため口を利いているからだ。
曰(エツ)


(甲骨文)
論語で最も多用される、”言う”を意味する言葉。初出は甲骨文。原義は「𠙵」=「口」から声が出て来るさま。詳細は論語語釈「曰」を参照。
夫子(フウシ)


「夫」(甲骨文)
論語の本章では”孔子先生”。従来「夫子」は「かの人」と訓読され、「夫」は指示詞とされてきた。しかし論語の時代、「夫」に指示詞の語義は無い。同音「父」は甲骨文より存在し、血統・姓氏上の”ちちおや”のみならず、父親と同年代の男性を意味した。従って論語における「夫子」がもし当時の言葉なら、”父の如き人”の意味での敬称。詳細は論語語釈「夫」を参照。


「子」(甲骨文)
論語の本章では”(孔子)先生”。初出は甲骨文。論語ではほとんどの章で孔子を指す。まれに、孔子と同格の貴族を指す場合もある。また当時の貴族や知識人への敬称でもあり、孔子の弟子に「子○」との例が多数ある。なお逆順の「○子」という敬称は、上級貴族や孔子のような学派の開祖級に付けられる敬称。「南子」もその一例だが、”女子”を意味する言葉ではない。字形は赤ん坊の象形で、もとは殷王室の王子を意味した。詳細は論語語釈「子」を参照。
爲(イ)


(甲骨文)
論語の本章では”助ける”。この語義は春秋時代では確認できない。新字体は「為」。字形は象を調教するさま。甲骨文の段階で、”ある”や人名を、金文の段階で”作る”・”する”・”…になる”を意味した。詳細は論語語釈「為」を参照。
衞君(エイクン)
論語の本章では、孔子亡命中の衛国の君主で、それも滞在末期の出公。
衛国は晋国の侵攻から何とか国を保ってきたやり手の霊公が死去すると、後継の国君・出公が立ったが、それ以前から晋国亡命中の元太子・蒯聵(カイカイ)が、晋国の実力者・趙簡子の後押しで衛国に押し込み、実の子であるのちの出公を廃そうとしていた。
出公に仕えていた孔子の弟子・子路は、出公とその若君を守って戦死することになる。論語の本章以前の衛国の状況については、論語雍也篇28を参照。本章の時期を確定することは難しいが、まだ霊公存命中とも、出公即位後とも考えられる。
出公排除ののち蒯聵は、衛の荘公として即位した。『史記』衛世家を参照。


(甲骨文)
「衞」の新字体は「衛」。初出は甲骨文。中国・台湾・香港では、新字体がコード上の正字として扱われている。甲骨文には、「韋」と未分化の例がある。現伝字体につながる甲骨文の字形は、「方」”首かせをはめられた人”+「行」”四つ角”+「夂」”足”で、四つ角で曝された奴隷と監視人のさま。奴隷はおそらく見せしめの異民族で、道路を封鎖して「入るな」と自領を守ること。のち「方」は「囗」”城壁”→”都市国家”に書き換えられる。甲骨文から”守る”の意に用い、春秋末期までに、国名・人名の例がある。詳細は論語語釈「衛」を参照。
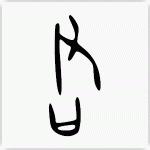

「君」(甲骨文)
「君」の初出は甲骨文。甲骨文の字形は「丨」”通路”+「又」”手”+「𠙵」”くち”で、人間の言うことを天界と取り持つ聖職者。「尹」に「𠙵」を加えた字形。甲骨文の用例は欠損が多く判読しがたいが、称号の一つだったと思われる。「先秦甲金文簡牘詞彙資料庫」は、春秋末期までの用例を全て人名・官職名・称号に分類している。甲骨文での語義は明瞭でないが、おそらく”諸侯”の意で用い、金文では”重臣”、”君臨する”、戦国の金文では”諸侯”の意で用いた。また地名・人名、敬称に用いた。詳細は論語語釈「君」を参照。
論語では「君子」との熟語で多出。その意味には多様性がある。「君子」については論語における「君子」を参照。
乎(コ)


(甲骨文)
論語の本章では、「か」と読んで疑問の意。この語義は春秋時代では確認できない。初出は甲骨文。甲骨文の字形は持ち手を取り付けた呼び鐘の象形で、原義は”呼ぶ”こと。甲骨文では”命じる”・”呼ぶ”を意味し、金文も同様で、「呼」の原字となった。句末の助辞や助詞として用いられたのは、戦国時代以降になる。ただし「烏乎」で”ああ”の意は、西周早期の金文に見え、句末でも詠嘆の意ならば論語の時代に存在した可能性がある。詳細は論語語釈「乎」を参照。
子貢(シコウ)
論語の本章では、孔子の直弟子の中で最も政才商才のあった、端木賜子貢のこと。姓は端木、いみ名は賜、あざ名が子貢。詳細は論語の人物・端木賜子貢を参照。
「子」は貴族や知識人への敬称。子貢のように学派の弟子や、一般貴族は「子○」と呼び、孔子のように学派の開祖や、上級貴族は、「○子」と呼んだ。原義は殷王室の一族。詳細は論語語釈「子」を参照。
「貢」は甲骨文からあるが金文は未発掘。「子貢」は「子贛」とも書かれる(『史記』貨殖列伝)。字形は「工」+「貝」”財貨”で、原義は”貢ぐ”。殷墟第三期の無名組甲骨文に「章丮」とあり、これは「贛」”献上する”を意味するという。詳細は論語語釈「貢」を参照。
定州竹簡論語では、通常「貢」を異体字「![]() 」としるすのだが、論語の本章がそうなっていない理由は不明。
」としるすのだが、論語の本章がそうなっていない理由は不明。
諾(ダク)→若(ジャク)
論語の本章では”よしわかった”。


(金文)
「諾」の初出は西周中期の金文。ただし字形は「𠙵」”くち”+「若」。字形は「言」+「若」”その通り”で、「その通り」と言うこと。春秋時代の金文に”うべなう”の用例がある。中国の時代劇では、目下の者の受け答え”承知しました”の意味で使われている(北京語nuò)。詳細は論語語釈「諾」を参照。


「若」(甲骨文)
定州竹簡論語の「若」の初出は甲骨文。字形はかぶり物または長い髪を伴ったしもべが上を仰ぎ受けるさまで、原義は”従う”。同じ現象を上から目線で言えば”許す”の意となる。甲骨文からその他”~のようだ”の意があるが、”若い”の語釈がいつからかは不詳。詳細は論語語釈「若」を参照。
吾(ゴ)


(甲骨文)
論語の本章では”わたし”。初出は甲骨文。字形は「五」+「口」で、原義は『学研漢和大字典』によると「語の原字」というがはっきりしない。一人称代名詞に使うのは音を借りた仮借だとされる。詳細は論語語釈「吾」を参照。
春秋時代までは中国語にも格変化があり、一人称では「吾」を主格と所有格に用い、「我」を所有格と目的格に用いた。しかし論語でその文法が崩れ、「我」と「吾」が区別されなくなっている章があるのは、後世の創作が多数含まれているため。
將(ショウ)


(甲骨文)
論語の本章では”今すぐ…しよう”。近い将来を言明する言葉。新字体は「将」。初出は甲骨文。字形は「爿」”寝床”+「廾」”両手”で、『字通』の言う、親王家の標識の省略形とみるべき。原義は”将軍”・”長官”。同音に「漿」”早酢”、「蔣」”真菰・励ます”、「獎」”すすめる・たすける”、「醬」”ししびしお”。詳細は論語語釈「将」を参照。
問(ブン)


(甲骨文)
論語の本章では”問う”。この語義は春秋時代では確認できない。定州竹簡論語では欠いている。初出は甲骨文。「モン」は呉音(遣隋使より前に日本に伝わった音)。字形は「門」+「口」。甲骨文での語義は不明。金文では人名に用いられ、”問う”の語義は戦国時代の竹簡以降になる。詳細は論語語釈「問」を参照。
之(シ)


(甲骨文)
論語の本章では”これ”・”…の”。初出は甲骨文。字形は”足”+「一」”地面”で、あしを止めたところ。原義はつま先でつ突くような、”まさにこれ”。殷代末期から”ゆく”の語義を持った可能性があり、春秋末期までに”~の”の語義を獲得した。詳細は論語語釈「之」を参照。
入(ジュウ)


(甲骨文)
論語の本章では”(孔子の居間に)入る”。初出は甲骨文。「ニュウ」は呉音(遣隋使より前に日本に伝わった音)。字形は割り込む姿。原義は、巨大ダムを水圧がひしゃげるように”へこませる”。甲骨文では”入る”を意味し、春秋時代までの金文では”献じる”の意が加わった。詳細は論語語釈「入」を参照。
伯夷(ハクイ)・叔齊(シュクセイ)
新字体では伯夷・叔斉。
論語では、古代中国の辺境にあったとされる孤竹国の公子兄弟とされる。その実、古代中国で最も有名なニートの兄弟。形式上、殷の臣下だった周が、いろんな事情で殷に反乱したのだが、「反乱」の後ろめたさに気付いたこの兄弟が、周の親玉・武王に、「お前さんはろくでなしだ(ワシらを黙らせたかったら官職を寄こせ)」とゆすった、と『史記』に書いてある。
西伯卒,武王載木主,號為文王,東伐紂。伯夷、叔齊叩馬而諫曰:「父死不葬,爰及干戈,可謂孝乎?以臣弒君,可謂仁乎?」左右欲兵之。太公曰:「此義人也。」扶而去之。

西伯が死んで武王があとを継いだ。武王は西伯の位牌を車に乗せて「文王」と記し、殷の紂王を討つ軍勢を東に向けて出発させようとした。すると草むらに潜んでいた伯夷・叔斉の兄弟が、武王の車の引き馬に飛び付いて言った。「父上が亡くなったのに葬式も出さない。代わりに戦争を始めた。親不孝にもほどがある。家臣の分際で主君を殺そうとしている。お前さんはろくでなしだ。」怒った衛兵が武器を向けた。
太公望「ハイハイご立派ご立派、ちょっとあっちへ行こうね。」衛兵に言い付けて、しがみついている二人を馬から引きはがし、「オイ! こいつらをどっかに捨ててこい。」(『史記』伯夷伝)

やったことはチンピラ左翼や街宣右翼のたぐいと変わらない。中国では生まれた男の子を歳の順に伯・仲・叔・季と呼ぶので、伯夷は”長男の夷”、叔斉は”三男の斉”という意味。孤竹国は竹簡や青銅器に物証があり、現在の遼寧省にあった殷の諸侯国。
上掲の『史記』に「孝」「仁」と出てくるが、殷末周初、「孝」の字はあったが”孝行”の意味では使われていない(論語語釈「孝」)。「仁」の字は長らく忘れられており、しかも”情け・思いやり”という語義が出来るのは、600年以上先の戦国時代のことだ(論語における「仁」)。
つまり上掲『史記』の伝説は怪しい。
なお論語公冶長篇22解説に記したが、戦国時代の孟子は伯夷は知っていても叔斉は知らなかった。すると孔子も知らなかったはずで、伯夷と叔斉を兄弟と言い出したのは、孟子と同時代人の荘子。論語の本章も「叔斉」部分は史実性が一層怪しい。
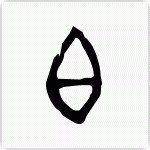

「白」(甲骨文)
「伯」の字は論語の時代、「白」と書き分けられていない。初出は甲骨文。字形の由来は蚕の繭。原義は色の”しろ”。甲骨文から原義のほか地名・”(諸侯の)かしら”の意で用いられ、また数字の”ひゃく”を意味した。金文では兄弟姉妹の”年長”を意味し、また甲骨文同様諸侯のかしらを意味し、五等爵の第三位と位置づけた。戦国の竹簡では以上のほか、「柏」に当てた。詳細は論語語釈「伯」を参照。


「夷」(甲骨文)
「夷」の初出は甲骨文。字形は「矢」+ひもで、いぐるみをするさま。おそらく原義は”狩猟(民)”。甲骨文での語義は不明。金文では地名に用いた。詳細は論語語釈「夷」を参照。


「叔」(甲骨文)
「叔」の初出は甲骨文。字形は「廾」”両手”+”きね”+”臼”で、穀物から殻を取り去るさま。ゆえに「菽」の意がある。原義は”殻剥き”。甲骨文では地名、”包み囲む”の意に、金文では人名、”赤い”の意に用いた。”次男”を意味するのは後世の転用。詳細は論語語釈「叔」を参照。
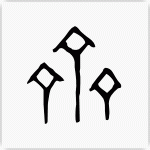

「齊」(甲骨文)
「齊」の新字体は「斉」。初出は甲骨文。新字体は「斉」。「サイ」は慣用音。甲骨文の字形には、◇が横一線にならぶものがある。字形の由来は不明だが、一説に穀粒の姿とする。甲骨文では地名に用いられ、金文では加えて人名・国名に用いられた。詳細は論語語釈「斉」を参照。
何(カ)


「何」(甲骨文)
「何」は論語の本章では”どんな”。この語義は春秋時代では確認できない。初出は甲骨文。字形は「人」+”天秤棒と荷物”または”農具のスキ”で、原義は”になう”。甲骨文から人名に用いられたが、”なに”のような疑問辞での用法は、戦国時代の竹簡まで時代が下る。詳細は論語語釈「何」を参照。
人(ジン)


(甲骨文)
論語の本章では”人間”。初出は甲骨文。原義は人の横姿。「ニン」は呉音。甲骨文・金文では、人一般を意味するほかに、”奴隷”を意味しうる。対して「大」「夫」などの人間の正面形には、下級の意味を含む用例は見られない。詳細は論語語釈「人」を参照。
也(ヤ)


(金文)
論語の本章では、「何人也」では「や」と読んで詠嘆の意。文末では「なり」と読んで断定の意。断定の語義は春秋時代では確認できない。初出は事実上春秋時代の金文。字形は口から強く語気を放つさまで、原義は”…こそは”。春秋末期までに句中で主格の強調、句末で詠歎、疑問や反語に用いたが、断定の意が明瞭に確認できるのは、戦国時代末期の金文からで、論語の時代には存在しない。詳細は論語語釈「也」を参照。
子曰(シエツ)(し、いわく)

論語の本章では”孔子先生が言った”。「子」は貴族や知識人に対する敬称で、論語では多くの場合孔子を指す。この二文字を、「し、のたまわく」と読み下す例がある。「言う」→「のたまう」の敬語化だが、漢語の「曰」に敬語の要素は無い。古来、論語業者が世間からお金をむしるためのハッタリで、現在の論語読者が従うべき理由はないだろう。
古(コ)


(甲骨文)
論語の本章では”むかし”。初出は甲骨文。甲骨文の字形は「口」+「中」”盾”で、原義は”かたい”。甲骨文では占い師の名、地名に用い、金文では”古い”、「故」”だから”の意、また地名に用いた。詳細は論語語釈「古」を参照。
賢(ケン)


(金文)
論語の本章では”偉い”。”知能が優れている”のみを示さないので、「かしこし」と訓読した。初出は西周早期の金文。字形は「臣」+「又」+「貝」で、「臣」は弓で的の中心を射貫いたさま、「又」は弓弦を引く右手、「貝」は射礼の優勝者に与えられる褒美。原義は”(弓に)優れる”。詳細は論語語釈「賢」を参照。
者(シャ)


(金文)
論語の本章では、”…である者”。旧字体は〔耂〕と〔日〕の間に〔丶〕一画を伴う。新字体は「者」。ただし唐石経・清家本ともに新字体と同じく「者」と記す。現存最古の論語本である定州竹簡論語も「者」と釈文(これこれの字であると断定すること)している。初出は殷代末期の金文。金文の字形は「木」”植物”+「水」+「口」で、”この植物に水をやれ”と言うことだろうか。原義は不明。初出では称号に用いている。春秋時代までに「諸」と同様”さまざまな”、”…は”の意に用いた。漢文では人に限らず事物にも用いる。詳細は論語語釈「者」を参照。
怨(エン)
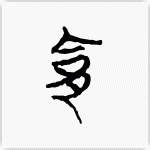

(楚系戦国文字)
論語の本章では”うらむ”。初出は楚系戦国文字で、論語の時代に存在しない。「オン」は呉音。同音に「夗」とそれを部品とする漢字群など。論語時代の置換候補は「夗」。現伝の字形は秦系戦国文字からで、「夗」”うらむ”+「心」。「夗」の初出は甲骨文、字形は「夊」”あしを止める”+「人」。行きたいのを禁じられた人のさま。原義は”気分が塞がりうらむ”。初出の字形は「亼」”蓋をする”+うずくまった人で、上から押さえつけられた人のさま。詳細は論語語釈「怨」を参照。

求(キュウ)

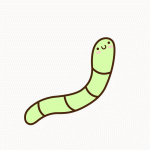
(甲骨文)
論語の本章では”もとめる”。初出は甲骨文。ただし字形は「豸」。字形と原義は足の多い虫の姿で、甲骨文では「とがめ」と読み”わざわい”の意であることが多い。”求める”の意になったのは音を借りた仮借。論語の時代までに、”求める”・”とがめる””選ぶ”・”祈り求める”の意が確認できる。詳細は論語語釈「求」を参照。
仁(ジン)


(甲骨文)
論語の本章では、とりあえず”貴族らしさ”。通説の”情け深い”という道徳的意味は、孔子没後一世紀後に現れた孟子による、「仁義」の語義であり、孔子や高弟の口から出た「仁」の語義ではない。字形や音から推定できる春秋時代の語義は、敷物に端座した”よき人”であり、”貴族”を意味する。詳細は論語における「仁」を参照。
初出は甲骨文。字形は「亻」”ひと”+「二」”敷物”で、原義は敷物に座った”貴人”。詳細は論語語釈「仁」を参照。
而(ジ)


(甲骨文)
論語の本章では”…であって同時に”。初出は甲骨文。原義は”あごひげ”とされるが用例が確認できない。甲骨文から”~と”を意味し、金文になると、二人称や”そして”の意に用いた。英語のandに当たるが、「A而B」は、AとBが分かちがたく一体となっている事を意味し、単なる時間の前後や類似を意味しない。詳細は論語語釈「而」を参照。
得(トク)


(甲骨文)
論語の本章では”手に入れる”。初出は甲骨文。甲骨文に、すでに「彳」”みち”が加わった字形がある。字形は「貝」”タカラガイ”+「又」”手”で、原義は宝物を得ること。詳細は論語語釈「得」を参照。
又(ユウ)


(甲骨文)
論語の本章では”それなのに”。初出は甲骨文。字形は右手の象形。甲骨文では祭祀名に用い、”みぎ”、”有る”を意味した。金文では”またさらに”・”補佐する”を意味した。詳細は論語語釈「又」を参照。
求仁而得仁
論語の本章では、”仁者と呼ばれるのを望んでそれを得た”。
伯夷と叔斉は周の武王を非難するのに、一つには父親の葬儀をまともに終えてない、もう一つは臣下の分際で主君を殺そうとする、この二点の不「仁」=貴族らしさが無い、ととがめ、その結果仁者だと言われた。「それで満足だろう?」と孔子は冷たく突き放したわけで、後世の儒者のように、オイオイ泣きまねして伯夷叔斉を持ち上げたわけではない。
出(シュツ/スイ)


(甲骨文)
論語の本章では”孔子の居室から出る”。初出は甲骨文。「シュツ」の漢音は”出る”・”出す”を、「スイ」の音はもっぱら”出す”を意味する。呉音は同じく「スチ/スイ」。字形は「止」”あし”+「凵」”あな”で、穴から出るさま。原義は”出る”。論語の時代までに、”出る”・”出す”、人名の語義が確認できる。詳細は論語語釈「出」を参照。
弗(フツ)


(甲骨文)
論語の本章では”~でない”。初出は甲骨文。甲骨文の字形には「丨」を「木」に描いたものがある。字形は木の枝を二本結わえたさまで、原義はおそらく”ほうき”。甲骨文から否定辞に用い、また占い師の名に用いた。金文でも否定辞に用いた。詳細は論語語釈「弗」を参照。
『学研漢和大字典』によると、漢代以前では、「弗」は「不(動詞)(目的語)」とあるべきところ、目的語を省いて言う場合に用いた。つまりぶっきらぼうな言い方で、「オイ冉有、先生はお助けにならねえおつもりだぜ。」
論語:付記
検証
論語の本章は春秋戦国の誰一人引用せず、前漢中期の『史記』伯夷伝が概要を引用し、「求仁而得仁」の言い廻しが前漢後半の『列女伝』に見られるに止まる。定州竹簡論語にあることから、前漢前半までには論語の一章に含まれていたのだろうが、「叔斉」の論語時代に於ける不在など、疑わしい点が多数ある。ただし後世の儒者が偽作する動機が見当たらず、何らかの史実を伝えるだろう。文字史上も論語の時代に遡りうるので、とりあえず史実として扱う。
解説
孔子塾生にとっての目標は、仁=貴族らしさを身につけて仕官し、差別を乗り越えることで、孔子にとっての目標は、そうした新しい人材=官僚が国政に携わり、家柄血統に縛られない国を作ることだった。だが衛国には人材がいすぎて、国盗りが出来そうに無い。
論語憲問篇20で、孔子自身がそう言っている。ただし衛国は、孔子と親しい国際的任侠道の大親分、顔濁鄒の本拠地であり、政府転覆さえ企てなければ、やり手の霊公も孔子を優遇する気が十分だった。だから最初の衛国滞在から逃げ出したにも関わらず、何度か戻っているわけ。
また顔濁鄒は、弟子の子路の縁戚であり、衛国には、アキンド子貢の本店もあった。その意味で衛国は孔子にとって、第二の故郷とも言え、衛国公に味方しそうな雰囲気はあっただろう。だが孔子は冷静に、衛国公に手を貸しても、一門の利益にはならないと判断した。
孔子はいい先生ではあったが、冷徹な革命家でもあったのだ。


孔子は政治工作に放った弟子のうち、公冶長には娘を妻合わせて優遇したが、司馬牛は見殺した。革命家の孔子は、革命のためなら非情になれる人物でもあった。ただし上級貴族出の司馬牛は、孔子塾に身分差別を持ち込んだ形跡がある。それが孔子には許せなかったのである。
なお本章は、論語公冶長篇22との重出である可能性がある。
余話
他人の食い物に仕立て
上記の通り「仁」が春秋の君子らしさだったのは孔子の時代までで、孟子が「仁義」を発明してからは情けや憐れみの意味となった。だが中国人にとって仁義は他人にやらせるもので、決して自分が実践してはならなかった。そうでもないとよってたかって食い物にされるからだ。
ドストエフスキーが『白痴』で描いた通りで、この現実は時代と共に中国人周知の公然的事実となり、明末の笑い話集『笑府』には、ただの一語も「仁」が出てこない。もはやからかい倒す対象でもなくなっていたからで、これもまた中華文明の教える智恵の一つになっている。
道徳的説教がたいがい失敗に終わるのは、「お前だってメシを食ったり異性といちゃついたり屁を垂れたりしているくせに」と、説教相手を操作しようとするさもしい根性を見透かされるからで、気の利いた子供でもこの程度の判別力は持っている。
聞けば今どきの親御さんには、論語業者に金を払って、子供に説教して貰ったりする人があるようだが、中華文明的見地からは、止めておいた方がよろしいと思う。すでに親のさもしさを子は見抜いているか、いずれ気が付いてものすごく怨まれるかのどちらかだからだ。
ブッダの言う因果応報は、これに限ればその通りで、用心するに如くはない。そもそも論語を道徳的に読んでいる時点で、「私は漢文が読めません」と白状しているのと同じだから、そういう業者にお金を渡すのは、ものすごく間抜けゆえにおすすめできない。
それにお子さんを、他人の食い物に仕立て上げてどうするというのですか。




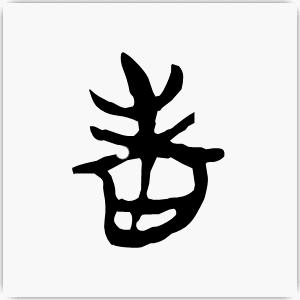

コメント