仁とは何か
論語における「仁」の意味は、大きく二つに分かれる。一つは現伝の儒教的解釈で、道徳的な意味をもち、薄い漢和辞典や国語辞典にさえ、それぞれに別の意味が載っている。つまりはっきりしない。世間がそれでよしとするのは、その程度しか論語に期待していないからだ。
もう一つは、孔子の肉声としての「仁」である。そのほとんどが庶民である孔子の弟子は、身分制社会の春秋時代にあって、官僚となることで身分差別を抜け出し、貴族になろうとする者たちだった。その彼らが身につけるべき「仁」とは、”貴族らしさ”に他ならない。
古漢字=古い中国語としての仁

「仁」(『甲骨文合集』 1098)
孔子の生きた春秋時代、「仁」とは忘れられた言葉だった。「仁」の初出は殷墟の甲骨文だが、そこでの「仁」の意味はよく分からない。一例しか知られない上に、前後の文字が解読されておらず、意味の推測すらできないからだ。ゆえに「仁」でないとする学説もあるらしい。
…癸未…方于…羌係一…馬二十丙㞢(又)□。一月,才(在)鼻卜。 二
(釈文に入っていないが、左から三行目の上端に見られる)
そしてその後「仁」は、長く遺物から見られなくなる。論語の時代、「仁」が通用したか極めて心細い。
「先秦甲金文簡牘詞彙資料庫」で西周から春秋までに見える例は三例しか無い。
- 魯白愈父盤(『殷周金文集成』101113)
「魯白愈父乍鼄姬(仁)般。其永寶用。」 - 魯白愈父鬲(『殷周金文集成』00690-00695)
「魯白愈〔父〕乍鼄姬(仁)羞鬲。其永寶用。」 - 魯白愈父鬲(『殷周金文集成』04566-04568)
「魯白俞父乍姬(仁)𠤳。其萬年。壽永寶用。」
これらで「仁」と釈文されているのは![]() 字だが、これは「仁」ではなく「二千」だろう(論語語釈「千」)。「漢語多功能字庫」千条が「二」だけ「二千」と書かないのは、中国らしく常に国家権力を背景にした学界の権威に対する、「報道しない自由」というやつだろうか。
字だが、これは「仁」ではなく「二千」だろう(論語語釈「千」)。「漢語多功能字庫」千条が「二」だけ「二千」と書かないのは、中国らしく常に国家権力を背景にした学界の権威に対する、「報道しない自由」というやつだろうか。
按「千」字非從「十」,古人借用「人」來表示千數,加「一」於「人」字中間一豎,用作「一千」之合文。另甲金文有於「人」字加三畫以為「三千」,加四畫以為「四千」等,可見加「一」於「人」的字本為合文。
仮に「仁」だとしても、青銅器の道具名の一部で何を意味しているのか分からない。その「仁」が再び明瞭にブツで現れるのは、戦国時代半ばの竹簡や金文からである。金文の例は甲骨文を用いた殷の滅亡から約730年が、孔子が世を去ってから約160年が過ぎていた。
「中山王鼎」(BC316頃)

…是從天降休命于朕邦、有厥忠臣、喜克順克卑、亡不率仁敬順天德、以佐右寡人使智。…
…是れ天の休を降して朕が邦于命ずるに従りて、厥れ忠臣有りて、喜びて克く順い克く卑い、仁敬率さ不る亡く天徳に従い、佐右以て寡人をして智から使む。…
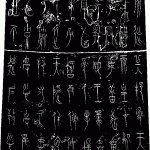
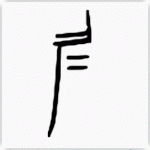
(幼くして即位した私は、)ありがたくも天が幸運を我が国に下して命じた結果、世にも希な忠実な家臣が現れて、(その家臣が)喜んで私に従い、奉仕し、いつも精一杯私を慈しみ敬いながら天の威光に従い、守り役に私を補佐させて私にもののことわりを教えさせた。
ここでは明らかに、「仁」を道徳的なそれの意で用いている。それが「仁義」を説いた孟子の生きた戦国時代の解釈というものだ。しかしだからと言って、孔子の口から出た「仁」まで、孟子の言う道徳的な何か、と解するわけにはいかない。孟子は孔子の学説の改造者だからだ。
現伝のキリスト教がイエスの教えと言うより、むしろパウロ教であるように、現伝の儒教は孟子教である。希代の世間師だった孟子は、ほぼ滅んでいた儒家を再興すると同時に、彼に都合のよい再解釈を行って戦国の諸侯に売りつけた。中山王もその教説を知っていたはずである。
『字通』は「仁」を次の通り説く。
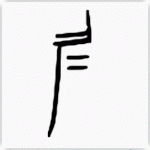
「仁」(「中山王鼎」金文・『説文』古文)[会意]人+二。〔説文〕八上に「親しむなり」とし、「人二に從ふ」と二人相親しむ意とする。金文や、〔説文〕に古文として録する字形は、人が衽(しきもの)を敷いている形で、二人相人偶するという形ではない。〔儀礼、士昏礼〕「衽を奧に御(すす)む」の注に「臥席なり」とあり、衽席を用いて安舒であることから、和親・慈愛の意が生まれたのであろう。一般に徳目に関する字は、正は征服、義は犠牲、道は道路の修祓、徳は遹省(いつせい)巡察を原義とするもので、具体的な行為や事実をいうものであった。のち次第に抽象化して、高度の観念に達する。仁もまた衽席(じんせき)によって和むことから、和親・仁愛の意に展開したものであろう。
つまり白川博士は、衽=敷物に座るとゆったりするから、仁に和親や慈愛の意が生まれたという。これは無理ではなかろうか。カールグレン上古音で衽はȵi̯əmであり、仁のȵi̯ĕnと極めて近いが、敷物→のんびり→仁は道徳的な意味、とするのは、個人的な感想の度合いが強すぎる。
(◌̥は無声音を、◌̯は音節副音=弱い音を、 ̆ブリーヴは極短音を、əはエに近いアを示す。)

(甲骨文)
音から敷物説を受け入れるにせよ、より古い甲骨文を見ると、人が敷物に対して尻を向けている。人体には目が前にしかなく、敷物に尻を向けて敷けるような構造を持っていない。もし博士の言う通り仁=人が敷物を敷く姿なら、字形は か
か でなければならないはずだ。
でなければならないはずだ。
甲骨文や金文の「人」は、左向きだけで書かれたわけではない。必要に応じ右向きにも書いた。戦国文字以降は左向きに固定され、亻へと変化したが、それ以前はそうでない。だからもし人が敷物を敷く姿なら、文字作家はためらわず右向きに書いたり、配置を変えただろう。
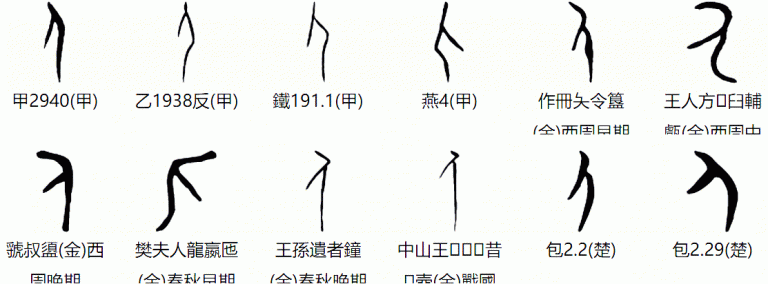
白川漢字学が時にインチキ呼ばわりされる原因となる、主観的断定は排除せねばならない。そのつもりで再度金文や古文を見直すと、「仁」の原義は”敷物に座った人”であると分かるだろう。中国に椅子が入るのは唐になってからで、それまでは皇帝もまた、敷物に座った。
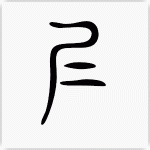
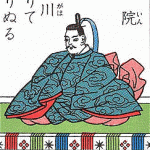
人は座るとき敷物に尻を向ける。平安朝の天皇や行楽のご家族と同じである。
一方で、「仁」のカールグレン上古音はȵi̯ĕnで、同音は「人」だけ。藤堂上古音の「仁」と「人」も、nienで全く同じ。そして人の口から野放図に生まれる口語よりも、大勢の同意が要る文字はおおかた少ない。ところがȵi̯ĕnの現象が逆なのは、特にその必要があったからだ。
つまり同じȵi̯ĕnなのに、区別する必要があった。”ひと”だが特別な”ひと”。わざわざ書き分ける必要がある人。それは古代ゆえに、身分が違うからだろう。そして中国古代の貴人は敷物に座った。庶民も時に筵ぐらい敷いただろうが、常に敷物を伴う印象を持たせる人がいた。
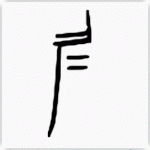
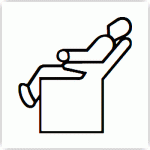
それは、貴族だろう。つまり「仁」とは”貴族”、または”貴族らしさ”である。そういえば、滅亡寸前まで旧国鉄は、いかなる山奥にも急行を走らせ、半室だけでもグリーン車を繋いだが、理由は上級公務員の出張旅費に、グリーン料金が含まれていたかららしい。官僚貴族である。
「彼は人物だ」と聞いて、”その男はヒトである”と理解する者はまずいない。A→Bで、かつA=Bである場合、聞き手はAとBの間に、何らかの違い=新しい意味を見出そうとする。「カモメはカモメ」という例外は、「これまでカモメでなかった」という前提があるからだ。
「皮人為仁」という春秋時代の中国語は、上掲の通り音としては、「かの人、人たり」を意味するだけだ。だが聞き手は=で結ばれた前後のȵi̯ĕnに、違う意味を見出そうとする。本来決して=ではないはずの、Я Чайка”私はカモメ”に違和感を感じないのと、それは同じだ。
そして元は、単なる通信符号としての「カモメ」に過ぎなかったのが、何やら人類史的に偉大な言葉として、左翼人士にもてはやされた。偉業ではあるが、もてはやしの程度は、真っ赤な脳内補完が強すぎたと言うべきである。では「かの人はȵi̯ĕn」である、をどう解すべきか。
やはり新たな価値をつけ加えて、古文で言う「よき人」=”貴族”となるだろう。
論語における仁
孔子が、世間から忘れられて久しい「仁」を、教説の中心に据えたのは、キャッチコピーだったかも知れない。現代日本の詐欺師が横文字を多用するように、耳慣れない言葉は新鮮だからだ。論語の時代の誰よりも読書家だった孔子は、過去の記録から「仁」を再発見したのかも。
その「仁」の定義を、孔子は最も優れた弟子である顔回に簡潔に説明している。
この言葉は、漢字の歴史的に後世の創作である証拠を持たない。つまり孔子の肉声と言ってよい。その中で孔子は、我欲を抑え礼儀作法を見事に演じきるのを「仁」だと言った。人前で涼しげに振る舞い、挙措動作が優雅であることは、古代も現代も、貴族らしさと一致する。
「礼」もまた、中華帝国の儒者官僚が主張した「行儀作法」に限られない。戦時に従軍義務があり、普段は政論や外交交渉に忙しい春秋の君子にとって、とっさに勝ちをつかむための常識に他ならない(論語における「礼」)。かように「仁」が”貴族(らしさ)”だからこそ、孔子はこうも言った。
子曰、人而不仁、如禮何。人而不仁、如樂何。(論語八佾篇3)
子曰く、人にし而仁ならざらば、礼の如きや何ならん。人にし而仁ならざらば、楽の如きや何ならん。
※条件反射のように「いかん」と読むのはもうやめよう。書き下しとは要するに、最も適切な日本古語に置換できればいいのだ。
先生が言った。「貴族らしくしようともしない者に、貴族の常識が何の役に立つ。音楽が何の役に立つ。」
孔子塾は官僚予備校である。礼・楽=礼法と音楽の素養が無い新弟子にこれらを授け、さらに他の必須科目、すなわち書(読み書き)、射(弓術)、御(戦車の操縦)、数(算術と帳簿)を教える事で、貴族として通用する人材を育成した。これら必須科目を合わせて六芸という。
礼儀作法が貴族に必須であることは言うまでも無い。音楽が求められたのは、政論や外交で交わされる言葉に、春秋の中華世界共通の歌詞集とされた『詩経』の歌詞が、しばしば織り込まれたからであり、楽の習得は、外国語学習と典雅な言葉を覚える古典学習を兼ねていた。
書と数は、官僚として文書や統計を扱う必要からであり、射と御は、当時の貴族に従軍義務があったからだ。論語時代の戦は、弩(クロスボウ)を扱う歩兵が出現して、戦車戦の一騎討ちから歩兵の集団戦へと主役が移り始めてはいたが、なおも貴族は、戦車で戦を指揮した。

つまり六芸は、全て貴族になるための教養であり、貴族になるつもりが無いなら、全く意味が無い、と孔子は言っているのだ。従来の解釈のように、「人情の無い者には、礼も楽も無用だ」と解して、礼楽とあまり関係の無い人情を引っ張り出さなくとも、この章は解読出来る。
さらに論語には、「仁」を”貴族(らしさ)”と解さないと読めない章がある。
孟武伯問、子路仁乎。子曰、不知也。又問、子曰、由也、千乘之國、可使治其賦也、不知其仁也。(論語公冶長篇7)
孟武伯問う、子路は仁なる乎。子曰く、知らざる也。又問う、子曰く、由也、千乗之国、其の賦を治め使む可き也、其の仁を知らざる也。


孟武伯が問うた。「子路さんは貴族と言えますかね。」先生が言った。「分かりませんなあ。」また問うた。先生が言った。「子路は、この魯国程度の軍事を任せることは出来ますが、貴族らしいかどうかは分かりませんなあ。」(同様の問答が他の弟子にも続く)
子路は記録のある孔子の最初の弟子だが、孔子が「由」と名を呼び捨てしているのに、孟武伯が「子路」=路さん、と敬称で呼んでいることに注目。孟武伯とは、魯国門閥家老の一家、孟孫氏の若き当主で、父の孟懿子は、孔子を政界に押し上げた、孔子と同世代の友人である。
孔子にとって孟武伯は「友人の坊や」であり、孟武伯にとって孔子は、子供の頃から世話になった「おじさま」だった。孔子の没後になるが、孟武伯は主君である哀公を、事実上国から追った「やり手」であり、これから当主として政界に乗り出そう、そんな頃の対話である。

だから孔子の弟子たちの協力を頼めるかどうか、「おじさま」に聞いたのだ。それゆえ孔子の弟子の子路にも、遠慮して「子路」と敬称した。孟武伯は弟子たちの「貴族らしさ」に期待したわけで、「人情」をただしたのでは全くない。そしてそう読んでは分からない。
別の例を挙げよう。
樊遲…問仁。曰、仁者先難而後獲、可謂仁矣。(論語雍也篇22)
樊遅仁を問う。曰く、「仁者は難きを先にし而て後に獲、仁と謂う可き矣。」
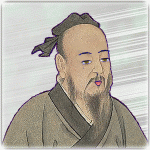

樊遅が貴族らしさを質問した。(先生が)言った。「これぞ貴族と言える者は、困難を解決した後でその報酬を得る。これこそサムライと言えるだろうな。」
樊遅は孔子の若い弟子で、孔子の御者を務めたことから、士=下級貴族だったらしい。さて情け深い者が、困難に立ち向かってその報酬を得ることは皆無とは言えないが、本章はむしろ、役人としての心構えを説いた話であって、情けうんぬんを持ち出すとわけが分からなくなる。
もう一つの証拠を挙げよう。
宰我問曰、仁者雖吿之曰、井有人焉。其從之也。子曰、何爲其然也。君子可逝也、不可陷也。可欺也、不可罔也。(論語雍也篇26)
宰我問うて曰く、仁者は之に吿げて、井に人有り焉と曰うと雖も、其れ之に従う也。子曰く、何ぞ其れ然りと為さん也。君子は逝く可き也、陷る可からざる也。欺す可き也、罔う可からざる也。


宰我が質問して言った。「仁者に”井戸に人が落ちた”と言ったら、のこのこと井戸に入りますか?」先生が言った。「どうしてそうなる。君子は行きはするだろうが、井戸に入りはしないぞ。だませはしても、目が見えなくなりはしないぞ。」
ここで孔子が、仁者を君子と言い換えて答えているのに注目。君子とは、孟子が道徳的な意味をつけ加える前、孔子の生前にはただ”貴族”を意味するだけだった。つまり本章は、人を導く立場にある貴族は、人の危難を救いには行くが、だまされはしない、と孔子が言ったのだ。
やり過ぎだった「仁」
隆慶一郎『一夢庵風流記』に、「お前の親父は、武士じゃなかったから、武士らしくしなけりゃいけなかったんだ」というセリフがある。小説ではあるが、それでもこの言葉は、古今東西の人間界に共通するものを突いている。それは孔子の生きた、春秋時代にも当てはまる。
春秋時代は、鉄器の普及期だった。鋼が出来なかったから刃物にはならなかったが、農具や工具が大幅に性能を高め、安くなって普及したのは間違いない。当然生産は上がり、旧来の貴族ではない者が力を蓄えるようになる。孔子が亡命先の衛で頼った、顔濁鄒親分もその一人。
顔濁鄒は『史記』にも載った人物で、領地も持たないのに、魯周辺の数カ国にまたがる勢力圏を持つ、任侠道の大親分だった。社会に余剰生産が無ければ、決して出ない人物である。その親分が、自分の屋敷に孔子が来ると、子分とこぞって入門したと『史記』が書いている。
それは史実だろう。現在でも無教養の小金持ちが骨董に凝って、手っ取り早い自己実現をしたがるように、卑賤から身を起こした者は、最後に身分を欲しがる。孔子に学んで貴族らしくなり、名実共に貴族になりたかったのだ。事実顔濁鄒はのちに、斉から爵位を受けている。
孔子もその弟子も、みな社会の底辺と言ってよい身分から身を起こした。そんな彼らは、立ち居振る舞いを門閥貴族よりも貴族らしくしたはずだ。そうでなければ、出世してもニセモノだとバカにされるだろう。だからとりわけ礼儀作法については、誰の目にも大げさだった。
子曰、事君盡禮、人以爲諂也。(論語八佾篇18)
子曰く、君に事えるに礼を尽くさば、人は以て諂いと為す也。
先生が言った。「主君に仕えるに当たって、こまごまとお作法通りにすると、人は”おべっかだ”といって馬鹿にするのだ。」
孔子自身がこう歎いただけでなく、他人からもそう見えた。


そもそもあの孔丘という男は、もったいぶった顔つきをし、言葉を大げさにして世間をだましています。鳴り物で人を集め、宮殿の上り下りをわざとらしくして儀礼だと言い張り、貴人の前では小走りの礼を見せつけますから、確かに学問は立派でも、政治を議論させるわけにはいきません。(『墨子』非儒下篇)
晏嬰とは孔子と同世代の斉の宰相で、これを記した墨子は、孔子と入れ替わるように春秋戦国の世を生きた。ほぼ同じ文が『史記』にも載る。孔子とその一門がやった礼儀作法は、彼らが貴族でなかったからこそ、貴族以上に貴族らしかった。その結集が、「礼」に他ならない。
孔子一門は、こうした孔子の趣味とまで言える貴族主義を奉じる、今で言うオタサーでもあった。孔子の言う理想の貴族を演じて高まる、コスプレ集団だったのだ。顔淵など「徳」に優れると評された弟子は、孔子と貴族趣味が一致したのであり、実務を評価されたのではない。
(ただしそれは陽の当たる実務であり、陽の当たらない実務に顔淵は優れていた。)
孔子は不世出の学者だったが、時代認識に欠陥があった。弟子の冉有に、「突破戦では歩兵に矛を持たせよ」と教えておきながら、廃れつつあった貴族の芸能、弓術と戦車の操縦にこだわった。それは孔子が味わった、生き地獄のような身分差別の結果である。責められはしない。
孔子は自分の経験から、社会の底辺にある人間が、どうやって身分差別を乗り越えるかを教えた。そこには、何ら非難すべき嗜虐趣味は無い。弟子のためによかれと思った精華がある。大貴族出身の司馬耕を見殺しにした史実はあるものの、だからこそ師匠として慕われた。
2,500年の長きにわたってである。
その後の仁
孔子没後、儒家は一旦滅んだ。孔子没後一世紀のちに生まれた孟子がそう証言している。

聖王不作,諸侯放恣,處士橫議,楊朱、墨翟之言盈天下。天下之言,不歸楊,則歸墨。
聖王あらわれず、諸侯ほしいままにほしいままをなし、処士よこしまにかたり、楊朱、墨翟の言、天下にみつ。天下の言、楊に帰せざらば、則ち墨に帰す。(『孟子』滕文公下)
そういった世に生まれて、孟子は歎いたのではない。舌なめずりしたのだ。たまたま孔子の父の出身地に生まれたという縁から、孟子は儒家を知ったらしい。そこで没落した儒家の当主、孔子の孫・子思に師事し、その教えを受け継いだと当人は言い回っている。
子思は孔子の一人息子、孔鯉の息子で、孔子は孔鯉にも、子思にもその素質無しと見てか、まともに学問や技芸を授けなかった。だからこそ子思は、儒家の当主に祭り上げられても、曽子を頼るほか無かった。だが曽子は儒者ではなく、孔子家の家事使用人でしかなかった。
同様に、孔子の優れた弟子たちの系統は他国に移った上、細々と生き残っているに過ぎなかった。一応子思という宗家があることに遠慮したというのもあったろうが、端的に儒家は儲からず、食えなかったからだ。子游派のように、開き直って冠婚葬祭業に徹した派閥もある。
対して墨家は儲かった。大規模土木や築城、攻城の技術者集団だった墨家は、喜んで諸侯が雇った。楊朱=列子派は、墨家の昆虫の如き合理性に嫌気が差した人々に、道家と共に受け入れられた。学んで役人になるにも、すでに廃れた射や御を教える儒学は、時代遅れだった。
そういう事情で、孟子が子思に学んだとしても、断片的にしか儒学を学べなかったはずだ。それより孟子には、創作の才が有った。孟子は儒家の衰微と共に、再び忘れられ始めた「仁」に着目し、貴族(らしさ)→立派な貴族らしさ→とても有り難い道徳的態度、へと作り替えた。
時代に合わせ、作り替える必要があったのだ。

だから孟子は「仁」ではなく、ほぼ「仁義」として売り出した。義とは”正しい”の意である。買い取り切った諸侯は出なかったが、一時的に有り難がる振りをし、捨て扶持をくれた諸侯は出た。中でも当時最も知られた学士院である、斉の「稷下」に交わったのが大きかった。
捨て扶持の額が大きかったのもあるが、そこで打ち上げれば、全中国に伝わったからだ。だから戦国期では、仁=道徳的な何か、になった。孟子はそれを説明して、仁=惻隠(推察する)の情、義=羞恥心、と言っている(『孟子』告子上)。だが常にそうでは無かった。
『孟子』の冒頭にあるように、相手の弱点を見て語義を変え、耳に入りやすいよう諸侯に売りつけた。要は売り言葉であり、定義はどうでもよかったのである。実際孟子は論敵から、「適材適所を実践するのが、貴殿の言う仁義ではないか」と言われている。
為天下得人者謂之仁。(『孟子』滕文公上)
そして孟子没後は秦帝国を経て、その学派が漢帝国の国教となった。仁=道徳的何か、は固定化された。仁=貴族という語義が忘れられた時代では、仁義と聞けば、人の正しさ、と聞いた者は思った。人間の正義は人間の数だけある。
だから仁義という言葉は、自分の(勝手な)筋を通すこと、と思う者もいたし、人を憐れむこと、と思う者もいた。それゆえ意味が多様になった。その解釈が、現代日本の辞書にも引き継がれている。
※なお「仁」に”果実の種の中身”の語義が出来たのは、確認できる初出は後漢末から三国にかけての『傷寒論』。どうしてそうなったかは推測の他はないが、「妊」ȵi̯əm→「仁」ȵi̯ĕnの、単なる言葉遊びからだろう。後漢の度が過ぎた偽善を、からかったのかも知れない。
發汗後,不可更行桂枝湯。汗出而喘,無大熱者,可與麻黃杏仁甘草石膏湯主之。
発汗の後、更に桂枝湯を行る可からず。汗出でて喘ぎ、大なる熱無き者は、麻黄杏仁甘草石膏湯を与うべく、之を主る。(『傷寒論』辨太陽病脈證并治)
付録:辞書上の「仁」
孔子が提唱した道徳観念。礼にもとづく自己抑制と他者へ思いやり。忠と恕の両面を持つ。(『広辞苑(第四版)』)
※忠と恕を言ったのは孔子でなく曽子で、しかも後世の創作である(論語里仁篇15)。
儒教に於ける最高の徳。人道の根本。(『新字源』)
自分と同じ仲間として、すべての人に接する心。隣人愛や同情の気持ち。また、そのような気持ちをもつさま。(『学研漢和大字典』『漢字源』)
あわれむ、おもいやり、なさけぶかい。…人としての徳、最高の徳。(『字通』)
人と二の合字。二人が彼此相親密する意。又、慈愛の徳をいい、善行の綜称とする。(『大漢和辞典』)
二+人。人と人との間に通う親しみの意味を表す。 (『新漢語林』)
仁愛:孔子の教えを一貫している政治上・倫理上の理想で,一切の諸徳を統べる主徳.(『中日大字典』)
金文は「人」と「二」の字形で構成。「人」は音をも表す。意味は人と人との親密な関係。戦国時代の竹簡は「心」の字形で構成。「身」の音。一説には「心」は人が他人に向ける気配りで、「身」の音は意味をも表し、妊娠中の女性を意味する。だから「仁」とは他人に対する心からの気配りを言うという。
『論語』顔淵篇22、「樊遲問仁,子曰:『愛人。』」『春秋左氏伝』隠公六年、「仁の心を養うこと、隣国との友好関係は、国の宝である。」『説文解字』「仁とは親しむことだ。人と二の字形で構成。忎は、仁の古い字形で、千と心の字形で構成。𡰥は、仁の古い字形で、尸の字形で構成されているかもしれない。」
金文は「人」ではなく「尸」の字形で構成され、『説文解字』にいう古い字形と同じ。古い字形の「尸」は「人」を描いた手法の一つで、あぐらを掻いた人の象形。「尸」は「仁」の音をも表す。『説文解字』にいう古い字形の「忎」は「身」と「心」で構成され、戦国時代の「仁」の字形をくずした文字であり、「千」は「仁」の音を表す。
金文では仁愛を意味した。中山王鼎、「克順克卑,亡(無)不䢦(率)仁」の意味は、”忠義を尽くし、仁徳に背くことがなかった”。
戦国時代の竹簡では仁徳を意味した。『郭店楚簡』唐虞之道の簡2号、「利天下而弗利也,仁之至也。」同じく性自命出の簡55号、「䈞(篤)於仁者也」とあり、ひたすら仁徳を堅持することを意味している。
判子の文字に使われた場合でも仁徳を意味し、『璽彙』4507に「忠仁」とある。
漢代の帛書では音を通じて「仞」と書かれ、馬王堆帛書『老子甲本』第57行に、「百仁(仞)之高,台(始)於足[下]。」とあり、『老子』第六十四章に「千里之行,始於足下。」とある。(漢語多功能字庫 仁条)

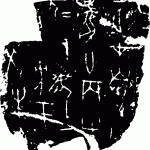


コメント