論語:原文・書き下し
原文(唐開成石経)
子曰二三子以我爲隱乎吾無隱乎爾吾無行而不與二三子者是丘也
校訂
東洋文庫蔵清家本
子曰二三子以我爲隱子乎吾無隱乎爾/吾無所行而不與二三子者是丘也
後漢熹平石経
(なし)
定州竹簡論語
□曰:「二三子以我為隱子a乎?吾無隱乎壐。吾無行而166……與二三子b,是丘也。」167
- 子、阮本無、皇本有。
- 今本「子」下有「者」字。
標点文
子曰、「二三子、以我爲隱子乎。吾無隱乎壐。吾無行而不與二三子、是丘也。」
復元白文(論語時代での表記)




























※隱→陰・壐→爾。論語の本章は「壐」「行」の用法に疑問がある。本章は戦国時代以降の儒者による捏造の可能性がある。
書き下し
子曰く、二三たりの子、我を以て子に隱せりと爲す乎。吾隱すこと無き乎壐。吾は行ひ而二三たりの子と與にせ不るは無し。是れ丘也。
論語:現代日本語訳
逐語訳

先生が言った。「諸君、私が諸君に隠し事をしていると言うのかね。私には全く隠すことはないよ。私には、諸君と共に行わない事はない。これがわたし丘だよ。」
意訳
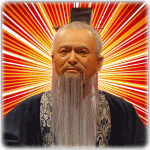
知りたければ何でも聞きなさい。もったいつけたりせんよ。知とはそういうものだ。それが私の信念だから。
従来訳
先師がいわれた。――
「お前たちは、私の教えに何か秘伝でもあって、それをお前たちにかくしていると思っているのか。私には何もかくすものはない。私は四六時中、お前たちに私の行動を見てもらっているのだ。それが私の教えの全部だ。丘という人間は元来そういう人間なのだ。」下村湖人『現代訳論語』
現代中国での解釈例
孔子說:「學生們,你們以為我教學有保留嗎?我沒有保留,我沒什麽不是同你們一起做的,孔丘就是這樣的人。」
孔子が言った。「学生諸君、お前達は私の教えに隠し事があると思っているのか?私には隠し事など無い、私には、お前達と共にしないことなど無い。孔丘とはそのような人物だ。」
論語:語釈
子曰(シエツ)(し、いわく)

論語の本章では”孔子先生が言った”。「子」は貴族や知識人に対する敬称で、論語では多くの場合孔子を指す。「子」は赤ん坊の象形、「曰」は口から息が出て来るさま。「子」も「曰」も、共に初出は甲骨文。辞書的には論語語釈「子」・論語語釈「曰」を参照。
この二文字を、「し、のたまわく」と読み下す例がある。「言う」→「のたまう」の敬語化だが、漢語の「曰」に敬語の要素は無い。古来、論語業者が世間からお金をむしるためのハッタリで、現在の論語読者が従うべき理由はないだろう。
二三子(ジサンシ)
論語の本種では”君たち”。孔子の弟子に対して、関守が語りかけた言葉。「ニ」を「ニ」と読むのは呉音。「子」は貴族や知識人に対する敬称。ここでは「きんだち」と訓読し、弟子に対する敬称。近代日本語で「諸子」と呼ぶのに近い。辞書的には論語語釈「二」・論語語釈「三」を参照。
以(イ)


(甲骨文)
論語の本章では”~を”。初出は甲骨文。人が手に道具を持った象形。原義は”手に持つ”。論語の時代までに、名詞(人名)、動詞”用いる”、接続詞”そして”の語義があったが、前置詞”~で”に用いる例は確認できない。ただしほとんどの前置詞の例は、”用いる”と動詞に解せば春秋時代の不在を回避できる。詳細は論語語釈「以」を参照。
我(ガ)


(甲骨文)
論語の本章では”わたし”。初出は甲骨文。字形はノコギリ型のかねが付いた長柄武器。甲骨文では占い師の名、一人称複数に用いた。金文では一人称単数に用いられた。戦国の竹簡でも一人称単数に用いられ、また「義」”ただしい”の用例がある。詳細は論語語釈「我」を参照。
古くは中国語にも格変化があった名残で、一人称では「吾」(古代音ŋag)を主格と所有格に用い、「我」(同ŋar)を所有格と目的格に用いた。ただし甲骨文の時代ですでに、両者の混同現象が見られる。
爲(イ)


(甲骨文)
論語の本章では”作る”→”…だとみなす”。新字体は「為」。字形は象を調教するさま。甲骨文の段階で、”ある”や人名を、金文の段階で”作る”・”する”・”…になる”を意味した。詳細は論語語釈「為」を参照。
隱(イン)


(秦系戦国文字)
論語の本章では”かくす”。初出は秦系戦国文字。論語の時代に存在しない。字形は「阝」”階段”+「爪」”手”+「工」「尹」”筆を持った手”+「心」。高殿でこそこそと分からないように思うところを記す様。同音に殷”さかん”・慇”ねんごろ”と、隱を部品とした漢字群。戦国最末期の竹簡に「隱官」とあり、判決を受けた犯罪者がまだ捕まっていない累犯者を自分で捕まえるよう命じられることであるらしい。論語時代の置換候補は近音の「陰」。詳細は論語語釈「隠」を参照。
乎(コ)


(甲骨文)
論語の本章では、「かな」と読んで詠歎の意。この語義は春秋時代では確認できない。「乎壐」では二文字で「のみ」と読み、”…だけだよ”というやはり詠嘆の意。初出は甲骨文。甲骨文の字形は持ち手を取り付けた呼び鐘の象形で、原義は”呼ぶ”こと。甲骨文では”命じる”・”呼ぶ”を意味し、金文も同様で、「呼」の原字となった。句末の助辞や助詞として用いられたのは、戦国時代以降になる。ただし「烏乎」で”ああ”の意は、西周早期の金文に見え、句末でも詠嘆の意ならば論語の時代に存在した可能性がある。詳細は論語語釈「乎」を参照。
藤堂明保博士の学研『大漢和辞典』を引くと「乎」は以下の通り。
「下部の伸びようとしたものが、一線につかえた形と、上部の発散する形とからなる会意文字で、胸からあがってきた息がのどにつかえて、はあと発散することをあらわす。感嘆・呼びかけ・疑問・反語など、文脈に応じて、はあという息でさまざまのムードをあらわすだけで、本来は一つである。呼(はあとのどをかすらせて呼ぶ)の原字。」
従って
以我(え?私が)爲隱(隠してるって?)乎(ハァ)。
吾無(私にはないよ)隱(隠す事なんて)乎(ハァ)爾(本当に)。
という、孔子のため息が聞こえるような句と分かる。
吾(ゴ)


(甲骨文)
論語の本章では”わたし”。初出は甲骨文。字形は「五」+「口」で、原義は『学研漢和大字典』によると「語の原字」というがはっきりしない。一人称代名詞に使うのは音を借りた仮借だとされる。詳細は論語語釈「吾」を参照。
春秋時代までは中国語にも格変化があり、一人称では「吾」を主格と所有格に用い、「我」を所有格と目的格に用いた。しかし論語でその文法が崩れ、「我」と「吾」が区別されなくなっている章があるのは、後世の創作が多数含まれているため。
無(ブ)


(甲骨文)
論語の本章では”ない”。初出は甲骨文。「ム」は呉音。甲骨文の字形は、ほうきのような飾りを両手に持って舞う姿で、「舞」の原字。その飾を「某」と呼び、「某」の語義が”…でない”だったので、「無」は”ない”を意味するようになった。論語の時代までに、”雨乞い”・”ない”の語義が確認されている。戦国時代以降は、”ない”は多く”毋”と書かれた。詳細は論語語釈「無」を参照。
爾(ジ)→壐(ジ)


(甲骨文)
論語の本章では”…だけ”。この語義は春秋時代では確認できない。初出は甲骨文。字形は剣山状の封泥の型の象形で、原義は”判(を押す)”。のち音を借りて二人称を表すようになって以降は、「土」「玉」を付して派生字の「壐」「璽」が現れた。甲骨文では人名・国名に用い、金文では二人称を意味した。詳細は論語語釈「爾」を参照。


(秦系戦国文字)
定州竹簡論語の「壐」の初出は斉系戦国文字。ただし字体は「鉨」。現行字体の初出は秦戦国文字。下が「玉」になるのは後漢の『説文解字』から。字形は「爾」”はんこ”+「土」または「玉」で、前者は封泥、後者は玉で作ったはんこを意味する。部品の「爾」が原字。「璽」は異体字。同音は無い。戦国最末期「睡虎地秦簡」の用例で”印章”と解せる。論語時代の置換候補は部品の「爾」。詳細は論語語釈「壐」を参照。
行(コウ)


(甲骨文)
論語の本章では”行う”。この語義は春秋時代では確認できない。初出は甲骨文。「ギョウ」は呉音。十字路を描いたもので、真ん中に「人」を加えると「道」の字になる。甲骨文や春秋時代の金文までは、”みち”・”ゆく”の語義で、”おこなう”の語義が見られるのは戦国末期から。詳細は論語語釈「行」を参照。
而(ジ)


(甲骨文)
論語の本章では”…であって同時に”。初出は甲骨文。原義は”あごひげ”とされるが用例が確認できない。甲骨文から”~と”を意味し、金文になると、二人称や”そして”の意に用いた。英語のandに当たるが、「A而B」は、AとBが分かちがたく一体となっている事を意味し、単なる時間の前後や類似を意味しない。詳細は論語語釈「而」を参照。
不(フウ)


(甲骨文)
漢文で最も多用される否定辞。初出は甲骨文。「フ」は呉音(遣隋使より前に日本に伝わった音)、「ブ」は慣用音。原義は花のがく。否定辞に用いるのは音を借りた派生義だが、甲骨文から否定辞”…ない”の意に用いた。詳細は論語語釈「不」を参照。
與(ヨ)


(金文)
論語の本章では”共に”。新字体は「与」。初出は春秋中期の金文。金文の字形は「牙」”象牙”+「又」”手”四つで、二人の両手で象牙を受け渡す様。人が手に手を取ってともに行動するさま。従って原義は”ともに”・”~と”。詳細は論語語釈「与」を参照。
是(シ)


(金文)
論語の本章では”これは…だ”。初出は西周中期の金文。「ゼ」は呉音(遣隋使より前に日本に伝わった音)。字形は「睪」+「止」”あし”で、出向いてその目で「よし」と確認すること。同音への転用例を見ると、おそらく原義は”正しい”。初出から”確かにこれは~だ”と解せ、”これ”・”この”という代名詞、”~は~だ”という接続詞の用例と認められる。詳細は論語語釈「是」を参照。
丘(キュウ)


(金文)
孔子の本名(いみ名)。いみ名は目上か自分だけが用いるのが原則で、論語の本章ではつまり自称。文字的には詳細は論語語釈「丘」を参照。
也(ヤ)


(金文)
論語の本章では、「かな」と読んで詠歎の意。初出は事実上春秋時代の金文。字形は口から強く語気を放つさまで、原義は”…こそは”。春秋末期までに句中で主格の強調、句末で詠歎、疑問や反語に用いたが、断定の意が明瞭に確認できるのは、戦国時代末期の金文からで、論語の時代には存在しない。詳細は論語語釈「也」を参照。
論語:付記
検証
論語の本章は、春秋戦国時代を含めた先秦両漢の誰一人引用していない。事実上の再出は、後漢末から南北朝にかけて編まれた古注になる。だが文字史上は論語の時代に遡れ、「我」と「吾」の使い分けが春秋時代の文法に叶っており、孔子の教説に沿っている。本章は史実の孔子の言葉として扱ってよい。
解説
その孔子の教説とは、「知るを知ると為し、知らざるを知らざると為せ、これ知るなり」(論語為政篇17)である。
「怪力乱神を語ら」なかった孔子は(論語述而篇20)、学びや稽古によって、知らない事を無くしていくことが、世の中を明るくするという信念を持っていた。分かることによって恐れや引け目が消える。だから隠し事はオカルトを語るのと同様に、孔子の信念に反する。
もちろん孔子が隠し事をしなかったわけではない。政治工作については、普通の学徒だった一般の弟子には隠しただろう。だがそれは自分のためであると同時に、相手のためでもある。「基礎も学ばないのに、いきなり奥義を聞こうというのか」とはそういうことだ。
知るべきでないことを知ることも知るの範疇にある。幼児の火遊びが危険なように、見込みの無いまま戦を起こす当時の貴族を見て、孔子はその思いを強くしただろう。現実とはえげつないものであり、そのえげつに耐えうる者のみが知っていい事がある。
宮崎アニメのように、綺麗なものだけ見せるのもよいが、人間が一呼吸毎に、粘膜で万単位の微生物を殺していることもまた事実で、それを思うと夜も寝られなくなったり、無いことにして忘れるのは「知る」ことではない。知とはそんな生やさしいものではない。
中国史上初めて「知」を発明した孔子は、そんな知の硬く厳しい側面に無論気付いていた。だから弟子に何を聞かれても答えられた。だが相手を見て言葉を選んでいる事は明白で、同じ質問でも答えを変えているのが論語雍也篇22と上掲為政篇17の違いとなって現れている。
余話
引いてたら寿命が尽きる
訳者が必ず三冊の辞書を引きながら論語を読んでいるのは、諸橋徹次『大漢和辞典』は、分厚い分冊で全十四冊組という、つい最近中国政府が国家事業として作った『漢語大詞典』が出るまで、世界最大の中国語辞典だったから。

次に藤堂明保『学研漢和大字典』は、古代音から現代音まで、ありとあらゆる漢字の、時代ごとの音を全て収録した大部な辞書だからで、音から漢文や論語の意味に迫るには、今でも最も優れているから。現在は名を変えた後継版があるが、旧版で十分である。
白川静『字通』を使うのは、諸橋・藤堂両博士と異なり、漢字の形の研究に生涯を費やした成果だからであり、両博士の研究が及ばなかった、金文(青銅器に鋳込んだ古い文章)や甲骨文にまで考察が及んでおり、漢字の形から漢文や論語の意味に迫るには、最も優れているから。
辞書といえども漢文を扱うことから、儒者や漢学者の狂信から来るハッタリから関係皆無とはいかないが、少なくとも漢字の意味に客観的な根拠があって、論語の解説本よりよほど信用できる。そもそも辞書を書けるというのは、調べることに怠惰では、出来ることではないから。
詳細は論語解説「漢文が読めるようになる方法2022」を参照。





コメント