論語:原文・書き下し
原文(唐開成石経)
子曰仁逺乎哉我欲仁斯仁至矣
校訂
東洋文庫蔵清家本
子曰仁逺乎哉我欲仁斯仁至矣
後漢熹平石経
(なし)
定州竹簡論語
……曰:「仁遠乎哉?我欲仁,斯176……
標点文
子曰、「仁遠乎哉。我欲仁、斯仁至矣。」
復元白文(論語時代での表記)













※仁→(甲骨文)・欲→谷。論語の本章は、「乎哉」の用法に疑問がある。
書き下し
子曰く、仁遠き乎哉。我仁を欲まば、斯に仁至り矣。
論語:現代日本語訳
逐語訳

先生が言った。「貴族らしさは遠くにあるのではないなあ。私が貴族らしさを求めれば、この場に貴族らしさがきっとやって来る。」
意訳

貴族になるのはそう難しいことではないぞ。自分が貴族だと思えば、もう貴族だ。
従来訳
先師がいわれた。――
「仁というものは、そう遠くにあるものではない。切実に仁を求める人には、仁は刻下に実現されるのだ。」下村湖人『現代訳論語』
現代中国での解釈例
孔子說:「仁離我們很遠嗎?我想要仁,仁就來了。」
孔子が言った。「仁は我らからそんなに遠くにあるものか?私が仁を求めるとき、仁はすぐにやって来る。」
論語:語釈
子曰(シエツ)(し、いわく)

論語の本章では”孔子先生が言った”。「子」は貴族や知識人に対する敬称で、論語では多くの場合孔子を指す。「子」は赤ん坊の象形、「曰」は口から息が出て来るさま。「子」も「曰」も、共に初出は甲骨文。辞書的には論語語釈「子」・論語語釈「曰」を参照。
この二文字を、「し、のたまわく」と読み下す例がある。「言う」→「のたまう」の敬語化だが、漢語の「曰」に敬語の要素は無い。古来、論語業者が世間からお金をむしるためのハッタリで、現在の論語読者が従うべき理由はないだろう。
仁(ジン)


(甲骨文)
論語の本章では、”貴族(らしさ)”。初出は甲骨文。字形は「亻」”ひと”+「二」”敷物”で、原義は敷物に座った”貴人”。詳細は論語語釈「仁」を参照。
通説的な解釈、”なさけ・あわれみ”などの道徳的意味は、孔子没後一世紀後に現れた孟子による、「仁義」の語義であり、孔子や高弟の口から出た「仁」の語義ではない。字形や音から推定できる春秋時代の語義は、敷物に端座した”よき人”であり、”貴族”を意味する。詳細は論語における「仁」を参照。
遠(エン)


(甲骨文)
論語の本章では”遠くにある”。初出は甲骨文。字形は「彳」”みち”+「袁」”遠い”で、道のりが遠いこと。「袁」の字形は手で衣を持つ姿で、それがなぜ”遠い”の意になったかは明らかでない。ただ同音の「爰」は、離れたお互いが縄を引き合う様で、”遠い”を意味しうるかも知れない。詳細は論語語釈「遠」を参照。
乎哉(コサイ)
二字で「かな・か・や」と読み、強い感嘆・疑問・反語を示す。
- (カナ)感嘆の気持ちをあらわすことば。「賜也賢乎哉=賜也賢なる乎哉」〔論語・憲問〕
- (カ)疑問の気持ちをあらわすことば。「若寡人者、可以保民乎哉=寡人(かじん)の若(ごと)き者は、もって民を保(やす)んず可きかな」〔孟子・梁上〕
- (ヤ)反問の気持ちをあらわすことば。「仁遠乎哉、我欲仁、斯仁至矣=仁は遠からんや、我仁を欲すれば、斯に仁至る」〔論語・述而〕
「乎哉」の用例は戦国末期までの出土品には見られない。論語の本章は元は「乎」または「哉」が一字だけで記されていたのを、秦漢帝国以降ににもったいを付けて二文字にしたか、あるいは本章そのものが後世の創作であるかのいずれかと考えるのが理に叶う。
しかも「乎」「哉」単独では、春秋末までに疑問の用例が見られない。従って論語の本章では詠嘆と見なすのに理がある。
『史記』の論賛(司馬遷が各篇の最後に付ける批評)には盛んに「乎哉」が用いられ、前漢中期までにはそう記すのが当たり前になっていたようだ。『春秋左氏伝』では「乎哉」はわずかにしか見られず、『国語』も同様。つまりその部分は前漢ごろに書き換えられたと見てよい。


(甲骨文)
「乎」の初出は甲骨文。甲骨文の字形は持ち手を取り付けた呼び鐘の象形で、原義は”呼ぶ”こと。甲骨文では”命じる”・”呼ぶ”を意味し、金文も同様で、「呼」の原字となった。句末の助辞や助詞として用いられたのは、戦国時代以降になる。ただし「烏乎」で”ああ”の意は、西周早期の金文に見え、句末でも詠嘆の意ならば論語の時代に存在した可能性がある。詳細は論語語釈「乎」を参照。


(金文)
「哉」の初出は西周末期の金文。ただし字形は「𠙵」”くち”を欠く「𢦏」で、「戈」”カマ状のほこ”+「十」”傷”。”きずつく”・”そこなう”の語釈が『大漢和辞典』にある。現行字体の初出は春秋末期の金文。「𠙵」が加わったことから、おそらく音を借りた仮借として語気を示すのに用いられた。金文では詠歎に、また”給与”の意に用いられた。戦国の竹簡では、”始まる”の意に用いられた。詳細は論語語釈「哉」を参照。
我(ガ)


(甲骨文)
論語の本章では”わたし”。初出は甲骨文。字形はノコギリ型のかねが付いた長柄武器。甲骨文では占い師の名、一人称複数に用いた。金文では一人称単数に用いられた。戦国の竹簡でも一人称単数に用いられ、また「義」”ただしい”の用例がある。詳細は論語語釈「我」を参照。
欲(ヨク)


(楚系戦国文字)
論語の本章では”求める”。初出は楚系戦国文字。新字体は「欲」。同音は存在しない。字形は「谷」+「欠」”口を膨らませた人”。部品で近音の「谷」に”求める”の語義がある。詳細は論語語釈「欲」を参照。
斯(シ)


(金文)
論語の本章では、”今この場に”。初出は西周末期の金文。字形は「其」”籠に盛った供え物を祭壇に載せたさま”+「斤」”おの”で、文化的に厳かにしつらえられた神聖空間のさま。意味内容の無い語調を整える助字ではなく、ある状態や程度にある場面を指す。例えば論語子罕篇5にいう「斯文」とは、ちまちました個別の文化的成果物ではなく、風俗習慣を含めた中華文明全体を言う。詳細は論語語釈「斯」を参照。
至(シ)
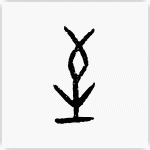

(甲骨文)
論語の本章では”至る”。甲骨文の字形は「矢」+「一」で、矢が届いた位置を示し、”いたる”が原義。春秋末期までに、時間的に”至る”、空間的に”至る”の意に用いた。詳細は論語語釈「至」を参照。
矣(イ)


(金文)
論語の本章では、”(きっと)~である”。初出は殷代末期の金文。字形は「𠙵」”人の頭”+「大」”人の歩く姿”。背を向けて立ち去ってゆく人の姿。原義はおそらく”…し終えた”。ここから完了・断定を意味しうる。詳細は論語語釈「矣」を参照。
論語:付記
検証
論語の本章は、春秋戦国時代の誰一人引用も再録もしておらず、前半「仁遠乎哉」部分が、後漢初期の『漢書』杜周伝に孔子の言葉として引用され、後半「我欲仁、斯仁至矣。」を含めた全文は、南北朝時代に編まれた『後漢書』列女伝に再出。
文字史的には論語の時代に遡れるものの、論語時代に於ける「乎哉」の不在を考えると、漢儒による偽作を疑いたくなる。とりあえず史実の孔子の発言として扱うが、話半分に読んだ方がいい。
仮に論語の本章が偽作の場合、従来訳のような解釈が適切と見るべきだ。だが「仁」を日本語化しないでは分けが分からないから、次のように解するべきだろう。
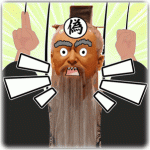
情け深い行為や心情は、自分とは関係の無い遠くにあるわけではない。自分が無さか深くあろうとするだけで、情け深さ、つまり人情はすぐさま立ち現れる。
解説
論語の本章は、論語八佾篇3「人にして不仁」と近い関係にあり、貴族に成り上がるには教養や態度も大事だが、まず志すことが必要だと説いた話。どことなくブッダの言う、「血統によってバラモンとなるのではない。行いによってバラモンとなる」に近いものを感じさせる。
だが春秋の君子=貴族になるのはそう易しいことではない(論語における君子)。当時の貴族の一般常識を「礼」というが(論語における「礼」)、礼儀作法部分はマニュアル化できても、政争や戦争での判断は、その場の勘に頼るしかなくマニュアル化できない。
ここを分からないのが役人という生き物で、何でもマニュアル化していないと文句を言う。マニュアルや先例がないと判断できず、初の判断をし損なうと責任を問われるからだ。現伝儒教の「礼」のたぐいが、全て漢儒による創作であると、漢文の読める者なら誰でも知っている。
また論語時代の君子が身につけるべき技能教養を六芸(「「礼」常識、「楽」音楽、「書」古典、「射」弓術、「御」馬車術、「数」算術)と言うが、どれ一つとっても即座に習得できるわけがない。儒者の教養にポエムのような演芸が入るのは、帝政時代になってからである。
六芸のいずれも、やりようによっては生涯を掛けて追求するに値する技能教養であり、それは現在も変わらない。従って「貴族と思えばすぐ貴族」という論語の本章は、やはり後世の創作と考えたくなるわけだ。本章については以上だが、新古の注は次の通り。
古注『論語集解義疏』
子曰仁逺乎哉我欲仁斯仁至矣註苞氏曰仁道不逺行之則是至也疏子曰至至矣 世人不肯行仁故孔子引之也問言仁道逺乎也言其不逺也但行之由我我行即是此非出自逺也故云我欲仁而斯仁至也斯此也江熙曰復禮一日天下歸仁是仁至近也


本文「子曰仁逺乎哉我欲仁斯仁至矣」。
注釈。苞氏「仁の道は遠くにはない。仁を行えばすぐさま実現するのである。」
付け足し。先生は極致の極致を言った。世間の者どもが、仁の情けを行おうとしないものだから、孔子はこういう譬えを言った。”仁が遠くにあるか”と訊ねたのは、つまり”遠くない”と言いたかったのだ。ただし”仁を行うのは自分”(論語顔淵篇1)だから、自分が仁を行いさえすればすぐに仁が現れる。だから「我欲仁而斯仁至」と言ったのだ。斯とは、”ここ”である。
江熙曰「”一日でも礼法に立ち返れば、天下は仁に満ちあふれる”(論語顔淵篇1)という言葉が、仁の近さを表している。」
新注『論語集注』
仁者,心之德,非在外也。放而不求,故有以為遠者;反而求之,則即此而在矣,夫豈遠哉?程子曰:「為仁由己,欲之則至,何遠之有?」


仁とは心の道徳であるから、自分の外にはない。それなのに知らんふりしてやろうとしないものだから、遠く思えるのである。対してやろうと思うなら、即座にこの場に出現するから、どうして遠いと言えようか。
程頤「仁を行うのは自分。やる気があるなら、どうして遠いだろうか。」
余話
論語とがらんどう

早くしないと船が沈むよ
思えばそうなる、という発想は、世間に甘やかされた役人によく見られる性癖で、現実と自分の見込みが食い違っている場合、現実の方がおかしいと平気で言う。あるいは徹底的に現実を認めず、言い分との乖離のツケは下役や庶民に押し付けて涼しい顔をしている。
権威主義的支配が、一見強大に見えてもあっさり崩壊することが歴史上にままあるのはそれゆえだ。「神州不滅」というのが前提の帝政日本は、負けを重ね銃後の国民にまで膨大な被害を強いながら、敵に天皇制の存続が認められるとあっさり降服した。タガが外れたわけである。
だが直前までタガはまことに強固だったようで、国内からは降服の動きも帝政打倒の動きも見られなかった。その代わり「一億玉砕」を叫んで回ったのだが、こういうけしきはカルト教団の崩壊とまったく同じで、戦前の日本社会がろくでもなかったことを証している。
社会の構成員が、その社会の存続価値を認める仕組みを社会契約という。各員がなにがしかの代償を払うので、各員が応分の保護を受けられるというからくりだ。だが契約に署名した覚えのある人は、近代以降の帰化人以外にほぼ皆無で、一種の幻想といってよい。
この幻想は、各員の生命・身体・財産の順にある程度保証されている限り存続する。その保証はひとえに、気候や地球資源が担保する。つまり環境がいいから社会が安定するのであって、構成員の努力は実のところ大して関係が無い。平和で幸福な世は、偶然に成り立っている。
だが少しでも環境が悪化すると、社会的弱者から順に割を食う。役人は予算を自分のカネだと思っているから、法定の社会保障に難癖を付けて支出を渋る。実際、書類を積んでおき放置するという方法は昔からあったし、今も変わらない。提出者が死ぬのを待っているのだ。
こうしたあぶれが甚だしくなると、人々は社会契約がウソと悟って自己防衛に走らざるをえない。その割合がどれほどか、訳者は統計を元にしないいわゆる社会学を全く信用していないので知らないが、軍隊では損害が1/3を超えると全滅判定されるから、その程度に違いない。
この自己防衛には大きく二つの手段がある。一つは宗教の類に入って数の力で社会の資源をもぎ取ることで、もう一つは自己救済、つまり論語の本章に言う「仁」の実践だ。「仁」が儒者の言うような気法楽の意味でないことは上述の通りで、極めて物騒な概念である。

孔子が生きた春秋後半は、気候が温暖期から寒冷期にまっしぐらだったから、人々はイヤでも自己防衛に走らざるを得なかった。それでも現代よりは温かかったのだが、その代わり人類の技術が稚拙に過ぎた。その中で「貴族と思えばすぐ貴族」という本章には首をかしげる。
論語の本章が史実なら、おそらくは、弟子を励ますための言葉と信じるゆえんだ。ともあれ中国人は帝政期の日本人ほどウブでなかったから、論語や儒教が説く説教は信じる振りさえしなかった。振りをしたのは儒教の霊感商法で飯を食った儒者や儒者官僚だけである。
儒にまつわるあれこれの中で、者どもが社会に施した洗脳技術を「儒術」という。戦国も末になってから出来た漢語で、孔子没後一世紀に生まれた世間師・孟子は言わなかったが、世間師で役人を兼ねた荀子は、「儒術まことに行わば、則ち天下ひろくして富む」と言った。
もちろん言い手と聞き手で「儒術」の意味は異なる。聞き手は荀子の顧客たる諸侯で、言う通りにすれば富国強兵が実現できると思わせるためだ。だがこんなメルヘンを真に受けた諸侯は、孟子の顧客のように瞬時に滅んだ実績があったから、誰も「儒術」を導入しなかった。
これは中国が古代から、「独特の民主主義」であったのを裏打ちする。「忠」の字が漢語に現れるのは戦国時代だが、忠君愛国を儒教的にいくら説教しても、領民は誰一人従わなかった。法と暴力で支配した方が、はるかに言うことを聞いたので、「儒術」は無価値と見なされた。
実のところ「儒術」の語が大流行りするのは、いわゆる儒教の国教化が行われた漢帝国以降で、「若い頃から儒術を好み…」とある列伝はあまたある。帝国というコケ脅しが眼前に存在して強大に見えるから、儒術を学んでのし上がろうとする動機が社会に広まったわけ。
中国史上の儒にまつわるあれこれは、社会契約と共通点があり、幻想であり、売人と顧客で共有しないと効果が無かった。大多数の中国人である庶民は、儒をお上がやっている芝居としか見なかった。現代国家が劇場型政治を行いたがるのも、存外その文脈の中にある。
漢語に「術」の語が現れるのは戦国時代で、自然には成り立ちがたいことを、人の手で慎重に実現させるさまを言った(論語語釈「術」)。そのままでは信じて貰えないことを、手練手管を尽くして信じて貰うのも「術」の内に入る。類義語の羅列「権謀数術」のいずれも同様。
すべて「はかりごと」と訓読できる。いずれにせよ儒術を信じているのは欺されているに等しいのだが、他人の不合理をあざ笑うのは簡単でも、自分がそれから自由でいられるのは難しい。多かれ少なかれ人は群れて生活しているからで、社会のお約束から逸脱しがたい。
もちろんどんなに謹厳荘重なお約束も、下の句を「ヘソの下」と言い換えるだけで全て艶笑譚に変じうるが、だからと言って誰もが笑ってくれるとは限らない。世の中には「私に性欲などありません」と澄ましたふりを張り続けないと、生きていけない人も居るからである。
性欲が無ければとうに人類は滅んでいるはずで、このふりは出鼻から破綻しているのだし、当人もたいていは教え込まれてそうしているだけで、特に確信があるわけではない。それでもこの偽善に頭がやられている人は二人に一人はおり、だから自分が自由でいるのは難しい。
あるいは、中国史が法治の古さを誇るのが挙げられよう。最も「法治だった」と儒者が言い張る秦帝国でも、始皇帝は「法による支配」を利用はしたが、「法の支配」に自らが服したことはなかった。この背理は現代民主国家も同様で、どこの国にも法を超越した上級国民はいる。
もとより史上の中国人は百も承知だった。だから数学の場合分け同様、生活の場と生存の場で行動様式を違える。生活の場では芝居を演じたり観たりして過ごしたが、生存の場になるとまず役人が舞台から逃亡し、観客はいなくなる。あとには空になった劇場と帝室だけが残る。
つまり論語を基礎にした帝国も赤い人民共和国も、わんわんと響くがらんどうに他ならない。帝国の場合はそのがらんどうに、帝室だけが取り残され、だから歴代の帝室は、帝国滅亡後には深山幽谷まで執拗に捜索されて、反乱軍や次の王朝によって九分九厘九毛が殺される。
明帝国は儒教的洗脳に対し比較的冷静な王朝だったが、それでも滅亡後に帝室はしらみつぶしに殺された。末代の崇禎帝が泣きながら皇女を手に掛けた話は、外国人にとっては悲劇だが、中国人にとっては胸のつかえをおろす爽快な場面となる。王朝存続の小屋は客が入らない。
なぜか? ピンカートンの出ない「蝶々夫人」と同じで、観客が納得しないからだ。旧帝室は帝国という虚構ゆえに特権を享受し、庶民を長年いじめたからには、新王朝は自らの生存欲求に余論から墨付きを貰い、公然と旧帝室を殺戮する。やはり「独特の民主主義」である。
対して日本人は、楠木正成伝説に涙を流した(らしい)。素朴さを思うべきである。
戦前の日本人は、中国人の愛国心の無さを笑ったが、帝国というハッタリから自由でいた点で、中国人の方がはるかに先を行った。日本帝国は全国民を死ぬ目に遭わせながら、君主は死ぬまで、ごめんなさいのごの字も国民に言わなかった。ろくでもないというゆえん。
訳者は、過去現在の日本人をおとしめ自分を拝ませたり金を取るやからを忌み嫌っているが、過去を美化して同様の目的を果たそうとする連中とも、語る言葉を持ち合わせない。あったことはあったとし、社会のハッタリから自由になれなければ、人間に生まれたかいがない。
もちろん、論語や漢文を読むかいもないわけだ。





コメント