論語:原文・書き下し
原文(唐開成石経)
子曰君子博學於文約之以禮亦可以弗畔矣夫
※論語顔淵篇15とほぼ同文。
校訂
諸本
- 武内本:釋文、一本君子の二字なし。
東洋文庫蔵清家本
子曰君子博學於文約之以禮亦可以弗畔矣夫
後漢熹平石経
(なし)
定州竹簡論語
子曰:「君子a[博b於]文,約之以[禮,亦]可以弗之c畔矣夫!」133
- 君子、『釋文』云「一本無”君子”字。」
- 今本「博」下有「學」字。
- 之、今本無。
標点文
子曰、「君子博於文、約之以禮、亦可以弗之畔矣夫。」
復元白文(論語時代での表記)



















※約→要・畔→反。論語の本章は、「可以」は戦国中期にならないと確認できない。「博」に”広い”の語義は春秋時代では確認できない。論語の本章は、少なくとも戦国時代以降の改変が加えられている。
書き下し
子曰く、君子文於博くして、之を約ぶるに禮を以ゆれば、亦た之に畔か弗るを以ゆ可き矣る夫。
論語:現代日本語訳
逐語訳

先生が言った。「諸君は幅広く知識を学んで、それをまとめるのに貴族の一般常識を用いるならば、それでひとまず、これに背かないことができるだろうな。」
意訳

諸君、幅広く勉強するとよいが、すればするほど、本によって言っていることが違うじゃないかと混乱するだろう。その時は貴族の常識に従ってどれを優先すべきか判断してくれ。そうすればまあとりあえず、相矛盾するように見える教えから外れる事は無いだろうよ。
従来訳
先師がいわれた。――
「君子は博く典籍を学んで知見をゆたかにすると共に、実践の軌範を礼に求めてその知見にしめくくりをつけて行かなければならない。それでこそはじめて学問の道にそむかないといえるであろう。」下村湖人『現代訳論語』
現代中国での解釈例
孔子說:「廣泛學習、遵紀守法,就不會誤入歧途!」
孔子が言った。「幅広く学び、規則を守れば、つまり間違った道に入ることがありえない。」
論語:語釈
子曰(シエツ)(し、いわく)

論語の本章では”孔子先生が言った”。「子」は貴族や知識人に対する敬称で、論語では多くの場合孔子を指す。「子」は赤ん坊の象形、「曰」は口から息が出て来るさま。「子」も「曰」も、共に初出は甲骨文。辞書的には論語語釈「子」・論語語釈「曰」を参照。


(甲骨文)
この二文字を、「し、のたまわく」と読み下す例がある。「言う」→「のたまう」の敬語化だが、漢語の「曰」に敬語の要素は無い。古来、論語業者が世間からお金をむしるためのハッタリで、現在の論語読者が従うべき理由はないだろう。
君子(クンシ)


論語の本性では”諸君”という呼びかけ。孔子の生前、「君子」は参戦義務を負う代わりに参政権を持った貴族を意味した。”情け深い教養人”などといった語義は、弩(クロスボウ)の実用化によって「君子」の価値が暴落した戦国時代になって、孟子がつけ加えた新解釈。詳細は論語における「君子」を参照。
博(ハク)


(甲骨文)
論語の本章では”幅広く”。この語義は春秋時代では確認できない。『大漢和辞典』の第一義は”あまねくゆきわたる”。初出は甲骨文。ただし「搏」”うつ”と釈文されている。字形は「干」”さすまた”+「𤰔」”たて”+「又」”手”で、武具と防具を持って戦うこと。原義は”戦う”(「博多」って?)。”ひろい”と読みうる初出は戦国中期の竹簡で、論語の時代の語義ではない。詳細は論語語釈「博」を参照。
於(ヨ)


(金文)
論語の本章では”~に”。初出は西周早期の金文。ただし字体は「烏」。「ヨ」は”…において”の漢音(遣隋使・遣唐使が聞き帰った音)、呉音(遣隋使より前に日本に伝わった音)は「オ」。「オ」は”ああ”の漢音、呉音は「ウ」。現行字体の初出は春秋中期の金文。西周時代では”ああ”という感嘆詞、または”~において”の意に用いた。詳細は論語語釈「於」を参照。
學(カク)
唐石経・清家本は「學」字を記すが、現存最古の論語本である定州竹簡論語は記さない。「博於學文」「約之以禮」と四字句でまとめた方が漢文としては調子がいいのだが、物証としては定州本の方が古いので無いものとして校訂した。
論語の伝承について詳細は「論語の成立過程まとめ」を参照。
原始論語?…→定州竹簡論語→白虎通義→ ┌(中国)─唐石経─論語注疏─論語集注─(古注滅ぶ)→ →漢石経─古注─経典釈文─┤ ↓↓↓↓↓↓↓さまざまな影響↓↓↓↓↓↓↓ ・慶大本 └(日本)─清家本─正平本─文明本─足利本─根本本→ →(中国)─(古注逆輸入)─論語正義─────→(現在) →(日本)─────────────懐徳堂本→(現在)


(甲骨文)
論語の本章では”学ぶ”。座学だけではなく実技演習をも意味する。「ガク」は呉音(遣隋使より前に日本に伝わった音)。初出は甲骨文。新字体は「学」。原義は”学ぶ”。座学と実技を問わない。上部は「爻」”算木”を両手で操る姿。「爻」は計算にも占いにも用いられる。甲骨文は下部の「子」を欠き、金文より加わる。詳細は論語語釈「学」を参照。
文(ブン)


(甲骨文)
論語の本章では「武」に対する「文」で、”学問一般”。初出は甲骨文。「モン」は呉音。原義は”入れ墨”で、甲骨文や金文では地名・人名の他、”美しい”の例があるが、”文章”の用例は戦国時代の竹簡から。詳細は論語語釈「文」を参照。
約(ヤク)


(楚系戦国文字)
論語の本章では”まとまりをつける基準にする”。同音は「要」”引き締まった腰”とそれを部品とする漢字群、「夭」”わかじに”とそれを部品とする漢字群、「葯」”よろいぐさ・くすり”。字形は「糸」+「勺」とされるが、それは始皇帝によって秦系戦国文字を基本に文字の統一が行われて以降で、楚系戦国文字の段階では「糸」+「與」の略体「与」で、糸に手を加えて引き絞るさま。原義は”絞る”。同音の「要」には西周末期の「散氏盤」に”まとめる”と読めなくもない用例がある。詳細は論語語釈「約」を参照。
之(シ)


(甲骨文)
論語の本章では”これ”。具体的にはさまざまな知識を言う。「此」が直近の事物を指し、「其」がやや離れた事物を指すのに対し、指示語としての「之」は、字形が地面につま先を突くことであるように、つま先でトントンと”これ”と示すことが出来る明らかな事物を指す。もし論語の本章が史実の孔子の発言とするなら、”わしが諸君に教えた事どもというものはだな、互いに食い違うことがあって当然なのじゃが、それはだな…”という孔子の語気を感じることが出来る。
字の初出は甲骨文。字形は”足”+「一」”地面”で、あしを止めたところ。原義はつま先でつ突くような、”まさにこれ”。殷代末期から”ゆく”の語義を持った可能性があり、春秋末期までに”~の”の語義を獲得した。詳細は論語語釈「之」を参照。
以(イ)


(甲骨文)
論語の本章では”用いる”→”それで”。初出は甲骨文。人が手に道具を持った象形。原義は”手に持つ”。論語の時代までに、名詞(人名)、動詞”用いる”、接続詞”そして”の語義があったが、前置詞”…で”に用いる例は確認できない。ただしほとんどの前置詞の例は、”用いる”と動詞に解せば春秋時代の不在を回避できる。詳細は論語語釈「以」を参照。
禮(レイ)


(甲骨文)
論語の本章では”貴族の一般常識”。新字体は「礼」。しめすへんのある現行字体の初出は秦系戦国文字。無い「豊」の字の初出は甲骨文。両者は同音。現行字形は「示」+「豊」で、「示」は先祖の霊を示す位牌。「豊」はたかつきに豊かに供え物を盛ったさま。具体的には「豆」”たかつき”+「牛」+「丰」”穀物”二つで、つまり牛丼大盛りである。詳細は論語語釈「礼」を参照。
孔子の生前、「礼」は文字化され固定化された制度や教科書ではなく、貴族の一般常識「よきつね」を指した。その中に礼儀作法「ゐや」は含まれているが、意味する範囲はもっと広い。詳細は論語における「礼」を参照。
亦(エキ)


(甲骨文)
論語の本章では”それでひとまず”。婉曲の意を示す。ただしこの語義は春秋時代以前には確認出来ない。字の初出は甲骨文。原義は”人間の両脇”。春秋末期までに”…もまた”の語義を獲得した。”おおいに”の語義は、西周早期・中期の金文で「そう読み得る」だけで、確定的な論語時代の語義ではない。詳細は論語語釈「亦」を参照。
可以(カイ)
論語の本章では”…できる”。現代中国語でも同義で使われる助動詞「可以」。ただし出土史料は戦国中期以降の簡帛書(木や竹の簡、絹に記された文書)に限られ、論語の時代以前からは出土例が無い。春秋時代の漢語は一字一語が原則で、「可以」が存在した可能性は低い。ただし、「もって~すべし」と一字ごとに訓読すれば、一応春秋時代の漢語として通る。
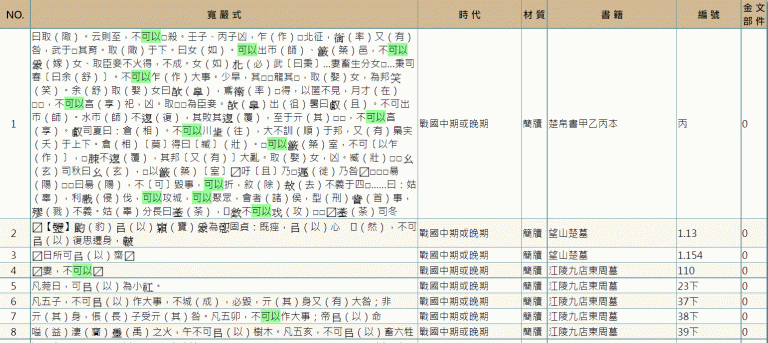
「先秦甲骨金文簡牘詞彙庫」
ただし「以て…す可し」と読めば、春秋時代での不在を回避できる。それでも言い訳であるには違いない。「春秋時代に絶無とは言えない」程度。


「可」(甲骨文)
「可」の初出は甲骨文。字形は「口」+「屈曲したかぎ型」で、原義は”やっとものを言う”こと。甲骨文から”…できる”を表した。日本語の「よろし」にあたるが、可能”~できる”・勧誘”~のがよい”・当然”~すべきだ”・認定”~に値する”の語義もある。詳細は論語語釈「可」を参照。
弗(フツ)


(甲骨文)
論語の本章では”~でない”。初出は甲骨文。甲骨文の字形には「丨」を「木」に描いたものがある。字形は木の枝を二本結わえたさまで、原義はおそらく”ほうき”。甲骨文から否定辞に用い、また占い師の名に用いた。金文でも否定辞に用いた。詳細は論語語釈「弗」を参照。
畔(ハン)


(楚系戦国文字)
論語の本章では”道を外れる”。この語義は春秋時代では確認できない。初出は楚系戦国文字。字形は「田」+「半」”ほとり”で、耕地の境界・あぜの意。原義は”あぜ”。”そむく”と読みうる初出は戦国時代中期または末期の、楚の竹簡。”そむく”の語義は甲骨文から存在する近音「反」に当てた言葉遊び。詳細は論語語釈「畔」を参照。
弗之畔
論語の本章では、”これに背かない”。「君子」を欠くのみで本章と同文である論語顔淵篇15の存在、それと本章の定州本を考えると、元来「君子」の語は無く、原文伝承の過程で情報の錯綜があったと判断する。
「弗之畔」は否定辞+目的語+動詞の順で、上古漢語の特例で、「弗」は「之」に「畔」するのを否定する。否定文の場合、否定辞の後ろの動詞-目的語の順を倒置できる。論語には「不我知」の例が多数見られる。
現代中国語にも否定文に伴う倒置はあり、「好学」”よく学ぶ・学んだ”の否定文は「学不好」”全然学んでいない”。
矣(イ)


(金文)
論語の本章では、”~である”。断定の意。初出は殷代末期の金文。字形は「𠙵」”人の頭”+「大」”人の歩く姿”。背を向けて立ち去ってゆく人の姿。原義はおそらく”…し終えた”。ここから完了・断定を意味しうる。詳細は論語語釈「矣」を参照。
夫(フ)


(甲骨文)
論語の本章では「かな」と読んで詠歎の意。この語義は春秋時代では確認できない。初出は甲骨文。論語では「夫子」として多出。「夫」に指示詞の用例が春秋時代以前に無いことから、”あの人”ではなく”父の如き人”の意で、多くは孔子を意味する。「フウ」は慣用音。字形はかんざしを挿した成人男性の姿で、原義は”成人男性”。「大夫」は領主を意味し、「夫人」は君主の夫人を意味する。固有名詞を除き”成人男性”以外の語義を獲得したのは西周末期の金文からで、「敷」”あまねく”・”連ねる”と読める文字列がある。以上以外の語義は、春秋時代以前には確認できない。詳細は論語語釈「夫」を参照。
論語:付記
検証
論語の本章は、前漢中期埋蔵の定州竹簡論語にはあるが、それを除き先秦両漢で引用や再録したのは、後漢末期の『前漢紀』のみ。文字は論語の時代に遡りうるが、漢語「博」の用例から見て史実が怪しい。約→要・畔→反の置換も、「そう言えないこともない」程度。
ただ文字史的に何とか論語の時代に遡れ、内容的にも孔子の教説と矛盾しないから、とりあえず史実として扱う。
解説
論語顔淵篇15との異同は以下の通り。顔淵篇にも元は「君子」があった。
- 子曰、「君子博學於文、約之以禮、亦可以弗畔矣夫。」(論語の本章)
- 子曰、「(君子)博學以文、約之以禮、亦可以弗畔矣夫。」(論語顔淵篇)
武内本が「釋文、一本君子の二字なし」と言うが、『経典釈文』は隋代の成立なので、日本に論語が入って間もない頃。顔淵篇の「君子」が復元出来るのは、清家本がそうなっているからだが、『経典釈文』の時代、版本によってはどちらの章にも「君子」が無かったことになる。
原始論語?…→定州竹簡論語→白虎通義→ ┌(中国)─唐石経─論語注疏─論語集注─(古注滅ぶ)→ →漢石経─古注─経典釈文─┤ ↓↓↓↓↓↓↓さまざまな影響↓↓↓↓↓↓↓ ・慶大本 └(日本)─清家本─正平本─文明本─足利本─根本本→ →(中国)─(古注逆輸入)─論語正義─────→(現在) →(日本)─────────────懐徳堂本→(現在)
さて論語の本章で漢語として壊れている部分、「弗之畔」を、儒者はどう始末したか。
古注『論語集解義疏』
註鄭𤣥曰弗畔不違道也

注釈。鄭玄「弗畔とは道に背かないことである。」
疏博廣也約束也畔違也背也言君子廣學六籍之文又用禮自約束能如此者亦可得不違背於道理也

付け足し。「博とは広いことだ。約は取り締まることだ。畔は違えることで、背くことだ。本章の言うところは、君子は広く六籍(詩経、書経、易経、礼記、春秋、楽経)の文章を学んで、礼法に従って自分でその取り締まりをつけ、そのようにすることが出来れば、或いは道理に背かないでいられるだろう、ということだ。
古注の「疏」=付け足しは、通常どうでもいいウンチクを長々と書くものだが、本章は珍しくあっさりしている。読めないから怖くて書けなかったのだろう。ここで白状しておくが、本サイトで古注を引用しても疏を訳出しないことが多いのは、面倒くさいのも理由の一つ。
だが真の理由は、読んでも意味の無いことしか書いてないからだ。だから訳者のやる気をガリガリ削られ、このサイトを維持していく陽気が保てない。ともあれ鄭玄の言う「道」は、孔子はただの一言も説かなかった。そのような形而上的暇つぶしをしている暇が無かったからだ。
孔子塾は鉄器や弩(クロスボウ)の実用化によって変動し始めた春秋後半の世で、庶民が入門し貴族にふさわしい技能教養を身につけて成り上がるための場であり、暇を持て余してカルチャーのたぐいに通う有閑階級とはわけが違う。弟子も必死に学んだし、孔子もそれに応じた。
鄭玄は「弗之畔」の違式に気付いてはいたが、始末の付け方に困り、どうとでも取れる「道」の一字で誤魔化した。それで済んだのは、鄭玄が天下の有名人だったからであり、後漢という世の特異性にもよるが、詳細は論語解説「後漢というふざけた帝国」を参照。
余談ながら江戸の川柳に、「虎はなんて鳴くのかと聞かれて儒者困り」というのが『誹風柳多留』に載るらしいが、確認できていない。江戸儒者の中国崇拝を馬鹿にした話は、『本朝二十不孝』にも見られるが、こういう批判精神は現代の論語読解にも、もっと発揮されてよい。
ついで新注を参照しよう。
新注『論語集注』
夫,音扶。約,要也。畔,背也。君子學欲其博,故於文無不考;守欲其要,故其動必以禮。如此,則可以不背於道矣。程子曰:「博學於文而不約之以禮,必至於汗漫。博學矣,又能守禮而由於規矩,則亦可以不畔道矣。」


夫は、扶の音で読む。約とは、締めくくることである。畔は、背くことである。君子たる者、学んだなら幅広く学ぼうとするもので、だから文という文を読破する。それをし続けた上で締めくくるなら、必ず礼法に従って締めくくる。そうすれば、必ず道にそむかないでいられる。
程頤「広く文章を学んでも礼法で締めくくりを付けないと、かならず締まりが無くなって浮ついてものに終わる。広く学んで、さらに礼法に従い掟を守れば、必ず道にぞむかないでいられる。」
漢語の違式に気付いていないし、鄭玄の猿真似をして、しかも「道」を説明しないままで終わった。こんなのを参照して論語を読もうとすれば、分けが分からなくなるのは必至で、論語に黒魔術性を付与する一助になっただろう。つまり分からないから有りがたいというわけ。

もちろん江戸儒者にも論語の本章の壊れようは分からなかったし、朱子を有り難がるのが精一杯だったから、のちに従一位大勲位公爵となる伊藤博文は、今から思えば間抜けないみ名を付けられてしまった。そこで本章の「君子」を仮に”諸君”以外に解すなら、こうなるだろう。

君子たる者、幅広く文献を学んで、それをまとめるのに礼法を用いれば、大いに君子らしさに背かないことができるだろうな。
もちろんここでの君子の意味は、孔子生前の”貴族”でなく、”情け深く教養のある人”という、孟子の提唱したものになる。詳細は論語における君子を参照して頂きたいが、戦国時代では、戦場の主力たり得なくなった血統貴族は、その特権を社会に説明する根拠を失っていた。
対して孔子生前の「君子」は、学ぶべきは古注の言う六籍ではなく、必須科目の六芸は、礼儀作法を含む貴族の常識、音楽と詩、弓術、戦車の操縦、読み書き、算術と記帳だった。いずれも貴族にとって不可欠の教養と技能で、ただ本だけ読んでも貴族にはなれなかった。
春秋の君子には、素手で人を殴刂殺せるえげつない暴カと、ただの乱暴者でないことを示す礼儀作法と、官吏や将校としての読み書き・帳簿付けと、巧みに歴史や古詩を引用して交渉相手を感心させる口の上手さが必要だった。その上琴の一つも披露できれば言うことなしだった。
その全てに通じたから孔子は師たりえた。だが古注儒者が挙げている、易を教えた形跡は無いし、孔子が易を学んだという論語述而篇16は後世の創作が判明している。六籍のうち楽経は早くに散逸したと言われ、元から存在した証拠も無い。つまり儒者の言う君子は春秋の君子ではない。
余話
そうだ漢学教授しよう
漢学教授はたいてい頭が悪い。
悪いのは生まれつきで責められないが、嘘をつき人を欺す者を好意的に扱うのは不可能だ。なぜなら欺されて食い物にされるからで、かつて日本人は漢学教授の嘘デタラメで、本土決戦という皆殺し寸前まで追い詰められたことがある。漢学教授の言い分に今日的意義は無い。
日中戦争は蒋介石が仕掛けて始まった。それ以前からしつこく日本にイヤガラセをした。それで日本人は激高したのだが、漢学教授が「孔子様の国」と言い募ったのが背景にあった。孔子様の国なのに、何ということをするのかと日本人が怒り狂ったのである。
はじめからそういう連中だと知れ渡っていたら、「またやってるよ」と冷静に観察できた。ひとえに漢学教授が漢文を読めず、自分の都合を世間に言いふらし続けた結果である。戦争が始まると「八紘一宇」とか漢語のスローガンを漢学教授が作り、日本人をたぶらかした。
対して孔子が古代人にもかかわらず、情報を集「約」することを強調したのには今日的意義がある。「やけどをしたらドクダミを擦り付けろ」という「おばあちゃんの知恵袋」は役に立つこともあるが、いつでもやけどを負うのを期待して、ドクダミを持ち歩くのは馬鹿げている。
オタクのウンチクと知識体系との違いはそこで、大系は個別の情報同士が合理で結びついている。ドクダミはデカノイルアセトアルデヒドを含むから抗菌作用があり、クェルチトリンを含むから炎症が静まるらしい(清水岑夫『生薬101の科学』)。双方が相まってやけどに効くのだそうだ。
従って「やけどとはどういう物理現象か」「その回復に生体はどのような活動をするか」「その活動を助ける物質は何か」「その物質をいつどのように生体に与えるか」「その物質を含む自然物がは何か」等々を知れば、ドクダミならずあらゆる薬を持ち歩く必要はないだろう。
私立文系オタクの訳者にとっては、ドクダミの知識の関連付けはここまでだが、薬学者や化学者なら、もっと広い知識体系を構築できるだろう。同様に漢文をどんなに読んだと称する人でも、漢文の文法にまで意識が及ばないなら、その場限りのカルトを知っているに過ぎない。
初めて見る漢文を読めないからだ。ゆえに中国も中国人も理解出来ず、中華文明にも思いが及ばず、世間から役立たずの穀潰しと見なされる。非漢文業界人が安易に、漢文について中途半端な聞きかじりを言い回って平気なのは、つまりは漢文業界がバカにされているからだ。
業界人はそれに腹を立てる意気地も無い。今世紀初頭に至るまで、日中台の漢学業界はカルトなオタクの集まりで、互いに分かるような話が出来なかった。分かると浅学がばれて困ったのが最大の理由だが、共通した議論の土台が出来ておらず、作ろうとする気も無かったからだ。
- 論語述而篇27余話「嫌われてるとも知らないで」
これが漢文業界を役人同様の、地位を利権と見なす世界に変えた。明治以来の日本の漢学教授は、子供に地位を継がせたがった。継いだ者を直接間接に何人も知っているが、判で捺いたように漢文が読めなかった。学生のレポートを奪い取り、自分の業績にしていただけである。
- 論語八佾篇16余話「不埒な帝大総長」
政治家や芸能人が子に継がせたがるのと同じで、漢学教授は美味しい稼業だった。しかも不真面目で不勉強でも務まり、学識も人に読ませ聞かせる努力も要らず、脳機能・人格障害でもコネがあればなれた。春夏秋冬には長期の休みがあり、週一の出勤で年収一千万は当たり前。

「シトー・エータ?」(これらは何ですか)
漢学教授ではないが甘やかされた漢文業者に、安岡正篤がいる。戦前は狂信的国家主義を語り身が危なくなると弟子を憲兵に売って逃げ回った。戦後になると戦前戦中のおのれの所業を、一切無かったことにして説教を続けた。論語述而篇18余話「カミサマじゃ」参照。
また首相や高級官僚など権力者に軍師と崇められた。その中に警察官僚の佐々淳行がおり、T大出の警察官僚も被疑者をそれと分からないようだ。理由は簡単、上司が拝む者を無批判に拝み、元データを自分で検証しないからだ。そういう者の言うことは、真に受けると損をする。
T大を首席で出て検事の親玉になり、趣味で無実の人を刑殺した平沼騏一郎に似ている。佐々は役人警官として彼なりに働いたのだろう。だが著作に安岡の説教を偉そうに混ぜているのは、「我が輩が漢文を読めないからには、読者も漢文を読めない」と見くびっているからだ。
試験秀才の傲慢が、世の中をどんなに不幸にするか、漢文を読める者なら皆知っている。
T大を出て高級官僚になったからには、人並み優れた秀才には違いないが、官僚のそれも司法関係となると、世間が怖がり甘やかして、全能感に包ませてしまうらしい。この現象は千年前から、すでに中国で発生していた。論語雍也篇3余話「宋儒のオカルトと高慢ちき」参照。


専門を得々と語るのは聞くに値するが、専門外の聞きかじりを説教する人ははなはだ人間が矮小に見える。佐々が拝んだ安岡は最期に売笑婦にたぶらかされて死に、遺族がえらい迷惑しただけでなく、漢文解釈は手抜きに猿真似を重ねたでたらめだった。話を漢学教授に戻そう。
- 論語為政篇4余話「天狗の作り方」
世間が甘やかすからただ威張っているだけで、研究も教育もしない。他人の金で快適な研究室に閉じこもり、高価な専門書を揃えるが、棚の飾りで読まないし、高価なのは教授互いの中元歳暮だからだ。こういう環境にいて、常人並みの知性や分別を保てるのは奇跡に近い。
かの者どもは、ナウル人に似ている。つまり働くという概念が始めから無く、汗流して働く人を不思議そうに見ている。ウソではなくそうした視線を何度も見た。だから高額な給与は当たり前に自分にやって来て当然と思っている。一種の化け物だから何を言っても分からない。
「そうだ漢学教授しよう。」訳者はT大教授が収賄する現場を、この目で何度か見ている。こういう根性は、ほぼ間違いなく中国儒者の猿真似で、論語泰伯編4(漢儒による偽作)がよくその図々しさを示している。論語業界は古来日中ともに、ずっとこんなのが居座っているのだ。
だが現在はITにより、「誰がやってみてもそうなる」という、漢文の原文を情報処理する手段が整った。漢文業界で今なおITを嫌がっている者は、自分の利権を守るに必死の小動物じみた何者かに過ぎない。若い漢学徒の諸君はどうか、そういう者の吠え声に怯えないで欲しい。
まず勉強して実力を蓄えることだ。砕氷船が荷重をかけて分厚い氷を砕くように。



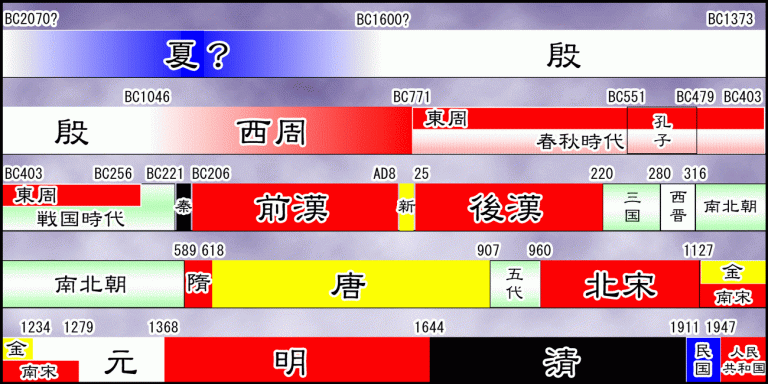

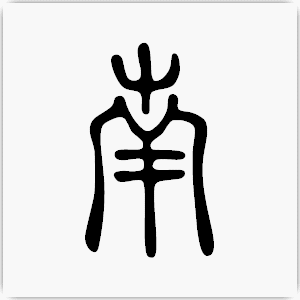
コメント