論語:原文・書き下し
原文(唐開成石経)
子曰聖人吾不得而見之矣得見君子者斯可矣子曰善人吾不得而見之矣得見有恒者斯可矣亡而爲有虛而爲盈約而爲泰難乎有恒矣
- 「恒」字:最後の一画を欠く。唐穆宗李恒の避諱。
校訂
東洋文庫蔵清家本
子曰聖人吾不得而見之矣得見君子者斯可矣/子曰善人吾不得而見之矣得見有恒者斯可矣亡而爲有虛而爲盈約而爲泰難乎有恒矣
後漢熹平石経
(なし)
定州竹簡論語
子曰:「聖人,吾弗a得而見之矣;得見君子者,斯可矣。」169子曰:「善人,吾弗得而見之矣;得見有恒者,斯可矣。170……而為有,虛而為盈,約而為泰,難乎有[恒矣]。」171
- 弗、今本作「不」。
標点文
子曰、「聖人、吾弗得而見之矣。得見君子者、斯可矣。」子曰、「善人、吾弗得而見之矣。得見有恒者、斯可矣。亡而爲有、虛而爲盈、約而爲泰、難乎有恒矣。」
復元白文(論語時代での表記)









































 虛
虛











※約→要・泰→大。論語の本章は「虛」の字が論語の時代に存在しない。本章は少なくとも、漢帝国以降の儒者による加筆がある。
書き下し
子曰く、聖人は吾得而之を見弗る矣。君子なる者を見るを得る者、斯るは可矣。子曰く、善る人は吾得而之を見弗る矣。恒有る者を見るを得る者、斯るは可矣。亡くし而有りと爲し、虛しくし而盈てりと爲し、約まり而泰かなりと爲す、難き乎恒有り矣こと。
論語:現代日本語訳
逐語訳

先生が言った。「神聖な人を、私は見ることが出来たことがない。地位ある立派な教養人を見ることが出来る可能性は、あり得る。」
先生が言った。「善良な人を、私は見ることが出来たことがない。心が不動の人を見る可能性は、あり得る。無くてもあると思い、空っぽでも満ちていると思い、追い詰められても安楽だと思う。難しいものだ、不動の心を保ち続けるのは。」
意訳


ありがたい聖人には会ったことがないが、りっぱな紳士らしい人には出会える。能力のある人には会ったことがないが、不動心を持った人には出会える。その人は不足があっても心配せず、泰然としていた。だがいつまで心の緊張が続くのだろう、不動心とは難しいものだ。
従来訳
先師がいわれた。――
「今の時代に聖人の出現は到底のぞめないので、せめて君子といわれるほどの人に会えたら、私は満足だ。」
またいわれた。――
「今の時代に善人に会える見込は到底ないので、せめてうそのない人にでも会えたら、結構だと思うのだが、それもなかなかむずかしい。無いものをあるように、からっぽなものを充実しているように、また行きづまっていながら気楽そうに見せかけるのが、この頃のはやりだが、そういう人がうそのない人間になるのは、容易なことではないね。」下村湖人『現代訳論語』
現代中国での解釈例
孔子說:「聖人,我不可能看到了;能看到君子,也就可以了。善人,我不可能看到了;能看到一心向善的人,也就可以了。沒有卻裝作擁有、空虛卻裝作充實、貧窮卻裝作富裕,打腫臉充胖子的人,很難一心向善!」
孔子が言った。「聖人は、私が出会うことはあり得ない。君子に出会えるかどうかは、まああり得るかも知れない。善人は、私が出会うことはあり得ない。一心に善を目指す人に出会えるかどうかは、まああり得るかも知れない。持っていないのに持っているように見せかける、空っぽなのに充実しているように見せかける、貧乏なのに飛んでいるように見せかける、こういうハッタリの人が、一心に善を目指すのは、とても難しい!」
論語:語釈
子 曰、「聖 人、吾 弗(不) 得 而 見 之 矣 得 見 君 子 者、斯 可 矣。」子 曰、「善 人、吾 弗(不) 得 而 見 之 矣 得 見 有 恒 者、斯 可 矣。亡 而 爲 有、虛 而 爲 盈、約 而 爲 泰、難 乎 有 恒 矣。」
子曰(シエツ)(し、いわく)

論語の本章では”孔子先生が言った”。「子」は貴族や知識人に対する敬称で、論語では多くの場合孔子を指す。「子」は赤ん坊の象形、「曰」は口から息が出て来るさま。「子」も「曰」も、共に初出は甲骨文。辞書的には論語語釈「子」・論語語釈「曰」を参照。
この二文字を、「し、のたまわく」と読み下す例がある。「言う」→「のたまう」の敬語化だが、漢語の「曰」に敬語の要素は無い。古来、論語業者が世間からお金をむしるためのハッタリで、現在の論語読者が従うべき理由はないだろう。
聖人(セイジン)
論語の本章では”神聖な人”。この語義は春秋時代では確認できない。


(甲骨文)
「聖」の初出は甲骨文。字形は「口」+「斧」+「人」。斧は王権の象徴で、殷代の出土品にその例がある。口は臣下の奏上、従って甲骨文の字形が示すのは、臣下の奏上を王が聞いて決済すること。春秋末期までに、”高貴な”・”すぐれた”・”聞く”・”(心を)研ぎ澄ます”の意に用いた。詳細は論語語釈「聖」を参照。
「耳順」が”天命を素直に聞き入れる”であることから(論語為政篇4)、論語での「聖」は史実の場合、”言語にならない天命を理解し、言語化して人に伝えることの出来る者”を意味する。


(甲骨文)
「人」の初出は甲骨文。原義は人の横姿。「ニン」は呉音。甲骨文・金文では、人一般を意味するほかに、”奴隷”を意味しうる。対して「大」「夫」などの人間の正面形には、下級の意味を含む用例は見られない。詳細は論語語釈「人」を参照。
吾(ゴ)


(甲骨文)
論語の本章では”わたし”。初出は甲骨文。字形は「五」+「口」で、原義は『学研漢和大字典』によると「語の原字」というがはっきりしない。一人称代名詞に使うのは音を借りた仮借だとされる。詳細は論語語釈「吾」を参照。
春秋時代までは中国語にも格変化があり、一人称では「吾」を主格と所有格に用い、「我」を所有格と目的格に用いた。しかし論語でその文法が崩れ、「我」と「吾」が区別されなくなっている章があるのは、後世の創作が多数含まれているため。
不(フウ)→弗(フツ)


(甲骨文)
漢文で最も多用される否定辞。初出は甲骨文。「フ」は呉音(遣隋使より前に日本に伝わった音)、「ブ」は慣用音。原義は花のがく。否定辞に用いるのは音を借りた派生義だが、甲骨文から否定辞”…ない”の意に用いた。詳細は論語語釈「不」を参照。


(甲骨文)
定州竹簡論語の「弗」の初出は甲骨文。甲骨文の字形には「丨」を「木」に描いたものがある。字形は木の枝を二本結わえたさまで、原義はおそらく”ほうき”。甲骨文から否定辞に用い、また占い師の名に用いた。金文でも否定辞に用いた。詳細は論語語釈「弗」を参照。
得(トク)


(甲骨文)
論語の本章では”手に入れる”→”会う”。初出は甲骨文。甲骨文に、すでに「彳」”みち”が加わった字形がある。字形は「貝」”タカラガイ”+「又」”手”で、原義は宝物を得ること。詳細は論語語釈「得」を参照。
而(ジ)


(甲骨文)
論語の本章では”…であって同時に”。初出は甲骨文。原義は”あごひげ”とされるが用例が確認できない。甲骨文から”~と”を意味し、金文になると、二人称や”そして”の意に用いた。英語のandに当たるが、「A而B」は、AとBが分かちがたく一体となっている事を意味し、単なる時間の前後や類似を意味しない。詳細は論語語釈「而」を参照。
見(ケン)


(甲骨文)
論語の本章では”見る”。初出は甲骨文。甲骨文の字形は、目を大きく見開いた人が座っている姿。原義は”見る”。甲骨文では原義のほか”奉る”に、金文では原義に加えて”君主に謁見する”、”…される”の語義がある。詳細は論語語釈「見」を参照。
之(シ)


(甲骨文)
論語の本章では”これ”。初出は甲骨文。字形は”足”+「一」”地面”で、あしを止めたところ。原義はつま先でつ突くような、”まさにこれ”。殷代末期から”ゆく”の語義を持った可能性があり、春秋末期までに”~の”の語義を獲得した。詳細は論語語釈「之」を参照。
矣(イ)


(金文)
論語の本章では、”~である”。断定の意。初出は殷代末期の金文。字形は「𠙵」”人の頭”+「大」”人の歩く姿”。背を向けて立ち去ってゆく人の姿。原義はおそらく”…し終えた”。ここから完了・断定を意味しうる。詳細は論語語釈「矣」を参照。
君子(クンシ)


論語の本章では、”地位も教養もある立派な人”。この語義は、孔子没後一世紀に現れた孟子が提唱した「仁義」を実践する者の語義で、原義とは異なる。
孔子の生前、「君子」とは従軍の義務がある代わりに参政権のある、士族以上の貴族を指した。「小人」とはその対で、従軍の義務が無い代わりに参政権が無かった。詳細は論語における「君子」を参照。また春秋時代の身分については、春秋時代の身分秩序と、国野制も参照。
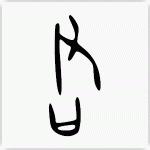

「君」(甲骨文)
「君」の初出は甲骨文。甲骨文の字形は「丨」”通路”+「又」”手”+「𠙵」”くち”で、人間の言うことを天界と取り持つ聖職者。「尹」に「𠙵」を加えた字形。甲骨文の用例は欠損が多く判読しがたいが、称号の一つだったと思われる。「先秦甲金文簡牘詞彙資料庫」は、春秋末期までの用例を全て人名・官職名・称号に分類している。甲骨文での語義は明瞭でないが、おそらく”諸侯”の意で用い、金文では”重臣”、”君臨する”、戦国の金文では”諸侯”の意で用いた。また地名・人名、敬称に用いた。詳細は論語語釈「君」を参照。
者(シャ)


(金文)
論語の本章では、”…である者”。旧字体は〔耂〕と〔日〕の間に〔丶〕一画を伴う。新字体は「者」。ただし唐石経・清家本ともに新字体と同じく「者」と記す。現存最古の論語本である定州竹簡論語も「者」と釈文(これこれの字であると断定すること)している。初出は殷代末期の金文。金文の字形は「木」”植物”+「水」+「口」で、”この植物に水をやれ”と言うことだろうか。原義は不明。初出では称号に用いている。春秋時代までに「諸」と同様”さまざまな”、”…は”の意に用いた。漢文では人に限らず事物にも用いる。詳細は論語語釈「者」を参照。
斯(シ)


(金文)
論語の本章では、”そのような場面”。「君子」や「恒ある者」に出会うような状況。初出は西周末期の金文。字形は「其」”籠に盛った供え物を祭壇に載せたさま”+「斤」”おの”で、文化的に厳かにしつらえられた神聖空間のさま。意味内容の無い語調を整える助字ではなく、ある状態や程度にある場面を指す。例えば論語子罕篇5にいう「斯文」とは、ちまちました個別の文化的成果物ではなく、風俗習慣を含めた中華文明全体を言う。詳細は論語語釈「斯」を参照。
可(カ)


「可」(甲骨文)
論語の本章では”…できる”。初出は甲骨文。字形は「口」+「屈曲したかぎ型」で、原義は”やっとものを言う”こと。甲骨文から”…できる”を表した。日本語の「よろし」にあたるが、可能”~できる”・勧誘”~のがよい”・当然”~すべきだ”・認定”~に値する”の語義もある。詳細は論語語釈「可」を参照。
善人(センジン)
論語の本章では”能力のある人”。春秋時代の漢語としても、本章が創作されたであろう漢代の漢語としても、”道徳的に立派な人”よりふさわしい。詳細は論語先進篇19語釈を参照。


(金文)
「善」はもとは道徳的な善ではなく、機能的な高品質を言う。「ゼン」は呉音。字形は「譱」で、「羊」+「言」二つ。周の一族は羊飼いだったとされ、羊はよいもののたとえに用いられた。「善」は「よい」「よい」と神々や人々が褒め讃えるさま。原義は”よい”。金文では原義で用いられたほか、「膳」に通じて”料理番”の意に用いられた。戦国の竹簡では原義のほか、”善事”・”よろこび好む”・”長じる”の意に用いられた。詳細は論語語釈「善」を参照。
恆(コウ)


(甲骨文)
論語の本章では”不動心”。新字体は「恒」。ただし定州竹簡論語は「恒」と釈文し、清家本も「恒」と記す。初出は甲骨文。ただし字形は「亙」(亘)。甲骨文の字形は、上下に横線、間に「月」。原義は不明。現伝字形は〔忄〕”こころ”+「亙」。「亙」のような心理状態を意味するが、「亙」の原義が分からないからどんな心理状態か分からない。満ち欠けに従って増減する月の横幅と違い、変化しない縦幅のような不動心を言うか。
仮にそうだとすれば、新字体「恒」は原義を失っているというべく、旧字体「恆」を正字と見なすのにはそれなりに理が通っているのかもしれない。
甲骨文では人名に用い、春秋末期までの金文では人名のほか”つねに”の意で用いた。詳細は論語語釈「恒」を参照。
刊行年不明の国会図書館蔵唐石経拓本は「恒」形だが、ただし最後の一画を欠く。唐穆宗李恒の避諱だが、天保年間刊行の京大蔵唐石経は写本であるためか、避諱していない。
亡(ボウ/ブ)


「亡」(甲骨文)
論語の本章では”失う”。初出は甲骨文。「ボウ」で”ほろぶ”、「ブ」で”無い”を意味する。字形は「人」+「丨」”築地塀”で、人の視界を隔てて見えなくさせたさま。原義は”(見え)ない”。甲骨文では原義で、春秋までの金文では”忘れる”、人名に、戦国の金文では原義・”滅亡”の意に用いた。詳細は論語語釈「亡」を参照。
爲(イ)


(甲骨文)
論語の本章では”作る”→”…だとする”。新字体は「為」。字形は象を調教するさま。甲骨文の段階で、”ある”や人名を、金文の段階で”作る”・”する”・”…になる”を意味した。詳細は論語語釈「為」を参照。
有(ユウ)


(甲骨文)
論語の本章では”ある”。初出は甲骨文。ただし字形は「月」を欠く「㞢」または「又」。字形はいずれも”手”の象形。原義は両腕で抱え持つこと。詳細は論語語釈「有」を参照。
虛(キョ)


(楚系戦国文字)
論語の本章では”空っぽ”。新字体は「虚」。初出は楚系戦国文字。字形は「虍」”トラの頭”+「丘」で、原義は未詳。戦国の竹簡では”むなしい”・”空っぽ”の意に用いた。論語時代の置換候補は存在しない。詳細は論語語釈「虚」を参照。
盈(エイ)


論語の本章では”満ちる”。初出は春秋末期の石鼓文。字形は「夃」+「皿」。「夃」は「人」+「又」”手”で、全体で皿に盛り付けるさま。同音に嬴”みちる”が存在する。春秋末期までの用例は断片の石鼓文しかなく語義未詳。戦国最末期の竹簡では、”満たす”の意に用いた。詳細は論語語釈「盈」を参照。
約(ヤク)


(楚系戦国文字)
論語の本章では”窮屈”。同音は「要」”引き締まった腰”とそれを部品とする漢字群、「夭」”わかじに”とそれを部品とする漢字群、「葯」”よろいぐさ・くすり”。字形は「糸」+「勺」とされるが、それは始皇帝によって秦系戦国文字を基本に文字の統一が行われて以降で、楚系戦国文字の段階では「糸」+「與」の略体「与」で、糸に手を加えて引き絞るさま。原義は”絞る”。同音の「要」には西周末期の「散氏盤」に”まとめる”と読めなくもない用例がある。詳細は論語語釈「約」を参照。
泰(タイ)
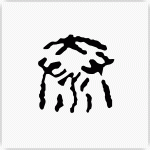

(秦系戦国文字)
論語の本章では”余裕がある”。初出は秦系戦国文字。同音に大・太。従って”大きい”・”太い”の意を持つ場合にのみ、大・太が論語時代の置換候補となりうる。字形は「大」”人の正面形”+「又」”手”二つ+「水」で、水から人を救い上げるさま。原義は”救われた”→”安全である”。
『説文解字』や『字通』の言う通り、「太」が異体字だとすると、楚系戦国文字まで遡れるが、漢字の形体から見て、「泰」は水から両手で人を救い出すさまであり、「太」は人を脇に手挟んだ人=大いなる人の形で、全く異なる。詳細は論語語釈「泰」を参照。
難(ダン/ダ)
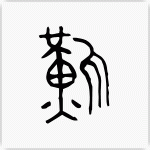

(金文)
論語の本章では”希有”→”難かしい”。初出は西周末期の金文。「ダン」の音で”難しい”、「ダ」の音で”鬼遣らい”を意味する。「ナン」「ナ」は呉音。字形は「𦰩」”火あぶり”+「鳥」で、焼き鳥のさま。原義は”焼き鳥”。それがなぜ”難しい”・”希有”の意になったかは、音を借りた仮借と解する以外にない。西周末期の用例に「難老」があり、”長寿”を意味したことから、初出の頃から、”希有”を意味したことになる。詳細は論語語釈「難」を参照。
乎(コ)


(甲骨文)
論語の本章では、「かな」と読んで詠歎の意。初出は甲骨文。甲骨文の字形は持ち手を取り付けた呼び鐘の象形で、原義は”呼ぶ”こと。甲骨文では”命じる”・”呼ぶ”を意味し、金文も同様で、「呼」の原字となった。句末の助辞や助詞として用いられたのは、戦国時代以降になる。ただし「烏乎」で”ああ”の意は、西周早期の金文に見え、句末でも詠嘆の意ならば論語の時代に存在した可能性がある。詳細は論語語釈「乎」を参照。
論語:付記
検証
論語の本章は春秋戦国の誰一人引用せず、一部似たような文字列が前漢中期の董仲舒『春秋繁露』にあるのみ。
是故孔子曰:「善人吾不得而見之,得見有常者斯可矣。」(『春秋繁露』深察名号4)
これ以降も、先秦両漢の引用・再録が皆無で、再出は後漢末期から南北朝にかけて編まれた古注になる。董仲舒は論語の偽作部分の少なからぬ章の偽作者と思われる。本章は文字史的にも論語の時代に遡れず、一部は董仲舒による偽作と断じてよい。董仲舒について詳しくは、論語公冶長篇24余話を参照。
ただし本章が文字史的に春秋時代まで遡れないのは、「虛」(虚)字だけであり、「恒有る者を見るを得る者、斯るは可矣。」までは史実の孔子の発言である可能性がある。句の並び方から見ても、それより後ろは余計に見える。
| 子曰、聖人、吾弗得而見之矣。得見君子者、斯可矣。 |
| 子曰、善人、吾弗得而見之矣。得見有恒者、斯可矣。 |
| 亡而爲有、虛而爲盈、約而爲泰、難乎有恒矣。 |
つまりもとからあった対句に、孔子の弟子でもない曽子の偉そうな説教で、後世の偽作である論語泰伯編5を、チョイチョイといじくって董仲舒あたりが本章にくっつけた可能性がある。
すると論語の本章の第一節、第二節は訓読と訳が異なってくる。下掲は春秋時代の漢語として解釈した例。
子曰く、聖人は吾得而之を見弗る矣。君子なる者を見るを得る者、斯るは可矣。子曰く、善人は吾得而之を見弗る矣。恒有る者を見るを得る者、斯るは可矣。
先生が言った。「(私より)身体能力の高い人には出会ったことがない。(だが修練を経て)貴族らしくなった人を見ること、そうした場面には立ち会うことが出来る。」先生が言った。「(何でも器用に)仕事の出来る人には出会ったことがない。だが不動心を保った人を見ること、そうした場面には立ち会うことが出来る。」
解説
論語の本章は、董仲舒の気持ちにならないと分からない。
始皇帝が帝政を始めると、皇帝自ら「聖」と言い出した。漢を起こした劉邦は、儒者嫌いもあって自分を”神聖”の意味では「聖」と呼ばせなかったが、董仲舒の仕えた武帝は自分から言い出して悦に入っていた。その武帝は正真正銘の暴君で、常人未満の知能しか無かった。
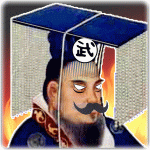
子供がおもちゃをいじり壊すように、国制を叩き壊して政府を破壊し、国軍を私兵化し、国富を戦争で蕩尽し、臣民を異郷の土へと追いやった。司馬遷のような宦官、司馬相如のようなメルヘンおたく、霍去病のような認知障害、東方朔のようなお笑い芸人しか使えなかった。
帝王の器ではなかったし、気まぐれに家臣を家族ごと皆殺しにした。武帝に「恒」はなかった。「聖」帝でもなかった。人でなしの君主に、ろくでなしの家臣が集まり、そこに「君子」は居なかった。互いに足を引っ張り、董仲舒も政敵のワナで収監され、死刑判決を受けた。
運良く武帝の気まぐれで釈放された。だから董仲舒は心から他人に「聖人」「善人」「君子」「恒心ある人」であることを望んだ。ゆえに論語の本章は、上記のように解せる。論語の本章の語り手は董仲舒で、「仏説なんたら経」同様、孔子は唯かこつけられただけである。
つまりすでに伝わっていた孔子の言葉に、董仲舒が自分の願望をくっつけて武帝の耳に入るようにしたわけだが、「気紛れでしょっちゅう家臣を殺したりするのは、いい加減にやめてください」という切実な願いがこもっている。
(武帝が)任命した宰相では、初期には田蚡が宰相らしい裁決をしたものの、武帝は気に入らずにイヤミを言った。「そちはもう、部下どもを気が済むまで任命し終えたか? ならワシにも好きな者を任命させよ。」この挙げ句、宰相はただその椅子に座っているだけの虚業になった。
公孫弘が宰相になって以降、内外の政治課題が積み上がって政治運営が難しくなったが、肝心の宰相が次から次へと、武帝の気分次第で殺されてしまった。理の当然で誰もが宰相になるのを嫌がった。
ある時武帝が公孫賀を宰相に任じようとすると、泣いて嫌がってなりたがらなかった。武帝は許さず無理やり宰相に据えたが、結局は気に入らなくて殺してしまった。(『十八史略』西漢・武帝)
論語の本章、新古の注は次の通り。
古注『論語集解義疏』
子曰聖人吾不得而見之矣得見君子者斯可矣註疾世無明君也子曰善人吾不得而見之矣得見有恒者斯可矣亡而為有虛而為盈約而為泰難乎有恒矣註孔安國曰難可名之為有常也

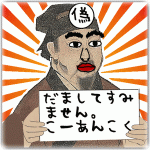
本文「子曰聖人吾不得而見之矣得見君子者斯可矣」。
注釈。「世の中に名君がいないことを歎いたのである。」
本文。「子曰善人吾不得而見之矣得見有恒者斯可矣亡而為有虛而為盈約而為泰難乎有恒矣」。
注釈。孔安国「名づけがたい事物が、恒常的な事物である。」
新注『論語集注』
三者皆虛夸之事,凡若此者,必不能守其常也。張敬夫曰:「聖人、君子以學言,善人、有恆者以質言。」愚謂有恆者之與聖人,高下固懸絕矣,然未有不自有恆而能至於聖者也。故章末申言有恆之義,其示人入德之門,可謂深切而著明矣。


無いのにあると言う…の三者は、どれもハッタリであり、こんな奴は誰だろうと、平常心を保てはしない。
張栻(張敬夫)「聖人君子は、学問を語る。善人や有恒者は中身を語る。」
愚か者である私(朱子)が考えるに、有恒者と聖人とは雲泥の違いだが、平常心を失ったことが無い者は、聖人に近づくことが出来る。だから本章の最後に、有恒の話をして、徳を身につける道筋を示したのだ。まことに懇ろなことであり、分かりやすい話であるなあ。
意地悪そうな似顔絵が語る通り、張栻は宋儒にふさわしい高慢ちきだった。宋代は科挙(高級官僚採用試験)制度の完成により、政界官界を儒者が独占したから、このような高慢ちきがまかり通った。「敬夫」=”敬うべき男”。自分からそう名乗ったのは幼稚と言うしかない。
論語雍也篇3余話「宋儒のオカルトと高慢ちき」を参照。
余話
神を拝むも人を拝むも
インド独立の父・ガンジーを映画化しようとしたリチャード・アッテンボローは、当時のネルー首相に協力を依頼した。首相は快諾したが条件を付けた。「ガンジーを神格化するようなことだけはしないで下さい。」とうの昔に無くしてしまったが、映画のパンフにそうあった。
ガンジーが人類史上の偉人であることはいささかも変わらない。だが前世紀末ごろから、「ガンジーって実はトンデモない人だったんじゃない?」という疑問や証言が続出した。そのうちのいくつかはその通りと思うしかないが、人を神のように崇める間抜けを思いもする。
ネルー首相の言葉は、実践政治家としての、インドの置かれた厳しい政治・宗教の状況を反映したものではあるが、人を敬っても、拝んではならないというのは人類共通の智恵でもある。敬うにしても、脅威か利益を動機に自分は敬っているのだと自覚するのも人類の智恵だ。
恐れこそが神の本質なのだ。(庵野秀明「巨神兵東京に現る」)

中華文明も無論、人間の生存を教える人類の智恵である(論語学而篇4余話)。無慮二千年間孔子を拝んだ帝政が崩壊し、拝み続けた民国が大陸を追われたわずか24年後、毛沢東が「批林批孔」を言い出した途端、全中国人がとんでもない山奥まで、丁寧に孔子廟を破壊して回った。
そのわずか16年後、孔子を拝むTVドラマが中国で作られた。福禄寿(乜-的快感・カネ・長寿と健康)だけを価値とする中国人が、興行成績だけを評価基準とするショービジネスを、権力だけが「善」悪を決める独裁国家で、「改革開放」を独裁者が言ったから出来たことである。
「聖人」孔子への「恒」ある崇敬など有り「難きかな」。
歌詞は英語版wikipediaを参照。



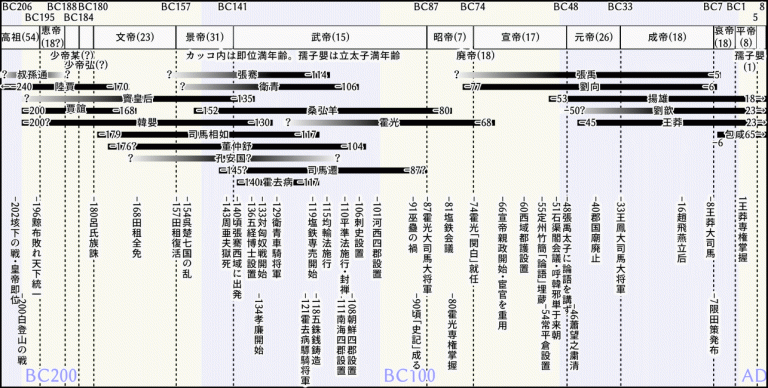


コメント