論語:原文・書き下し
原文(唐開成石経)
季康子問政於孔子孔子對曰政者正也子帥以正孰敢不正
校訂
諸本
- 武内本:清家本により、子帥以正を子帥而正に作る。諸本子帥以正に作る。以而通。
東洋文庫蔵清家本
季康子問政於孔子孔子對曰政者正也子帥而正孰敢不正
後漢熹平石経
(なし)
定州竹簡論語
(なし)
標点文
季康子問政於孔子。孔子對曰、「政者、正也。子帥而正、孰敢不正。」
復元白文(論語時代での表記)
























※論語の本章は「也」「帥」の用法に疑問がある。
書き下し
季康子政を孔子於問ふ。孔子對へて曰く、政者正也、子帥ゐ而正しからば、孰か敢て正しからざらむ。
論語:現代日本語訳
逐語訳
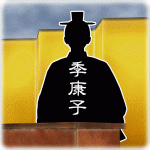

季康子が政治を問うた。先生が答えて言った。「政治とは正事です。あなたが国を率いて正しさが実現するなら、誰がわざわざ正しくならないでしょうか。」
意訳
季康子「政治の要点とは?」
孔子「政とは正です。正義を実現するのが政治の仕事です。あなたがそういう政治をとっているなら、だれが正義から足を踏み外しましょうか。」
従来訳
季康子が、政治について先師にたずねた。先師はこたえられた。――
「政治の政は正であります。あなたが真先に立って正を行われるならば、誰が正しくないものがありましょう。」下村湖人『現代訳論語』
現代中国での解釈例
季康子問政。孔子說:「所謂政治,就是正直。您以正直做表率,誰還敢不正直?」
季康子が政治を問うた。孔子が言った。「いわゆる政治とは、つまり公正です。あなたが公正の模範になれば、誰がわざわざ不正を働きますか?」
論語:語釈
季康子(キコウシ)
?-BC468。別名、季孫肥。魯国の門閥家老「三桓」の筆頭、季氏の当主、魯国正卿。BC492に父・季桓子(季孫斯)の跡を継いで当主となる。この時孔子59歳。孔子を魯国に呼び戻し、その弟子、子貢・冉有を用いて国政に当たった。
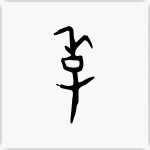

「季」(甲骨文)
「季」は”末っ子”を意味する。初出は甲骨文。魯の第15代桓公の子に生まれた慶父・叔牙・季友は、長兄の第16代荘公の重臣となり、慶父から孟孫氏(仲孫氏)、叔牙から叔孫氏、季友から季孫氏にそれぞれ分かれた。辞書的には論語語釈「季」を参照。


「康」(甲骨文)
「康」の初出は甲骨文。春秋時代以前では、人名または”(時間が)永い”のいで用いられた。辞書的には論語語釈「康」を参照。


「子」(甲骨文)
「子」は貴族や知識人に対する敬称。初出は甲骨文。字形は赤ん坊の象形で、古くは殷王族を意味した。春秋時代では、貴族や知識人への敬称に用いた。孔子のように学派の開祖や、大貴族は、「○子」と呼び、学派の弟子や、一般貴族は、「子○」と呼んだ。詳細は論語語釈「子」を参照。
問(ブン)


(甲骨文)
論語の本章では”質問する”。この語義は春秋時代では確認できない。初出は甲骨文。「モン」は呉音(遣隋使より前に日本に伝わった音)。字形は「門」+「口」。甲骨文での語義は不明。西周から春秋に用例が無く、一旦滅んだ漢語である可能性がある。戦国の金文では人名に用いられ、”問う”の語義は戦国最末期の竹簡から。それ以前の戦国時代、「昏」または「𦖞」で”問う”を記した。詳細は論語語釈「問」を参照。
政(セイ)(まつりごと)
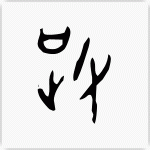

(甲骨文)
論語の本章では”政治(の要点)”。初出は甲骨文。ただし字形は「足」+「丨」”筋道”+「又」”手”。人の行き来する道を制限するさま。現行字体の初出は西周早期の金文で、目標を定めいきさつを記すさま。原義は”兵站の管理”。論語の時代までに、”征伐”、”政治”の語義が確認できる。詳細は論語語釈「政」を参照。
論語の本章は『定州竹簡論語』に欠いているが、そこでは通常「正」と書く。すでにあった「政」の字を避けた理由は、おそらく秦帝国時代に、始皇帝のいみ名「政」を避けた名残。加えて”政治は正しくあるべきだ”という儒者の偽善も加わっているだろう。
ただ本章の場合は、「政」ȶi̯ĕŋ(去)と「正」ȶi̯ĕŋ(平/去)の語呂合わせなので、もとより「政」は「政」と書かれていただろう。論語語釈「正」も参照。
於(ヨ)


(金文)
論語の本章では”~に”。初出は西周早期の金文。ただし字体は「烏」。「ヨ」は”~において”の漢音(遣隋使・遣唐使が聞き帰った音)、呉音は「オ」。「オ」は”ああ”の漢音、呉音は「ウ」。現行字体の初出は春秋中期の金文。西周時代では”ああ”という感嘆詞、または”~において”の意に用いた。詳細は論語語釈「於」を参照。
孔子(コウシ)

論語の本章では”孔子”。いみ名(本名)は「孔丘」、あざ名は「仲尼」とされるが、「尼」の字は孔子存命前に存在しなかった。BC551-BC479。詳細は孔子の生涯1を参照。
論語で「孔子」と記される場合、対話者が目上の国公や家老である場合が多い。本章もおそらくその一つ。詳細は論語先進篇11語釈を参照。


(金文)
「孔」の初出は西周早期の金文。字形は「子」+「乚」で、赤子の頭頂のさま。原義は未詳。春秋末期までに、”大いなる””はなはだ”の意に用いた。詳細は論語語釈「孔」を参照。
對(タイ)


(甲骨文)
論語の本章では”回答する”。初出は甲骨文。新字体は「対」。「ツイ」は唐音。字形は「丵」”草むら”+「又」”手”で、草むらに手を入れて開墾するさま。原義は”開墾”。甲骨文では、祭礼の名と地名に用いられ、金文では加えて、音を借りた仮借として”対応する”・”応答する”の語義が出来た。詳細は論語語釈「対」を参照。
曰(エツ)


(甲骨文)
論語で最も多用される、”言う”を意味する言葉。初出は甲骨文。原義は「𠙵」=「口」から声が出て来るさま。詳細は論語語釈「曰」を参照。
者(シャ)


(金文)
論語の本章では”するのは…だ”。新字体は「者」(耂と日の間に点が無い)。ただし唐石経・清家本ともに新字体と同じく「者」と記す。初出は殷代末期の金文。金文の字形は「木」”植物”+「水」+「口」で、”この植物に水をやれ”と言うことだろうか。原義は不明。初出では称号に用いている。春秋時代までに「諸」と同様”さまざまな”、”~する者”・”~は”の意に用いた。漢文では人に限らず事物にも用いる。詳細は論語語釈「者」を参照。
正(セイ)
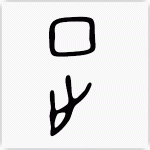

(甲骨文)
論語の本章では”正しい”。初出は甲骨文。字形は「囗」”城塞都市”+そこへ向かう「足」で、原義は”遠征”。論語の時代までに、地名・祭礼名、”征伐”・”年始”のほか、”正す”、”長官”、”審査”の意に用い、また「政」の字が派生した。詳細は論語語釈「正」を参照。
也(ヤ)


(金文)
論語の本章では「なり」と読んで”~である”。断定の意を示す。断定の語義は春秋時代では確認できない。初出は事実上春秋時代の金文。字形は口から強く語気を放つさまで、原義は”…こそは”。春秋末期までに句中で主格の強調、句末で詠歎、疑問や反語に用いたが、断定の意が明瞭に確認できるのは、戦国時代末期の金文からで、論語の時代には存在しない。詳細は論語語釈「也」を参照。
帥(スイ)


(甲骨文)
論語の本章では”率いる”。この語義は春秋時代では確認できない。初出は甲骨文。字形は軍旗の象形。「ソツ」は”率いる”の場合の漢音。天神様が左遷された「太宰権帥」(だざいのごんのそつ)の「ソツ」音がこれで、日本の官職名ではこう読む座敷わらしになっている。春秋末期までに人名のほか、”軍隊”・”司令官”・”従う”・”倣う”の意に用いた。”率いる”の用例は戦国時代以降に見られる。詳細は論語語釈「帥」を参照。
以(イ)→而(ジ)
現存最古の論語本である定州竹簡論語は論語の本章全体を欠き、唐石経は「以」と記し、清家本は「而」と記す。清家本の年代は唐石経より新しいが、より古い古注系の文字列を伝えており、唐石経を訂正しうる。これにより「而」へと校訂した。論語の伝承について詳細は「論語の成立過程まとめ」を参照。
原始論語?…→定州竹簡論語→白虎通義→ ┌(中国)─唐石経─論語注疏─論語集注─(古注滅ぶ)→ →漢石経─古注─経典釈文─┤ ↓↓↓↓↓↓↓さまざまな影響↓↓↓↓↓↓↓ ・慶大本 └(日本)─清家本─正平本─文明本─足利本─根本本→ →(中国)─(古注逆輸入)─論語正義─────→(現在) →(日本)─────────────懐徳堂本→(現在)


(甲骨文)
論語の本章、唐石経「以」では”用いる”。初出は甲骨文。人が手に道具を持った象形。原義は”手に持つ”。論語の時代までに、名詞(人名)、動詞”用いる”、接続詞”そして”の語義があったが、前置詞”~で”に用いる例は確認できない。ただしほとんどの前置詞の例は、”用いる”と動詞に解せば春秋時代の不在を回避できる。詳細は論語語釈「以」を参照。


(甲骨文)
論語の本章、清家本では「而」”そして”。初出は甲骨文。原義は”あごひげ”とされるが用例が確認できない。甲骨文から”~と”を意味し、金文になると、二人称や”そして”の意に用いた。英語のandに当たるが、「A而B」は、AとBが分かちがたく一体となっている事を意味し、単なる時間の前後や類似を意味しない。詳細は論語語釈「而」を参照。
唐石経「子帥以正」は「子正しきを以ゐて帥ゐたらば」と読み、”あなたが正義に従って指導するなら”の意。具体的な正義の條件が先にあって、それに従って政治を行うなら、ということ。
清家本「子帥而正」は「子帥ゐ而正しからば」と読み、”あなたが指導して正義が実現するなら”の意。前提の正義は抽象的で、正義とは何かは未知だが、政治を行った結果が正義と言えるなら、ということ。
両者同じ事を言っているようで重大な違いがある。
唐石経の彫られた時代は、儒家が諸学派を圧倒してはいなかったが優位ではあった。従って儒家の言う「仁義」を「正義」として前提に置くことが可能だった。一方仮に論語の本章が史実の孔子の発言なら、従うべき「正義」は確立しておらず、政治の結果がよろしければ正義、という言い方になる。
孰(シュク)


(金文)
論語の本章では”誰が…か”。初出は西周中期の金文。「ジュク」は呉音。字形は鍋を火に掛けるさま。春秋末期までに、「熟」”煮る”・”いずれ”の意に用いた。詳細は論語語釈「孰」を参照。
敢(カン)


(甲骨文)
論語の本章では”自発的に”。わざわざする、の意。初出は甲骨文。字形はさかさの「人」+「丨」”筮竹”+「𠙵」”くち”+「廾」”両手”で、両手で筮竹をあやつり呪文を唱え、特定の人物を呪うさま。原義は”強い意志”。金文では原義に用いた。漢代の金文では”~できる”を意味した。詳細は論語語釈「敢」を参照。
不(フウ)


(甲骨文)
漢文で最も多用される否定辞。初出は甲骨文。「フ」は呉音、「ブ」は慣用音。原義は花のがく。否定辞に用いるのは音を借りた派生義だが、甲骨文から否定辞”…ない”の意に用いた。詳細は論語語釈「不」を参照。
論語:付記
検証
論語の本章は、前漢中期の定州竹簡論語に欠き、漢語の用法に疑問はあるものの、文字史的に全て論語の時代に遡れるので、史実の孔子の発言と判断して構わない。ただし上掲語釈の通り、孔子が言ったのは”政治の結果で正義を実現せよ”であって、”確立した正義に従って政治を行え”ではない。
また論語の本章は、物証として最古なのは戦国時代の竹簡になるが、やや文字列が違う。
孔□(孔子)曰:「唯正者;正也。夫子唯又(有)與(舉);女(汝)蜀(獨)正之;幾(豈)不又(有)〔忄止壬〕也。」
孔子が言った。そもそも政治とは、正義の実現です。あなたが正義を実現できていたら、一人で政治をとりなされ。どうして〔忄止壬〕があるでしょうか。(「上海博物館蔵戦国楚竹簡」中弓附簡)
〔忄止壬〕の語義が分からないので想像するしかないのだが、部品から見て”とがめ”るような何らかの感情を言うのだろうか。
解説
上記の通り論語の本章が史実とするなら、従うべき「正義」はまだ社会に確立されていなかった。「正義」を確立するにはそれに対する盲目という信仰が必要で、それを社会に確立するには国教やマルクス主義のような疑似国教が必要だが、春秋時代は人間の技術力が乏しく、そういう絵空事に人々が夢中になれるほど社会の生産に余裕が無かった。
古代の貴族は東西世界を問わず、坊主でなければ戦士だが、社会の食糧に余裕が無ければ、絵空事を説く坊主や儒者に食い扶持が無い道理である。だから『春秋左氏伝』や金文を読んでも、当時の貴族=「君子」はほぼ戦士で坊主ではない(論語における「君子」)。宗教も抽象的な天地の神や精霊、祖先に対してひたすら供え物を捧げるだけで、神も精霊も、何が正義かは言わなかった。
神や精霊は、ただ雨を降らせたり風を吹かせたりするだけで、祈ったところで人間の言うことなど聞きはしないと見られており、この点春秋時代の中国人は、ある種の現代人よりよほど迷信から自由でいた。
(家老の)臧文仲「そんなことでは日照りは収まりません。城壁を堅固にして飢えた賊の襲来を防ぎ、食事を質素にして出費を減らし、農耕に力を入れて貧者に配給し、労働力を増すのが、当面のやるべき事です。みこなど焼き殺して何になるのですか。天がみこを殺すおつもりなら、今なおのうのうと生きている道理が無いではないですか。」(『春秋左氏伝』僖公二十一年(BC639))
神霊精霊はもの言わずとも、ただし祖先は「血統を繋げ」と言っただろう。金文のおしまいに定型として「子々孫々この道具を使って…」と後世に言い残すものが多いが、ここから春秋時代に「正義」といえるものがあったとするなら、それは血統を絶やすなということだろう。
すると論語の本章で孔子が季康子に説教したのは、”政治とは人々の血統を絶やさないようにするいとなみである”ということであり、具体的には蛮族や異国の凶行から武力で領民を守ること、同時に飢え死にがないよう、開拓や治水、備蓄や適切な税制を行うことだろう。
それを踏まえての論語顔淵篇7「子貢政を問う」であり、そこでは具体的に軍備と食糧確保を孔子は説いたが、本章では相手が若いとは言え目上の季康子であり、むやみに武威をちらつかせる呉国のヒモ付きで帰国した孔子は、季康子が本気で問うたわけでないのに気付いてもいただろう。
言ったところで、従うつもりが無いのにも気付いていた。当時季康子は孔子の高弟である冉有を執事に雇い、新税制を施行しようとしていたが、孔子は冉有に新税制の是非を問われて反対している(論語顔淵篇9解説)。その答え方から見ても、孔子は自分がすでに魯国政界の中心に無いと悟っていた。
だから長老として、現執政から政治の要点を「ちょっと聞かれた」だけなのに対し、「ちょっと答えてやった」程度に思っていただろう。老い先短い自分の運命をかけた説得などではぜんぜんない。同じ門閥家老でも、若年時より縁の深かった孟孫家の坊ちゃん相手とは意気込みが違う。
その孟武伯相手の孔子の答えは、論語為政篇6を参照。下掲のように無考えな儒者や仕事嫌いの漢学教授が出任せを言う(論語雍也篇27余話「そうだ漢学教授しよう」)のとは異なり、史実の孔子と魯国門閥との関係は決して悪く無かったが、筆頭家老の季孫家に対しては、孔子は義理立ての必要がなかったのだ。
論語の本章、新古の注は次の通り。
古注『論語集解義疏』
季康子問政於孔子孔子對曰政者正也子帥而正孰敢不正註鄭𤣥曰季康子魯上卿諸臣之帥也
本文「季康子問政於孔子孔子對曰政者正也子帥而正孰敢不正」。
注釈。鄭玄「季康子は魯の上級家老で諸臣の指導者だった。」
新注『論語集注』
季康子問政於孔子。孔子對曰:「政者,正也。子帥以正,孰敢不正?」范氏曰:「未有己不正而能正人者。」胡氏曰:「魯自中葉,政由大夫,家臣效尤,據邑背叛,不正甚矣。故孔子以是告之,欲康子以正自克,而改三家之故。惜乎康子之溺於利欲而不能也。」
本文「季康子問政於孔子。孔子對曰:政者,正也。子帥以正,孰敢不正?」
范祖禹「自分が不正なのに他人を正せる人物は、今に至るまでいないのである。
胡寅「魯はその歴史の中頃から、政治は家老が取り仕切った。家臣は威勢を張り合って、自領に立てこもって反乱を起こし、正義で無いこと甚だしかった。だから孔子はこのように言って、季康子自らが我欲に打ち勝って正義に立ち戻り(論語顔淵篇1)、その結果門閥三家老家の悪事を改めさせようとした。だが残念なことに季康子は欲の皮が張っていて出来なかった。」
余話
(思案中)





コメント