論語:原文・書き下し
原文(唐開成石経)
顔淵季路侍子曰盍各言爾志子路曰願車馬衣裘與朋友共敝之而無憾顔淵曰願無伐善無施勞子路曰願聞子之志子曰老者安之朋友信之少者懷之
- 「淵」字:〔𣶒〕は〔丿〕の右に上下に〔八一八〕。唐高祖李淵の避諱。
校訂
東洋文庫蔵清家本
顔淵季路侍子曰盍各言爾志子路曰願車馬衣輕裘與朋友共敝之而無憾/顔淵曰願無伐善/無施勞/子路曰願聞子之志子曰𦒳者安之朋友信之少者懷之
- 「季」字:「子」と傍記。京大本・宮内庁本傍記無し。
- 「友」字:右側に〔丶〕一画あり。
後漢熹平石経
(なし)
定州竹簡論語
……而毋![]() a。顏淵曰:「願毋b伐□,毋□104……[願]聞子之志。」子曰:「老者安[之,
a。顏淵曰:「願毋b伐□,毋□104……[願]聞子之志。」子曰:「老者安[之,![]() c友信之,少者]105……
c友信之,少者]105……
- 毋
 、今本作「無憾」。
、今本作「無憾」。 - 毋、今本作「無」。
 、今本作「朋」。「
、今本作「朋」。「 」為「傰」之省、「傰」字読為「朋」。
」為「傰」之省、「傰」字読為「朋」。
※「![]() 」字:「垐」”にくむ”の異体字と仮定。下掲「垐」語釈参照。
」字:「垐」”にくむ”の異体字と仮定。下掲「垐」語釈参照。
標点文
顏淵、季路侍。子曰、「盍各言爾志。」子路曰、「願車馬衣輕裘、與朋友共、敝之而毋垐。」顏淵曰、「願毋伐善、毋施勞。」子路曰、「願聞子之志。」子曰、「老者安之、朋友信之、少者懷之。」
復元白文(論語時代での表記)










 志
志 

 願
願

 輕
輕







 垐
垐 

 願
願







 願
願

















※志→思・![]() →朋・施→(甲骨文)。論語の本章は上記の赤字が論語の時代に存在しない。「盍」「各」「與」「敝」「之」「伐」「信」の用法に疑問がある。本章は漢帝国の儒者による創作である。
→朋・施→(甲骨文)。論語の本章は上記の赤字が論語の時代に存在しない。「盍」「各」「與」「敝」「之」「伐」「信」の用法に疑問がある。本章は漢帝国の儒者による創作である。
書き下し
顏淵季路侍る。子曰く、盍ぞ各爾の志を言はざる。子路曰く、願はくは車馬衣輕き裘、朋友與共にし、之を敝り而垐ふ毋からむ。顏淵曰く、願はくは善きに伐る毋く、勞を施ぼす毋からむ。子路曰く、願はくは子の志を聞かむ。子曰く、老者は之を安んじ、朋友は之に信あり、少者は之を懷けむ。
論語:現代日本語訳
逐語訳


顔淵(=顔回)と季路が近くにいた。先生が言った。「なぜ自分たちの志を言わないのか。」子路が言った。「出来るなら車馬・普段着・軽い外套を友人と共有し、損ねても怨みがないようにしたいです。」顔淵が言った。「出来るなら善事を誇らず、苦労を人に押し付けないようにしたいです。」子路が言った。「出来ますなら先生の志を聞きたいです。」先生が言った。「老人は安心させ、友人には信頼され、若者には懐かれたい。」
意訳


顔淵と子路がそばにいた。
孔子「黙ってないで、将来の希望でも言ったらどうだね。」
子路「持ち物を友人と共有し、壊しても恨みっこ無しにしたいものです。」
顔淵「して上げたことを忘れ、されたくないことを人にしたくないです。」
子路「で、先生は?」

「そうさな。老人は安心させ、同世代には信じられ、若者には懐かれたい。」
従来訳
顔渕と季路とが先師のおそばにいたときのこと、先師がいわれた。――
「どうだ、今日は一つ、めいめいの理想といったようなものを語りあって見ようではないか。」
すると、子路がすぐいった。
「私が馬車に乗り、軽い毛皮の着物が着れるような身分になりました時に、友人と共にそれに乗り、それを着て、かりに友人がそれをいためましても、何とも思わないようにありたいものだと思います。」
顔渕はいった。――
「私は、自分の善事を誇ったり、骨折を吹聴したりするような誘惑に打克って、自分の為すべきことを、真心こめてやれるようになりたいと、それをひたすら願っております。」
しばらくして子路が先師にたずねた。――
「どうか、先生のご理想も承らしていただきたいと思います。」
先師は答えられた。――
「私は、老人たちの心を安らかにしたい。友人とは信をもって交りたい。年少者には親しまれたい、と、ただそれだけを願っているのだ。」下村湖人『現代訳論語』
現代中国での解釈例
顏淵、季路侍奉時。孔子說:「為什麽不說說各人的願望呢?」子路說:「願將車馬和裘衣和朋友共用,壞了也不遺憾。」顏淵說:「但願能做到不夸耀優點、不宣揚功勞。」子路說:「您的願望呢?」孔子說::「但願老人能享受安樂,少兒能得到關懷,朋友能夠信任我。」
顔淵(顔回)と季路が孔子の近くに控えていたとき、孔子が言った。「なぜそれぞれの希望を話さないのかね?」子路が言った。「できるなら車馬と皮衣を友人と共有して、ダメにしても怨まないでいたい。」顔淵が言った。「自分の長所を誇らず、功績を言い立てないようにしたい。」子路が言った。「先生の希望は?」孔子が言った。「ただ老人に安楽を与え、子供から懐かれ、友達に信用されたい。」
論語:語釈
顏 淵 、季 路 侍 。子 曰、「盍 各 言 爾 志。」子 路 曰、「願 車 馬 衣 裘、與 朋 友 共、敝 之 而 無 垐(憾) 。」 顏 淵 曰、「願 毋(無) 伐 善、毋(無) 施 勞。」子 路 曰、「願 聞 子 之 志。」子 曰、「老 者 安 之、朋 友 信 之、 少 者 懷 之。」
顏淵(ガンエン)
孔子の弟子、顏回子淵。あざ名で呼んでおり敬称。「顏」の新字体は「顔」だが、定州竹簡論語も唐石経も清家本も新字体と同じく「顔」と記している。ただし文字史からは「顏」を正字とするのに理がある。詳細は論語の人物:顔回子淵を参照。


「顏」(金文)
「顏」の新字体は「顔」だが、定州竹簡論語も唐石経も清家本も新字体と同じく「顔」と記している。ただし文字史からは「顏」を正字とするのに理がある。初出は西周中期の金文。字形は「文」”ひと”+「厂」”最前線”+「弓」+「目」で、最前線で弓の達者とされた者の姿。「漢語多功能字庫」によると、金文では氏族名に用い、戦国の竹簡では”表情”の意に用いた。詳細は論語語釈「顔」を参照。


「淵」(甲骨文)
「淵」の初出は甲骨文。カールグレン上古音はʔiwen(平)。「渕」は異体字。字形は深い水たまりのさま。甲骨文では地名に、また”底の深い沼”を意味し、金文では同義に(沈子它簋・西周早期)に用いた。詳細は論語語釈「淵」を参照。
季路(キロ)
論語の本章では、おそらく「子路」の誤り。理由は三つある。
- 本章の他の箇所では「子路」と記している。
- 図形的に「季」は「子」を含んでおり誤写しやすい。
漢語は文書では縦書きを原則とする。従っての字が二文字が一文字に誤記されることが善くある。また本文のはしに小さく書いた註記が、本文と混同されることもある。「子」の上に「禾」が加わった理由は判然としないが、図形的にまるで無関係でもない。 - 「子路曰」に対して「子曰」と記している。
論語では孔子を主語とする場合、「子(動詞」と「孔子(動詞)」では動作対象の身分に区別がある。相手が目下の場合は「子」と記すが、同格以上の場合「孔子」と記す(論語先進篇11語釈)。「季路」は顔回子淵の父・顔路のあざ名で、弟子の親御さんとして本来孔子と同格以上の存在。論語先進篇7の定州竹簡論語では顔路に対して「孔子曰」と記しており、顔路が孔子と同格以上だったことを裏付ける。 - 論語の本章のこの部分に関して、もっとも古い清家本は、東洋文庫本は「季」に「子」と傍記している。
論語の本章の「季路」を「子路」だと言い出したのは、孔子没後967年後に生まれた、古注『論語集解義疏』に「疏」”付け足し”を書き付けた南朝梁の皇侃であり、その断定に論拠もなく、とうてい信用するに値しない。
古注『論語集解義疏』
…疏…季路即子路也。
…付け足し。季路とはすなわち子路である。
論語で「季路」と記す章は以下の通り。
| 章 | 現伝論語 | 定州竹簡論語 | 備考 | |
| 1 | 論語公冶長篇25(本章) | 季路侍 | (欠損) | 偽作 |
| 2 | 論語先進篇1 | 季路 | 子路 | 後世の付加 |
| 3 | 論語先進篇11 | 季路問 | 季路問 | |
| 4 | 論語季氏篇1 | 季路見 | (欠損) | 偽作 |
顔回子淵の父親は、『史記』弟子伝ではいみ名(本名)は無繇、あざ名は「路」とあるが、いみ名が二文字なのは春秋時代の漢語として理に合わない。『史記』よりやや時代が下り、論語と同様定州漢墓竹簡に含まれる『孔子家語』では、いみ名は「由」、あざ名は「季路」。春秋時代の名乗りとしてはむしろこちらの方が理にかなう。

子路は名の伝わる中で最も早く入門した孔子の弟子。姓は仲、いみ名は由、あざ名が子路。いみ名が顔路と同じであることから混同された。子路は一門の長老として、弟子と言うより年下の友人で、節操のない孔子がふらふらと謀反人のところに出掛けたりすると、どやしつける気概を持っていた。詳細は論語の人物:仲由子路を参照。
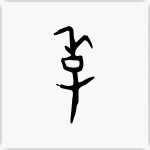

「季」(甲骨文)
「季」の初出は甲骨文。同音は存在しない。甲骨文の字形は「禾」”イネ科の植物”+「子」で、字形によっては「禾」に穂が付いている。字形の由来は不明。甲骨文では人名に用いた。金文でも人名に用いたほか、”末子”を意味した。詳細は論語語釈「季」を参照。


「路」(金文)
「路」の初出は西周中期の金文。字形は「足」+「各」”夊と𠙵”=人のやって来るさま。全体で人が行き来するみち。原義は”みち”。「各」は音符と意符を兼ねている。金文では「露」”さらす”を意味した詳細は論語語釈「路」を参照。
侍*(シ)


(金文)
論語の本章では(貴人の)”近くに待機する”。初出は西周中期の金文。ただし字形は「𢓊」。現行字形の初出は秦系戦国文字。原義は”はべる”。「ジ」は呉音(遣隋使より前に日本に伝わった音)。春秋末期までに、”はべる”・”列席する”の意に用いた。詳細は論語語釈「侍」を参照。
子曰(シエツ)(し、いわく)

論語の本章では”孔子先生が言った”。「子」は貴族や知識人に対する敬称で、論語では多くの場合孔子を指す。「子」は赤ん坊の象形、「曰」は口から息が出て来るさま。「子」も「曰」も、共に初出は甲骨文。辞書的には論語語釈「子」・論語語釈「曰」を参照。


(甲骨文)
この二文字を、「し、のたまわく」と読み下す例がある。「言う」→「のたまう」の敬語化だが、漢語の「曰」に敬語の要素は無い。古来、論語業者が世間からお金をむしるためのハッタリで、現在の論語読者が従うべき理由はないだろう。
盍(コウ)


(甲骨文)(玉器)
論語の本章では「何不」の合音字で、”なぜ~しないのか”。この語義は春秋時代では確認できない。『大漢和辞典』の第一義は”覆う”初出は甲骨文。ただし字形は「去」とされる。現行字体の初出は春秋末期の玉器。ただし字形は僅かに異なり「盇」。字形は器に盛った誓約の血に蓋をしたさまで、原義は”蓋をする”。”なんぞ…せざる”の用例は、文献時代まで時代が下る。詳細は論語語釈「盍」を参照。
各(カク)
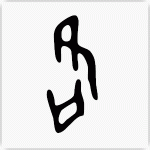

(甲骨文)
論語の本章では”それぞれ”。初出は甲骨文。字論語の本章では”それぞれ”。この語義は春秋時代では確認できない。初出は甲骨文。字形は「夊」”あし”+「𠙵」”くち”で、人がやってくるさま。原義は”来る”。甲骨文・金文では原義に用いた。”~に行く”・”おのおの”の意も西周の金文で確認できる。詳細は論語語釈「各」を参照。
言(ゲン)


(甲骨文)
論語の本章では”言う”。初出は甲骨文。字形は諸説あってはっきりしない。「口」+「辛」”ハリ・ナイフ”の組み合わせに見えるが、それがなぜ”ことば”へとつながるかは分からない。原義は”言葉・話”。甲骨文で原義と祭礼名の、金文で”宴会”(伯矩鼎・西周早期)の意があるという。詳細は論語語釈「言」を参照。
爾(ジ)


(甲骨文)
論語の本章では”お前”。初出は甲骨文。字形は剣山状の封泥の型の象形で、原義は”判(を押す)”。のち音を借りて二人称を表すようになって以降は、「土」「玉」を付して派生字の「壐」「璽」が現れた。甲骨文では人名・国名に用い、金文では二人称を意味した。詳細は論語語釈「爾」を参照。


定州竹簡論語では「璽」の異体字「壐」を用いる例が多い。「爾」の担っていた語義のうち”はんこ”を分担する語として派生した。初出は楚系戦国文字。同音無し。詳細は論語語釈「壐」を参照。
あえて派生した「壐」の字を用いたのは、昭和の珍走団が「夜露死苦」「仏恥義理」と書いたり、今世紀以降、如何わしい世間師が横文字を使っているのと同じハッタリで、つまりは筆記者の精神的虚弱を示している。
志(シ)


(金文)
論語の本章では”のぞみ”。平素こうありたいとする理想像のこと。『大漢和辞典』の第一義は”こころざし”。初出は戦国末期の金文で、論語の時代に存在しない。論語時代の置換候補は”知る”→「識」を除き存在しない。字形は「止」”ゆく”+「心」で、原義は”心の向かう先”。詳細は論語語釈「志」を参照。
子路(シロ)
論語の本章では、記録に残る孔子の最初の弟子、仲由子路のこと。
現伝論語の文頭では「季路」”次男坊の路”と記し、ここでは「子路」”お弟子の路”と記す。後世、顔回子淵の父親「顔路」と、弟子の仲由「子路」の区別がつかなくなったゆえの表記揺れ。
定州竹簡論語ではどちらも欠損しているため物証が無いが、上記の通り「季路」を「子路」だと言い出したのは、論語の時代より千年も後であり、とうてい信用するに値しない。
「子路」の名は「上海博物館蔵戦国楚竹簡」弟子問19などから見えるが、「季路」は文献時代にならないと見えず、『孟子』は言わず『荀子』が初出。現伝『孔子家語』が仲由子路について「一字季路」と言うのは、前漢中期にはすでに、「子路」と「季路」の区別が分からなくなったことを反映している。
曰(エツ)


(甲骨文)
論語で最も多用される、”言う”を意味する言葉。初出は甲骨文。原義は「𠙵」=「口」から声が出て来るさま。詳細は論語語釈「曰」を参照。
願(ゲン)


(燕系戦国文字)
論語の本章では”願う”。初出は燕系戦国文字。現行字体の初出は前漢の隷書。論語の時代に存在しない。論語時代の置換候補もない。「ガン」は慣用音、「ゴン」は呉音。同音は元や原を部品とする漢字群だが、”願う”の語義を持った文字は無い。部品の「原」には、”たずねる・根本を推求する”の語釈を『大漢和辞典』が載せるが、春秋時代以前の用例が無い。同音同訓「愿」の初出は後漢の『説文解字』。初出の字形は「月」”にく”+「复」”麺類生地の延べ棒”だが、字形から語義を導くのは困難。詳細は論語語釈「願」を参照。
車(シャ)


(甲骨文)
論語の本章では”くるま”。初出は甲骨文。甲骨文・金文の字形は多様で、両輪と車軸だけのもの、かさの付いたもの、引き馬が付いたものなどがある。字形はくるまの象形。原義は”くるま”。甲骨文では原義で、金文では加えて”戦車”に用いる。また氏族名・人名に用いる。「キョ」の漢音は将棋の「香車」を意味する。詳細は論語語釈「車」を参照。
馬(バ)


(甲骨文)
論語の本章では馬車を引く”馬”。初出は甲骨文。初出は甲骨文。「メ」は呉音。「マ」は唐音。字形はうまを描いた象形で、原義は動物の”うま”。甲骨文では原義のほか、諸侯国の名に、また「多馬」は厩役人を意味した。金文では原義のほか、「馬乘」で四頭立ての戦車を意味し、「司馬」の語も見られるが、”厩役人”なのか”将軍”なのか明確でない。戦国の竹簡での「司馬」は、”将軍”と解してよい。詳細は論語語釈「馬」を参照。
衣(イ)


(甲骨文)
論語の本章では”衣類”。初出は甲骨文。ただし「卒」と未分化。金文から分化する。字形は衣類の襟を描いた象形。原義は「裳」”もすそ”に対する”上着”の意。甲骨文では地名・人名・祭礼名に用いた。金文では祭礼の名に、”終わる”、原義に用いた。詳細は論語語釈「衣」を参照。
輕*(ケイ)
現存最古の論語本である定州竹簡論語は、この部分の簡に欠損があり、唐石経は「輕」字を記さず、清家本は記す。清家本は年代こそ唐石経より新しいが、より古い古注系の文字列を伝承しており、唐石経を訂正しうる。従って「輕」字があるものとして校訂した。
論語の伝承について詳細は「論語の成立過程まとめ」を参照。
原始論語?…→定州竹簡論語→白虎通義→ ┌(中国)─唐石経─論語注疏─論語集注─(古注滅ぶ)→ →漢石経─古注─経典釈文─┤ ↓↓↓↓↓↓↓さまざまな影響↓↓↓↓↓↓↓ ・慶大本 └(日本)─清家本─正平本─文明本─足利本─根本本→ →(中国)─(古注逆輸入)─論語正義─────→(現在) →(日本)─────────────懐徳堂本→(現在)


(楚系戦国文字)
論語の本章では”軽い”。新字体は「軽」。初出は楚系戦国文字で、論語の時代に存在しない。論語時代の置換候補もない。同音に「傾」など。語義を共有する文字は無い。字形は「車」+「巠」”たていと”で、「巠」は音符。原義は”軽い”。『大漢和辞典』で音ケイ訓かるいは他に存在しない。詳細は論語語釈「軽」を参照。
武内本は「輕の字唐石経行旁にあり、後人の加えし所、原刻輕字無きよし」とあるが、つまり武内博士は元の刻石や拓本を参照していないらしい。拓本では「輕の字行旁に」無い。

国会図書館蔵『唐開成石経』
裘*(キュウ)


(甲骨文)
論語の本章では”かわごろも”。初出は甲骨文。「求」と同音。甲骨文の字形はかわごろもの襟元で、原義は”毛皮の服”。「求」は後に音を表すため付けられたと見える。甲骨文では地名に用い、金文では氏族名、また原義で用いた。詳細は論語語釈「裘」を参照。

『三才圖會』所収「羔裘」(コウキュウ、仔羊の毛皮張り)。東京大学東洋文化研究所蔵
與(ヨ)


(金文)
論語の本章では”~と”。新字体は「与」。初出は春秋中期の金文。金文の字形は「牙」”象牙”+「又」”手”四つで、二人の両手で象牙を受け渡す様。人が手に手を取ってともに行動するさま。従って原義は”ともに”・”~と”。詳細は論語語釈「与」
朋(ホウ)→ (ホウ?)
(ホウ?)
唐石経・清家本は「朋」と記し、現存最古の論語本である定州竹簡論語は「![]() 」と記す。定州本の校勘記に従って「朋」のままとした。
」と記す。定州本の校勘記に従って「朋」のままとした。
論語の伝承について詳細は「論語の成立過程まとめ」を参照。
原始論語?…→定州竹簡論語→白虎通義→ ┌(中国)─唐石経─論語注疏─論語集注─(古注滅ぶ)→ →漢石経─古注─経典釈文─┤ ↓↓↓↓↓↓↓さまざまな影響↓↓↓↓↓↓↓ ・慶大本 └(日本)─清家本─正平本─文明本─足利本─根本本→ →(中国)─(古注逆輸入)─論語正義─────→(現在) →(日本)─────────────懐徳堂本→(現在)


(甲骨文)
論語の本章では”友人”。「朋友」で”友人・仲間”を意味する。初出は甲骨文。字形はヒモで貫いたタカラガイなどの貴重品をぶら下げたさまで、原義は単位の”一差し”。春秋末期までに原義と”朋友”の語義が確認できる。詳細は論語語釈「朋」を参照。
定州竹簡論語の「![]() 」は、『大漢和辞典』にもなくunicodeの指定も無い。定州竹簡論語の注釈に言う通り、「傰」の字を略して書いたとみられ、「傰」の字の初出は秦系戦国文字だが、『大漢和辞典』は戦国時代に編まれた『管子』を引いて、「朋」の意で通用したことを記す。
」は、『大漢和辞典』にもなくunicodeの指定も無い。定州竹簡論語の注釈に言う通り、「傰」の字を略して書いたとみられ、「傰」の字の初出は秦系戦国文字だが、『大漢和辞典』は戦国時代に編まれた『管子』を引いて、「朋」の意で通用したことを記す。
友(ユウ)
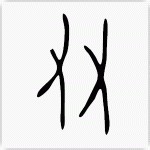

(甲骨文)
論語の本章では”友人”。初出は甲骨文。甲骨文の字形は複数人が腕を突き出したさまで、原義はおそらく”共同する”。論語の時代までに、”友人”・”友好”の用例がある。詳細は論語語釈「友」を参照。
共(キョウ)


(甲骨文)
論語の本章では”共有する”。原義の”差し出す”の派生義と考えられなくはない。初出は甲骨文。字形は「又」”手”二つ=両手+「口」。原義は”両手でものを捧げ持つさま”。派生義として”敬う”。「供」の原字。論語の時代までに”謹んで従う”の用例があり、「恭」を「共」と記している。また西周の金文に、”ともに”と読み得る例がある。詳細は論語語釈「共」を参照。
敝(ヘイ)


(甲骨文)
論語の本章では”破れ壊れる”。この語義は春秋時代では確認できない。初出は甲骨文。「弊」は異体字で15画。字形は「巾」”ぬの”+埃を示す点+「攴」”棒を持った手”で、汚れた布をはたいて清めるさま。甲骨文では埃の数や棒の有無など字形の異同がある。原義は”洗う”。甲骨文では地名に用い、金文には情報が無く、戦国の竹簡で「幣」”供え物”、「弊」”破れ疲れる”の意が、漢代の出土物で「蔽」”覆う”の意があると言う。詳細は論語語釈「敝」を参照。
之(シ)


(甲骨文)
論語の本章では、「敝之」「安之」「信之」「懷之」では”これ”。「子之志」では”~の”。初出は甲骨文。字形は”足”+「一」”地面”で、あしを止めたところ。原義はつま先でつ突くような、”まさにこれ”。殷代末期から”ゆく”の語義を持った可能性があり、春秋末期までに”…の”の語義を獲得した。詳細は論語語釈「之」を参照。
而(ジ)


(甲骨文)
論語の本章では”同時に”。初出は甲骨文。原義は”あごひげ”とされるが用例が確認できない。甲骨文から”~と”を意味し、金文になると、二人称や”そして”の意に用いた。英語のandに当たるが、「A而B」は、AとBが分かちがたく一体となっている事を意味し、単なる時間の前後や類似を意味しない。詳細は論語語釈「而」を参照。
無(ブ)→毋(ブ)


(甲骨文)
論語の本章では”~しない”。初出は甲骨文。「ム」は呉音。甲骨文の字形は、ほうきのような飾りを両手に持って舞う姿で、「舞」の原字。その飾を「某」と呼び、「某」の語義が”…でない”だったので、「無」は”ない”を意味するようになった。論語の時代までに、”雨乞い”・”ない”の語義が確認されている。戦国時代以降は、”ない”は多く”毋”と書かれた。詳細は論語語釈「無」を参照。


(金文)
定州竹簡論語の「毋」の、現行書体の初出は戦国文字で、無と同音。春秋時代以前は「母」と書き分けられておらず、「母」の初出は甲骨文。「毋」と「母」の古代音は、頭のmが共通しているだけで似ても似付かないが、「母」məɡ(上)には、”暗い”の語義が甲骨文からあった。詳細は論語語釈「毋」を参照。
憾*(カン)→ (カン?)→垐(シ)
(カン?)→垐(シ)
唐石経・清家本は「憾」と記し、現存最古の論語本である定州竹簡論語は「![]() 」と記す。「
」と記す。「![]() 」字は『大漢和辞典』にもunicodeにも無く、「垐」”にくむ”の異体字と仮に釈文し校訂した。
」字は『大漢和辞典』にもunicodeにも無く、「垐」”にくむ”の異体字と仮に釈文し校訂した。


(楷書)
「憾」は論語では本章のみに登場。初出は不明。論語の時代に存在しない。論語時代の置換候補もない。『春秋左氏伝』、『孟子』、『戦国策』、『後漢書』、南北朝時代の字書『玉篇』に用例があるようだが、どれが初出とも言いがたい。部品「感」の初出は戦国末期の金文。結論として論語時代の置換候補は無い。詳細は論語語釈「憾」を参照。

(定州竹簡論語)
定州竹簡論語の「![]() 」は『大漢和辞典』になく、unicodeの指定も無い。『大漢和辞典』の音カン訓うらむに「坎」があり、初出は後漢の『説文解字』。また近似の字形に「㰪」があり、上古音・初出共に不明だが、”なげく”・”よこしまなさま”の語釈を『大漢和辞典』が載せる。ただし南北朝期の『玉篇』、宋代の『集韻』を出典としており、語義も遠い。
」は『大漢和辞典』になく、unicodeの指定も無い。『大漢和辞典』の音カン訓うらむに「坎」があり、初出は後漢の『説文解字』。また近似の字形に「㰪」があり、上古音・初出共に不明だが、”なげく”・”よこしまなさま”の語釈を『大漢和辞典』が載せる。ただし南北朝期の『玉篇』、宋代の『集韻』を出典としており、語義も遠い。

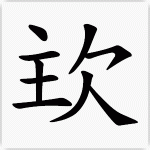
「垐」(篆書)(楷書化篆書)
「垐」(漢音シ)の初出は後漢の『説文解字』で「以土增大道上」とあることから”土を盛る”の意だが、篆書以前の字形は〔主〕”位牌”+〔欠〕”あくび”で、〔士壬〕+〔欠〕の「![]() 」字と近似。尊崇すべき対象に飽き、いとうさま。「小学堂」によると「堲」(漢音シツ)の異体字とされ、「堲」は漢代にはまとめられたとみられる『書経』舜典に「朕堲讒說殄行」とあり、”いとう”と解せる。詳細は論語語釈「垐」を参照。
」字と近似。尊崇すべき対象に飽き、いとうさま。「小学堂」によると「堲」(漢音シツ)の異体字とされ、「堲」は漢代にはまとめられたとみられる『書経』舜典に「朕堲讒說殄行」とあり、”いとう”と解せる。詳細は論語語釈「垐」を参照。
伐(ハツ)
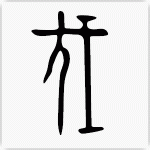

(甲骨文)
論語の本章では”自慢する”。この語義は春秋時代では確認できない。初出は甲骨文。「バツ」は慣用音。呉音は「ボチ」。字形は「人」+「戈」”カマ状のほこ”で、ほこで人の頭を刈り取るさま。原義は”首を討ち取る”。甲骨文では”征伐”、人の生け贄を供える祭礼名を意味し、金文では加えて人名(弔伐父鼎・年代不詳)に用いた。戦国の竹簡では加えて”刈り取る”を意味したが、”誇る”の意は文献時代にならないと見られない。詳細は論語語釈「伐」を参照。
善(セン)


(金文)
論語の本章では、”善事”。もとは道徳的な善ではなく、機能的な高品質を言う。「ゼン」は呉音。字形は「譱」で、「羊」+「言」二つ。周の一族は羊飼いだったとされ、羊はよいもののたとえに用いられた。「善」は「よい」「よい」と神々や人々が褒め讃えるさま。原義は”よい”。金文では原義で用いられたほか、「膳」に通じて”料理番”の意に用いられた。戦国の竹簡では原義のほか、”善事”・”よろこび好む”・”長じる”の意に用いられた。詳細は論語語釈「善」を参照。
施(シ/イ)
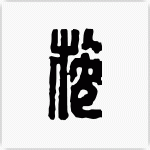
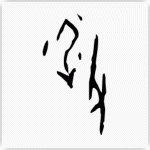
「施」(戦国時代篆書)/「𢼊」(甲骨文)
論語の本章では”およぼす”。初出は殷代末期あるいは西周早期の金文。現行字体の初出は戦国秦の篆書。”ほどこす”場合の漢音は「シ」、呉音は「セ」。”のびる”場合は漢音呉音共に「イ」。同音同義に「𢼊」(𢻱)が甲骨文から存在する。甲骨文「𢼊」の字形は”水中の蛇”+「攴」(攵)”棒を手に取って叩く”さまで、原義はおそらく”離れたところに力を及ぼす”。春秋末期までに、”のばす”・”およぼす”の意がある。詳細は論語語釈「施」を参照。
勞(ロウ)


(甲骨文)
論語の本章では”苦労”。新字体は「労」。初出は甲骨文。ただし字形は「褮」-「冖」。現行字体の初出は秦系戦国文字。甲骨文の字形は「火」二つ+「衣」+汗が流れるさまで、かがり火を焚いて昼夜突貫工事に従うさま。原義は”疲れる”。甲骨文では地名、”洪水”の意に用い、金文では”苦労”・”功績”・”つとめる”の用例がある。また戦国時代までの文献に、”ねぎらう”・”いたわる”・”はげます”の用例がある。詳細は論語語釈「労」を参照。
聞(ブン)
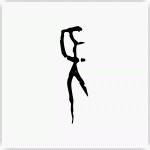
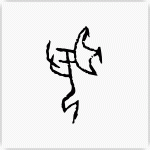
(甲骨文1・2)
論語の本章では”聞く”。初出は甲骨文。「モン」は呉音。甲骨文の字形は”耳の大きな人”または「斧」+「人」で、斧は刑具として王権の象徴で、殷代より装飾用の品が出土しており、玉座の後ろに据えるならいだったから、原義は”王が政務を聞いて決済する”。詳細は論語語釈「聞」を参照。
老(ロウ)


(甲骨文)
論語の本章では”老いた”。初出は甲骨文。字形は髪を伸ばし杖を突いた人の姿で、原義は”老人”。甲骨文では地名に用い、金文では原義で、”父親”、”老いた”の意に用いた。戦国の金文では”国歌の元老”の意に用いた。詳細は論語語釈「老」を参照。
者(シャ)


(金文)
論語の本章では”(…である)者”。旧字体は〔耂〕と〔日〕の間に〔丶〕一画を伴う。新字体は「者」。ただし唐石経・清家本ともに新字体と同じく「者」と記す。現存最古の論語本である定州竹簡論語も「者」と釈文(これこれの字であると断定すること)している。初出は殷代末期の金文。金文の字形は「木」”植物”+「水」+「口」で、”この植物に水をやれ”と言うことだろうか。原義は不明。初出では称号に用いている。春秋時代までに「諸」と同様”さまざまな”、”…は”の意に用いた。漢文では人に限らず事物にも用いる。詳細は論語語釈「者」を参照。
安(アン)


(甲骨文)
論語の本章では”安らがせる”。初出は甲骨文。字形は「宀」”やね”+「女」で、防護されて安らぐさま。論語の時代までに、”順調である”・”訪問する”を意味した。疑問詞・反問詞などに用いるのは戦国時代以降の当て字で、焉と同じ。詳細は論語語釈「安」を参照。
信(シン)
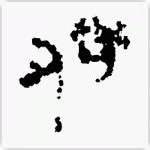

(金文)
論語の本章では、”信じさせる”。この語義は春秋時代では確認できない。初出は西周末期の金文。字形は「人」+「口」で、原義は”人の言葉”だったと思われる。西周末期までは人名に用い、春秋時代の出土が無い。”信じる”・”信頼(を得る)”など「信用」系統の語義は、戦国の竹簡からで、同音の漢字にも、論語の時代までの「信」にも確認出来ない。詳細は論語語釈「信」を参照。
少(ショウ)


(甲骨文)
論語の本章では”若い”。初出は甲骨文。カールグレン上古音はɕi̯oɡ(上/去)。字形は「∴」で”小さい”を表す「小」に一点足したもので、細かく小さいさま。原義は”小さい”。金文になってから、”少ない”、”若い”の意を獲得した。詳細は論語語釈「少」を参照。
懷(カイ)


(金文)
論語の本章では”好ましく思わせる”。新字体は「懐」。初出は西周早期の金文。ただし字形は「褱」。現行字体の初出は秦系戦国文字。同音は同訓の「褱」と異訓の「壊」(去)。「褱」の字形は「眔」+「衣」で、「眔」はのちに”視線で跡を追う”と解されたが、原義は「目」+「水」で”涙を流す”こと。「褱」は全体で”泣いて衣を濡らす”ことであり、そのような感情のさま。秦系戦国文字で”心”を示す「忄」がついたのは感情を示すダメ押し。原義は”泣くほどの思い”。金文では”思い”、”ふところ”、”与える”、「鬼」”亡霊”、”招き寄せる”の意に用いた。詳細は論語語釈「懐」を参照。
論語:付記
検証
論語の本章は、春秋戦国の誰一人引用していないし、先秦の誰も再録していない。前漢中期の定州竹簡論語が事実上の初出だが、簡の欠損がひどくて原文を再現しがたい。ただし弟子に子貢を加えて三人に答えさせている話が『韓詩外伝』『説苑』『孔子家語』にはある。
その三つとも話は似通っているが、論語の本章とはずいぶん違っている。例として『孔子家語』を挙げる。
孔子が北の農山へ山遊びに行き、子路、子貢、顔淵がお供をした。山上から孔子が四方を眺めて、感動のあまり長くため息をついて言った。「こんな所でものを考えれば、想像力に限りはあるまい。どうかね君たち、それぞれの思うところを言ってみなさい。知恵比べをしよう。」
子路が進み出て言った。「私の願いは戦場です。月のように白く、太陽のように赤い羽根飾りをかぶとに付け、軍楽が天に轟き、軍旗が所狭しと大地にはためく戦場で、私は一隊を率いて敵を迎え撃ち、必ず千里を進撃して、敵の軍旗をぶんどり、首を取りましょう。これは私だけが出来ることです。子貢と顔淵は使い走りにしましょう。」
先生が言った。「勇ましいことだな。」
子貢が次に進み出て言った。「私の願いは外交です。斉・楚両国に使いに出て、果て無き平原で合戦させてみましょう。両軍の陣が互いに見えるほど近づき、互いの戦車が砂煙を上げて近突撃し、兵は刀を抜き切り結ぶでしょう。まさにその時私が礼服を着て、両軍の陣を往復して利害を説き、戦乱の惨禍から国を守りましょう。これは私だけが出来ることです。子路と顔淵は使い走りにしましょう。」
先生が言った。「口の達者なことだな。」
しかし顔回は引き下がったまま答えなかった。孔子が言った。「顔回よ、来なさい。お前には願いがないのか?」
顔回が答えて言った。「文武の事は、もうすでにお二方が言ってしまいました。私が言えることなどありません。」
孔子が言った。「それはそうだろうが、二人とも言いたい事を言ったのだ。お前も言いなさい。」
顔回が答えて言った。「私はこう聞いています。香草と悪臭のする草は、同じ容れ物に入れない。聖王の堯は悪王の桀が居る限り、国を治めない。それはまるで違う二つだからだ、と。私の願いは、名君のもとで補佐することです。仁義礼智忠の五つの教えを世に広め、民を礼法と音楽で躾けます。そして民には築城や掘り割り工事の苦労を掛けず、武器は鋳つぶして農具にし、牛馬は原野に放ち、家族が荒野でさまよい離散する悲劇をなくし、千年の後まで戦争の惨禍を防ぎましょう。そうなれば子路は武勇を発揮する場所が無く、子貢が弁舌を発揮する場所も無くなるでしょう。」
先生は顔色を引き締めて顔淵に答えて言った。「よろしい、人徳のあることだ。」
子路が手を上げて尋ねた。「先生はどれがいいと思われたのですか。」
孔子が言った。「国富を浪費することもなく、民を痛めつけることもなく、べらべらと口車を回さない点では、とりもなおさず顔氏の子が一番だな。」(『孔子家語』致思第八1)


これはつまり、前漢前半の董仲舒による顔淵神格化キャンペーンを経た後だからこうなっているので、おそらく論語の本章はこれらより先行して元ネタとなっただろう。『韓詩外伝』より前ということは、成立は遅くとも前漢初期になる。
また本章の古注は、もとは前章「巧言令色足恭は…恥ず」とセットになっていた。前章がおそらく董仲舒の創作であることは前章を参照して頂きたいが、本章はセットであることから、顔淵神格化のために董仲舒が論語に取り込んだと思われる。
董仲舒についてより詳しくは、論語公冶長篇24余話を参照。また董仲舒による顔淵神格化の詳細は、論語先進篇3解説を参照。
解説
既存の論語本では吉川本が古注を引いて、晋の殷仲堪の説として、「自分のものを友達にくれてやる、というのは普通の行為であって、一行に変哲もない。友達の車馬衣裘を、自分がぼろぼろになるまで使っても気がおけないということでなければならぬ」と書く。
原文に当たると確かにそう書いてある。
殷仲堪曰施而不恨士之近行也若乃用人之財不覺非已推誠闇往感思不生斯乃交友之至仲由之志與也
殷仲堪曰く、施し而恨ま不るは士之近行也。若し乃ち人之財を用いて已が非を覺え不誠を推し闇かに往しても感じ思うところ生ぜ不るあらば、斯れ乃ち交友之至りにして仲由之志たる與也。
ずいぶん図々しい願いのように思う。
余話
死んでも地位は離さない

幕末のトンデモ儒者、佐藤一斎の『言志録』はおそらく本章から表題を取っている。どうトンデモかは論語里仁篇9余話「アルツハイマーの最高顧問」を参照。



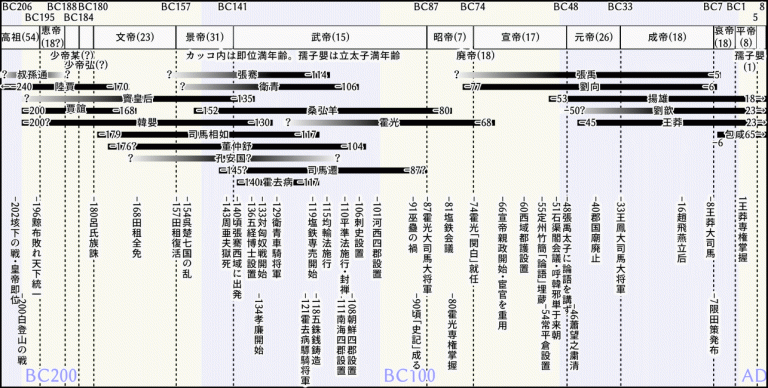


コメント