論語:原文・書き下し
原文(唐開成石経)
子張問曰令尹子文三仕爲令尹無喜色三巳之無愠色舊令尹之政必以吿新令尹何如子曰忠矣曰仁矣乎曰未知焉得仁崔子弒齊君陳文子有馬十乗弃而違之至於他邦曰猶吾大夫崔子也違之之一邦則又曰猶吾大夫崔子也違之何如子曰淸矣曰仁矣乎曰未知焉得仁
- 「弃」字:「棄」字の異体字。
校訂
東洋文庫蔵清家本
子張問曰令尹子文/三仕爲令尹無喜色三已之無愠色舊令尹之政必以吿新令尹何如也子曰忠矣曰仁矣乎曰未知焉得仁/崔子弒齊君陳文子有馬十乗棄而違之/至於他邦則又曰猶吾大夫崔子也違之至一邦則又曰猶吾大夫崔子也違之何如子曰清矣曰仁矣乎曰未知焉得仁
後漢熹平石経
(なし)
定州竹簡論語
子張問曰:97……違之。至於也國a,則曰,『猶吾大夫□子也。』違之。之一98……□曰:『猶吾大夫□子也。』違之。何如?」子曰:「□矣。」曰:99……
- 也國、今本作「他邦」。古文也与它字形近、『説文』無「他」字、有它、佗。佗可隷変為他、古文多作它。
標点文
子張問曰、「令尹子文、三仕爲令尹、無喜色。三已之、無慍色。舊令尹之政、必以吿新令尹。何如也。」子曰、「忠矣。」曰、「仁矣乎。」曰、「未知、焉得仁。」「崔子弒齊君、陳文子有馬十乘、棄而違之、至於也邦則曰、『猶吾大夫崔子也。』違之。之一邦則又曰、『猶吾大夫崔子也。』違之。何如。」子曰、「淸矣。」曰、「仁矣乎。」曰、「未知、焉得仁。」
復元白文(論語時代での表記)





































 忠
忠






 焉
焉


 弒
弒






















































 焉
焉

※張→(金文大篆)・仁→(甲骨文)・崔→衰。論語の本章は「忠」「焉」「弑」が論語の時代に存在しない。「問」「必」「何」「如」「乎」「未」「也」「猶」の用法に疑問がある。本章は漢帝国の儒者による創作である。
書き下し
子張問ふて曰く、令尹子文は、三たび仕へて令尹と爲りしも、喜ぶ色無く、三たび之を已めしも、慍む色無く、舊の令尹之政は、必ず以て新なる令尹に吿ぐ。何如ならん也と。子曰く、忠矣。曰く、仁あり矣乎。曰く、未だ知しからず、焉んぞ仁あるを得む。崔子齊の君を弑す。陳文子馬十乘有るも、棄て而之を違る。也なる邦於至れば則ち曰く、猶ほ吾が大夫崔子のごとき也と、之を違る。一なる邦に之けば則ち又曰く、猶ほ吾が大夫崔子のごとき也と、之を違る。何如ならんと。子曰く、淸げ矣。曰く、仁あり矣乎。曰く、未だ知しからず、焉んぞ仁あるを得むと。
論語:現代日本語訳
逐語訳


子張が質問して言った。「令尹の子文は、三度令尹に任じられても喜ばず、三度免職されても怒らず、それまでの令尹の仕事を新令尹に引き継ぎました。どうでしょう」。先生が言った。「正直者だ」。「情け深いと言えますか?」「知者ではないから情け深くない」。「崔子が斉の国君を殺した際、陳文子は馬車十台分の馬を飼っていましたがそれを捨てて国を出ました。ある外国に行けば”やはり我が国の大臣、崔子のような者がいる”と言って出国しました。別の国に行けば”やはり我が国の大臣、崔子のような者がいる”と言って出国しました。どうでしょう」。「潔癖症だな」。「情け深いと言えますか?」「知者ではないから情け深くない」。
意訳


子張「楚の宰相だった子文は、三度職についてそのたび首になりましたが、喜びも怒りもしませんでした。仕事の引き継ぎはちゃんとしました。どうでしょう?」
孔子「正直者だ。」
「情け深いと言えますか?」「頭が悪い。情け深い者としては失格だ。」
「斉の家老崔子が国君を殺した時、陳文子は財産を放り出して亡命しました。逃げ先で”ここにも崔みたいな奴が!”と言って次々逃亡しました。どうでしょう?」
「潔癖にもほどがある。」
「情け深いと言えますか?」「頭が悪い。情け深い者としては失格だ。」
従来訳
子張が先師にたずねた。――
「子文は三度令尹の職にあげられましたが、べつにうれしそうな顔もせず、三度その職をやめられましたが、べつに不平そうな顔もしなかったそうです。そして、やめる時には、気持よく政務を新任の令尹に引きついだということです。こういう人を先生はどうお考えでございましょうか。」
先師はいわれた。――
「忠実な人だ。」
子張がたずねた。――
「仁者だとは申されますまいか。」
先師がこたえられた。――
「どうかわからないが、それだけきいただけでは仁者だとは断言出来ない。
子張が更にたずねた。――――
「崔子が斉の荘公を弑したときに、陳文子は馬十乗もあるほどの大財産を捨てて国を去りました。ところが、他の国に行って見ると、そこの大夫もよろしくないので、『ここにも崔子と同様の大夫がいる。』といって、またそこを去りました。それから更に他の国に行きましたが、そこでも、やはり同じようなことをいって、去ったというのです。かような人物はいかがでしょう。」
先師がこたえられた。――
「純潔な人だ。」
子張がたずねた。――
「仁者だとは申されますまいか。」
先師がいわれた。――
「どうかわからないが、それだけきいただけでは、仁者だとは断言出来ない。」下村湖人『現代訳論語』
現代中国での解釈例
子張問:「子文三次做宰相時,沒感到高興;三次被罷免時,沒感到委屈。卸任前,總是認真地辦理交接事宜,怎樣?」孔子說:「算忠心了。」問:「算仁嗎?」答:「不知道,哪來仁?」又問:「崔子殺了齊莊公,陳文子拋棄家產跑了。到了另一國,他說:『這裏的大夫同崔子一樣。』又跑了。再到一國,再說:『他們同崔子一樣。』再跑了。怎樣?」孔子說:「算清白了。」問:「算仁嗎?」答:「不知道,哪來仁?」
子張が問うた。「子文は三度宰相になったとき、喜びを感じませんでしたし、三度クビになったとき、落ち込みを感じませんでした。免職の前、いずれもまじめに引き継ぎの事務を処理しました。どうでしょう?」孔子が言った。「忠義者に数えていいな。」問うた。「仁者に数えていいですか?」答えた。「知らぬ。どうして仁だ?」また問うた。「崔子は斉の荘公を殺し、陳文子は家産を放り出して逃げました。外国の一つに至ると、彼は言いました。”ここの家老も崔子と同じだ。”また逃げました。さらに外国の一つに至ると、また言いました。”彼らも崔子と同じだ。”また逃げました。どうでしょう?」孔子が言った。「潔癖者に数えてよい。」問うた。「仁者ですか?」答えた。「知らぬ。どうして仁だ?」
論語:語釈
子 張 問 曰、「令 尹 子 文、三 仕 爲 令 尹、無 喜 色。三 已 之、無 慍 色。舊 令 尹 之 政、必 以 吿 新 令 尹 。何 如。」子 曰、「忠 矣。」曰、「仁 矣 乎。」曰、「未 知、焉 得 仁。」「 崔 子 弒 齊 君、陳 文 子 有 馬 十 乘、棄 而 違 之、至 於 也(他) 邦、則 曰、『猶 吾 大 夫 崔 子 也。』違 之、之 一 邦、則 又 曰、『猶 吾 大 夫 崔 子 也。』違 之。何 如。」子 曰、「 淸 矣。」曰、「仁 矣 乎。」曰、「未 知、焉 得 仁。」
子張

「張」(金文大篆)
孔子の弟子。「何事もやりすぎ」と評された。張の字は論語の時代に存在しないが、固有名詞なので偽造と断定できない。詳細は論語の人物・子張参照。
「子」の初出は甲骨文。原義は”殷王室の男子”。春秋時代では、子張のように学派の弟子や一般貴族は「子○」と呼び、孔子のように学派の開祖や陳文子のような大貴族は、「○子」と呼ぶ。本章の「子文」は黄河文明圏ではない楚国ゆえの例外。論語語釈「子」を参照。
「張」の初出は楚系戦国文字。論語の時代に存在しないが、固有名詞のため、同音近音のあらゆる漢語が置換候補になり得る。字形は「弓」+「長」で、弓に長い弦を張るさま。原義は”張る”。「戦国の金文に氏族名で用いた例がある。論語語釈「張」を参照。
問(ブン)


(甲骨文)
論語の本章では”質問する”。この語義は春秋時代では確認できない。初出は甲骨文。「モン」は呉音(遣隋使より前に日本に伝わった音)。字形は「門」+「口」。甲骨文での語義は不明。西周から春秋に用例が無く、一旦滅んだ漢語である可能性がある。戦国の金文では人名に用いられ、”問う”の語義は戦国最末期の竹簡から。それ以前の戦国時代、「昏」または「𦖞」で”問う”を記した。詳細は論語語釈「問」を参照。
曰(エツ)


(甲骨文)
論語で最も多用される、”言う”を意味する言葉。初出は甲骨文。原義は「𠙵」=「口」から声が出て来るさま。詳細は論語語釈「曰」を参照。
令尹(レイイン)
論語の本章では、南方の大国・楚の宰相のこと。越など南方諸国も宰相職として置いた。
元々は古代中国の殷王朝における役職で宰相の位に相当する。原義は神官職の長のことであり、古代の政治は祭事と一体であったことが伺われる。
殷が周に滅ぼされたとき殷の役人の多くが南に亡命し、南方の王国楚は殷の進んだ文化を吸収するためにこれらの人々を積極的に受け入れた。このため春秋時代の楚では殷の官職の呼称が受け継がれ、楚における宰相の地位に相当する位は令尹と呼ばれた。(wikipedia令尹条)
wikipediaの記述は中国語版の翻訳ではなく独自のもので、殷代にその官名があり神官長を指すと言う話は役者にとっては初耳。「尹」の字は甲骨文からあり、「令尹乍大田」=尹を令て大いに田を乍らしむ(『甲骨文合集』9472正)とあるから、「尹」は確かに官名の一つでありうる。

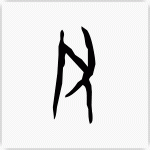
(甲骨文)
子文(シブン)
鬬㝅於菟(とう こくおと、生没年不詳)は、中国春秋時代の楚の公族で宰相(令尹)。姓は羋、氏は鬬、諱は㝅於菟(㝅は乳、於菟は虎)、字は子文。楚の君主の若敖の子の鬬伯比の子。清廉で知られ、楚屈指の賢相といわれる。(wikipedia鬬㝅於菟条)
若敖は位BC790?-BC764?。丁度西周が滅び東周が成立した、春秋時代当初の楚王。孔子の生年はBC551とされる。
子文は楚の成王八年(BC664)に令尹となり、地方領主の組合に過ぎなかった楚国の集権化を図って国家らしくし、弦国を滅ぼして併合し、随国を攻めた。
姓が楚王と同じく「羋」であることから王族で、氏の「鬬」は『大漢和辞典』にも見えないが「闘」の異体字とされる。いみ名の「㝅於菟」とも合わせ、楚国が長江文明を代表する一つの世界で、黄河文明を代表する周とその諸侯国群とは異質であることが見て取れる。
またあざ名の「子文」も黄河文明圏の常識からすると異質で、宰相を務めるような大貴族は通常、本章の「陳文子」のように「○子」と呼ばれる。あざ名や贈り名としての「文」は、晋の文公やのちの文帝のように、”教養も慈悲もある最高の業績を挙げた人”の意味だが、「子文」という呼び方は、異文明である楚に対する若干のさげすみを伴っている。おそらく当時の楚人が付けた名ではあるまい。
三(サン)


(甲骨文)
論語の本章では”三たび”。初出は甲骨文。原義は横棒を三本描いた指事文字で、もと「四」までは横棒で記された。「算木を三本並べた象形」とも解せるが、算木であるという証拠もない。詳細は論語語釈「三」を参照。
仕(シ)
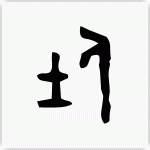

(戦国金文)
論語の本章では”出仕する”。この語義は春秋時代では確認できない。初出は甲骨文。春秋末期までの金文は未発掘。字形は「士」+「人」で、原義は”役人”。戦国の金文で地名や人名に用いた。同音異調の「事」や部品の「士」が論語時代の置換候補となる。詳細は論語語釈「仕」を参照。
訳者の個人的感想では、おそらく「士」と記して論語の時代に”つかえる”を意味したろうが、物証の無いことは無いと受け入れねばならない。
爲(イ)
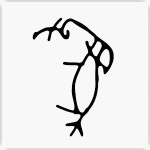

(甲骨文)
論語の本章では”地位に就く”。新字体は「為」。字形は象を調教するさま。甲骨文の段階で、”ある”や人名を、金文の段階で”作る”・”する”・”~になる”を意味した。詳細は論語語釈「為」を参照。
無(ブ)


(甲骨文)
論語の本章では”出さない”。日本語では「ない」は形容詞か助動詞だが、漢語では動詞。英語の”deny”に相当する。初出は甲骨文。「ム」は呉音。甲骨文の字形は、ほうきのような飾りを両手に持って舞う姿で、「舞」の原字。その飾を「某」と呼び、「某」の語義が”…でない”だったので、「無」は”ない”を意味するようになった。論語の時代までに、”雨乞い”・”ない”の語義が確認されている。戦国時代以降は、”ない”は多く”毋”と書かれた。詳細は論語語釈「無」を参照。
喜(キ)
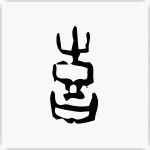

(甲骨文)
論語の本章では”よろこんだ”。初出は甲骨文。初出は甲骨文。字形は「壴」”つづみ”+「𠙵」”くち”で、太鼓を叩きながら歌を歌うさま。原義は”神楽”。甲骨文では原義のほか人名・国名に、”よろこぶ”の意に用い、金文では人名と楽曲名のほかは、”祭祀”、原義に用いた。詳細は論語語釈「喜」を参照。
色(ソク)
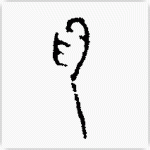

(金文)
論語の本章では”表情”。初出は西周早期の金文。「ショク」は慣用音。呉音は「シキ」。金文の字形の由来は不詳。原義は”外見”または”音色”。詳細は論語語釈「色」を参照。
巳(シ)→已(イ)
論語の本章では”辞める”。
唐石経は「巳」と記し、清家本は「已」と記す。現存最古の論語本である定州竹簡論語はこの部分を欠く。清家本は唐石経より年代は新しいが、唐石経より古い古注系の文字列を伝える。従って清家本で唐石経を訂正しうる。
論語の古本では、このほか「己」字も「巳」字・「已」字と混用される。つまり唐代頃までは「巳」”へび”と「已」”すでに”と「己」”おのれ”は相互に異体字として通用した。
論語の伝承について詳細は「論語の成立過程まとめ」を参照。
原始論語?…→定州竹簡論語→白虎通義→ ┌(中国)─唐石経─論語注疏─論語集注─(古注滅ぶ)→ →漢石経─古注─経典釈文─┤ ↓↓↓↓↓↓↓さまざまな影響↓↓↓↓↓↓↓ ・慶大本 └(日本)─清家本─正平本─文明本─足利本─根本本→ →(中国)─(古注逆輸入)─論語正義─────→(現在) →(日本)─────────────懐徳堂本→(現在)


(甲骨文)
「巳」の初出は甲骨文。字形はヘビの象形。「ミ」は呉音。甲骨文では干支の六番目に用いられ、西周・春秋の金文では加えて、「已」”すでに”・”ああ”・「己」”自分”・「怡」”楽しませる”・「祀」”まつる”の意に用いた。詳細は論語語釈「巳」を参照。


(甲骨文)
「已」の初出は甲骨文。字形と原義は不詳。字形はおそらく農具のスキで、原義は同音の「以」と同じく”手に取る”だったかもしれない。論語の時代までに”終わる”の語義が確認出来、ここから、”~てしまう”など断定・完了の意を容易に導ける。詳細は論語語釈「已」を参照。
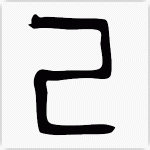

(甲骨文)
なお「己」字の初出は甲骨文。「コ」は呉音。字形はものを束ねる縄の象形だが、甲骨文の時代から十干の六番目として用いられた。従って原義は不明。”自分”の意での用例は春秋末期の金文に確認できる。詳細は論語語釈「己」を参照。
之(シ)


(甲骨文)
論語の本章では「三已之」などでは”これ”。「舊令尹之政」では”…の”。「之一邦」では”行く”。初出は甲骨文。字形は”足”+「一」”地面”で、あしを止めたところ。原義はつま先でつ突くような、”まさにこれ”。殷代末期から”ゆく”の語義を持った可能性があり、春秋末期までに”…の”の語義を獲得した。詳細は論語語釈「之」を参照。
慍(ウン)


(金文)
論語の本章ではうらむ、ではなく”怒る”。現行字体の初出は後漢の説文解字。異体字の初出は春秋時代の金文。原義は最古の字体が「人」+「風呂桶」+「心」であることから、”怒る”と思われる。詳細は論語語釈「慍」を参照
舊(キュウ)


(甲骨文)
論語の本章では”もと”。新字体は「旧」。初出は甲骨文。字形は鳥が古い巣から飛び立つ姿で、原義は”ふるい”。甲骨文では原義、地名に用い、金文では原義、”昔の人”、”長久”の意に用いた。詳細は論語語釈「旧」を参照。
政(セイ)


(甲骨文)
論語の本章では”政治”。初出は甲骨文。ただし字形は「足」+「丨」”筋道”+「又」”手”。人の行き来する道を制限するさま。現行字体の初出は西周早期の金文で、目標を定めいきさつを記すさま。原義は”兵站の管理”。論語の時代までに、”征伐”、”政治”の語義が確認できる。詳細は論語語釈「政」を参照。
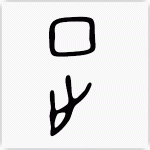

「正」(甲骨文)
定州竹簡論語では本章の前半を欠くが、他の例から見ておそらく「正」と記しただろう。初出は甲骨文。字形は「囗」”城塞都市”+そこへ向かう「足」で、原義は”遠征”。甲骨文では「正月」をすでに年始の月とした。また地名・祭礼名にも用いた。金文では、”征伐”・”年始”のほか、”長官”、”審査”の意に用いた。”正直”の意は戦国時代の竹簡からで、同時期に「征」”徴税”の字が派生した。詳細は論語語釈「正」を参照。


前漢宣帝期の定州竹簡論語が「正」と記した理由は、恐らく前王朝・秦の始皇帝のいみ名「政」を避けたため(避諱)。前漢帝室の公式見解では、漢帝国の開祖・高祖劉邦は秦帝国に反乱を起こして取って代わったのではなく、秦帝国の正統な後継者と位置づけていた。
必(ヒツ)


(甲骨文)
論語の本章では”必ず”。この語義は春秋時代では確認できない。初出は甲骨文。原義は先にカギ状のかねがついた長柄道具で、甲骨文・金文ともにその用例があるが、”必ず”の語義は戦国時代にならないと、出土物では確認できない。『春秋左氏伝』や『韓非子』といった古典に”必ず”での用例があるものの、論語の時代にも適用できる証拠が無い。詳細は論語語釈「必」を参照。
以(イ)


(甲骨文)
論語の本章では”それで”。初出は甲骨文。人が手に道具を持った象形。原義は”手に持つ”。論語の時代までに、名詞(人名)、動詞”用いる”、接続詞”そして”の語義があったが、前置詞”…で”に用いる例は確認できない。ただしほとんどの前置詞の例は、”用いる”と動詞に解せば春秋時代の不在を回避できる。詳細は論語語釈「以」を参照。
吿(コク)


(甲骨文)
論語の本章では”告げる”→”引き継ぎをする”。初出は甲骨文。新字体は「告」。字形は「辛」”ハリまたは小刀”+「口」。甲骨文には「辛」が「屮」”草”や「牛」になっているものもある。字解や原義は、「口」に関わるほかは不詳。甲骨文で祭礼の名、”告げる”、金文では”告発する”の用例がある。詳細は論語語釈「告」を参照。
新(シン)


(甲骨文)
論語の本章では”新しい”。初出は甲骨文。甲骨文の字形は「辛」”針または刃物”+「木」+「斤」”おの”で、早期の字形では「木」を欠く。切り出した丸太の中央に太い針を刺し、それを軸に回しながら皮を剥くさま。真新しい木肌が現れることから、原義は”新しい”。甲骨文では原義で、また地名・人名・祭祀名に用いた。金文でも同様。詳細は論語語釈「新」を参照。
何如(いかならん)


論語の本章では”どうでしょう”。「何」が「如」=”同じ”か、の意。対して「如何」は”どうしましょう”。
- 「何・如」→何に従っているか→「いかならん」”どうでしょう”。
- 「如・何」→従うべきは何か→「いかんせん」”どうしましょう”。
「いかん」と読み下す一連の句形については、漢文読解メモ「いかん」を参照。


「何」(甲骨文)
「何」は論語の本章では”なに”。この語義は春秋時代では確認できない。初出は甲骨文。字形は「人」+”天秤棒と荷物”または”農具のスキ”で、原義は”になう”。甲骨文から人名に用いられたが、”なに”のような疑問辞での用法は、戦国時代の竹簡まで時代が下る。詳細は論語語釈「何」を参照。


「如」(甲骨文)
「如」は論語の本章では”…のような(もの)”。この語義は春秋時代では確認できない。初出は甲骨文。字形は「口」+「女」。甲骨文の字形には、上下や左右に部品の配置が異なるものもあって一定しない。原義は”ゆく”。詳細は論語語釈「如」を参照。
古注では「令尹子文…如何也」となっており、定州竹簡論語ではこの部分が欠損している、または始めから存在しないが、「陳文子…如何」では「也」を欠いている。従って古注の「也」は後漢儒による付け足しとみられ、校訂に反映しなかった。
子曰(シエツ)(し、いわく)

論語の本章では”孔子先生が言った”。「子」は貴族や知識人に対する敬称で、論語では多くの場合孔子を指す。「子」は赤ん坊の象形、「曰」は口から息が出て来るさま。「子」も「曰」も、共に初出は甲骨文。辞書的には論語語釈「子」・論語語釈「曰」を参照。


(甲骨文)
この二文字を、「し、のたまわく」と読み下す例がある。「言う」→「のたまう」の敬語化だが、漢語の「曰」に敬語の要素は無い。古来、論語業者が世間からお金をむしるためのハッタリで、現在の論語読者が従うべき理由はないだろう。
忠(チュウ)

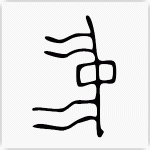
「忠」(金文)/「中」(甲骨文)
論語の本章では”忠実”。初出は戦国末期の金文。ほかに戦国時代の竹簡が見られる。字形は「中」+「心」で、「中」に”旗印”の語義があり、一説に原義は上級者の命令に従うこと=”忠実”。ただし『墨子』・『孟子』など、戦国時代以降の文献で、”自分を偽らない”と解すべき例が複数あり、それらが後世の改竄なのか、当時の語義なのかは判然としない。「忠」が戦国時代になって現れた理由は、諸侯国の戦争が激烈になり、領民に「忠義」をすり込まないと生き残れなくなったため。詳細は論語語釈「忠」を参照。
矣(イ)


(金文)
論語の本章では、”~である”。初出は殷代末期の金文。字形は「𠙵」”人の頭”+「大」”人の歩く姿”。背を向けて立ち去ってゆく人の姿。原義はおそらく”…し終えた”。ここから完了・断定を意味しうる。詳細は論語語釈「矣」を参照。
仁(ジン)


(甲骨文)
論語の本章では、”情け深さ”。仮に本章が史実なら、”貴族(らしさ)”。初出は甲骨文。字形は「亻」”ひと”+「二」”敷物”で、原義は敷物に座った”貴人”。詳細は論語語釈「仁」を参照。
”なさけ・あわれみ”などの道徳的意味は、孔子没後一世紀後に現れた孟子による、「仁義」の語義であり、孔子や高弟の口から出た「仁」の語義ではない。字形や音から推定できる春秋時代の語義は、敷物に端座した”よき人”であり、”貴族”を意味する。詳細は論語における「仁」を参照。
乎(コ)


(甲骨文)
論語の本章では、”…か”。疑問の意を示す。この語義は春秋時代では確認できない。初出は甲骨文。甲骨文の字形は持ち手を取り付けた呼び鐘の象形で、原義は”呼ぶ”こと。甲骨文では”命じる”・”呼ぶ”を意味し、金文も同様で、「呼」の原字となった。句末の助辞として用いられたのは、戦国時代以降になる。ただし「烏乎」で”ああ”の意は、西周早期の金文に見え、句末でも詠嘆の意ならば論語の時代に存在した可能性がある。詳細は論語語釈「乎」を参照。
未(ビ)


(甲骨文)
論語の本章では”まだ…でない”。この語義は春秋時代では確認できない。初出は甲骨文。「ミ」は呉音。字形は枝の繁った樹木で、原義は”繁る”。ただしこの語義は漢文にほとんど見られず、もっぱら音を借りて否定辞として用いられ、「いまだ…ず」と読む再読文字。ただしその語義が現れるのは戦国時代まで時代が下る。詳細は論語語釈「未」を参照。
知(チ)


「知」(甲骨文)
論語の本章では”智恵者”。「知」の現行書体の初出は春秋早期の金文。春秋時代までは「智」と区別せず書かれた。甲骨文で「知」・「智」に比定されている字形には複数の種類があり、原義は”誓う”。春秋末期までに、”知る”を意味した。”知者”・”管掌する”の用例は、戦国時時代から。現在最古の論語のテキストである、定州漢墓竹簡論語は、論語の本章のこの部分を欠いているが、他の例では「知」を「智」の古書体「𣉻」で書いている。詳細は論語語釈「知」・論語語釈「智」を参照。
焉(エン)
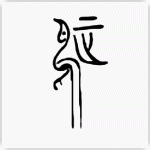

(金文)
論語の本章では「いずくんぞ」と読んで、”どうして”を意味する反語のことば。初出は戦国早期の金文で、論語の時代に存在せず、論語時代の置換候補もない。漢学教授の諸説、「安」などに通じて疑問辞や完了・断定の言葉と解するが、いずれも春秋時代以前に存在しないか、その用例が確認できない。ただし春秋時代までの中国文語は、疑問辞無しで平叙文がそのまま疑問文になりうるし、完了・断定の言葉は無くとも文意がほとんど変わらない。
字形は「鳥」+「也」”口から語気の漏れ出るさま”で、「鳥」は装飾で語義に関係が無く、「焉」は事実上「也」の異体字。「也」は春秋末期までに句中で主格の強調、句末で詠歎、疑問や反語に用いたが、断定の意が明瞭に確認できるのは、戦国時代末期の金文からで、論語の時代には存在しない。詳細は論語語釈「焉」を参照。
得(トク)


(甲骨文)
論語の本章では”資質を身につける”。初出は甲骨文。甲骨文に、すでに「彳」”みち”が加わった字形がある。字形は「貝」”タカラガイ”+「又」”手”で、原義は宝物を得ること。詳細は論語語釈「得」を参照。
崔子(サイシ)

?ーBC546。孔子が生まれた頃の斉の大夫、崔抒。妻を国君の荘公に寝取られたため、荘公を殺した。その後専権をふるった。
(荘公)六年(BC548)、棠公の妻は美貌で知られていた。棠公が死んだので、崔杼が娶った。ところが荘公がこの女と密通し、たびたび崔杼の屋敷に行き、留守の間にくすねた崔杼の冠を人にやった。侍従は「いけません」と諌めた。当然、崔杼は怒った。
五月…崔杼は病気だと言って、政治を執らなくなった。乙亥、荘公が崔杼の見舞いに来たが、そこで崔杼の妻を追いかけ回した。崔杼の妻は居間に逃げ、崔杼と共に戸を閉じて出てこなかった。
荘公は柱を抱いて歌った。…崔杼の家臣が武器を持ち、居間から出てきた。荘公は台に登って、解き放つよう願ったが、家臣は許さなかった。崔杼と約束したいと願ったが、許さなかった。斉国の祖先祭殿で自殺したいと願ったが、許さなかった。
崔杼の家臣は口を揃えて言った。「殿の家臣、崔杼は病気で、その命令を聞くことが出来ません。ここは斉国の宮殿にも近いので、我らは夜警に立っていました。間男を見つけたら殺せと崔杼に命じられています。その他の命令は聞きません。」
荘公は屋敷の外壁を飛び越えたが、家臣の射た矢が股に当たった。荘公は転げ落ち、とうとう殺されてしまった。(『史記』斉世家)
「崔子」とは、崔杼に対する敬称。”崔杼どの”にあたる。

(前漢隷書)
崔の字の初出は前漢の隷書で、論語の時代に存在しないが、固有名詞なので、近音のいかなる漢字も論語時代の置換候補になりうる。春秋末期の金文では、人名「崔」を「衰」と記し、「衰」の初出は西周中期の金文。語義は”山が高くそびえたさま”。同音は「摧」”おさえる”のみで、初出は後漢の『説文解字』。詳細は論語語釈「崔」を参照。
弒(シ)


(篆書)
論語の本章では”(主君を)殺す”。初出は後漢の『説文解字』で、戦国時代の竹簡に「式」を「弑」と釈文した例がある。論語の時代に存在しない。論語時代の置換候補もない。字形は「𣏂」”殺の略体”+「式」。「式」に”する”の意があり、『学研漢和大字典』によると、下が上を殺すというのを避けて、「する、やった」といった一種の忌みことば、という。詳細は論語語釈「弑」を参照。
齊君(セイクン)
「齊」の新字体は「斉」。上掲の通り、崔杼に殺された姜氏(太公望の家系)斉国の第25代国君、荘公(立派な殿様、の意)のこと。位BC553-BC548。在位年間は孔子の生誕(BC551)前後になる。
武を好み、気性が荒かったため、父の霊公に廃嫡されるが、霊公の死後、宰相である崔杼に擁立されて太子牙を幽閉して斉公となる。一説には病床の霊公を殺して斉公として立ったとも言われる。その後、再び確執があり、太傅の高厚を殺害した。
彼の時代には斉は隆盛し、政治的には安定していたが、荘公自身は贅沢を好み、諫言を嫌った。晋の卿の欒盈(中国語版)が反乱を起こして敗れ、斉へ亡命してきたときは、これを歓迎して復讐に手を貸そうとして晏嬰に諫言された。それゆえ荘公は晏嬰を退けた。(wikipedia斉荘公条)
陳文子(チンブンシ)
陳 須無(ちん しゅぶ、生没年不詳)は、春秋時代の斉の大夫で、田氏の宗主。姓は嬀、氏は陳、あるいは田、諱は須無、諡は文。陳文子あるいは田文子とも呼称される。…紀元前548年、崔杼が棠姜を妻に迎えようとしたため、陳須無はこれに反対したが、崔杼は聞き入れなかった。荘公が棠姜と密通し、崔杼は激怒して、荘公を殺害した。(wikipedia陳須無条)
陳文子の三代前を陳完といい、南方の陳国の公族だったが、政争に敗れて斉に亡命した。この家系がのちに姜氏の斉国を乗っ取って国主となり、それ以降の斉国を田斉ともいう。


田斉の5代宣王に仕えたのが孟子で、孟子は田斉王家の後ろめたさを誤魔化すため、当時墨家が主張していた中国最古の君主・禹に位を譲った聖王として舜を創作した。その末裔が陳の公室で、田斉王室もまた同じというのである。

後世、孟子の系統を引く儒者が儒教や政界官界を牛耳ったので、舜の存在や陳や田斉の祖先伝説は疑いない事実として扱われ、「周の武王は聖王舜の末裔を探し出して諸侯に任じ、陳の地を与えた」というでっち上げは史実として扱われた。

九年衛鼎・西周中期
これが事実とするなら、「陳」の字は西周当初からあるはずだが、2021年現在、初出は西周中期の金文。国名としての用例は、西周末期まで時代が下る。詳細は論語語釈「陳」を参照。なお「舜」の字の初出も楚系戦国文字。論語語釈「舜」を参照。
有(ユウ)


(甲骨文)
論語の本章では”所有する”。初出は甲骨文。ただし字形は「月」を欠く「㞢」または「又」。字形はいずれも”手”の象形。原義は両腕で抱え持つこと。詳細は論語語釈「有」を参照。
馬(バ)


(甲骨文)
論語の本章では馬車を引く”馬”。初出は甲骨文。初出は甲骨文。「メ」は呉音。「マ」は唐音。字形はうまを描いた象形で、原義は動物の”うま”。甲骨文では原義のほか、諸侯国の名に、また「多馬」は厩役人を意味した。金文では原義のほか、「馬乘」で四頭立ての戦車を意味し、「司馬」の語も見られるが、”厩役人”なのか”将軍”なのか明確でない。戦国の竹簡での「司馬」は、”将軍”と解してよい。詳細は論語語釈「馬」を参照。
十(シュウ)


(甲骨文1・2)
論語の本章では数字の”じゅう”。初出は甲骨文。「ジュウ」は呉音。甲骨文の字形には二種類の系統がある。横線が「1」を表すのに対して、縦線で「10」をあらわしたものと想像される。「ト」形のものは、「10」であることの区別のため一画をつけられたものか。詳細は論語語釈「十」を参照。
乘(ショウ)
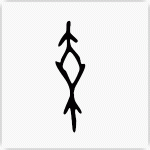

(甲骨文)
論語の本章では馬車を数える助数詞”両”。初出は甲骨文。新字体は「乗」。「ジョウ」は呉音。甲骨文の字形は人が木に登ったさまで、原義は”のぼる”。甲骨文では原義に加えて人名に、金文では”乗る”、馬車の数量詞、数字の”四”に用いられた。詳細は論語語釈「乗」を参照。
棄(キ)
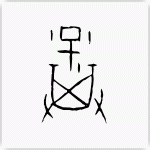

(甲骨文)
論語の本章では”捨てる”。初出は甲骨文。字形は「子」+「∴」”ごみ”+「其」+「廾」”両手”で、子をゴミと共にちりとりに取って捨てるさま。原義は”捨てる”。西周の金文では”捨てる”を意味し、春秋の金文では人名に用いた。詳細は論語語釈「棄」を参照。
而(ジ)


(甲骨文)
論語の本章では”~かつ~”。初出は甲骨文。原義は”あごひげ”とされるが用例が確認できない。甲骨文から”~と”を意味し、金文になると、二人称や”そして”の意に用いた。英語のandに当たるが、「A而B」は、AとBが分かちがたく一体となっている事を意味し、単なる時間の前後や類似を意味しない。詳細は論語語釈「而」を参照。
違(イ)
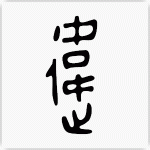

(金文)
論語の本章では”逃げる”。初出は西周早期の金文。字形は「辵」”あし”+「韋」”めぐる”で、原義は明らかでないが、おそらく”はるかにゆく”だったと思われる。論語の時代までに、”そむく”、”はるか”の意がある。詳細は論語語釈「違」を参照。
至(シ)
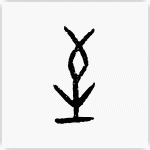

(甲骨文)
論語の本章では”(その国に)到着する”。甲骨文の字形は「矢」+「一」で、矢が届いた位置を示し、”いたる”が原義。春秋末期までに、時間的に”至る”、空間的に”至る”の意に用いた。詳細は論語語釈「至」を参照。
於(ヨ)


(金文)
論語の本章では”~に”。初出は西周早期の金文。ただし字体は「烏」。「ヨ」は”…において”の漢音(遣隋使・遣唐使が聞き帰った音)、呉音は「オ」。「オ」は”ああ”の漢音、呉音は「ウ」。現行字体の初出は春秋中期の金文。西周時代では”ああ”という感嘆詞、または”~において”の意に用いた。詳細は論語語釈「於」を参照。
他(タ)→也(ヤ)
唐石経・清家本は「他」と記し、現存最古の論語本である定州竹簡論語は「也」と記す。あるいは異体字の一種としての略字としてもよいが、時系列に従い「也」に校訂した。
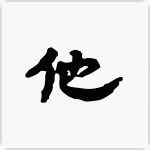

(前漢隷書)
論語の本章では”ほかの”。初出は前漢の隷書で、論語の時代に存在しない。同音の「它」に”ほか”の意があり、甲骨文から存在する。「它」は「他」の原字と見なしてよく、甲骨文では”へび”のほか、地名・人名に用いられ、金文では”あの”・”ほか”を意味した。また「也」とともに「匜」”水差し”を意味した。隷書よりのち、”かれ”の意を独立させてにんべんをつけたと思われる。詳細は論語語釈「他」を参照。


(金文)
定州竹簡論語では「也」と記し、「也邦」では”よその”。「崔子也」では”~である”。これらの語義は春秋時代では確認できない。初出は春秋時代の金文。原義は諸説あってはっきりしない。「や」と読み主語を強調する用法は、春秋中期から例があるが、「也」を句末で断定に用いるのは、戦国時代末期以降の用法で、論語の時代には存在しない。詳細は論語語釈「也」を参照。
邦(ホウ)
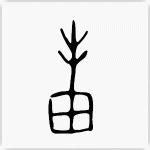

(甲骨文)
論語の本章では、建前上周王を奉じる”春秋諸侯国”。初出は甲骨文。甲骨文の字形は「田」+「丰」”樹木”で、農地の境目に木を植えた境界を示す。金文の形は「丰」+「囗」”城郭”+「人」で、境を明らかにした城郭都市国家のこと。詳細は論語語釈「邦」を参照。
現伝の論語が編まれたのは前後の漢帝国だが、「邦」の字は開祖の高祖劉邦のいみ名(本名)だったため、一切の使用がはばかられた。つまり事実上禁止され、このように歴代皇帝のいみ名を使わないのを避諱という。王朝交替が起こると通常はチャラになるが、定州竹簡論語では秦の始皇帝のいみ名、「政」も避諱されて「正」と記されている。
論語の本章で「邦」が使われているのは、本章の成立が後漢滅亡後か、あるいは前漢初期に「國」→「邦」へと改められたことを意味する。
則(ソク)


(甲骨文)
論語の本章では、”そこで”。初出は甲骨文。字形は「鼎」”三本脚の青銅器”と「人」の組み合わせで、大きな青銅器の銘文に人が恐れ入るさま。原義は”法律”。論語の時代=金文の時代までに、”法”・”則る”・”刻む”の意と、「すなわち」と読む接続詞の用法が見える。詳細は論語語釈「則」を参照。
猶(ユウ)
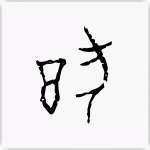

(甲骨文)
論語の本章では、”やはり~のような”。「なお~のごとし」と読む再読文字の一つ。この語義は春秋時代には無かった可能性がある。初出は甲骨文。字形は「酉」”酒壺”+「犬」”犠牲獣のいぬ”で、「猷」は異体字。おそらく原義は祭祀の一種だったと思われる。甲骨文では国名・人名に用い、春秋時代の金文では”はかりごとをする”の意に用いた。戦国の金文では、”まるで…のようだ”の意に用いた。詳細は論語語釈「猶」を参照。
吾(ゴ)


(甲骨文)
論語の本章では”わたしの”。初出は甲骨文。字形は「五」+「口」で、原義は『学研漢和大字典』によると「語の原字」というがはっきりしない。一人称代名詞に使うのは音を借りた仮借だとされる。詳細は論語語釈「吾」を参照。
古くは中国語にも格変化があり、一人称では「吾」(藤堂上古音ŋag)を主格と所有格に用い、「我」(同ŋar)を所有格と目的格に用いた。しかし論語で「我」と「吾」が区別されなくなっているのは、後世の創作が多数含まれているため。
大夫(タイフ)
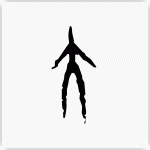

(甲骨文)
春秋時代の領主貴族のこと。諸侯国の閣僚級の仕事に就いた。邑(都市国家)の領主である「卿」(郷)の下位で、領地を持たない貴族である「士」の上位。詳細は春秋時代の身分秩序を参照。辞書的には論語語釈「大」・論語語釈「夫」を参照。
崔杼は斉の大夫であり、実権を握っていたがあくまでその地位は大夫に過ぎず、江戸期の日本で言うなら老中筆頭であり、大老ではなかった。楚の令尹が、明確に楚王の代理人で宰相だったのとは事情が異なる。従って論語の本章では、「令尹」は「おほおみ」と訓読したが、「大夫」は「おとど」と訓読して解釈を分けた。
一(イツ)


(甲骨文)
論語の本章では、”とある一つの”。「イチ」は呉音。初出は甲骨文。重文「壹」の初出は戦国文字。字形は横棒一本で、数字の”いち”を表した指事文字。詳細は論語語釈「一」を参照。
又(ユウ)


(甲骨文)
論語の本章では”それでもやはり”。初出は甲骨文。字形は右手の象形。甲骨文では祭祀名に用い、”みぎ”、”有る”を意味した。金文では”またさらに”・”補佐する”を意味した。詳細は論語語釈「又」を参照。
清家本では一度目の陳文子の発言にも「又」を付けるが、先行する定州本ではそうなっていない。従って校訂しなかった。
淸(セイ)


(金文)
論語の本章では”清潔”。新字体は「清」。「シン」は唐音(遣唐使廃止後から明治維新までに日本に伝わった音)。初出は春秋早期の金文。新字体は「清」で、中国・台湾・香港ではこちらのコードが正字体として扱われている。字形は「氵」+「青」で、青く澄み切った綺麗な水のさま。金文での語義は濁り酒が”澄んだ”、戦国の竹簡では酒が”すっきりとしてコクがある”、”静か”の意に用いた。詳細は論語語釈「清」を参照。
論語:付記
検証
おおざっぱな傾向として、論語の章の中でも長い文は、後世の偽造である可能性が高い。本章もその一つ。おそらく前半と後半は別の話だったのが、後漢儒あたりの手によって合成され、子張と孔子の問答へと作り替えられた。
論語の本章、前半の令尹子文の部分は、後漢の王充による『論衡』問孔25に再録された以外、先秦両漢の引用や再録がない。後半の崔杼と陳文子の話は、先秦両漢に全く引用や再録がない。定州竹簡論語は後半のみ残簡があるが、崔杼も陳文子も名が出ない。
両者が揃って論語の一部となるのは、後漢末から南北朝にかけて成立した古注『論語集解義疏』で、おそらく前半は後漢儒による創作、後半は別の話だった可能性がある。
解説
孔子の生前、貴族=君子の一般常識を「礼」と言い、「礼」を知らなければ「仁」=貴族らしくならなかった(論語における「礼」/論語における「仁」)。だから「知でなければ仁でない」と孔子が言った可能性はあるが、文字史から論語の本章が史実でないことは明らか。
従って「仁」も孟子が説いた「仁義」=情け深さと解するしかないのだが、そうなると本章の言う「知でなければ仁でない」での「知」とは、精神修養やいわゆるお勉強に限られてしまう。対して孔子は、あるがままを認めることを「知」だと言った(論語為政篇17)。
孟子は惻隠の情=かわいそうだと思う心を持たないのは人間ではなく、惻隠の情こそが仁のはじまりだと言っている(『孟子』公孫丑上)。だが孟子の生きた世は「仁が塞ぎ止められている」(滕文公下)ので、ケダモノをけしかけて人を殺すようになったと言った。
孟子が言う人でなしが人でありに立ち戻るためには、浩然の気=広々として自由な精神を養わねばならず、その養い方は言葉で伝えるのは難しいという(公孫丑上)。その難しい「気」なるものを体得するのが、孟子の言う「知」になるのだろう。
余談ながら合気道では「気」を体得しなければならないのだが、言葉で説明するのは難しいとされているのは、開祖の植芝盛平が『孟子』から取ってきたからかもしれない。訳者は僅かながら「気」を使えるが、それがどのようなものかはやはり言葉には出来ない。
ただ当たり前に「気を付ける」と言う言葉が指すところと、そう遠くはないように感じる。普段から「気を付ける」に「気を付け」て、体得出来るのではないかしらん。話を『論語』に戻そう。論語の本章、楚の子文が令尹(宰相)を辞めたいきさつを、『春秋左氏伝』はこう記す。
僖公二十三年…秋,楚成得臣帥師伐陳,討其貳於宋也,遂取焦夷,城頓而還,子文以為之功使為令尹,叔伯曰,子若國何,對曰,吾以靖國也,夫有大功而無貴仕,其人能靖者與,有幾。
僖公二十三年(BC637)…秋、楚の成得臣(子玉)が軍を率いて陳を撃ち、敵軍を宋の地で撃ち、ついに焦夷のまちを占領し、一部占領軍を残して凱旋した。子文は合戦の功績で成得臣に令尹の地位を譲った。
叔伯「あなたは国政をどうするつもりですか?」子文「みなを落ち着けるためです。」
そもそも、大きな功績があるのに高位に即かず、その人がよく落ち着いているなら、完璧な人格に近いと言える。(『春秋左氏伝』僖公二十三年2)
これ以前、子文が令尹に就任した話は『春秋左氏伝』に無い。だからこの文を就任記事として読めなくはないのだが、そうすると後世の評「大きな功績があるのに高位に即かず」と繋がらない。
崔杼については中国の史官にまつわる有名な伝説がある。
大史書曰,崔杼弒其君,崔子殺之,其弟嗣書,而死者二人,其弟又書,乃舍之,南史氏聞大史盡死,執簡以往,聞既書矣,乃還。
斉の史官の長官が、「崔杼がその主君を殺した」と記録した。崔杼は長官を殺した。長官の弟が同様に書いて殺され、その弟がまた書いて殺され、その弟がまた書いた。そこでやっと崔杼は許した。南史氏(南方但当の派遣記録官?)は史官がことごとく殺されたと聞いて、筆記用の簡を持って斉の都に上ろうとした。途上ですでに崔杼の一件が記録されたと聞いて、そこでやっと引き返した。(『春秋左氏伝』襄公二十五年2)
「こうした勇敢な史官のおかげで、中国は世界に冠たる歴史書を残せた」と誇るのが通例だが、論語ですらこの通りうそデタラメに満ちているのに、史書に事実ばかりが書いてあると信じるのは、妙なものを拝めと命じられる程度には不可能だ。
そもそも「弒」の字が無い春秋時代に、書きて曰く「崔杼弒其君」とはこれいかに?
殺された荘公はそもそも崔杼に擁立して貰ったのに、崔杼夫人と密通していた事が上掲『史記』に記されているが、春秋の殿様にはこういう、殺されても仕方がないようなバカ殿が出る。それに「荘公」という目出度いおくり名が付いたのは、ずいぶん如何わしいと言える。
古注には例によって、前漢の人物とされる孔安国が注を付けているが、この人物は高祖劉邦の名を避諱(はばかってつかわない)しないなど、実在そのものが疑わしい。
古注『論語集解義疏』
註孔安國曰令尹子文楚大夫姓鬬名㝅字於菟…註孔安國曰但聞其忠事未知其仁也…註孔安國曰皆齊大夫也崔杼作亂陳文子惡之捐其四十匹馬違而去之也…註孔安國曰文子避惡逆去無道求有道當春秋時臣陵其君皆如崔杼無有可止者也
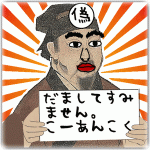
注釈。孔安国「令尹子文とは楚の大夫で姓は鬬、名は㝅、あざ名は於菟である。…孔子は子文が忠義者だったと聞いていただけで、仁者かどうかは知らなかったのである。…いずれも斉の大夫である。崔杼は反乱を起こし、陳文子はこれを嫌って四十頭の馬を捨てて崔杼から遠ざかり、国を去ったのである。…陳文子は主君殺しの大罪を避け無道から離れ原則のある社会を求めた。春秋時代、臣下は主君を迫害し、誰もが崔杼のようだった。それを止めようとする者もいなかった。」
孔安国は400年近く昔の話を、見てきたようなウソをついているだけである。
余話
春秋時代人の誠実
春秋時代にも忠臣はいたし、世の乱れを憂いできる限りの手を尽くした貴族も少なくなかった。「忠」という字が漢語に現れるのは戦国時代だが、「忠」という絵空事をでっち上げて領民にすり込み、先の見えないいくさに引っ張った戦国や帝政の時代よりも、よほどましな人間像を見て取れる。
斉の襄公といえば、妹と姦通するため夫だった魯の桓公を彭生という男に殺させ、さらに彭生をも殺してうやむやにした暴君だったが、そんな襄公にも忠臣がいた。ある時襄公が狩りに出ると、彭生の亡霊が出て襄公は車から落ち、怪我をした上に靴をなくしてしまった。
反,誅屨於徒人費,弗得,鞭之見血,走出,遇賊于門,劫而束之,費曰,我奚御哉,袒而示之背,信之,費請先入,伏公而出鬥,死于門中。

襄公は公宮に帰ると、召使いの費を「靴をどこにやった!」と責め、鞭で背中を打って血が出るほどになった。費が逃げ出して宮門まで来ると、丁度襄公の暴政に怒った反乱軍が押し寄せてくる所だった。反乱軍は口止めにと費を縛り付けた。
費「なんで手向かいしましょう。ご覧下さい、私の背中を。」反乱軍が気の毒がって縄をほどくと、「案内つかまつります。用心しながら後にお続きあれ」と言い、走って反乱軍を引き離すと、襄公に急を告げて隠れさせ、手に武器を取って反乱軍に立ち向かった。そして門を守って討ち死にした。(『春秋左氏伝』荘公八年(BC686)2)
また孔子と同時代の魯の貴族、公山弗擾と言えば、論語陽貨篇5で反乱を起こした悪党とされているが、確かに国を離れたものの、発言からは良識ある人物だったと分かる。
それを「春秋時代、臣下は主君を迫害し…」とは、聞いて呆れる漢儒のデタラメだ。






コメント