論語:原文・書き下し
原文(唐開成石経)
顔淵死子哭之慟從者曰子慟矣曰有慟乎非夫人之爲慟而誰爲
- 「淵」字:最後の一画〔丨〕を欠く。唐高祖李淵の避諱。
校訂
東洋文庫蔵清家本
顔淵死子哭之慟/從者曰子慟矣子曰有慟乎/非夫人之爲慟而誰爲慟
- 「淵」字:〔氵丿丰丰丨〕。
後漢熹平石経
(なし)
定州竹簡論語
[顏淵死,子哭之動a。從者曰:「子動矣!」曰b]:269……
- 動、今本作”慟”。動借為慟。
- 皇本、”曰”上有”子”字。
標点文
顏淵死、子哭之動。從者曰、「子動矣。」曰、「有慟乎。非夫人之爲慟而誰爲慟。」
復元白文(論語時代での表記)














 慟
慟




 慟
慟

 慟
慟
※論語の本章は、「慟」の字が論語の時代に存在しない。「動」「乎」「夫」「誰」の用法に疑問がある。
書き下し
顏淵死ぬ。子之を哭きて動く。從者曰く、子動け矣と。曰く、慟く有らむ乎。夫の人之爲に慟くに非ずし而、誰が爲に慟かむ。
論語:現代日本語訳
逐語訳


顔淵が死んだ。先生はそれを泣き、わなわなと震えた。そばの者が言った。「先生は震えています。」先生がが言った。「震えるようなことをしたか。この人のために震えないなら、誰のために震えるのか。」
意訳
顔回が死んだ。先生は泣き、悲しみのあまりわなわなと震えた。
弟子「先生。礼法にそむきます。」
孔子「顔回が死んだんだぞ。礼法など知ったことか。」
従来訳
顔渕が死んだ。先師はその霊前で声をあげて泣かれ、ほとんど取りみだされたほどの悲しみようであった。お供の門人が、あとで先師にいった。――
「先生も今日はお取りみだしのようでしたね。」
先師がこたえられた。――
「そうか。取りみだしていたかね。だが、あの人のためになげかないで、誰のためになげこう。」下村湖人『現代訳論語』
現代中国での解釈例
顏淵死,孔子痛哭。身邊的人說:「您不要過於悲痛了!」孔子說:「過於悲痛了嗎?不為他悲痛為誰悲痛?」
顔淵が死んで孔子がひどく泣いた。近くの者が言った。「先生あまりお嘆きになりますな。」孔子が言った。「悲しみすぎか? 彼のために悲しまないで、誰のために悲しむのだ?」
論語:語釈
顏淵(ガンエン)

孔子の弟子、顏回子淵。あざ名で呼んでおり敬称。詳細は論語の人物:顔回子淵を参照。

『孔子家語』などでも顔回を、わざわざ「顔氏の子」と呼ぶことがある。後世の儒者から評判がよく、孔子に次ぐ尊敬を向けられているが、何をしたのか記録がはっきりしない。おそらく記録に出来ない、孔子一門の政治的謀略を担ったと思われる。孔子の母親は顔徴在といい、子路の義兄は顔濁鄒(ガンダクスウ)という。顔濁鄒は魯の隣国衛の人で、孔子は放浪中に顔濁鄒を頼っている。しかも一説には、顔濁鄒は当時有力な任侠道の親分だった(『呂氏春秋』)。詳細は孔子の生涯(1)を参照。


「顏」(金文)
「顏」の新字体は「顔」だが、定州竹簡論語も唐石経も清家本も新字体と同じく「顔」と記している。ただし文字史からは「顏」を正字とするのに理がある。初出は西周中期の金文。字形は「文」”ひと”+「厂」”最前線”+「弓」+「目」で、最前線で弓の達者とされた者の姿。「漢語多功能字庫」によると、金文では氏族名に用い、戦国の竹簡では”表情”の意に用いた。詳細は論語語釈「顔」を参照。


「淵」(甲骨文)
「淵」の初出は甲骨文。「渕」は異体字。字形は深い水たまりのさま。甲骨文では地名に、また”底の深い沼”を意味し、金文では同義に(沈子它簋・西周早期)に用いた。詳細は論語語釈「淵」を参照。
「上海博物館蔵戦国楚竹簡」では「淵」を「囦」と記す。上掲「淵」の甲骨文が原字とされる。
死(シ)
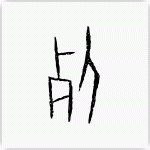

(甲骨文)
論語の本章では”死去した”。字形は「𣦵」”祭壇上の祈祷文”+「人」で、人の死を弔うさま。原義は”死”。甲骨文では、原義に用いられ、金文では加えて、”消える”・”月齢の名”、”つかさどる”の意に用いられた。戦国の竹簡では、”死体”の用例がある。詳細は論語語釈「死」を参照。
子(シ)


(甲骨文)
論語の本章では”(孔子)先生。初出は甲骨文。論語ではほとんどの章で孔子を指す。まれに、孔子と同格の貴族を指す場合もある。また当時の貴族や知識人への敬称でもあり、孔子の弟子に「子○」との例が多数ある。なお逆順の「○子」という敬称は、上級貴族や孔子のような学派の開祖級に付けられる敬称。「南子」もその一例だが、”女子”を意味する言葉ではない。字形は赤ん坊の象形で、もとは殷王室の王子を意味した。詳細は論語語釈「子」を参照。
哭(コク)


(甲骨文)
論語の本章では”葬礼で泣く”。初出は甲骨文。字形は中央に犠牲獣の「犬」+「𠙵」”くち”二つで、犬を供え物にして故人の冥福を祈ること。同形の「器」より「𠙵」の数が半分であることから、より小規模な祭祀を言う。類義語の「喪」は現行字体は「𠙵」が二つだが、甲骨文では一つ~四つと安定しない。甲骨文では地名、”泣く”に用いる。「在线汉语字典」「国学大師」に金文を載せるが出所が不明。それ以降は戦国時代の竹簡に”なく”の用例がある。詳細は論語語釈「哭」を参照。
現伝儒教では、大声を上げて泣き叫ぶのを「哭礼」といって作法とするが、春秋時代にその作法があったかどうかは定かではない。
之(シ)


(甲骨文)
論語の本章、「哭之」では”これ”。「夫人之」では”~の”。初出は甲骨文。字形は”足”+「一」”地面”で、あしを止めたところ。原義はつま先でつ突くような、”まさにこれ”。殷代末期から”ゆく”の語義を持った可能性があり、春秋末期までに”~の”の語義を獲得した。詳細は論語語釈「之」を参照。
慟*(トウ)→動(トウ)


(篆書)
論語の本章では”体をわなわなと震わせてなげく”。論語では本章のみに登場。初出は後漢の説文解字。論語の時代に存在しない。論語時代の置換候補もない。字形は〔忄〕”こころ”+「動」。心身が大きく揺れ動いてなげくさま。同音に「同」とそれを部品とする漢字群、「童」とそれを部品とする漢字群、「動」など。「ドウ」は慣用音。呉音は「ズウ」。文献時代の初出は論語の本章。戦国時代の諸子百家には見えず、前漢中期の『史記』弟子伝にみえる以降は、後漢初期まで時代が下る。つまり『史記』は後世になっていじられた可能性がある。詳細は論語語釈「慟」を参照。
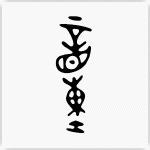

(金文)
定州竹簡論語は「動」と記す。初出は西周末期の金文。ただし字形は「童」。その後は楚系戦国文字まで見られず、現行字体の初出は秦の嶧山碑。その字は「うごかす」とも「どよもす」とも訓める。初出の字形は〔䇂〕(漢音ケン)”刃物”+「目」+「東」”ふくろ”+「土」で、「童」と釈文されている。それが”動く”の語義を獲得したいきさつは不明。「ドウ」は慣用音。呉音は「ズウ」。西周末期の金文に、「動」”おののかせる”と解釈する例がある。春秋末期までの用例はこの一件のみ。原義はおそらく”力尽くでおののかせる”。詳細は論語語釈「動」を参照。
定州竹簡論語の欠損部分でも、「慟」が「動」と記されていたと考えてもいいが、物証がないので、今は次いで古い清家本に従う。清家本の年代は唐石経より新しいが、より古い古注系の文字列を伝えており、唐石経訂正しうる。
| 定州竹簡論語 | 子哭之動從者曰子動矣曰 | (欠損) |
| 清家本 | 子哭之慟從者曰子慟矣曰 | 有慟乎非夫人之爲慟而誰爲慟 |
從者(ショウシャ)
論語の本章では”そば近く仕える者”。


(甲骨文)
「從」の初出は甲骨文。新字体は「従」。「ジュウ」は呉音。字形は「彳」”みち”+「从」”大勢の人”で、人が通るべき筋道。原義は筋道に従うこと。甲骨文での解釈は不詳だが、金文では”従ってゆく”、「縦」と記して”好きなようにさせる”の用例があるが、”聞き従う”は戦国時代の「中山王鼎」まで時代が下る。詳細は論語語釈「従」を参照。


(金文)
「者」の旧字体は〔耂〕と〔日〕の間に〔丶〕一画を伴う。新字体は「者」。ただし唐石経・清家本ともに新字体と同じく「者」と記す。現存最古の論語本である定州竹簡論語も「者」と釈文(これこれの字であると断定すること)している。初出は殷代末期の金文。金文の字形は「木」”植物”+「水」+「口」で、”この植物に水をやれ”と言うことだろうか。原義は不明。初出では称号に用いている。春秋時代までに「諸」と同様”さまざまな”、”~する者”・”~は”の意に用いた。漢文では人に限らず事物にも用いる。詳細は論語語釈「者」を参照。
曰(エツ)


(甲骨文)
論語で最も多用される、”言う”を意味する言葉。初出は甲骨文。原義は「𠙵」=「口」から声が出て来るさま。詳細は論語語釈「曰」を参照。
矣(イ)


(金文)
論語の本章では、”…した”。驚くべき事を、確かになさいました、の意。初出は殷代末期の金文。字形は「𠙵」”人の頭”+「大」”人の歩く姿”。背を向けて立ち去ってゆく人の姿。原義はおそらく”…し終えた”。ここから完了・断定を意味しうる。詳細は論語語釈「矣」を参照。
有(ユウ)


(甲骨文)
論語の本章では”…した”。初出は甲骨文。ただし字形は「月」を欠く「㞢」または「又」。字形はいずれも”手”の象形。原義は両腕で抱え持つこと。詳細は論語語釈「有」を参照。
乎(コ)


(甲骨文)
論語の本章では、「か」と読んで疑問の意。この語義は春秋時代では確認できない。初出は甲骨文。字形は持ち手の柄を取り付けた呼び鐘を、上向きに持って振り鳴らし、家臣を呼ぶさまで、原義は”呼ぶ”こと。甲骨文では”命じる”・”呼ぶ”を意味し、金文も同様で、「呼」の原字となった。句末の助辞として用いられたのは、戦国時代以降になるという。詳細は論語語釈「乎」を参照。
非(ヒ)


(甲骨文)
論語の本章では”~でない”。初出は甲骨文。甲骨文の字形は互いに背を向けた二人の「人」で、原義は”…でない”。「人」の上に「一」が書き足されているのは、「北」との混同を避けるためと思われる。甲骨文では否定辞に、金文では”過失”、春秋の玉石文では「彼」”あの”、戦国時代の金文では”非難する”、戦国の竹簡では否定辞に用いられた。詳細は論語語釈「非」を参照。
夫(フ)


(甲骨文)
論語の本章では「かの」と読んで”あの”という指示詞。この語義は春秋時代では確認できない。初出は甲骨文。論語では「夫子」として多出。「夫」に指示詞の用例が春秋時代以前に無いことから、”あの人”ではなく”父の如き人”の意で、多くは孔子を意味する。「フウ」は慣用音。字形はかんざしを挿した成人男性の姿で、原義は”成人男性”。「大夫」は領主を意味し、「夫人」は君主の夫人を意味する。固有名詞を除き”成人男性”以外の語義を獲得したのは西周末期の金文からで、「敷」”あまねく”・”連ねる”と読める文字列がある。以上以外の語義は、春秋時代以前には確認できない。詳細は論語語釈「夫」を参照。
人(ジン)


(甲骨文)
論語の本章では”人”。初出は甲骨文。原義は人の横姿。「ニン」は呉音。甲骨文・金文では、人一般を意味するほかに、”奴隷”を意味しうる。対して「大」「夫」などの人間の正面形には、下級の意味を含む用例は見られない。詳細は論語語釈「人」を参照。
爲(イ)


(甲骨文)
論語の本章では”する”。新字体は「為」。字形は象を調教するさま。甲骨文の段階で、”ある”や人名を、金文の段階で”作る”・”する”・”…になる”を意味した。詳細は論語語釈「為」を参照。
而(ジ)


(甲骨文)
論語の本章では”それなのに”。初出は甲骨文。原義は”あごひげ”とされるが用例が確認できない。甲骨文から”~と”を意味し、金文になると、二人称や”そして”の意に用いた。英語のandに当たるが、「A而B」は、AとBが分かちがたく一体となっている事を意味し、単なる時間の前後や類似を意味しない。詳細は論語語釈「而」を参照。
誰(スイ)


「誰」(金文)
論語の本章では”だれ”。この語義は春秋時代では確認できない。初出は西周中期の金文。字形は字形は「䇂」”小刀”+「𠙵」”くち”+「隹」だが由来と意味は不詳。春秋までの金文では”あお馬”の意で用い、戦国の金文では「隹」の字形で”だれ”を意味した。詳細は論語語釈「誰」を参照。
論語:付記
検証
論語の本章の史実性については、機械的に偽作と言えるが心情的には史実と考えて仕舞うかもしれない。上記「慟」の語釈に記した通り、定州竹簡論語の欠損部分も「動」と記されていたなら、「用法に疑問がある」が一応春秋時代に遡れる文字列になるからだ。だが春秋以前「童」と記された「動」は”おののかせる”の一例のみで、”なげく”・”わななく”ではない。
加えて孔子が弟子に過ぎない顔淵を「夫人」”あのお人”と尊称していることから、顔淵神格化のためにでっち上げられた可能性が極めて強い。論語で孔子が「夫人」と呼んだのは、他に閔子騫(論語先進篇13)と子羔の親(論語先進篇24)のみである。教師が弟子の親を尊称するのは当然で(論語先進篇7)、閔子騫は他の記録から見てとうてい孔子の弟子とは言えず、むしろ先達と考えるべき人物。だが顔淵は明らかに孔子の弟子で、それは儒者や漢学教授でも否定しないだろう。
にも関わらず「夫人」と尊称したことを、儒者や漢学教授は「孔子にとって畏敬すべき弟子だったのだ」と言い募った。それならば他の章で、「回」と呼び捨てにしているのをどう説明するのか、という問題が生じる。論語にすでに出てきた、それらの章を検討しよう。
- 論語為政篇9「吾回と言ること終日」→×後世の捏造。
- 論語公冶長篇8「なんじと回とは」→×後世の捏造。
- 論語雍也篇3「弟子だれか学を」→×後世の捏造。
- 論語雍也篇7「回やその心三月」→△後世の捏造の疑いあり。
- 論語雍也篇11「賢なる哉回や」→×後世の捏造。
- 論語子罕篇20「これに語りて」→×後世の捏造。
- 論語先進篇3「回や我を助くる者に」→△後世の捏造の疑いあり。
- 論語先進篇6「季康子問う、弟子」→×後世の捏造。
つまり論語に出て来る顔淵ばなしはうさんくさい話ばっかりであり、顔淵神格化キャンペーンを始めた前漢の董仲舒の思うつぼに、儒者も漢学教授もまんまとはまっていることになる。顔淵神格化キャンペーンの詳細は論語先進篇3解説を参照。
また論語の本章は、ほぼ同文を定州竹簡論語よりやや先行する『史記』弟子伝が記したほかは、後漢初期・王充『論衡』まで時代が下る。王充は生まれる百年以上も昔に滅びたと自分で言い出した『古論語』『魯論語』『斉論語』を、見てきたようにペラペラ語って後世を惑わしたけしからん男だが、定州竹簡論語よりは後の人間だから記すのは当然だ。
いずれにせよ、現伝論語や古注が「慟」と記している後半が「動」だった物証が無い以上、人為で勝手に「動」だったと言うのは科学的とは言いかねる。似ている文字列があったら何でも同じに修復する間抜けは、論語先進篇6余話「正直爺さん」を参照。鉄砲担いで「花咲かじいさん」の歌を高歌放吟しながら天安門前広場を闊歩するのを、間抜けと思わないような趣味人と、訳者の趣味はぜんぜん合わない。
だから論語の本章は漢儒、おそらく董仲舒による偽作である。
解説
論語の本章、新古の注は次の通り。
古注『論語集解義疏』
顔淵死子哭之慟註馬融曰慟哀過也從者曰子慟矣子曰有慟乎註孔安國曰不自知己之悲哀過也非夫人之為慟而誰為慟
本文「顔淵死子哭之慟」。
注釈。馬融「慟は哀しみのはげしいものである。」
本文「從者曰子慟矣子曰有慟乎」。
注釈。孔安国「自分でも気付かないうちに悲しみが度を超したのである。」
本文「非夫人之為慟而誰為慟」。
新注『論語集注』
顏淵死,子哭之慟。從者曰:「子慟矣。」從,去聲。慟,哀過也。曰:「有慟乎?哀傷之至,不自知也。非夫人之為慟而誰為!」夫,音扶。為,去聲。夫人,謂顏淵。言其死可惜,哭之宜慟,非他人之比也。胡氏曰:「痛惜之至,施當其可,皆情性之正也。」
本文「顏淵死,子哭之慟。從者曰:子慟矣。」
從は尻下がりに読む。慟は哀しみのはげしいものである。
本文「曰:有慟乎?哀傷之至,不自知也。非夫人之為慟而誰為!」
夫の音は扶である。為は尻下がりに読む。夫人とは顔淵のことである。ここで言ったのは次の通り。顔淵の死は惜しんで当然で、嘆きの礼をするにわなないたのも適切である。他人の死とは比べものにならないからである。
胡寅「失った衝撃の大きさがここまでになると、このように振る舞うのは正当で礼法にかなっている。人間本来の心情、つまり人間の本質と一致しているからだ。」
宋儒の言う「情性」の何たるかを説くのは、彼らのオカルトに付き合うことになるから馬鹿馬鹿しいのでやらない。あえていえば、宋儒の説は何を言っているか誰にも分からず、当人も分かっていない。詳細は論語雍也篇3余話「宋儒のオカルトと高慢ちき」を参照。
余話
ワラワン殿下

「燃料が!」「司厨長が揚げ油を持ってるぞ」
©ロタール・ギュンター・ブーフハイム@『U・ボート』
現代日本の文系大学入試では、たいてい法学部が一番難しい。これは明治時代に帝大法科卒を無試験で官僚に採用し、企業も法科(のちに経済科が独立するとそれも含めた)とそれ以外、帝大と私大を初任給から露骨に差別した(中山茂『帝国大学の誕生』)のを引きずっている。
ゆえに今の法学士が人界の問題をより解決できるわけでなく、思考がより科学的でありもしない。司法試験の予備試験には形式論理学が課されるが、その程度は地方自治体の大卒公務員採用試験とさほど変わらない。従って現職の判事も、科学的に判決を出しているわけではない。
憲法の政教分離原則は…わが国の社会的・文化的諸条件に照らし…限度を超えるもの…を許さないとするものである。(最高裁判決・昭和46(行ツ)69)
つまり最高裁判所も常に世論をチラ見しながら判決を出しているわけで、法令の条文から方程式のように、結果が一意に定まるわけではないわけだ。その当否は訳者ごときの判断を超えるが、漢籍の判読に当たって、世論をチラ見しながら適当なことを言う連中は信用できない。
漢文の基本は古今、日中共に論語にあるが、その解釈がチラ見しかしない世間師稼業、でしかめしを食えない儒者や漢学教授によって、二千年以上にわたって実にデタラメに行われてきたわけだが、今なおそれを引きずっている事に限れば、めでたいと言わねばならない。
おめでたい世間師にとってめでたいだけでなく、論語の読者や非読者にとってもそうである。なぜなら古典の解釈がデタラメで良いと認めない社会は、宗教裁判が流行る社会に他ならず、たとえば残忍この上ないローマ坊主がやって来て、人を火炙って回る社会だからだ。
今でもそういう残忍な社会は近場に転がっている。隣国ロシアもスターリン時代は、マルクス・レーニンの著作をどう解釈したかで、シベリア流刑にも遭ったし裁判無しの銃殺にも遭った。今でも政府に都合の悪い人が、いつの間にか居なくなっていたりもする。
そもそも漢文の本場である中国が、そういう野蛮な社会であり続けている。ゆえに現代中国の漢学教授も中共にゴマをすった解釈しか書けず(論語語釈「衆」)、論語も漢文もゆがんだままだ。不思議にも日本の漢学教授も中共の回し者が多く、その講釈は鼻で笑える程度には低い。
ゆえに現代人はのんびりと好き勝手に論語を読んで良いわけだが、なにがしか人様に言えるだけのことを論語について言おうとするなら、好き勝手というわけにはいかない。だが漢文の融通無碍は、方程式的解釈を極度に難しくもしている(漢文が読めるようになる方法2022)。
どうすればよいのか。それは我が国の法運用がそうであるように、英米法がそうであるように、漢籍に対する良識(good sense)を養うことだ。おおかたは上掲リンク先に書いたが、大学入試程度の世界史日本史古文漢文はもちろん、かたよりの無い漢籍読書体験が要る。
読むべき本に論語が入るのは言うまでも無い。雑多なデタラメ本でもいいからまず読み通すことだ。その次には何を読もうか? 訳者の経験から言うなら、抄訳でいいからまず『史記』、次いで『水滸伝』。そして抄訳は出ていないが『笑府』を読むことを勧める。
全訳でも笑話集だから読みやすいはずだ。『笑府』がなぜ漢文や中国理解に不可欠なのかは、論語子張篇1余話「笑府読まずの中国知らず」を参照。『水滸伝』が不可欠なのも『笑府』と同様で、北京放送のような官製中国人の話ばかり読んでも、生身の中国人は分からない。
何より官製道徳には笑いが無い。笑いの無い社会は人間の社会ではない。
古今來莫非話也話莫非笑也兩儀之混沌開闢列聖之揖譲征誅見者其誰耶夫亦話之而已
古来、笑い飛ばせない説教など無い。天地開闢の神話から、聖賢の礼儀作法、聖王の政治軍事まで、ただ語るだけで終わり、笑って仕舞えないお堅い話など無かったのだ。(『笑府』序)
『水滸伝』と『笑府』を読み終えてから論語を読み直すと、まるで違って読めるはずだ。つまり世間師のデタラメに振り回されず、自分で判読できる力が付いたわけ。それでやっと、『老子』など哲学書、『唐詩選』など詩文、演義を含めた『三国志』など史書が分かる。
なぜ『三国演義』でなく『水滸伝』なのかにはわけがある。『三国演義』はしょせん君子の視点でしかなく、九分九厘の中国人がずっとそうであり続けている、民百姓の物語ではない。自分は君子などではないのだと思い知らない限り、漢籍をずっと誤読し続けることになる。
こういう人間界の、当たり前の常識に通じないまま、哲学書やら易やらを読めば、まず間違いなく頭がやられて気が狂う。そういう人外に堕ちた生き物を、訳者は何人もこの目で見てきた。かかる人外になれば社会的栄達が得られるわけではない。ただの𠮷外になるだけだ。
- 論語公冶長篇27余話「吉川にあらずんば人にあらず」
漢学を志望する若い学徒の諸君には、特に気を付けて頂きたい。現在威張っている連中の多くがかかる生物であっても、論理は威張る→𠮷外であり、𠮷外→威張れるではない。人生を棒に振ってはならない。棒術の有段者でもある訳者がそういうのだ(笑)*。精神健康に生きよう。
こういう人界の書を読みながら訓読を訓練すれば、辞書類さえ揃えれば、自力で漢文を原書で読めるようになる(漢和辞典ソフトウェア比較)。句読点の無い文字列でも恐れるに足りない。閲覧者諸賢の多くには訓読の必要は無かろうが、中国を知るにはやはり四冊を読むといい。
その前に、諸賢がなぜ漢籍を読むのかを問い直すといい。世間師になるためなら、こんな手間などせず有力者に気に入られるよう努力するといい。ただ暇つぶしのためなら、そこらに転がっている訳本にお金を出せばいい。中国を知る必要があるなら、上記のようにするといい。
全ては諸賢の、お気に召すままである。
*余談ながら『水滸伝』第八回「柴進門招天下客 林沖棒打洪教頭」で、豹子頭林中が洪教頭を打ち据えたときのお互いの棒術型、「把火焼天」と「𫝼草尋蛇」は、芝居の台本だけに実態が分からない。だが漢和辞典が引け少々棒の手を知っていれば想像は付く。
洪教頭の「把火焼天」は「火を把りて天を焼く」の意で、おそらくたいまつを持つような、いわゆる八相の構え。対する林中は「草を𫝼いて蛇を尋ぬ」の意で、いわゆる下段の構え。八相は剣道型でも「万能」とまで言われるが、どうしても下段からの攻めには弱い。
日本の棒術で代表的な神道夢想流の開祖・夢想権之助は、下段の構えで宮本武蔵を破ったとされる。「下から上へと突き上げよ」というのは、棒術の心得として今なお良く言われる。徒手の合気道にもこの理があり、大男につかまれても下からくるりと抜ければ投げるを得る。





コメント