論語:原文・書き下し
原文(唐開成石経)
顔淵死門人欲厚葬之子曰不可門人厚葬之子曰回也視予猶父也予不得視猶子也非我也夫二三子也
- 「淵」字:最後の一画〔丨〕を欠く。唐高祖李淵の避諱。
- 「葬」字:〔艹〕→〔十十〕。
校訂
東洋文庫蔵清家本
顔淵死門人欲厚葬之子曰不可/門人厚葬之子曰回也視予猶父也予不得視猶子也非我也夫二三子也
- 「淵」字:〔氵丿丰丰丨〕。
- 「葬」字:〔艹〕→〔十十〕。
後漢熹平石経
…我…
定州竹簡論語
[顏淵死,門]人欲厚葬之。子曰:「不可。」270……[回]也視予猶父也,予不[得視□子也。非我也,夫二三]271……
標点文
顏淵死、門人欲厚葬之。子曰、「不可。」門人厚葬之。子曰、「回也視予猶父也、予不得視猶子也、非我也、夫二三子也。」
復元白文(論語時代での表記)










































※欲→谷・葬→(甲骨文)。論語の本章は、「門」「也」「猶」「夫」の用法に疑問がある。
書き下し
顏淵死ぬ。門人厚く之を葬らむと欲む。子曰く、可しから不るなり。門人厚く之を葬る。子曰く、回也予を視るに猶ほ父のごとくなりし也、予猶ほ子のごとく視るを得ざりかる也。我に非ざる也、夫の二三子也。
論語:現代日本語訳
逐語訳


顔淵が死んだ。門人はこれを手厚く葬ろうとした。先生が言った。「いけない。」しかし門人は手厚く葬った。先生が言った。「顔回は私を父親のように見たものだよ。私は子のように見ることが出来なかったのだよ。私がしたのではないのだよ。あの門人達がしたのだよ。」
意訳
顔淵が死んだ。
弟子「立派なお葬式を出しましょう」
孔子「いかん。礼法にそむく。」
しかし弟子は盛大な葬儀を挙げた。
孔子「顔回は私を父親のように慕ってくれた。しかし私は実の子のように扱ってやれなかった。礼法破りをさせてしまったのだからな。だが私のせいではない、弟子たちが勝手にやったことだ。」
従来訳
顔渕が死んだ。門人たちが彼のために葬儀を盛大にしようともくろんだ。先師はそれを「いけない」といって、とめられたが、門人たちはかまわず盛大な葬儀をやってしまった。すると先師はいわれた。――
「囘は私を父のように思っていてくれた。私も彼を自分の子供同様に葬ってやりたかったが、それが出来なかった。それは私のせいではない。みんなおまえたちのせいなのだ。」下村湖人『現代訳論語』
現代中国での解釈例
顏淵死,學生們要厚葬他。孔子說:「不可。」學生們還是厚葬了他。孔子說:「顏回把我當作父親,我卻沒把他當作兒子。不是我要這樣,是學生們背著我乾的。」
顔淵が死んで弟子たちが厚く弔おうとした。孔子が言った。「いかん。」弟子たちはやはり厚く弔った。孔子が言った。「顔回は私を父のように見てくれた。しかし私は顔回を子のように見てやれなかった。私がそのようにせよと望んだのではない。弟子たちが私にそむいて勝手にやったのだ。」
論語:語釈
顏淵(ガンエン)

孔子の弟子、顏回子淵。あざ名で呼んでおり敬称。詳細は論語の人物:顔回子淵を参照。

『孔子家語』などでも顔回を、わざわざ「顔氏の子」と呼ぶことがある。後世の儒者から評判がよく、孔子に次ぐ尊敬を向けられているが、何をしたのか記録がはっきりしない。おそらく記録に出来ない、孔子一門の政治的謀略を担ったと思われる。孔子の母親は顔徴在といい、子路の義兄は顔濁鄒(ガンダクスウ)という。顔濁鄒は魯の隣国衛の人で、孔子は放浪中に顔濁鄒を頼っている。しかも一説には、顔濁鄒は当時有力な任侠道の親分だった(『呂氏春秋』)。詳細は孔子の生涯(1)を参照。


「顏」(金文)
「顏」の新字体は「顔」だが、定州竹簡論語も唐石経も清家本も新字体と同じく「顔」と記している。ただし文字史からは「顏」を正字とするのに理がある。初出は西周中期の金文。字形は「文」”ひと”+「厂」”最前線”+「弓」+「目」で、最前線で弓の達者とされた者の姿。「漢語多功能字庫」によると、金文では氏族名に用い、戦国の竹簡では”表情”の意に用いた。詳細は論語語釈「顔」を参照。


「淵」(甲骨文)
「淵」の初出は甲骨文。「渕」は異体字。字形は深い水たまりのさま。甲骨文では地名に、また”底の深い沼”を意味し、金文では同義に(沈子它簋・西周早期)に用いた。詳細は論語語釈「淵」を参照。
「上海博物館蔵戦国楚竹簡」では「淵」を「囦」と記す。上掲「淵」の甲骨文が原字とされる。
死(シ)
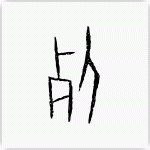

(甲骨文)
論語の本章では”死去した”。字形は「𣦵」”祭壇上の祈祷文”+「人」で、人の死を弔うさま。原義は”死”。甲骨文では、原義に用いられ、金文では加えて、”消える”・”月齢の名”、”つかさどる”の意に用いられた。戦国の竹簡では、”死体”の用例がある。詳細は論語語釈「死」を参照。
門人(ボンジン)
論語の本章では”弟子”。「モンジン」は呉音+漢音の変則読み。


(甲骨文)
「門」の初出は甲骨文。”一門の”の語義は春秋時代では確認できない。「モン」は呉音。字形はもんを描いた象形。甲骨文では原義で、金文では加えて”門を破る”(庚壺・春秋末期)の意に、戦国の竹簡では地名に用いた。詳細は論語語釈「門」を参照。


(甲骨文)
「人」の初出は甲骨文。原義は人の横姿。「ニン」は呉音。甲骨文・金文では、人一般を意味するほかに、”奴隷”を意味しうる。対して「大」「夫」などの人間の正面形には、下級の意味を含む用例は見られない。詳細は論語語釈「人」を参照。
欲(ヨク)


(楚系戦国文字)
論語の本章では”求める”。初出は楚系戦国文字。新字体は「欲」。同音は存在しない。字形は「谷」+「欠」”口を膨らませた人”。部品で近音の「谷」に”求める”の語義がある。詳細は論語語釈「欲」を参照。
厚(コウ)


(甲骨文)
論語の本章では”盛大な”。初出は甲骨文。甲骨文の字形は「厂」”がけ”+”酒壺”で、崖の洞穴で酒を醸し、味が濃厚になることだと言うが、その他諸説あって原義は不明。金文の段階で”多い”・”大きい”を意味した。詳細は論語語釈「厚」を参照。
葬(ソウ)


(甲骨文)/(秦系戦国文字)
論語の本章では”葬儀を行う”。初出は甲骨文。甲骨文の字形は「囗」”墓室”+「爿」”寝台”で、現行の字体とは大きく異なるが、古文字学者がなぜ「葬」と断じているかは明らかでない。西周・春秋に用例が無く、一旦滅んだ漢語である可能性がある。その場合、論語時代の置換候補は漢音で同音、上古音で近音の「喪」。現行の字体の初出は秦系戦国文字。「死」+「又」”手”が二つで、丁寧に死者を弔うさま。原義は”ほうむる”。甲骨文では、原義に用いられ、戦国の金文や竹簡でも同様。詳細は論語語釈「葬」を参照。
之(シ)


(甲骨文)
論語の本章では”これ”。初出は甲骨文。字形は”足”+「一」”地面”で、あしを止めたところ。原義はつま先でつ突くような、”まさにこれ”。殷代末期から”ゆく”の語義を持った可能性があり、春秋末期までに”~の”の語義を獲得した。詳細は論語語釈「之」を参照。
子曰(シエツ)(し、いわく)

論語の本章では”孔子先生が言った”。「子」は貴族や知識人に対する敬称で、論語では多くの場合孔子を指す。この二文字を、「し、のたまわく」と読み下す例がある。「言う」→「のたまう」の敬語化だが、漢語の「曰」に敬語の要素は無い。古来、論語業者が世間からお金をむしるためのハッタリで、現在の論語読者が従うべき理由はないだろう。


(甲骨文)
「子」の初出は甲骨文。論語の本章では、「子曰」で”先生”、「猶子也」で”息子”、「二三子」で”諸君”の意。字形は赤ん坊の象形。春秋時代では、貴族や知識人への敬称に用いた。季康子や孔子のように、大貴族や開祖級の知識人は「○子」と呼び、一般貴族や孔子の弟子などは「○子」と呼んだ。詳細は論語語釈「子」を参照。


(甲骨文)
「曰」の初出は甲骨文。原義は「𠙵」=「口」から声が出て来るさま。詳細は論語語釈「曰」を参照。
不(フウ)


(甲骨文)
論語の本章では”~でない”。漢文で最も多用される否定辞。「フ」は呉音、「ブ」は慣用音。初出は甲骨文。原義は花のがく。否定辞に用いるのは音を借りた派生義。詳細は論語語釈「不」を参照。現代中国語では主に「没」(méi)が使われる。
可(カ)


(甲骨文)
論語の本章では”~できる”。可能の意を示す。初出は甲骨文。字形は「口」+「屈曲したかぎ型」で、原義は”やっとものを言う”こと。甲骨文から”~できる”を表した。日本語の「よろし」にあたるが、可能”~できる”・勧誘”…のがよい”・当然”…すべきだ”・認定”…に値する”の語義もある。詳細は論語語釈「可」を参照。
回(カイ)


「回」(甲骨文)
論語の本章では、顔回子淵のいみ名(本名)。いみ名は自分自身か、同格以上の者が呼ぶ際の呼称。初出は甲骨文。ただし「亘」と未分化。現行字体の初出は西周早期の金文。字形は渦巻きの象形で、原義は”まわる”。詳細は論語語釈「回」を参照。
也(ヤ)


(金文)
論語の本章では、「回也」では「や」と読んで主格の強調。「猶父也」「猶子也」「非我也」「二三子也」は「なり」と読んで断定の意”~である”か、「かな」と読んで詠嘆”だなあ”の意。断定の語義は春秋時代では確認できない。初出は事実上春秋時代の金文。字形は口から強く語気を放つさまで、原義は”…こそは”。春秋末期までに句中で主格の強調、句末で詠歎、疑問や反語に用いたが、断定の意が明瞭に確認できるのは、戦国時代末期の金文からで、論語の時代には存在しない。詳細は論語語釈「也」を参照。
視(シ)


(甲骨文)
論語の本章では、”見なす”。新字体は「視」。初出は甲骨文。甲骨文の字形は大きく目を見開いた人で、原義は”よく見る”。現行字体の初出は秦系戦国文字。甲骨文では”視察する”の意に、金文では”見る”の意に用いられた(𣄰尊・西周早期)。また地名や人名にも用いられた。詳細は論語語釈「視」を参照。
予(ヨ)

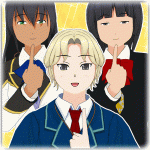
(金文)
論語の本章では”わたし”。初出は西周末期の金文で、「余・予をわれの意に用いるのは当て字であり、原意には関係がない」と『学研漢和大字典』はいうが、春秋末期までに一人称の用例がある。”あたえる”の語義では、現伝の論語で「與」となっているのを、定州竹簡論語で「予」と書いている。字形の由来は不明。金文では氏族名・官名・”わたし”の意に用い、戦国の竹簡では”与える”の意に用いた。詳細は論語語釈「予」を参照。
猶(ユウ)
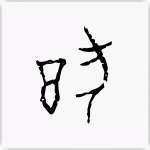

(甲骨文)
論語の本章では、”まるで…のようだ”。この語義は春秋時代では確認できない。初出は甲骨文。字形は「酉」”酒壺”+「犬」”犠牲獣のいぬ”で、「猷」は異体字。おそらく原義は祭祀の一種だったと思われる。甲骨文では国名・人名に用い、春秋時代の金文では”はかりごとをする”の意に用いた。戦国の金文では、”まるで…のようだ”の意に用いた。詳細は論語語釈「猶」を参照。
父(フ)


(甲骨文)
論語の本章では”父親”。初出は甲骨文。手に石斧を持った姿で、それが父親を意味するというのは直感的に納得できる。金文の時代までは父のほか父の兄弟も意味し得たが、戦国時代の竹簡になると、父親専用の呼称となった。詳細は論語語釈「父」を参照。
得(トク)


(甲骨文)
論語の本章では”手に入れる”→”~できる”。初出は甲骨文。甲骨文に、すでに「彳」”みち”が加わった字形がある。字形は「貝」”タカラガイ”+「又」”手”で、原義は宝物を得ること。詳細は論語語釈「得」を参照。
非(ヒ)


(甲骨文)
論語の本章では”~でない”。初出は甲骨文。甲骨文の字形は互いに背を向けた二人の「人」で、原義は”…でない”。「人」の上に「一」が書き足されているのは、「北」との混同を避けるためと思われる。甲骨文では否定辞に、金文では”過失”、春秋の玉石文では「彼」”あの”、戦国時代の金文では”非難する”、戦国の竹簡では否定辞に用いられた。詳細は論語語釈「非」を参照。
我(ガ)


(甲骨文)
論語の本章では”わたし”。初出は甲骨文。字形はノコギリ型のかねが付いた長柄武器。甲骨文では占い師の名、一人称複数に用いた。金文では一人称単数に用いられた。戦国の竹簡でも一人称単数に用いられ、また「義」”ただしい”の用例がある。詳細は論語語釈「我」を参照。
非我(われにあらず)
先秦の文章では、「非我」は本章同様、下に目的語などを持たない場合に用いられる。「非吾」は下に目的語を伴っている。ただし漢代に入るとこの原則は崩れる。
夫(フ)


(甲骨文)
論語の本章では「かの」と読んで”あの”という指示詞。この語義は春秋時代では確認できない。初出は甲骨文。論語では「夫子」として多出。「夫」に指示詞の用例が春秋時代以前に無いことから、”あの人”ではなく”父の如き人”の意で、多くは孔子を意味する。「フウ」は慣用音。字形はかんざしを挿した成人男性の姿で、原義は”成人男性”。「大夫」は領主を意味し、「夫人」は君主の夫人を意味する。固有名詞を除き”成人男性”以外の語義を獲得したのは西周末期の金文からで、「敷」”あまねく”・”連ねる”と読める文字列がある。以上以外の語義は、春秋時代以前には確認できない。詳細は論語語釈「夫」を参照。
二三子(ジサンシ)
論語の本種では”弟子諸君”。弟子たちに対する孔子による呼称。「ニ」を「ニ」と読むのは呉音。「子」は貴族や知識人に対する敬称。
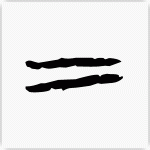

(甲骨文)
「二」の初出は甲骨文。字形は「上」「下」字と異なり、上下同じ長さの線を引いた指事文字で、数字の”に”を示す。「ニ」は呉音。甲骨文・金文では数字の”2”の意に用いた。詳細は論語語釈「二」を参照。


(甲骨文)
「三」の初出は甲骨文。原義は横棒を三本描いた指事文字で、もと「四」までは横棒で記された。「算木を三本並べた象形」とも解せるが、算木であるという証拠もない。詳細は論語語釈「三」を参照。
論語:付記
検証
論語の本章は前漢中期の定州竹簡論語にあるが、春秋戦国を含め先秦両漢の誰一人引用も再録もしていない。「門人欲厚葬之」は戦国中期の『荘子』に見えるが、もちろん荘子ばなしであり顔淵ばなしではない。ただ文字史上は全て論語の時代に遡り得るので、史実として扱ってよい。
ただ論語の本章は、論語子罕篇19と似た点が無いではない。
| 本章 | 門人欲厚葬之 | 夫二三子也 |
| 子罕篇19 | 子路使門人爲臣 | 死於二三子之手乎 |
解説
顔回子淵が仕官したという記録は無い。論語雍也篇11が「陋巷に在り」という貧乏暮らしは後世の創作だが、「厚葬」を受けるに足る身分があったこともまた証拠が無い。それにもかかわらず弟子仲間は盛大な葬儀を行おうとした。顔淵の人望が篤くなければ考えられない。
それに対して孔子は「不可」と言った。現伝儒教が言う、葬儀に関するややこいい格差や規則は、司馬遷が「儒教の礼法は前漢武帝以前に綺麗さっぱり失われていた」と証言する通り、漢儒のでっち上げだが(論語における「礼」)、だからといって孔子の生前、身分によって葬儀の格式に差があったことを否定出来はしない。
仕官して以降の孔子は、革命家と体制維持者の両側面を持った。公職=家職である伝統を打破し、身分に拘わらず能力ある者がふさわしい公職に就くのを目指した点で革命家だったが、身分秩序そのものの護持者でもあった。無政府状態を好んでいたわけではないのである。
従って顔淵の厚葬に反対する根拠があったわけだが、弟子仲間は強行した。それに対してグチグチ言っている孔子はいつもの孔子らしくない。晩年でもあり息子や顔淵に先立たれたのが打撃だった時期でもあり、弟子を圧倒できず、愚痴を言うしか無かったのだろう。
なお顔淵の死去は魯の哀公十四年(BC481)とされており、すでにBC495に世を去っているはずの先代・定公が弔問の使いを出したという『孔子家語』の記事は理屈に合わない。
顏回死,魯定公弔焉,使人訪於孔子。孔子對曰:「凡在封內,皆臣子也。禮:君弔其臣,升自東階,向尸而哭,其恩賜之施,不有笇也。」
顔回が死んで、魯の定公が弔問の使いを孔子の所へ送った。孔子が使者に言った。「すべて領域内に住む者は、身分を問わす国公の臣下です。礼法の定めでは、主君が臣下を弔問するには、喪主宅の東の階段より入り、なきがらに向かって哭きの礼をし、追贈品には、ここまでという数量の限度がありません。(好きなだけ追贈品を贈ってよろしいのです。)(『孔子家語』公西赤問)
この文字列は現存でも古い方である「欽定四庫全書」でも「定公」となっているから、時系列にいい加減な漢儒によるでっち上げと断じてよいのだが、まるで孔子が「もっと下され物を出せ」と請求したかのように読める。それに、「不可」と孔子が言った、論語の本章とも矛盾している。「身分を問わす国公の臣下」なら、どんな厚葬もまかり通ることになるからだ。
論語の本章、新古の注は次の通り。
古注『論語集解義疏』
顔淵死門人欲厚葬之子曰不可註禮貧富各有宜顔淵家貧而門人欲厚葬之故不聽也門人厚葬之子曰囘也視予猶父也予不得視猶子也非我也夫二三子也註馬融曰言囘自有父父意欲聽門人厚葬之我不得制止也非其厚葬故云爾也
本文「顔淵死門人欲厚葬之子曰不可」。
注釈。礼法では、貧富に応じて適切な葬儀の規模がある。顔淵は家が貧しいのに弟子仲間が派手な葬儀を出そうとした。だから孔子は許さなかった。
本文「門人厚葬之子曰囘也視予猶父也予不得視猶子也非我也夫二三子也」。
注釈。馬融「つまり、顔淵の父親がもともと世間体のよい葬儀を出したがり、弟子仲間が派手な葬儀をしたのを、自分は止められなかったと言い、そんな葬儀はよろしくないと言っている。だからこのように言ったのだ。」
新注『論語集注』
顏淵死,門人欲厚葬之,子曰:「不可。」喪具稱家之有無,貧而厚葬,不循理也。故夫子止之。門人厚葬之。蓋顏路聽之。子曰:「回也視予猶父也,予不得視猶子也。非我也,夫二三子也。」歎不得如葬鯉之得宜,以責門人也。
本文「顏淵死,門人欲厚葬之,子曰:不可。」
葬儀にはその家の家格の有無にふさわしくする必要があり、貧乏なのに派手な葬儀を出すのは、道理に従っていない。だから先生は止めた。
本文「門人厚葬之。」
たぶん顔淵の父顔路が厚葬を許したのだろう。
本文「子曰:回也視予猶父也,予不得視猶子也。非我也,夫二三子也。」
孔子は自分の一人息子である孔鯉の葬儀を無位無冠にふさわしく安上がりに済ませた(論語先進篇7)ように、顔淵の葬儀もふさわしくできなかったのを嘆き、弟子を責めたのである。
余話
一視同仁

読者の不可解は筆者の責任と筆者は思え
論語の本章で孔子は、顔淵が自分を父のように見なしたからには、自分も顔淵を実の子のように見なさねばならないとする立場を表明した。帝政儒教の言う一方的・片利共生的な孝行を孔子はここでも否定し、人間関係は相互的・互恵的であると言った(論語における「恕」)。
同時に、人間関係にはそれぞれ違いがあって、親子関係は他人同士の関係とは違う特別なものだと表明した。これは帝国儒者の言い出した図々しさにも合致している。
権力者が身内びいき、仲間びいきしたのを見て民が感動するなど絵空事だが、そうしたひいきは中国の民百姓の道徳でもあった。これに反する「一視同仁」”万人を差別なく憐れむ”を台湾の植民地化に際して明治政府が言い出し、通じてしまったのは台湾だったからだ。
つまりそれほど「中国化」していなかったからだ。日清戦争の前年(183)の台湾の人口は255万人とwikiが言うが、これは清朝が把握していた数だけで、台湾原住民を全て勘定していない。また清朝は漢人女性の台湾渡航を認めなかったため。住民の多くが混血だった。
子の思考が父より母の影響を大きく受けるのは理の当然で、「一視同仁」と言われて「そんなものかな」と思ってしまったのだろう。対して朱子学にどっぷり浸かっていた朝鮮人は「一視同仁」にものすごく反発し、テロや暴動を繰り返したのは伊藤博文の最期に現れている。
こんにち一部の保守派論客が言うように、「一視同仁」が台湾・朝鮮人にとって有り難いものであった道理はなく、政治経済を日本人が独占し現地原住民を見下したのは明らかだが、日本人がそれなりに漢文を読んでこのスローガンを言い出したのも間違いない。
元ネタは唐の大儒・韓愈の「原人」。現代語訳は以下の通り。
形於上者謂之天,形於下者謂之地,命於其兩間者謂之人。形於上,日月星辰皆天也;形於下,草木山川皆地也;命於其兩間,夷狄禽獸皆人也。曰:然則吾謂禽獸人,可乎?曰:非也。指山而問焉,曰:山乎?曰:山,可也;山有草木禽獸,皆舉之矣。指山之一草而問焉,曰:山乎?曰:山,則不可。故天道亂,而日月星辰不得其行;地道亂,而草木山川不得其平;人道亂,而夷狄禽獸不得其情。天者,日月星辰之主也;地者,草木山川之主也;人者,夷狄禽獸之主也。主而暴之,不得其為主之道矣。是故聖人一視而同仁,篤近而舉遠。
はるか高みにある存在を天と言い、世の全てを載せる存在を地という。その間に生きる者を人という。高みにある太陽・月や星座は全て天に属する。下に載せられた草木山川は地に属する。その間に生きる者たち、蛮族・トリやケダモノは中国人に属する。ある者「ではトリやケダモノを中国人と言ってよいのか?」
韓愈「いいわけがない。山を指さして、山か? と問われたら山だと答えていい。その山には草木やトリやケダモノが居る。どれも指さすことが出来る。そこで山に生えた一本の草を指さして、山か? と問われて、山だと答えてよいわけがない。
だから天の運行が乱れると、太陽も月も星座も動くに動けない。地の道理が崩れると、草木も山川も穏やかではいられない。人の世のことわりがおかしくなると、蛮族もトリ・ケダモノも生存が危なくなる。
天は、日月星座の主である。地は、草木山川の主である。中国人は、蛮族・トリ・ケダモノの主である。その主である中国人が、ものごとの分類を滅茶苦茶にすれば、主ではいられなくなってしまう。
だから聖人だけが、万物を”一視同仁”できるし、身近な者を手厚く扱いながら、縁遠い者の身分を上げてやれるのだ。」(韓愈「原人」)
「是故聖人一視而同仁」は「これゆえ聖人は一に視て仁(なさけ)を同じくす」と訓読するのはいいが、”聖人にしかできないことだ”と解釈しないと誤読することになる。「これ聖人ゆえ」と読み下した方が正確な読解と言うべきだ。「一視同仁」とは”万人が平等”の意ではない。
もともと、中国人とそれ以外、一般中国人と聖人を厳しく差別するのを前提にしていた。差別無しに一視同仁は無い。ただそんな厳しさをどの中国人も意識していたわけでなく、明代に完成した『金瓶梅』『封神演義』は、陽気に”みんな平等”という脳天気な意味で用いている。
しかし朝鮮人が首まで漬かった朱子学ではそうでもなかった。
問「孝弟為仁之本」。曰:「此是推行仁道,如『發政施仁』之『仁』同,非『克己復禮為仁』之『仁』,故伊川謂之『行仁』。學者之為仁,只一念相應便是仁。然也只是這一箇道理。『為仁之本』,就事上說;『克己復禮』,就心上說。」又論「本」字云:「此便只是大學『其本亂而末治者否矣』意思。理一而分殊,雖貴乎一視同仁,然不自親始,也不得。」
(朱子の弟子・伯羽)「論語学而篇2、”孝弟は仁の本”とはどういう意味ですか?」
朱子「年上への奉仕が、仁の道を実践する方法だ、ということだ。”政治を手段に仁を実現する”というのと同じだ。
だから、論語顔淵篇1で”我欲に打ち勝って礼法に従うのを仁という”とあるのとは、仁は仁でも理屈が違う。だから程伊川先生は、わざわざ”仁を行う”と言って、仁そのものとは区別した。
儒学を学ぶ者が仁を実践するには、ひたすらその場にふさわしいように振る舞えばそれでいい。だが一つだけ条件がある。学而篇が言う”仁の本”とは行動の話で、顔淵篇が言う”我欲に打ち勝って礼法に従う”のは心の話だ。(心身ともに仁を伴わねばならない。)
また学而篇で”本”と言ったのは、『大学』に”基本が乱れては枝葉の事柄がうまく行くわけがない”と説くのと同じ道理で、原則はいつも堅く守りつつ、かつ行動はその場にふさわしくなければならない。一視同仁=いつでもどこでも扱いは同じ、というわけにはいかないのだ。
そして自分で心身ともに仁を実践しなければ、他人に仁を期待できる道理が無い。」(『朱子語類』有子曰其為人也孝弟章)
朱子学を含め宋学はオカルトが基本で、話者以外に何を言っているか分からないのが当たり前なのだが、この部分に限っては言っていることが明らかだ。つまり、一視同仁は好ましくなく、「自分が仁のつもりでいるなら、その場にふさわしければ何をやって仁になる。」
これは容易に、好き勝手に振る舞っても仁だと言い張る免罪符になった。韓愈同様に宋学は中国人以外の人間を劣等人種だと決めつけて差別したが、なるほど朱子学を国教とした朝鮮人が、蛮族と見下した日本人に「一視同仁」と言われて、素直に従うわけが無い。
話を朱子に戻せば、儒者という世間師稼業で食っている以上、朱子はオカルトばかり語るわけにはいかなかった。しかも政争に負けて個人事業主として開帳せざるを得なかったから、程頤や周敦頤のように左うちわで俸禄やワイロが手に入らない。客を逃しては食えなかった。
- 論語雍也篇3余話「宋儒のオカルトと高慢ちき」
それが上掲の文字列に反映している。日本人は西田幾多郎や真っ赤な連中のおかげで、わけのわからない事を書く者を詐欺師と見なしてよいという知恵を獲得したが、とりわけ文系諸学問について当てはまる。漢文もその範疇にあるから、オカルトの解読に付き合う必要は無い。
訳者が本サイトの改訂を繰り返すのもそれゆえだ。閲覧者諸賢のご理解を賜れば幸いである。
参考記事
- 論語泰伯編17「羊頭狗肉」






コメント