論語:原文・書き下し
原文(唐開成石経)
子曰狂而不直侗而不愿悾悾而不信吾不知之矣
- 「直」字:〔十𠀃三〕。
校訂
東洋文庫蔵清家本
子曰狂而不直/侗而不愿/悾〻而不信/吾不知之矣
- 「直」字:〔十𠀃三〕。
定州竹簡論語
[子曰]:「狂而不直,俑a而不願,[空空b]而不信,吾弗智c[之矣]。」206
- 俑、今本作「侗」。俑与侗音近、仮借為侗。
- 空空、今本作「悾悾」。空借為悾。
- 弗智、今本作「不知」。
標点文
子曰、「狂而不直、俑而不願、空空而不信、吾弗智之矣。」
復元白文(論語時代での表記)





 俑
俑
 願
願 









※空→孔。論語の本章は、赤字が論語の時代に存在しない。本章は前漢儒による創作である。
書き下し
子曰く、狂なにし而直から不、俑にし而願なら不、空空にし而信なら不るは、吾之を智ら不る矣。
論語:現代日本語訳
逐語訳

先生が言った。「強情なのに正直でない者。幼稚なのに素直でない者。無知なのにうそをつく者。そのような者を知らないよ。」
意訳
やれやれ終わった終わった。田舎者はたちが悪い。

すぐカッとなるくせに小ずるい。
幼稚でダサいくせに見栄を張る。
無知なくせにウソをつく。
知らんよ、あんな連中。
弟子「…それはさっき帰った呉の使いのことですか?」「コラあ!」
従来訳
先師がいわれた。――
「熱狂的な人は正直なものだが、その正直さがなく、無知な人は律義なものだが、その律儀さがなく、才能のない人は信実なものだが、その信実さがないとすれば、もう全く手がつけられない。」下村湖人『現代訳論語』
現代中国での解釈例
孔子說:「狂妄而不直率、幼稚而不老實、看上去忠厚卻不講信用,我無法理解這種人。」
孔子が言った。「狂い回って素直でなく、幼稚で不正直で、見た目は誠実だが実は信用できない、かような者は私にとって理解する方法が無い。」
論語:語釈
子曰(シエツ)(し、いわく)

論語の本章では”孔子先生が言った”。「子」は貴族や知識人に対する敬称で、論語では多くの場合孔子を指す。「子」は赤ん坊の象形、「曰」は口から息が出て来るさま。「子」も「曰」も、共に初出は甲骨文。辞書的には論語語釈「子」・論語語釈「曰」を参照。
この二文字を、「し、のたまわく」と読み下す例がある。「言う」→「のたまう」の敬語化だが、漢語の「曰」に敬語の要素は無い。古来、論語業者が世間からお金をむしるためのハッタリで、現在の論語読者が従うべき理由はないだろう。
狂(キョウ)


(甲骨文)
論語の本章では”自分でやる”→”自分の信念を貫く”。初出は甲骨文。同音に「俇」(上)=”あわただしいさま”。近音にgi̯waŋに「王」(平/去)、「往」(上)、「迋」(去)=”ゆく”。去声の音は不明。甲骨文の字形は「止」”ゆく”+「斧」+「犬」で、その場に出向いて犠牲獣の犬を屠るさま。原義は”自分で”・”近くで”。甲骨文で”近い”・”近づく”、金文で人名での用例がある。詳細は論語語釈「狂」を参照。
而(ジ)


(甲骨文)
論語の本章では”~でありかつ~”。初出は甲骨文。原義は”あごひげ”とされるが用例が確認できない。甲骨文から”~と”を意味し、金文になると、二人称や”そして”の意に用いた。英語のandに当たるが、「A而B」は、AとBが分かちがたく一体となっている事を意味し、単なる時間の前後や類似を意味しない。詳細は論語語釈「而」を参照。
不(フウ)


(甲骨文)
漢文で最も多用される否定辞。初出は甲骨文。「フ」は呉音、「ブ」は慣用音。原義は花のがく。否定辞に用いるのは音を借りた派生義だが、甲骨文から否定辞”…ない”の意に用いた。詳細は論語語釈「不」を参照。
直(チョク)


(甲骨文)
論語の本章では”正直”。初出は甲骨文。「𥄂」は異体字。「ジキ」は呉音。甲骨文の字形は「丨」+「目」で、真っ直ぐものを見るさま。原義は”真っ直ぐ見る”。甲骨文では祭礼の名に、金文では地名に、戦国の竹簡では「犆」”去勢した牡牛”の意に、「得」”…できる”の意に用いられた。詳細は論語語釈「直」を参照。
侗*(トウ)→俑*(ヨウ)
唐石経・清家本は「侗」と記し、現存最古の論語本である定州竹簡論語は「俑」と記す。時系列により「俑」へと校訂した。論語の伝承について詳細は「論語の成立過程まとめ」を参照。
原始論語?…→定州竹簡論語→白虎通義→ ┌(中国)─唐石経─論語注疏─論語集注─(古注滅ぶ)→ →漢石経─古注─経典釈文─┤ ↓↓↓↓↓↓↓さまざまな影響↓↓↓↓↓↓↓ ・慶大本 └(日本)─清家本─正平本─文明本─足利本─根本本→ →(中国)─(古注逆輸入)─論語正義─────→(現在) →(日本)─────────────懐徳堂本→(現在)


(戦国印璽文字)
唐石経・清家本の「侗」は、論語の本章では、”愚かであること”。論語では本章のみに登場。武内本は「無知の貌」という。初出は戦国の印章文字。論語の時代に存在しない。字形は「亻」+「同」で”中身の無い筒”。中身の無い人間のこと。同音は同とそれを部品とする漢字群など。春秋末~戦国初期の『墨子』では”柱”の意に用いた。論語時代の置換候補は部品の「同」”うつろ”。詳細は論語語釈「侗」を参照。


(篆書)
定州竹簡論語では「俑」と記す。人形のことだが、初出は定州竹簡論語。論語の時代に存在しない。字形は「亻」+「甬」で、”中が空洞の釣り鐘”。中身が空っぽの人形のこと。戦国の竹簡で”人形”の意に用いた。論語時代の置換候補は存在しない。詳細は論語語釈「俑」を参照。
愿*(ゲン)→願(ゲン)


(前漢隷書)
論語の本章では”まじめ”。論語では本章のみに登場。初出は戦国の竹簡。ただし字形は上下に〔无+心〕。論語の時代に存在しない。論語時代の置換候補もない。字形は音符「原」+「心」。「原」は崖からほとばしり出る水のことで、「心」からほとばしり出るもの、すなわち”ねがい”。「ガン」は慣用音。同音に元、原、源、芫(”フジモドキ”。「莞」とは別字)、願など。戦国の竹簡では”ねがい”の意に用いた。詳細は論語語釈「愿」を参照。


(燕系戦国文字)
定州竹簡論語は「願」と記す。「愿」の異体字。初出は燕系戦国文字。現行字体の初出は前漢の隷書。論語の時代に存在しない。論語時代の置換候補もない。「ガン」は慣用音、「ゴン」は呉音。同音は元や原を部品とする漢字群だが、”願う”の語義を持った文字は無い。部品の「原」には、”たずねる・根本を推求する”の語釈を『大漢和辞典』が載せるが、春秋時代以前の用例が無い。同音同訓「愿」の初出は後漢の『説文解字』。初出の字形は「月」”にく”+「复」”麺類生地の延べ棒”だが、字形から語義を導くのは困難。詳細は論語語釈「願」を参照。
悾*(コウ)→空*(コウ)


(後漢隷書)
論語の本章では”心がうつろなさま”。初出は後漢の隷書。論語の時代に存在しない。論語時代の置換候補もない。字形は〔忄〕”こころ”+「空」。うつろなこころのさま。同音は「空」「孔」「跫」”足音”。「クウ」は呉音。論語の本章のほか、戦国の編とされる『六韜』に「有悾悾而不信者」とあり、また後漢の『太玄経』に「次二,勞有恩,勤悾悾,君子有中。」とあり、いずれも”こころがうつろなさま”。詳細は論語語釈「悾」を参照。
武内本は、「悾悾は卑しくて文なきなり」という。


(戦国金文)
定州竹簡論語は「空」と記す。初出は西周早期の金文。ただし字形は部品の「工」。現伝字形の初出は戦国末期の金文。字形は「穴」+「工」。加工して穴を開けたさま。人為的に造成した空間を言う。「クウ」は呉音。西周早期~春秋末期まで、「司工」または「司攻」と記し、国歌の最高官の一つ、司空(土木工事と司法を司る)を意味した。詳細は論語語釈「空」を参照。
信(シン)
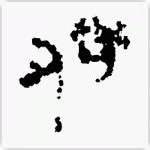

(金文)
論語の本章では、”信用がある”。この語義は春秋時代では確認できない。初出は西周末期の金文。字形は「人」+「口」で、原義は”人の言葉”だったと思われる。西周末期までは人名に用い、春秋時代の出土が無い。”信じる”・”信頼(を得る)”など「信用」系統の語義は、戦国の竹簡からで、同音の漢字にも、論語の時代までの「信」にも確認出来ない。詳細は論語語釈「信」を参照。
吾(ゴ)


(甲骨文)
論語の本章では”わたし”。初出は甲骨文。字形は「五」+「口」で、原義は『学研漢和大字典』によると「語の原字」というがはっきりしない。一人称代名詞に使うのは音を借りた仮借だとされる。詳細は論語語釈「吾」を参照。
春秋時代までは中国語にも格変化があり、一人称では「吾」を主格と所有格に用い、「我」を所有格と目的格に用いた。しかし論語でその文法が崩れ、「我」と「吾」が区別されなくなっている章があるのは、後世の創作が多数含まれているため。
不(フウ)→弗(フツ)
現伝の「吾不知之矣」を定州竹簡論語は「吾弗智之矣」と記す。


(甲骨文)
「弗」の初出は甲骨文。甲骨文の字形には「丨」を「木」に描いたものがある。字形は木の枝を二本結わえたさまで、原義はおそらく”ほうき”。甲骨文から否定辞に用い、また占い師の名に用いた。金文でも否定辞に用いた。詳細は論語語釈「弗」を参照。
知(チ)→智(チ)


(甲骨文)
論語の本章では”知るということ”。現行書体の初出は春秋早期の金文。春秋時代までは「智」と区別せず書かれた。甲骨文で「知」・「智」に比定されている字形には複数の種類があり、原義は”誓う”。春秋末期までに、”知る”を意味した。”知者”・”管掌する”の用例は、戦国時時代から。詳細は論語語釈「知」を参照。
定州竹簡論語は、普段は「智」の異体字「𣉻」と記す。通例、清家本は「知」と記し、正平本も「知」と記す。文字的には論語語釈「智」を参照。
之(シ)


(甲骨文)
論語の本章では”これ”。初出は甲骨文。字形は”足”+「一」”地面”で、あしを止めたところ。原義はつま先でつ突くような、”まさにこれ”。殷代末期から”ゆく”の語義を持った可能性があり、春秋末期までに”~の”の語義を獲得した。詳細は論語語釈「之」を参照。
矣(イ)


(金文)
論語の本章では、”(きっと)…だ”。初出は殷代末期の金文。字形は「𠙵」”人の頭”+「大」”人の歩く姿”。背を向けて立ち去ってゆく人の姿。原義はおそらく”…し終えた”。ここから完了・断定を意味しうる。詳細は論語語釈「矣」を参照。
武内本は、「不知之とは之を教うる所以を知らざる意」という。「矣」は断定とともに、”知らねえヨ”の「ヨ」に当たる詠嘆の語気を示す。
論語:付記
検証
論語の本章は、「悾悾而不信」が戦国時代の編と言われる兵法書『六韜』にあるほかは、春秋戦国を含めた先秦両漢の誰一人引用していないし、再録していない。事実上の初出は前漢中期の定州竹簡論語で、再出は後漢から三国に掛けて編まれた古注『論語集解義疏』になる。
文字史的に論語の時代に遡れない事を合わせ考えて、論語の本章は前漢儒による創作と断じてよい。
解説
本章を含む論語泰伯編が、孔子と呉国使節の応対であるかのように作られた意図が見えることを、すでに論語泰伯編1で述べた。その会見を、『史記』が伝えるように孔子若年の時とすると史実性が怪しくなるが、他の年ならありうる話ではある。
孔子が仕えた魯の定公は、治世の十五年(BC495)に世を去った。この時孔子57歳で諸国放浪の時期だったが、定公の葬儀に参列するためか、一時帰国していたらしい。孔子が正式に魯国貴族団から排除された記録は無いから、葬儀や弔問外交に列席するのはありうることである。
ただし仮に孔子と呉国使節の対話として本編が編まれたとしても、頭の悪すぎる後漢儒が間に曽子話をねじ込み、後ろに居もしない古代の聖王話をくっつけたので、わけが分からなくなってしまった。しかも呉国話に限っても、これまで検討した通りほとんどが偽作である。
| 章 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 話題 | 呉 | 呉 | 曽 | 曽 | 曽 | 曽 | 曽 | 呉 | 呉 | 呉 | 呉 | 呉 | 呉 | 呉 | 呉 | 呉 | ? | 聖 | 聖 | 聖 | 聖 |
| 真偽 | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | × | × | ○ | × | × | × | × |
そして次章論語泰伯編17「学は及ばざるが如く」は、対話と言うより孔子の独白と言ってよく、対話と捉えることは可能だが、泰伯編の呉国話はとりあえず本章で終わると言ってよい。
孔子は魯国存続のため、新興の呉国に期待はしつつも、ついに行くことは生涯無かった。行こうとしたと思われる記述は論語子罕篇14に見えるが後世の偽作で、呉越地方に向かった話も後世の創作にしかない(『呉越春秋』外伝)。
余話
理屈倒れの
論語の本章、「狂而不直」な人物は現代日本でもよく見かける。例えばT大で理Ⅲに受からない程度の理系人におり、中途半端にしか数学が出来ないくせに、自分は頭がいいと威張っている。思い上がった文系男女は言うまでも無い。要するに甘やかされ思い込みが強いのだ。
もちろん誰もが津軽海峡を泳いで渡れないように、数学が出来ないこと自体は、誰も責められるべきではない。だが出来ないのを出来ると言い張る人格は愚劣だ。そういう動物は、自分が勝手に立てた理数的?な理屈が現実に当てはまらないと、現実の方がおかしいと言い出す。
「狂」とは本来そうした脳の機能障害や、人格障害を言う。これには数理能力だけでなく、人文的教養も関わってくる。かかる障害者はサディストであることが多く、自分が卑しいサドにふけっているのに、これはサドでなく正当で立派な行為だと言い張って聞く耳を持たない。
そして自分は正しいのだから、言い分は誰にも通じて当然と思っている。
そうした例を論語泰伯編5余話に記した。現実に眼前の人間が苦しんでいるのに、苦しむのがおかしいと言い出す。つまり言い出した者の頭がおかしいのであり、「狂」がのちにそのような意味に転用されたのは理由のないことではない。『史記』にもそのような伝説がある。
帝紂資辨捷疾,聞見甚敏;材力過人,手格猛獸;知足以距諫,言足以飾非;矜人臣以能,高天下以聲,以為皆出己之下。
殷の紂王は生まれつき頭の回転が早くて体もよく動き、観察眼や人の話を吟味する能力が人並み優れていた。肉体と体力は誰よりも優れ、素手で猛獣と格闘して倒し、反対意見を言いくるめるだけの知能と弁舌を持ち、その弁舌は自分の欠点を全て無かったと他人が納得してしまうほどだった。家臣たちにはその才能を見せつけて従わせ、天下万民には優れた評判を轟かせて従えた。だから世界中の人間を、自分より劣りだと見下していた。(『史記』殷本紀)
こんな紂王は、やがて西方から攻め寄せた周によって攻められ追い詰められて自殺するのだが、あえて自殺を選んだのも、「この現実は間違っている」という思い込みからだろう。敗北を悟った人間なら、従容として降服したり、処刑台に首を差し伸べるだろうから。
人文的教養とはあるいはそのようなものだ。人文の目的は人間を知ることにある。だから眼前の人間も我と同じく、ひとしくいたましいと腑に落ちていないと話にならない。言い換えると人文を学んだのに人が悪い者は、つまり中途半端にしか人文を学べなかったのだ。
人文的教養なき紂王ほどの才を持たない連中で、かつ威張り返っている者は、役人や軍人にいくらでもいる。日本では誤解されやすいが軍人も公務員で、威張る者ほど戦争に行きたがらず、クビになったり退職金や年金が減ったりするのを恐れるだけの小役人に過ぎない。
急いで大声で書くが、立派な兵隊さんと威張り返った穀潰し軍人は、まるで別の生き物だ。
戦後のいかがわしい宣伝により、帝政日本史上、海軍はまともで陸軍が悪者であるかのように言いふらされてきたが、敗戦前後に皇室と海軍はつるんで、アメリカとなにがしかの密約を結んだ節がある。終戦の詔勅にある「國體ヲ護持シ得テ」とあるのがそれ。
または戦後に海軍の宣伝ばかりしていた阿川弘之が1999年に文化勲章を受けているのに、遠藤周作が受けたのはその4年前でしかないことを思ってもいい。1966年刊『沈黙』の書き手と帝国海軍の代理広告業者とで、作品の文学性を比較して論じることそのものが馬鹿馬鹿しい。
アメリカB-29部隊の総司令官として、罪の無い赤ん坊に至るまで日本人を焼き殺したルメイに、![]() ン丿一は敗戦後勲章をくれてやった。日本に乗り込んで占拠したあと、それまでの大王家を野蛮人呼ばわりして面白がった天武持統朝以降、
ン丿一は敗戦後勲章をくれてやった。日本に乗り込んで占拠したあと、それまでの大王家を野蛮人呼ばわりして面白がった天武持統朝以降、![]() ン丿一は価値判断の基準に出来ない。
ン丿一は価値判断の基準に出来ない。
阿川は『海軍こぼれ話』に、敗戦の理由を米海軍と戦ったからだと書いた。古今東西これほど卑劣な言い訳も無い。無敵海軍を言い回り、米海軍相手に戦うことを名目に、昭和恐慌のさなか身売り娘が出たというのに、莫大な国富を食い潰していたのは、一体どこの組織だろう。
訳者が帝国海軍を、日本史上最も無能で破廉恥な組織と断じるゆえんである。
なお中韓の回し者だった司馬遼太郎は、狐狸庵先生の前年に同勲章を受けているが、戦後日本の文壇論壇を、redとアメリカとそれらの回し者が相談して独占したと考えれば、多くのことに説明が付く。加えて日本のredは元はといえば、占領軍が育てたことも忘れられない。
- 論語公冶長篇15余話「マルクス主義とは何か」
うんざりでしょうが重ねて記す。帝国陸軍の総帥だった山県有朋を、回し者の司馬がしつこくこき下ろしたので誤解されているが、山県が京都に有隣庵を造り、趣味の築園のついでに池を掘り、琵琶湖疎水から水を取ろうとしたら、担当官から断られた。
「莫大な国費を投じて疎水を作ったのは、京都市民のためです。」もっともと思った山県は、「では池を近隣の防火水槽として献じるから、導水を認めて貰いたい」と言ってやっと認められた。真冬に庵を訪れて、職員さんに頂いたお茶を楽しみながら庭を見たのが懐かしい。

話を帝国海軍に戻せば、腐り始めるのは陸軍よりはるかに早かった。日本史を知る人なら、シーメンス事件は誰でも知っているだろう。加えて軍艦は陸戦兵器より国産化が困難で遅れたから、列強の造船所や兵器メーカーと海軍軍人との間で、後ろ暗い他人のカネをやりとりした。
- 論語泰伯編14余話「美味しいご飯はみんなで食べよう」
つまり中国の儒者官僚そっくりの連中が、帝国海軍では年々要職を占めていったわけで、昭和になって主力艦の「対米七割」を強固に主張したのも、海軍は軍艦が人事の単位だから、フネが減るとポストが減る→早期退職を余儀なくされる→老後はどうなるんだ、というわけ。
これは日露戦までは表沙汰にならなかった。今でも三笠の吹きさらしな艦橋に、東郷平八郎の足跡が残っているが、ロシア艦隊の砲弾がバンバン飛んでくる先頭で指揮を執った東郷と違い、山本は部下に任せて自分は妾を連れて呉で砂糖饅頭を食っていた。
その山本を弁護する書き物は戦後大量に溢れたが、全部アメリカ公認の世論操作だったと訳者は睨んでいる。その山本が建てた目算は、ハワイの太平洋艦隊を一挙に全滅させれば、米国は戦意を失ってすぐに和平できる、というチョコレートの砂糖がけのようなおとぎ話だった。
そのおとぎ話を陸軍も政府も真に受けて、地獄のような3年8ヶ月を日本人は味わわされ、戦後はアメリカの属国に落ちぶれた。愚劣は山本だけでなく、ミッドウェーに向かう南雲中将に、海軍大臣の及川は、「陛下の軍艦を沈めずに連れて帰ってくれ」と訓示したらしい。
出征軍司令官にこんな馬鹿げたことを言った軍務大臣は、おそらく古今東西に居ないと思う。山本はアメリカ通だったと言うが、いったい現地で何を見てきたのだろう。大和魂があるとすれば、アメリカにもヤンキー魂や南部魂があるはずだという、当たり前の道理が分からない。
珊瑚海海戦で撃沈同然になった空母ヨークタウンは、からくも真珠湾にたどり着いた後、わずかな日時で修理と補給を終え、新米パイロットと共にミッドウェーに向かった。そして空母蒼龍を撃沈、他艦と共同して日本機動部隊を全滅させた。闘志のすさまじさを思うべきである。
この時山本は戦艦大和以下の「主力部隊」を率いて南雲艦隊の後方にいたが、南雲の敗北を聞いてすごすごと帰ってしまった。「航空援護が無いから帰った」とは役人的言い訳に過ぎず、しかもそれすら山本と帝国海軍にとり、一方的に都合のよいウソだ。

ゲー・エム・コルジェフ 「Проводы」(送別)
手に武器があり、眼前に敵が居て、故国には護るべき大勢の人が待ち、我の無事を祈っている。ならば四の五の言わず押し込む。それが戦士というもので、米海軍はミッドウェーをそうやって勝った。米英ソも日独も楽に戦ったわけでない。狂おしく戦い、辛勝し惜敗したのだ。
戦はまた親も討たれよ、子も討たれよ、死ぬれば乗り越え乗り越え戦ふ候ふ。(『平家物語』富士川)
こうして南雲艦隊は全滅したが、なお山本は軽空母と水上機母艦を従えていた。大和に加え戦艦を何隻も連れていた。大和の主砲を当てれば、正規空母だろうと消し飛ぶだろうに。なのに帰った山本を、アメリカの回し者かと訳者は疑う。少なくとも自分が可愛いだけの小役人だ。
そして小役人どもがいま再び、日本人を悲惨へと追いやっている。





コメント