論語:原文・書き下し
原文(唐開成石経)
曽子曰士不可以不弘毅任重而道逺仁以爲己任不亦重乎死而後巳不亦逺乎
- 「曽」字:〔八田日〕。
校訂
東洋文庫蔵清家本
曽子曰士不可以不弘毅任重而道逺/仁以爲已任不亦重乎死而後已不亦逺乎
定州竹簡論語
……不可以不弘毅,任重而道遠。[仁以為己]197……死而後已,不亦遠乎?」198……
標点文
曽子曰、「士不可以不弘毅、任重而道遠。仁以爲己任、不亦重乎。死而後已、不亦遠乎。」
復元白文(論語時代での表記)
































※仁→(甲骨文)。論語の本章は、文字的には論語の時代に遡れるが、そもそも曽子は孔子の弟子ではない。「弘」「毅」「重」「乎」の用法に疑問がある。本章はおそらく前漢儒による創作である。
書き下し
曽子曰く、士は弘く毅からざるを以ゐる可から不、任重くし而道遠し。仁以て己の任と爲す、亦に重から不乎。死し而後に已む、亦に遠から不乎。
論語:現代日本語訳
逐語訳

曽子が言った。「士族は心が広くて意志が固くなければならない。その務めは重く、長く続く。常時無差別の愛を自分の務めとするのは、大層重いことだ。死んでやっと終わる、大層長いことだ。」
意訳

曽子「士族は寛大でなくてはならないが、志がブレるようではいけない。その責任は重く、一生続くのだ。いつも誰にでもわけへだてのない愛を注ぐべき、重大な立場だ。死ぬまでそれをやり通す、その長さを思うべきだ。」
従来訳
曾先生がいわれた。――
「道を行おうとする君は大器で強靭な意志の持主でなければならない。任務が重大でしかも前途遼遠だからだ。仁をもって自分の任務とする、何と重いではないか。死にいたるまでその任務はつづく、何と遠いではないか。」下村湖人『現代訳論語』
現代中国での解釈例
曾子說:「有志者不可以不培養堅強的意志,因為責任重大而且道路遙遠。以實現全人類和平友愛為自己的責任,這樣的責任不是很重大嗎?為理想奮斗終身,這樣的道路不是很遙遠嗎?」
曽子が言った。「志の有る者は強固な意志を養わないわけにはいかない。なぜなら責任は重大で道ははるか遠いからだ。全人類の平和と友愛の実現を自分の責務とする、このような責任は非常に重大ではないか?理想のために生涯奮闘する、このような道は非常に遠くはないか?」
論語:語釈
曾子(ソウシ)
新字体は「曽子」。後世、孔子晩年の高弟とされた人物。その実は孔子家の家事使用人。「○子」との呼び名は、孔子のような学派の開祖や、大貴族に用いる。孔子は論語先進篇17で、曽子を”ウスノロ”と評している。詳細は前々々章の語釈、また論語の人物・曽参子輿を参照。


(甲骨文)
「曾」(曽)の初出は甲骨文。旧字体が「曾」だが、唐石経・清家本ともに「曽」またはそれに近い字体で記している。字形は蒸し器のせいろうの象形で、だから”かさねる”の意味がある。「かつて」・「すなはち」など副詞的に用いるのは仮借で、西周の金文以降、その意味が現れたため、「甑」”こしき”の字が作られた。「甑」の初出は前漢の隷書。詳細は論語語釈「曽」を参照。


「子」(甲骨文)
「子」の初出は甲骨文。論語ではほとんどの章で孔子を指す。まれに、孔子と同格の貴族を指す場合もある。また当時の貴族や知識人への敬称でもあり、孔子の弟子に「子○」との例が多数ある。なお逆順の「○子」という敬称は、上級貴族や孔子のような学派の開祖級に付けられる敬称。「南子」もその一例だが、”女子”を意味する言葉ではない。字形は赤ん坊の象形で、もとは殷王室の王子を意味した。詳細は論語語釈「子」を参照。
曰(エツ)


(甲骨文)
論語で最も多用される、”言う”を意味する言葉。初出は甲骨文。原義は「𠙵」=「口」から声が出て来るさま。詳細は論語語釈「曰」を参照。
士(シ)


(金文)
論語の本章では、”士族”→”(我ら)儒者”。本章は発言者が曽子であることから、後世の偽作が疑われるので、「士」が戦時には出陣する士族であったことを考慮する必要がない。単に社会の上流階級を意味する。従って「よきひと」と訓読する。
もとは最下級の貴族で、現代で言う下士官に当たる。春秋時代は都市の商工民であることが多い。初出は西周早期の金文。「王」と字源を同じくする字で、斧を持った者=戦士を意味する。字形は斧の象形。春秋までの金文では”男性”を意味した。藤堂説では男の陰●の突きたったさまを描いたもので、牡(おす)の字の右側にも含まれる。成人して自立するおとこ、という。詳細は論語語釈「士」・論語解説「論語解説春秋時代の身分秩序」を参照。
儒者は官僚ではあっても、領主貴族ではない場合がほとんどで、宋帝国以降、中華帝国の官界が儒者によって独占されると、「士」=「儒者」になった。それ以前も官界の主流は儒者であり、事実上漢帝国以降は「士」=「儒者」と考えてほぼ間違いではない。
不可以不弘毅(コウキたらざるをもちゐるべからず)
論語の本章では”度量が広くなく、意志が強くないわけにはいかない”。
ここでの管到(語が支配する範囲)の関係は、「不可」”であってはならない”→「以」”用いる”→「不弘毅」”度量が大きく意志が強い、ではない”。「可以」”できる”で語を区切っては文意が通じない。
| 管到する語 | 管到の及ぶ範囲 | |
| 不可 ”~であってはならない” |
以 ”用いる” |
不弘毅 ”度量が広くも意志が堅くもない” |


(甲骨文)
「不」は漢文で最も多用される否定辞。初出は甲骨文。「フ」は呉音(遣隋使より前に日本に伝わった音)、「ブ」は慣用音。原義は花のがく。否定辞に用いるのは音を借りた派生義だが、甲骨文から否定辞”…ない”の意に用いた。詳細は論語語釈「不」を参照。


「可」(甲骨文)
「可」の初出は甲骨文。字形は「口」+「屈曲したかぎ型」で、原義は”やっとものを言う”こと。甲骨文から”…できる”を表した。日本語の「よろし」にあたるが、可能”~できる”・勧誘”~のがよい”・当然”~すべきだ”・認定”~に値する”の語義もある。詳細は論語語釈「可」を参照。


(甲骨文)
「以」の初出は甲骨文。人が手に道具を持った象形。原義は”手に持つ”。論語の時代までに、名詞(人名)、動詞”用いる”、接続詞”そして”の語義があったが、前置詞”~で”に用いる例は確認できない。ただしほとんどの前置詞の例は、”用いる”と動詞に解せば春秋時代の不在を回避できる。詳細は論語語釈「以」を参照。
「以不弘毅」は下に目的語を持つ動詞であり、「仁以爲己任」は仁と爲己任を繋ぐ接続詞。漢文の読解は日本古文の品詞判定と同様に、意味内容を確認しつつ読まねば意味が分からない。一つ覚えのように「もって」とばかり読んでいると、いつまでたっても漢文が読めるようにならない。
弘*(コウ)


(甲骨文)
論語の本章では”度量が広い”。初出は甲骨文。字形は「弓」+「𠙵」”くち”。原義は明瞭でない。甲骨文、春秋末期までの金文では、人名に用いた。詳細は論語語釈「弘」を参照。
毅*(ギ)
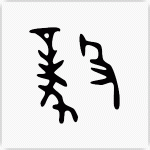

(金文)
論語の本章では”意志が強い”。この語義は春秋時代では確認できない。初出は西周末期の金文。字形は〔辛〕”小刀”+〔豕〕”ぶた”+〔殳〕”さばく”であり、ぶたを解体して肉や皮革にするさま。「キ」は慣用音。論語の時代以前では、西周末期の金文の例が6例知られるが、全て器名か人名。詳細は論語語釈「毅」を参照。
任*(ジン)


(甲骨文)
論語の本章では”責務”。初出は甲骨文。字形は「亻」+「工」”官職”。官職を持つ者の意。「ニン」は呉音。春秋末期までに、”官職”・姓氏名に用いた。詳細は論語語釈「任」を参照。
重(チョウ)
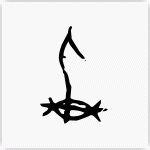
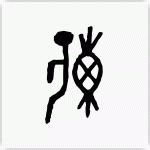
(甲骨文・金文)
論語の本章では”重い”。この語義は春秋時代では確認できない。初出は甲骨文。「ジュウ」は呉音。字形は「人」+「東」”ふくろ”で、金文の字形では、ふくろを背負う姿になっているものがある。原義は不詳。明確に”重い”・”重さ”の意が確認できるのは、戦国時代以降になる。詳細は論語語釈「重」を参照。
而(ジ)


(甲骨文)
論語の本章では”~でありかつ~”。初出は甲骨文。原義は”あごひげ”とされるが用例が確認できない。甲骨文から”~と”を意味し、金文になると、二人称や”そして”の意に用いた。英語のandに当たるが、「A而B」は、AとBが分かちがたく一体となっている事を意味し、単なる時間の前後や類似を意味しない。詳細は論語語釈「而」を参照。
道(トウ)
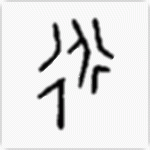

「道」(甲骨文・金文)
論語の本章では”…を行う過程”。動詞で用いる場合は”みち”から発展して”導く=治める・従う”の意が戦国時代からある。”言う”の意味もあるが俗語。初出は甲骨文。字形に「首」が含まれるようになったのは金文からで、甲骨文の字形は十字路に立った人の姿。「ドウ」は呉音。詳細は論語語釈「道」を参照。
遠(エン)


(甲骨文)
論語の本章では”遠く長い”。初出は甲骨文。字形は「彳」”みち”+「袁」”遠い”で、道のりが遠いこと。「袁」の字形は手で衣を持つ姿で、それがなぜ”遠い”の意になったかは明らかでない。ただ同音の「爰」は、離れたお互いが縄を引き合う様で、”遠い”を意味しうるかも知れない。詳細は論語語釈「遠」を参照。
仁(ジン)


(甲骨文)
論語の本章では、”常に憐れみの気持を持ち続けること”。初出は甲骨文。字形は「亻」”ひと”+「二」”敷物”で、原義は敷物に座った”貴人”。詳細は論語語釈「仁」を参照。
仮に孔子の生前なら、単に”貴族(らしさ)”の意だが、後世の捏造の場合、通説通りの意味に解してかまわない。つまり孔子より一世紀のちの孟子が提唱した「仁義」の意味。詳細は論語における「仁」を参照。
爲(イ)
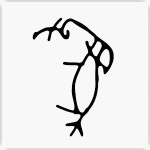

(甲骨文)
論語の本章では”…にする”。新字体は「為」。字形は象を調教するさま。甲骨文の段階で、”ある”や人名を、金文の段階で”作る”・”する”・”…になる”を意味した。詳細は論語語釈「為」を参照。
己(キ)
現存最古の論語本である定州竹簡論語では「己」と釈文され、唐石経も同じく「己」と記し、東洋文庫蔵清家本は「已」と記す。清家本は唐石経より前の古注系論語を伝承しており、唐石経を訂正しうるが、より古い定州本に従い校訂しなかった。
「巳」字であれ「已」字であれ語義は”自分”で変わらないし、つまり唐代頃までは「巳」”へび”と「已」”すでに”と「己」”おのれ”は相互に異体字として通用した。従って本章でも異体字として扱った。
論語の伝承について詳細は「論語の成立過程まとめ」を参照。
原始論語?…→定州竹簡論語→白虎通義→ ┌(中国)─唐石経─論語注疏─論語集注─(古注滅ぶ)→ →漢石経─古注─経典釈文─┤ ↓↓↓↓↓↓↓さまざまな影響↓↓↓↓↓↓↓ ・慶大本 └(日本)─清家本─正平本─文明本─足利本─根本本→ →(中国)─(古注逆輸入)─論語正義─────→(現在) →(日本)─────────────懐徳堂本→(現在)
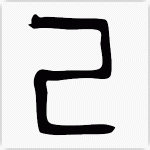

(甲骨文)
論語の本章では”自分”。初出は甲骨文。「コ」は呉音。字形はものを束ねる縄の象形だが、甲骨文の時代から十干の六番目として用いられた。従って原義は不明。”自分”の意での用例は春秋末期の金文に確認できる。詳細は論語語釈「己」を参照。


(甲骨文)
「已」の初出は甲骨文。字形と原義は不詳。字形はおそらく農具のスキで、原義は同音の「以」と同じく”手に取る”だったかもしれない。論語の時代までに”終わる”の語義が確認出来、ここから、”~てしまう”など断定・完了の意を容易に導ける。詳細は論語語釈「已」を参照。


(甲骨文)
慶大蔵論語疏は本章を欠くが、現存する章ではやはり同じく「己」「已」を「巳」と記す。「巳」の初出は甲骨文。字形はヘビの象形。「ミ」は呉音。甲骨文では干支の六番目に用いられ、西周・春秋の金文では加えて、「已」”すでに”・”ああ”・「己」”自分”・「怡」”楽しませる”・「祀」”まつる”の意に用いた。詳細は論語語釈「巳」を参照。
亦(エキ)


(甲骨文)
論語の本章では”おおいに・たいそう”。本章は発言者が孔子の弟子ではない曽子なので、後世の派生義で解釈して構わない。初出は甲骨文。字形は人間の両脇で、派生して”…もまた”の意に用いた。”おおいに”の意は甲骨文・春秋時代までの金文では確認できず、初出は戦国早期の金文。のちその意専用に「奕」の字が派生した。詳細は論語語釈「亦」を参照。
乎(コ)


(甲骨文)
論語の本章では”…ではないか”。この語義は春秋時代では確認できない。「乎」の初出は甲骨文。甲骨文の字形は持ち手を取り付けた呼び鐘の象形で、原義は”呼ぶ”こと。甲骨文では”命じる”・”呼ぶ”を意味し、金文も同様で、「呼」の原字となった。句末の助辞や助詞として用いられたのは、戦国時代以降になる。ただし「烏乎」で”ああ”の意は、西周早期の金文に見え、句末でも詠嘆の意ならば論語の時代に存在した可能性がある。詳細は論語語釈「乎」を参照。
死(シ)
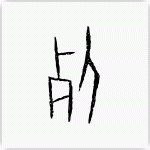

(甲骨文)
論語の本章では”死ぬ”。字形は「𣦵」”祭壇上の祈祷文”+「人」で、人の死を弔うさま。原義は”死”。甲骨文では、原義に用いられ、金文では加えて、”消える”・”月齢の名”、”つかさどる”の意に用いられた。戦国の竹簡では、”死体”の用例がある。詳細は論語語釈「死」を参照。
後(コウ)


(甲骨文)
論語の本章では時間的な”あと”。「ゴ」は慣用音、呉音は「グ」。初出は甲骨文。その字形は彳を欠く「幺」”ひも”+「夂」”あし”。あしを縛られて歩み遅れるさま。原義は”おくれる”。甲骨文では原義に、春秋時代以前の金文では加えて”うしろ”を意味し、「後人」は”子孫”を意味した。また”終わる”を意味した。人名の用例もあるが年代不詳。詳細は論語語釈「後」を参照。
已(イ)


(甲骨文)
論語の本章では”やめる”。この語義は春秋時代では確認できない。初出は甲骨文。字形と原義は不詳。字形はおそらく農具のスキで、原義は同音の「以」と同じく”手に取る”だったかもしれない。論語の時代までに”終わる”の語義が確認出来、ここから、”~てしまう”など断定・完了の意を容易に導ける。詳細は論語語釈「已」を参照。
論語:付記
検証
論語の本章は、春秋戦国時代の誰一人引用も再録もせず、後漢初期の王充が『論衡』で全文を「曽子曰く」として引用しているのみ。定州竹簡論語にあることから、前漢半ばには創作されていたのだろうが、あまりに下らないことが書いてあるので、さすがの中国人もうんざりして引用したがらなかったらしい。
もとより曽子は孔子の弟子ではなく、人に説教できるような儒学の教師でもない。論語の本章は文字史的には論語の時代に遡れるが、春秋時代に無い語義で使われている部分が多数あり、前漢儒による偽作と断じてよい。
解説
「あまりに下らないことが書いてある」というのは大げさでも何でも無い。他人の自己犠牲は、どんなに泣き濡れても荘重に讃えても我が身に危険は及ばないが、「お前だけそうしろ」と臆面もなく言える図々しさは、脳がある種の構造に出来ていないと不可能だからだ。
要するに一種の知能障害であり、価値判断を他人任せにしているとそうだと気付かない。
後世の儒者が曽子に語らせたことは、全て自分らの金儲けのために他人を洗脳するための言葉だが、論語の本章もその一つで、言わせた儒者に「仁義」のかけらもないくせに、「死してのち已む」などと大げさな表現で、読む者聞く者をクルクルパーにしようと狙っている。
死んだ後は死んでいるのだから、やめるも何もないはずで、「トムとジェリー」世界の物理現象と同様、そんなことあり得ない笑い話でしかない。
ところが今なお、それをまじめ腐った顔で説く者、有り難そうに聞く者がいるというのだから、どんなに世の中が進んでも、どんな人間集団でも、一定数頭のおかしな者は常にいるという事実を明らかにしている。こういうバカバカしい話が量産されそののち滅びなかった理由については、論語学而篇4余話「中華文明とは何か」を参照。
余話
日暮れて道遠し

もし漢文に興味を持つなら、同じ言葉でも曽子でなく伍子胥の言葉を知った方がいい。伍子胥は楚の上級貴族の生まれで、孔子と同時代人。色欲に血迷った楚の平王を、父と兄が諌めて殺され、平王が幼い王孫をも手に掛けようとしたので、手を引いて国外に逃亡した。
始伍員與申包胥為交,員之亡也,謂包胥曰:「我必覆楚。」包胥曰:「我必存之。」及吳兵入郢,伍子胥求昭王。既不得,乃掘楚平王墓,出其尸,鞭之三百,然後已。申包胥亡於山中,使人謂子胥曰:「子之報讎,其以甚乎!吾聞之,人眾者勝天,天定亦能破人。今子故平王之臣,親北面而事之,今至於僇死人,此豈其無天道之極乎!」伍子胥曰:「為我謝申包胥曰,吾日莫途遠,吾故倒行而逆施之。」於是申包胥走秦告急,求救於秦。秦不許。包胥立於秦廷,晝夜哭,七日七夜不絕其聲。秦哀公憐之,曰:「楚雖無道,有臣若是,可無存乎!」乃遣車五百乘救楚擊吳。六月,敗吳兵於稷。會吳王久留楚求昭王,而闔廬弟夫概乃亡歸,自立為王。闔廬聞之,乃釋楚而歸,擊其弟夫概。夫概敗走,遂奔楚。楚昭王見吳有內亂,乃復入郢。封夫概於堂谿,為堂谿氏。楚復與吳戰,敗吳,吳王乃歸。
もともと、伍子胥は貴族仲間の申包胥と仲がよかった。伍子胥が亡命するとき、申包胥にこう言い残した。「俺は必ず楚国を滅ぼしてやる」と。申包胥は答えて、「では私は何としてでもそれを阻止しましょう」と言った。
伍子胥は呉国に亡命し、呉王の参謀となって富国強兵に成功し、その呉軍を率いて楚の都を落とした。当時の楚王、昭王はすでに逃げ去った後だった。伍子胥は怨み重なる平王の墓を掘り返すと、死体を引きずり出して鞭打った。三百も打ってやっとやめた。
この時申包胥は山に避難していたが、話を聞いて使いを出して言わせた。「あなたの怒りはごもっともですが、やり過ぎではありませんか。私はこう言う話を聞いています。人々がみな同意するなら天にも勝てる、天がそう決めたらどんな敵にも勝てる、と。あなたは仮にも平王殿下の家臣だったではありませんか。殿下の生前、まめまめしく仕え申し上げたのをよく覚えています。それが今はこんな仕打ちをなさる。天の怒りを買うのではありませんか?」
伍子胥は使者に言った。「申包胥どのに、よくお礼申し上げてくれ。だがな、ワシにとっては”日暮れて途遠し”なのだ。この先も楚国全土を征服するまで忙しい。そのためなら、天にも人にも逆らおうがかまってはいられない。」
使いの言葉を聞くと、申包胥は秦国へ急行し、秦の哀公に援軍を頼んだが、哀公は首を縦に振らなかった。(当時軍事大国と言えば北の晋と南の楚、そして新興の呉で、その呉と正面から戦えるほど、秦は強大化していなかったからだ。)
万策尽きた申包胥は、秦の政庁の庭に立ち、七日七晩泣き続けた。
「あーーー、ああー、あー!」
大の男で、上級貴族が休みもせずに立ち尽くし、もちろん粥の一杯どころか水一滴も飲まずに泣き尽くした。
哀公はさすがに気の毒になって言った。「楚はこれまで無茶苦茶なことばかりしてきた兇暴な国だが、それでもこのような家臣がいる。滅びることはありえない。」
そこで五百両の戦車隊を出して伍子胥を討伐させ、稷の地で破った。この時呉王闔廬は逃げた楚の昭王を追って楚国を転戦していたが、弟の夫概が勝手に帰国し、自立して王を称した。やむを得ず闔廬は軍を反転させて夫概を破り、敗れた夫概は逆に楚へ亡命した。
呉の内乱でやっと都へ帰れた楚の昭王は、夫概を堂谿の領主に任じた。そしてさらに呉に攻め込み、呉軍を破った。呉王はとうとう楚の征服をあきらめた。(『史記』伍子胥伝13)
伍子胥が手を引いて守った王孫はのちに白公と呼ばれ、孔子に操られて楚で反乱を起こし、殺された。孔子とすれ違うように生きた墨子が、そのように証言している。『墨子』非儒下篇現代語訳を参照。
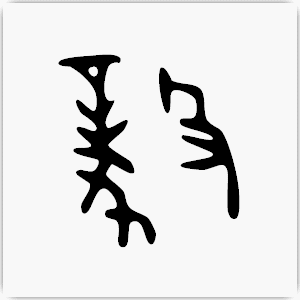


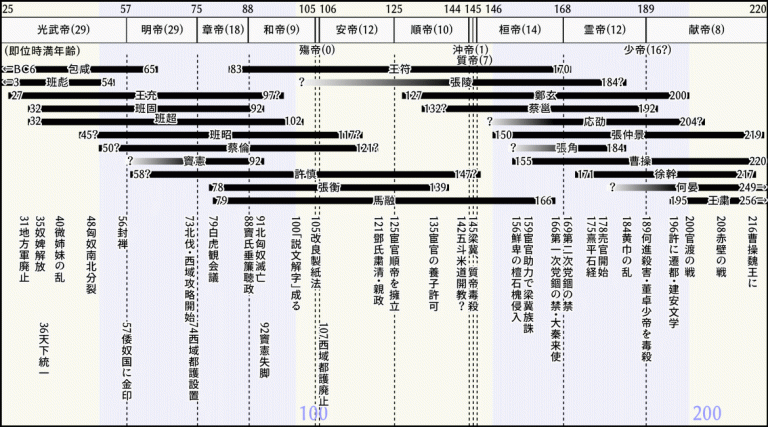


コメント