論語:原文・書き下し
原文
子曰吾有知乎哉無知也有鄙夫問於我空空如也我叩其兩端而竭焉
校訂
諸本
- 武内本:清家本により、夫の下に來の字を補う。空空如、鄭本悾悾如に作る。
※東洋文庫蔵・宮内庁蔵・京大蔵清家本に「來」字無し。武内本誤りか。 - 『経典釈文』巻二十三:「鄭或作悾悾」。
東洋文庫蔵清家本
子曰吾有知乎哉無知也/有鄙夫問於我空〻如也我叩其兩端而竭焉
慶大蔵論語疏
子曰吾有知〔爫丁〕1〔𢦏く丿〕2(㦲)3无4知也有〔口面阝〕5夫問扵6我空〻如也我𨙫7其兩端而竭〔万丂一灬〕8
- 「乎」の異体字。「魏鄭羲碑」(北魏)刻。
- 「哉」の異体字。「隋羊本墓誌」刻字に近似。
- 「哉」の異体字。「唐高岑墓誌」刻。傍記。
- 「無」の異体字。「睡虎地秦簡」記。
- 「鄙」の異体字。「樊毅修華嶽碑」(後漢)刻。
- 「於」の異体字。『新加九経字様』(唐)所収。
- 「叩」の異体字。「孔龢碑」(後漢)刻。
- 「焉」の異体字。「魏孝文帝弔比干文」(北魏)刻。
後漢熹平石経
(
定州竹簡論語
……智a□哉?無智a也。有鄙夫b問乎c我,空空d如□219……[其兩端]而竭焉。」220
- 智、今本作「知」。
- 皇本「夫」下有「來」字。
- 乎、今本作「於」字。
- 空空、『釋文』云、「空空、鄭本或作悾悾、同、音空」。
標点文
子曰、「吾有智乎哉、無智也。有鄙夫問乎我、空空如也、我叩其兩端而竭焉。」
書き下し
子曰く、吾智る有る乎哉、智る無き也。鄙夫有りて我乎問ひ、空空如也に、我其の兩端を叩い而竭し焉も。
復元白文(論語時代での表記)



















 扣
扣
 端
端 竭焉
竭焉
※論語の本章は「扣」「端」「竭」「焉」の字が論語の時代に存在しない。「乎」「也」「鄙」「問」「如」の用法に疑問がある。本章は戦国時代以降の儒者による創作である。
論語:現代日本語訳
逐語訳

先生が言った。「私に知識があるかな、知っていることはない。田舎者が私に問うても、空っぽだったが、私は自分の両端を叩いて出し切ったのだが。」
意訳

(前章からの続き)これ子貢よ。私は物知りとは云えぬよ。呉の田舎者があれこれ聞いたので、政治の手練手管を、酒壺を叩いて出すように出し切ったが、最近様子が怪しいではないか。
従来訳
先師がいわれた。
「私が何を知っていよう。何も知ってはいないのだ。だが、もし、田舎の無知な人が私に物をたずねることがあるとして、それが本気で誠実でさえあれば、私は、物事の両端をたたいて徹底的に教えてやりたいと思う。」下村湖人『現代訳論語』
現代中国での解釈例
孔子說:「我知識豐富嗎?我無知埃有個農民問我,他提出的問題,我一無所知,我問了事情的來龍去脈後,才徹底清楚了。」
孔子が言った。「私の知識は豊富か?私は無知だ。ある農民が私に質問して、彼が出した問いに対し、私は全く知る所が無かった。私は問いのいきさつを調べたあと、やっとはっきりと分かった。」
論語:語釈
子曰(シエツ)(し、いわく)

論語の本章では”孔子先生が言った”。「子」は貴族や知識人に対する敬称で、論語では多くの場合孔子を指す。「子」は赤ん坊の象形、「曰」は口から息が出て来るさま。「子」も「曰」も、共に初出は甲骨文。辞書的には論語語釈「子」・論語語釈「曰」を参照。


(甲骨文)
この二文字を、「し、のたまわく」と読み下す例がある。「言う」→「のたまう」の敬語化だが、漢語の「曰」に敬語の要素は無い。古来、論語業者が世間からお金をむしるためのハッタリで、現在の論語読者が従うべき理由はないだろう。
吾(ゴ)


(甲骨文)
論語の本章では”わたし”。初出は甲骨文。字形は「五」+「口」で、原義は『学研漢和大字典』によると「語の原字」というがはっきりしない。一人称代名詞に使うのは音を借りた仮借だとされる。詳細は論語語釈「吾」を参照。
春秋時代までは中国語にも格変化があり、一人称では「吾」を主格と所有格に用い、「我」を所有格と目的格に用いた。しかし論語でその文法が崩れ、「我」と「吾」が区別されなくなっている章があるのは、後世の創作が多数含まれているため。
有(ユウ)


「有」(甲骨文)
論語の本章では”保有する”。初出は甲骨文。ただし字形は「月」を欠く「㞢」または「又」。字形はいずれも”手”の象形。金文以降、「月」”にく”を手に取った形に描かれた。原義は”手にする”。原義は腕で”抱える”さま。甲骨文から”ある”・”手に入れる”の語義を、春秋末期までの金文に”存在する”・”所有する”の語義を確認できる。詳細は論語語釈「有」を参照。
知(チ)→智(チ)


(甲骨文)
論語の本章では”知るということ”。現行書体の初出は春秋早期の金文。春秋時代までは「智」と区別せず書かれた。甲骨文で「知」・「智」に比定されている字形には複数の種類があり、原義は”誓う”。春秋末期までに、”知る”を意味した。”知者”・”管掌する”の用例は、戦国時時代から。詳細は論語語釈「知」を参照。
定州竹簡論語は、普段は「智」の異体字「𣉻」と記す。通例、清家本は「知」と記し、正平本も「知」と記す。文字的には論語語釈「智」を参照。
原始論語?…→定州竹簡論語→白虎通義→ ┌(中国)─唐石経─論語注疏─論語集注─(古注滅ぶ)→ →漢石経─古注─経典釈文─┤ ↓↓↓↓↓↓↓さまざまな影響↓↓↓↓↓↓↓ ・慶大本 └(日本)─清家本─正平本─文明本─足利本─根本本→ →(中国)─(古注逆輸入)─論語正義─────→(現在) →(日本)─────────────懐徳堂本→(現在)
乎(コ)


(甲骨文)
論語の本章では、「乎哉」では「哉」と組み合わせで詠嘆の意。一字ずつ分解すると、「乎」は疑問、「哉」は詠嘆で、”知ることあるかなぁ”という訳になる。「問乎我」では”~に”。この語義は春秋時代では確認できない。初出は甲骨文。論語の本章では形容詞・副詞についてそのさまを意味する接尾辞。この用例は春秋時代では確認できない。字形は持ち手の柄を取り付けた呼び鐘を、上向きに持って振り鳴らし、家臣を呼ぶさまで、原義は”呼ぶ”こと。甲骨文では”命じる”・”呼ぶ”を意味し、金文も同様で、「呼」の原字となった。句末の助辞として用いられたのは、戦国時代以降になるという。詳細は論語語釈「乎」を参照。
![]()
慶大蔵論語疏は異体字「〔爫丁〕」と記す。「魏鄭羲碑」(北魏)刻。
哉(サイ)


(金文)
論語の本章では”…だなあ”。詠歎を表す。初出は西周末期の金文。ただし字形は「𠙵」”くち”を欠く「𢦏」で、「戈」”カマ状のほこ”+「十」”傷”。”きずつく”・”そこなう”の語釈が『大漢和辞典』にある。現行字体の初出は春秋末期の金文。「𠙵」が加わったことから、おそらく音を借りた仮借として語気を示すのに用いられた。金文では詠歎に、また”給与”の意に用いられた。戦国の竹簡では、”始まる”の意に用いられた。詳細は論語語釈「哉」を参照。
![]()
慶大蔵論語疏では上掲異体字「〔𢦏く丿〕」と記し、「㦲」と傍記している。前者は「隋羊本墓誌」刻字に近似。後者は「唐高岑墓誌」刻。
無(ブ)


(甲骨文)
論語の本章では”無い”。初出は甲骨文。「ム」は呉音。甲骨文の字形は、ほうきのような飾りを両手に持って舞う姿で、「舞」の原字。その飾を「某」と呼び、「某」の語義が”…でない”だったので、「無」は”ない”を意味するようになった。論語の時代までに、”雨乞い”・”ない”の語義が確認されている。戦国時代以降は、”ない”は多く”毋”と書かれた。詳細は論語語釈「無」を参照。


庚兒鼎・春秋中期/睡虎地簡54.43
慶大蔵論語疏では「无」と記す。初出は春秋中期の金文。ただし字形は「𣞤」で「無」の古形。現行字形の初出は秦系戦国文字。初出の字形は両端に飾りを下げた竿を担ぐ人の姿で、「無」の原義と同じく”舞う”姿。「ム」は呉音(遣隋使より前に日本に伝わった音)。春秋の金文では”ない”の意に、戦国最末期の秦系戦国文字に「先冬」とあり、「先」は「无」と釈文されている。詳細は論語語釈「无」を参照。
也(ヤ)


(金文)
論語の本章では「なり」と読んで断定の意。断定の意は春秋時代では確認できない。だからといって「や」「かな」と読んで”…だなあ”、詠嘆の意に取るのは無理がある。初出は事実上春秋時代の金文。字形は口から強く語気を放つさまで、原義は”…こそは”。春秋末期までに句中で主格の強調、句末で詠歎、疑問や反語に用いたが、断定の意が明瞭に確認できるのは、戦国時代末期の金文からで、論語の時代には存在しない。詳細は論語語釈「也」を参照。
鄙(ヒ)


(甲骨文)
論語の本章では”卑しい”または”田舎の”。この語義は春秋時代では確認できない。初出は甲骨文。ただし字形は「啚」。「囗」”囲い”+「大」”屋根”+「冬」”穀物”で、原義は”穀物倉”。甲骨文では”穀物倉”・”貯蔵した穀物”・”住民”の意に用い、春秋末期までの金文では加えて”田舎”の意に用いた。詳細は論語語釈「鄙」を参照。
![]()
慶大蔵論語疏は異体字「〔口面阝〕」と記す。「樊毅修華嶽碑」(後漢)刻。
夫(フ)


(甲骨文)
論語の本章では”おとこ”。初出は甲骨文。論語では「夫子」として多出。「夫」に指示詞の用例が春秋時代以前に無いことから、”あの人”ではなく”父の如き人”の意で、多くは孔子を意味する。「フウ」は慣用音。字形はかんざしを挿した成人男性の姿で、原義は”成人男性”。「大夫」は領主を意味し、「夫人」は君主の夫人を意味する。固有名詞を除き”成人男性”以外の語義を獲得したのは西周末期の金文からで、「敷」”あまねく”・”連ねる”と読める文字列がある。以上以外の語義は、春秋時代以前には確認できない。詳細は論語語釈「夫」を参照。
問(ブン)


(甲骨文)
論語の本章では”質問する”。この語義は春秋時代では確認できない。定州竹簡論語では欠いている。初出は甲骨文。「モン」は呉音(遣隋使より前に日本に伝わった音)。字形は「門」+「口」。甲骨文での語義は不明。金文では人名に用いられ、”問う”の語義は戦国時代の竹簡以降になる。詳細は論語語釈「問」を参照。
於(ヨ)→乎(コ)


(金文)
論語の本章では”~に”。初出は西周早期の金文。ただし字体は「烏」。「ヨ」は”~において”の漢音(遣隋使・遣唐使が聞き帰った音)、呉音は「オ」。「オ」は”ああ”の漢音、呉音は「ウ」。現行字体の初出は春秋中期の金文。西周時代では”ああ”という感嘆詞、または”~において”の意に用いた。詳細は論語語釈「於」を参照。
慶大蔵論語疏は、異体字「扵」と記す。『新加九経字様』所収。
現存最古の定州竹簡論語では「乎」と記す。これに従い校訂した。
我(ガ)


(甲骨文)
論語の本章では”わたし”。初出は甲骨文。字形はノコギリ型のかねが付いた長柄武器。甲骨文では占い師の名、一人称複数に用いた。金文では一人称単数に用いられた。戦国の竹簡でも一人称単数に用いられ、また「義」”ただしい”の用例がある。詳細は論語語釈「我」を参照。
空*空如(コウコウジョ)
論語の本章では”空っぽ”。

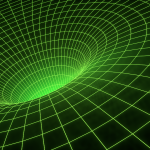
(金文)
「空」の初出は西周早期の金文。ただし字形は部品の「工」。現伝字形の初出は戦国末期の金文。字形は「穴」+「工」。加工して穴を開けたさま。人為的に造成した空間を言う。「悾」”まこと”、「孔」”通る・あな・大きい・空しい”、「控」。「クウ」は呉音。西周早期~末期までの用例は全て「司工」としるして「司空」と釈文している。司空は国家の最高官の一つで、土木工事とそれに使役する罪人の管理や司法を取り扱う。春秋時代の用例も同様で、ただし「司攻」と記した例がある。詳細は論語語釈「空」を参照。


(後漢隷書)
『経典釈文』では「鄭本或」と断りながら「悾」と記す。初出は後漢の隷書。論語の時代に存在しない。論語時代の置換候補もない。字形は〔忄〕”こころ”+「空」。うつろなこころのさま。同音は「空」「孔」「跫」”足音”。「クウ」は呉音。論語の本章のほか、戦国の編とされる『六韜』に「有悾悾而不信者」とあり、また後漢の『太玄経』に「次二,勞有恩,勤悾悾,君子有中。」とあり、いずれも”こころがうつろなさま”。詳細は論語語釈「悾」を参照。
『経典釈文』はしばしば「鄭本」なるものを引用し、後漢末の鄭玄が記した論語の版本が、隋初までは残っていたことになるが、「或」”あるいは”と言い訳しなければならないほど、中身や字面が違う版本が多数あって混乱したらしい。


「如」(甲骨文)
「如」は”~であるさま”。この語義は春秋時代では確認できない。初出は甲骨文。字形は「口」+「女」。甲骨文の字形には、上下や左右に部品の配置が異なるものもあって一定しない。原義は”ゆく”。詳細は論語語釈「如」を参照。
扣*(コウ)→𨙫(コウ)
論語の本章では”たたく”。唐石経を祖本とする現伝論語では「扣」と記し、現存最古の古注本である慶大蔵論語疏では「叩」の異体字「𨙫」と記す。定州竹簡論語はこの部分を欠くので、慶大本に従って校訂した。


(楚系戦国文字)
「扣」は論語では本章のみに登場。初出は楚系戦国文字。論語の時代に存在しない。論語時代の置換候補もない。現行字形は「扌」+「𠙵」”くち”で、大声を上げて手を出すことだが、初出の字形は「扌」には見えない。楚系戦国文字「郭店楚簡」で「手」に比定されている文字は上下に「上」+「氺」で、上掲字体とは全く異なる。へんは何らかの道具を意味するか。詳細は論語語釈「扣」を参照。


(甲骨文)/(前漢隷書)
慶大蔵論語疏は「𨙫」と記す。「叩」の異体字で「孔龢碑」(後漢)刻。「叩」の初出は甲骨文だが、金文~戦国文字まで見られず、殷周交替で一旦絶えた漢語と思われる。字形は「𠙵」”くち”+卩”ひざまずいた人”。言葉で人従わせる意か。詳細は論語語釈「叩」を参照。
其(キ)


(甲骨文)
論語の本章では”その”という指示詞。初出は甲骨文。甲骨文の字形は「𠀠」”かご”。それと指させる事物の意。金文から下に「二」”折敷”または「丌」”机”・”祭壇”を加えた。人称代名詞に用いた例は、殷代末期から、指示代名詞に用いた例は、戦国中期からになる。詳細は論語語釈「其」を参照。
兩(リョウ)


(金文)
論語の本章では”二つの”。新字体は「両」。初出は西周早期の金文。字形は車を牽く家畜のくびきの象形で、原義は不明。金文では”二つ”、量の単位に用いた。詳細は論語語釈「両」を参照。
端(タン)

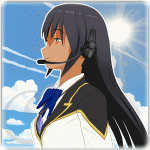
(楚系戦国文字)
論語の本章では、”はし”。初出は楚系戦国文字。論語の時代に存在しない。”はし”の語義では論語時代の置換候補もない。同音に「耑」とそれを部品に持つ漢字群、「段」を部品に持つ漢字群、「短」・「断」など。部品で同音の「耑」の初出は甲骨文。「耑」の字形は根を含む植物が雨に潤うさまで、原義は”みずみずしく美しい”。「端」は”みずみずしく美しい位置に立つ”。原義は”端正”。「耑」は甲骨文では国名に、金文では酒器の一種を意味し(義楚觶・春秋末期)、また人名に用いた。戦国時代の竹簡では、「端」を「耑」と記し、また「短」として使われた。詳細は論語語釈「端」を参照。
而(ジ)


(甲骨文)
論語の本章では”そして”。初出は甲骨文。原義は”あごひげ”とされるが用例が確認できない。甲骨文から”~と”を意味し、金文になると、二人称や”そして”の意に用いた。英語のandに当たるが、「A而B」は、AとBが分かちがたく一体となっている事を意味し、単なる時間の前後や類似を意味しない。詳細は論語語釈「而」を参照。
竭(ケツ)


(篆書)
論語の本章では”尽くす”。『大漢和辞典』の第一義は”背負い上げる”。初出は後漢の『説文解字』。論語の時代に存在しない。論語時代の置換候補もない。字形は「立」+「曷」”乾く”・”尽きる”で、人が力を尽くして立ち働くさま。詳細は論語語釈「竭」を参照。
焉(エン)
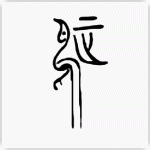

(金文)
論語の本章では「ぬ」と読んで、断定または完了を意味することば。初出は戦国早期の金文で、論語の時代に存在せず、論語時代の置換候補もない。漢学教授の諸説、「安」などに通じて疑問辞と解するが、いずれも春秋時代以前に存在しないか、疑問辞としての用例が確認できない。ただし春秋時代までの中国文語は、疑問辞無しで平叙文がそのまま疑問文になりうる。
字形は「鳥」+「也」”口から語気の漏れ出るさま”で、「鳥」は装飾で語義に関係が無く、「焉」は事実上「也」の異体字。「也」は春秋末期までに句中で主格の強調、句末で詠歎、疑問や反語に用いたが、断定の意が明瞭に確認できるのは、戦国時代末期の金文からで、論語の時代には存在しない。詳細は論語語釈「焉」を参照。
![]()
慶大蔵論語疏はこの部分に虫食いがあり明瞭でないが、通例、上掲異体字「〔万丂一灬〕」と記す。「魏孝文帝弔比干文」刻。
我扣其兩端而竭焉

論語当時の酒瓶には上掲「缶」があり、漏れやアルコールの揮発を防いだのだろう。それ以外の酒瓶には気密性が低いものが多いが、当時の技術では5%程度の酒しか醸せなかっただろうし、食卓に並べてすぐ呑むのなら、「缶」でなくともよかったはず。
ともあれ酒を蓄えるには大きな酒瓶に入れて口を布と泥で密封するか、「缶」を使うしかなかったはず。「両端を叩いて」というのは、「缶」を叩いてしずくを出すような様と解した。
論語:付記
検証
論語の本章は前漢中期の定州竹簡論語に記されているものの、史実性は極めて乏しい。
前半「吾有知乎哉、無知也。」は春秋戦国を含む先秦両漢の文献に引用や再録が無い。似た文字列が戦国末期の『荀子』にあるばかり。
後半「有鄙夫問於我,空空如也,我叩其兩端而竭焉。」は先秦両漢の文献に全く見られない。文字史上も論語の時代に遡れず、本章は戦国時代以降の儒者、おそらく前漢儒による偽作と断じてよい。
解説
論語の前篇、泰伯篇はもと孔子と呉使節の応対ばなしとして作成されたのを、後漢儒がおろかにもぶつ切りにした上デタラメを混ぜ込んで滅茶苦茶になった。そもそも贋作だから驚くには当たらないが、本子罕篇もまた、弟子による孔子の思い出話として編まれた節がある。
孔子一門が新興の呉国や、その背後にある越国とつるんで陰謀ばたらきをしたという証言を、孔子とすれ違うように生きた墨子がしており(現代語訳)、それを踏まえると本章は、呉の田舎者に教えを呉れてやったが、どうにも結果が思わしくない、との孔子のグチと解せる。
その意味である程度史実を伝えている可能性はある。呉国は国王さえ体に入れ墨し、髷を切ってザンバラ髪という、いまだ野蛮性を残した国だった。それだけに強兵だったのだろうが、国王夫差を孔子一門が焚き付けて、いろいろと政治外交の手練手管を伝えたのである。


なお上掲の「缶」はまた「缻」(フ)とも書き、西方の秦国では酔っぱらうと、これをチャンチキ叩いて歌う風習があった。『史記』戦国時代の名シーンの一つ、趙の名宰相・藺相如が、秦王にこれを叩かせて恥をかかせるくだりは、漢文業界に名高い。詳細はこちら。
論語の本章、新古の注は次の通り。
古注『論語集解義疏』
子曰吾有知乎哉無知也註知者知意之知也言知者言未必盡也今我誠盡也有鄙夫來問於我空空如也我叩其兩端而竭焉註孔安國曰有鄙夫來問於我其意空空然我則發事之終始兩端以語之竭盡所知不為有愛也
本文「子曰吾有知乎哉無知也」。
注釈。知とは思いを知るという意味での知である。知と言った所で、思いを言い尽くせはしない。しかし今は、”私は思いを知り尽くしている”という表明である。
本文「有鄙夫來問於我空空如也我叩其兩端而竭焉」。
注釈。孔安国「田舎者が孔子のところへ来てものを尋ねたが、中身の無いことばかりだった。どうにかしてやろうと思い、言っている事の初めから終わりまで、分かるように惜しみなく教えてやった、ということである。」
新注『論語集注』
子曰:「吾有知乎哉?無知也。有鄙夫問於我,空空如也,我叩其兩端而竭焉。」叩,音口。○孔子謙言己無知識,但其告人,雖於至愚,不敢不盡耳。叩,發動也。兩端,猶言兩頭。言終始、本末、上下、精粗,無所不盡。程子曰:「聖人之教人,俯就之若此,猶恐眾人以為高遠而不親也。聖人之道,必降而自卑,不如此則人不親,賢人之言,則引而自高,不如此則道不尊。觀於孔子、孟子,則可見矣。」尹氏曰:「聖人之言,上下兼盡。即其近,眾人皆可與知;極其至,則雖聖人亦無以加焉,是之謂兩端。如答樊遲之問仁知,兩端竭盡,無餘蘊矣。若夫語上而遺下,語理而遺物,則豈聖人之言哉?」
本文。「子曰:吾有知乎哉?無知也。有鄙夫問於我,空空如也,我叩其兩端而竭焉。」
叩は口の音で読む。孔子は謙遜して自分に知識が無いと言った。私はものを知りません、というのは愚かの限りを尽くしてはいるが、知っていて言い尽くさなかっただけである。叩とは、動き始めるの意。両端とは、二つの頭というような意味。言葉には二つの頭があるようことをいう。言葉には終始、本末、上下、精粗があって、言い尽くさないことは出来ない、言う側からバレるのである。
程頤「聖人が人に説教するに当たっては、このように謙遜していた。高飛車にものを言えば、みんなが怖がって近寄ってこないんじゃないかと恐れたのである。聖人が人の道を説くにあたっては、必ずあいてに合わせて程度を低くしてやる。そうでないとやはりみんなが怖がってしまう。聖人より一歩劣る賢人の説教は、自分から偉そうに語る。そうでないとみんなが有り難がってくれないからだ。広視野も牛を観察すれば、説教のやり方を知ることができる。」
尹焞「聖人の説教は、高尚も下劣も全部含んでいる。だから親しみやすいので、みんながもののことわりを知ることが出来る。教説の奥義については、聖人でもそれ以上付け足すことが無い。だから聖人の説教に、両端があると言うのだ。樊遅が仁や知を問うた時(論語雍也篇22)、両端を余すところなく説いた。隠しておくウンチクなどなかったのである。もしその説教が高尚なばかりだったら、ことわりだけ言って事例を示さなかったら、聖人の説教とは言えないのだ。」
余話
(思案中)





コメント