論語:原文・書き下し
原文(唐開成石経)
樊遲問知子曰務民之義敬鬼神而逺之可謂知矣問仁曰仁者先難而後獲可謂仁矣
- 「民」字:「叚」字のへんで記す。唐太宗李世民の避諱。
- 「敬」字:〔艹〕→〔十十〕。
- 「鬼」字:〔由〕→〔田〕。
校訂
東洋文庫蔵清家本
樊遲問知子曰務民之義/敬鬼神而逺之可謂知矣/問仁子曰仁者先難而後獲可謂仁矣
- 「鬼」字:〔由〕→〔田〕。
- 「問仁子曰」:正平本同。
後漢熹平石経
(なし)
定州竹簡論語
樊遲問智。子曰:「務民之義,敬鬼a而遠之,可謂智b矣。」129
- 今本「鬼」下有「神」字。
- 智、今本作「知」。
標点文
樊遲問智。子曰、「務民之義、敬鬼而遠之、可謂智矣。」問仁。子曰、「仁者先難而後獲、可謂仁矣。」
復元白文(論語時代での表記)


































※仁・獲→(甲骨文)。論語の本章は、「問」の用法に疑問がある。
書き下し
樊遲智を問ふ。子曰く、民之義を務め、鬼を敬い而之を遠ざくるを、智と謂ふ可き矣。仁を問ふ。子曰く、仁なる者は難を先にし而獲を後にす、仁と謂ふ可き矣と。
論語:現代日本語訳
逐語訳
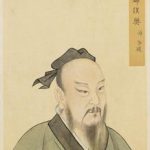
樊遅が知を問うた。先生が言った。「民が正しいとすることの実現に務め、亡霊を敬いつつ遠ざける。これを知と言っていい。」貴族らしさを問うた。先生が言った。「貴族たる者は難しい仕事を先に行って、報酬を後で受け取るものだ。貴族らしいと言っていい。」
意訳
ボディーガード樊遅「知って何です?」
孔子「治水のような民が望む政策推進に励み、妖怪話は敬う振りして真に受けないことだな。」
樊遅「仁って何です?」
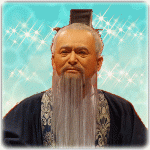
孔子「貴族が難しい仕事を終えた後で、自分の報酬を受け取ることだな。それでこそ立派なサムライだ。」
従来訳
樊遅が「知」について先師の教えを乞うた。先師がこたえられた。――
「ひたすら現実社会の人倫の道に精進して、超自然界の霊は敬して遠ざける、それを知というのだ。」
樊遅はさらに「仁」について教えを乞うた。先師がこたえられた。――
「仁者は労苦を先にして利得を後にする。仁とはそういうものなのだ。」下村湖人『現代訳論語』
現代中国での解釈例
樊遲問智,孔子說:「做事順應民心,尊重宗教卻遠離宗教,就算明智了。」又問仁,答:「吃苦在前、享受在後,就算仁了。」
樊遅が智を問うた。孔子が言った。「民の心にかなったことを行い、宗教を重んじつつ遠ざければ、つまり明智と言って良い。」また仁を問うた。答えた。「目前の苦労を味わい、収穫をその後で受け取れば、つまり仁と言って良い。」
論語:語釈
樊遲(ハンチ)
孔子の弟子、『史記』によると孔子より36年少。おそらくは子路が仕官してのち、身辺警護を樊遅が務めたと思われる。哀公十一年(BC484)の対斉防衛戦では、武勲を挙げている。詳細は論語の人物:樊須子遅を参照。
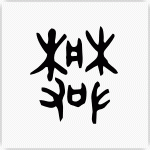

「樊」(金文)
「樊」の初出は西周早期の金文。金文の字形は早くは「口」を欠く。字形は「棥」”垣根”+「又」”手”二つで、垣根を作るさま。金文では人名に用いた。詳細は論語語釈「樊」を参照。


「遲」(甲骨文)
「遲」の初出は甲骨文。新字体は「遅」。唐石経・清家本は、異体字「遟」(〔尸〕の下が〔辛〕)と記す。現行字体に繋がる字形は〔辶〕+「犀」で、”動物のサイ”。字形に「牛」が入るようになったのは後漢の『説文解字』からで、それまでの「辛」を書き間違えたと思われる。詳細は論語語釈「遅」を参照。
問(ブン)


(甲骨文)
論語の本章では”問う”。この語義は春秋時代では確認できない。初出は甲骨文。「モン」は呉音(遣隋使より前に日本に伝わった音)。字形は「門」+「口」。甲骨文での語義は不明。西周から春秋に用例が無く、一旦滅んだ漢語である可能性がある。金文では人名に用いられ、”問う”の語義は戦国時代の竹簡以降になる。詳細は論語語釈「問」を参照。
知(チ)→智(チ)


(甲骨文)
論語の本章では”知るということ”。現行書体の初出は春秋早期の金文。春秋時代までは「智」と区別せず書かれた。甲骨文で「知」・「智」に比定されている字形には複数の種類があり、原義は”誓う”。春秋末期までに、”知る”を意味した。”知者”・”管掌する”の用例は、戦国時時代から。詳細は論語語釈「知」を参照。
定州竹簡論語は、普段は「智」の異体字「𣉻」と記すのに、本章で「智」となっている理由は明らかでない。清家本は「知」と記し、正平本も「知」と記す。古注に従い、本章の「知」は全て「智」と校訂した。文字的には論語語釈「智」を参照。
論語の伝承について詳細は「論語の成立過程まとめ」を参照。
原始論語?…→定州竹簡論語→白虎通義→ ┌(中国)─唐石経─論語注疏─論語集注─(古注滅ぶ)→ →漢石経─古注─経典釈文─┤ ↓↓↓↓↓↓↓さまざまな影響↓↓↓↓↓↓↓ ・慶大本 └(日本)─清家本─正平本─文明本─足利本─根本本→ →(中国)─(古注逆輸入)─論語正義─────→(現在) →(日本)─────────────懐徳堂本→(現在)
子曰(シエツ)(し、いわく)

論語の本章では”孔子先生が言った”。「子」は貴族や知識人に対する敬称で、論語では多くの場合孔子を指す。「子」は赤ん坊の象形、「曰」は口から息が出て来るさま。「子」も「曰」も、共に初出は甲骨文。辞書的には論語語釈「子」・論語語釈「曰」を参照。


(甲骨文)
この二文字を、「し、のたまわく」と読み下す例がある。「言う」→「のたまう」の敬語化だが、漢語の「曰」に敬語の要素は無い。古来、論語業者が世間からお金をむしるためのハッタリで、現在の論語読者が従うべき理由はないだろう。
二回目の孔子の答えは、現存最古の論語本である定州竹簡論語はこの部分の簡を欠き、唐石経の系統を引く現伝論語では「子」を省略する。清家本は「子」を記す。清家本の年代は唐石経より新しいが、より古い古注系の文字列を伝えており、唐石経を訂正しうる。従って「子曰」に校訂した。
務(ブ)
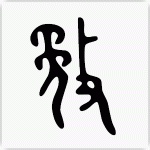

(金文)
論語の本章では、”実現に努力する”。この語義は春秋時代では確認できない。初出は殷代末期の金文。「ム」は呉音。字形は頭にかぶり物をかぶった人の背後から、「又」”手”に持ったカマ状のほこ「戈」で打ちかかるさまで、原義はおそらく”油断する”。春秋末期までに、”努力する”・”気にかける”の意、また人名に用いた。詳細は論語語釈「務」を参照。
「務める」→「つとめる」→「努める」の連想のように、日本語に引きずられたいわゆる「和臭」ではなく、”はげむ”の語義が諸橋『大漢和辞典』にも載っている。
民(ビン)


(甲骨文)
論語の本章では”たみ”。初出は甲骨文。「ミン」は呉音。字形は〔目〕+〔十〕”針”で、視力を奪うさま。甲骨文では”奴隷”を意味し、金文以降になって”たみ”の意となった。唐の太宗李世民のいみ名であることから、避諱して「人」などに書き換えられることがある。唐開成石経の論語では、「叚」字のへんで記すことで避諱している。詳細は論語語釈「民」を参照。
之(シ)


(甲骨文)
論語の本章では「民之義」では”…の”。「遠之」では”これ”。初出は甲骨文。字形は”足”+「一」”地面”で、あしを止めたところ。原義はつま先でつ突くような、”まさにこれ”。殷代末期から”ゆく”の語義を持った可能性があり、春秋末期までに”~の”の語義を獲得した。詳細は論語語釈「之」を参照。
義(ギ)


(甲骨文)
論語の本章では”(民が)正義(と思う事)”→”要求”。初出は甲骨文。字形は「羊」+「我」”ノコギリ状のほこ”で、原義は儀式に用いられた、先端に羊の角を付けた武器。春秋時代では、”格好のよい様”・”よい”を意味した。詳細は論語語釈「義」を参照。
論語での「民」とは、為政者としていたわってやる対象であるだけでなく、ひとたび怒らせれば一揆を起こして、君子=為政者層を皆殺しにかかる恐ろしい生き物でもあった。
敬(ケイ)
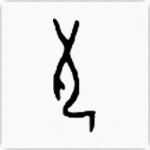

(甲骨文)
論語の本章では”敬う”。初出は甲骨文。ただし「攵」を欠いた形。頭にかぶり物をかぶった人が、ひざまずいてかしこまっている姿。現行字体の初出は西周中期の金文。原義は”つつしむ”。論語の時代までに、”警戒する”・”敬う”の語義があった。詳細は論語語釈「敬」を参照。
鬼(キ)
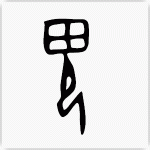

(甲骨文)
論語の本章では、角を生やした”オニ”ではなく、”亡霊・祖先の霊”。字形は「囟」”大きな頭”+「卩」”ひざまずいた人”で、目立つが力に乏しい霊のさま。原義は”亡霊”。甲骨文では原義で、また国名・人名に用い、金文では加えて部族名に、「畏」”おそれ敬う”の意に用いられた。詳細は論語語釈「鬼」を参照。
神(シン)


(金文)
論語の本章では、あらゆる神や超自然的存在。新字体は「神」。台湾・大陸ではこちらがコード上の正字として扱われている。初出は西周早期の金文。字形は「示」”位牌”・”祭壇”+「申」”稲妻”。「申」のみでも「神」を示した。「申」の初出は甲骨文。「申」は甲骨文では”稲妻”・十干の一つとして用いられ、金文から”神”を意味し、しめすへんを伴うようになった。「神」は金文では”神”、”先祖”の意に用いた。詳細は論語語釈「神」を参照。
殷代の漢字では「申」だけで”天神”を意味し、「土」だけで”大地神”意味し得た。「示」は両方を包括する神霊一般を意味した。西周になったとたんに「神」と書き始めたのは、殷王朝を滅ぼして国盗りをした周王朝が、「天命」に従ったのだと言い張るためで、文字を複雑化させたのはもったいを付けるため。「天子」の言葉が中国語に現れるのも西周早期で、殷の君主は自分から”天の子”などと図々しいことは言わなかった。詳細は論語述而篇34余話「周王朝の図々しさ」を参照。論語語釈「示」も参照。
而(ジ)


(甲骨文)
論語の本章では”と同時に”。初出は甲骨文。原義は”あごひげ”とされるが用例が確認できない。甲骨文から”~と”を意味し、金文になると、二人称や”そして”の意に用いた。英語のandに当たるが、「A而B」は、AとBが分かちがたく一体となっている事を意味し、単なる時間の前後や類似を意味しない。詳細は論語語釈「而」を参照。
遠(エン)


(甲骨文)
論語の本章では”遠ざける”。初出は甲骨文。字形は「彳」”みち”+「袁」”遠い”で、道のりが遠いこと。「袁」の字形は手で衣を持つ姿で、それがなぜ”遠い”の意になったかは明らかでない。ただ同音の「爰」は、離れたお互いが縄を引き合う様で、”遠い”を意味しうるかも知れない。詳細は論語語釈「遠」を参照。
可(カ)


「可」(甲骨文)
論語の本章では”…できる”。初出は甲骨文。字形は「口」+「屈曲したかぎ型」で、原義は”やっとものを言う”こと。甲骨文から”…できる”を表した。日本語の「よろし」にあたるが、可能”~できる”・勧誘”~のがよい”・当然”~すべきだ”・認定”~に値する”の語義もある。詳細は論語語釈「可」を参照。
謂(イ)


(金文)
論語の本章では”言う”。本来、ただ”いう”のではなく、”~だと評価する”・”~だと認定する”。下掲新注で朱子が「冉雍に直接言った話ではない」と語った説に、この漢語はある程度の根拠を提供している。現行書体の初出は春秋後期の石鼓文。部品で同義の「胃」の初出は春秋早期の金文。金文では氏族名に、また音を借りて”言う”を意味した。戦国の竹簡になると、あきらかに”~は~であると言う”の用例が見られる。詳細は論語語釈「謂」を参照。
矣(イ)


(金文)
論語の本章では、”~である”。断定の意。初出は殷代末期の金文。字形は「𠙵」”人の頭”+「大」”人の歩く姿”。背を向けて立ち去ってゆく人の姿。原義はおそらく”…し終えた”。ここから完了・断定を意味しうる。詳細は論語語釈「矣」を参照。
仁(ジン)


(甲骨文)
論語の本章では、”貴族(らしさ)”。初出は甲骨文。字形は「亻」”ひと”+「二」”敷物”で、原義は敷物に座った”貴人”。詳細は論語語釈「仁」を参照。
通説的な解釈、”なさけ・あわれみ”などの道徳的意味は、孔子没後一世紀後に現れた孟子による、「仁義」の語義であり、孔子や高弟の口から出た「仁」の語義ではない。字形や音から推定できる春秋時代の語義は、敷物に端座した”よき人”であり、”貴族”を意味する。詳細は論語における「仁」を参照。
者(シャ)


(金文)
論語の本章では”実践する者”。旧字体は〔耂〕と〔日〕の間に〔丶〕一画を伴う。新字体は「者」。ただし唐石経・清家本ともに新字体と同じく「者」と記す。現存最古の論語本である定州竹簡論語も「者」と釈文(これこれの字であると断定すること)している。初出は殷代末期の金文。金文の字形は「木」”植物”+「水」+「口」で、”この植物に水をやれ”と言うことだろうか。原義は不明。初出では称号に用いている。春秋時代までに「諸」と同様”さまざまな”、”…は”の意に用いた。漢文では人に限らず事物にも用いる。詳細は論語語釈「者」を参照。
先(セン)


(甲骨文)
論語の本章では、”先に行う”。初出は甲骨文。字形は「止」”ゆく”+「人」で、人が進む先。甲骨文では「後」と対を為して”過去”を意味し、また国名に用いた。春秋時代までの金文では、加えて”先行する”を意味した。詳細は論語語釈「先」を参照。
難(ダン/ダ)
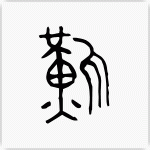

(金文)
論語の本章では”困難”。初出は西周末期の金文。「ダン」の音で”難しい”、「ダ」の音で”鬼遣らい”を意味する。「ナン」「ナ」は呉音。字形は「𦰩」”火あぶり”+「鳥」で、焼き鳥のさま。原義は”焼き鳥”。それがなぜ”難しい”・”希有”の意になったかは、音を借りた仮借と解する以外にない。西周末期の用例に「難老」があり、”長寿”を意味したことから、初出の頃から、”希有”を意味したことになる。詳細は論語語釈「難」を参照。
後(コウ)


(甲骨文)
論語の本章では”あとで”。「ゴ」は慣用音、呉音は「グ」。初出は甲骨文。その字形は彳を欠く「幺」”ひも”+「夂」”あし”。あしを縛られて歩み遅れるさま。原義は”おくれる”。甲骨文では原義に、春秋時代以前の金文では加えて”うしろ”を意味し、「後人」は”子孫”を意味した。また”終わる”を意味した。人名の用例もあるが年代不詳。詳細は論語語釈「後」を参照。
獲(カク)


(甲骨文)/「隻」(金文)
論語の本章では”得る”。初出は甲骨文。金文は戦国末期のものが初出。字形は「鳥」+「又」”手”で、鳥を捕るさま。原義は”取る”。古くは「隻」と分化していない。詳細は論語語釈「獲」を参照。
論語:付記
検証
論語の本章は前半のみが前漢中期埋蔵の定州竹簡論語に見え、それ以外は先秦両漢でばらばらに一部が収録されるのみ。
- 務民之義
- 文學曰:「民人藏於家,諸侯藏於國,天子藏於海內。故民人以垣牆為藏閉,天子以四海為匣匱。天子適諸侯,升自阼階,諸侯納管鍵,執策而聽命,示莫為主也。是以王者不畜聚,下藏於民,遠浮利,務民之義;義禮立,則民化上。若是,雖湯、武生存於世,無所容其慮。工商之事,歐冶之任,何姦之能成?三桓專魯,六卿分晉,不以鹽鐵。故權利深者,不在山海,在朝廷;一家害百家,在蕭牆,而不在朐邴也。」
はな垂れ儒者「民は家に蓄え、諸侯は領国に蓄え、天子は天下に蓄える。だから民は敷地の境に垣根を作って仕舞い込んでも当然だが、天子は天下そのものが収納箱である。
天子が諸侯の元を訪れると、自分で階段を上がって宮殿に入り、諸侯は入り口の鍵を差し出し、鞭を手に取って天子の言葉を拝聴する。そうやって自分がその場の主人でないことを表す。
だから王者は蓄えをしようとせず、蓄えは民にさせ、浮ついた投機で金儲けせず、民にとっての正義を行う。こうして正義と礼法が確立するから、民は目上を敬うことを知る。
このようであれば、旧王室を討伐した湯王武王が世に現れても、武略を用いる場面が無い。工業や商業は、名工欧冶のような者にまかせておけば、どうやって悪だくみが実現するというのか。
魯国では門閥三家老が政権を好き放題にし、晋国では六卿が国を分け取りにしたほどだが、塩や鉄を専売にして儲けようと図ったことは無い。だから利権などというものは、自然界にあるのではなく、政界官界が勝手に作り出すのだ。
欲張りな権勢家が百家から搾り取るのは、朝廷の荘厳具である屏風を背にするから出来ることで、その手先の専売商人、朐邴ごときが、勝手に出来ることではない。」(『塩鉄論』禁耕2)
- 敬鬼神而遠之
- 聖人甚重卜筮,然不疑之事,亦不問也。甚敬祭祀,非禮之祈,亦不為也。故曰:「聖人不煩卜筮」,「敬鬼神而遠之」。夫鬼神與人殊氣異務,非有事故,何奈於我?故孔子善楚昭之不祀河,而惡季氏之旅泰山。今俗人筴於卜筮,而祭非其鬼,豈不惑哉!
聖人は占いをはなはだ重んじたが、元から明らかなことは、占おうともしなかった。祭祀をはなはだ重んじたから、礼法にかなわない祈りは、そもそもやろうとしなかった。だから言う。「聖人は占いの結果に悩まない」、「鬼神は敬して遠ざく」と。
そもそも鬼神と人はなり立ちも務めも違うから、こちらからいじくり回さなければ、どうして祟ったり出来るだろうか? だから孔子は楚の昭王が淮河の神を祀らなかったのを讃えたし、季康子が泰山の祭を行ったのを忌み嫌った。
今の世で凡俗が筮竹を操って占ったり、自分に縁の無い鬼神を祀ったりすれば、どうして迷わないでいられようか!(『潜夫論』卜列4)
後半の「問仁」以降は、さっぱり文献に出てこない。事実上の初出は、後漢末から南北朝にかけて編まれた古注。だが全ての文字が論語の時代に遡れ、内容的にも孔子の教説と矛盾しないから、本章は史実と扱って構わない。
解説
論語の本章の要点は3つ。
- 為政者として民衆の要求を満たせ。
- 信仰はしてはならないが弾圧もするな。
- 仕事をしてからその報酬を得ろ。
孔子塾が庶民を入門させ貴族に相応しい技能教養を教授して成り上がらせる場であるからには、「智」(知)とは役人・政治家に必要な知識のことで、その前提が1.の民の求めを満たすことだった。これについて孔子は、弟子の子貢に別の言葉で説明している。
つまり民の要望の全てを叶えることではなく、そんなことが不可能なのを孔子はもとより承知していた。「義」とは”正しいこと”だから、「民の義」とは”民が正しいと思うこと。顔淵篇の説く三ヶ条が実践できていれば、それで民は十分”正しい”と思ってくれるというわけ。
だがそれだけでは為政者としての知識に欠けると孔子は思った。だから「鬼神を敬遠」という言葉が出て来るわけで、古代ゆえに民衆はもちろん迷信深かった。だが拝み屋の母を持つ孔子は、馬鹿げた仕草におののき恐れる民衆の姿を、やはり馬鹿馬鹿しいと思っていた。
詳細は孔子はなぜ偉大なのかを参照。
残るは3.の「仁者は先に…」だが、「仁者」を孟子以降の”情け深い教養人”と解しては全く意味が分からない。「仁」とは貴族らしさのことであり、「仁者」とは理想的な、あるいは一人前の貴族を意味する。春秋の貴族は身勝手をすると、まず天寿を全うできなかった。
詳細は論語雍也篇16余話「世襲の合理」を参照。従って公職を果たして社会の要望に応えもしないのに、利益だけ吸い取った貴族は、必ず地位を追われ、多くは殺された。そうならずにワイロ生活を楽しめるようになったのは、君子が戦士であることを止め、空理空論とポエムをいじり回す、帝国の官僚に成り下がった帝政期からである。
論語の本章、新古の注は次の通り。
古注『論語集解義疏』
…註王肅曰務所以化導民之義也…註苞氏曰敬鬼神而不瀆也…註孔安國曰先勞苦乃後得功此所以為仁也
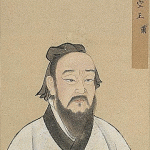

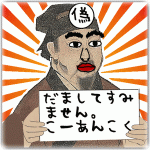
注釈。王粛「民の義を行うとは、民を正義に導くための教育に努力することである。」
注釈。包咸「敬遠とは、鬼神を敬いつつもバカにしないことである。」
注釈。孔安国「まず苦労してその後で報酬を貰うのが、仁と呼ばれる理由になる。」
新注『論語集注』
知、遠,皆去聲。民,亦人也。獲,謂得也。專用力於人道之所宜,而不惑於鬼神之不可知,知者之事也。先其事之所難,而後其效之所得,仁者之心也。此必因樊遲之失而告之。

知も遠も、皆な尻下がりに読む。民とは人のことである。獲とは、報酬を貰うことである。人の道がよいと評価することにひたすら力を尽くし、鬼神の正体不明な話には耳を貸さないのが、知者のあるべき姿である。まず困難な仕事に携わってから、その功績に従って報酬を得るのが、仁者の心である。このお説教は、樊遅がそうできていないから教え諭したに違いない。
程子曰:「人多信鬼神,惑也。而不信者又不能敬,能敬能遠,可謂知矣。」又曰:「先難,克己也。以所難為先,而不計所獲,仁也。」呂氏曰:「當務為急,不求所難知;力行所知,不憚所難為。」


程頤「すぐに鬼神を真に受けること、それを惑という。だがまるで信じない者は敬うこともできないから、よく敬いつつもよく遠ざける、これが出来るのを知という。」「先難とは、自分を抑制しきることだ、その困難な抑制をやってみせて、そのつもりが無いのに報酬を貰うのが、仁である。」
呂大臨「差し迫った仕事に励み、知り難いことは突き詰めず、知りうることに注力し、難しいことから逃げない。」
なお以下は、話の前提として、論語における君子を参照されたい。
文字史的にも内容的にも、史実の孔子の発言であることを疑えない論語の本章だが、疑問点が無いではない。まず樊遅は孔子が帰国する寸前に、上記の通り対斉防衛戦で武勲を揚げた。その際魯国の筆頭家老だった季康子に、「まだ子供だから無理なんじゃないか」と言われた。
それでも兄弟子の冉有が「これも運命です」と季康子に言って、樊遅は車上でほこを執って戦ったのだが、「子供」がすでに孔子の弟子だったかが疑問に思える。樊遅は『史記』によれば孔子より36年少、『孔子家語』によれば46年少というが、まるまる信用できるわけではない。
もし戦役の時点で樊遅が孔子の弟子ではなかったとしたら、もとからの貴族だったと考えるべき。武芸の稽古に明け暮れる暇のない庶民が、当時の武芸を身につけ得たとは考えがたいからだ。戦役の直後孔子は帰国するが、冉有との縁でその時入門したのが真相ではないか。
つまり樊遅はすでに士分だったが、改めて貴族としての心得を問うたことになる。
余話
孔子が弟子の中でもとりわけ幼い樊遅に、「鬼神」への「敬遠」を説教したには上記の通り理由がある。鬼神なぞおらん、と確信していた超人孔子に対し、そこは凡俗だった樊遅や、こんにちの凡俗の一人である訳者ごときは、信じて損なモノを信じてしまうからだ。
人の行動原則は自我=我欲に他ならず、若いとは経験可能性の絶対的少なさを意味もするから、我欲を満たしてくれそうなものに対し、若者はついつい頼ってしまいやすい。鬼神もその一つで、居もしない神サマを拝むのはアホしい、と思いきれるにはそれなりに経験が要る。
もちろん年食ったからと言って、誰もが賢くなるわけではない。だから経験可能性なのだ。
日本にはDK世代というわかりやすい例(論語子罕篇23余話)があるから誰の目にも明らかなのだが、年齢と共に兇暴と傲慢が膨らむばかりで、あまつさえ大して掛け金も払わなかった社会保障を図々しく食い潰して、同国人を苦しめることしか出来ない動物も人界には存在し得る。
頭が悪い上に痴呆も加わっているから、新興宗教のいい食い物だったりもする(論語述而篇19余話)。つまり馬齢しか重ねず鬼神を敬うかどうかは別にして遠ざけないどころか、我から好んで近づけているわけで、かような生き物には説教好きな孔子にも説教の法が無かった。
なり果てた猛獣は、もうどうしようもないから全力で関わらないでおくしかないが、まだ先がある人にとっては、この先の自分を救う必要がある。これにつき孔子の教説はこんにちの通説とはぜんぜん異なり、抽象的な道徳を全く説かず、生存のための技能と教養に限られていた。
それは当時は六芸だった。すなわち礼(貴族の社会常識)・楽(音楽と詩歌)・射(弓術)・御(戦車操縦術)・書(言語と歴史)・数(算術)だった。このうち数だけは、こんにちでもなお人類の必須技能であり続けている。それ以外に何を学ぶべきかは、人によってさまざまだろう。
だが論語ばなしとして着目すべきは、「抽象的でない」という六芸の共通点で、「それを描けなければ、それを知る事は出来ない」とアインシュタインが言ったらしい。つまり抽象的とは分かっていないことを意味し、それは時に、ありもしない勝手な妄想の結果だったりする。
儒者は空理空論をいじくり回して、無慮二千年間人々を奴隷化した。DK世代が担ぎ回ったred主義は、抽象的→無闇に難しい言葉遣いをするくせに、人類を何ら救わなかった(論語公冶長篇15余話)。分かった振りして抽象を説くのは、自他の不幸しか生み出さない。
前世紀以来、人類にとって科学を理解することは我欲の達成にものすごく重要な事だと思われるようになったが、科学も向き不向きで、誰もが分かるとは限らない。そこに付け込んで科学らしさを臭わせて、人を食い物にする悪党も出た。そういう教説をオカルトという。
中途半端に生物学をかじった者が、人間は遺伝子の情報量が多いから偉いのだ、と嬉しそうに語るのを聞いたことがある。実はゲノムの規模は人間より小麦の方が大きいらしいから、人間は小麦を拝まねばならないことになる。知識も他人に威張るために学んでは価値が無い。
そうでなくありのままに見ること。困難ではあるが、我を救うには必須の技能と訳者は思う。

…ありがたいには違いないが、家畜化されているのかも。





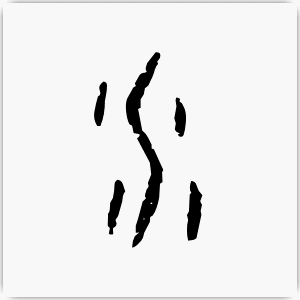
コメント