論語:原文・書き下し
原文(唐開成石経)
子曰文莫吾猶人也躬行君子則吾未之有得
校訂
東洋文庫蔵清家本
子曰文莫吾猶人也/躬行君子則吾未之有得也
後漢熹平石経
(なし)
定州竹簡論語
……曰:「文幕a,吾猶人也,躬b君子,則吾未之有得也c。」182
- 幕、今本作「莫」、二字通。
- 今本「躬」下有「行」字。
- 也、阮本無、皇本・高麗本「得」下有「也」字。
※「高麗本」は正平本の誤り。
標点文
子曰、「文幕吾猶人也。躬君子、則吾未之有得也。」
復元白文(論語時代での表記)


















※幕→莫・躬→身。論語の本章は、「猶」「行」「未」の用法に疑問がある。ただし定州竹簡論語では「行」を欠く。
書き下し
子曰く、文り幕すは吾猶ほ人のごとき也。躬ら君子たるは、則ち吾未だ之を得る有らざる也。
論語:現代日本語訳
逐語訳

先生が言った。「うわべを取り繕い、正体を隠すのは私も人並みだなあ。この身で貴族らしく振る舞うことは、全くまだ出来るようになっていないなあ。」
意訳

人並みに他人をたぶらかしはする。それをしなくて良いような、貴族らしくはまだなっていない。
従来訳
先師がいわれた。――
「典籍の研究は、私も人なみに出来ると思う。しかし、君子の行を実践することは、まだなかなかだ。」下村湖人『現代訳論語』
現代中国での解釈例
孔子說:「在理論知識方面,我還過得去;在品德修養方面,我卻做得不夠好。」
孔子が言った。「理論や知識については、私はよく分かっているが、人格修養では、私は今なお十分ではない。」
論語:語釈
子曰(シエツ)(し、いわく)

論語の本章では”孔子先生が言った”。「子」は貴族や知識人に対する敬称で、論語では多くの場合孔子を指す。「子」は赤ん坊の象形、「曰」は口から息が出て来るさま。「子」も「曰」も、共に初出は甲骨文。辞書的には論語語釈「子」・論語語釈「曰」を参照。
この二文字を、「し、のたまわく」と読み下す例がある。「言う」→「のたまう」の敬語化だが、漢語の「曰」に敬語の要素は無い。古来、論語業者が世間からお金をむしるためのハッタリで、現在の論語読者が従うべき理由はないだろう。
文莫(ブンバク)→文幕(ブンバク)
論語の本章では、”うわべを飾ってごまかす”。論語の本章は、文字史的に後世の創作を疑えないので、孔子の生きた春秋時代の語義で解釈しないと、誤読することになる。
孔子は拝み屋の母の子に生まれただけあって、宗教や占いの馬鹿げた仕草に一般人がどれほど怯えるか知っており、地方都市の代官も、宰相代行も務めたから、政治の手段としてのハッタリが、民を躾けるのに極めて有効であることを知っていた。

諸君は貴族を目指すのであるから、迷信に惑わされてはならない。天命を占ったところで、信じるに足りる理由は何もない。他人を納得させるために占いの真似を見せはしても、自分が信じてどうする。(論語衛霊公篇37)


(甲骨文)
「文」は”かざる”。初出は甲骨文。「モン」は呉音。原義は”入れ墨”で、甲骨文や金文では地名・人名の他、”美しい”の例があるが、”文章”の用例は戦国時代の竹簡から。詳細は論語語釈「文」を参照。
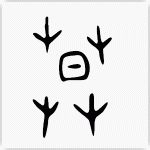

(甲骨文)
「莫」は”隠す”。初出は甲骨文。漢音「ボ」で”暮れる”、「バク」で”無い”・”かくす”を示す。字形は「茻」”くさはら”+「日」で、平原に日が沈むさま。原義は”暮れる”。甲骨文では原義のほか地名に、金文では人名、”墓”・”ない”の意に、戦国の金文では原義のほか”ない”の意に、官職名に用いた。詳細は論語語釈「莫」を参照。
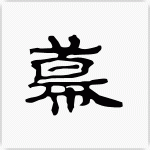

(前漢隷書)
定州竹簡論語では「幕」と記す。初出は戦国の竹簡。ただし西周中期の金文に「![]() 」を「幕」と釈文した例がある。字形は「莫」”かくす”+「巾」”ぬの”。布で作った覆い。春秋末期までに、”まく”の意に用いた。詳細は論語語釈「幕」を参照。
」を「幕」と釈文した例がある。字形は「莫」”かくす”+「巾」”ぬの”。布で作った覆い。春秋末期までに、”まく”の意に用いた。詳細は論語語釈「幕」を参照。
この部分は伝統的には「文は吾れ人の猶(ごと)くなること莫(な)からんや」と読み、従来訳”典籍の研究は、私も人なみに出来ると思う”のように訳する。論語の解説本の中では藤堂本によると「文莫」=勉慕であり、”つとめ求めること”。北中国の方言だという。この説はおそらく下掲晋・欒肇の『論語駁』に拠る。
| 字 | 藤堂上古音 | カールグレン上古音 | 語釈 | 原義 | 呉音 | 初出 |
| 文 | mɪuən(平) | mi̯wən(平) | 論語語釈「文」 | 入れ墨 | モン | 甲骨文 |
| 勉 | mɪuən(上) | mi̯an(上) | 論語語釈「勉」 | 努める | メン | 戦国金文 |
| 莫 | mag(去)「暮」と同 | 不明 | 論語語釈「莫」 | 暮れる | モ | 甲骨文 |
| mak(入)「幕」と同 | 〃 | 隠す | マク | |||
| 慕 | mag(去) | mɑɡ(去) | 論語語釈「慕」 | たくらむ | モ | 西周金文 |
武内本には、「忞慔の仮借黽勉と同意」とある。「忞慔」「黽勉」は”努力する”。『字通』には”勉強”とある。『大漢和辞典』の語釈は以下の通り。
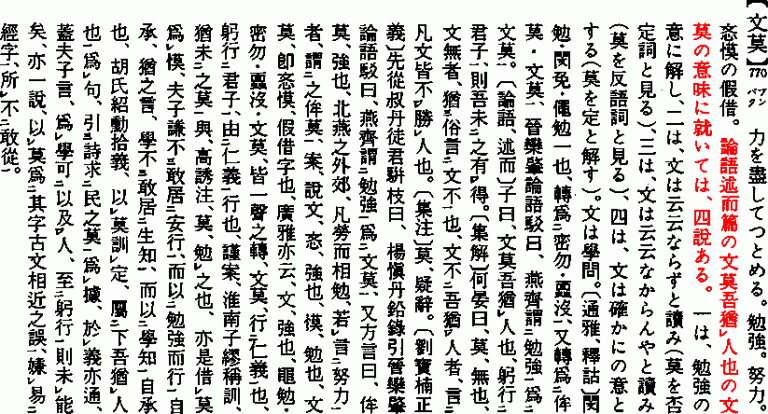
「国学大師」は次のように言う。
犹黾勉。努力。文,通“忞”。《通雅·释诂》:“闵勉、闵免、勉,一也,转为密勿、蠠没,又转为侔莫、文莫。……栾肇《论语驳》曰:燕齐谓勉强为文莫。
”新しいことを学ぶ。努力。「文」は「忞」”努める”に通じる。『通雅』(明・方以智撰)の釋詁に「閔勉、閔免、僶勉は同義である。密勿”勤勉に努力する”、蠠沒”努め励む”もまた、書き換えて侔莫、文莫と記す」とある。晋・欒肇の『論語駁』に、「燕や斉では努力を文莫という」とある。
いずれも論語の時代よりはるかな後世の儒者が、根拠無き個人的感想を言ったのに基づいており、儒者は一人残らず孔子聖者説の信者だから、狂信者の妄言や商売人の客寄せ言葉と同じで、信用できる解釈ではない。論語雍也篇9余話「漢文の本質的虚偽」を参照。
吾(ゴ)


(甲骨文)
論語の本章では”わたし”。初出は甲骨文。字形は「五」+「口」で、原義は『学研漢和大字典』によると「語の原字」というがはっきりしない。一人称代名詞に使うのは音を借りた仮借だとされる。詳細は論語語釈「吾」を参照。
春秋時代までは中国語にも格変化があり、一人称では「吾」を主格と所有格に用い、「我」を所有格と目的格に用いた。しかし論語でその文法が崩れ、「我」と「吾」が区別されなくなっている章があるのは、後世の創作が多数含まれているため。
猶(ユウ)
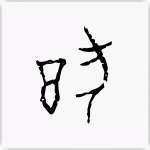

(甲骨文)
論語の本章では、”まるで…のようだ”。この語義は春秋時代では確認できない。初出は甲骨文。字形は「酉」”酒壺”+「犬」”犠牲獣のいぬ”で、「猷」は異体字。おそらく原義は祭祀の一種だったと思われる。甲骨文では国名・人名に用い、春秋時代の金文では”はかりごとをする”の意に用いた。戦国の金文では、”まるで…のようだ”の意に用いた。詳細は論語語釈「猶」を参照。
人(ジン)


(甲骨文)
論語の本章では”他人”。初出は甲骨文。原義は人の横姿。「ニン」は呉音。甲骨文・金文では、人一般を意味するほかに、”奴隷”を意味しうる。対して「大」「夫」などの人間の正面形には、下級の意味を含む用例は見られない。詳細は論語語釈「人」を参照。
也(ヤ)


(金文)
論語の本章では、「かな」と読んで詠歎の意。初出は事実上春秋時代の金文。字形は口から強く語気を放つさまで、原義は”…こそは”。春秋末期までに句中で主格の強調、句末で詠歎、疑問や反語に用いたが、断定の意が明瞭に確認できるのは、戦国時代末期の金文からで、論語の時代には存在しない。詳細は論語語釈「也」を参照。
躬*(キュウ)

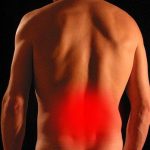
(楚系戦国文字)
論語の本章では”自らする”。この文字の初出は戦国文字で、論語の時代に存在しない。論語時代の置換候補は部品の「身」。字形は「身」+「呂」”背骨”で、原義は”からだ”。詳細は論語語釈「躬」を参照。
行(コウ)


(甲骨文)
論語の本章では”行う”。この語義は春秋時代では確認できない。初出は甲骨文。「ギョウ」は呉音。十字路を描いたもので、真ん中に「人」を加えると「道」の字になる。甲骨文や春秋時代の金文までは、”みち”・”ゆく”の語義で、”おこなう”の語義が見られるのは戦国末期から。詳細は論語語釈「行」を参照。
論語の本章、定州竹簡論語ではこの字を欠いている。
君子(クンシ)


論語の本章では、”貴族”。後世広まった、”地位も教養もある立派な人”という語義は、孔子没後一世紀に現れた孟子が提唱した「仁義」を実践する者の語義で、原義とは異なる。本章は文字史的に後世の偽作を疑えないので、原義で解釈しなければならない。
孔子の生前、「君子」とは従軍の義務がある代わりに参政権のある、士族以上の貴族を指した。「小人」とはその対で、従軍の義務が無い代わりに参政権が無かった。詳細は論語における「君子」を参照。また春秋時代の身分については、春秋時代の身分秩序と、国野制も参照。
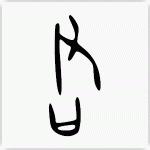

「君」(甲骨文)
「君」の初出は甲骨文。甲骨文の字形は「丨」”通路”+「又」”手”+「𠙵」”くち”で、人間の言うことを天界と取り持つ聖職者。「尹」に「𠙵」を加えた字形。甲骨文の用例は欠損が多く判読しがたいが、称号の一つだったと思われる。「先秦甲金文簡牘詞彙資料庫」は、春秋末期までの用例を全て人名・官職名・称号に分類している。甲骨文での語義は明瞭でないが、おそらく”諸侯”の意で用い、金文では”重臣”、”君臨する”、戦国の金文では”諸侯”の意で用いた。また地名・人名、敬称に用いた。詳細は論語語釈「君」を参照。
則(ソク)


(甲骨文)
論語の本章では、”~については”。初出は甲骨文。字形は「鼎」”三本脚の青銅器”と「人」の組み合わせで、大きな青銅器の銘文に人が恐れ入るさま。原義は”法律”。論語の時代=金文の時代までに、”法”・”則る”・”刻む”の意と、「すなわち」と読む接続詞の用法が見える。詳細は論語語釈「則」を参照。
未(ビ)


(甲骨文)
論語の本章では”まだ…ない”。この語義は春秋時代では確認できない。初出は甲骨文。「ミ」は呉音。字形は枝の繁った樹木で、原義は”繁る”。ただしこの語義は漢文にほとんど見られず、もっぱら音を借りて否定辞として用いられ、「いまだ…ず」と読む再読文字。ただしその語義が現れるのは戦国時代まで時代が下る。詳細は論語語釈「未」を参照。
之(シ)


(甲骨文)
論語の本章では”それ”。初出は甲骨文。字形は”足”+「一」”地面”で、あしを止めたところ。原義はつま先でつ突くような、”まさにこれ”。殷代末期から”ゆく”の語義を持った可能性があり、春秋末期までに”~の”の語義を獲得した。詳細は論語語釈「之」を参照。
有(ユウ)


(甲骨文)
論語の本章では”身につける”。初出は甲骨文。ただし字形は「月」を欠く「㞢」または「又」。字形はいずれも”手”の象形。原義は両腕で抱え持つこと。詳細は論語語釈「有」を参照。
得(トク)


(甲骨文)
論語の本章では”手に入れる”→”身につける”。初出は甲骨文。甲骨文に、すでに「彳」”みち”が加わった字形がある。字形は「貝」”タカラガイ”+「又」”手”で、原義は宝物を得ること。詳細は論語語釈「得」を参照。
躬君子、則吾未之有得也
「躬君子」が主部、「則吾未之有得也」が述部でしかあり得ない。すると「躬君子」は”自分で貴族になること”の意で、「躬」に”自分で…する”の語釈を『大漢和辞典』が載せる。直訳すれば「躬君子」は”自分で君子を実行する”。つまり、君子=貴族らしく振る舞うこと。
「則吾未之有得」を「未だ之を得る有らず」と訓んだのは、「否定辞+目的語代名詞+述語動詞」の古い形だから。「之」は「有得」の主語ではなく、目的語である。この点から、本章は古い中国語の形を残しており、史実である可能性は高い。
論語:付記
検証
論語の本章は、春秋戦国時代を含めた先秦両漢に引用や再録が無い。「文莫」の使用例が前漢中期の『塩鉄論』に見えるのみ。
大夫曰:「至美素璞,物莫能飾也。至賢保真,偽文莫能增也。故金玉不琢,美珠不畫。」
大臣が言った。「透き通った宝石は、飾り立てるにもそれ用の物が無い。飛び抜けた賢者はうそ偽りを言わないから、演技で努力してももっと賢く見えるわけが無い。だから混じりけの無い黄金や宝石は磨かず、美しい真珠は刻み目を付けない。」(『塩鉄論』殊路3)
だが文字史的に全て論語の時代に遡れるので、史実の孔子の発言として扱ってよい。
解説
論語の本章、新古の注は次の通り。
古注『論語集解義疏』
子曰文莫吾猶人也註莫無也文無者猶俗言文不也文不吾猶人者言凡文皆不勝於人也躬行君子則吾未之有得也註孔安國曰躬為君子行己未能得之也疏子曰至得也 云文莫吾猶人也者孔子謙也文文章也莫無也無猶不也孔子言我之文章不勝於人故曰吾猶人也云躬行君子則吾未之有得也者又謙也躬身也言我文既不勝人故身自行君子之行者則吾亦未得也 註文無者猶俗言文不也 何云俗云文不當是于時呼文不勝人為文不也

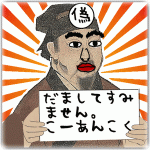
本文「子曰文莫吾猶人也」。
注釈。莫は無である。文無は、俗な言葉で言う文不と同じである。「文不吾猶人」とは、なべて文とは全て人より優れない事を言う。
本文躬行君子則吾未之有得也」。
注釈。孔安国「自分で君子になることが、まだ出来ないと言っている。」

付け足し。先生は得ることの極致を言った。「文莫吾猶人也」とは、孔子の謙遜である。文とは文章である。莫とは無である。無とは不のようなものだ。孔子は”私の文章は人より不出来だ”と言った。だから「吾猶人也」と言った。「躬行君子則吾未之有得也」とは、これも謙遜である。躬とは身である。”私の文章は人より不出来だから、君子らしく振る舞うこともまだ出来ない”と言ったのである。
注釈。文無とは俗な言葉で言う文不である。
何晏「俗に文不と言うのは、つまり当時人より文章が優れないのを”文不”と言ったのである。」
新注『論語集注』
莫,疑辭。猶人,言不能過人,而尚可以及人。未之有得,則全未有得,皆自謙之辭。而足以見言行之難易緩急,欲人之勉其實也。謝氏曰「文雖聖人無不*與人同,故不遜;能躬行君子,斯可以入聖,故不居;猶言君子道者三我無能焉。」


莫とは疑問詞である。「猶人」とは、人より優れることが出来ないが、人並みではある、の意である。「未之有得」とは、つまり全く出来ないの意だが、これらは全部謙遜である。このことから、言行の難しさと緩やかに言うことの容易さを見て取れる。このように言って、人に言行の裏付けに努めるよう願ったのである。
謝良佐「文章について聖人は人と同程度ではなかったから、あえて譲らなかった。だが君子を実践できるなら、それはもう聖人の境地だ。だからその境地に居ないと思い、”君子の三つの道が出来ていない”(論語憲問篇30)と言ったのである。」
※無不:不の誤りとして読まないと文意が通じない。
余話
騒がしい中国語
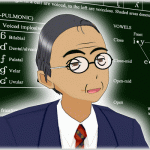
論語の本章の解釈では従わなかったが、藤堂博士は音から漢字学を究めた人だけあって、所説に説得力がある。藤堂博士の言い分が仮に正しいなら、孔子が普段地元の方言で授業を行っていた証拠になる。
ご存じかも知れないが、中国語は方言の違いが甚だしく、北京から100km強離れただけの天津に行くと、もう言葉が通じない。現代日本人が中国語を聞くと、「チャ・チ・チュ・チェ・チョ」が多くて時に滑稽に聞こえるが、これは清朝の時代に満州語が入った影響だという。
それでも生粋の北京人が話す北京語(北京官話)は、耳で聞いた音が音楽のようでなるほど美しく、清末の政治家・康有為が、大幅な社会改革を唱えながら、中国語に関してのみ、「音の妙なるものあり」と言って(『大同書』)、北京官話にこだわったのもうなづける。

孔子は自分の話す華北方言をどう思ったのだろうか。魯国は文化的には由緒正しい国だから、劣等感は持たなかっただろう。ただし古典文化をあこがれるように眺めた孔子にとっては、講義の解説は地元の言葉で言っても、古典の読みは古語だったと論語述而篇17に記されている。
するといわゆる標準語にあこがれたのだろうか。それとも、中国全土からやって来た弟子たちに教えるには、方言の違いを乗り越えた標準語が必要だったのだろうか。日本の江戸時代、まるで言葉が通じない薩摩と津軽の藩士は、謡曲の言葉で語ったと司馬遼太郎が書いている。
その元ネタはたぶん春台先生だが、とあれ標準語へのあこがれは、中国人も同様だった。
有兄弟徑商者。學得一二官語。將到家。兄因如廁。暫留隔河。命弟先往見父。々一見問曰。汝兄何在。弟曰。撒屎。父驚曰。何䖏![]() 死。荅曰。河南。父方哀苦。而兄適至。父遂罵其次子曰。汝何妄言如是。曰。我官話耳。父曰。如此官話。只好嚇你爺。
死。荅曰。河南。父方哀苦。而兄適至。父遂罵其次子曰。汝何妄言如是。曰。我官話耳。父曰。如此官話。只好嚇你爺。

兄弟で行商をしている者がいた。出稼ぎ先ですこし標準語をかじり、家に帰って自慢しようとしたのだが、兄は急に腹具合が悪くなって、川岸にしゃがんだ。先に家に帰った弟が、父に帰りの挨拶をしていると、父は兄はどこだと聞いた。
弟「撒屎(サースー:大きいのをしにいきました)。」
父「殺死(サースー:殺されたって)! どこでじゃ。」
弟「河南(ホーナン:川の南岸です)。」
父「河南(ホーナン:河南省じゃと)!」
そんな異境の地で哀れな、と父がシクシク泣いていると、兄がさっぱりした顔で帰ってきた。父は真っ赤になって弟を怒鳴りつけて言った。
「このウソツキめが! お前の標準語など、わしを怒らせるタネにしかならぬわ!」
論語時代の中国にも、きっと似たようなけしきがあっただろう。
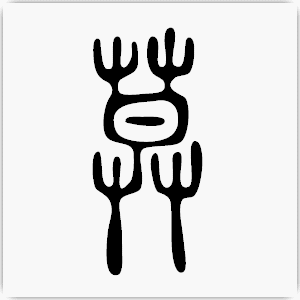




コメント