論語:原文・書き下し
原文(唐開成石経)
子曰爲政以德譬如北辰居其所而衆星共之
校訂
東洋文庫蔵清家本
子曰爲政以德譬如北辰居其所而衆星共之
後漢熹平石経
(なし)
定州竹簡論語
子曰:「為正a以德,辟b如北辰,2……
- 正、今本作「政」。正・政可通、古多以政為正。以下同。
- 辟、阮本、皇本均作「譬」。辟借為譬。
標点文
子曰、「爲正以德。辟如北辰。居其所而、衆星共之。」
復元白文(論語時代での表記)


















※論語の本章は、「辟」「如」「辰」「其」の用法に疑問がある。
書き下し
子曰く、正を爲ふるに德を以ふ。辟へば北辰の如し。其の所に居而、衆星之を共ぐ。
論語:現代日本語訳
逐語訳
先生が言った。政治を思い通りに行うには利益(誘導)を用いる。例えば北斗星のようだ。その場にいて、他の全ての星がそれを仰ぎ見る。

意訳
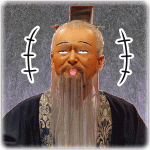

政治のかなめは利益誘導だ。かねのキンキラキンを見たら、誰だって同じ表情になるだろ?
従来訳
先師がいわれた。――
「徳によつて政治を行えば、民は自然に帰服する。それは恰も北極星がその不動の座に居て、もろもろの星がそれを中心に一絲みだれず運行するようなものである。」下村湖人『現代訳論語』
現代中国での解釈例
孔子說:「管理國家要以身做則。如同北極星,安然不動而衆星繞之。」
孔子が言った。「国家を支配するには我が身を〔民の〕模範としなければならない。北極星と同様に、じっと動かずにいて、他の全ての星がそれをとりまく。」
論語:語釈
子曰(シエツ)(し、いわく)

論語の本章では”孔子先生が言った”。「子」は貴族や知識人に対する敬称で、論語では多くの場合孔子を指す。「子」は赤ん坊の象形、「曰」は口から息が出て来るさま。「子」も「曰」も、共に初出は甲骨文。辞書的には論語語釈「子」・論語語釈「曰」を参照。
この二文字を、「し、のたまわく」と読み下す例がある。「言う」→「のたまう」の敬語化だが、漢語の「曰」に敬語の要素は無い。古来、論語業者が世間からお金をむしるためのハッタリで、現在の論語読者が従うべき理由はないだろう。
爲(イ)
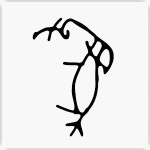

(甲骨文)
論語の本章では”思い通りに動かす”。新字体は「為」。字形は象を調教するさま。甲骨文の段階で、”ある”や人名を、金文の段階で”作る”・”する”・”~になる”を意味した。詳細は論語語釈「為」を参照。
政(セイ)→正(セイ)

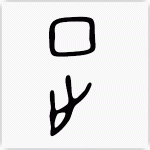
「政」(甲骨文)/「正」(甲骨文)
論語の本章では”政治”。初出は甲骨文。ただし字形は「足」+「丨」”筋道”+「又」”手”。人の行き来する道を制限するさま。現行字体の初出は西周早期の金文で、目標を定めいきさつを記すさま。原義は”兵站の管理”。論語の時代までに、”征伐”、”政治”の語義が確認できる。詳細は論語語釈「政」を参照。
定州竹簡論語では「正」と記す。初出は甲骨文。字形は「囗」”城塞都市”+そこへ向かう「足」で、原義は”遠征”。甲骨文では「正月」をすでに年始の月とした。また地名・祭礼名にも用いた。金文では、”征伐”・”年始”のほか、”長官”、”審査”の意に用いた。”正直”の意は戦国時代の竹簡からで、同時期に「征」”徴税”の字が派生した。詳細は論語語釈「正」を参照。
前漢宣帝期の定州竹簡論語が「正」と記した理由は、恐らく前王朝・秦の始皇帝のいみ名「政」を避けたため(避諱)。前漢帝室の公式見解では、漢帝国は秦帝国に反乱を起こして取って代わったのではなく、秦帝国の正統な後継者と位置づけていた。
だから前漢の役人である司馬遷は、高祖劉邦と天下を争った項羽を本紀に記し、あえて正式の中華皇帝として扱った。項羽の残虐伝説が『史記』に記され、劉邦の正当性を訴えたのはそれゆえだ。そう書かなければ司馬遷は、ナニだけでなくリアルに首までちょん切られた。
以(イ)


(甲骨文)
論語の本章では”用いる”。初出は甲骨文。人が手に道具を持った象形。原義は”手に持つ”。論語の時代までに、名詞(人名)、動詞”用いる”、接続詞”そして”の語義があったが、前置詞”~で”に用いる例は確認できない。ただしほとんどの前置詞の例は、”用いる”と動詞に解せば春秋時代の不在を回避できる。詳細は論語語釈「以」を参照。
德(トク)


(甲骨文)
論語の本章では”利益”・”利権”。ゆえに訓読は「かひ」。新字体は「徳」。初出は甲骨文。甲骨文の字形は、〔行〕”みち”+〔丨〕”進む”+〔目〕であり、見張りながら道を進むこと。甲骨文では”進む”として用いられており、金文になると”道徳”と解せなくもない用例が出るが、その解釈には根拠が無い。前後の漢帝国時代の漢語もそれを反映して、サンスクリット語puṇyaを「功徳」”行動によって得られる利益”と訳した。詳細は論語語釈「徳」を参照。
孔子の生前では、”道徳”を意味しない。権力や人生経験や技能教養に裏打ちされた、隠然とした人格的圧力=人間の機能。武力もその背景となる。さらに人格から進んで、政治力や現世的利益「得」をも意味する。詳細は論語における「徳」を参照。
従来訳や既存の論語本が言うような、人徳や道徳では全くない。そんなものに民は従いはしない。実際に魯国の宰相格だった孔子にも、そんなことは重々分かっている。論語に言う「徳」は多くの場合、「得」で書き換えると理解しやすい。実際、前漢宣帝期の定州竹簡論語では「徳」を「得」と書いている箇所がある。
譬(ヒ)→辟(ヘキ)


(篆書)
論語の本章では”たとえる”。初出は後漢の『説文解字』。字形は「言」+「辟」”王の側仕え”で、”たとえる”の語義は戦国時代以降に音を借りた仮借。『大漢和辞典』で音ヒ訓たとえるは「譬」のみ。日本語音で近音かつ類似語に「比」”ならべる・くらべる・たぐい”。詳細は論語語釈「譬」を参照。
定州竹簡論語「辟」の初出は甲骨文。”たとえる”の語義は春秋時代では確認できない。字形は「卩」”うずくまった奴隷”+「口」”さしず”+「辛」”針または小刀で入れる入れ墨”で、甲骨文では「口」を欠くものがある。原義は指図に従う奴隷で、王の側仕え。甲骨文では原義のほか人名に用い、金文では論語の時代までに、”君主”、”長官”、”法則”、”君主への奉仕”の用例がある。”たとえる”の語義は戦国時代以降に音を借りた仮借。詳細は論語語釈「辟」を参照。
如(ジョ)
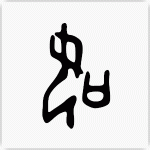

甲骨文
論語の本章では”~のようである”。この語義は春秋時代では確認できない。初出は甲骨文。甲骨文の字形は「女」+「𠙵」”くち”で、”ゆく”の意と解されている。春秋末期までの金文には、「女」で「如」を示した例しか無く、語義も”ゆく”と解されている。詳細は論語語釈「如」を参照。
北辰(ホクシン)


(甲骨文)
論語の本章では”北極星”。
『学研漢和大字典』によると、白居易の詩に「北辰微暗少光色=北辰微暗にして光色少なし」〔司天台〕というのがある。転じて、天子や朝廷の不動の地位のこと。北極星の位置が変わらず天の中心とされたことから。「北極朝廷終不改=北極の朝廷終に改まらず」〔杜甫・登楼〕

旧制第七高等学校(現・鹿児島大学)造士館寮歌に、「北辰斜めにさすところ」とあるのは、緯度が低いため北極星が低く見えることを歌ったもの。
「北」の初出は甲骨文。字形は互いに背を向けた二人の「人」で、原義は”背中”。「背」の初出は後漢の隷書で、用例はないものの、それまで”せなか”の語義を保持したと思われる。古代中国では北を正面とし、天子が北を背にして座ることから、方角の”きた”の派生義が生まれた。金文では国名にも用いられた。それ以外の語義は漢代以降まで時代が下る。詳細は論語語釈「北」を参照。
「辰」の初出は甲骨文。”北斗星”の語義は春秋時代では確認できない。甲骨文の字形は人が死神のような大ガマを持った姿で、原義は”刈り取り”。その語義には後世「耨」を用いた。甲骨文では地名や国名に、金文では十二支の五番目や日時の表記に、また氏族名・人名に用いた。詳細は論語語釈「辰」を参照。
居(キョ)


(金文)
論語の本章では”位置する”。初出は春秋時代の金文。字形は横向きに座った”人”+「古」で、金文以降の「古」は”ふるい”を意味する。全体で古くからその場に座ること。詳細は論語語釈「居」を参照。
其(キ)


(甲骨文)
論語の本章では”その”という指示詞。初出は甲骨文。甲骨文の字形は「𠀠」”かご”。かごに盛った、それと指させる事物の意。金文から下に「二」”折敷”または「丌」”机”・”祭壇”を加えた。人称代名詞に用いた例は、殷代末期から、指示代名詞に用いた例は、戦国中期からになる。詳細は論語語釈「其」を参照。
所(ソ)


(金文)
論語の本章では”場所”。初出は春秋末期の金文。「ショ」は呉音。字形は「戸」+「斤」”おの”。「斤」は家父長権の象徴で、原義は”一家(の居所)”。論語の時代までの金文では”ところ”の意があるが、「…するところの…」の用法は、戦国時代まで時代が下る。詳細は論語語釈「所」を参照。
而(ジ)


(甲骨文)
論語の本章では”そして”。初出は甲骨文。原義は”あごひげ”とされるが用例が確認できない。甲骨文から”~と”を意味し、金文になると、二人称や”そして”の意に用いた。英語のandに当たるが、「A而B」は、AとBが分かちがたく一体となっている事を意味し、単なる時間の前後や類似を意味しない。詳細は論語語釈「而」を参照。
眾(シュウ)
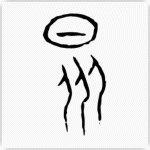

(甲骨文)
論語の本章では”多くの”。「眾」「衆」は異体字。初出は甲骨文。字形は「囗」”都市国家”、または「日」+「人」三つ。都市国家や太陽神を祭る神殿に隷属した人々を意味する。論語の時代では、”人々一般”・”多くの”を意味した可能性がある。詳細は論語語釈「衆」を参照。
星(セイ)


(甲骨文)
論語の本章では夜空に輝く”ほし”。初出は甲骨文。字形は「晶」”三つ星”+「生」で、原義は”ほし”。「生」が加わった理由は不明だが、「晶」と何らかの意味の違いがあったと思われる。甲骨文では原義のほか”晴れる”、金文では加えて人名に用いられ、戦国の竹簡で”なまぐさい”を意味した。詳細は論語語釈「星」を参照。
共(キョウ)


(甲骨文)
論語の本章では”同じくする”→”一斉にその方向を見る”。初出は甲骨文。字形は「又」”手”二つ=両手+「口」。原義は”両手でものを捧げ持つさま”。派生義として”敬う”。「供」の原字。論語の時代までに”謹んで従う”の用例があり、「恭」を「共」と記している。また西周の金文に、”ともに”と読み得る例がある。詳細は論語語釈「共」を参照。
武内本に「共は向と同音仮借、めぐるとよむ」とあるが、今回は中心点を”共にする”と解した。「向」にも”顔をまともに向けて従う”の語義があるから、無理に”めぐる”と解する必要は無いだろう。論語語釈「向」を参照。
日本伝承の古注本は、清家本・正平本までは「共」と記すが、本願寺坊主の手に成る文明本は「供」と書き換え、以降の足利本・根本本・懐徳堂本は文明本に従う。中国伝承本はもちろん坊主の勝手など知らぬので、「共」のまま。文明本は他の箇所でも同じ様な改竄を行っており、善本とは言えない。論語の伝承について詳細は論語の成立過程まとめを参照。
原始論語?…→定州竹簡論語→白虎通義→ ┌(中国)─唐石経─論語注疏─論語集注─(古注滅ぶ)→ →漢石経─古注─経典釈文─┤ ↓↓↓↓↓↓↓さまざまな影響↓↓↓↓↓↓↓ ・慶大本 └(日本)─清家本─正平本─文明本─足利本─根本本→ →(中国)─(古注逆輸入)─論語正義─────→(現在) →(日本)─────────────懐徳堂本→(現在)
論語の本章では、「拱」は”仰ぎ見る”の意。この語義は春秋時代では確認できない。初出は西周末期の金文。ただし字形は「龏」。原義は”手を持ち上げて取り上げる”。後漢になってから、”うやうやしく捧げ出す”の意となった。詳細は論語語釈「拱」を参照。
之(シ)


(甲骨文)
論語の本章では、”これ”という代名詞。初出は甲骨文。字形は”足”+「一」”地面”で、あしを止めたところ。原義はつま先でつ突くような、”まさにこれ”。殷代末期から”ゆく”の語義を持った可能性があり、春秋末期までに”~の”の語義を獲得した。詳細は論語語釈「之」を参照。
論語:付記
検証
論語の本章、「爲政(正)以德」は先秦両漢の誰も引用していないし、再録していない。「北辰」うんぬんは、幼少期のトラウマを引きずった前漢武帝に、ヘンな教えを吹き込んでいわゆる儒教の国教化を進めた、董仲舒が言うまで誰も言っていない。
故受命而海內順之,猶眾星之共北辰。

だから天の命を受けた皇帝に全人類が従うのは、北極星にあまたの星が従うのと同じだ。(『春秋繁露』観徳1)
董仲舒についてより詳しくは、論語公冶長篇24余話を参照。
上掲の通り、「辰」に”星座”の意が見られるのは戦国時代からで、「譬」→「辟」の用例にも疑問がある。従って論語の本章は、孔子の肉声である可能性が極めて如何わしいのだが、ブツとしての漢字は論語の時代に揃っているから、とりあえず史実として扱う。
今後、そのような用例を示す出土がないとは限らないからだ。
解説
論語の本章は、漢語や漢文が、我が国でいかにデタラメに解されてきたかを示す好例。「徳」を黒魔術のように扱い、まともに解釈せず、曖昧模糊のまま済ませている。現代中国のように、下記の条件付きながら「率先垂範する」と解した方がまだ合理的で意味が明瞭だ。
「徳」を”人徳”と解するメリットは儒者側にある。人徳と解することで意味が曖昧になり、その解釈や判断を儒者が独占出来る。いわゆる儒教の国教化以降、解釈の独占は政治権力の独占でもあり、事実1911年の辛亥革命まで、帝室と折半する形で儒者が政治利権を独占した。
史実の孔子は行政に携わって苦労した政治家であって、単に道徳を言い募るイジワルじいさんではない。一度は道徳を言い募ったから、貴族にも民衆にも嫌われて亡命するハメになった。「徳」を道徳だと言い出したのは、孔子没後一世紀の孟子である。

孟子が申しました。「武力で仁義のふりをする者を覇者と言い、覇者は必ず大国の主だ。道徳で仁義を行う者を王者と言い、必ずしも大国の主ではない。殷の開祖湯王はたったの七十里四方、周の開祖文王はたったの百里四方しか領地がなかった。」(『孟子』公孫丑上3)
現代中国の解釈が、「以德」を「以身做則」”身を以て規則になる”→”率先垂範”と解している背景には政治がある。現代中国での論語の解釈は、おおむね朱子の新注の受け売りだが、論語の本章に関しては、古注も新注も「以身做則」とは言っていない。
註鄭玄曰徳者無為譬猶北辰之不移而衆星共之也
注釈。鄭玄「徳は何ら働きもしないもので、北斗星にたとえてその動かないこと、全ての星が中心を共有することを示している。」
政之為言正也,所以正人之不正也。德之為言得也,得於心而不失也。北辰,北極,天之樞也。居其所,不動也。共,向也,言眾星四面旋繞而歸向之也。為政以德,則無為而天下歸之,其象如此。
政の言わんとするところは正である。人の不正をただす原動力である。徳の言わんとするところは得ることである。人心を得て失わないことを言う。北辰とは北の極み、天の極みである。居其所とは、動かないことである。共は、そちらを向くという事である。つまり四方の星がめぐりながらも、北斗星を向いている様を言う。政治に徳を用いれば、何もしないでも天下が従う。その有様は本章に記されたとおりである。
種明かしをすれば、現代中国の解釈は『毛主席語録』に由来する。中から一例を挙げる。
「共产党员的先锋作用和模范作用是十分重要的。共产党员在八路军和新四军中,应该成为英勇作战的模范,执行命令的模范,遵守纪律的模范,政治工作的模范和内部团结统一的模范。」《中国共产党在民族战争中的地位》,1938年10月
共産党員の前衛的役割と模範的役割が非常に重要である。共産党員は、八路軍と新四軍のなかでは、英雄的に戦う模範、命令執行の模範、規律遵守の模範、政治工作の模範、内部の団結と統一の模範となるべきである。
この訳文は中国政府お墨付きの日本語版を転記した。
古典の解釈が政治と不可分なことかくの如し。現代中国の学説だからと言って、むやみに飛び付くのが危険だとお分かり頂けるだろうか。『毛主席語録』では道徳の場合「道徳」と言い、ドイツを意味するときは「徳国」と書くが、「徳」一字だけなのは一例しかない。
「要使文艺很好地成为整个革命机器的一个组成部分,作为团结人民、教育人民、打击敌人、消灭敌人的有力的武器,帮助人民同心同德地和敌人作斗争。」《在延安文艺座谈会上的讲话》,1942年5月
文芸をよくよく改良して、革命のための機械のよく働く一部分としなければならない。つまり人民を団結させ、人民を教育し、敵を打倒し、敵を滅ぼす有力な武器とする。そうして人民の心を統一し、「徳」を統一するのを助ける事で、敵と戦うのである。

中国政府発行の日本語版は、「徳」あたりをなぜかぼかして訳しているので、先の例とは違い訳者が訳した。人民を扇動して山賊から中国のボスに納まった毛沢東が、人民の「徳を統一する」といえばもちろん「欲求を統一する」を意味する。でなければ成功できた道理がない。
中国共産党が支配地域を広げた方法は、歴代の王朝創業者と同じで、まず地主=金持ち屋敷を襲って身ぐるみ剝がし、自分らと村人に分配する。歴代と違うのはそのあとで、地主一族をすぐには皆殺しにせず、村人を集めて「人民大会」を開き、それまでの恨み辛みを言わせる。
その結果「悪党だ」と宣言して、結局は共産党が皆殺しにするのだが、間に一手間入るわけ。「大会」で言いたい放題に言い、時に共産党を手伝ってせっせと地主一族を殺した村人は、そのまま共産党に入って兵隊にならないと後がない。地主の私兵が戻ったりもするからだ。
毛沢東はそうした人民大衆の「徳」を、よくわきまえていたのである。
余話
古代文明の終焉
鄭玄の記した本はすでに滅びており、今はその断片が敦煌本などによって知られるだけだが、中国の南朝では、むしろ鄭玄によって校訂されたテキストが、論語の本流として扱われていた。
『経典釈文』を編んだ陸徳明は、南朝最後の陳の儒者で、『旧唐書』の伝によると、若い頃から俊才として知られ、陳が隋に攻め潰されると隠居した。煬帝が即位すると呼ばれて顧問官の下働きとなったが、あるとき学問大会があってそれで勝ち抜いたので、国立大学の講師になった。
隋が内乱状態になると独立勢力から招かれたが、猛毒のハズを砕いて飲み、わざと病気になって応じず、唐が興ると太宗李世民に呼ばれて国立大学の教授になった。間もなく世を去ったが、太宗は『経典釈文』を読んでいたく感心し、陸徳明の遺族に褒美を与え、子を高級官僚として召し出した。
高校教科書的には、「隋の統一、589年」とあってそれでおしまいだが、中華文明的には小さからぬ破壊を伴った。東晋以降、南朝は時折の抗戦はありつつも、主に鮮卑人=鐙を発明した匈奴が支配する北朝によって領土を徐々に削り取られ、最後の陳は最も小さかった。

陳の領域©俊武
ただし南朝は、漢帝国の言葉や文化を保存し伝え続けた。
そこへ隋は50万を超える大軍を南下させ、翌年陳は滅んだ。この時何があったかは余り伝わらないが、おそらく徹底的な略奪暴行と破壊が伴ったと思われる。総司令官がのちの煬帝であるからにはなおさらだ。この時おそらく、鄭玄が校訂した論語のテキストは失われた。
対して古注が失われなかったのは、北朝にも伝わっていたことを窺わせるが、陳の滅亡にともなって、漢帝国以来の中華文明は、その精華の多くを失った。陸徳明は陳→隋→唐と命を長らえたが、蔵書を持ったままでは逃げ切れなかったらしい。おそらく家も焼かれただろう。
中国史では南北朝時代を六朝時代ともいう。六朝とは長江下流の建康(現・南京市)に都を置いた、三国呉・東晋・宋・斉・梁・陳の六王朝で、その文化を六朝文化という。政治・風俗的には不真面目の極みだったが、道教仏教を儒教同等に尊重し、中華文明の一つの盛時だった。
詳細は論語為政篇16余話「魏晋南朝の不真面目」を参照。
なお明末清初の儒者、王夫之は、それなりに発達した中国の伝統天文学に基づき、「北辰」についてなかなかのことを言っている。ただし論語の本章に対する語釈として、当たっているかどうかは別。テキストデータがまだ無いため、『論語集釋』から孫引きして引用。
集注云:「北辰,北極,天之樞也。」於義自明。小注紛紜,乃指爲天樞星,誤矣,辰者,次舍之名。辰非星,星非辰也。北極有其所而無其跡,可以儀測而不可以像觀,與南極對立,而爲天旋運之紐。

朱子の新注に、「北辰とは北極のことで、天の回転軸である」とあり、この言葉には分かりにくいところがない。だが新注に付けられた注はでたらめで、北極星を指すと言うが、間違っている。辰というのは星座の名で、星ではないし、星と星座は別物だ。天の北極をどんなに見つめても何も無く、座標を示すことは出来るがものを見つけることは出来ない。南極と対になる概念であり、天の回転軸のことである。(『四書稗疏』)
科学的にはその通りだが、論語の本章を理解するには役立たない。
なお「北辰」の説明に「天子」と書いた。この言葉は殷代までの中国語には無く、殷に謀反して取って代わった周が、後ろめたさを誤魔化すため、自分から”天の子”と言い出し、「天に代わって不義を討ったのだ」と世間に言い訳した。漢文の本質的な虚偽はここから始まる。
詳細は論語述而篇34余話「周王朝の図々しさ」を参照。



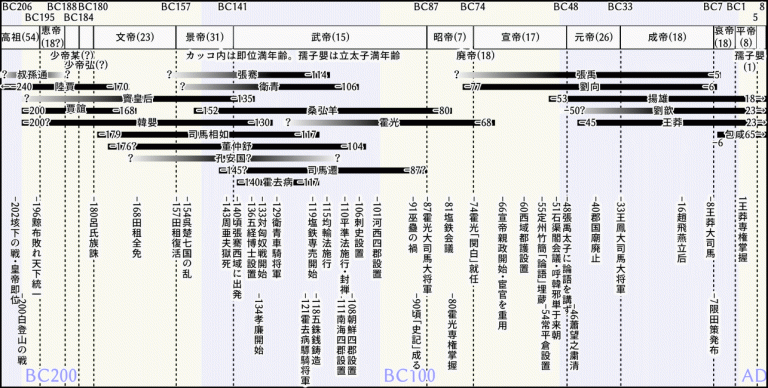


コメント