論語:原文・書き下し
原文(唐開成石経)
子曰君子不器
校訂
東洋文庫蔵清家本
子曰君子不器
後漢熹平石経
子…噐子贛問…
定州竹簡論語
子曰:「君子不[器]。」17
標点文
子曰、「君子不器。」
復元白文(論語時代での表記)






書き下し
子曰く、君子は器なら不れ。
論語:現代日本語訳
逐語訳

先生が言った。「諸君は道具になってはいけない。」
意訳

諸君は他人や本能の飼い犬になったまま、一生を終えるな。
従来訳
先師がいわれた。――
「君子は機械的な人間であってはならぬ。」下村湖人『現代訳論語』
現代中国での解釈例
孔子說:「君子不能象器皿一樣,衹有一種用途。」
孔子が言った。「君子は、食器のようにただ一つの用途しかもたないものと、そっくりにはなれない。」
論語:語釈
子曰(シエツ)(し、いわく)

論語の本章では”孔子先生が言った”。「子」は貴族や知識人に対する敬称で、論語では多くの場合孔子を指す。「子」は赤ん坊の象形、「曰」は口から息が出て来るさま。「子」も「曰」も、共に初出は甲骨文。辞書的には論語語釈「子」・論語語釈「曰」を参照。


(甲骨文)
この二文字を、「し、のたまわく」と読み下す例がある。「言う」→「のたまう」の敬語化だが、漢語の「曰」に敬語の要素は無い。古来、論語業者が世間からお金をむしるためのハッタリで、現在の論語読者が従うべき理由はないだろう。
君子(クンシ)
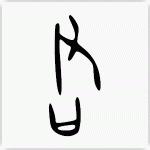

(甲骨文)
論語の本章では、「きんだち」と読んで”君たち”という弟子への呼びかけ。ちょっと古い日本語に「諸子」”君たち”というのがあり、目下の集団に対して敬意を払った呼びかけ。論語での「君子」の役割に、弟子たちに対する敬意を込めた呼びかけがある。孔子は弟子に対しても丁寧な言葉を使う人だった。
「きんだち」が「公」”貴人”+「達」”かたがた”=”貴公子たち”であるのは高校古文的知識だが、日本古語「たち」は目上の複数に対する接尾辞で、目下は「ども」。前近代の日本人にとって、「子」は勝手に生えてくる目下だったから「子ども」と複数を呼んだ。現代日本語の「子供たち」は、この区別がつかなくなった事を表している。
字はどちらも初出は甲骨文。「君」は「丨」”筋道”を握る「又」”手”の下に「𠙵」”くち”を記した形で、原義は天界と人界の願いを仲介する者の意。古代国家の君主が最高神官を務めるのは、どの文明圏でも変わらない。「子」は生まれたばかりの子供の象形。春秋時代以降は明確に、知識人や貴族への敬称になった。孔子や孟懿子のように、開祖級の知識人や大貴族は、「○子」と記して”○先生”・”○様”の意だが、孔子の弟子や一般貴族は、「子○」と記して”○さん”の意。
現代中国語でも「○先生」と言えば、”○さん”の意で”教師”ではない。辞書的には論語語釈「君」・論語語釈「子」を参照。


以上の様な事情で、「君子」とは孔子の生前は単に”貴族”を意味するか、孔子が弟子に呼びかけるときの”諸君”の意でしかない。それが後世、”情け深い教養人”などと偽善的意味に変化したのは、儒家を復興して世間から金を取る商材にした、孔子没後一世紀の孟子から。詳細は論語における「君子」を参照。
孟子とその一党は、政治的謀略をたくましくした孔子一門(『墨子』非儒篇)とは違った意味で素行が悪く、たとえば滞在先の備品をくすねるなどの小悪事を平気でやった。
孟子が子分どもを引き連れて滕の国へ巡業し、殿様の屋敷に逗留した。子分の一人が、窓の上に置いてあったスリッパをくすね、屋敷の管理人が探しても見つからない。
管理人「ああたの従者って、平気で人のものを盗むんですね。」
孟子「管理人どの、我らがスリッパ泥棒の巡業に来たとでも?」
管理人「そうまでは言いませんが…。」(『孟子』盡心下76)
孟子のやり口はいつもこのでんで、相手を言いくるめるのが実に美味かった。
不(フウ)


(甲骨文)
漢文で最も多用される否定辞。初出は甲骨文。「フ」は呉音(遣隋使より前に日本に伝わった音)、「ブ」は慣用音。原義は花のがく。否定辞に用いるのは音を借りた派生義だが、甲骨文から否定辞”…ない”の意に用いた。詳細は論語語釈「不」を参照。
器(キ)
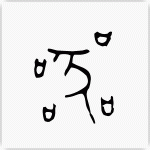

(金文)
論語の本章では、”道具”。徹頭徹尾この意味で、伝統的には”一つの用を足すだけで他に用途のないもの”と解するが、下記するように根拠が無い。
初出は西周早期の金文。新字体は「犬」→「大」と一画少ない「器」。字形は中央に「犬」、周囲に四つの「𠙵」”くち”。犬を犠牲に捧げて大勢で祈るさま。原義は祭祀に用いる道具。金文で人名に用いられた例がある。詳細は論語語釈「器」を参照。
「犬」は古代から現在に至るまで中国では食用にするほか、犠牲獣として鳥類の次に安価なけものとして用いられた。ただしだからと言ってその祭祀の格が低いわけではなく、殷代の甲骨文では、天を祭るにふさわしい犠牲獣としての用例がある。詳細は論語語釈「犬」を参照。


「哭」(甲骨文)/「喪」(甲骨文)
「器」と同系のことばに「哭」があり、葬儀で犬を供えて故人の冥福を祈ることだが、「口」の数が半分であることから、「器」よりは小規模な祭祀を示す。詳細は論語語釈「哭」を参照。また「𠸶」(喪の本字)も同様で、「桑」と「口」一つ~四つで「亡」=”姿を隠した”人を供養する行為を示している。詳細は論語語釈「喪」を参照。
武内本は「不器とは一つの用に滞らざる意」という。現代中国での解釈は、これに沿っている。その元を探れば、やはり儒者の個人的感想だった。
古注『論語集解義疏』
註苞氏曰器者各周其用至於君子無所不施也
註。苞氏曰く器者各の其の用に周う。君子於至りては施ば不る所無き也。

注。包咸「器というものはそれぞれ特定の用途に特化している。しかし君子には出来ない事がない。」
じゃあ空でも飛んでみたらどうだろう。
新注『論語集注』
器者,各適其用而不能相通。成德之士,體無不具,故用無不周,非特為一才一藝而已。
器者、各の其用に適い而相い通ずる能わ不。德を成せる之士は、體に具わら不る無く、故に用て周わ不る無く、特に一才一藝を為す而已に非ず。

朱子「器というものは、特定の用途に特化しており、融通が利かない。徳を身につけたサムライは、自分に足りない所が無く、だから出来ない事が無く、特に一芸に秀でているだけではない。」
じゃあ夏は暑いから水中で暮し、そのまま浮かんでこなければどうだろう。
儒者がこういう出任せを言い出した背景には、帝国儒者の子貢おとしめキャンペーンがある。子貢は孔子一門の中で最も政才商才に優れた弟子で、一門の政略財政は子貢なしでは成り立たなかったが、子貢は教師稼業をしなかったから、子貢派が後世残らなかった。
戦国末の儒者の頭領だった荀子は、儒家の派閥それぞれをこき下ろしているが、子貢派の存在を記していない。だから後世の儒者は言いたい放題の悪口を子貢に向けた。下記する偽作はその一例で、だから儒者にとっては、「器」は”くだらない道具”でなければならなかった。
これ以外にも論語には子貢おとしめ話があるが、論語以外の古典では、前漢までは子貢は悪口を言われていない。言い始めたのは後漢初期の王充で、この男は550年前の論語の時代について、勝手な出任せを『論衡』にいくつも書き込んだ。子貢おとしめ話もこの男が始めている。
或曰:「欲攻子貢之短也。子貢不好道德,而徒好貨殖,故攻其短,欲令窮服而更其行節。」夫攻子貢之短,可言「賜不好道德,而貨殖焉。」何必立「不受命」,與前言「富貴在天」相違反也?


ある人が(孔子に)言った。「子貢の性根の悪さを叩き直してはどうです? 子貢は道徳を馬鹿にし、不埒にも勝手に金儲けばかりしています。だからその悪行を責め立て、恐れ入らせて性根を入れ替えさせるべきです。」
王充「もし子貢の悪を言い立てるなら、”あいつは道徳を馬鹿にして、金儲けばかりしている”と言えばよい。孔子はどうして”勝手に”と言ったのだ(論語先進篇18。偽作) ? ”財産や地位は、天が決めることでどうにもならない”(論語顔淵篇5。偽作)と普段言っているのと矛盾しているではないか。(『論衡』問孔45)
論語:付記
検証
論語の本章は、論語には珍しく文字的・文法語法的に史実を疑えない章なのだが、後漢滅亡までの後世に引用した者が一人もいない。唯一の例外が前漢ごろ成立の『小載礼記』だが、言い廻しはかなり異なっている。
君子曰:大德不官,大道不器,大信不約,大時不齊。察於此四者,可以有志於學矣。三王之祭川也,皆先河而後海;或源也,或委也。此之謂務本。

君子が言った。「大きな道徳は仕事をしない。大きな道は道具にならない。大きな信頼はチマチマしない。大きな時勢は連動しない。この四つを悟るなら、学問を志す資格があると言ってよい。夏・殷・周王朝が祭ったのは川の神である。なぜなら水はまず川となって流れて海に至るからだ。言い換えると川は海の水源である。あるいは川は海を従えている。こういう理屈を、根本を知るというのだ。(『小載礼記』学記17)
つまりこの『礼記』の記述は、論語の本章に由来するとは断じかねる。むしろ下掲『老子道徳経』のもじりではないか。ただ本章は定州竹簡論語にあることから、前漢前半には成立していたことになる。
解説
論語の本章で孔子が言う器とは、意味ある役割を果たす道具。孔子が弟子に求めたのは、腕の立つ戦士を兼ねた有能な行政官になることで、本能の道具として振り回されるただの人=小人でも、他人の道具として振り回される小役人=斗筲之人(論語子路篇20)でもいけなかった。
孔子塾は確かに公務員予備校だったが、孔子の革命思想に共鳴しない弟子であっても、本能の道具であるままに仕官すると、君主や民が迷惑する。大日本帝国の滅亡原因が、軍人ばかりではない文武の役人の身勝手と公私混同にあることを思えば、このことわりは自明だろう。
論語の時代から中国人が求めて止まないのは福禄寿(子だくさん・財産・長寿と健康)だが、それゆえ役人の九分九厘は福禄寿を求めてワイロは取り放題、職権は乱用し放題、公私は混同し放題だった。ただし孔子の時代はまだ官僚制の普及前で、官界の腐敗は問題にならなかった。
春秋時代ではおおむね、政府の官職は世襲であり、それは家職であり家財でもある。孔子の時代になってやっと、世襲が崩れて実力主義が芽生えた。官僚の発生もその一つで、社会の底辺に生まれた孔子が、宰相格にまで出世したことが、その現象をよく示している。
だからこそ孔子は塾を開き、役人への道が開けたから弟子も入門した。確かに若き日の孔子が就いた職のように、下っ端を庶民から採用するのは古くからあっただろうが、孔子の就いた大司冦=司法長官のような、長官職は門閥が代々受け継いできたものだったろう。
そして恐らく下僚職も、世襲長官の家臣のごときものだったはずである。要するに軍事と同様、行政もまた司法なら司法、土木なら土木と言ったようなおおざっぱな単位で、君主から門閥へ丸投げで、門閥は家の子郎党を率いて、家職の運営に当たったのだろう。
孔子に数学の才があり、法律の専門家になれたのは、若き日の孔子を見出した孟孫家が、代々大司空だったからに他ならない。大司空は空(間)=土木を司る職で、平時に動員できるのは囚人だったことから、司法もまた管掌した。家職のおおざっぱさは、こうしたことにも表れた。
そんな時代に孔子が、官界に弟子を送り出すからには、それまでの貴族と同等以上の技能を、身につけさせたことだろう。どの世界でも新参者ほど、その能力が問われるからだ。
余話
大器晩成
現伝の『老子道徳経』の成立は、現存の竹簡から戦国時代と思われるが、漢儒と違って戦国の道家は子貢をおとしめる必要が無く、「器」を”うつわ”・”人間の度量”として記している。故事成句、「大器晩成」の出典となったのだが、以下の通り。
上士聞道,勤而行之;中士聞道,若存若亡;下士聞道,大笑之。不笑不足以為道。故建言有之:明道若昧;進道若退;夷道若纇;上德若谷;太白若辱;廣德若不足;建德若偷;質真若渝;大方無隅;大器晚成;大音希聲;大象無形;道隱無名。夫唯道,善貸且成。

立派なサムライは、道(宇宙の根本法則)を耳にしたら熱心に実践する。ほどほどのサムライは、都合次第で聞かなかったことにする。ダメなサムライは、道を聞くと大笑いする。だが聞かせて笑われずにいられないような話が、道というものだ。
だからこういう言い伝えがある。明らかな道は暗くてよく分からず、役に立つ道は遠回りに思え、よく分かる道のようなものは実は偏っている。本当の能力は無能に見え、本当の清潔は汚らしく見える。多芸な人は役立たずに見え、熱心な稽古は不真面目に見える。本物は濁ったように見える。広大な平面には角が無い。大きな器(人物)は年月を経て出来上がる。大きすぎる音は聞こえない。大きすぎるものには形が無い。
道は姿が見えず名前が無い。だがこの道だけが、よく働きかけてものごとを成り立たせるのだ。(『老子道徳経』41)







コメント