論語:原文・書き下し
原文(唐開成石経)
子曰君子周而不比小人比而不周
校訂
東洋文庫蔵清家本
子曰君子周而不比/小人比而不周
後漢熹平石経
(なし)
定州竹簡論語
[子]曰:「君子[周而不比,小人比]而不周。」19
標点文
子曰、「君子周而不比、小人比而不周。」
復元白文(論語時代での表記)














※論語の本章は、「小人」の語が論語の時代に存在しない。
書き下し
子曰く、君子は周にして比ば不、小人は比びて周なら不。
論語:現代日本語訳
逐語訳

先生が言った。身分教養人格に優れた君子は、何でもできるがつるまない。身分教養人格に劣った小人は、つるんで何も出来ない。
意訳

立派な君子は、何でも自分で出来るが、仲間内だけで固まって人を追い出したりしないのであるぞよ。下らない小人は、何も出来ないので、仲間内だけで固まって人を追い出しているのであるぞよ。
従来訳
先師がいわれた。――
「君子の交りは普遍的であつて派閥を作らない。小人の交りは派閥を作って普遍的でない。」下村湖人『現代訳論語』
現代中国での解釈例
孔子說:「君子團結群衆而不拉幫結派,小人拉幫結派而不團結群衆。」
孔子が言った。「君子は群衆を団結させるが、つるんで党派は作らない。小人はつるんで党派は作るが、群衆を団結させ〔る能は〕ない。」
論語:語釈
子曰(シエツ)(し、いわく)

論語の本章では”孔子先生が言った”。「子」は貴族や知識人に対する敬称で、論語では多くの場合孔子を指す。「子」は赤ん坊の象形、「曰」は口から息が出て来るさま。「子」も「曰」も、共に初出は甲骨文。辞書的には論語語釈「子」・論語語釈「曰」を参照。


(甲骨文)
この二文字を、「し、のたまわく」と読み下す例がある。「言う」→「のたまう」の敬語化だが、漢語の「曰」に敬語の要素は無い。古来、論語業者が世間からお金をむしるためのハッタリで、現在の論語読者が従うべき理由はないだろう。
君子(クンシ)
論語の本章では、”身分教養のある立派な人”。
「君」は「丨」”筋道”を握る「又」”手”の下に「𠙵」”くち”を記した形で、原義は天界と人界の願いを仲介する者の意。古代国家の君主が最高神官を務めるのは、どの文明圏でも変わらない。「子」は生まれたばかりの子供の象形。春秋時代以降は明確に、知識人や貴族への敬称になった。孔子や孟懿子のように、開祖級の知識人や大貴族は、「○子」と記して”○先生”・”○様”の意だが、孔子の弟子や一般貴族は、「子○」と記して”○さん”の意。
なお現代中国語で「○先生」と言えば、”○さん”の意で”教師”ではない。


以上の様な事情で、「君子」とは孔子の生前は単に”貴族”を意味するか、孔子が弟子に呼びかけるときの”諸君”の意でしかない。それが後世、”情け深い教養人”などと偽善的意味に変化したのは、儒家を乗っ取って世間から金をせびり取る商材にした、孔子没後一世紀の孟子から。詳細は論語における「君子」を参照。
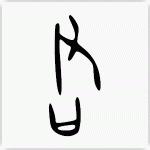

(甲骨文)
「君」の初出は甲骨文。甲骨文の字形は「丨」”通路”+「又」”手”+「口」で、人間の言うことを天界と取り持つ聖職者。春秋末期までに、官職名・称号・人名に用い、また”君臨する”の語義を獲得した。詳細は論語語釈「君」を参照。
周(シュウ)
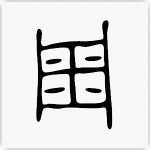

(甲骨文)
論語の本章では”よく細工された”→”行き届いた”の意。初出は甲骨文。極近音に「彫」など。甲骨文の字形は彫刻のさま。原義は”彫刻”。金文の字形には下に「𠙵」”くち”があるものと、ないものが西周早期から混在している。甲骨文では”周の国”を意味し、金文では加えて原義に、人名・器名に、また”周の宗室”・”周の都”・”玉を刻む”を意味した。それ以外の語義は、出土物からは確認できない。ただし同音から、”おわる”、”掃く・ほうき”、”奴隷・人々”、”祈る(人)”、”捕らえる”の語義はありうる。詳細は論語語釈「周」を参照。
従来のような解釈は、”行き届く”から「転じて、すべての人と欠け目なくまじわっている。また、そのさま」(『学研漢和大字典』)という。しかしその典拠はいずれも論語の本章である上に、本来の語義からは遠ざかる。その匂いの元はやはり、儒者のデタラメだった。
古注『論語集解義疏』
註孔安國曰忠信為周阿黨為比也
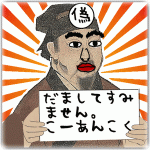
注釈。孔安国「忠実で信義のあることを周と言い、互いにゴマをする集まりを比という。」
新注『論語集注』
周,普遍也。比,偏黨也。皆與人親厚之意,但周公而比私耳。君子小人所為不同,如陰陽晝夜,每每相反。然究其所以分,則在公私之際,毫釐之差耳。故聖人於周比、和同、驕泰之屬,常對舉而互言之,欲學者察乎兩閒,而審其取舍之幾也。
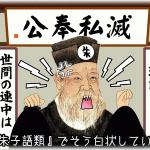
周とはあまねく行き渡るという事だ。比とは利益集団に偏るということだ。どちらも人と親しむことだが、ただし周は公平で比は私利私欲である違いがある。君子と小人ではすることが違う。陰陽の気の動きや昼夜のようなもので、ことごとく相反する。だがそれを分ける基準を求めると、公平か私欲かの、ほんの僅かな違いでしかない。だから聖人は二つを取りあげて、その対比を和同、驕泰のような対語で例え、いつもこの対比を語った。儒学を学ぼうとする者は、この二つの違いをよく観察して、僅かな違いを明らかにして、自分の行いとして取る取らないを決めるのだ。
要するに「比」を馬鹿者の集まりと解したのは古注からで、新注では「周」もまた、つるむことだとされた。「比」はともかく、「周」の解釈には何の根拠も無く、ただの個人的感想。
また論語の本章が「小人」の語の不在から、戦国時代に偽作されたものであっても、出土史料で「周」を”あまねく”と読み得る金文・竹簡・帛書は無く、やはり”行き届いた”の意は確認できる。
《□(詩)》員(云):「人之□(好)我,□(示)我周行。」
ひとのわれをよみし、われによきおこないをしめせ
(先祖の霊よ、)あなたは私に好意を示し、進むべき道をお教え下さい。(「上海博物館蔵戦国楚竹簡」緇衣21)
※現伝『小載礼記』緇衣22、『詩経』鹿鳴と同文。
而(ジ)


(甲骨文)
論語の本章では”そして”。初出は甲骨文。原義は”あごひげ”とされるが用例が確認できない。甲骨文から”~と”を意味し、金文になると、二人称や”そして”の意に用いた。英語のandに当たるが、「A而B」は、AとBが分かちがたく一体となっている事を意味し、単なる時間の前後や類似を意味しない。詳細は論語語釈「而」を参照。
不(フウ)


(甲骨文)
漢文で最も多用される否定辞。初出は甲骨文。「フ」は呉音(遣隋使より前に日本に伝わった音)、「ブ」は慣用音。原義は花のがく。否定辞に用いるのは音を借りた派生義だが、甲骨文から否定辞”…ない”の意に用いた。詳細は論語語釈「不」を参照。
比(ヒ)


(甲骨文)
論語の本章では”ならぶ”→”つるむ”。初出は甲骨文。字形は「人」二つ。原義は”ならぶ”。甲骨文では「妣」(おば)として用いられ、語義は”先祖のきさき”。また”補助する”・”楽しむ”の意に用いた。金文では人名・器名の他”ならべる”・”順序”の意に用いた。詳細は論語語釈「比」を参照。
小人(ショウジン)

論語の本章では”下らない人間”。孔子の生前、仮に漢語に存在したにせよ、「小人」は「君子」の対となる言葉で、単に”平民”を意味した。孔子没後、「君子」の意が変わると共に、「小人」にも差別的意味合いが加わっていった。最初に「小人」を差別し始めたのは戦国末期の荀子で、言いたい放題にバカにし始めたのは前漢の儒者からになる。詳細は論語における「君子」を参照。
「君子」の用例は春秋時代以前の出土史料にあるが、「小人」との言葉が漢語に現れるのは、出土史料としては戦国の簡書(竹簡や木簡)からになる。その事例の中で謙遜の語としての「小人」(わたくしめ)ではなく、”くだらない奴”の用例は、例えば次の通り。
子曰:唯君子能好其駜(匹),小人剴(豈)能好亓(其)駜(匹)。古(故)君子之友也
子曰く、唯だ君子のみ好く其の匹たるを能う。小人豈に好く其の匹たるを能うや。故に君子の友也。(『郭店楚簡』緇衣42・戦国中期或いは末期)


(甲骨文)
「小」の初出は甲骨文。甲骨文の字形から現行と変わらないものがあるが、何を示しているのかは分からない。甲骨文から”小さい”の用例があり、「小食」「小采」で”午後”・”夕方”を意味した。また金文では、謙遜の辞、”若い”や”下級の”を意味する。詳細は論語語釈「小」を参照。


(甲骨文)
「人」の初出は甲骨文。原義は人の横姿。「ニン」は呉音(遣隋使より前に日本に伝わった音)。甲骨文・金文では、人一般を意味するほかに、”奴隷”を意味しうる。対して「大」「夫」などの人間の正面形には、下級の意味を含む用例は見られない。詳細は論語語釈「人」を参照。
論語:付記
検証
論語の本章は、文字史的には春秋時代まで遡れるのに、内容的に孔子の教説とは言えない理由で、後世の偽作と判断できる。「君子」と「小人」の対比論から、おそらく戦国時代以降の創作。また、論語の時代での漢語「小人」の不在はどうにもならない。
本章は、まるまる同じではないが、戦国末期の荀子が似たようなことを言っている。
君子易知而難狎,易懼而難脅,畏患而不避義死,欲利而不為所非,交親而不比,言辯而不辭,蕩蕩乎其有以殊於世也。

君子と知り合うのは簡単だが、なれなれしくするのは難しい。君子は慎重ではあるが、人に脅されはしない。不幸を避けるため全力を尽くすが、正義のためなら死も恐れない。人間だから幸福を求めるが、悪いことはしない。人と親しく付き合うが、つるみはしない。明確に言い切るが、くだらないおしゃべりはしない。だから君子は余裕たっぷりに見えるのだが、世間一般の人とは生き方が違うのだ。(『荀子』不苟2)
解説
論語の本章は、戦国時代になって「君子」の存在意義が問われ、「小人」と対比しおとしめることでその意義を社会に説教した文で、しかもあまり成功しているとは言えない。帝政時代の高慢ちきな儒者官僚ならともかく、殺し合いの戦場に引っ張られた戦国の「小人」=庶民が、こんな上から目線の説教を聞いても納得するはずが無い。
孔子の生きた時代、小麦の栽培と弩(クロスボウ)が実用化され、経済が活発になると同時に戦争の長期化や敗戦国の併合が見られるようになった。いくさもそれまで君子=貴族が戦車をあやつり、車上から長い稽古のいる打撃や射撃を担うことで戦士の役を果たしていたのが、庶民を徴兵してさほど稽古の要らない弩を渡し、一斉射撃で戦車隊を圧倒できるようになった。
つまり武芸を磨く暇のある君子の価値が暴落し、戦国時代になると君子が貴族だったことも忘れられるようになった。だから本章のような偽作が求められたわけ。
「比」”つるむ”は古代からの中華文明の知恵と言うべきで、それは生命保険、損害保険を兼ねていた。剥き身の個人で生きる中国人は古今一人も居ないと言っていい。血統集団である姓、同業集団である氏は論語の昔から存在したし、現在ではそれを宗族とよぶ。宗族からはみ出した個人は、青幇紅幇のような秘密結社に入って身を守る。
つまり「つるまない君子」などメルヘンの産物で、現実にはあり得ない生物だった。
余話
羊と役人は群れたがる
君子=貴族が儒者官僚に取って代わられようとした晩唐、儒者がつるんで悪さを始めた。

今の朋党は、誰もが時代の出世人を頼りに取り巻いて、立派な君子を落とし入れ、天下の動きを大げさに言うことで結束を強め、儒教の知識を親玉の大悪党に伝授して手助けしている。いわゆるサルをおだてて木に登らせ、犬をけしかけて人に噛みつかせ、津々浦々の見えない所に隠れはびこり、いぶり出そうとしても出し切れない、というやつだ。(李徳裕『朋党論』)
理徳裕は、事実上中国史上最後の貴族出身の宰相で、つるんだ儒者官僚に手を焼いた。だが唐が滅び、官僚の採用が儒教的教養を試験する科挙に絞られると、儒者官僚は孔子の教えを棚に上げ、大手を振って「つるむのはよいことだ」と言い始めた。

小人に朋は無く、ただ君子だけが朋を持ちます。そのわけは何でしょう。小人が好むのは利益や収入で、欲しがるのは財産です。そうした利益を、たまたま協力すれば得られる時に限り、しばらくの間互いにつるんでなった朋は、ニセモノです。利益を目の前にして我先に争ったり、あるいは利益が無くなって互いに離れたら、必ず今までとは反対に互いを傷付け、それが兄弟親戚だろうと、お互いを無事で済ませる事が出来ません。
…対して君子は全然違います。守るのは道義、行うのは忠義、惜しむのは名誉と節操だからです。これらで自分自身を躾けるので、必ず道徳を共有して互いに精神修養し、その上で国に仕えますから、必ず心を一つにして共に協力するさまは、始めから終わりまで変わりがありません。これが君子の朋です。
だから君主たる者は、ただ小人のニセモノの朋党を追い払い、君子のホンモノの朋党を用いれば、必ず天下が治まるのです。(欧陽修『朋党論』)
宋儒のものすごい高慢ちきを見て取れるだろうか。
詳細は論語雍也篇3余話「宋儒のオカルトと高慢ちき」を参照。普段から平気でワイロを取り、そのワイロと筆と箸以上に重いものを持とうとしなかった連中が、科挙に受からない者を「小人」として見下している。しかもこの文章は、欧陽修が勝手に皇帝に送りつけた説教文。
これに「馬鹿者が!」と真っ赤になって怒ったのが、清の雍正帝だった。

朕は即位して後、初めて決裁の場に出たとき、貴族諸賢や文武の閣僚に面と向かって、ねんごろに申し渡した。つるんで党派を作ってはならん、と。それから一年。党派の弊風は今なお根絶してはおらん。
父上康煕帝陛下も、世継ぎの問題に苦悩され、同じように時にふれ党派の問題を廷臣に戒めたが、廷臣一体となって父上の言葉を噛みしめ、実現させることが出来なかった。どの者もどの皇子を帝位に就けるか、自他の党派を区別し、陰口をたたいては他派の者を陥れ、最終的に六派に分かれ、誰もが目当ての皇子に帝位を継がせようとし、一時期には無知なやからが、ある党派でなければ必ず別の党に入っているありさまだった。
…だから朕は、いま自ら朋党論を書いて諸君等に配り読ませる。諸君等はこれを読んで、必ずすっかりと心を洗い欲望を清めよ。この分を一字一句味わいながら読み、欠けることの無いよう実現せよ。もしはじめから自分が党派に属していないと信じる者は、必ず一層の努力を払って党派を寄せ付けぬようにせよ。もし党派と無関係ではいられない者は、必ずこれまでの過ちを痛感して行いを改めよ。
諸君等の努力によって、明るい未来が開けている。君主と臣下が行動規範と心を一つにして、好悪を同じくし善悪の判断を公平にしよう。すっぱりと党派の利益に沿った見解を断ち切ろう。
…諸君は自分の胸に手を当てて、党派に属しているかどうか、自分に問え。表で朕の命を奉り、裏でないがしろにし、それで君主をだましお上を誤魔化し、道理に外れ天に逆らう結果になってはならぬ。朕が憐れみ深く、寛大で、一度に大勢の者を罰することなど出来はしない、などと思うな。もし自分から国法に違反するなら、万に一つも目こぼしすることはありえない。
…それにもかかわらず欧陽修めは、おかしな君臣関係を述べ立てて言った。「君子は道徳を共有するから朋党を作る」と。主君を無視して勝手な理屈を述べ立てるのの、どこが道徳か。こやつが言った道徳というのは、小人の道徳に過ぎない。
この論が流行ってよりのち、小人が結託しただけで、それは正義の党だという表の言い訳が出来て、その裏で私利私欲にふけっていたのだ。欧陽修めは「小人に朋党なく、君子に朋党あり」と言ったが、朕の思うところ、君子こそ朋党を作らない。結託するのは小人だけだ。その上欧陽修めの言い分では、結託したままで朋党を維持する者が君子で、解散するのは小人であるかのようだ。
もし欧陽修めが今日に生きており、こうした論を言い立てるなら、朕は必ず説教して、その間違いを正してやろうぞ。(清雍正帝『御製朋党論』)
明清の中華帝国は、高校世界史的には「皇帝独裁権の確立期」とされる。ただし清は明と違って多民族に君臨する定義通りの帝国で、配下の満蒙回蔵(満洲・蒙古・ウイグル・チベット)の土侯を貴族に迎えざるを得なかった。ただし唐ほどには国政に関与させなかった。

雍正帝は中国史上指折りのまじめ皇帝で、本気で「諸君ら次第で、明るい未来が開けている。君臣が心を一つにし、世の中を公平にしよう」と訴えた。だがお説教で言うことを聞くほど、中国人は人が善くない。始皇帝や洪武帝、雍正帝のような怖い君主がいないと宋儒同然。
だからいつまでたっても、中国から強権政治や独裁者が絶えない。それが役人の横暴に苦しむ、大多数の人民の要望でもあるから。ロシアの人民も中国語で同義の老百姓も、「皇帝陛下が悪代官を退治して下さる」ことを、皇帝が大統領や国家首席と名を変えた今なお期待している。
それは空振ると言うしかない。中国人はそのあたりスレていて、国家主席に期待しない一面はあるが、国家経済の半分近くが統計に出ない闇経済であるのと肩を並べる程度には、国家投資→国内需要の割合が多い。
つまりぜにカネについては、相変わらず皇帝陛下のお恵みを期待しているわけだ。





コメント