論語:原文・書き下し
原文(唐開成石経)
子貢問君子子曰先行其言而後從之
校訂
東洋文庫蔵清家本
子貢問君子子曰先行其言而後從之
後漢熹平石経
…噐子贛問…
定州竹簡論語
[子]![]() 問君子。子曰:「先行,其言從之a。」18
問君子。子曰:「先行,其言從之a。」18
- 先行其言從之、今本作「先行其言而後從之」。
標点文
子![]() 問君子。子曰、「先行、其言從之。」
問君子。子曰、「先行、其言從之。」
復元白文(論語時代での表記)













※![]() →貢(甲骨文)。論語の本章は、「行」「其」の用法に疑問がある。
→貢(甲骨文)。論語の本章は、「行」「其」の用法に疑問がある。
書き下し
子貢、君子を問ふ。子曰く、先づ行ひ、其の言は之に從へ。
論語:現代日本語訳
逐語訳


子貢が君子を問うた。先生が言った。「まずやれ。発言はそれに従え。」
意訳
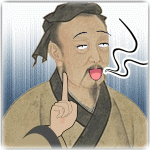

まず行動しろ。そのあとで行動の裏付けがあることを言え。
従来訳
子貢が君子たるものの心得をたずねた。先師はこたえられた。――
「君子は、言いたいことがあったら、先ずそれを自分で行ってから言うものだ。」下村湖人『現代訳論語』
現代中国での解釈例
子貢問君子,孔子說:「先將要說的做出來,然後再說。」
子貢が君子を問うた。孔子が言った。「まず言いたい事をやって見せてから、その後で言え。」
論語:語釈
子貢(シコウ)


「子」(甲骨文)・「貢」(金文大篆)
孔子の弟子。論語の人物:端木賜子貢参照。
「子」は赤子の象形。初出は甲骨文。春秋時代以降では知識人や貴族への敬称として用いられた。孔子や孟懿子など開祖級の知識人や大貴族は「○子」と呼び、孔子の弟子など一般知識人や貴族は「子○」と呼んだ。詳細は論語語釈「子」を参照。「貢」の初出は甲骨文。詳細は論語語釈「貢」を参照。
問(ブン)


(甲骨文)
論語の本章では”問う”。この語義は春秋時代では確認できない。初出は甲骨文。「モン」は呉音。字形は「門」+「口」。甲骨文での語義は不明。西周から春秋に用例が無く、一旦滅んだ漢語である可能性がある。戦国の金文では人名に用いられ、”問う”の語義は戦国最末期の竹簡から。それ以前の戦国時代、「昏」または「𦖞」で”問う”を記した。詳細は論語語釈「問」を参照。
君子(クンシ)
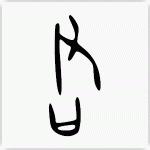

(甲骨文)
論語の本章では、”貴族”。どちらも初出は甲骨文。
「君」は「丨」”筋道”を握る「又」”手”の下に「𠙵」”くち”を記した形で、原義は天界と人界の願いを仲介する者の意。古代国家の君主が最高神官を務めるのは、どの文明圏でも変わらない。「子」は生まれたばかりの子供の象形。春秋時代以降は明確に、知識人や貴族への敬称になった。孔子や孟懿子のように、開祖級の知識人や大貴族は、「○子」と記して”○先生”・”○様”の意だが、孔子の弟子や一般貴族は、「子○」と記して”○さん”の意。
現代中国語でも「○先生」と言えば、”○さん”の意で”教師”ではない。辞書的には論語語釈「君」・論語語釈「子」を参照。


以上の様な事情で、「君子」とは孔子の生前は単に”貴族”を意味するか、孔子が弟子に呼びかけるときの”諸君”の意でしかない。それが後世、”情け深い教養人”などと偽善的意味に変化したのは、儒家を乗っ取って世間から金をせびり取る商材にした、孔子没後一世紀の孟子から。詳細は論語における「君子」を参照。
子曰(シエツ)(し、いわく)

論語の本章では”孔子先生が言った”。「子」は貴族や知識人に対する敬称で、論語では多くの場合孔子を指す。「子」は赤ん坊の象形、「曰」は口から息が出て来るさま。「子」も「曰」も、共に初出は甲骨文。辞書的には論語語釈「子」・論語語釈「曰」を参照。


(甲骨文)
この二文字を、「し、のたまわく」と読み下す例がある。「言う」→「のたまう」の敬語化だが、漢語の「曰」に敬語の要素は無い。古来、論語業者が世間からお金をむしるためのハッタリで、現在の論語読者が従うべき理由はないだろう。
先(セン)


(甲骨文)
論語の本章では、”はじめに”。初出は甲骨文。字形は「止」”ゆく”+「人」で、人が進む先。甲骨文では「後」と対を為して”過去”を意味し、また国名に用いた。春秋時代までの金文では、加えて”先行する”を意味した。詳細は論語語釈「先」を参照。
行(コウ)


(甲骨文)
論語の本章では”行え”。この語義は春秋時代では確認できない。初出は甲骨文。「ギョウ」は呉音。十字路を描いたもので、真ん中に「人」を加えると「道」の字になる。甲骨文や春秋時代の金文までは、”みち”・”ゆく”の語義で、”おこなう”の語義が見られるのは戦国末期から。詳細は論語語釈「行」を参照。
其(キ)


(甲骨文)
論語の本章では”その”という指示詞。この語義は春秋時代では確認できない。初出は甲骨文。甲骨文の字形は「𠀠」”かご”。かごに盛った、それと指させる事物の意。金文から下に「二」”折敷”または「丌」”机”・”祭壇”を加えた。人称代名詞に用いた例は、殷代末期から、指示代名詞に用いた例は、戦国中期からになる。詳細は論語語釈「其」を参照。
言(ゲン)


(甲骨文)
論語の本章では”発言”。初出は甲骨文。字形は諸説あってはっきりしない。「口」+「辛」”ハリ・ナイフ”の組み合わせに見えるが、それがなぜ”ことば”へとつながるかは分からない。原義は”言葉・話”。甲骨文で原義と祭礼名の、金文で”宴会”(伯矩鼎・西周早期)の意があるという。詳細は論語語釈「言」を参照。
而(ジ)


(甲骨文)
論語の本章では”そして”。初出は甲骨文。原義は”あごひげ”とされるが用例が確認できない。甲骨文から”~と”を意味し、金文になると、二人称や”そして”の意に用いた。英語のandに当たるが、「A而B」は、AとBが分かちがたく一体となっている事を意味し、単なる時間の前後や類似を意味しない。詳細は論語語釈「而」を参照。
後(コウ)


(甲骨文)
現伝本について、論語の本章では”あとでは”。「ゴ」は慣用音、呉音は「グ」。初出は甲骨文。その字形は彳を欠く「幺」”ひも”+「夂」”あし”。あしを縛られて歩み遅れるさま。原義は”おくれる”。甲骨文では原義に、春秋時代以前の金文では加えて”うしろ”を意味し、「後人」は”子孫”を意味した。また”終わる”を意味した。人名の用例もあるが年代不詳。詳細は論語語釈「後」を参照。
而後(してのちは)
唐石経、清家本以降の日中の論語の伝承では、ともに「先行其言」と「從之」の間に「而後」を記すが、これは「いち、にっ、さん、し」のリズムで口ずさみやすい、四言句が定着した唐代の韻文の影響でそうなったと思われる。
下掲はカールグレンによる再建音だが、リズムを知るには難しい事を飛ばして、語尾だけ着目するとよい。「而後」の無い上古なら「アン・アンク・アク・アン、ウンク・アク」と読んでいたが、詩文らしく書き換えた唐石経では、「エン・アンク・イァ・アン、イ・アウ・ウォンク・イ」と口ずさんだことになる。
| 調子 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 字 | 先 | 行 | 其 | 言 | 而 | 後 | 從 | 之 |
| 声調 | 平/去 | 平/去 | 平 | 平 | 平 | 上/去 | 平/平/去 | 平 |
| 上古音 | siən | ɡʰɑŋ/ɡʰăŋ | gʰi̯əɡ/ki̯əɡ | ŋi̯ăn | (ȵi̯əɡ) | (gʰu/?) | dzʰi̯uŋ/tsʰi̯uŋ/dzʰi̯uŋ | ȶi̯əɡ |
| 隋唐音 | sien | ɣɑŋ/ɣɐŋ | gǐə/kǐə | ŋǐɐn | ȵʑi | ɣə̯u/? | dzʰi̯woŋ/tsʰi̯woŋ/dzʰi̯woŋ | tɕi |
漢石経はこの部分を欠くが、定州竹簡論語は明確に「而後」を記さない。これに従い無いものとして校訂した。論語の伝承について詳細は「論語の成立過程まとめ」を参照。
原始論語?…→定州竹簡論語→白虎通義→ ┌(中国)─唐石経─論語注疏─論語集注─(古注滅ぶ)→ →漢石経─古注─経典釈文─┤ ↓↓↓↓↓↓↓さまざまな影響↓↓↓↓↓↓↓ ・慶大本 └(日本)─清家本─正平本─文明本─足利本─根本本→ →(中国)─(古注逆輸入)─論語正義─────→(現在) →(日本)─────────────懐徳堂本→(現在)
從(ショウ)


(甲骨文)
論語の本章では、現伝本については”やり続けろ”。定州本については”かなったことをする”。初出は甲骨文。新字体は「従」。「ジュウ」は呉音。字形は「彳」”みち”+「从」”大勢の人”で、人が通るべき筋道。原義は筋道に従うこと。甲骨文での解釈は不詳だが、金文では”従ってゆく”、「縦」と記して”好きなようにさせる”の用例があるが、”聞き従う”は戦国時代の「中山王鼎」まで時代が下る。詳細は論語語釈「従」を参照。
之(シ)


(甲骨文)
論語の本章では、現伝本については、「先行其言」を指し示す指示代名詞。定州竹簡論語については、「先行」を指し示す指示代名詞。初出は甲骨文。字形は”足を止めたところ”で、原義は”これ”。”これ”という指示代名詞に用いるのは、音を借りた仮借文字だが、甲骨文から用例がある。”…の”の語義は、春秋早期の金文に用例がある。詳細は論語語釈「之」を参照。
先行其言而後從之→先行其言從之
まず現伝本について、「先行其言而後從之」は「而」があることから「先行其言、而後從之」と句読を切るしかない。「而後從之」は、”その後でそれに従え”としか解せない。「先行其言」のうち動詞になり得るのは「先」=”先んじる”か、「行」=”行う”。
「先」を動詞とした場合、”行動に先んじてその言葉は”としか解せない。そして”その後でそれに従え”と繋がらない。つまりわけが分からない。「行」を動詞とした場合、”先に行ってからその言葉は”となり、”その後でそれに従え”と繋がるから、意味が通じる。
次に定州竹簡論語について。「而後」が抜けたので全体で一句、動詞になり得るのは同じく「先」と「行」だが、「先」が動詞の場合”行動に先んじてその言葉はそれに従え”となりわけワカメ。「行」を動詞と解し、”まず行動してその言葉はそれに従え”が正解。
論語:付記
検証
論語の本章は、文字史的に偽作を疑えず、定州竹簡論語にもあるが、それ以外に春秋戦国・秦両漢の誰一人引用していない。「而後從之」が、一般的な言い廻しとして見られるのみ。漢字の用法に疑いは残るが、とりあえず史実と扱ってかまわない。
解説
既存の論語本の中では吉川本に、「君子すなわち紳士たるものの資格を問うたのに対し、与えられた孔子の答えは、不言実行ということであった。」とある。代々の論語に注を付けた儒者もほぼそう解している。しかしそう読むためには、語順が「行先其言」でなければならない。
儒者はおそらく意図的に、論語の本章の解釈をねじ曲げた。多くの儒者は教師稼業で食ったから、弟子には黙っていて貰いたかったのだろう。文句も言わずに黙って授業料を払ってくれる弟子ほど、有り難いからだ。
古注『論語義疏』
註孔安國曰疾小人多言而行之不周也。
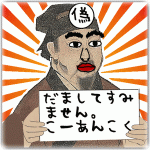
注釈。孔安国「下らぬ人間はべらべら喋るくせに行動が伴わないのを憎んだのである。」
孔安国にとって、孔門十哲の子貢が「下らない人間」ということになるのだが? なお孔安国は、高祖劉邦の名を避諱(はばかって使わない)するという法を平気で破っていることから、実在の人物でない可能性が高い。三国魏で古注を編んだ何晏が、無名の漢儒を代表させるためこしらえた創作人物とみてよい。
新注『論語集注』
周氏曰:「先行其言者,行之於未言之前;而後從之者,言之於既行之後。」范氏曰:「子貢之患,非言之艱而行之艱,故告之以此。」

周孚先「”先行其言”とあるのは、言わない前に行えという事だ。”而後從之”とは、言うならやった後で言えということだ。」
范祖禹「子貢の下らない所は、口が回らない点でなく行動が出来ない点だ。だから孔子はこう言って戒めたのだ。」
周孚先は明代にも同名の儒者がいるようだが、北宋儒の親玉である程頤(伊川)の弟子で、性格破綻者が多い北宋儒者の中でも、極めつけに悪どい楊時のマブダチだったらしい。

楊時とは論語の新注に偉そうな説教を残した男で、北宋が金に都を攻め落とされ、皇帝が拉致され滅ぶという大事件さえ、「利にさとって」政敵の新法党を弾劾する好機に変え、それ以外は何をするでなく、のうのうと逃げ延び、特に「義を選ぶ」ことなく南宋で出世した。

范祖禹は司馬光を補佐して『資治通鑑』の編纂に携わり、れっきとした進士合格者なのに、珍しくあまり官界での出世を求めなかった、とされる。難しい顔をした謹厳居士だったようで、「無駄口を聞いたことが無い」と口数の多い蘇東坡が言っている。
だが「子貢は行動が出来ない」というのは大ウソで、そうでなければまじめに史書や経典を読んでいないことになる。『史記』弟子伝だけでも、子貢の行動は他の弟子を圧倒した量が記されている。范祖禹ほどの学者が読んでいなかったはずが無いが、これも宋儒の悪い癖。
ものごとを「AはBだ」と最初に決めてかかり、それに反する情報は全て無かったことにする。だから緻密な思考を積み重ねたようでいながら、その結論はおよそ現実離れしている。こういう理由で、朱子学など宋の新儒教はオカルトのたぐいだと思った方がいい。
- 論語雍也篇3余話「宋儒のオカルトと高慢ちき」
以上の様に、儒者は論語の他箇所で孔子が口数の少なさを称揚していること(論語公冶長篇5)を理由に、この章の解釈をねじ曲げた。だが黙って行って成功すれば、自分の手柄だと後出しじゃんけんで言い放題だし、失敗しても黙っていれば、うまくすれば人のせいに出来る。
つまり孔子がよほど陰険な人間に読める。だが仮に孔子が多言を憎んだにせよ、孔子自身は極めて饒舌な上に、弁舌無しで政治や革命ができるだろうか?

演説する革命家、トロツキー赤衛軍司令官
論語の本章の解釈について、まず発言者が子貢であることを考える。子貢は弁舌の才を孔子に評価された弟子であり(論語先進篇2)、その弁舌で五カ国をひっくり返した(『史記』弟子列伝)。なるほど多弁な人物だったろう。しかし言っただけのことは行ってもいる。
しかし仕官以前は行いようがなかったろうし、仕官後も至らぬ事はあっただろう。孔子はそれをたしなめたのであって、自分が認めた子貢の弁才をおとしめはしなかったろう。「角を矯めて牛を殺す」愚は、孔子も十分承知していただろうから。だから優れた師匠として仰がれた。

既存の論語本が言うように、孔子が子貢の弁舌を、「不言実行」などと言って封じてしまえば、度重なった一門の危難と、『史記』にあるような魯国の危機を子貢は救えなかった。となると「不言実行」は子貢のような才と、孔子と同等の弟子を見抜く才が無い者の言う事。
重ねて孔子が子貢の弁才を封じたらどうなるか考えよう。その日から孔子一門は確実に食うにも困るは必定である。塾経営で孔子が儲かった話は見たことがなく、高給取りだったが、政治にはとにかくカネが要る。弟子でカネを持っているのは子貢だけで、彼が財政を支えたのだ。
中国儒者の多くも日本の漢学教授も雇われ人に過ぎない。サラリーマン社会(官場、と漢文では言う)の手練手管は知っているかも知れないが、働かなくとも給料が出るのが当たり前と思っている人間に、経営のなんたるかが分かる動機が無い。その経営論に価値はあるのだろうか?
孔子が多弁を嫌った場面はあるだろう。だがそれは”バカどもが一日中、集まって下らないことをわあわあ言い合っている。救いようが無い”(論語衛霊公篇17)けしきに対してであり、”平均以上の者には奥義が語れる”(論語雍也篇21)子貢に対する嫌悪ではなかった。
また儒者は本章を「不言実行」と解する証拠に、論語学而篇14の孔子の言葉、「慎於言」”言葉を慎重に”を挙げたのだろうが、そもそも該章のこの部分が戦国時代以降の捏造であり、ともすると本章を「不言実行」と解するためのつじつま合わせだった可能性すらある。
余話
戦勝は全てを合理化する
漢儒に始まる論語の本章の「不言実行」的解釈は、あるいは漢初の帝室が儒家よりも道家に共感を覚えていた事へのお追従かも知れない。前漢第5代文帝の竇皇后は、第6代景帝の母で、晩年は第7代武帝の祖母として帝国に君臨したが、道家を好んで儒家を毛嫌いしていた。
景帝の母である竇太后は、老子の書を好んで読んでいた。あるとき儒教を奉じる生=学者の轅固を呼んで老子の書について意見を聞いた。
轅固「これは奴隷根性のたわごとです。」太后は真っ赤になって怒った。「お前を牢に放り込んで、毎朝城壁造りにコキ使ってやろうか!」というわけで固は牢に放り込まれ、それもイノシシの檻に入れられて戦うよう命じられた。
景帝「母上は怒っておいでだが、轅固の正直はお認めの筈だ。」というわけで轅固に切れ味のいい刃物を渡し、イノシシの檻に閉じこめた。轅固は一突きでイノシシの心臓を貫いたが、それが通じたと見えてイノシシは倒れた。
見物していた太后は黙ってしまい、といって新たな罪をでっち上げることも出来ず、うやむやになった。ほとぼりが冷めるのを待って、景帝は轅固の正直を愛でて、息子の清河王の守り役頭に取り立てた。轅固は長く務め、老年を理由に退職となった。(『史記』儒林伝11)
その道家の政治スローガンが、「無為」であることはよく知られている。「為すべからざるして治まる」のを理想とした。
天下皆知美之為美,斯惡已。皆知善之為善,斯不善已。故有無相生,難易相成,長短相較,高下相傾,音聲相和,前後相隨。是以聖人處無為之事,行不言之教;萬物作焉而不辭,生而不有。為而不恃,功成而弗居。夫唯弗居,是以不去。
天下の者はみな、美しいものを美しいと言うが、美は醜さの始まりである。善を善だと言うが、善は不善の始まりである。ある/なしは互いにその存在を保証し、難しい/易しいはお互いがあって成り立ち、長短は比べられるからあり得、高下は互いに自分へと引き寄せようとし、音は違う音階だから響き合い、前後は相手が無いと行き場が無い。だから聖人は何もしないことをする。言わないでも人々が従い、何もしないから万物が生まれて止まず、形有るものはやがて消え去る。働きながら結果を期待せず、成功してもさっさと逃げ出す。居座ろうとしないからこそ、その座が失われないのだ。
不尚賢,使民不爭;不貴難得之貨,使民不為盜;不見可欲,使心不亂。是以聖人之治,虛其心,實其腹,弱其志,強其骨。常使民無知無欲。使夫知者不敢為也。為無為,則無不治。
賢臣を求めなければ地位をめぐって民は争わず、得がたい宝物を有り難がらなければ民は盗もうとしない。欲しいものを始めから知らなければ、心は乱れない。だから聖人の政治は、民の心をうつろにし、腹は満たしてやり、体は丈夫にしてやる。常に民を無知無欲にしておけば、知ったかぶりが余計な事をするすきが無くなる。しないからこそ出来る、そうすれば世が治まらないはずが無い。(『老子道徳経』2-3)
だがこれは、巨大な人口と国土を抱える中国を、現実的に統治できる法にはなり得ない。ともすればある種の儒家と同じく、空理空論をもてあそぶだけの結果に終わってしまう。饑饉も盗賊も蛮族の侵入も疫病も洪水も、抜き差しならない現実なのだ。放置できるわけがない。
とりわけ重大な課題は北方の匈奴で、初代高祖劉邦が大敗して以来、漢帝国は負け続けた。匈奴は漢より優れた騎馬術と製鉄技術を持ち、その武力的優位から気軽に漢に攻め込んで、略奪と拉致を繰り返した。拉致問題を他人事として済ませる国に、存在意義はあるのだろうか?
皇后や太后、太皇太后という気楽な立場に居たから、竇皇后は道家を好んで済ませられたが、実務担当者にはこうした贅沢は許されない。前漢前期は中華帝国史上でもよく治まった盛時だったが、その裏には法務や統計や土木に長けた実務官僚の仕事があった。
毛沢東も同様に思っていたようである。
“互通情报”。就是说,党委各委员之间要把彼此知道的情况互相通知、互相交流。这对于取得共同的语言是很重要的。有些人不是这样做,而是象老子说的“鸡犬之声相闻,老死不相往来”,结果彼此之间就缺乏共同的语言。
「情報を知らせ合うこと」。つまり、党委員会の各委員はそれぞれの知りえたことがらをたがいに知らせ合い、交流し合わなければならない。これは、共通の言葉をもつうえでひじょうに大切なことである。一部の人びとはそうしないで、老子の言う「鶏犬の声あい聞こゆれども、老いて死ぬまであい往来せず」を地でいき、その結果、おたがいのあいだに共通の言葉が欠けている。(『毛主席語録』「党委員会の活動方法」一九四九年三月十三日)
毛沢東が批判した元ネタは次の通り。
小國寡民。使有什伯之器而不用;使民重死而不遠徙。雖有舟輿,無所乘之,雖有甲兵,無所陳之。使民復結繩而用之,甘其食,美其服,安其居,樂其俗。鄰國相望,雞犬之聲相聞,民至老死,不相往來。
小さな国で人口が少ない。兵器があっても使わない。民には命を大事にさせて遠くへ行かせない。船や車があっても、どこへも行かない。鎧や刀があっても、使う機会が無い。民には読み書きを教えないで、縄目の印だけを使わせる。その場にあるものを美味しいと思わせ、着心地が良いと思わせ、住まいやすいと思わせる。隣の国は目で見えて、鶏や犬の声が互いに聞こえるが、老いて死ぬまで互いに行き来しない。(『老子道徳経』80)
前漢前期の盛時を無茶苦茶にしたのは、竇太后死後に親政を始めた武帝で、対匈奴戦を派手に行いある程度の効果をみた。その代わり財政は破綻し、生活に困る庶民が続出し、前漢は滅亡への長い道を始めることになる。だがそれでも廃位されなかったのは、ひとえに戦勝ゆえだ。
匈奴とは漢にとって、それほどの存在だったのである。






コメント