論語:原文・書き下し
原文(唐開成石経)
子曰温故而知新可以爲師矣
校訂
東洋文庫蔵清家本
子曰温故而知新可以爲師矣
後漢熹平石経
子白温故而知…
定州竹簡論語
……「溫故而智a新,可以為師矣。」16
- 智、今本作「知」。古「知」、「智」通。
標点文
子曰、「溫故而智新、可以為師矣。」
復元白文(論語時代での表記)












※溫→(甲骨文)。論語の本章は、「故」の用法に疑問がある。「可以」は戦国中期以降しか確認できない。
書き下し
子曰く、故きを溫し而新しきを智らば、以ゐて師爲る可き矣。
論語:現代日本語訳
逐語訳

先生が言った。古い常識を風呂に入るようにすっかり洗い落とし、新しい情報を知っているなら、それでやっと教師稼業が務まる。
意訳

古い常識を、綺麗さっぱり捨て去った上で、新しい学問に通じるなら、それでやっと教師稼業が務まる。
従来訳
先師がいわれた。――
「古きものを愛護しつつ新しき知識を求める人であれば、人を導く資格がある。」下村湖人『現代訳論語』
現代中国での解釈例
孔子說:「溫習舊知識時,能有新收穫,就可以做老師了。」」
孔子が言った。「古い知識を実践する時に、新しい発見ができるなら、それでもう教師になってしまえる。」
論語:語釈
子曰(シエツ)(し、いわく)

論語の本章では”孔子先生が言った”。「子」は貴族や知識人に対する敬称で、論語では多くの場合孔子を指す。「子」は赤ん坊の象形、「曰」は口から息が出て来るさま。「子」も「曰」も、共に初出は甲骨文。辞書的には論語語釈「子」・論語語釈「曰」を参照。


(甲骨文)
この二文字を、「し、のたまわく」と読み下す例がある。「言う」→「のたまう」の敬語化だが、漢語の「曰」に敬語の要素は無い。古来、論語業者が世間からお金をむしるためのハッタリで、現在の論語読者が従うべき理由はないだろう。
漢石経では「曰」字を「白」字と記す。古義を共有しないから転注ではなく、音が遠いから仮借でもない。前漢の定州竹簡論語では「曰」と記すのを後漢に「白」と記すのは、春秋の金文や楚系戦国文字などの「曰」字の古形に、「白」字に近い形のものがあるからで、後漢の世で古風を装うにはありうることだ。この用法は「敬白」のように現代にも定着しているが、「白」を”言う”の意で用いるのは、後漢の『釈名』から見られる。論語語釈「白」も参照。
温(オン)→溫(オン)


(甲骨文)
論語の本章では”洗い落とす”。旧字体は「溫」。新字体は「温」。ただし唐石経も清家本も新字体と同じく「温」と記す。定州本も「温」と釈文する。字源からは旧字体を正字とするのに理がある。初出は甲骨文だが、金文は未発掘。「ウン」は唐音。同音に「𥁕」(カールグレン上古音不明)を部品とする文字群。従来の解釈や武内本は「温は習熟の意」という。従って「たずねる」という読みをするが現在では通用しない。



「水」「人」「皿」(甲骨文)
藤堂・白川両博士もこの漢字を、鍋に蓋をして下からゆるゆる温める姿とみるが、平明に見ればそれは間違いで、この甲骨文は人を火あぶりにする姿でなければ、水+人+皿(平らな風呂桶)の”風呂”の象形。それゆえ『大漢和辞典』にも、「温」に”いでゆ”の語釈を載せる。

両博士の誤読の理由は、甲骨文が入手できなかったからだろう。その証拠に『学研漢和大字典』も『字通』も、篆書しか参照していない。また「𥁕」を、従来の説では甲骨文が初出と言うが、字形は全て「因」または「困」であり、「𥁕」に比定したのは儒者の出任せに過ぎない。詳細は論語語釈「温」を参照。
故(コ)
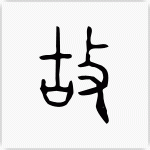

(金文)
論語の本章では、”旧来の学問”。『大漢和辞典』の第一義は”もと・むかし”。攵(のぶん)は”行為”を意味する。初出は西周早期の金文。ただし字形が僅かに違い、「古」+「攴」”手に道具を持つさま”。「古」は「𠙵」”くち”+「中」”盾”で、”口約束を守る事”。それに「攴」を加えて、”守るべき口約束を記録する”。従って”理由”・”それゆえ”が原義で、”ふるい”の語義は戦国時代まで時代が下る。西周の金文では、「古」を「故」と釈文するものがある。詳細は論語語釈「故」を参照。
而(ジ)


(甲骨文)
論語の本章では”そして”。初出は甲骨文。原義は”あごひげ”とされるが用例が確認できない。甲骨文から”~と”を意味し、金文になると、二人称や”そして”の意に用いた。英語のandに当たるが、「A而B」は、AとBが分かちがたく一体となっている事を意味し、単なる時間の前後や類似を意味しない。詳細は論語語釈「而」を参照。
知(チ)→智(チ)


(甲骨文)
論語の本章では”知る”。現行書体の初出は秦系戦国文字。孔子在世当時の金文では「知」・「智」は区別せず書かれた。甲骨文で「知」・「智」に比定されている字形には複数の種類があり、原義は明瞭でない。ただし春秋時代までには、すでに”知る”を意味した。”知者”・”管掌する”の用例は、戦国時時代から。詳細は論語語釈「知」を参照。
新(シン)


(甲骨文)
論語の本章では”新しい”。初出は甲骨文。甲骨文の字形は「辛」”針または刃物”+「木」+「斤」”おの”で、早期の字形では「木」を欠く。切り出した丸太の中央に太い針を刺し、それを軸に回しながら皮を剥くさま。真新しい木肌が現れることから、原義は”新しい”。甲骨文では原義で、また地名・人名・祭祀名に用いた。金文でも同様。詳細は論語語釈「新」を参照。
可以(カイ)
論語の本章では”それで~できる”。現代中国語でも同義で使われる助動詞「可以」。ただし出土史料は戦国中期以降の簡帛書(木や竹の簡、絹に記された文書)に限られ、論語の時代以前からは出土例が無い。春秋時代の漢語は一字一語が原則で、「可以」が存在した可能性は低い。ただし、「もって~すべし」と一字ごとに訓読すれば、一応春秋時代の漢語として通る。
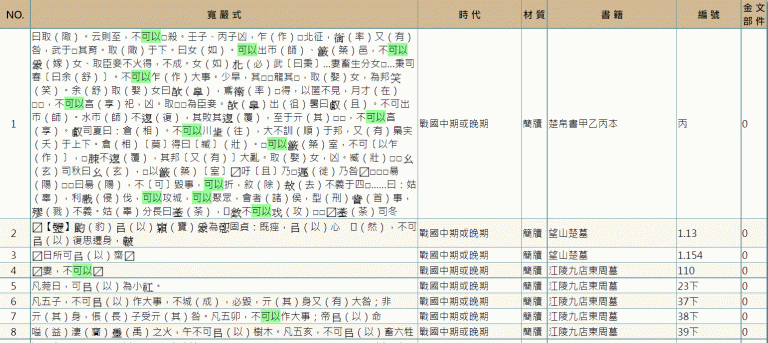
「先秦甲骨金文簡牘詞彙庫」


「可」(甲骨文)
「可」の初出は甲骨文。字形は「口」+「屈曲したかぎ型」で、原義は”やっとものを言う”こと。甲骨文から”~できる”を表した。日本語の「よろし」にあたるが、可能”~できる”・勧誘”~のがよい”・当然”~すべきだ”・認定”~に値する”の語義もある。詳細は論語語釈「可」を参照。


「以」(甲骨文)
「以」の初出は甲骨文。人が手に道具を持った象形。原義は”手に持つ”。論語の時代までに、名詞(人名)、動詞”用いる”、接続詞”そして”の語義があったが、前置詞”~で”に用いる例は確認できない。ただしほとんどの前置詞の例は、”用いる”と動詞に解せば春秋時代の不在を回避できる。詳細は論語語釈「以」を参照。
爲(イ)
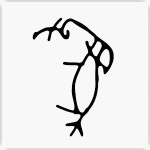

(甲骨文)
論語の本章では”~になる”。新字体は「為」。字形は象を調教するさま。甲骨文の段階で、”ある”や人名を、金文の段階で”作る”・”する”・”~になる”を意味した。詳細は論語語釈「為」を参照。
師(シ)
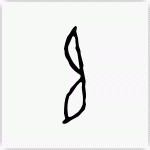

「𠂤」(甲骨文)
論語の本章では”師匠”。初出は甲骨文。部品の「𠂤」の字形と、すでに「帀」をともなったものとがある。「𠂤」は兵糧を縄で結わえた、あるいは長い袋に兵糧を入れて一食分だけ縛ったさま。原義は”出征軍”。「帀」の字形の由来と原義は不明だが、おそらく刀剣を意味すると思われる。全体で兵糧を担いだ兵と、指揮刀を持った将校で、原義は”軍隊”。
金文では原義の他、教育関係の官職名に、また人名に用いられた。さらに甲骨文・金文では、”軍隊”の意ではおもに「𠂤」が用いられ、金文でははじめ「師」をおもに”教師”の意に用いたが、東周になると「帀」を”技能者”の意に用いた。詳細は論語語釈「師」を参照。
矣(イ)


(金文)
論語の本章では、”(きっと)~である”。初出は殷代末期の金文。字形は「𠙵」”人の頭”+「大」”人の歩く姿”。背を向けて立ち去ってゆく人の姿。原義はおそらく”…し終えた”。ここから完了・断定を意味しうる。詳細は論語語釈「矣」を参照。
論語:付記
検証
論語の本章の再出は、前漢ごろ成立の『小載礼記』中庸篇で、その間他学派も含めて誰一人引用していない。更なる再出は、後漢初期の王充による『論衡』になる。ただ定州竹簡論語にあることから、本章は前漢前半には出来ていただろう。とりあえず史実と見てよい。
解説
以下に『小載礼記』の本章再出部分の訳文を示す。儒者の頭がどのように出来上がっていたか、おおむねを知ることが出来るだろう。
大哉,聖人之道!洋洋乎發育萬物,峻極于天。優優大哉!禮儀三百,威儀三千,待其人然後行。故曰:苟不至德,至道不凝焉。故君子尊德性而道問學,致廣大而盡精微,極高明而中庸。溫故而知新,敦厚以崇禮。是故居上不驕,為下不倍;國有道,其言足以興,國無道,其默足以容。《詩》曰:「既明且哲,以保其身。」其此之謂與!

♪あ~りが~たや、ありがたや~。聖人さまはありがたや。宇宙に隅々広がって、万物を養い育て、天高くそびえ立っている。♪み~ち~は広い~な、お~き~な~。お作法三百、躾け三千。しゅごい人でないと、出来ないな。
だから言う、道徳が身に付くまでは、やらなきゃいけないことが沢山ある。だから君子は道徳を尊んで、学問に努め、それも広く深く極めて、完璧超人を目指して偏らない。ムカシの偉い人に学び、新しい知識も得る。何でも学び取ってお作法をしゅごいのにする。
だから地位が高くても威張らず、低くても逆らわない。国がまともなら、その言葉で国が盛んになり、まともでないなら、黙って困難に耐える。詩経に言う、「はっきりとものが見えるなら、危ない目に遭うことがない。」それはこういう事を言うのだ!(『小載礼記』中庸28)
たわごとでしかないが、なんとこれは科挙の必須科目だった「中庸」に入っている。二千年ほどこんなものばかり暗記していたから、中国の知識人はメルヘンがハンダ付けになって国を滅ぼしたのだが、教義が共産主義に変わっただけで、今なおこういう幻想を平気で言う。
そもそも「中庸」というタイトルが詐欺もいいところで、ある行為が偏っているかどうかは、常に事後にならないと分からない。標準偏差を取ったところで、その後の傾向が変わってしまえば、事前の平均値など意味が無い。だが儒者はそれを心得ているとウソをついてきたのだ。

宇宙の温度 © KAVLI INSTITUTE FOR THE PHYSICS AND MATHEMATICS OF THE UNIVERSE
さて論語の本章を史実とするなら、革命家だった孔子の面目躍如たる発言。社会の底辺から宰相格まで上り詰めた孔子は、当時の秩序の破壊者だった。だからこそ故国を追われ、諸国でもつまはじきされて、放浪するハメになった。ここを見逃すと論語は読めない。
確かに孔子は共和政を目指さなかったし、周王朝の打倒も企てなかった。だが行政に当たるべきは教育を受けた平民出身の新興士族と思っていたし、社会変動について行けなくなった旧勢力も、それを一部認めた。孔子の政界デビューは、門閥貴族の後押し無しでは考えられない。
だが「全ての権力を血統貴族へ」との旧い常識は、徹底的に洗い落とさねばならなかった。

(→youtube)
論語の本章の「温」を”旧来の学問を究める”と解したのは漢代の儒者だが、それは彼らの金儲けのためだった。旧来の学問に誰より通じていたのは、他ならぬ儒者だったからだ。古い情報を偽造までして独占した儒者は、自分らの宣伝に余念が無かった。その必要があったからだ。
前漢では武帝の時代にいわゆる儒教の国教化が行われたが、まだ他学派も力を持っていた。武帝没後に重臣の霍光は、武帝の不始末の後始末のため、実績の無い青二才の儒者を、帝国全土から呼び寄せて気勢を上げた(論語八佾篇4付記)。後世の文革によく似ている。
だが儒家に属さない重臣の桑弘羊に、青二才どもは一喝されてしまった。これが『塩鉄論』の内容で、その様子を、のちの宣帝はじっと見ていた。だから即位後、儒者を「古証文を真理であるかのように言いふらしているうつけ者」(『漢書』元帝紀)と罵倒した。
新古の注は次の通り。
古注『論語集解義疏』
此章明為師之難也溫温燖也故謂所學已得之事也所學已得者則溫燖之不使忘失此是月無忘其所能也新謂即時所學新得者也知新謂日知其所亡也若學能日知所亡月無忘所能此乃可為人師也

この章は、教師にふさわしい人間であることの困難を言っている。温とは温め直すことである。一度学んだ知識を、温め直すように常に復習して手入れすれば、忘れるという事が無い。これを”月ごとに身につけた知識を忘れない”というのである。新とは新たに得た知識のことである。知新とは、日々の記憶喪失を取り戻す行為である。毎日これに努めて、毎月忘れるという事から逃れ得たら、他人の教師になれるのである。
新注『論語集注』
言學能時習舊聞,而每有新得,則所學在我,而其應不窮,故可以為人師。若夫記問之學,則無得於心,而所知有限,故學記譏其「不足以為人師」,正與此意互相發也。

朱子「学習に当たって、時々過去の情報を習い覚え、そのたびごとに新しい発見があるなら、それは自分を教師に学んでいるということに他ならず、それゆえに行き詰まることが無いから、他人の教師になれるのである。ただチクチクと暗記に励むだけでは、心に気付きという事が無い。だから知識に限りが出来てしまうので、『学記』はそれをたしなめて、”他人の教師になる資格が無い”と言ったのだ。このこころに同意する者なら、互いに啓発し合えることだろう。
孔子は論語のあちこちに見られるように、当時の平均寿命である三十代を超え四十代になっても、新しい知識を貪欲に学ぶ人だった(論語述而篇16など)。孔子の見聞範囲は論語時代の貴族としては広い方だが、中国全土を股に掛けた弟子の子貢ほどではなかったはず。

しかしその子貢が、孔子没後に至るまで師を敬い、くさす人物には食ってかかったのが論語から分かる(論語顔淵篇8など)。子貢の言では、孔子は日月ほども高い存在で、その学識は自分には到底及ばないという。そう言わせるだけの勉強を、孔子が止めなかったからだろう。
論語を読んでいると、礼法や古典など、孔子がいわゆる文系知識だけを教えたように思いがちだが、同時代史料にまで視野を及ぼすと、論語時代としては文理両方に通じた教養人であり、その博物学的知識は外国使節をも驚かせている(『史記』)。専門バカではなかったのだ。
実際孔子は、自分が多芸なのを半ばさげすみつつも、専門バカにはならないと明言している(論語憲問篇34)。弟子に厳しい要求をするからには、自分にもまた厳しくなければならないと思っていただろうし、そうでなければドライな中国人のことだから、弟子は逃げただろう。
余話
古だった理由
「温故知新」と言えば、1972年のいわゆる日中国交正常化を想起する諸賢もおられよう。田中首相と大平外相が、周恩来総理との交渉を終えた後、毛沢東の私邸に揃って向かったとき、毛沢東は「喧嘩はもう済みましたか。喧嘩をしないと仲良くなれません」と言ったとされるのも名高い。その公式記録に当たることは出来なかったが、おそらくは事実なのだろう。
当時外相だった大平正芳氏は、台湾とのつながりが強い自民党の有力者の中にあって、最も早く中共政権との国交樹立を主張した一人と言われる。のちに首相になった際には、再度中国を訪問し、その時西安で大平氏が揮毫したのが「溫古知新」だったという。
大平首相に、「古」が「故」を意味しうるという、金文の知識があったとは思えないが、一橋→大蔵省入りのエリートが、誤字で「古」と書くほど無教養でもなかろう。「反故紙」という日本語があるぐらいだから、「故」「古」どちらも”ふるい”を意味すると知っていたはずだ。
またおそらくは新注の読みで、「ふるきをたずねてあたらしきをしる」と覚えておられただろうと想像するが、なぜあえて「古」と揮毫したのだろうか?
おそらくこの揮毫には、金印など古くは弥生時代に始まる日中の交流に加え、まだ真新しい日中戦争の記憶を忘れない、そして両国の新時代を開こうという決意が込められていたに違いない。戦禍の記憶が、「事故」を想像させかねない「故」を避けさせたのだろうか。
中国側も何ら苦情を言い立てずその揮毫を受け取り、現在でも西安の博物館に収蔵されているという。ただし展示はされておらず、それなりに地位のある人が依頼をして、やっと倉庫から出して見せて貰えるという。今後末永く、保存されるとよいのだが。
なお「故」を「古」と記した論語の版本は、定州本~慶大本を含め、日本伝承・中国伝承共に見当たらない。日本伝承の中でも文字列が特異な文明本は、前章の後半と本章の経(本文)を含めた前半を、1ページ丸ごと欠く。論語の伝承について詳細は「論語の成立過程まとめ」を参照。
原始論語?…→定州竹簡論語→白虎通義→ ┌(中国)─唐石経─論語注疏─論語集注─(古注滅ぶ)→ →漢石経─古注─経典釈文─┤ ↓↓↓↓↓↓↓さまざまな影響↓↓↓↓↓↓↓ ・慶大本 └(日本)─清家本─正平本─文明本─足利本─根本本→ →(中国)─(古注逆輸入)─論語正義─────→(現在) →(日本)─────────────懐徳堂本→(現在)



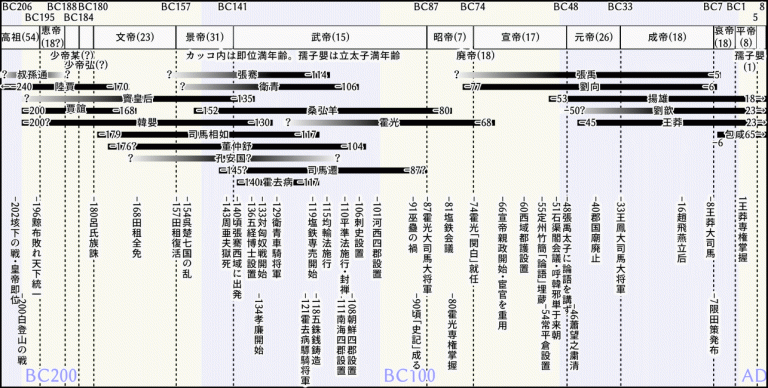


コメント