論語:原文・書き下し
原文(唐開成石経)
子謂仲弓曰犁牛之子騂且角雖欲勿用山川其舍諸
校訂
東洋文庫蔵清家本
子謂仲弓曰犁牛之子騂且角雖欲勿用山川其舍諸
後漢熹平石経
(なし)
定州竹簡論語
(なし)
標点文
子謂仲弓曰、「犁牛之子、騂且角、雖欲勿用、山川其舍諸。」
復元白文(論語時代での表記)





















※犁→利・欲→谷。論語の本章は、「其」の用法に疑問がある。
書き下し
子、仲弓を謂ひて曰く、犁牛之子、騂くして且つ角あらば、用ゐる勿らんと欲むと雖も、山川、其れ諸を舍かむや。
論語:現代日本語訳
逐語訳

先生が仲弓を評して言った。「スキを引かせる牛の子でも、毛並みが赤くて角が立派なら、生け贄にしないでおこうと思っても、山や川の神はなんともはや、決してそれらを捨てないことよ。」
意訳

冉雍や、百姓家の牛に生まれても、毛並みや角が立派なら、着飾って祭りに出るものだ。お前も身分が低いからと言って、卑屈になることはない。大地の精霊はきっと、認めてくれるだろうよ。
従来訳
先師は仲弓のことについて、こんなことをいわれた。――
「まだら牛の生んだ子でも、毛が赤くて、角が見事でさえあれば、神前に供えられる資格は十分だ。人がそれを用いまいとしても、山川の神々が決して捨ててはおかれないだろう。」下村湖人『現代訳論語』
現代中国での解釈例
孔子講到仲弓時,說:「他雖然出身貧寒,但他卻象小牛犢一樣,長出了紅紅的毛、尖尖的角,適宜於祭祀山神,即使沒人想用,山神也不會答應。」
孔子が仲弓に講義していたときに、言った。「彼が貧しい生まれだからといって、もし彼が子牛のように、成長して真っ赤な毛、尖った角が生えたら、山の神を祀るのに丁度いいから、誰も用いようと考えなくとも、山の神なら応じるしかなくなる。」
論語:語釈
子(シ)


(甲骨文)
論語の本章では、冒頭「子謂仲弓曰」では”(孔子)先生”。「犁牛之子」では”こども”。初出は甲骨文。字形は赤ん坊の象形。春秋時代では、貴族や知識人への敬称に用いた。季康子や孔子のように、大貴族や開祖級の知識人は「○子」と呼び、一般貴族や孔子の弟子などは「○子」と呼んだ。詳細は論語語釈「子」を参照。
謂(イ)


(金文)
論語の本章では”言う”。本来、ただ”いう”のではなく、”~だと評価する”・”~だと認定する”。下掲新注で朱子が「冉雍に直接言った話ではない」と語った説に、この漢語はある程度の根拠を提供している。現行書体の初出は春秋後期の石鼓文。部品で同義の「胃」の初出は春秋早期の金文。金文では氏族名に、また音を借りて”言う”を意味した。戦国の竹簡になると、あきらかに”~は~であると言う”の用例が見られる。詳細は論語語釈「謂」を参照。
仲弓(チュウキュウ)


(甲骨文)
孔子の弟子、孔門十哲の一人、冉雍仲弓のこと。詳細は論語の人物:冉雍仲弓を参照。『史記』弟子伝には「仲弓父,賤人」とあり、父親の身分が低かったという。ただし孔子も「吾少也賤」”私も若い頃は身分が低かった”と言った事に論語子罕篇6ではなっている。文字的には論語語釈「仲」・論語語釈「弓」を参照。
曰(エツ)


(甲骨文)
論語で最も多用される、”言う”を意味する言葉。初出は甲骨文。原義は「𠙵」=「口」から声が出て来るさま。詳細は論語語釈「曰」を参照。
犁(リ/レイ)


(前漢隷書)
論語の本章では”まだら牛”。論語では本章のみに登場。初出は前漢の隷書。論語の時代に存在しない。論語時代の置換候補もない。「リ」の音で”まだらうし”を、「レイ」の音で”からすき(ですく)”を意味する。「からすき」は動物に引かせる大型のすき。「犂」は異体字。字形は”からすき”+「人」+「牛」で、からすきで土を耕すさま。原義は”すく”。詳細は論語語釈「犁」を参照。

中国史上、論語の時代=春秋時代は鉄器の普及期で、牛耕もこのころ始まったとされる。従ってスキを牽くウシもいたはずだが、「犂」とは呼ばれていなかったのだろう。そこで、鋭い刃物を牽いた牛=「利牛」と書かれたと考える。
なお武内本には、「犁牛は雑文の牛祭祀の用に当たらず、騂は赤色、赤牛以て山川を祭る。仲弓の父賎しけれど其子の賢を害せざるに譬う」とある。
牛(ギュウ)


甲骨文/牛鼎・西周早期
初出は甲骨文。字形は牛の象形。原義は”うし”。西周初期まで象形的な金文と、簡略化した金文が併存していた。甲骨文では原義に、金文でも原義に、また人名に用いた。詳細は論語語釈「牛」を参照。
之(シ)


(甲骨文)
論語の本章では、”…の”。初出は甲骨文。字形は”足”+「一」”地面”で、あしを止めたところ。原義はつま先でつ突くような、”まさにこれ”。殷代末期から”ゆく”の語義を持った可能性があり、春秋末期までに”…の”の語義を獲得した。詳細は論語語釈「之」を参照。
騂(セイ)


(甲骨文)(篆書)
論語の本章では”あかい”。論語では本章のみに登場。初出は甲骨文。ただし字形は上下に「羊」+「牛」で、篆書の段階でへんとして「馬」が加わり。さらに前漢の隷書でつくりが省略されて現行書体となる。原義は”犠牲獣”。甲骨文では原義に用い、金文では”赤い犠牲獣”、”赤い”の意に用いた。詳細は論語語釈「騂」を参照。
犠牲獣の色は王朝によって異なるとされ、周では赤を重んじ、論語の堯曰篇2では、夏王朝では玄だったとし、殷の湯王が「あえて玄牡を用いて」と言っている。探し回ったが殷にふさわしい色の牛が居なかったか、まだ色が決まっていなかったか、そもそもでっちあげだろう。
且(シャ)


(甲骨文)
論語の本章では”その上”。初出は甲骨文。字形は文字を刻んだ位牌。甲骨文・金文では”祖先”、戦国の竹簡で「俎」”まな板”、戦国末期の石刻文になって”かつ”を意味したが、春秋の金文に”かつ”と解しうる用例がある。詳細は論語語釈「且」を参照。
角(カク)


(甲骨文)
論語の本章では”つの”。論語では本章のみに登場。初出は甲骨文。入声で屋-来の音は不明。字形はつのの象形。原義は”つの”。「漢語多功能字庫」によると、甲骨文では地名に、金文では”慎み深い”の意に用いた。戦国の竹簡では原義に用いた。詳細は論語語釈「角」を参照。
雖(スイ)


(金文)
論語の本章では”たとえ…でも”。初出は春秋中期の金文。字形は「虫」”爬虫類”+「隹」”とり”で、原義は不明。春秋時代までの金文では、「唯」「惟」と同様に使われ、「これ」と読んで語調を強調する働きをする。また「いえども」と読んで”たとえ…でも”の意を表す。詳細は論語語釈「雖」を参照。
欲(ヨク)


(楚系戦国文字)
論語の本章では”求める”。初出は楚系戦国文字。新字体は「欲」。同音は存在しない。字形は「谷」+「欠」”口を膨らませた人”。部品で近音の「谷」に”求める”の語義がある。詳細は論語語釈「欲」を参照。
勿(ブツ)


(甲骨文)
論語の本章では”~しない”。初出は甲骨文。金文の字形は「三」+「刀」で、もの切り分けるさまと解せるが、その用例を確認できない。甲骨文から”無い”を意味し、西周の金文から”するな”の語義が確認できる。詳細は論語語釈「勿」を参照。
用(ヨウ)


(甲骨文)
論語の本章では、”用いる”。初出は甲骨文。字形の由来は不詳。ただし甲骨文で”犠牲に用いる”の例が多数あることから、生け贄を捕らえる拘束具のたぐいか。甲骨文から”用いる”を意味し、春秋時代以前の金文で、”…で”などの助詞的用例が見られる。詳細は論語語釈「用」を参照。
山(サン)


(甲骨文)
論語の本章では、”山(の神)”。初出は甲骨文。「セン」は呉音。甲骨文の字形は山の象形、原義は”やま”。甲骨文では原義、”山の神”、人名に用いた。金文では原義に、”某山”の山を示す接尾辞に、氏族名・人名に用いた。詳細は論語語釈「山」を参照。
川(セン)


(甲骨文)
論語の本章では”川(の神)”。初出は甲骨文。字形は川の象形”。げんぎは”かわ”。甲骨文では原義、”洪水”、地名に用い、金文では原義に加えて耕地の単位の意に用いた。戦国の竹簡では、”従う”、”大地”、”穴を開ける”の意に用いた。詳細は論語語釈「川」を参照。
其(キ)


(甲骨文)
論語の本章では”まったく”という強調。この語義は春秋時代では確認できない。
『学研漢和大字典』「其」条
②「それ」とよみ、
- 感嘆・強調などの語気を示す。▽「其~乎(哉・矣・也)(与)」は、「それ~かな」とよみ、「なんと~だなあ」と訳す。感嘆の意を示す。「語之而不惰者、其回也与=これに語(つ)げて惰(おこた)らざる者は、それ回なるか」〈話をしてやって、それに怠らないのは、顔淵だけだね〉〔論語・子罕〕
- 「そもそも」「なんと」と訳す。反語・感嘆を強調する意を示す。▽多く文頭に使用され、物事の起源・原因などをのべる。「其言之不俊、則為之也難=それ言の怍(は)ぢざるは、則(すなは)ちこれを為すや難(かた)し」〈そもそも自分の言葉に恥じないようでは、それを実行するのは難しい〉〔論語・憲問〕
- 「もし~ならば」と訳す。仮定を強調する意を示す。▽多く仮定の意を示す語とともに用いる。「其如是、孰能禦之=それかくの如(ごと)くんば、孰(いづれ)かよくこれを禦(とど)めん」〈もしこのような時、いったい誰が抑えとどめることができるでしょう〉〔孟子・梁上〕
字の初出は甲骨文。原義は農具の箕。ちりとりに用いる。金文になってから、その下に台の形を加えた。のち音を借りて、”それ”の意をあらわすようになった。人称代名詞に用いた例は、殷代末期から、指示代名詞に用いた例は、戦国中期からになる。詳細は論語語釈「其」を参照。
舍(シャ)


(甲骨文)
論語の本章では”放置する”。「宿舎」のように”いえ”の意で用いられることが多いが、『字通』によると”捨てる”が原義だという。初出は甲骨文。新字体は「舎」。下が「𠮷」で「舌」ではない。字形は「𠆢」”屋根”+「干」”柱”+「𠙵」”くち=人間”で、人間が住まう家のさま。原義は”家屋”。春秋末期までの金文では”捨てる”、”与える”、”発布する”、”楽しむ”の意、また人名に用い、戦国の金文では一人称に用いた。戦国の竹簡では人名に用いた。
論語では全て”顧みない・置く・隠す”の語義で用いられる。現行の「捨」の初出は後漢の説文解字で、それまでは「舎」が”すてる”の語義を兼任した。詳細は論語語釈「舎」を参照。
諸(ショ)


(秦系戦国文字)
論語の本章では”その条件に合うさまざまな存在”。天下に必ず複数いるであろう”角があって赤い立派な牛”たちを指す。論語の時代では、まだ「者」と「諸」は分化していない。「者」の初出は西周末期の金文。現行字体の初出は秦系戦国文字。金文の字形は「者」だけで”さまざまな”の意がある。詳細は論語語釈「諸」を参照。

「諸」は「之乎」の合字で”これを”と読む漢文業界の座敷わらしになっている。合字だと言い出したのは清儒で、最古の文献である論語には、安易に当てはめるべきではない。
論語:付記
検証
論語の本章は、全文が前漢中期成立の『史記』弟子伝にあるが、前漢後期初めの定州竹簡論語には欠けている。また先秦両漢で引用・再録したのは、他に後漢前期の『漢書』樊噲伝の論賛のみで、論語の一章として確認できるのは前漢から南北朝にかけて成立した古注から。
古注『論語集解義疏』
…註犁雜文也騂赤色也角者角周正中犧牲也雖欲以其所生犁而不用山川寜有舍之乎言父雖不善不害於其子之美也
注釈。犁とはまだら模様があることである。騂は赤色である。角はつのの形がどこも立派で犠牲にするのに適しているというのである。雖欲とは、生まれがまだら模様だから犠牲に用いないでおこうということである。だが山川の神は却って用いようとするのである。舍というのは、父が善人でなくともその子の美点を損ないはしないという事である。
ただ文字史的には論語の時代まで遡れる上、用法上の疑問も少ないことから、論語の本章は史実として扱って構わない。
解説
孔子の弟子の中で、冉雍仲弓は顔淵と同じく、何をやったか事跡が明らかでないにもかかわらず、偉い人物ということになっている。顔淵を称揚したのは前漢前期の董仲舒でほぼ確定で、それはいわゆる儒教の国教化政策の一環として行われた。拝む対象が要り用だったからだ。
董仲舒についてより詳しくは、論語公冶長篇24余話を参照。
だが冉雍の称揚運動は聞かないし、後世の儒者も、冉雍を誉める本章を引用や再録したがっていない。冉雍を称揚することで何か現世利益があるとも思えないから、論語の本章が論語に加わったのは少なくとも、何らかの史実を反映しているからだろう。
そして儒者がこぞって根拠無く冉雍の父親の悪口を言う。例として新注を挙げる。
新注『論語集注』
犁,利之反。騂,息營反。舍,上聲。犁,雜文。騂,赤色。周人尚赤,牲用騂。角,角周正,中犧牲也。用,用以祭也。山川,山川之神也。言人雖不用,神必不舍也。仲弓父賤而行惡,故夫子以此譬之。言父之惡,不能廢其子之善,如仲弓之賢,自當見用於世也。然此論仲弓云爾,非與仲弓言也。

犁の字は、利之の反切で読む。騂の字は、息営の反切で読む。舍は尻上がりに読む。犁はまだら模様のことである。騂は赤色である。周の人は赤色を尊んだので、犠牲には色の赤い動物を用いた。角とは、つのが申し分なく整っており、犠牲にするのにふさわしいことをいう。用とは、それでもって血祭りをすることである。山川とは、山川の神である。人が誰も用いようとしなくとも、神は必ず捨てておかない、と書いてある。
仲弓の父は身分が低い上に悪党だった。だから孔子先生はこのようなたとえ話をしたのである。父親がどんなに悪くとも、その子の善良を無いことには出来ないと言っている。仲弓ほどの才能があれば、放置しても世の中に役立つ人材として立ち現れるというのである。ただしここで仲弓がうんぬんとは、仲弓自身に聞かせた話ではない。
范氏曰:「以瞽瞍為父而有舜,以鯀為父而有禹。古之聖賢,不係於世類,尚矣。子能改父之過,變惡以為美,則可謂孝矣。」

范祖禹「瞽瞍のような悪党の父親の子に聖王の舜がいた。鯀のような悪党の父親の子に聖王の禹がいた。昔の聖人賢者は、人の血統をどうこう言う事無く、聖人賢者を尊んだ。子は父親の悪行を叩き直す事が出来て、悪党を善人に仕立て上げることこそ、まことの孝行というものである。」
…無茶言うなよ、あんた方。息子に聞く耳持たないからクソおやじなのである。
余話
激動の世でのし上がる
現代人の感覚では、犠牲獣にされて殺されるより、スキは牽かされるが生きていた方が幸せと思うのだが、古代人はそう考えないらしい。もっとも古代人と言っても『荘子』などでは、訳者と同じような感想を犠牲獣について言っている。

荘子が濮水で釣りをしていた。楚王が家老二人を使いに寄こして、目通りするかどうか尋ねさせた。
家老「どうか国内の政治をお取り下さい。」
荘子は竿を持ったまま、振り返りもせずに言った。
「噂では、楚国には神の如き亀の甲羅があるとか。死んでもう三千年になるのに、楚王は甲羅を布に包み、箱にしまって、祖先祭殿の上座に置いているとか。さて諸君、この亀は死んで甲羅を崇められるのがいいのか、それとも生きて泥の中でしっぽを引いていた方がいいのか、どっちだろうね。」
家老「生きて泥の中、でしょう。」
荘子「お行きなさい。私も泥の中でしっぽを引くとしよう。」(『荘子』外篇・秋水)
論語の本章で訳者が引っかかっている一点もここにある。孔子は神を説かなかった。詳細は孔子はなぜ偉大なのかを参照。その孔子が出自の低さを悩む弟子に、山川の神々を持ち出して慰めるだろうか。慰める優しい師匠だったかも知れないが、むしろ孔子なら言っただろう。
「冉雍よ。新興氏族の生まれを気に病むことは無い。見よ、血統だけに頼る貴族は時代の流れについて行けず、右往左往し没落しているではないか。生まれの良さが、却ってあだになっている。だからお前はひたすら学びひたすら稽古し、この激動の世でのし上がるのだ。」
…と。ゆえに本章を、まるまる史実とは信じたくないのである。



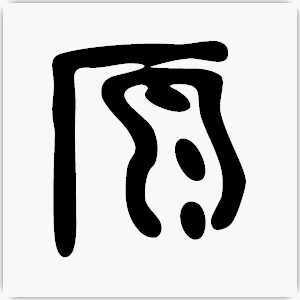

コメント