論語:原文・白文・書き下し
原文・白文
子貢問曰、「有一言而可以終身行*之者乎。」子曰、「其恕乎。己所不欲、勿施於人*。」
校訂
武内本
清家本により、文末唐石経行の下之の字あり、章末也の字なし。
定州竹簡論語
子貢問曰:「有壹a言而可b終身[行c者乎?」子曰:「其恕乎]!437
- 壹、今本作”一”。
- 近本”可”下有”以”字。
- 阮本”行”下有”之”字。
→子貢問曰、「有壹言而可終身行者乎。」子曰、「其恕乎。己所不欲、勿施於人。」
復元白文(論語時代での表記)




























※貢→江・恕→如・欲→谷・施→(甲骨文)。論語の本章は恕の字が論語の時代に存在しない。”思いやり”の意では、置換候補が無い。「身」「行」の用法に疑問がある。「可以」は戦国中期にならないと確認できない。本章は漢帝国の儒者による捏造の可能性がある。
書き下し
子貢問ふて曰く、壹言にし而身を終ふるまで行ふ可き者有らん乎。子曰く、其れ恕乎。己の欲せざる所、人於施す勿れ。
論語:現代日本語訳
逐語訳


子貢が訊ねて言った。「一言で、生涯を終えるまで行うことが出来るものはありますか。」先生が言った。「それは我が身に引き比べて他人を思いやることか。自分が求めないことは、人に施すな。」
意訳


子貢「一生守り続けられる教えってありますかね?」
孔子「そりゃあ恕だろうな。他人を自分と思え。要するに、されたくないことは、人にするな。」
従来訳
子貢がたずねた。――
「ただ一言で生涯の行為を律すべき言葉がございましょうか。」
先師がこたえられた。――
「それは恕だろうかな。自分にされたくないことを人に対して行わない、というのがそれだ。」下村湖人『現代訳論語』
現代中国での解釈例
子貢問:「有一個字可以終身奉行嗎?」孔子說:「那就是恕字吧?自己不願意的,不要強加於人。」
子貢が問うた。「生涯心得ておく価値のある言葉で、たった一字のはありますか?」孔子が言った。「それは恕の字だろうか。自分が願わないことを、人に強制してはいけない。」
論語:語釈
可以(カイ)→可(カ)
論語の本章では”~できる”。現代中国語でも同義で使われる助動詞「可以」。ただし出土史料は戦国中期以降の簡帛書(木や竹の簡、絹に記された文書)に限られ、論語の時代以前からは出土例が無い。春秋時代の漢語は一字一語が原則で、「可以」が存在した可能性は低い。ただし、「もって~すべし」と一字ごとに訓読すれば、一応春秋時代の漢語として通る。
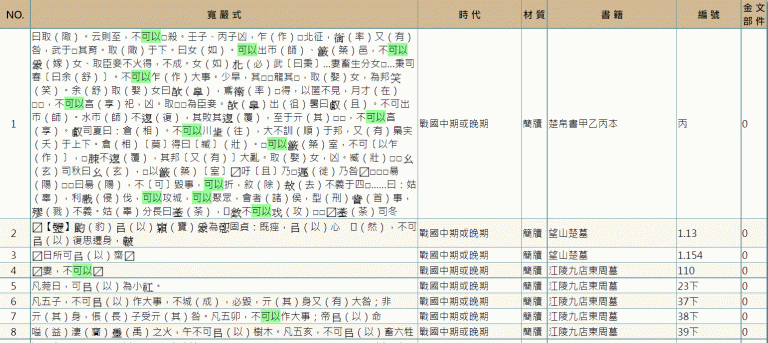
「先秦甲骨金文簡牘詞彙庫」


「可」(甲骨文)
定州竹簡論語は「以」を欠く。「可」の初出は甲骨文。字形は「口」+「屈曲したかぎ型」で、原義は”やっとものを言う”こと。甲骨文から”~できる”を表した。日本語の「よろし」にあたるが、可能”~できる”・勧誘”…のがよい”・当然”…すべきだ”・認定”…に値する”の語義もある。詳細は論語語釈「可」を参照。


「以」(甲骨文)
「以」の初出は甲骨文。人が手に道具を持った象形。原義は”手に持つ”。論語の時代までに、名詞(人名)、動詞”用いる”、接続詞”そして”の語義があったが、前置詞”~で”に用いる例は確認できない。ただしほとんどの前置詞の例は、”用いる”と動詞に解せば春秋時代の不在を回避できる。詳細は論語語釈「以」を参照。
身(シン)


(甲骨文)
論語の本章では”生涯”。この語義は春秋時代に確認できない。初出は甲骨文。甲骨文では”お腹”を意味し、春秋時代には”からだ”の派生義が生まれた。詳細は論語語釈「身」を参照。
行(コウ)


(甲骨文)
論語の本章では”行う”。初出は甲骨文。「ギョウ」は呉音。十字路を描いたもので、真ん中に「人」を加えると「道」の字になる。甲骨文や春秋時代の金文までは、”みち”・”ゆく”の語義で、”おこなう”の語義が見られるのは戦国末期から。詳細は論語語釈「行」を参照。
恕

(篆書)
論語の本章では、”自分のように他人を思いやること”。この字は論語の時代に存在しない。カールグレン上古音はɕi̯o(去)。「如」ȵi̯o(平)と一語で言ったか、「如心」と二文字で書いた可能性はある。詳細は論語語釈「恕」を参照。
論語の本章が史実の孔子の言葉と仮定すると、「如」には”同じくする”との語釈が『大漢和辞典』にあり、本章は「其れ如る乎」と読み下し、”他人と自分を同じに扱う”の意となる。詳細は論語における「恕」を参照。
欲

(金文大篆)
論語の本章では、”求める”。初出は戦国文字。論語の時代に存在しない。ただし『字通』に、「金文では谷を欲としてもちいる」とある。『学研漢和大字典』によると、谷は「ハ型に流れ出る形+口(あな)」の会意文字で、穴があいた意を含む。欲は「欠(からだをかがめたさま)+(音符)谷」の会意兼形声文字で、心中に空虚な穴があり、腹がへってからだがかがむことを示す。空虚な不満があり、それをうめたい気持ちのこと、という。詳細は論語語釈「欲」を参照。
勿


(甲骨文・金文)
論語の本章では、”~するな”。初出は甲骨文。『学研漢和大字典』によると象形文字で、さまざまな色の吹き流しの旗を描いたもの。色が乱れてよくわからない意を示す。転じて、広く「ない」という否定詞となり、「そういう事がないように」という禁止のことばとなった、という。詳細は論語語釈「勿」を参照。
施

(金文大篆)
論語の本章では、”他人に行う”。
初出は戦国文字で、論語の時代に存在しない。カールグレン上古音はɕia(平/去)またはdia(去)で、前者の同音は鉈(ほこ・なた)・弛(ゆるむ)と施を部品とする漢字群。後者の同音は移などだが、いずれも”ほどこす”意を持ちながら、論語の時代に存在した文字は無い。
論語時代の置換候補は異体字の「𢻫」。春秋末期までに、”のばす”・”およぼす”の意がある。詳細は論語語釈「施」を参照。
論語:付記
「己所不欲、勿施於人」は同じ事を子貢が論語公冶長篇11で述べているが、そこでは子貢おとしめ話になっている。
孔子「子貢よ、それはお前には出過ぎた望みだぞ。」
論語の本章でこの通り教えておきながら、子貢がそのように言うとたしなめた、とあるのが事実なら、孔子は相当に性格が悪いバカ教師であることになる。従って本章か公冶長篇かどちらかが、後世のでっち上げという事になるが、上掲の通り文字史的には本章が怪しい。
だが公冶長篇も「也」を句末で用いており、その意味では全き孔子の発言と断じることは出来ない。それでも孔子が現行の「恕」と言った可能性は無く、論語の本章は前漢帝国の儒者がでっち上げた、新しい恕という概念を、ニセ孔子によって権威づけた疑いがある。
ただし塩冶判官が出てこない忠臣蔵に客が入らないように、恕の出てこない論語などとんでもない、と言われそうなので、もう少し言い訳をする。孔子没後にほぼ滅びていた儒家を再興したのは、一世紀後の孟子だが、現伝『孟子』では「恕」が用いられた箇所は一箇所しか無い。
孟子曰:「萬物皆備於我矣。反身而誠,樂莫大焉。強恕而行,求仁莫近焉。」

孟子が申しました。「全てのものがこの身に備わっている。自分自身を反省して誠実を尽くせば、人生を大いに楽しめる。出来る限り人を思いやるよう努めるなら、仁=常時無差別の愛を実現するのに、これほど適した道は無い。」(『孟子』盡心上4)
自説を常にしゃべっていないと死んでしまいそうな孟子が、仮に「恕」の発明者だったら、もっとベラベラと説教するはずで、たった一文字しかないというのは、孟子の発明でないことを示しているだろう。孟子から60年後、戦国末期の荀子にも同様に、一箇所しか言及がない。
孔子曰:「君子有三恕:有君不能事,有臣而求其使,非恕也;有親不能報,有子而求其孝,非恕也;有兄不能敬,有弟而求其聽令,非恕也。士明於此三恕,則可以端身矣。」


孔子「君子は三種類の”恕”を身につけねばならぬ。とうてい仕えられないバカ殿が、”ワシに仕えよ”と求めるのは、恕ではない。恩返しする気にもならないバカ親がいて、子供に”孝行しろ”と求めるのは、恕ではない。尊敬する気にもならないバカ兄がいて、”俺の言う通りにしろ”と弟に言うのは、恕ではない。君子たる者この三つをわきまえて、やっと身持ちをすがすがしく出来るのだ。」(『荀子』法行7。ほぼ同文が『孔子家語』三恕1にある)
孔子に言わせた時点でニセなのだが、「恕」とこのニセは、荀子が言い出したのだろうか。荀子は孟子と違って、自説をわあわあと言い回るような男ではなかった。大国斉の筆頭家老を数度にわたって務め、学士院の親分だった荀子は、孟子ほど意地汚くなる動機が無いからだ。
故に一箇所だけでも不思議は無い。加えて荀子の時代から、「恕」の字が発掘されている。
というわけで、儒家における「恕」の発明は荀子だと言ってよかろうが、論語の本章で従来解されたような、相手の身になって思いやることではない。上掲の言葉はどう読んでも、「お互い様」の精神を言っているだけであり、頼まれもせぬのに思いやれ、とは言っていない。
では現伝儒教の言う「恕」は、秦帝国の儒者による改造なのか。悪名高い焚書坑儒は後半がでっち上げだが、それでも秦代の儒者は始皇帝が怖くて、不真面目な捏造に励めなかった。大部な『呂氏春秋』に、「怒」の誤字と思える一箇所を除き、「恕」はただの一字も出て来ない。
鄭公子歸生率師伐宋。宋華元率師應之大棘,羊斟御。明日將戰,華元殺羊饗士,羊斟不與焉。明日戰,恕謂華元曰:「昨日之事,子為制;今日之事,我為制。」遂驅入於鄭師。宋師敗績,華元虜。

春秋時代中期、鄭の公子帰生が宋に攻め込み、宋の華元が軍を率いて大棘の地で迎え撃とうとした。華元の乗る車の御者を羊斟と言った。戦いの前日、華元は士気を上げようと、高価な羊のスープを作らせて将兵に振る舞った。「うまいうまい」と早い者勝ちでみなが食い尽くしてしまい、羊斟はお預けを食らわされた。
翌日戦いが始まると、羊斟は華元に怒りをぶちまけた。「昨日の振る舞いは閣下の思い通りになったが、今日の戦いは私の好きなようにさせて貰う。」そう言ってビシバシと馬に鞭打って車を走らせ、味方を振り切ってどんどん進んだばかりか、勢いのまま鄭の陣のまっただ中に突っ込んだ。指揮官を失って宋軍は大敗、華元はそのまま捕虜になった。(『呂氏春秋』察微4)
この話はあるいは、『平家物語』「子牛健児」の元ネタかもしれないが、今は措く。ともあれ大富豪で時の権力者を兼ねた男が、「この世の全てを網羅し尽くす」と豪語した百科全書に、「恕」が事実上ただの一字も無いことから、現伝「恕」の概念は秦儒の創作ではあるまい。
すると本章は、恐らく前漢の儒者による改作。『礼記』『説苑』はじめ、前漢儒者の書き物には、盛んに「恕」が出てくるし、論語の本章のような好意の押しつけとして記されている。戦国末期に「お互い様」として登場した「恕」は、かくして儒家のスローガンとなった。
清の康煕帝と言えば、満洲人王朝の清を儒教化しようとせっせと働いた皇帝だが、その御代に焦袁熹という、隠れた賢者がいたらしい。もちろん政治ショーの結果で賢者とされたのであり、隠れた「賢者」を召し出して重用すると、清朝に対する世間の評判が上がるからである。
十七年,詔曰:「自古一代之興,必有博學鴻儒,備顧問著作之選。我朝定鼎以來,崇儒重道,培養人才。四海之廣,豈無奇才碩彥、學問淵通、文藻瑰麗、追蹤前哲者?凡有學行兼優、文詞卓越之人,不論已仕、未仕,在京三品以上及科、道官,在外督、撫、布、按,各舉所知,朕親試錄用。其內、外各官,果有真知灼見,在內開送吏部,在外開報督、撫,代為題薦。」

康煕十七年(1678)、康煕帝は詔書を下して命じた。
「昔より王朝が繁栄する時は、必ず博識な大学者がおり、君主の相談役や勅語の添削役に当たっていた。我が清朝もまた帝国を創業して以来、儒学を尊び道教を重んじて、人材を育成しようと努めてきた。
だが天下は広く、どこかに一芸に秀でた者や、計りがたいもの知りが隠れていて、学問に深く通じ、素晴らしい文章を書き、いにしえの哲人に近づこうとしているか、知れたものではない。朕はそうした在野の賢者を求めておる。
ゆえに学問と人格が伴い、文章に卓越した者をもし見知っているならば、すでに出仕しているかどうかを問わず推薦するよう、次の者どもに命ずる。帝都在勤の三品以上の官位を持つ科挙合格者と道教監督官、地方の総督・巡撫(準総督)・民政長官・監察長官。
推薦された者は朕自ら試験し、優秀な者は取り立てる。また帝都と地方の役人で、まことに優れた見識を持つ者がいれば、帝都の者は吏部(人事院)に、地方の者は総督・巡撫に報告し、報告を受けた長官は、報告者の代わりに推薦状を記し、朕に届けよ。」(『清史稿』選挙志・制科薦擢)
「隠れた賢者」とは言い換えると、王朝にとって〒囗刂ス卜予備軍に他ならない。清朝は少数の満洲人が膨大な漢人を治めるという事情から、こうやって下手に出て不満の回収に努めた。これは清朝のみならず歴代皇帝にとって、生死に関わる大問題だったからでもある。
中華帝国は煎じ詰めるとどれも同じで、支配層の強欲を下へ下へと押し付ける収奪機構に他ならないから、王朝は常に反乱の危険にさらされる。これは共和政になった今も変わらない。しかも中国のひねくれ知識人は日本人のように、大人しく配所の月を眺めたりしない。
世を儚んで身投げもしない。その少なからぬ者がテロに走り、反乱を煽った。叛乱軍の親玉は、ひねくれ知識人自身(ex.李元昊)でなければ筋肉ダルマだが、その場合も必ず参謀役にひねくれ知識人がいて悪知恵を授け(ex.張良)、どうかすると王朝は滅び帝室は皆殺しに遭う。
『鹿州公案』という、清の雍正帝期の記録がある。海沿いの寒村地帯に赴任した知事の日誌だが、王朝盛時のこんな田舎にもちゃんと山賊と海賊が揃っていて、必ずひねくれ知識人が参謀にいた。こういう連中も機会が無いだけで、時運に乗ればもちろん王朝を乗っ取る気でいた。
ともあれそんな「賢者」の書いた文に、康煕帝自ら題を付けてやったが、こう記している。
聖賢學問無不從人己相接處做工夫既有此身決無與人不交闗之理自家而國而天下何處無人何處不當行之以恕

聖賢の学問というものは、すべて人と人とのつながりの中で効果をあらわすものであり、すでに自分がこの世に生きているからには、人と関わらずに生きていくことなど決して出来ない。自分の家族から始まり、国や世界に至るまで、どの人に対しても、恕の精神で付き合うほかにないではないか。(『御製題此木軒四書説』巻六128)
古今東西変わりなく、一歩外を歩けば強欲な者が横行する人間界で、「どの人に対しても、恕の精神」とはメルヘンにも程がある。所詮は「あいつら中国を盗み取った野蛮人だ」と言われるのが嫌でしょうがない清朝の、愚民化政策の一環に過ぎない。
江戸の町人も、高師直が実は吉良上野介だと分かって観劇したわけで、まじめに論語を読もうとするなら承知すべきだろう。恕なんて孔子は言わなかったし、言っても如=”お互い様”と言っただけだ、と。帝大教授だって自分と同程度には如何わしいのだ。それが恕の精神である。

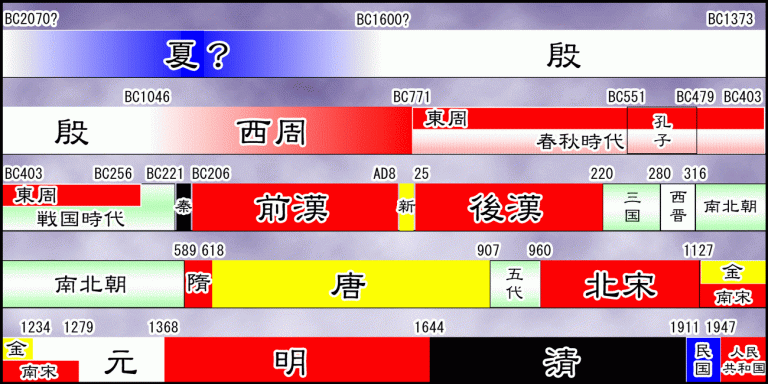
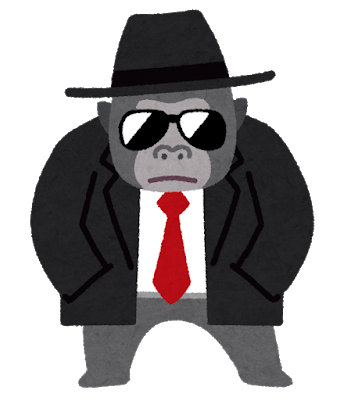

コメント