論語:原文・白文・書き下し
原文・白文
子曰、「君子不以言舉人、不以人廢言。」
校訂
定州竹簡論語
子曰:「君子不以言舉人,不以人廢言。」436
復元白文(論語時代での表記)














※舉→居・廢→祓(甲骨文)
書き下し
子曰く、君子は言を以て人を擧げず、人を以て言を廢てず。
論語:現代日本語訳
逐語訳

先生が言った。「君子は言葉で人をよいものとして評価しない。人で言葉を悪いものとして評価しない。」
意訳
甲
君子は、いい事を言ったからといってその人をよく思わないし、人が悪いからと言ってその言葉を捨て去りはしない。
乙
諸君。いいこと言う者がいい人とは限らないし、悪党の言葉にもいい言葉はある。
従来訳
先師がいわれた。――
「君子は、言うことがりっぱだからといって人を挙用しないし、人がだめだからといって、その人の善い言葉をすてはしない。」下村湖人『現代訳論語』
現代中国での解釈例
孔子說:「君子不會因為某人說話動聽而舉薦他,不會因為某人品德不好而不採納他的善意規勸。」
孔子が言った。「君子はする話を理由に話した人を誰かに勧めたりしないし、品性劣悪を理由に劣悪な人の善意から来る勧誘を断ったりしない。」
論語:語釈
君子

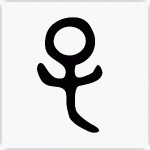
(金文)
論語の本章では、(1)庶民に対する”貴族”、(2)孔子から弟子に対する”諸君”という呼びかけ、の二つの解釈があり得る。”常時無差別の愛を持つ教養人”といった曖昧な語義は、孔子より一世紀後の孟子が唱えたもの。詳細は論語における「君子」を参照。
言(ゲン)


(甲骨文)
論語の本章では”ことば”。初出は甲骨文。字形は諸説あってはっきりしない。「口」+「辛」”ハリ・ナイフ”の組み合わせに見えるが、それがなぜ”ことば”へとつながるかは分からない。原義は”言葉・話”。甲骨文で原義と祭礼名の、金文で”宴会”(伯矩鼎・西周早期)の意があるという。詳細は論語語釈「言」を参照。
舉(挙)

(金文)
論語の本章では、”よいものとして持ち上げる”。初出は戦国時代の金文。論語の時代に存在しない。同音に居とそれを部品とする漢字群。居に”おく・すまわせる”の語釈が『大漢和辞典』にあり、ある人物をある地位に就けることを意味する。
『学研漢和大字典』によると與(ヨ)は手をそろえ、力をあわせて動かすこと。擧は「手+(音符)與」で、息を合わせて持ちあげること、という。詳細は論語語釈「挙」を参照。
人(ジン)


(甲骨文)
論語の本章では”他人”。初出は甲骨文。原義は人の横姿。「ニン」は呉音(遣隋使より前に日本に伝わった音)。甲骨文・金文では、人一般を意味するほかに、”奴隷”を意味しうる。対して「大」「夫」などの人間の正面形には、下級の意味を含む用例は見られない。詳細は論語語釈「人」を参照。
『学研漢和大字典』によると身近な親族や隣人を意味したが、孔子はその範囲を「四海同胞」というところまで拡大し、広く隣人愛の心を仁(ジン)(ヒューマニズム)と名づけた、とも著者の藤堂博士はいう。
訳者の見解はやや異なって、孔子は異民族を蛮族呼ばわりしてはばからない人だったし、利用するとなると、どんなお追従でも言ったから、仁の適用範囲は中華文明圏に限ったことだと考える。
また「四海同胞」を言ったのは孔子ではなく、弟子の子夏で、石頭で融通の利かないまじめな文学青年だったから、孔子の言うタテマエを真に受けただけだろう。
廢(廃)

(金文大篆)
論語の本章では”よくないものとして捨て去る”。初出は後漢の『説文解字』で、論語の時代に存在しない。同音は祓のみ、甲骨文のみ出土。この字に”とりのぞく”の語義がある。詳細は論語語釈「廃」を参照。
論語:付記
論語の本章は、千古不易の真理でありながら、なかなかそうは思えない教訓。論語学而篇3の「巧言令色」(おべっか使いと作り笑いする奴には、気を付けろ)はまだ耳に入りやすいが、イヤな奴の発言にも価値ある言葉はある、の方は、分かっていても感情が邪魔をする。
感情とはつまり人間の本能から吹き出す想いだから、本能を抑えて礼法に従う=仁という、孔子の教説にはそぐわない。そこを何とかして感情を抑えろと孔子は言うのだが、顔回のようにそれを趣味にしてしまうか、あるいは自分を機械人形に作り替えて仕舞わないと、困難だ。
あるいは、徹頭徹尾悪党になり切ることかも。映画『ゴッドファーザー3』で、ファミリーの長であるヴィトー・コルレオーネが、息子のマイケルを諭して言った言葉、「敵を憎むな。判断が鈍る」(Never hate your enemies. It affects your judgement.)がそれだろう。

これこそまさに「人を以て言を廃てず」の代表例で、これが徹底できないから、訳者も失敗だらけの人生を歩むハメになった。孔子もまた仁を説きながら、自分は仁にそむいた政治工作にいそしんで、失敗を繰り返した。孔子も「言を以て人を挙げ」ない対象なのかも知れない!
論語の本章に関して、古注はいつも通り本文の内容を繰り返しているばかりで、全く読む意味が無い。新注に至ってはどういうわけか、何一つ注釈を加えていない。朱子は自分が口先男だという、自覚でもあったのだろうか。
対して明末清初の儒者・李颙(季二曲)は、こういうことを書いている。
不以言舉人、則徒言者不得倖進。不以人廢言、庶言路不至壅塞、此致治之機也。以言舉人則人皆尚言、以行舉人則皆尚行、上之所好、下卽成俗、感應之機、捷於影響、風俗之淳漓、世道之升沈係之矣。三代舉人一本於德、兩漢舉人意猶近古、自隋季好文、始專以言辭舉人、相沿不改、遂成定制。雖其閒不無道德經濟之彦、隨時表見、若以爲制之盡善、則未也、是在圖治者隨時調停焉。
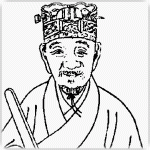
言っていることで人を推薦しなければ、無駄口を叩く者が偶然の昇進を掴むことがなくなり、言った人を理由に言葉を捨てなければ、皆が口をつぐんでしなうようなことがなくなる。これが政治の機微というものだ。
言っている事で人を推薦すると、人は皆言葉を慎むが、行動で人を推薦すれば、人は行動を慎むようになる。そうすれば為政者の思いのままが、すぐさま下々の風俗となるだろう。そのからくりは、速やかに世間に作用して、人情の善悪、世情の浮沈は、ひとえにこの選択に掛かっている。
だから夏・殷・周の三代では、役人の採用は人徳の有る無しで決め、前後の漢は、やはりそれに近いやり方で取った。ところが隋の末年から文章で試験するようになり、書いた言葉だけで採用の当否を決めるようになった。これが代々受け継がれて、とうとう中国の常識になってしまった。
もちろんそうして採用された役人にも、品格や世間の救済にすぐれた人物は出た。この制度は本来、そうした優れた人材を採ることにあった。ただし常にそうした人材を選び続けようとしても、まだ達成されたことがない。つまり上に英主を頂き、よき人材を採ろうとする作為が無ければ、なんともならないのだ。(『四書反身録』巻三)
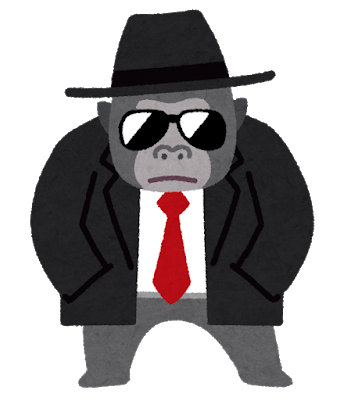







コメント