(検証・解説・余話の無い章は未改訂)
論語:原文・白文・書き下し
原文・白文
子夏曰、「君子信而後勞其民、未信、則以爲厲己也。信而後諫、未信、則以爲謗己矣*。」
校訂
諸本
- 武内本:矣、唐石経也に作る。
後漢熹平石経
…白…
- 前章である可能性あり。
定州竹簡論語
……而後諫;未[信,則]以為謗a也。」579
- 今本”謗”下有”己”字。
→子夏曰、「君子信而後勞其民、未信、則以爲厲己也。信而後諫、未信、則以爲謗矣。」
復元白文(論語時代での表記)



























 謗
謗

※論語の本章は「謗」の字が論語の時代に存在しない。「信」「以」「也」「則」の用法に疑問がある。本章は戦国時代以降の儒者による創作である。
書き下し
子夏曰く、君子は信あり而後其の民を勞ふ。未だ信あらざらば、則ち以て己を厲むると爲す也。信あり而後諫む。未だ信あらざらば、則ち以て謗ると爲す矣。
論語:現代日本語訳
逐語訳

子夏が言った。「役人は信用を作ってから管轄する民を労役に駆り出す。まだ信用がないと、必ず民はいじめられたと思うのだ。信用を作ってから諌める。まだ信用がないと、必ず自分の悪口を言ったと思うに違いないのだ。」
意訳
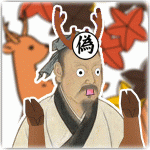
子夏「信用もないのに民を労役に駆り出すな。悪代官として怨まれるぞ。信用もないのに殿様の欠点を言うな。ただの悪口だと思われて危ないぞ。」
従来訳
子夏がいった。――
「君子は人民の信頼を得て然る後に彼等を公けのことに働かせる。信頼を得ないで彼等を働かせると、彼等は自分たちが苦しめられているように思うだろう。また、君子は君主の信任を得て然る後に君主を諌める。まだ信任されないうちに諌めると、君主は自分がそしられているように思うだろう。」下村湖人『現代訳論語』
現代中国での解釈例
子夏說:「領導樹立了威信後,才可以指使群衆;沒信譽時,群衆會以為你在虐待他們。下屬取得了領導的信任後,才可以去勸諫領導;沒得到信任時,領導就會以為你在誹謗他。」
子夏が言った。「指導者は威信を確立したら、やっと群衆を使役することが出来る。信頼や名誉がないなら、群衆はお前を、彼らをいじめる者だと思うだろう。部下は指導者の信頼を獲得した後、やっと指導者の間違いを意見できるようになる。信頼がないなら、指導者はお前を悪口者だと思うだろう」
論語:語釈
子夏

論語では、孔子の若い弟子で孔門十哲の一人、卜商子夏を指す。孔子より44年下で、孔子が放浪に出たとき子夏は11歳、帰国したときは26歳。おそらく放浪には同行しなかった。それゆえ孔子塾のいわゆるお勉強的側面をよく伝え、必須科目だった武芸の話は出てこない。
君子
論語の本章では、為政者階級の末端である役人を指す。孔子の生前にもその語義があり、当時は”貴族”を意味した。”教養ある人格者”などの曖昧な語義は、孔子没後一世紀の孟子から。詳細は論語における「君子」を参照。
信(シン)
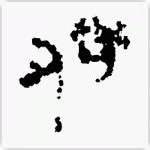

(金文)
論語の本章では、”信用される”。初出は西周末期の金文。字形は「人」+「口」で、原義は”人の言葉”だったと思われる。西周末期までは人名に用い、春秋時代の出土が無い。”信じる”・”信頼(を得る)”など「信用」系統の語義は、戦国の竹簡からで、同音の漢字にも、論語の時代までの「信」にも確認出来ない。詳細は論語語釈「信」を参照。
以(イ)


(甲骨文)
論語の本章では”それで”。初出は甲骨文。人が手に道具を持った象形。原義は”手に持つ”。論語の時代までに、名詞(人名)、動詞”用いる”、接続詞”そして”の語義があったが、前置詞”~で”に用いる例は確認できない。ただしほとんどの前置詞の例は、”用いる”と動詞に解せば春秋時代の不在を回避できる。詳細は論語語釈「以」を参照。
勞/労


(金文)
論語の本章では”労働させる”。中国の税はつい最近まで、穀物・貨幣など財貨で取り立てるのと、労役を課すのとの二本立てだった。伝統的には「労す」と読み下すが、音読みのままで済ませるのは訓読とは言い難く賛成しない。
初出は甲骨文。『学研漢和大字典』によると、𤇾(ケイ)・(エイ)は、熒の原字で、火を周囲に激しく燃やすこと。勞は「𤇾+力」の会意文字で、火を燃やし尽くすように、力を出し尽くすこと。激しくエネルギーを消耗する仕事や、そのつかれの意、という。詳細は論語語釈「労」を参照。
厲


「厲」(金文)
論語の本章では”いじめる”。蠣殻でガリガリ削るような目に遭わせること。初出は西周中期の金文。『学研漢和大字典』によると、萬(=万)は、二つの毒刺をもったさそりを描いた象形文字。厲は「厂(いし)+萬(さそり、強い毒)」で、さそりの毒のようにきびしい摩擦を加える石、つまり、といしを示す。また、猛毒を持つ意から、毒気や毒のひどい病気の意。ひどい、きついなどの意を含む、という。詳細は論語語釈「厲」を参照。
則(ソク)


(甲骨文)
論語の本章では、”…の場合は”。初出は甲骨文。字形は「鼎」”三本脚の青銅器”と「人」の組み合わせで、大きな青銅器の銘文に人が恐れ入るさま。原義は”法律”。論語の時代=金文の時代までに、”法”・”則る”・”刻む”の意と、「すなわち」と読む接続詞の用法が見える。詳細は論語語釈「則」を参照。
則以爲厲己也
論語の本章では、”自分に辛く当たると必ず思う”。思うのは伝統的に「民」と解するが、主語が明示されていないので、ひどく分かりづらい。
ここでの「以」は以前の「勞其民、未信」を受ける代名詞で、”信用も無いのに労役を課すこと、それを”の意。詳細は論語語釈「以」を参照。
句末で「也」が用いられるようになった物証は、春秋時代以前からは出土していない。詳細は論語語釈「也」を参照。
諫

「諌」(金文)
論語の本章では”目上の間違いに意見する”。初出は西周末期の金文。『学研漢和大字典』によると、「言+(音符)柬(カン)(よしあしをわける、おさえる)」の会意兼形声文字、という。詳細は論語語釈「諌」を参照。
日本の中等教育の漢文では、『十八史略』を教材に使う例が多いので、中国古代のニート兄弟で、街宣右翼のように官職をたかろうとした伯夷と叔斉が、武王を「いさめた」という漢字として知られている、かも知れない。
叩馬諫曰、「父死不葬、爰及干戈、可謂孝乎。以臣弑君、可謂仁乎。」左右欲兵之。太公曰、「義士也。」扶而去之。

草むらに潜んでいた伯夷と叔斉が、武王の車の引き馬に飛び付いて言った。「父上が亡くなったのに葬式も出さない。代わりに戦争を始めた。親不孝にもほどがある。家臣の分際で主君を殺そうとしている。お前さんはろくでなしだ。」怒った衛兵が武器を向けた。
太公望「ハイハイご立派ご立派、ちょっとあっちへ行こうね。」衛兵に言い付けて、しがみついている二人を馬から引きはがし、「オイ! こいつらをどっかに捨ててこい。」(『十八史略』)
信而後諫
論語の本章では、”信用が出来た後で(主君を)諌める”。ここも主語がないので文意が明瞭でないが、漢文はわかりきったことは書かないし、筆記に多大な手間暇が掛かった古代では、できるだけ省力して書くのが当たり前だった。
謗

(古文)
論語の本章では”批判する”。論語では本章のみに登場。初出は秦系戦国文字。論語の時代に存在しない。論語時代の置換候補もない。『学研漢和大字典』によると「言+(音符)旁(ボウ)(両わき、わきに広げる)」の会意兼形声文字、という。詳細は論語語釈「謗」を参照。
則以爲謗己矣
論語の本章では、”(主君は)自分の悪口を言うのだときっと思うに違いない”。ここも主語がないので文意が明瞭でない。
「則」はAならば必ずBの意で、「レバ則(ソク)」といわれるように、順接の仮定条件の文で多く用いる。詳細は論語語釈「則」を参照。
「以為」は漢文では熟語として「おもえらく」と読み、”思うことには・考えてみると”と解するが、「以って~と為す」と返り読みする場合との判断基準は明悪でない。ただ全ての「おもえらく」は「以って~と為す」と読めるが逆はそうではない。論語語釈「以」に説明がある。
矣(イ)


(金文)
論語の本章では、”(きっと)…である”。初出は殷代末期の金文。字形は「𠙵」”人の頭”+「大」”人の歩く姿”。背を向けて立ち去ってゆく人の姿。原義はおそらく”…し終えた”。ここから完了・断定を意味しうる。詳細は論語語釈「矣」を参照。
論語:付記
論語の本章は上掲定州竹簡論語にあるから、前漢宣帝期ににはすでにあったことになるが、戦国や秦帝国時代の文章で、似たような言い廻しを探したが見つからない。「労」で検索して、近いニオイがするのは次の例だろうか。
萬章曰:「父母愛之,喜而不忘;父母惡之,勞而不怨。然則舜怨乎?」
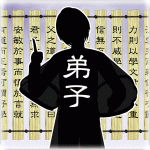
孟子の弟子の万章「(いにしえの聖王舜は、庶民だった頃にクズな父母にいじめられて、天に向かってワンワン泣きました。ところが)父母がたまに気が変わって優しい言葉をかけるとずっと忘れず、いつも通りいたぶるとそれでもよく言うことを聞いて恨みませんでした。ということは、父母は恨まなかったが天は恨んだ、ということですか? 頭がおかしいです。」(『孟子』万章篇上1)
亂世不然,汙漫突盜以先之,權謀傾覆以示之,俳優、侏儒、婦女之請謁以悖之,使愚詔知,使不肖臨賢,生民則致貧隘,使民則極勞苦。是故,百姓賤之如尪,惡之如鬼,日欲司閒而相與投藉之,去逐之。

乱世はそうでない。あくどい連中が美味い汁を吸い、悪だくみをした方が儲かると誰もが知るから、俳優やお笑い芸人や女子供がもてはやされる。馬鹿者が政令を出し、愚か者が賢者のふりをするから、一般人はとんでもない貧乏に追い詰められ、こき使われて悶え苦しむ。だから一般人は、羽振りの良い者をマムシや毒虫のように忌み嫌い、悪霊が祟ったのと同じに思うくせに、毎日役人のお目こぼしは期待し、こぞって役人の虎の威を借り、そうでなければ逃げ散る。(『荀子』王覇篇18)


上の例では孟子は万章に問い詰められているが、これには背景があって、舜王を創作したのは実は孟子だった。顧客である当時の斉王家は、国を乗っ盗って間が無かったから、その後ろめたさを誤魔化すために、孟子が聖王舜をこしらえ、祖先に据え家格の格上げを図ってやった。
だが作ったばかりのラノベに、ボコボコと設定の穴があるのは避けがたく、それで弟子の万章に「頭おかしい」とまで言われた。だが世間師・孟子は少しも騒がず、万章の言う穴にその都度新たな膏薬を貼り、舜王をもっともらしく仕立て上げ、つまり弟子を共犯に引き込んだ。
悪い男である。

み~た~な~
なお上記の「信」の語釈で、従来の「信ぜらる」という受身ではなく、「信あり」と動詞に読んだ。漢文は極めて単純な文法を持つ代わりに、個々の漢字=漢語の品詞が安定せず、その時の都合で動詞にも名詞にも形容詞にも副詞にもなるのは、まるで着替えの多いお化けだ。
だから品詞についてはあまり詰めて考えると読解が詰んでしまう。その代わり、原文に無いことは無いとしておかないと、融通無碍がデタラメに陥ることになる。勝手に語順を変えないこともその一つだし、文法的な背景を持たない能動→受動態の解釈には賛成できない。
そうまでしないと読めないなら、仕方がないのだが。それは多分、原文が壊れている。





コメント