論語:原文・白文・書き下し
原文・白文
子張曰、「執德不弘、信道不篤、焉能爲有、焉能爲亡。」
校訂
後漢熹平石経
子張白德不弘信道…
- 「弘」字:〔弓口〕
定州竹簡論語
(なし)
復元白文(論語時代での表記)



















※張→(金文大篆)・篤→督・焉→安。論語の本章は、「信」の用法に疑問がある。
書き下し
子張曰く、德を執るに弘からず、道を信ずるに篤からずんば、焉んぞ能く有りと爲し、焉んぞ能く亡しと爲さむ。
論語:現代日本語訳
逐語訳

子張が言った。「能力を獲得するについて幅広くなく、先生の教えを信じるについて熱心でなければ、どうして有ると言えようか。どうして無いと言えようか。」
意訳

子張「少しばかり修行して、生半可に先生の教えを受け取っただけの連中には、学の有るも無しもないものだ。」
従来訳
子張がいった。――
「何か一つの徳に固まって、ひろく衆徳を修めることが出来ず、正道を信じても、それが腹の底からのものでなければ、そんな人は居ても大して有りがたくないし、いなくても大して惜しくはない。」下村湖人『現代訳論語』
現代中国での解釈例
子張說:「擁有優點不發揚,信仰道義不忠誠,這樣的人,有他沒他一個樣。」
子張が言った。「長所を持ちながら発揮できない。道義を信仰しながら真面目でない。こんな人は、居ても居なくても変わらない。」
論語:語釈
子張

論語では、孔子の高弟の一人。孔門十哲には入っていないが、その理由は一つに、年齢の若さにあると思われる。つまり孔子の放浪など危機の時代に、同行できなかったことにあるだろう。加えて師匠の孔子からは、何事に付け”やり過ぎ”と評された。
ただし孔門十哲の一人・子夏からは4つ若いだけだから、恐らく孔子は子夏も同様に連れていけなかったし、連れて行きたくなかった*と思われるので、同じく同行しなかった子張を、年齢を理由に”十哲ではない”と評価を下げるのは意味が無いと思う。
そもそも「孔門十哲」とは、孔子より一世紀後の孟子が、勝手に自分の好き好みを言ったに過ぎない。詳細は孔門十哲の謎を参照。また、論語の人物・顓孫師子張も参照。
*衣食住も医療も何もかも当ての無い旅に、11歳の子供を連れて行こうと思うわけがない。
執德(徳)

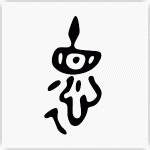
(金文)
論語の本章では、”能力を高める”。論語での「徳」は”能力・人の持つ人格的迫力”を意味し、道徳とは関係が無い。詳細は論語における「徳」を参照。
「執」の初出は甲骨文。『学研漢和大字典』によると「手かせ+人が両手を出してひざまずいた姿」の会意文字であり、確実にとらえること。つまり能力を獲得する意になる。詳細は論語語釈「執」を参照。
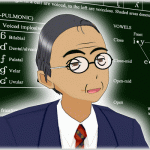

『学研漢和大字典』を編んだ藤堂博士の論語本では、「徳」を”人が生まれつき持っている素直な本性”と解し、それにはそれなりの根拠があるが、それでは理解できない章が論語には多数ある。従って賛成できないし、盲目的に”道徳”と解するのはもっと賛成できない。
信(シン)
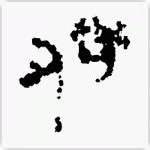

(金文)
論語の本章では、”他人を欺かないこと”。初出は西周末期の金文。字形は「人」+「口」で、原義は”人の言葉”だったと思われる。西周末期までは人名に用い、春秋時代の出土が無い。”信じる”・”信頼(を得る)”など「信用」系統の語義は、戦国の竹簡からで、同音の漢字にも、論語の時代までの「信」にも確認出来ない。詳細は論語語釈「信」を参照。
道(トウ)


(甲骨文)
論語の本章では”やり方”。初出は甲骨文。「ドウ」は呉音。字形は「行」”十字路”+「人」で、原義は人の通る”道”。「首」の形が含まれるのは金文から。春秋時代までの語義は”道”または官職名?で、”みちびく”・”道徳”の語義は戦国時代にならないと見られない。詳細は論語語釈「道」を参照。
孔子の生前では、”原則・やり方”という一般的意味があるだけで、道徳的な意味はなかった。そういうめんどうくさいもったい付けをしたのは、孔子没後約一世紀の孟子からになる。
信道
論語の本章では”孔子の説いた教えを信じる”。「道」とは人が行き来するみちのことで、この語義に関しては漢字を呪術的に解釈する傾向のある『字通』でも変わりはない。孔子は自分が人の進むべき道の創造者であるとは思っていなかった。
弟子の子張ならなおさらで、子張が信ずべき道と言えば、孔子の説いた教えに他ならない。同様の例は同じく弟子の冉有の発言として、論語雍也篇12に「子の道を説ばざるにあらず」として記されている。
これに対して伝統的な解釈では、この「道」に重々しい意味を見いだそうとして、”道義”などと訳すが、それは却って論語をわかりにくくしているだけに思う。
芸事を習った方にはおわかり頂けると期待したいが、お師匠様は例えば”ここに足を置きなさい。視線は真っ直ぐ正しなさい。得物は親指は添えるだけで小指で握りなさい”と一々教えて下さる。その通りにしないと技が効かない。それが「道」ということだ。
篤(トク)

(秦系戦国文字)
論語の本章では、「厚」と同様に”あつく”。この文字は甲骨文・金文には見えず、秦系戦国文字と古文から見られる。古文での字形は安定しておらず、竺や![]() に記されることがある。
に記されることがある。

この字が古文に見られる事から、論語の本章が新しい成立であるとは断定できないが、言葉やその音に対応する文字が作られなかった程度には、珍しい言葉だったことが想像できる。論語時代の置換候補は「督」。甲骨文から存在し、”しらべる・かんがえる・ただす”の語釈を『大漢和辞典』が載せる。
また異体字の「竺」は、いわゆる「天竺」の「ジク」だが、春秋末期とも推定される晋系戦国文字から見られ、論語の時代に存在した可能性がある。詳細は論語語釈「篤」を参照。
焉能爲有、焉能爲亡
論語の本章では、”どうしてあると言えようか、どうしてないと言えようか”。「焉」はもとエンという名の黄色い鳥のことだが、漢文ではその意味で使われることはほとんど無く、文頭では疑問辞に、文末では完了・断定の助辞として用いられる。詳細は論語語釈「焉」を参照。
「能」は”できる”。初出は西周早期の金文。『学研漢和大字典』によると㠯(イ)(=以)は、力を出して働くことを示す。能は「肉+かめの足+〔音符〕厶(㠯の変形)」の会意兼形声文字で、かめや、くまのようにねばり強い力を備えて働くことをあらわす、という。。詳細は論語語釈「能」を参照。


「能~」は「よく~す」と訓読するのが漢文業界の座敷わらしだが、”上手に~できる”の意と誤解するので賛成しない。読めない漢文を読めるとウソをついてきた、大昔に死んだおじゃる公家の出任せに付き合うのはもうやめよう。
学研『全訳用例古語辞典』「よく」条
《副詞》
- 十分に。念入りに。詳しく。
《竹取物語・御門の求婚》 「よく見てまゐるべき由(ヨシ)のたまはせつるになむ」
《訳》
念入りに見てまいるようにとの意向をおっしゃられたので。- 巧みに。上手に。うまく。
《宇治拾遺物語・一三・九》 「木登りよくする法師」
《訳》
木登りを上手にする法師。- 少しの間違いもなく。そっくり。
《万葉集・一二八》 「わが聞きし耳によく似る葦(アシ)のうれの足ひくわが背」
《訳》
私が聞いたうわさにそっくり似ている葦の葉先のように足の弱々しいわが夫よ。
む甚だしく。たいそう。
《今昔物語集・二七・四一》 「よく病みたる者の気色(ケシキ)にて」
《訳》
甚だしく病んでいるようすで。- よくぞ。よくも。よくもまあ。▽並々でない事を成しとげたとき、また、成しとげられなかったときに、その行為の評価に用いる。
《竹取物語・竜の頸の玉》 「よく捕らへずなりにけり」
《訳》
よくもつかまえなかったものだ。- たびたび。ともすれば。
《浮世床・滑稽》 「てめえ、よくすてきと言ふぜ」
《訳》
おまえ、たびたびすてきと言うぜ。
「為」は”…とみなす”。初出は甲骨文。『学研漢和大字典』によると爲の甲骨文字は「手+象」の会意文字で、象に手を加えて手なずけ、調教するさま。人手を加えて、うまくしあげるの意。転じて、作為を加える→するの意となる。また原形をかえて何かになるとの意を生じた、という。詳細は論語語釈「為」を参照。
「有」は”ある”。初出は甲骨文。『学研漢和大字典』によると又(ユウ)は、手でわくを構えたさま。有は「肉+〔音符〕又」の会意兼形声文字で、わくを構えた手に肉をかかえこむさま。空間中に一定の形を画することから、事物が形をなしてあることや、わくの中にかかえこむことを意味する、という。詳細は論語語釈「有」を参照。
「亡」は”無い”。初出は甲骨文。『学研漢和大字典』によると、L印(囲い)の会意文字で、隠すさまを示すもの。あったものが姿を隠す、という。詳細は論語語釈「亡」を参照。
論語の本章について武内本は、「この章道徳理想を高くすべきを説く、小徳は有無を論ずる価値も無しとなり」と記す。つまり少々孔子の教えをかじり、少しばかり信じただけでは、習ったも習わないも無いものだ、とこの句を解する。新古の注も同様に言う。
従って訳者も同様に解したが、”有る無しも言えない”は「莫有無也」など簡潔に言えるにも関わらず、「どうして」と強調した言い廻しの上に、同じ語句の繰り返しをしているのは、もったいぶった言い廻しで、「やり過ぎ」子張らしいと言える。
論語:付記
論語の本章は、漢以降帝国のイデオロギーとなった儒家や儒者には思いも寄らぬことで、孔子の直弟子でありながら、不真面目な弟子が少なからずいたことを示している。だが学校とか塾の類は本来そういうもので、弟子が皆おりこうさんと言い張るのは、うそデタラメの世界だ。
その意味で独裁政権と帝政期の儒教は相性がよく、今世紀に入って中共が世界各地に孔子学院なるうさんくさい学校を建てて回ったのは、むべなるかなと言える。要するに「偉大なる指導者ナニガシ」と「弟子は皆おりこう」は、うそデタラメの点で非常によく似ているのだ。

かつてブレジネフが挙げもしない戦功を理由に、勲章をいくつもぶら下げていたように、こういういんちきと共産主義は相性がよいが、何も真っ赤な国に限った話ではない。逃げ込んだ蒋介石が台湾で何をしたか、そして台湾人もやはり中国人であることを忘れない方がいい。
赤いのもそうでないのも揃って科学を主張したが、批判を許さない時点でオカルトだ。
さて論語の本章について従来訳の最終部分「そんな人は~」は、新古の注に従った重厚な訳と言うべきで、そういう解釈もあるかなと思う。漢文には事実上文法が無いからで、大勢の人が「うまいこと言った」と感じれば、それがその時代の正統的な訳になる。古注を見よう。
人執徳能至𢎞大信道必便篤厚此人於世乃為可重若雖執徳而不𢎞雖信道而不厚此人於世不足可重如有如無故云焉能為有焉能為亡也

人は徳を大いに学んだのなら、道への信頼も厚いはずで、こういう人は世間で重んじられる。だがろくに徳を身につけず、道への信頼もいい加減なら、世間で重んじられるわけがない。(『論語集解義疏』)
新注はやや違う。
有所得而守之太狹,則德孤;有所聞而信之不篤,則道廢。焉能為有無,猶言不足為輕重。

学びはしたが範囲が狭い。それで十分と開き直っていると、誰ともわかり合うことが出来ない。話を聞いたが小バカにしている。それでは道徳が身に付かない。だからその人に、能の有る無しは言えないし、その人の人格も判断のしようが無い。(『論語集注』)
漢文は意思の伝達という、言語のある部分の機能を放棄している。その意味で実用品と言うよりも、芸術作品に近い。それも前衛芸術で、分かる人だけに分かるものでもある。つまり文の意味は筆者にしか分からず、その筆者にも分かっていない可能性すらある。
だがあり得ない解釈を削ることは出来る。訳者がもったいを削るのもその一環だ。というわけで古注や従来訳の解釈はありではあるが、もったいの付けすぎだ。子張が言ったのはもっと単純で、不真面目で不埒な弟子は、身に付いた技能教養の程度すら判断出来ないということ。
『笑府』から一つ例を挙げよう。
一富翁世不識字。人勸以延師訓子。師至。始訓之執筆臨朱。書一畫。則訓曰一字。二畫。則訓曰二字。三畫。則訓曰三字。其子便欣然投筆。告父曰。児已都曉字義。何煩師為。乃謝去之。踰時。父擬招所親萬姓者飲令子晨起。治狀。久之不成。父趣之。其子恚曰。姓亦多矣。奈何偏姓萬。自朝至今。𦂯完得五百餘畫。

ある金持ち、代々字が読めないのを苦にしていた。人から「では先生を呼んで息子さんに習わせたらよい」と言われて、呼ぶことにした。先生は早速朱筆で字を書き、子供に墨でなぞらせる。
先生「これが一の字。これが二の字。これが三の字。」
子供「あ! ぼく全部わかっちゃった! 先生はもう要らないや。」
おやじはそうかと思って先生を断って帰してしまった。
しばらくして、おやじが客を呼ぶことになり、招待状を子供に書かせた。子供は夜明けから書き始めたがちっとも書き終わらない。
おやじ「ずいぶん手間がかかっているな。どうしたんだ。」
子供「よりにもよって、なんで万さんなんて姓を名乗るのかな。まだ五百しか線を引き終わらないや。」(『笑府』巻一・訓子)


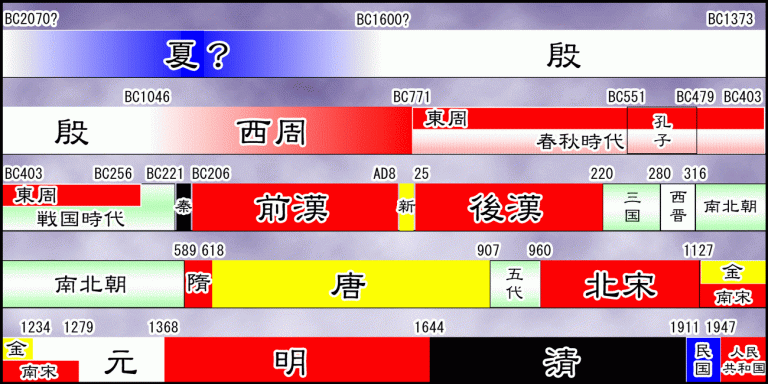


コメント