論語:原文・書き下し
原文(唐開成石経)
子曰士志於道而恥惡衣惡食者未足與議也
校訂
東洋文庫蔵清家本
子曰士志於道而恥惡衣惡食者未足與議也
後漢熹平石経
子曰士志乎…衣惡
※『漢石經考異補正』に無く『漢熹平石經殘字集録』より。後者は「曰」を「白」と釈文しない。
定州竹簡論語
(なし)
標点文
子曰、「士志乎道而、恥惡衣惡食者、未足與議也。」
復元白文(論語時代での表記)


 志
志

 恥
恥






 議
議
※論語の本章は赤字が論語の時代に存在しない。「乎」「未」「足」「也」の用法に疑問がある。本章は後世の儒者による創作である。
書き下し
子曰く、士の道乎志し而、惡しき衣惡しき食を恥づる者は、未だ與に議るに足らざる也。
論語:現代日本語訳
逐語訳

先生が言った。「正しい道を求める志士が、粗末な衣料や食事を恥じるようでは、まだ議論を共に出来ない。」
意訳
質素な生活を嫌がるようでは、志のあるサムライとは言えない。
従来訳
先師がいわれた。――
「いやしくも道に志すものが、粗衣粗食を恥じるようでは、話相手とするに足りない。」下村湖人『現代訳論語』
現代中国での解釈例
孔子說:「立志追求真理,而恥於粗布淡飯的人,不值得交談。」
孔子が言った。「真理を追求しようと志を立てて、それなのに粗衣粗食を恥じる人は、語り合う価値が無い。」
論語:語釈
子曰(シエツ)(し、いわく)

論語の本章では”孔子先生が言った”。「子」は貴族や知識人に対する敬称で、論語では多くの場合孔子を指す。「子」は赤ん坊の象形、「曰」は口から息が出て来るさま。「子」も「曰」も、共に初出は甲骨文。辞書的には論語語釈「子」・論語語釈「曰」を参照。


(甲骨文)
この二文字を、「し、のたまわく」と読み下す例がある。「言う」→「のたまう」の敬語化だが、漢語の「曰」に敬語の要素は無い。古来、論語業者が世間からお金をむしるためのハッタリで、現在の論語読者が従うべき理由はないだろう。
漢石経では「曰」字を「白」字と記す。古義を共有しないから転注ではなく、音が遠いから仮借でもない。前漢の定州竹簡論語では「曰」と記すのを後漢に「白」と記すのは、春秋の金文や楚系戦国文字などの「曰」字の古形に、「白」字に近い形のものがあるからで、後漢の世で古風を装うにはありうることだ。この用法は「敬白」のように現代にも定着しているが、「白」を”言う”の意で用いるのは、後漢の『釈名』から見られる。論語語釈「白」も参照。
論語の本章に限ると、上掲のように『漢石經考異補正』(1825)に無く『漢熹平石經殘字集録』(1930)より転記したので「曰」字のままにしてある。後者に掲載された残石拓本を見ると、「曰」のあるべき箇所にはっきりと「白」と分かる字、または「曰」とどっちつかず、両方の用例がある。本章の場合は下掲の通りどっちつかずで、とりあえず「曰」のままとした。
士(シ)


(金文)
論語の本章では、”仁政への志を持った貴族の末席・その予備軍”。初出は西周早期の金文。「王」と字源を同じくする字で、斧を持った者=戦士を意味する。字形は斧の象形。「春秋までの金文では”男性”を意味した。藤堂説では男の陰●の突きたったさまを描いたもので、牡(おす)の字の右側にも含まれる。成人して自立するおとこ、という。詳細は論語語釈「士」・春秋時代の身分秩序を参照。
仮に本章が史実だとすると、孔子が呼びかけたのはすでに仕官して士族の籍に入った弟子で、仕官前の大多数の弟子ではないことになる。ただし本章は文字史から、後世の創作が確定しているので、偽作者がこの点に注意を払ったとは思えない。
志(シ)


(金文)
論語の本章では”こころざし”。『大漢和辞典』の第一義も”こころざし”。初出は戦国末期の金文で、論語の時代に存在しない。論語時代の置換候補は”知る”→「識」を除き存在しない。字形は「止」”ゆく”+「心」で、原義は”心の向かう先”。詳細は論語語釈「志」を参照。
於(ヨ)→乎(コ)
論語の本章では”~に”。唐石経、清家本では「於」と記し、漢石経では「乎」と記す。時系列に従い「乎」に校訂した。
論語の伝承について詳細は「論語の成立過程まとめ」を参照。
原始論語?…→定州竹簡論語→白虎通義→ ┌(中国)─唐石経─論語注疏─論語集注─(古注滅ぶ)→ →漢石経─古注─経典釈文─┤ ↓↓↓↓↓↓↓さまざまな影響↓↓↓↓↓↓↓ ・慶大本 └(日本)─清家本─正平本─文明本─足利本─根本本→ →(中国)─(古注逆輸入)─論語正義─────→(現在) →(日本)─────────────懐徳堂本→(現在)


(金文)
「於」の初出は西周早期の金文。ただし字体は「烏」。「ヨ」は”~において”の漢音(遣隋使・遣唐使が聞き帰った音)、呉音(遣隋使より前に日本に伝わった音)は「オ」。「オ」は”ああ”の漢音、呉音は「ウ」。現行字体の初出は春秋中期の金文。西周時代では”ああ”という感嘆詞、または”~において”の意に用いた。詳細は論語語釈「於」を参照。


(甲骨文)
「乎」を”~”に”に用いる例は春秋時代以前では確認出来ない。字の初出は甲骨文。甲骨文の字形は持ち手を取り付けた呼び鐘の象形で、原義は”呼ぶ”こと。甲骨文では”命じる”・”呼ぶ”を意味し、金文も同様で、「呼」の原字となった。句末の助辞として用いられたのは、戦国時代以降になる。ただし「烏乎」で”ああ”の意は、西周早期の金文に見え、句末でも詠嘆の意ならば論語の時代に存在した可能性がある。詳細は論語語釈「乎」を参照。
道(トウ)
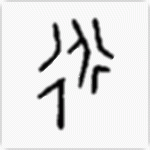

「道」(甲骨文・金文)
論語の本章では”筋道”→”理想的な生き方”。動詞で用いる場合は”みち”から発展して”導く=治める・従う”の意が戦国時代からある。”言う”の意味もあるが俗語。初出は甲骨文。字形に「首」が含まれるようになったのは金文からで、甲骨文の字形は十字路に立った人の姿。「ドウ」は呉音。詳細は論語語釈「道」を参照。
而(ジ)


(甲骨文)
論語の本章では”~かつ~”。初出は甲骨文。原義は”あごひげ”とされるが用例が確認できない。甲骨文から”~と”を意味し、金文になると、二人称や”そして”の意に用いた。英語のandに当たるが、「A而B」は、AとBが分かちがたく一体となっている事を意味し、単なる時間の前後や類似を意味しない。詳細は論語語釈「而」を参照。
恥(チ)


(楚系戦国文字)
論語の本章では”はじる”。初出は楚系戦国文字。論語の時代に存在しない。論語時代の置換候補も無い。字形は「耳」+「心」だが、「耳」に”はじる”の語義は無い。詳細は論語語釈「恥」を参照。
”はじ”おそらく春秋時代は「羞」と書かれた。音が通じないから置換字にはならないが、甲骨文から確認できる。
惡(アク/オ)


(金文)
論語の本章では”粗末な”。現行字体は「悪」。初出は西周中期の金文。ただし字形は「䛩」。漢音(遣隋使・遣唐使が聞き帰った音)「アク」で”わるい”を、「オ」で”にくむ”を意味する。初出の字形は「言」+「亞」”落窪”で、”非難する”こと。現行の字形は「亞」+「心」で、落ち込んで気分が悪いさま。原義は”嫌う”。詳細は論語語釈「悪」を参照。
衣(イ)


(甲骨文)
論語の本章では”衣類”。初出は甲骨文。ただし「卒」と未分化。金文から分化する。字形は衣類の襟を描いた象形。原義は「裳」”もすそ”に対する”上着”の意。甲骨文では地名・人名・祭礼名に用いた。金文では祭礼の名に、”終わる”、原義に用いた。詳細は論語語釈「衣」を参照。
食(ショク)

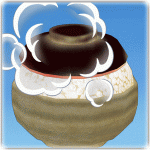
(甲骨文)
論語の本章では”食べもの”。初出は甲骨文。甲骨文の字形は「亼」+点二つ”ほかほか”+「豆」”たかつき”で、食器に盛った炊きたてのめし。甲骨文・金文には”ほかほか”を欠くものがある。「亼」は穀物をあつめたさまとも、開いた口とも、食器の蓋とも解せる。原義は”たべもの”・”たべる”。詳細は論語語釈「食」を参照。
者(シャ)


(金文)
論語の本章では”…する者”。旧字体は〔耂〕と〔日〕の間に〔丶〕一画を伴う。新字体は「者」。ただし唐石経・清家本ともに新字体と同じく「者」と記す。現存最古の論語本である定州竹簡論語も「者」と釈文(これこれの字であると断定すること)している。初出は殷代末期の金文。金文の字形は「木」”植物”+「水」+「口」で、”この植物に水をやれ”と言うことだろうか。原義は不明。初出では称号に用いている。春秋時代までに「諸」と同様”さまざまな”、”~する者”・”~は”の意に用いた。漢文では人に限らず事物にも用いる。詳細は論語語釈「者」を参照。
未(ビ)


(甲骨文)
論語の本章では”今ではない”。この語義は春秋時代では確認できない。初出は甲骨文。「ミ」は呉音。字形は枝の繁った樹木で、原義は”繁る”。ただしこの語義は漢文にほとんど見られず、もっぱら音を借りて否定辞として用いられ、「いまだ…ず」と読む再読文字。ただしその語義が現れるのは戦国時代まで時代が下る。詳細は論語語釈「未」を参照。
足(ショク/シュ)
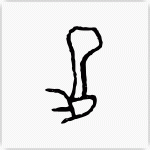

「疋」(甲骨文)
論語の本章では”足りる”→”…をする価値がある”。この語義は春秋時代では確認できない。初出は甲骨文。ただし字形は「疋」と未分化。「ソク」「ス」は呉音。甲骨文の字形は、足を描いた象形。原義は”あし”。甲骨文では原義のほか人名に用いられ、金文では「胥」”補助する”に用いられた。”足りる”の意は戦国の竹簡まで時代が下るが、それまでは「正」を用いた。詳細は論語語釈「足」を参照。
與(ヨ)


(金文)
論語の本章では、”ともに”。新字体は「与」。新字体初出は春秋中期の金文。金文の字形は「牙」”象牙”+「又」”手”四つで、二人の両手で象牙を受け渡す様。人が手に手を取ってともに行動するさま。従って原義は”ともに”・”~と”。詳細は論語語釈「与」を参照。
議(ギ)
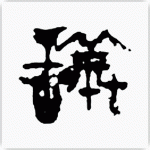
(戦国金文)
論語の本章では”語り合う”。初出は戦国末期の金文。論語の時代に存在しない。論語時代の置換候補もない。字形は「言」+「義」”ただしい”で、言葉で正しさを求める行為。原義は”はかる”。詳細は論語語釈「議」を参照。
也(ヤ)


(金文)
論語の本章では、「なり」と読んで断定の意。この語義は春秋時代では確認できない。初出は事実上春秋時代の金文。字形は口から強く語気を放つさまで、原義は”…こそは”。春秋末期までに句中で主格の強調、句末で詠歎、疑問や反語に用いたが、断定の意が明瞭に確認できるのは、戦国時代末期の金文からで、論語の時代には存在しない。詳細は論語語釈「也」を参照。
論語:付記
検証
論語の本章は、春秋戦国はおろか、先秦の誰一人引用していないし、再録もしていない。再出は漢石経になり、前後の漢帝国にかけて偽作されたと考えるのが筋が通る。
解説
論語の本章は、今後の考古学的発掘の親展いかんによっては、何とか孔子の肉声として言い張るだけの理屈が見つかるかも知れない。しかしおそらく、そのような努力によって本章の史実性が認められることはあるまい。本章はとうてい、孔子の言葉とは思えないからだ。
本章の聞き手は弟子たちだろうが、彼らはまだ仕官していないのがほとんどであり、「士」ではない。「士」は彼らが目指している、領主ではないが最下級の貴族であり、仕官して「士」になることが、孔子塾生の第一の目標だった。
中には学業優秀にも拘わらず、顔回のように仕官しなかった者もいるがそれは例外で、塾生は身分差別と「悪衣悪食」にうんざりしているからこそ、厳しい学業や稽古に励んでいた。そんな彼らに、教師の孔子が「悪衣悪食を恥じるな」などと言うだろうか?
ゆえにもし論語の本章が史実だったとすると、いくつか条件が必要になる。まず聞き手は塾生一般ではなく、放浪の旅にも同行した、子路・顔回・子貢・冉有といった一門の古参に限られる。孔子の私兵として陰謀にも手を貸した彼らなら、「悪衣悪食を恥じ」てはいかんだろう。
だがそんなことは、彼らに改めて説教する必要などなかっただろう。確かに一行の被包囲中、憤った子貢が孔子に怒りをぶちまけたことはあった。だが孔子に諭されて、すぐさま落ち着きを取り戻し、いつもの「アキンド子貢」に戻って政治工作の脱出行に出かけている。

子貢よ、お前の手も血に汚れている。わしについて来た以上、討ち死には覚悟の上じゃろう。闘士は革命に倒れるのが本望ではないか。それともあれか、私がおとなしいばかりのもの知り爺さんとでも思っていたのかね。今さら何を言っている。(論語衛霊公篇3)
以上を踏まえ、儒者は以下のように本章を評論しているが、とうてい賛成できない。
古注『論語集解義疏』
疏子曰至議也 若欲志於道而恥惡衣惡食者此則是無志之人故不足與共謀議於道也一云不可與其共行仁義也李充曰夫貴形骸之內者則忘其形骸之外矣是以昔之有道者有為者乃使家人忘其貧王公忘其榮而況於衣食也
疏。子曰く、議るを至す也。若し道於志すを欲し而惡衣惡食を恥じる者は、此れ則ち是れ志無き之人、故に與に共に道於謀り議るに足不る也。一に云う、與に其れ共に仁義を行う可から不る也。李充曰く、夫れ形骸之內なる者を貴ぶは、則ち其の形骸之外を忘るる矣。是れ以て昔之有道者の為す者有るは、乃ち家人を使て其の貧しきを忘れしむ。王公も其の榮えを忘る、し而況んや衣食に於いてを也。

付け足し。孔子様は、語るべきことを記した(この部分は江戸儒者の根本武夷による要約)。もし道に志そうとして衣食の粗末を恥じるなら、それは志がない人間であって、共に道を語り合うには足りないのだ。一説にはこう言う。一緒に仁義を実現する事が出来ないのだ、と。
李充「肉体を重んじる者は、それを取り巻く大自然を忘れているのだ。だから昔の道を心得た人が業績を残せたのは、家族に貧しさを我慢させたからに他ならない。その中には王侯もいるが、彼らの栄華でさえ捨て去ることが出来たのだ。衣食を放念できるのは言うまでも無い。」
*李充:東晋の儒者。
これが儒者の高慢ちき史上最高潮だった宋儒の手になると、もっと猛烈なことを言っている。
新注『論語集注』
心欲求道,而以口體之奉不若人為恥,其識趣之卑陋甚矣,何足與議於道哉?程子曰:「志於道而心役乎外,何足與議也?」
心に道を求むるを欲し、し而口體之奉を以て人の若から不るの恥と為すは、其れ識趣之卑しく陋しきの甚しき矣、何ぞ與に道於議るに足る哉。程子曰く、「道於志し而心の外乎役すは、何ぞ與に議るに足る也」と。


心で道を求めようとしながら、衣食が人並みでないのを恥とする者は、猛烈に頭が悪く人間も卑しい。どうして共に道を語るに足りよう。
程頤「道を志しておきながら、他ごとに心を働かせている者は、どうして共に語るに足りようか。」
*口體之奉:身体を養うための食べ物や衣服のこと。/識趣:識見志趣。見識や志望。
言うものは知らず、知る者は言わずという。過激な言葉が、却って本心を表している。
余話
アルツハイマーの最高顧問
漢語「志」は戦国時代になって、諸侯が領民に忠君愛国をすり込む必要から生まれた言葉で、孔子とは全然関係が無い。だがそれが分かるのは現代だからで、ネットが普及するまで儒者も漢学者も、「孔子先生は遠大な志を持っておられたのだ」と信じていた。
孔子に志があったとしても、それは弟子を仕官させること、出来れば母国の魯が滅びないことだけだったろうが、孔子を教祖として拝み倒し、人にも拝ませるのを生業としていた儒者(と多くの漢学教授)にとって、孔子が冷徹な打算家であっては、本尊としての価値が無かった。
そして儒者もまた志士でなければならぬという常識がまかり通ったが、日本の江戸時代に限れば、ある程度社会の福祉に貢献した。「武士は食わねど高楊枝」で、米相場の上下に生活を右往左往させられながらも、一生懸命民政に励んだ武士は少なくなかった。

だがそうでもない者もいた。『言志録』というお説教本を記した佐藤一斎は、昌平黌長官、今で言えば文科相とT大総長を兼ねたような職にあったが、地位にしがみついて離さず、アルツハイマーが激しくなった後も居座り続けた。黒船来航時に幕府の最高顧問がこのありさま。
阿部正弘をはじめ、老中たちもずいぶん困ったらしい。佐藤より時代はずいぶん前だが、この「言志」を『笑府』はからかっている。『笑府』は一旦中国では亡失して日本から逆輸入されたから、あるいは佐藤は読んでいた可能性はあるが、こういう顔の人だからねえ。
鐵匠柴行與樂戶三人言志。鉄匠曰。欲得屋大磁石一塊。不拘鋤頭斧頭。自然都吸來。不消買鐵。柴行曰。欲得屋大琥珀一塊。不拘茅艸松箍。自然都吸來。不消買柴。樂戶曰。欲得驢子大卵袋一張。不拘了頭婆娘。自然都吸來。不消買粉頭。
痴烏龜。大卵當不得銀子用的。
鍛冶屋と薪売りと女郎屋が、三人寄って日頃の志を言った。
鍛冶屋「家ほどもある大きな磁石が欲しい。そうすればスキだろうとオノだろうと、勝手に鉄が吸い付いて集まるだろう。わざわざ鉄塊を買わなくて済む。」
薪売り「家ほどもある大きな琥珀が欲しい。そうすれば付け木だろうと薪束だろうと、勝手に木が吸い付いて集まるだろう。わざわざ山木を買わなくて済む。」
女郎屋「ロバほど大きなキ●●マが欲しい。そうすれば人妻だろうと素人娘だろうと、勝手に女が吸い付いて集まるだろう。わざわざ女郎を買わなくて済む。」
ふざけた奴だ。大キ●●マに、一銭の価値もあるものか。(『笑府』巻十・巨卵)
「卵」に”キ●●マ”の語釈は、ちゃんと『大漢和辞典』にも載っている。
睾丸。〔難經〕足厥陰氣絕,即筋縮引卵與舌卷。(『大漢和辞典』卵条)
『難経』は漢代の医学書。”足裏の陰気が極まると、意識が途絶え、筋肉はこわばり、キ●●マが縮んで、舌がまくれ上がる”と書いてある。うわあ。「厥陰」は「ケッチン」と読み、『傷寒論』以降の漢方でも、病が極まった死相の一つとされる。なるほど縮むわけだ。






コメント