論語:原文・書き下し
原文(唐開成石経)
子曰富與貴是人之所欲也不以其道得之不處也貧與賤是人之所惡也不以其道得之不去也君子去仁惡乎成名君子無終食之閒違仁造次必於是顚沛必於是
校訂
東洋文庫蔵清家本
子曰冨與貴是人之所欲也不以其道得之不處也/貧與賤是人之所惡不以其道得之不去也/君子去仁惡乎成名/君子無終食之間違仁造次必於是顚沛必於是
- 「處」字:〔几〕をつくりのように記す。
後漢熹平石経
子白富與貴是人之𠩄欲也…顚沛必於…
- 「是」字:上下に〔日一乙〕
定州竹簡論語
……貧與賤,是人之所惡也,不以其道得之,不去也。君子63……仁,惡乎成名?君子無□食之間違仁,造次必64……
標点文
子曰、「富與貴、是人之所欲也。不以其道、得之不處也。貧與賤、是人之所惡也。不以其道、得之不去也。君子去仁、惡乎成名。君子無終食之閒違仁、造次必於是、顚沛必於是。」
復元白文(論語時代での表記)




















 賤
賤 



































 顚沛
顚沛


※欲→谷・仁→(甲骨文)。論語の本章は、赤字が論語の時代に存在しない。「貴」「也」「其」「惡」「乎」「閒」「次」「必」の用法に疑問がある。本章は漢帝国の儒者による創作である。ただし後半「君子去仁」以降は、孔子の肉声の可能性がある(解説を参照)。
書き下し
子曰く、富與貴とは、是れ人之欲むる所也。其の道を以ゐ不らば、之を得るとも處ら不る也。貧與賤とは、是れ人之惡む所也。其の道を以ゐ不らば、之を得るとも去ら不る也。君子仁を去りて、惡に乎名を成さむ。君子は食を終ふる之間も仁に違う無く、造次きも必ず是に於り、顚沛も必ず是に於れ。
論語:現代日本語訳
逐語訳

財産と地位は、人が欲しがるものである。筋の通った方法でないなら、もし手に入れても長くは続かない。貧困と低身分は、人が嫌がるものである。筋の通った方法でないなら、もし陥っても抜け出せない。諸君は仁の情けを捨てて、どこで名声を得ようというのか。諸君は食事の間だろうと、仁を忘れないで欲しい。誰かを真似る時も、大洪水の際にも、必ず仁を忘れないで欲しい。
意訳

人情を踏みつけたやり方では、財産も地位も長続きしないし、貧困無職からも抜け出せない。諸君は人でなしになっては困る。人まねだろうと大災害だろうと、ひたすら無差別の愛を保つのだ。
従来訳
先師がいわれた。――
「人は誰しも富裕になりたいし、また尊貴にもなりたい。しかし、正道をふんでそれを得るのでなければ、そうした境遇を享受すべきではない。人は誰しも貧困にはなりたくないし、また卑賎にもなりたくはない。しかし、道を誤ってそうなったのでなければ、無理にそれを脱れようとあせる必要はない。君子が仁を忘れて、どうして君子の名に値しよう。君子は、箸のあげおろしの間にも仁にそむかないように心掛くべきだ。いや、それどころか、あわを食ったり、けつまずいたりする瞬間も、心は仁にしがみついていなければならないのだ。」下村湖人『現代訳論語』
現代中国での解釈例
孔子說:「富和貴,人人嚮往,不以正當的方法得到的,不要享受;貧和賤,人人厭惡,不以正當方法擺脫的,不要逃避。君子扔掉了仁愛之心,怎麽算君子?君子時刻不會違反仁道,緊急時如此,顛沛時如此。」
孔子が言った。「財産と地位は、人々が飛びつく。正当な方法で得ないなら、受け取る事ができない。貧窮と低い身分は、人々が嫌がる。正当な方法で抜け出ないなら、逃げることができない。君子が仁の憐れみを投げ捨てたなら、どうして君子でいられるだろう? 君子は瞬間でも仁の道に外れてはならない。緊急事態も同じで、躓き倒れた瞬間も同様だ。」
論語:語釈
子曰(シエツ)(し、いわく)

論語の本章では”孔子先生が言った”。「子」は貴族や知識人に対する敬称で、論語では多くの場合孔子を指す。「子」は赤ん坊の象形、「曰」は口から息が出て来るさま。「子」も「曰」も、共に初出は甲骨文。辞書的には論語語釈「子」・論語語釈「曰」を参照。


(甲骨文)
この二文字を、「し、のたまわく」と読み下す例がある。「言う」→「のたまう」の敬語化だが、漢語の「曰」に敬語の要素は無い。古来、論語業者が世間からお金をむしるためのハッタリで、現在の論語読者が従うべき理由はないだろう。
漢石経では「曰」字を「白」字と記す。古義を共有しないから転注ではなく、音が遠いから仮借でもない。前漢の定州竹簡論語では「曰」と記すのを後漢に「白」と記すのは、春秋の金文や楚系戦国文字などの「曰」字の古形に、「白」字に近い形のものがあるからで、後漢の世で古風を装うにはありうることだ。この用法は「敬白」のように現代にも定着しているが、「白」を”言う”の意で用いるのは、後漢の『釈名』から見られる。論語語釈「白」も参照。
富(フウ)


(甲骨文)
論語の本章では”財産”。「フ」は呉音(遣隋使より前に日本に伝わった音)。初出は甲骨文。字形は「冖」+「酉」”酒壺”で、屋根の下に酒をたくわえたさま。「厚」と同じく「酉」は潤沢の象徴で(→論語語釈「厚」)、原義は”ゆたか”。詳細は論語語釈「富」を参照。
與(ヨ)


(金文)
論語の本章では、”~と”。新字体は「与」。新字体初出は春秋中期の金文。金文の字形は「牙」”象牙”+「又」”手”四つで、二人の両手で象牙を受け渡す様。人が手に手を取ってともに行動するさま。従って原義は”ともに”・”~と”。詳細は論語語釈「与」を参照。
貴(キ)
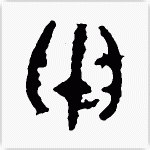
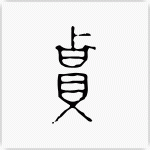
(金文)/(晋系戦国文字)
論語の本章では”高い地位”。この語義は春秋時代では確認できない。初出は西周の金文。現行字体の初出は晋系戦国文字。金文の字形は「貝」を欠いた「𠀐」で、「𦥑」”両手”+中央に●のある縦線。両手で貴重品を扱う様。おそらくひもに通した青銅か、タカラガイのたぐいだろう。”とうとい”の語義は、戦国時代まで時代が下る。詳細は論語語釈「貴」を参照。
是(シ)


(金文)
論語の本章では「~これ…」と読み、”~は…だ”と訳す。認定の意を示す。英語のbe動詞にあたる。初出は西周中期の金文。「ゼ」は呉音。字形は「睪」+「止」”あし”で、出向いてその目で「よし」と確認すること。同音への転用例を見ると、おそらく原義は”正しい”。初出から”確かにこれは~だ”と解せ、”これ”・”この”という代名詞、”~は~だ”という接続詞の用例と認められる。詳細は論語語釈「是」を参照。
人(ジン)


(甲骨文)
論語の本章では”世間の人”。初出は甲骨文。原義は人の横姿。「ニン」は呉音。甲骨文・金文では、人一般を意味するほかに、”奴隷”を意味しうる。対して「大」「夫」などの人間の正面形には、下級の意味を含む用例は見られない。詳細は論語語釈「人」を参照。
之(シ)


(甲骨文)
論語の本章では”~の”。初出は甲骨文。字形は”足”+「一」”地面”で、あしを止めたところ。原義はつま先でつ突くような、”まさにこれ”。殷代末期から”ゆく”の語義を持った可能性があり、春秋末期までに”…の”の語義を獲得した。詳細は論語語釈「之」を参照。
所(ソ)


(金文)
論語の本章では”…するところの…”。初出は春秋末期の金文。「ショ」は呉音。字形は「戸」+「斤」”おの”。「斤」は家父長権の象徴で、原義は”一家(の居所)”。論語の時代までの金文では”ところ”の意がある。詳細は論語語釈「所」を参照。
欲(ヨク)


(楚系戦国文字)
論語の本章では”欲しがる”。初出は楚系戦国文字。新字体は「欲」。同音は存在しない。字形は「谷」+「欠」”口を膨らませた人”。部品で近音の「谷」に”求める”の語義があり、全体で原義は”欲望する”。論語時代の置換候補は部品の「谷」。詳細は論語語釈「欲」を参照。
也(ヤ)
論語の本章、「是人之所惡」のうしろについては、現存最古の論語本である定州竹簡論語は「也」を記し、唐石経も記す。対して清家本は記さない。清家本は年代的には唐石経より新しいが、唐石経より古い文字列を伝えている。ただし本章の場合、定州本に「也」があるので、「是人之所惡」のうしろに「也」があるままに取り扱った。
論語の伝承について詳細は「論語の成立過程まとめ」を参照。
原始論語?…→定州竹簡論語→白虎通義→ ┌(中国)─唐石経─論語注疏─論語集注─(古注滅ぶ)→ →漢石経─古注─経典釈文─┤ ↓↓↓↓↓↓↓さまざまな影響↓↓↓↓↓↓↓ ・慶大本 └(日本)─清家本─正平本─文明本─足利本─根本本→ →(中国)─(古注逆輸入)─論語正義─────→(現在) →(日本)─────────────懐徳堂本→(現在)


(金文)
「也」は論語の本章では、「なり」と読んで、断定の意に用いている。この語義は春秋時代では確認できない。初出は春秋時代の金文。原義は諸説あってはっきりしない。「や」と読み主語を強調する用法は、春秋中期から例があるが、「也」を句末で断定に用いるのは、戦国時代末期以降の用法で、論語の時代には存在しない。詳細は論語語釈「也」を参照。
不(フウ)


(甲骨文)
漢文で最も多用される否定辞。初出は甲骨文。「フ」は呉音、「ブ」は慣用音。原義は花のがく。否定辞に用いるのは音を借りた派生義だが、甲骨文から否定辞”…ない”の意に用いた。詳細は論語語釈「不」を参照。
以(イ)


(甲骨文)
論語の本章では”…を用いて”。初出は甲骨文。人が手に道具を持った象形。原義は”手に持つ”。論語の時代までに、”率いる”・”用いる”・”携える”の語義があり、また接続詞に用いた。さらに”用いる”と読めばほとんどの前置詞”…で”は、春秋時代の不在を回避できる。詳細は論語語釈「以」を参照。
其(キ)


(甲骨文)
論語の本章では「それ」とよみ、”それにふさわしい”と解釈するしかない。この語義は春秋時代では確認できない。初出は甲骨文。甲骨文の字形は「𠀠」”かご”。かごに盛った、それと指させる事物の意。金文から下に「二」”折敷”または「丌」”机”・”祭壇”を加えた。人称代名詞に用いた例は、殷代末期から、指示代名詞に用いた例は、戦国中期からになる。詳細は論語語釈「其」を参照。
”ふさわしい”の語義は字形や音をどういじくっても出てこない。つまり儒者が本章を偽作するに当たって、曖昧にありがたさを臭わせたふざけた演出。
道(トウ)


「道」(甲骨文・金文)
論語の本章では”やり方”。動詞で用いる場合は”みち”から発展して”導く=治める・従う”の意が戦国時代からある。”言う”の意味もあるが俗語。初出は甲骨文。字形に「首」が含まれるようになったのは金文からで、甲骨文の字形は十字路に立った人の姿。「ドウ」は呉音。詳細は論語語釈「道」を参照。
得(トク)


(甲骨文)
論語の本章では”手に入れる”。初出は甲骨文。甲骨文に、すでに「彳」”みち”が加わった字形がある。字形は「貝」”タカラガイ”+「又」”手”で、原義は宝物を得ること。詳細は論語語釈「得」を参照。
處(ショ)


(金文)
論語の本章では”その状態でいる”。新字体は「処」。初出は西周中期の金文。字形は”人の横姿”+「几」で、腰掛けに座った人の姿。原義は”そこに居る”。金文では原義で用いた。詳細は論語語釈「処」を参照。
貧(ヒン)


(楚系戦国文字)
論語の本章では”貧しい”。初出は楚系戦国文字。論語の時代に存在しない。論語時代の置換候補も無い。字形は「分」+「貝」で、初出での原義は確認しがたい。「ビン」は呉音。詳細は論語語釈「貧」を参照。
賤(セン)


(楚系戦国文字)
論語の本章では”低い身分”。この文字の初出は戦国時代の金文で、論語の時代に存在しない。論語時代の置換候補もない。同音に戔を部品とする漢字群。字形は「貝」”貨幣”+「戔」で、原義は”価格が安い”。詳細は論語語釈「賤」を参照。
惡(アク/オ)


(金文)
論語の本章では”にくむ”・”どこに”。後者の語義は春秋時代では確認できない。現行字体は「悪」。初出は西周中期の金文。ただし字形は「䛩」。漢音(遣隋使・遣唐使が聞き帰った音)「アク」で”わるい”を、「オ」で”にくむ”を意味する。初出の字形は「言」+「亞」”落窪”で、”非難する”こと。現行の字形は「亞」+「心」で、落ち込んで気分が悪いさま。原義は”嫌う”。詳細は論語語釈「悪」を参照。
去(キョ)


(甲骨文)
論語の本章では”去る”。初出は甲骨文。字形は「大」”ひと”+「𠙵」”くち”で、甲骨文での「大」はとりわけ上長者を指す。原義はおそらく”去れ”という命令。甲骨文・春秋までの金文では”去る”の意に、戦国の金文では”除く”の意に用いた。詳細は論語語釈「去」を参照。
君子(クンシ)
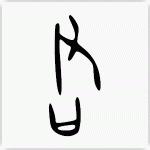

(甲骨文)
論語の本章では、”諸君”。「君」「子」共に初出は甲骨文。
「君」は「丨」”筋道”を握る「又」”手”の下に「𠙵」”くち”を記した形で、原義は天界と人界の願いを仲介する者の意。古代国家の君主が最高神官を務めるのは、どの文明圏でも変わらない。辞書的には論語語釈「君」を参照。
「子」は春秋時代では、貴族や知識人に対する敬称。原義は王族の幼い子供。詳細は論語語釈「子」を参照。


以上の様な事情で、「君子」とは孔子の生前は単に”貴族”を意味するか、孔子が弟子に呼びかけるときの”諸君”の意でしかない。それが後世、”情け深い教養人”などと偽善的意味に変化したのは、儒家を乗っ取って世間から金をせびり取る商材にした、孔子没後一世紀の孟子から。詳細は論語における「君子」を参照。
仁(ジン)


(甲骨文)
論語の本章では、”慈悲深さ”。本章は後世の創作が確定しているので、通説通り「仁義」の意で解すべき。初出は甲骨文。字形は「亻」”ひと”+「二」”敷物”で、原義は敷物に座った”貴人”。詳細は論語語釈「仁」を参照。
孔子の生前、「仁」は単に”貴族(らしさ)を意味したが、孔子没後一世紀後に現れた孟子は「仁義」を発明し、それ以降は「仁」→「仁義」となった。詳細は論語における「仁」を参照。
乎(コ)


(甲骨文)
論語の本章では、”…か”。疑問を示す。この語義は春秋時代では確認できない。初出は甲骨文。甲骨文の字形は持ち手を取り付けた呼び鐘の象形で、原義は”呼ぶ”こと。甲骨文では”命じる”・”呼ぶ”を意味し、金文も同様で、「呼」の原字となった。句末の助辞として用いられたのは、戦国時代以降になる。ただし「烏乎」で”ああ”の意は、西周早期の金文に見え、句末でも詠嘆の意ならば論語の時代に存在した可能性がある。詳細は論語語釈「乎」を参照。
成(セイ)


(甲骨文)
論語の本章では”作り上げる”。初出は甲骨文。字形は「戊」”まさかり”+「丨」”血のしたたり”で、処刑や犠牲をし終えたさま。甲骨文の字形には「丨」が「囗」”くに”になっているものがあり、もっぱら殷の開祖大乙の名として使われていることから、”征服”を意味しているようである。いずれにせよ原義は”…し終える”。甲骨文では地名・人名、”犠牲を屠る”に用い、金文では地名・人名、”盛る”(弔家父簠・春秋早期)に、戦国の金文では”完成”の意に用いた。詳細は論語語釈「成」を参照。
名(メイ)


(甲骨文)
論語の本章では、有名である状態。初出は甲骨文。「ミョウ」は呉音。字形は「夕」”夕暮れ時”+「𠙵」”くち”で、伝統的には”たそがれ時には誰が誰だか分からないので、名を名乗るさま”と言う。甲骨文では地名に用い、金文では”名づける”、”銘文”の意に用い、戦国の竹簡で”名前”を意味した。詳細は論語語釈「名」を参照。
無(ブ)


(甲骨文)
論語の本章では”…なくせ”。初出は甲骨文。「ム」は呉音。甲骨文の字形は、ほうきのような飾りを両手に持って舞う姿で、「舞」の原字。その飾を「某」と呼び、「某」の語義が”…でない”だったので、「無」は”ない”を意味するようになった。論語の時代までに、”雨乞い”・”ない”の語義が確認されている。戦国時代以降は、”ない”は多く”毋”と書かれた。詳細は論語語釈「無」を参照。
終(シュウ)


(甲骨文)
論語の本章では、”終える”。初出は甲骨文。字形はひもの先端を締めくくったさまで、すなわち”おわり”が原義となる。詳細は論語語釈「終」を参照。
食(ショク)


(甲骨文)
論語の本章では”食べる”。初出は甲骨文。甲骨文の字形は「亼」+点二つ”ほかほか”+「豆」”たかつき”で、食器に盛った炊きたてのめし。甲骨文・金文には”ほかほか”を欠くものがある。「亼」は穀物をあつめたさまとも、開いた口とも、食器の蓋とも解せる。原義は”たべもの”・”たべる”。詳細は論語語釈「食」を参照。
閒(カン)


(金文)
論語の本章では”あいだ”。この語義は春秋時代では確認できない。新字体は「間」。ただし唐石経も清家本も新字体と同じく「間」と記す。ただし文字史からは旧字「閒」を正字とするのに理がある。「ケン」は呉音。初出は西周末期の金文。字形は「門」+「月」で、門から月が見えるさま。原義はおそらく”かんぬき”。春秋までの金文では”間者”の意に、戦国の金文では「縣」(県)の意に用いた。詳細は論語語釈「間」を参照。
違(イ)


(金文)
論語の本章では”反対する”。初出は西周早期の金文。字形は「辵」”あし”+「韋」”めぐる”で、原義は明らかでないが、おそらく”はるかにゆく”だったと思われる。論語の時代までに、”そむく”、”はるか”の意がある。詳細は論語語釈「違」を参照。
造(ソウ)


(甲骨文)
論語の本章では”行為する”。初出は甲骨文。「ゾウ」は呉音。甲骨文の字形は多様で、「艸」”くさ”だけのもの、下に「𠙵」”くち”をくわえたものなど。これがどうして「造」に比定されたのか明瞭でない。金文の字形は「广」”屋根”+「舟」+「辛」”刃物”+「𠙵」”人のくち”で、造船のさま。原義は”舟を作る”。金文では”進む””・至る”・”作る”の意、官職名に用い、戦国の竹簡では”至る”、人名に用いた。詳細は論語語釈「造」を参照。
次(ジ)


(甲骨文)
論語の本章では”次ぐ”→”真似る”。この語義は春秋時代では確認できない。初出は甲骨文。現行字体の字形は「冫」+「欠」だが、甲骨文の字体は「𠂤」の下に「一」または「二」。「𠂤」は兵士が携行する兵糧袋で、”軍隊”を意味する。下の数字は部隊番号と思われ、全体で”予備兵”を意味する。原義は”予備”。金文では氏族名・人名に用いる例が多い。詳細は論語語釈「次」を参照。
造次(ソウジ)
論語の本章では”誰かの真似をする”。論語を除く再出は、『史記』五世世家の河間献王条で、「好儒學,被服造次必於儒者」”儒学を好み、必ず儒者に真似て作った服を着た”とあり、「造次」は”真似て作る”の意。次の再出は『塩鉄論』で、論語の本章をそのまま引用しており、どのような意味で用いたか明らかでない。これを”慌ただしい”の意と言い出したのは後漢儒の馬融で、論拠がないから信用ならない。詳細は論語解説「後漢というふざけた帝国」を参照。
古注『論語集解義疏』
註馬融曰造次急遽也顛沛僵仆也雖急遽僵仆不違於仁也

注釈。馬融「造次とは”あわただしい”ことである。顛沛とは”倒れ伏す”ことである。慌ただしく転んだ際にも、仁に背くなと言ったのである。」
必(ヒツ)


(甲骨文)
論語の本章では”必ず”。この語義は春秋時代では確認できない。初出は甲骨文。原義は先にカギ状のかねがついた長柄道具で、甲骨文・金文ともにその用例があるが、”必ず”の語義は戦国時代にならないと、出土物では確認できない。『春秋左氏伝』や『韓非子』といった古典に”必ず”での用例があるものの、論語の時代にも適用できる証拠が無い。詳細は論語語釈「必」を参照。
於(ヨ)


(金文)
論語の本章では”…で”。初出は西周早期の金文。ただし字体は「烏」。「ヨ」は”~において”の漢音(遣隋使・遣唐使が聞き帰った音)、呉音は「オ」。「オ」は”ああ”の漢音、呉音は「ウ」。現行字体の初出は春秋中期の金文。西周時代では”ああ”という感嘆詞、または”~において”の意に用いた。詳細は論語語釈「於」を参照。
顚(テン)


(戦国金文)
論語の本章では”ひっくり返る”。論語では本章のみに登場。初出は戦国末期の金文。論語の時代に存在しない。論語時代の置換候補もない。台湾や中国では、「顛」がコード上の正字体として扱われている。字形は「眞」(真)”人を釜ゆでにする”+「頁」”大きな頭”で、原義は”釜ゆでのいけにえ”。詳細は論語語釈「顚」を参照。
沛(ハイ)


(篆書)
論語の本章では”大雨”・”洪水”。論語では本章のみに登場。初出は後漢の『説文解字』。論語の時代に存在しない。論語時代の置換候補もない。字形は「氵」+「巿」”さかん”。水量の多い川を指す。詳細は論語語釈「沛」を参照。
顚沛(テンハイ)
論語の本章では”洪水”。論語を除く再出は、前漢武帝死去直後の『塩鉄論』で、論語の本章をそのまま再録しているので、語義を読み取ることが出来ない。『詩経』大雅・顛に、「顛沛之揭」とあるのはおそらく”洪水”の意。
「文王曰咨、咨女殷商。」文王曰く咨、咨女殷商よ。
(周の文王は言った。「ああ、ああ、あなた方殷王朝よ。)
「人亦有言、顛沛之揭。」人亦た言う有り、顛沛の揭げと。
(誰でも言うだろう、洪水の時には裾からげしなければならない、と。)
「枝葉未有害、本實先撥。」枝葉未だ害い有らざるも、本は實に先に撥れぬ。
(あなた方の枝葉にはまだ大丈夫なのもあるが、幹や根本はすでに腐り果てている。)
「殷鑒不遠、在夏后之世。」殷鑒遠から不、夏后之世に在り。
(殷が鑒=教訓とすべき歴史は遠くない、あなた方が滅ぼした夏王朝に他ならない。)
故事成句「殷鑒遠からず」の出典で(論語八佾篇14余話参照)、「顚沛」の最古の用例と言って差し支えない。「顚沛」を”倒れ伏す”と言い出したのは上掲の通り古注の馬融で、もとより信じるに足りない。
論語:付記
検証
論語の本章は、春秋戦国時代の誰一人引用せず、再出は定州竹簡論語で、それ以降も後漢の王充が『論衡』に全文を引用したほかは、先秦両漢の誰も引用も再録もしていない。『論衡』以降は、南北朝時代に成立した『後漢書』での引用が再出。
「富與貴」に限れば、戦国時代の『韓非子』に論がある。
人有禍則心畏恐,心畏恐則行端直,行端直則思慮熟,思慮熟則得事理,行端直則無禍害,無禍害則盡天年,得事理則必成功,盡天年則全而壽,必成功則富與貴,全壽富貴之謂福。而福本於有禍,故曰:「禍兮福之所倚。」以成其功也。

人間は不幸に出くわすと恐れ慎み、恐れ慎むと行動が真っ直ぐになる。行動が真っ直ぐになればよく考えるようになり、よく考えるようになれば物事がはっきりと見える。また行動が真っ直ぐになれば不幸に出くわすことが無いし、不幸に出くわさなければ、天寿を全うできる。またものがはっきり見えれば、必ず成功を掴む。そして天寿を全うするとは、寿命が長いことに他ならない。長寿ゆえに、必ず成功を掴み、富み栄えて身分も上がる。天寿を全うし富貴を全うできることが、つまり幸福だ。そう考えると、不幸こそが幸福の元であり、だから老子先生は、「災いは幸福のタネ」と言った。災いの結果、幸福になるからだ。(『韓非子』解老9)
「災い転じて福となす」(『戦国策』)、「禍福はあざなえる縄の如し」(『史記』南越伝)と同工異曲の話で、このように孔子と同世代のブッダが説いた、「無常」を中国人が初めて思い知ったのは、ブッダや孔子より一世紀はのちの、戦国時代のことであるらしい。
「忠」の字が戦国の世に現れたのもその一例。詳細は論語語釈「忠」を参照。
解説
論語の本章は、上掲の検証の通り後世の創作だが、章の前半と後半でおそらく成立した時代が異なる。定州竹簡論語が分割していないことから、前漢宣帝期にはすでに一章にまとめられていたが、前半は「也」で句を締めくくっているのに対し、後半はそうでない。
子曰、富與貴、是人之所欲也。不以其道、得之不處也。貧與賤、是人之所惡也。不以其道、得之不去也。
君子去仁、惡乎成名。君子無終食之閒違仁、造次必於是、顚沛必於是。
すると前半は戦国時代以降に作られたのが確実だが、後半は「顚沛」の文字が春秋時代に見られないことを除けば、孔子の肉声である可能性が出て来る。
「顚」の藤堂上古音はtenであり、「轉(転)」と音通しそうだがtuanで同音ではない。加えて「転」は甲骨文や金文があるようなことを大陸中国のサイトが言うが、典拠がないので信用できない。意外にも「展」に”ころがる”の語釈があって、藤音はtɪan。ɪはエに近いイで、tenに近いが初出は後漢の『説文解字』。
ここで発想を変えて、「天」の藤音はt’en。ほぼ同音と言っていい。
「沛」は『字通』の言う通り氵=水が巿んなことで、巿は西周早期の金文から存在し、カ音は「沛」pʰwɑdまたはpwɑdに対して「巿」はpi̯wət。◌̯は音節副音=弱い音を示し、両者は近い。
以上から「顚沛」→「天巿」、つまり天が降らせたさかんな雨だと出来るなら、論語の本章の後半は、以下の通り孔子の肉声として解釈出来る。無論「仁」の語釈も改めねばならず、論語の時代の意味、”貴族(らしさ)”。
君子去仁、惡乎成名。君子無終食之閒違仁、造次必於是、天巿必於是。
君子仁を去りて、惡くに乎名を成さん。君子食を終える之閒にも仁に違う無く、造しき次も必ず是に於り、天巿も必ず是に於れ。

諸君が貴族を目指すのではないなら、どうやって名を挙げようというのか(=成り上がるつもりなのか)。諸君は食事を終える間でも貴族らしい挙措動作を心掛け、とっさの時も同様、洪水の時も同様にしなさい。
さて、本章の前半についても考察を加えておこう。前半は人間の口から出た話し言葉と言うより、整った形式の元で読み上げる韻文、つまりは詩に似ている。
富與貴、是人之所欲也。不以其道、得之不處也。
貧與賤、是人之所惡也。不以其道、得之不去也。
富貴と貧賤、欲めると悪む、処ると去る、こうした置換可能なパーツを同じ骨組みに組み合わせる修辞法を、漢文では対句という。対句の起こりは春秋時代の『詩経』にも見られるが、それが散文の常識になるのは、論語よりも千年後、六朝時代になってからだった。
それを受けて、対句の全盛期である唐詩の時代が始まるのだが、それゆえもし話し言葉として論語の時代に放たれたなら、人はおそろしくしゃちこばった言い方だと受け取ったに違いない。有り体に言えば経典をそらんずる時の物言いであり、人間の肉声とは言いがたい。


こういう対句を孟子は書かなかった。とにかくしゃべっていたい男で、口から出任せにものを言ったから、『孟子』には地の文が少ない。対して戦国末期の荀子は書斎で沈思して文を書き、「青は藍より出でて藍より青し、氷は水より出でて水より寒し」と冒頭に書いた。
漢代の儒者も書斎に閉じこもってものを書く者が多かったし、こうした対句的言い廻しはことわざになって流布していたらしい。2世紀の王符は『潜夫論』のなかで、「ことわざに言う、一犬形に吠ゆれば、百犬声に吠ゆと」と書いている。前漢にはこうした言い廻しが定着した。
従って、論語の本章の前半は、その成立はかなり遅れ、おそらくは漢代に入ってからだろう。儒教の国教化に伴って、多くの経典整備が必要になったはずである。その一環として本章前半のような「誦す」文字列が作られ、いつの間にか後半とつなぎ合わされたのだろう。
もう一つ前半について言えることは、「貴」「貧」といった、貨幣経済を前提にした言葉は、論語の時代に遡るのが困難である。論語の時代は鋳鉄器と小麦の普及により、経済発展の時代ではあったが、まだ規格品の貨幣が登場するほど社会は豊かではない。
孔子が俸給を粟で受け取ったように、いまだ穀物が貨幣の役割を果たし、貝貨はあり得はしても、通用は極めて限られた範囲だったはずである。金属貨幣も楚の金塊が、秤量貨幣としてやっとあったかどうかという時代に過ぎない。前半を史実と言えないゆえんである。
余話
富貴は自分の努力でない
清末民初の儒者、程樹徳は論語の本章について次のように言う。
常人之情,好富貴而惡貧賤。不知富貴貧賤皆外來物,不能自主,君子所以不處不去者,正其達天知命之學。何者?福者禍之基,無故而得非分之位,颠越者其常,幸免者其偶也。無端而得意外之财,常人所喜,君子之所懼也。世之得貧賤之道多矣,如不守繩檢,博弈鬪狠,奢侈縱肆,皆所以取貧賤之道。無此等事以致貧賤,是其貧賤生於天命也。君子於此惟有素其位而行,所謂素貧賤行乎貧賤者。稍有怨天尤人之心,或思打破環境,則大禍立至矣。故不處不去,正君子之智,所謂智者利仁也。君子去仁,惡乎成名?

一般人の心理として、富貴を好んで貧賤を嫌う。だが富貴も貧賤もよそからやって来て、自分の思い通りにはならないものであることを知らない。君子がそういう場に居なかったり抜け出そうとしなかったりするのは、まさに人生が天命であることを知るためだ。
なぜなら、幸福は災いの元だし、理由も無く幸福でいると、それは分不相応だからだ。偶然で幸運を掴んだ者は、それが当たり前だと思っているが、天罰を喰らわずに済んでいるのは、それこそ偶然に過ぎない。まっとうでない方法で思いがけない財産を掴むと、一般人は喜ぶが、君子は危険を感じて危ながる。
世の中で貧賤になる方法はいくらでもある。例えば、分相応の生活をしない。バクチに走って暴利を求める。ぜいたくにふけって思い上がる。これらは全て貧賤に至る道だ。こういうことをしないのに、貧賤になってしまったのなら、それは天命というものだ。だから君子は、普段から分相応を心がけるが、我から貧乏になるようなことをし、賎しい行いをする者を、本当の貧賤ものと言う。
そういう手合いには、僅かでも天を怨み、人に文句をつけることで、貧賤から抜け出そうとする者が居るが、いずれものすごいしっぺ返しに遭うだろう。だから貧賤に居ようと居まいと、君子があくせくしないのは、まさしく君子の智恵を心得ているからで、論語に言う「仁を利とする」(論語里仁篇2)のの実践だ。
だから本章に言う、君子たる者仁を離れて、どこで名を売ろうというのか?(『論語集釋』)


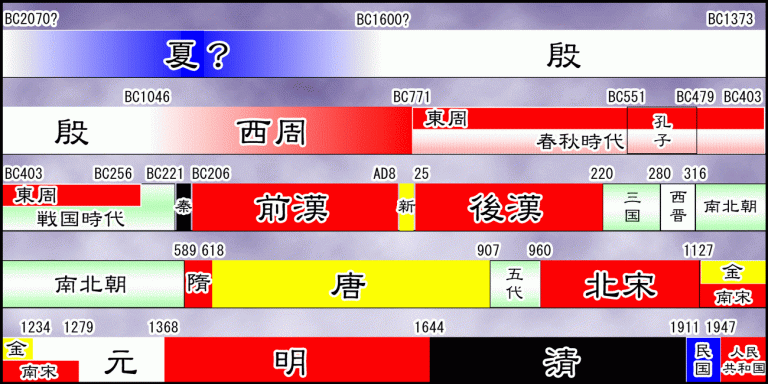


コメント